- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1468 歴史・文明・文化 『サピエンス全史(上・下巻)』 ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳(河出書房新社)
2017.08.16
世界的大ベストセラーの『サピエンス全史』上・下巻、ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳(河出書房新社)を読みました。「文明の構造と人類の幸福」というサブタイトルがついています。著者は1976年生まれのイスラエル人歴史学者です。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して博士号を取得し、現在、エルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えています。
この読書館でも紹介した名著『銃・病原菌・鉄』、『世界史』もそうですが、わたしは時々、スケールの大きな歴史の本を読むことにしています。日常の生活や仕事で狭くなりがちな視野を一気に拡大してくれるからです。本書は、「ビジネス書大賞2017」の 大賞を受賞し、「ビジネス書グランプリ2017」の リベラルアーツ部門の第1位にも輝いています。
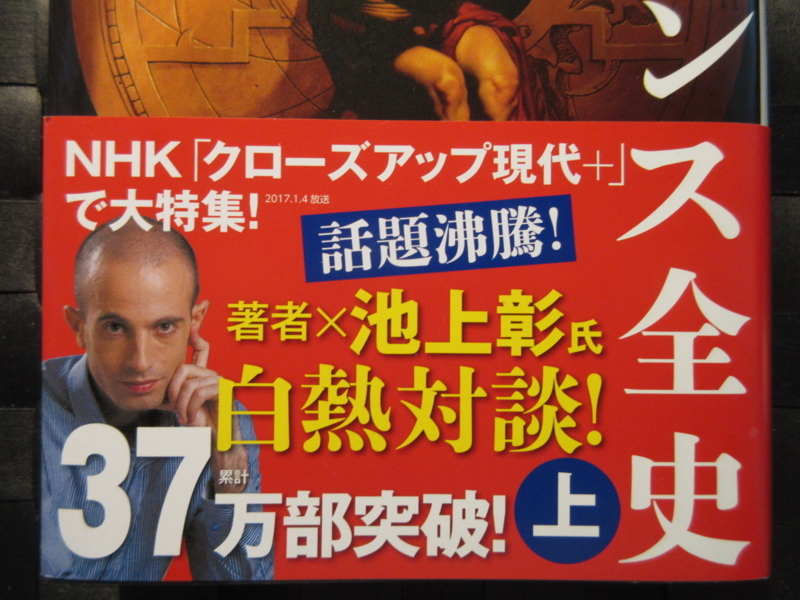 上巻の帯
上巻の帯
本書の上巻の帯には、著者の写真とともに、「『NHKクローズアップ現代+』で大特集! 2017・1・4」「話題沸騰! 著者×池上彰氏 白熱対談!」「37万部突破!」と書かれています。
 下巻の帯
下巻の帯
下巻の帯には、著者の写真とともに、「『NHKクローズアップ現代+』で大特集! 2017・1・4」「大反響!第1位 オール紀伊國屋日別ベストセラー(2017/1/5)Amazon.co.jp(2017/1/5 和書総合)」「実に魅力的で、刺激的な書―バラク・オバマ(『CNN』ホームページより)」と書かれています。
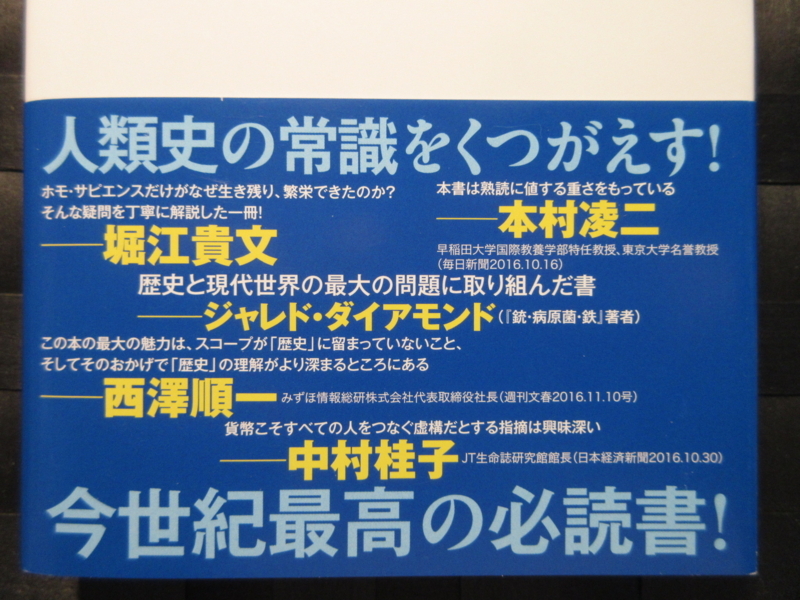 下巻の帯の裏
下巻の帯の裏
上・下巻ともに帯の裏には「人類史の常識をくつがえす!」「今世紀最高の必読書!」として、堀江貴文、本村凌二(早稲田大学国際教養学部特任教授、東京大学名誉教授)、ジャレド・ダイヤモンド(『銃・病原菌・鉄』著者)、西澤順一(みずほ情報総研株式会社代表取締役社長)、中村桂子(JT生命誌研究館館長)といった人々が推薦文を寄せています。
上巻のカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「アフリカでほそぼそと暮していたホモ・サピエンスが、食物連鎖の頂点に立ち、文明を築いたのはなぜか。その答えを解く鍵は『虚構』にある。我々が当たり前のように信じている国家や国民、企業や法律、さらには人権や平等といった考えまでもが虚構であり、虚構こそが見知らぬ人同士が協力することを可能にしたのだ。やがて人類は農耕を始めたが、農業革命は狩猟採集社会よりも苛酷な生活を人類に強いた、史上最大の詐欺だった。そして歴史は統一へと向かう。その原動力の1つが、究極の虚構であり、最も効率的な相互信頼の制度である貨幣だった。なぜ我々はこのような世界に生きているのかを読み解く、記念碑的名著!」
下巻のカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「近代に至って、なぜ文明は爆発的な進歩を遂げ、ヨーロッパは世界の制覇を握ったのか? その答えは『帝国、科学、資本』のフィードバック・ループにあった。帝国に支援された科学技術の発展にともなって、『未来は現在より豊かになる』という、将来への信頼が生まれ、起業や投資を加速させる『拡大するパイ』という、資本主義の魔法がもたらされたのだ。そして今、ホモ・サピエンスは何を望み、テクノロジーはあなたをどのような世界に連れて行くのだろうか? 人類史をたどることで、我々はどのような存在なのかを明らかにする、かつてないスケールの大著!」
本書の上巻目次は、以下のようになっています。
「歴史年表」
第1部 認知革命
第1章 唯一生き延びた人類種
第2章 虚構が協力を可能にした
第3章 狩猟採集民の豊かな暮らし
第4章 史上最も危険な種
第2部 農業革命
第5章 農耕がもたらした繁栄と悲劇
第6章 神話による社会の拡大
第7章 書記体系の発明
第8章 想像上のヒエラルキーと差別
第3部 人類の統一
第9章 統一へ向かう世界
第10章 最強の征服者、貨幣
第11章 グローバル化を進める帝国のビジョン
「原註」「図版出典」
下巻目次は、以下のようになっています。
第12章 宗教という超人間的秩序
第13章 歴史の必然と謎めいた選択
第4部 科学革命
第14章 無知の発見と近代科学の成立
第15章 科学と帝国の融合
第16章 拡大するパイという資本主義のマジック
第17章 産業の推進力
第18章 国家と市場経済がもたらした世界平和
第19章 文明は人間を幸福にしたのか
第20章 超ホモ・サピエンスの時代へ
「あとがき―神になった動物」
「謝辞」「訳者あとがき」
「原註」「図版出典」「索引」
第1部「認知革命」の第1章「唯一生き延びた人類種」の冒頭は、「これぞ、リベラルアーツ!」と声を上げたくなるような素晴らしい名文です。
「今からおよそ135億年前、いわゆる『ビッグバン』によって、物質、エネルギー、時間、空間が誕生した。私たちの宇宙の根本を成すこれらの要素の物語を『物理学』という。
物質とエネルギーは、この世に現れてから30万年ほど後に融合し始め、原子と呼ばれる複雑な構造体を成し、やがてその原子が結合して分子ができた。原子と分子とそれらの相互作用の物語を『化学』という。 およそ38億年前、地球と呼ばれる惑星の上で特定の分子が結合し、格別大きく入り組んだ構造体、すなわち有機体(生物)を形作った。有機体の物語を『生物学』という。
そしておよそ7万年前、ホモ・サピエンスという種に属する生き物が、なおさら精巧な構造体、すなわち文化を形成し始めた。そうした人間文化のその後の発展を『歴史』という」
その「歴史」の道筋は3つの重要な革命が決めたとして、著者は述べます。
「約7万年前に歴史を始動させた認知革命、約1万2000年前に歴史の流れを加速させた農業革命、そしてわずか500年前に始まった科学革命だ。3つ目の科学革命は、歴史に終止符を打ち、何かまったく異なる展開を引き起こす可能性が十分ある。本書ではこれら3つの革命が、人類をはじめ、この地上の生きとし生けるものにどのような影響を与えてきたのかという物語を綴っていく」
著者は、「兄弟たちはどうなったか?」として、約3万年前にネアンデルタール人が絶滅し、約1万3000年前に最後の小人のような人類がフローレス島から消えたことを指摘し、以下のように述べています。
「彼らは数々のものを残していった―骨や石器、私たちのDNAの中にはいくつかの遺伝子、そして答えのない多くの疑問を。彼らは私たちホモ・サピエンスという、最後の人類種も後に残した」
続けて著者は、以下のような数々の問いを発します。
「サピエンスの成功の秘密は何だったのか? 私たちはどうやって、これほど多くの、遠くて生態学的に異なる生息環境に、これほど速く移り住むことができたのか? 私たちはどうやって他の人類種をすべて忘却の彼方へ追いやったのか? なぜ、強靭で、大きな脳を持ち、寒さに強いネアンデルタール人たちでさえ、私たちの猛攻撃を生き延びられなかったのか?」
このような議論は今なお尽きません。最も有力な答えは、その議論を可能にしているものにほかならないとして、著者は「すなわち、ホモ・サピエンスが世界を征服できたのは、何よりも、その比類なき言語のおかげではなかろうか」と述べるのでした。
第2章「虚構が協力を可能にした」では、著者は、7万年前から3万年前にかけて見られた、新しい思考と意思疎通の方法の登場のことを「認知革命」として紹介します。その原因は定かではないとして、著者は以下のように述べます。
「最も広く信じられている説によれば、たまたま遺伝子の突然変異が起こり、サピエンスの脳内の配線が変わり、それまでにない形で考えたり、まったく新しい種類の言語を使って意思疎通をしたりすることが可能になったのだという。その変異のことを『知恵の木の突然変異』と呼んでもいいかもしれない(訳註 知恵の木は『創世記』に出てくるエデンの園に生えていた木で、アダムとイブはその実を食べて『目が開け』た)。なぜその変異がネアンデルタール人ではなくサピエンスのDNAに起こったのか? 私たちの知るかぎりでは、それはまったくの偶然だった。だが、より重要なのは、『知恵の木の突然変異』の原因よりも結果を理解することだ」
伝説や神話、神々、宗教は、認知革命に伴って初めて現れたとして、著者は以下のように述べます。
「それまでも、『気をつけろ! ライオンだ!』と言える動物や人類種は多くいた。だがホモ・サピエンスは認知革命のおかげで、『ライオンはわが部族の守護霊だ』と言う能力を獲得した。虚構、すなわち架空の事物について語るこの能力こそが、サピエンスの言語の特徴として異彩を放っている」
しかし、著者によれば、虚構のおかげで、人類は単に物事を想像するだけではなく、集団でそうできるようになったといいます。わたしたちは、聖書の天地創造の物語や、オーストラリア先住民の「夢の時代(天地創造の時代)」の神話、近代国家の国民主義の神話のような、共通の神話を紡ぎ出すことができます。そのような神話は、大勢で柔軟に協力するという空前の能力をサピエンスに与えるというのです。
認知革命によって、ホモ・サピエンスはより大きくて安定した集団を形成しました。そこには噂話の助けがあったのですが、噂話にも自ずと限界があるとして、著者は以下のように述べています。
「社会学の研究からは、噂話によってまとまっている集団の『自然な』大きさの上限がおよそ150人であることがわかっている。ほとんどの人は、150人を超える人を親密に知ることも、それらの人について効果的に噂話をすることもできないのだ。今日でさえ、人間の組織の規模には、150人というこの魔法の数字がおおよその限度として当てはまる。この限界値以下であれば、コミュニティや企業、社会的ネットワーク、軍の部隊は、互いに親密に知り合い、噂話をするという関係に主に基づいて、組織を維持できる。秩序を保つために、正式な位や肩書、法律書は必要ない」
続けて、人間の組織の規模について、著者は以下のように述べます。
「30人の兵から成る小隊、あるいは100人の兵から成る中隊でさえ、親密な関係を基に、うまく機能でき、正式な規律は最低限で事足りる。人望のある軍曹は、『中隊の王』となり、将校たちにさえ指図できる。小さな家族経営事業は、役員会やCEO(最高経営責任者)や経理部なしでも生き延びて、繁盛できる。だが、いったん150人という限界値を超えると、もう物事はそのようには進まなくなる。小隊を指揮するのと同じ方法で、1万を超える兵から成る師団を指揮することはできない。繁盛している家族経営の店も、規模が大きくなり、多くの人を雇い入れると、たいてい危機を迎える。根本から再編できなければ、倒産の憂き目に遭う」
著者によれば、近代国家にせよ、中世の教会組織にせよ、古代の都市にせよ、太古の部族にせよ、人間の大規模な協力体制は何であれ、人々の集合的想像の中にのみ存在する共通の神話に根差しているといいます。その上で、教会組織は共通の宗教的神話に根差しているとして、著者は以下のように述べます。
「たとえばカトリック教徒が、互いに面識がなくてもいっしょに信仰復興運動に乗り出したり、共同で出資して病院を建設したりできるのは、神の独り子が肉体を持った人間として生まれ、私たちの罪を贖うために、あえて十字架に架けられたと、みな信じているからだ。国家は、共通の国民神話に根差している。たとえばセルビア人が、互いに面識がなくても命を懸けてまで助け合うのは、セルビアという国民やセルビアという祖国、セルビアの国旗が象徴するものの存在を、みな信じているからだ。司法制度は共通の法律神話に根差している。互いに面識がなくても弁護士どうしが力を合わせて、赤の他人の弁護をできるのは、法と正義と人権―そして弁護料として支払われるお金―の存在を信じているからだ」
とはいえこれらのうち、人々が創作して語り合う物語の外に存在しているものは1つとしてないとして、著者は述べます。
「宇宙に神は1人もおらず、人類の共通の想像の中以外には、国民も、お金も、人権も、法律も、正義も存在しない。『原子的な人々』は死者の霊や精霊の存在を信じ、満月の晩には毎度集まって焚火の周りでいっしょに踊り、それによって社会秩序を強固にしていることを、私たちは簡単に理解できる。だが、現代の制度がそれとまったく同じ基盤に依って機能していることを、私たちは十分理解できていない」
著者によれば、サピエンスが発明した想像上の現実の計り知れない多様性と、そこから生じた行動パターンの多様性はともに、わたしたちが「文化」と呼ぶものの主要な構成要素です。いったん登場した文化は、けっして変化と発展をやめませんでした。こうした止めようのない変化のことを、わたしたちは「歴史」と呼びます。「歴史と生物学」として、著者は「認知革命は歴史が生物学から独立を宣言した時点だ。認知革命までは、すべての人類種の行為は、生物学(あるいは、もしお望みなら先史学と呼んでもいい)の領域に属していた」と述べるのでした。
さらに著者は、「認知革命以降は、ホモ・サピエンスの発展を説明する主要な手段として、歴史的な物語が生物学の理論に取って代わる。キリスト教の台頭あるいはフランス革命を理解するには、遺伝子やホルモン、生命体の相互作用を把握するだけでは足りない。考えやイメージ、空想の相互作用も考慮に入れる必要があるのだ」と述べています。 ホモ・サピエンスが、食物連鎖の頂点に立ち、文明を築いた鍵は「虚構」にあるという考え方は非常に刺激的であり、本書の白眉とも言えます。この考えを知ったわたしは、故吉本隆明の「共同幻想論」および、岸田秀氏の「唯幻論」を連想しました。
2012年に逝去した「思想の巨人」吉本隆明の「共同幻想論」とは唯物史観すなわち「唯物論」に対するアンチテーゼにほかなりませんでした。吉本は、何よりも日本人の「こころ」を追求しました。そして、この読書館でも紹介した『共同幻想論』で、『古事記』や『遠野物語』などの日本人の「こころ」の琴線に触れる書物を取り上げました。『古事記』からは初期国家における共同幻想、『遠野物語』からは村落社会の共同幻想の姿をあぶり出しています。非常にラディカルな問題提起の書なのだが、その「序」には次のように書かれている。
「ここで共同幻想というのは、おおざっぱにいえば個体としての人間の心的な世界と心的な世界がつくりだした以外のすべての観念世界を意味している。いいかえれば人間が個体としてではなく、なんらかの共同体としてこの世界と関係する観念の在り方のことを指している」
また、心理学者の岸田秀氏は『ものぐさ精神分析』を発表し、「唯幻論」を打ち出しました。唯幻論とは「本能が壊れた動物である人間は、現実に適合できず、幻想を必要とする。人間とは幻想する動物である」という考え方です。岸田氏は、この読書館でも紹介した著書『唯幻論物語』において、人間にとっての幻想について、以下のように述べています。
「本能に頼れないので、人間は、発明したこれらの自己、集団、世界などの存在を、そして、世界のなかでどう行動するかの道徳を価値づけ、正当化する必要があった。そこで、中心的な起源神話、創世神話に付随してさらにさまざまな神話が作られ、いろいろな制度が発明された。これらすべてのものを支えているのは、幻想(観念)であった」
本書『サピエンス全史』でいう「虚構」とは、吉本隆明のいう「共同幻想」、岸田秀のいう「幻想」とほぼ同じものであると考えてよいと思います。
第2部「農業革命」の第5章「農耕がもたらした繁栄と悲劇」では、著者は人間の暮らし方の革命としての「農業革命」について述べています。
「農業革命は、安楽に暮らせる新しい時代の到来を告げるにはほど遠く、農耕民は狩猟採集民よりも一般に困難で、満足度の低い生活を余儀なくされた。狩猟採集民は、もっと刺激的で多様な時間を送り、飢えや病気の危険が小さかった。人類は農業革命によって、手に入る食糧の総量をたしかに増やすことはできたが、食糧の増加は、より良い食生活や、より長い余暇には結びつかなかった。むしろ、人口爆発と飽食のエリート層の誕生につながった。平均的な農耕民は、平均的な狩猟採集民よりも苦労して働いたのに、見返りに得られる食べ物は劣っていた。農業革命は、史上最大の詐欺だったのだ」
「史上最大の詐欺」とはずいぶんとショッキングな表現ですが、それは誰の責任だったのでしょうか。著者は、「王のせいでもなければ、聖職者や商人のせいでもない。犯人は、小麦、稲、ジャガイモなどの、一握りの植物種だった。ホモ・サピエンスがそれらを栽培化したのではなく、逆にホモ・サピエンスがそれらに家畜化されたのだ」と述べています。
第6章「神話による社会の拡大」では、「未来に関する懸念」として、著者は農耕のストレスについて以下のように述べています。
「農耕のストレスは、広範な影響を及ぼした。そのストレスが、大規模な政治体制や社会体制の土台だった。悲しいかな、勤勉な農耕民は、現在の懸命な労働を通してなんとしても手に入れようと願っていた未来の経済的安心を達成できることは、まずなかった。至る所で支配者やエリート層が台頭し、農耕民の余剰食糧によって暮らし、農耕民は生きていくのが精一杯の状態に置かれた」
続けて、著者は農耕による影響について述べます。 「こうして没収された食糧の余剰が、政治や戦争、芸術、哲学の原動力となった。余剰食糧のおかげで宮殿や砦、記念碑や神殿が建った。近代後期まで、人類の9割以上は農耕民で、毎朝起きると額に汗して畑を耕していた。彼らの生み出した余剰分を、王や政府の役人、兵士、聖職者、芸術家、思索家といった少数のエリート層が食べて生きており、歴史書を埋めるのは彼らだった。歴史とは、ごくわずかの人の営みであり、残りの人々はすべて、畑を耕し、水桶を運んでいた」
また著者は、「想像上の秩序」として、神話の存在に言及します。
「生物学的本能が欠けているにもかかわらず、狩猟採集時代に何百もの見知らぬ人どうしが協力できたのは、彼らが共有していた神話のおかげだ。だが、この種の協力は緩やかで限られたものだった。どのサピエンスの集団も、独立した生活を営み、自らの必要の大半を自ら満たし続けた。2万年前に社会学者が住んでいたなら、農業革命以降の出来事をまったく知らないから、神話が威力を発揮できる範囲はかなり限られていると結論づけるのではないか。祖先の霊や部族のトーテムについての物語は、500人が貝殻を交換し、風変わりな祭りを祝い、力を合わせてネアンデルタール人の集団を一掃できるほど強力ではあったが、それが限度だった」
神話は何百万もの見知らぬ人同士が日常的に協力することを可能にしたのです。
さらに、著者は神話の偉大な力について、以下のように述べます。
「神話は誰一人想像できなかったほど強力だったのだ。農業革命によって、混雑した都市や無敵の帝国を打ち立てる機会が開かれると、人々は偉大なる神々や母国、株式会社にまつわる物語を創作し、必要とされていた社会的つながりを提供した。人類の進化がそれまでどおりの、カタツムリの這うようなペースで続くなか、人類の想像力のおかげで、地球上ではかつて見られなかった類の、大規模な協力の驚くべきネットワークが構築されていた」
そして著者は、「脱出不能の監獄」として述べるのでした。
「キリスト教や民主主義、資本主義といった想像上の秩序の存在を人々に信じさせるにはどうしたらいいのか? まず、その秩序が想像上のものだとは、けっして認めてはならない。社会を維持している秩序は、偉大な神々あるいは自然の法則によって生み出された客観的実体であると、つねに主張する。人々が同等ではないのは、ハンムラビがそう言ったからではなく、エンリルとマルドゥクがそう定めたからだ。人々が平等なのは、トマス・ジェファーソンがそう言ったからではなく、神がそのように人々を創造したからだ。自由市場が最善の経済制度なのは、アダム・スミスがそう言ったからではなく、それが不変の自然法則だからだ」
第3部「人類の統一」の第9章「統一へ向かう世界」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「農業革命以降、人間社会はしだいに大きく複雑になり、社会秩序を維持している想像上の構造体も精巧になっていった。神話と虚構のおかげで、人々はほとんど誕生の瞬間から、特定の方法で考え、特定の標準に従って行動し、特定のものを望み、特定の規則を守ることを習慣づけられた。こうして彼らは人工的な本能を生み出し、そのおかげで厖大な数の見ず知らずの人どうしが効果的に協力できるようになった。この人工的な本能のネットワークのことを『文化』という」
第10章「最強の征服者、貨幣」では、「貝殻とタバコ」として、著者は貨幣について述べています。
「貨幣というのは硬貨や紙幣とはかぎらない。品物やサービスを交換する目的で、他のものの価値を体系的に表すために人々が進んで使うものであれば、それは何であれ貨幣だ。貨幣のおかげで人々はさまざまな品物やサービス(たとえばリンゴ、靴、離婚)の価値を素早く簡単に比較し、交換し、手軽に富を蓄えることができる。これまで貨幣にはさまざまな種類があった。最も馴染み深いのは硬貨で、規格化し、刻印した金属片だ。だが、貨幣は硬貨の鋳造が発明されるはるか前から存在しており、さまざまな文化が貝殻や牛、皮、塩、穀物、珠、布、約束手形など、他のものを通貨として使い、栄えた」
また、「貨幣はどのように機能するのか?」として、著者は述べます。
「信頼こそ、あらゆる種類の貨幣を生み出す際の原材料にほかならない。裕福な農民が自分の財産を売ってタカラガイの貝殻一袋にし、別の地方に移ったのは、彼は目的地に着いたとき、他の人が米や家や田畑をその貝殻と引き換えに売ってくれると確信していたからだ。したがって、貨幣は相互信頼の制度であり、しかも、ただの相互信頼の制度ではない。これまで考案されたもののうちで、貨幣は最も普遍的で、最も効率的な相互信頼の制度なのだ」
さらに著者は、「金の福音」として、宗教的信仰に関して同意できないキリスト教徒とイスラム教徒も、貨幣に対する信頼に関しては同意できると言います。なぜなら、宗教は特定のものを信じるように求めるが、貨幣は他の人々が特定のものを信じていることを信じるように求めるからだとして、著者は以下のように述べます。
「哲学者や思想家や預言者たちは何千年にもわたって、貨幣に汚名を着せ、お金のことを諸悪の根源と呼んできた。それは当たっているかもしれないが、貨幣は人類の寛容性の極みでもある。貨幣は言語や国家の法律、文化の規準、宗教的信仰、社会習慣よりも心が広い。貨幣は人間が生み出した信頼制度のうち、ほぼどんな文化の間の溝をも埋め、宗教や性別、人種、年齢、性的指向に基づいて差別することのない唯一のものだ。貨幣のおかげで、見ず知らずで信頼し合っていない人どうしでも、効果的に協力できる」
著者は、貨幣は以下の2つの普遍的原理に基づいていると指摘します。
a 普遍的転換性―貨幣は錬金術師のように、土地を忠誠に、正義を健康に、暴力を知識に転換できる。
b 普遍的信頼性―貨幣は仲介者として、どんな事業においてもどんな人どうしでも協力できるようにする。
そして、「貨幣の代償」として、著者は述べるのでした。
「これら2つの原理のおかげで、厖大な数の見知らぬ人どうしが交易や産業で効果的に協力できるようになった。だが、一見すると当たり障りのないこの原理には、邪悪な面がある。あらゆるものが転換可能で、信頼が個性のない硬貨やタカラガイの貝殻に依存しているときには、各地の伝統や親密な関係、人間の価値が損なわれ、需要と供給の冷酷な法則がそれに取って代わるのだ。
上巻の最終章となる第11章「グローバル化を進める帝国のビジョン」では、著者は「帝国とは何か?」として、以下のように述べています。
「文化的多様性と領土の柔軟性のおかげで、帝国は独特の特徴を持つばかりでなく、歴史の中で、自らの中心的役割も得る。帝国が多様な民族集団と生態圏を単一の政治的傘下に統一し、人類と地球のますます多くの部分を融合させられたのも、これら2つの特徴があればこそだ。ここで強調しておかなければならないが、帝国は、その由来や統治形態、領土の広さ、人口によってではなく、文化的多様性と変更可能な国境によってもっぱら定義される」
「帝国は軍事的征服によって出現する必要はない」として、著者は以下のように具体例をあげます。
「アテネ帝国(デロス同盟)は自主的な同盟として始まったし、ハプスブルク帝国は、一連の抜け目ない婚姻同盟によってまとめ上げられたのだから、結婚から誕生したわけだ。また、帝国は独裁的な皇帝に支配されている必要もない。史上最大の帝国である大英帝国は、民主政体によって支配されていた。それ以外にも、オランダ、フランス、ベルギー、アメリカといった民主制(あるいは少なくとも共和制)の近代の帝国や、ノヴゴロド、ローマ、カルタゴ、アテネといった近代以前の帝国がある」
下巻の最初の章である第12章「宗教という超人間的秩序」では、今日、宗教は差別や意見の相違、不統一の根源と見なされることが多いが、じつは、貨幣や帝国と並んで、宗教もこれまでずっと、人類を統一する3つの要素の1つだったのだとして、著者は以下のように述べます。
「社会秩序とヒエラルキーはすべて想像上のものだから、みな脆弱であり、社会が大きくなればなるほど、さらに脆くなる。宗教が担ってきたきわめて重要な歴史的役割は、こうした脆弱な構造に超人間的な正当性を与えることだ。宗教では、私たちの法は人間の気まぐれではなく、絶対的な至上の権威が定めたものだとされる。そのおかげで、根本的な法の少なくとも一部は、文句のつけようのないものとなり、結果として社会の安定が保証される。したがって宗教は、超人間的な秩序の信奉に基づく、人間の規範と価値観の制度と定義できる」
また、「神々の台頭と人類の地位」として、著者は再び神話に言及します。
「神々の起源についての有力な説によれば、神々はこの問題の解決策を提供したから重要性を獲得したという。豊饒の女神や空の神、医術の神のような神々は、動植物が話す能力を失ったときに舞台の中央を占めた。神々の主な役割は、人間と口の利けない動植物との仲立ちをすることだった。古代の神話の多くは、じつは法的な契約で、動植物の支配権と引き換えに、神々への永遠の献身を約束するものだった。『創世記』の最初のほうの章はその最たる例だ。農業革命以降何千年にもわたって、宗教の礼拝方式は、人間がヒツジを生贄にし、ブドウ酒とパンを神聖な神々に捧げることが主体で、それと引き換えに、神々は豊作と家畜の多産を約束した」
続けて、著者は以下のように多神教の出現について述べます。
「農業革命は当初、岩や泉、死者の霊、魔物といったアニミズムの体系の他の成員の地位には、はるかに小さな影響しか及ぼさなかった。とはいえ、これらも徐々に地位を失い、新たな神々に取って代わられた。人々が数百平方キロメートルの限られた縄張りの中で一生を送っているかぎり、彼らの必要は地元の精霊たちに満たしてもらえた。だが、王国や交易ネットワークが拡大すると、人々は王国や交易圏全体に力と権威が及ぶ存在と接触する必要が出てきた。こうした必要に応える試みが、多神教の宗教の出現につながった。これらの宗教は、世界は豊饒の女神や雨の神、軍神など、一団の強力な神々によって支配されていると考えた。人間はこれらの神々に訴えることができ、祈禱や生贄を捧げれば、神々はありがたくも雨や勝利や健康をもたらしてくださりうるのだった」
偉大な神々の台頭がもたらした最大の影響とは何か。著者によれば、それはヒツジや魔物ではなく、ホモ・サピエンスの地位に対してのものでした。アニミズムの信奉者たちは、人間は世界に暮らしている多くの生き物の1つにすぎないと考えていたが、多神教信者たちは次第に世界を神々と人間の関係の反映と見るようになったとして、著者は述べます。
「私たちの祈りや生贄、罪、善行が生態系全体の運命を決めた。ひどい洪水では何十億ものアリやバッタ、カメ、レイヨウ、ゾウが地上から消し去られかねないが、それは数人の愚かなサピエンスが神々を怒らせたがためなのだ。こうして多神教信者は神々の地位を高めただけでなく、人類の地位をも高めた。従来のアニミズムの体系の成員のうち、人間ほど恵まれていない者たちは零落し、人類と神々の関係を軸とする一大ドラマの、エキストラあるいは物言わぬ舞台装置と化した」
第4部「科学革命」の第14章「無知の発見と近代科学の成立」では、過去500年間に、人間の力は前例のない驚くべき発展を見せたとして、著者は以下のように述べています。
「1500年には、全世界にホモ・サピエンスはおよそ5億人いた。今日、その数は70億に達する。1500年に人類によって生み出された財とサービスの総価値は、今日のお金に換算して、2500億ドルと推定される。今日、人類が1年間に生み出す価値は、60兆ドルに近い。1500年には人類は1日当たりおよそ13兆カロリーのエネルギーを消費していた。今日、私たちは1日当たり1500兆カロリーを消費している(これらの数字を見直してほしい。私たちの人口は14倍、生産量は240倍、エネルギー消費量は115倍に増えたのだ)」
また、「科学界の教義」として、著者は以下のように述べています。
「聖書やクルアーン、ヴェーダ、儒教の権威ある書物には、方程式やグラフ、計算はほとんど出てこない。伝統的な神話や聖典が一般法則を規定するときには、数学的形式ではなく物語の形式で提示した。たとえばマニ教の根本原理では、世界は善と悪の戦場であるというふうに断言されている。悪の力が物質を生み出す一方、善の力が精神を生み出した。人間はこれら2つの力に引き裂かれているが、悪ではなく善を選ばなければならない。だが、マニ教の始祖である預言者のマニは、これら2つの力のそれぞれの強さを定量化することで人間の選択を予想するのに使える、数学的公式を提供しようとはしなかった。彼は、『人間に働く力は当人の精神の加速度を当人の身体の質量で割った値に等しい』などという計算は、ついぞしなかった」 しかし、それこそ、科学者たちが成し遂げようとしていることでした。
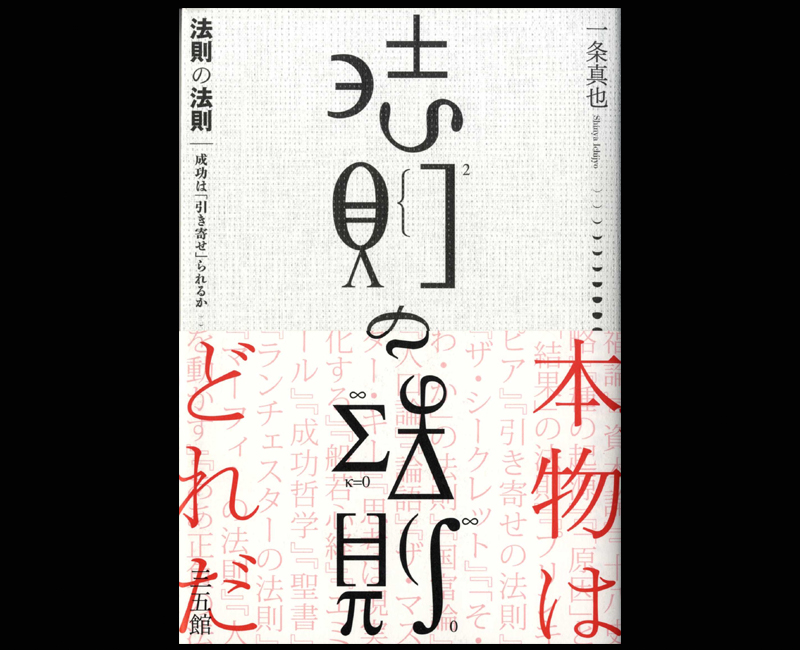 『法則の法則』(三五館)
『法則の法則』(三五館)
拙著『法則の法則』(三五館)に書いたように、『聖書』も『クルアーン』も『ヴェーダ』も『論語』も、いずれも「法則」というものを求めた書ではないでしょうか。数学や自然科学の世界でも「法則」が求められましたが、人類史上最大の「法則王」はアイザック・ニュートンであり、彼の発見した「万有引力の法則」こそは、史上最大の法則であると思います。
さて、著者は「ギルガメシュ・プロジェクト」というものを紹介しています。このくだりは、本書全体の中でも、最も強く印象に残りました。著者は、表向きは解決不可能とされる人類のあらゆる問題のうちでも、最も困難で興味深く、重要であり続けているものがあるとして、以下のように述べています。
「ほかならぬ死の問題だ。近代後期以前は、ほとんどの宗教とイデオロギーは、死が私たちにとって免れられない運命であるのは当然だと考えていた。そのうえ、多くの信仰は死を、生命の意味の主要な源泉に変えていた。死のない世界では、イスラム教やキリスト教、古代エジプトの宗教がどうなるか想像してほしい。これらの宗教の教義は人々に、死を克服してこの地上で永遠に生きようとするのではなく、死を受け容れ、死後の生に望みを託すよう教えた。賢者たちは死を逃れようとすることではなく、死に意味を与えることに励んだ。それが私たちに伝わっている最古の神話、すなわち古代シュメールのギルガメシュ神話のテーマだ」
多くの著書でも言い続けてきましたが、わたしは、「死」こそは人類最大の問題であると思います。では、人類にとっての「死」は、どのように変わってきたか。著者は以下のように述べます。
「ワーテルローの戦いから2世紀が過ぎた今、状況は一変した。飲み薬や注射、高度な手術のおかげで私たちは、かつては免れようのない死の宣告を突きつけてきた無数の病気や負傷でも、命が助かるようになった。また、日常的な痛みや軽い病気の数々からも守られている。近代以前の人は、そうしたものも人生の一部として淡々と受け容れざるをえなかった。平均寿命は、25~40歳から、全世界では約67歳、先進国では約80歳まで大幅に伸びた」
死が最大の敗北を喫したのが、小児死亡率の分野でした。
著者は、小児死亡率について以下のように述べています。
「20世紀まで、農耕社会の子供の4分の1から3分の1が成人前に亡くなった。そのほとんどがジフテリアや麻疹、天然痘のような疾患で命を落とした。17世紀のイングランドでは、新生児1000人のうち150人が最初の1年で死亡し、すべての子供の3分の1が15歳になる前に死んだ。今日、最初の1年で亡くなるイングランドの赤ん坊は1000人中わずか5人で、15歳になる前に死亡する子供も1000人に7人にすぎない」
第15章「科学と帝国の融合」では、人類史で中心的な役割を果たしてきたとされるヨーロッパが取り上げられます。「なぜヨーロッパなのか?」として、著者は以下のように述べています。
「ヨーロッパがようやく軍事的、政治的、経済的、文化的発展の重要地域になったのは、15世紀末のことだった。1500年から1750年までの間に、ヨーロッパ西部は勢いをつけ、『外界』、つまり南北のアメリカ大陸と諸大洋の征服者になった。だがそのときでさえヨーロッパはアジアの列強には及ばなかった。ヨーロッパ人がアメリカを征服し、海上での覇権を得ることができたのは、主としてアジアの国々がそれらに興味をほとんど持っていなかったからだ」
続けて、著者はヨーロッパについて、以下のように述べます。
「近代前期は地中海地方のオスマン帝国、ペルシアのサファヴィー帝国、インドのムガル帝国、中国の明朝と清朝の黄金時代だった。それらの国々は領土を大幅に拡げ、かつてなかったほどの人口増加と経済成長を遂げた。1775年にアジアは世界経済の8割を担っていた。インドと中国の経済を合わせただけでも全世界の生産量の3分の2を占めていた。それに比べると、ヨーロッパ経済は赤子のようなものだった。ようやく世界の権力の中心がヨーロッパに移ったのは、1750年から1850年にかけてで、ヨーロッパ人が相次ぐ戦争でアジアの列強を倒し、その領土の多くを征服したときだった。1900年までにはヨーロッパ人は世界経済をしっかりと掌握し、世界の領土の大部分を押さえていた」
ヨーロッパは、近代前期の貯金があったからこそ近代後期に世界を支配することができました。では、その近代前期に、どのような潜在能力を伸ばしたのでしょうか? この問いについて、著者は「互いに補完し合う2つの答えがある」として、以下のように答えています。
「近代科学と近代資本主義だ。ヨーロッパ人は、テクノロジー上の著しい優位性を享受する以前でさえ、科学的な方法や資本主義的な方法で考えたり行動したりしていた。そのため、テクノロジーが大きく飛躍し始めたとき、ヨーロッパ人は誰よりもうまくそれを活用することができた。したがって、ヨーロッパ帝国主義が21世紀のポスト・ヨーロッパ世界に遺した最も重要な財産は科学と資本主義が形成しているというのは、けっして偶然ではないのだ。ヨーロッパやヨーロッパの人々はもはや世界を支配してはいないが、科学と資本はますます強力になっている」
ここで、いよいよ資本主義が登場します。第16章「拡大するパイという資本主義のマジック」では、「拡大するパイ」として、著者は述べます。
「資本主義は『資本』をたんなる『富』と区別する。資本を構成するのは、生産に投資されるお金や財や資源だ。一方、富は地中に埋まっているか、非生産的な活動に浪費される。非生産的なピラミッドの建設に資源を注ぎ込むファラオは資本主義者ではない。スペイン財宝艦隊を襲い、金貨のぎっしり詰まった箱をカリブ海のどこかの島の砂浜に埋めて隠す海賊は資本主義者ではない。だが、自分の収入のいくばくかを株式市場に再投資する勤勉な工場労働者は資本主義者だ」
第18章「国家と市場経済がもたらした世界平和」では、今日、地球上の大陸には70億近くものサピエンスが暮らしているとして、著者は述べます。
「全員を巨大な秤に載せたとしたら、その総重量はおよそ3億トンにもなる。もし乳牛やブタ、ヒツジ、ニワトリなど、人類が農場で飼育している家畜を、さらに巨大な秤にすべて載せたとしたら、その重量は約7億トンになるだろう。対照的に、ヤマアラシやペンギンからゾウやクジラまで、残存する大型の野生動物の総重量は、1億トンに満たない。児童書や図面やテレビ画面には、今も頻繁にキリンやオオカミ、チンパンジーが登場するが、現実の世界で生き残っているのはごく少数だ。世界には15億頭の畜牛がいるのに対して、キリンは8万頭ほどだ。4億頭の飼い犬に対して、オオカミは20万頭しかいない。チンパンジーがわずか25万頭であるのに対して、ヒトは何十億人にものぼる。人類はまさに世界を征服したのだ」
著者は「家族とコミュニティの崩壊」として、以下のように述べています。
「産業革命以前は、ほとんどの人の日常生活は、古来の3つの枠組み、すなわち、核家族、拡大家族、親密な地域コミュニティの中で営まれていた。人々はたいてい、家族で営む農場や工房といった家業に就いていた。さもなければ、近隣の人の家業を手伝っていた。また、家族は福祉制度であり、医療制度であり、教育制度であり、建設業界であり、労働組合であり、年金基金であり、保険会社であり、ラジオ・テレビ・新聞であり、銀行であり、警察でさえあった」
続けてのくだりは、わたしの心に突き刺さりました。
「誰かが病気になると、家族が看病に当たった。誰かが歳を取れば家族が世話をし、子供たちが年金の役割を果たした。誰かが亡くなると、家族が残された子供の面倒を見た。誰かが家を建てたいと思えば、家族が手伝った。誰かが新たな仕事を始めたいと思えば、家族が必要な資金を用立てた。誰かが身を固めたいと思えば、家族がその相手候補を選んだり、少なくとも厳しく審査したりした。誰かが隣人と揉め事を起こせば、家族が加勢に入った。だが、病状が重すぎて家族の手には負えなくなったとき、あるいは、新たな商売を起こすために大きな投資が必要なとき、さらには、近隣の揉め事が暴力沙汰にまで発展したときには、地域コミュニティが助け舟を出した」
 『隣人の時代』(三五館)
『隣人の時代』(三五館)
拙著『隣人の時代』(三五館)で、わたしは「助け合いは人類の本能だ!」と訴えました。よく、「人」という字は互いが支えあってできていると言われます。では、それが人類の本能であるということは知っていましたか?
チャールズ・ダーウインは1859年に『種の起源』を発表して有名な自然選択理論を唱えましたが、そこでは人類の問題はほとんど扱っていませんでした。進化論が広く知れわたった12年後の1871年、人間の進化を真正面から論じた『人間の由来』を発表します。
この本でダーウインは、道徳感情の萌芽が動物にも見られること、しかもそのような利他性が社会性の高い生物でよく発達していることから、人間の道徳感情も祖先が高度に発達した社会を形成して暮らしていたことに由来するとしたのです。そのような環境下では、お互いに助け合うほうが適応的であり、相互の利他性を好むような感情、すなわち道徳感情が進化してきたのだというわけです。
このダーウインの道徳起源論をさらに進めて人間社会を考察したのが、ピョートル・クロポトキンです。クロポトキンといえば、一般にはアナキストの革命家として知られています。しかし、ロシアでの革命家としての活動は1880年半ばで終わっています。その後、イギリスに亡命して当地で執筆し、1902年に発表したのが『相互扶助論』です。ダーウインの進化論の影響を強く受けながらも、それの「適者生存の原則」や「不断の闘争と生存競争」を批判し、声明が「進化」する条件は「相互扶助」にあることを論証した本です。
この本は、トーマス・ハクスレーの随筆に刺激を受けて書かれたそうです。ハクスレーは、自然は利己的な生物同士の非情な闘争の舞台であると論じていました。この理論は、マルサス、ホッブス、マキアヴェリ、そして聖アウグスティヌスからギリシャのソフィスト哲学者にまでさかのぼる古い伝統的な考え方の流れをくみます。その考え方とは、文化によって飼い慣らされなければ、人間の本性は基本的に利己的で個人主義的であるという見解です。それに対して、クロポトキンは、プラトンやルソーらの思想の流れに沿う主張を展開しました。人間は高潔で博愛の精神を持ってこの世に生まれ落ちるが、社会によって堕落させられるという考え方です。平たく言えば、ハクスレーは「性悪説」、クロポトキンは「性善説」ということになります。
『相互扶助論』の序文には、ゲーテのエピソードが出てきます。博物学的天才として知られたゲーテは、相互扶助が進化の要素としてつとに重要なものであることを認めていました。1827年のことですが、ある日、『ゲーテとの対話』の著者として知られるエッカーマンが、ゲーテを訪ねました。そして、エッカーマンが飼っていた二羽のミソサザイのヒナが逃げ出して、翌日、コマドリの巣の中でそのヒナと一緒に養われていたという話をしました。
ゲーテはこの事実に非常に感激して、彼の「神の愛はいたるところに行き渡っている」という汎神論的思想がそれによって確証されたものと思いました。「もし縁もゆかりもない他者をこうして養うということが、自然界のどこにでも行なわれていて、その一般法則だということになれば、今まで解くことのできなかった多くの謎はたちどころに解けてしまう」とゲーテは言いました。さらに翌日もそのことを語りながら、必ず「無尽蔵の宝庫が得られる」と言って、動物学者だったエッカーマンに熱心にこの問題についての研究をすすめたといいます。
クロポトキンによれば、きわめて長い進化の流れの中で、動物と人類の社会には互いに助け合うという本能が発達してきました。近所に火事があったとき、私たちが手桶に水を汲んでその家に駆けつけるのは、隣人しかも往々まったく見も知らない人に対する愛からではありません。愛よりは漠然としていますが、しかしはるかに広い、相互扶助の本能が私たちを動かすというのです。クロポトキンは、ハクスレーが強調する「生存競争」の概念は、人間社会はもちろんのこと、自然界においても自分の観察とは一致しないと述べています。
生きることは血生臭い乱闘ではないし、ハクスレーが彼の随筆に引用したホッブスの言葉のように「万人の万人に対する戦い」でもなく、競争よりもむしろ協力によって特徴づけられている。現に、最も繁栄している動物は、最も協力的な動物であるように思われる。もし各個体が他者と戦うことによって進化していくというなら、相互利益が得られるような形にデザインされることによっても進化していくはずである。 以上のように、クロポトキンは考えました。
クロポトキンは、利己性は動物の伝統であり、道徳は文明社会に住む人間の伝統であるという説を受け入れようとはしませんでした。彼は、協力こそが太古からの動物の伝統であり、人間もまた他の動物と同様にその伝統を受け継いでいるのだと考えたのです。 「オウムは他の鳥たちよりも優秀である。なぜなら、彼らは他の鳥よりも社交的であるからだ。それはつまり、より知的であることを意味するのである」とクロポトキンは述べています。また人間社会においても、原始的部族も文明人に負けず劣らず協力しあいます。農村の共同牧草地から中世のギルドにいたるまで、人々が助けあえば助けあうほど、共同体は繁栄してきたのだと、クロポトキンは論じます。
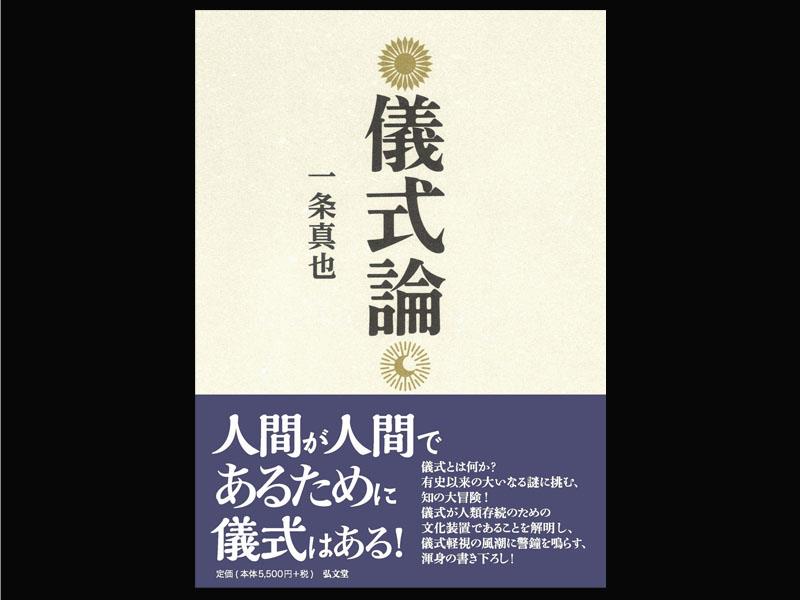 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
アリストテレスは「人間は社会的動物である」と言いましたが、近年の生物学的な証拠に照らし合わせてみると、この言葉はまったく正しかったことがわかります。結局、人間はどこまでも社会を必要とするのです。人間にとっての「相互扶助」は生物的本能であるとともに、社会的本能でもあります。
さて、「人間は社会的動物である」とともに、わたしが座右の銘にしている言葉があります。20世紀最大の哲学者・ヴィトゲンシュタインの「人間は儀式的動物」という言葉です。拙著『儀式論』(弘文堂)で、わたしは「人間が人間であるために儀式はある」と訴え、人類は生存し続けるために儀式を必要としたという仮説を提唱しました。ですので、本書『サピエンス全史』に儀式の話題がまったく登場しなかったことが不満であり、残念でした。
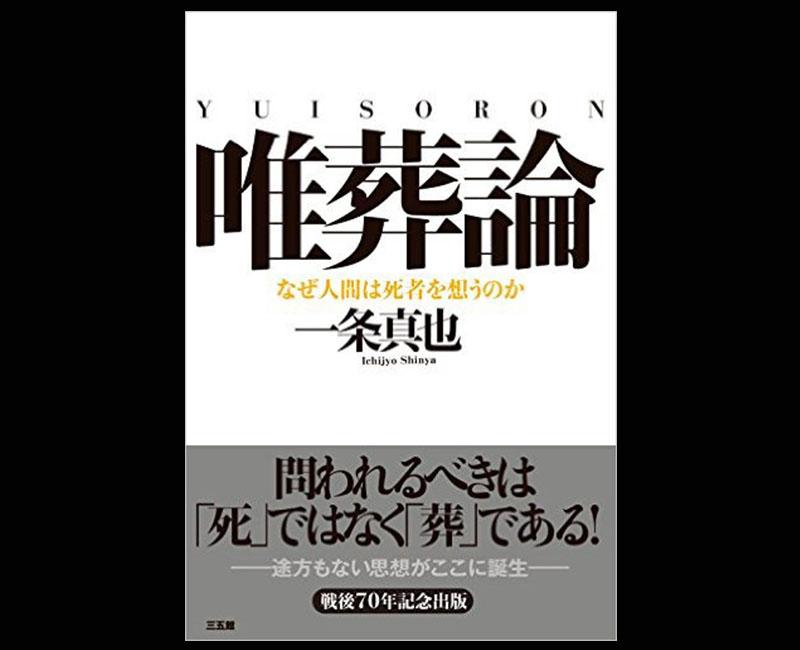 『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』 (三五館)
『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』 (三五館)
特に、人類史の重要事件である「埋葬の習慣」が出てこなかったのは非常に残念でした。拙著『唯葬論』(三五館)にも書いたように、わたしは、葬儀とは人類の存在基盤であると考えています。
「人類の歴史は墓場から始まった」という言葉がありますが、たしかに埋葬という行為には人類の本質が隠されていると言えるでしょう。それは、古代のピラミッドや古墳を見てもよく理解できます。「ギルガメシュ・プロジェクト」として、著者は「死」の問題は取り上げましたが、「死」はすべての生物に共通の現象です。人間の本質に迫るならば、問われるべきは「死」ではなく「葬」であるはずです。そのあたりが抜け落ちていることに目をつぶれば、本書は最高に知的好奇心を刺激してくれる本でした。
本書の内容は、「歴史」というよりも「教養」そのものです。