- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.06.11
『芸術学事始め』小林道憲著(中公叢書)を読みました。 2015年2月に刊行された本で、「宇宙を招くもの」というサブタイトルがついています。著者は、この読書でも紹介した『宗教とはなにか』の著者で、元福井大学教授。専攻は哲学・文明論です。
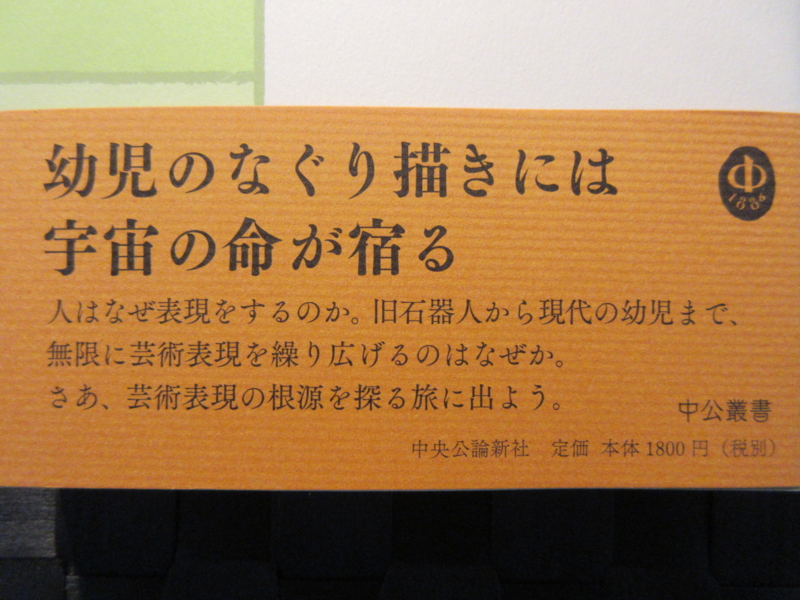 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「幼児のなぐり描きには宇宙の命が宿る」と大書され、続けて以下のように書かれています。
「人はなぜ表現をするのか。旧石器人から現代の幼児まで、無限に芸術表現を繰り広げるのはなぜか。さあ、芸術表現の根源を探る旅に出よう」
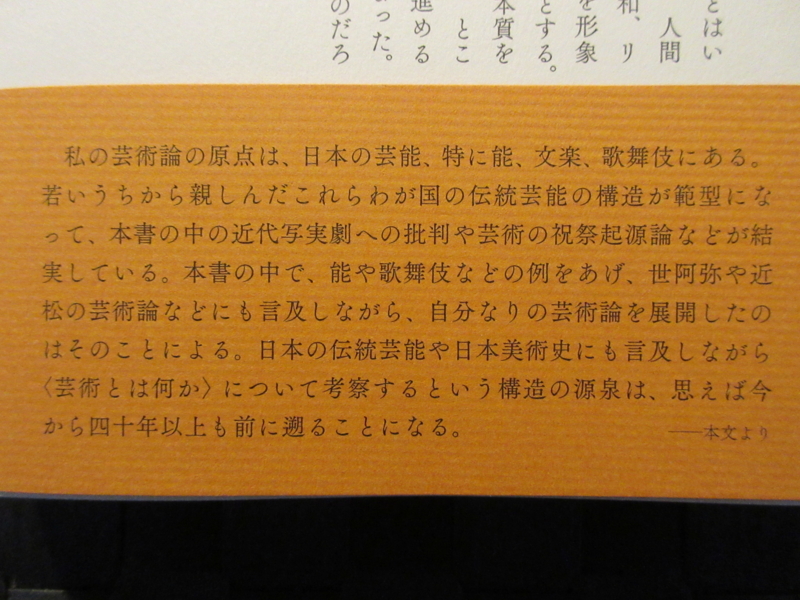 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また、カバーの裏には以下のように書かれています。
「人間の芸術は自然の再現であるとはいえ、単なる自然の模倣ではない。人間は、自然の造形が持つ均衡や調和、リズムや運動という自然の造形を形象化しながら、本質を抽出しようとする。自然の動と静、あらゆる形から本質を取りだし、抽象化するのである。ところが現代芸術は、抽象を推し進めるあまり、自然から離反してしまった。二一世紀の芸術はどこに向かうのだろうか」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
プロローグ「幼児画からの出発」
(1)芸術は祝祭から―芸術の起源
1 芸術の始まり
2 ギリシア悲劇
3 仮想空間
4 変身
5 カタルシス
(2)芸術は生命の表現―芸術の真実
1 抽象と象徴
2 生命の表現
3 表現される宇宙
(3)芸術製作の現場から―創作者たちの立場
1 創作とは何か
2 表現する身体
3 能動と受動
(4)参加する芸術―鑑賞者の視点
1 鑑賞者の参加
2 評価と解釈
(5)現代芸術の行方―何が失われたのか
1 神なき時代の芸術
2 キュービズムと抽象主義
3 シュールリアリズムと反芸術
4 アクション・ペインティングと偶然性の芸術
5 現代芸術はどこに向かうのか
エピローグ「造形の根源を求めて」
「あとがき」
(1)「芸術は祝祭から―芸術の起源」の1「芸術の始まり」で、著者は呪術について以下のように述べています。
「呪術は、単なる呪術にとどまらない。そこには、動物のうちに潜む限りない命への信仰があった。動物を捕獲して、その肉を人間が食うということは、人間がその偉大な生命力に与るということを意味していた。狩猟の成功を祈って洞窟の奥深くに生き生きと描かれた動物像の描写には、人間生活と動物の命が一体化した呪術的な力が宿っていると信じられていたのである。そこには、動物の生命力と人間の生命力の共鳴があり、それを可能にする大きな宇宙的生命力への期待があった」
また、旧石器時代の洞窟壁画を取り上げて、著者は述べます。
「呪術的行為はやがて儀礼化し、祭祀となっていく。現に、洞窟の奥深くでは、成年式が行なわれていたであろうといわれる。成年式は、少年が一人前の大人になる儀式であり、少年から子供の霊を除去して、大人の霊を宿らせる儀式である。しかも、狩猟時代には、少年を一人前の狩人にしなければならないから、少年に動物の霊力を吹き込む必要があった。そうして、はじめて、少年は大人になりえた。動物画は、そのために描かれたのである。洞窟の奥深くは聖所であり、一種の祭壇であった。獣の毛皮で身を包んだ呪術師は、そこで狩猟の踊りを踊り、動物そのものになりきって、成年を迎える少年たちに動物の霊を吹き込んだと思われる。洞窟の奥深くの聖なる場所で、呪術師と参加者は1つになり、聖なる儀礼が行なわれていたのであろう。そして、そのような儀礼から祖霊や精霊の観念が成立し、祖霊と動物霊を同一視するトーテム信仰も成立したと思われる」
続けて、著者は芸術について以下のように述べています。
「宗教は聖なるものに対する信念であり、大いなるものへの帰一の感情であるが、芸術も、また、このような呪術と儀礼に起源をもつ。舞踊や演劇は、呪術的儀礼での狩りの所作の再現から生まれ、そこから原初期の音楽や絵画も生まれた。呪術的儀礼の興奮状態こそ、日常的生からの超越であり、芸術が生まれ出る場であった。今日芸術的行為とされている舞踊、演劇、音楽、絵画、彫刻、詩などの源流を尋ねていけば、原初の呪術と儀礼に至る。逆に言えば、今日の芸術にも、一種の呪術的性格が残っているのである。芸術の歴史は、人類の歴史とともに古い」
著者は、儀礼における時間について以下のように述べています。
「時間もまた、絶えず原初の渾沌に帰って、そこから秩序を形成し、それを繰り返すものと考えられ、それが儀礼となって表現された。例えば、冬至、太陽の力が最も弱まり、太陽が西の地平線に沈んで、地下の死の世界に帰っていったとき、その太陽の力の再生を祈って、盛んな歌舞音曲を交えた儀礼が執り行なわれた。そのような儀礼から、舞踊や演劇や詩歌が生まれたのである」
また、ヨーロッパの先史文化、新石器時代の巨石建造物であるストーンヘンジ(環状列石)について以下のように述べます。
「このストーンヘンジは、祖先を葬る埋葬地から次第に神殿的意味をもつようになったものであろう。これらの巨石のまわりでは、季節ごとに歌舞音曲を交えた祭祀が行なわれていたと思われる。メンヒル(立石)にしても、ドルメン(支石墓)にしても、巨石は生命の永遠を意味し、太陽や月の再生への信仰と深くつながっていた。先史時代の芸術作品は、どれも象徴的な意味をもち、大きな宇宙観の表現であった。しかも、そのシンボルは特別な力をもち、宇宙生命への直接の通路と考えられていた。わが国の縄文文化やヨーロッパの新石器文化などに見られる同心円紋様や連続渦巻模様も、生命の永遠回帰を象徴し、先史時代の宇宙観を表現するものである。旧石器時代や新石器時代の造形芸術は、大宇宙を象徴する小宇宙だったのである」
2「ギリシア悲劇」では、「祝祭から始まったギリシア悲劇」として、著者は以下のように述べています。
「ギリシア悲劇の上演で、人間が陥らねばならない運命と人の世のはかなさを謳いあげるのは、歌舞団(コロス)であった。歌舞団は、ギリシア悲劇の誕生の母体である。もとは歌舞団だけが存在し、この歌舞団の合唱や舞踊の間に所作が挿入されることで、劇の形態が生まれた。ソフォクレスの時代になると、所作の方が優先し、所作と所作の間に歌舞団の合唱や舞踊を挿入して悲劇を構成するようになったが、歌舞団の役割は、この時代でも大きな役割を果たしている。歌舞団はもとは神の語り部であり、神の体現者であり、神への転身者であった。歌舞団が、神の定めた運命に支配されている人間の過酷な現実を謳いあげるのは、そのことに起源している」
また、ギリシア悲劇について、著者は以下のように述べます。
「今日残されているギリシア悲劇の作品群は、もともと、アテナイの国家祝祭行事であった大ディオニュシア祭で上演された台本であった。大ディオニュシア祭は、3月末、春になって新しい生命が再生するのを祝う祭である。この祭では、まず、開演に先立つ供犠の後、松明に照らされた長い行列に守られて、ディオニュソスの神像が神殿から劇場内に運ばれ、神像への献酒が行なわれた。そして、数日に及ぶ悲劇の競演が行なわれたのである。これらの悲劇の上演で歌舞団が活躍し、音楽や舞踊の要素が無視することのできない重要性をもっていたのは、悲劇の上演が春の到来を祝う祝祭に起源があったからである。春に行なわれるこの祭式をディテュラムボスというが、もともと、それは激しい踊りを意味していた。人々は、激しい音楽と踊りと陶酔の中で、ディオニュソス神の復活を祝ったのである」
さらに、この読書館でも紹介したE・ハリソンの著書『古代芸術と祭式』に言及して、「芸術は祝祭から」として、著者は以下のように述べます。
「古代エジプトでも、オシリスの祭のときには、はじめ耕作と種蒔きの儀礼が行なわれ、次いで、オシリスの受苦と復活を再現する儀礼が、毎年、奇蹟劇として演じられた。オシリス神は、死んで再生する穀霊神であり、オシリスの祭は、小麦の豊饒を祈る予祝行事であった。そして、ここでも、オシリス神話は演劇として演じられていたのである。 ハリソンの言うように、演劇は祭式から生まれる。祭式における行為(所作)をドロメノンと言うが、そのドロメノンからドラマが生まれたのだと、ハリソンは言う。行為の再現が定式化され周期的に繰り返されれば、祭式となり、そこから舞台芸術も生まれた。祝祭には誰もが参加し、そこでは、誰もが演技者であるとともに観客でもある。それどころか、この祝祭には、死んだ祖霊も参加し、神々も参加する。祝祭で演じられる舞踊や演劇の中で、人も踊り、祖霊も踊り、神も踊る。これがやがて、演じる者とそれを見る者が分離することによって、演劇や音楽や絵画など、芸術が成立する。原始的祝祭の踊りは再現的な踊りだが、そこから、ドラマも生まれてくるのである」
続けて、著者は芸術の発生について、以下のように述べます。
「芸術は、神々を祀る祭祀から始まり、祝祭から生み出されてくるのである。古代にしても、中世にしても、絵画や彫刻など、芸術作品そのものがこのような祭式から生み出されるとともに、その芸術作品自身が、神々への奉納品として、祝祭的意味をもっていた。行為が再現され、祭式化されることによって、演劇も生まれてくる。その意味では、模倣とその反復は創造である。儀礼は、身体行為を介して神々に近づくシステムであり、それはいつも演劇的構造をもっている。神々の世界へ演劇的行為によって接近することが、祝祭の本質である。祝祭そのものが、激しい音楽と舞や踊りの陶酔の中で神々の到来を祝う芸術作品である」
祝祭について、著者は以下のように述べています。
「祝祭は、われわれを日常性から解放してくれる。辛い労働から人々を解放し、日常の生活から離脱させてくれるのが、祝祭空間である。そこでは、奉献、供儀、舞踊、演劇、競技などが挙行され、人々は、この特別な聖なる時間と空間の中へ、我を忘れて没入する。この忘我の場で、人々は祖先の霊につながり、天神地祇と交わる。 祝祭の中でしばしば行なわれる無制限な浪費や底抜け騒ぎを伴うオルギー(集団の激しい興奮状態)は、天地創造の再現である」
共同体についても、著者は以下のように述べます。
「共同体は、人々がそこから生まれそこへ死す大地に支えられている。そして、そのもとで催される祝祭は、生命の復活を象徴する儀礼を通して、大いなるものとのつながりを確認 する。舞踊、演劇、音楽、絵画、彫刻、どれも、芸術作品はその象徴的表現である。だから、芸術作品は、少なくとも、それが古典的なものであるかぎり、いつも、それを超える大いなるものに支えられている。人間が支配されている運命の世界を抉り出すギリシア悲劇の世界の偉大さも、祝祭に宿る大いなるものに源泉をもっている。現代芸術とは違って、古典的な芸術作品に偉大なものが感じられるのは、それが本来祝祭空間に囲まれていたからであり、その祝祭空間が人間を越えたより大きな世界に開かれていたからである」
3「仮想空間」では、「日本芸能の祝祭空間」として述べます。
「芸術が祝祭から始まるということは、日本の芸術史を見ても言えることである。 わが国の中世芸能の始原は、古代の神楽にあるといわれる。神々を招き、その前で舞われる古代の祭の舞は、中世芸能の素型となった。実際、能楽の1つの起源、申楽は、滑稽な物真似を伴う芸能であったが、その源泉は神楽にある」
また、著者は「本来の芸能」について、以下のように述べています。
「本来の芸能は、神々を招き、神々を喜ばせるために、神々に捧げられた演技であった。そこでは、演技者も観客も神々に向かっており、両者の区別もなかった。そこから、やがて、観客と演技者が分かれ、その演技に劇的なものが付け加えられ、芸能化していった。そして、神事や祭が芸能化してくるにつれて、それを専門に担当する芸能専業者が現われ、その芸能は次第に演劇的なスタイルをもつようになっていった。演劇は祝祭から生まれ、神事から始まったのである」
この読書館でも紹介したした鎌田東二氏の名著『世阿弥』では能楽を深く考察していましたが、本書の著者である小林氏も能楽について説明します。
「能楽に登場してくる主人公(シテ)は、多くの場合、神、亡霊、鬼、精霊など、他界からの来訪者である。例えば、『紅葉狩』『土蜘蛛』『黒塚』など、切能物では、前ジテは、鬼女、僧侶、老女といった世俗の形で現われるが、後ジテは、その本性を現わし、荒々しく足を踏みならしながら悪霊となって登場し、舞台は乱拍子とともに急展開する。他方、諸国一見の僧などワキは、他界から神や霊を呼び出し、悪霊を鎮める司祭の役割を果たしている。ワキは、あの世とこの世、見所(観客)とシテ(神や霊)の仲介者であり、演能の重要な要をなしている」
続けて、著者は能楽の原型についても以下のように述べます。
「このような能楽の様式は、ギリシア悲劇同様、祭式なくして成立しなかったであろう。神や祖霊を迎え送るとともに、怨霊を鎮めるわが国古来の神事が、能楽の原型としてあり、その祝祭空間の中で、神と霊と人の交歓が、芸能という形で可能になったのである。わが国の芸能は、あの世とこの世の間、そこから命が生まれてくる以前の世界と、そこへと命が終わる死後の世界の架け橋のところに成り立つ祭式なのである」
著書は「役者」についても以下のように述べます。
「<役者>という言葉は、もとは、神社の祭祀において、一定の役割を引き受けて儀式に参加する者の意味であった。彼らは、日常では普通の市井の人にすぎないのだが、祭祀空間に入ることによって、日常から離脱し、一定の役を務める。役を務める者が役者である。とすれば、役者には、役の霊が取り憑いてくるのだと言わねばならない。演技は、役者の内面の表現ではなく、むしろ、外から霊が憑依してくる現象に近いと言わねばならない」
続けて、著者は以下のように述べます。
「その意味では、先史時代のシャーマンは、人類史最初の俳優であった。シャーマンには神や動物や精霊の霊魂が取り憑いて、彼自身、そういう異類に変身して踊った。今日の俳優の技能にも、そのような一種の呪術がある。変身も、また、祝祭的起源をもっているのである。男女異装も、祝祭的起源をもつと考えてよいであろう。祝祭のオルギーでは、男が女に変装し女が男に変装する乱痴気騒ぎがあった。そのような秩序の逆転によって、原始の渾沌を呼び出そうとしたのである。新しい秩序は、この原始の渾沌から再生してくる。それが祝祭の機能であった」
著者は、いわゆる仮面劇についても以下のように述べます。
「仮面劇の源泉は、遠く後期旧石器時代にまで遡ることができる。後期旧石器時代の洞窟壁画に描かれた呪術師らしい像は、動物の毛皮や仮面を被って、動物の霊そのものに成りきったシャーマンの姿であろう。シャーマンは動物の仮面を被り、大自然の恵みでもあった動物の多産を祈ったのである。新石器時代の、例えば、わが国の縄文時代後期の土隅の顔にも奇怪な表情をもつものが多いが、その中には、動物や女性の仮面を被っている状態のものがある。大地の恵みである動物や植物の豊穣を祈る祭が行なわれていたのであろう。農耕社会では、多くの場合、祭の折、仮面舞踏が演じられるが、その仮面は、死んだ祖先の霊、祖霊を表わすことが多い。村人は仮面をつけることによって、祖霊そのものになり、生者の生活を励ました。村人は、他界から訪れた祖霊と交流し、その年の五穀豊穣を祈ったのである」
続けて、著者は以下のように述べています。
「ヨーロッパでも、聖ニコラウスの日や冬至、大晦日や謝肉祭など、しばしば、人々が仮面をつけて仮装し踊り明かす祭が行なわれている。それは、まるで仮面や仮装の競技のようにさえ見える行事である。これは、もとはケルトやゲルマンの儀礼だったが、キリスト教の伝来とともに、キリスト教の暦に吸収されていったものである。特に、ヨーロッパの冬に行なわれる謝肉祭は、日本の小正月に行なわれていた田遊びに当たる。春を迎えるに当たり、その年の豊作を祈る予祝行事である」
仮面とは何か。著者は以下のように述べます。
「仮面は人を自由にする。祭の日、人は、仮面を被り踊ることによって異次元の空間へと超越する。と同時に、神々や精霊もこの世に来訪し、人々と交わる。仮面は、この世とあの世の交流の手だてである。演劇の源泉もここにある。たとえ仮面を用いない演劇であっても、役者は一時的に自分自身を失い、演じている役に成りきって、この世の空間と時間を超越し、観客を別世界へと誘う。そのような日常世界から離脱した次元を創り出すのが演劇であり、祝祭なのである」
続けて、模倣についても以下のように述べています。
「芸術は単なる模倣ではない。しかし、芸術を一種の祝祭として理解するなら、そこには模倣の要素が多分に含まれている。わが国の能楽の大成者である世阿弥も、『風姿花伝』の中で、申楽能の根本を(物真似)に見ている」
模倣とは、単に写実的に模写したり、複製することではありません。 それは再現することによって、ものに表現を与えることなのです。 さらに著者は、以下のように述べています。
「再現には<共鳴>ということが含まれる。例えば、歌舞伎の変化舞踊では、その名人ともなると、花を見ている役者が花と一体化し、腰や肩、扇を持つ手、すべてがひとりでに動いて花の感じを見事に表現し、花の精そのものになる。そこには、花と役者が同じ呼吸によって支配され、同調し、共鳴するということがなければならない。模倣とは共感であり、共鳴なのである。そうして、はじめて、それを見ている観客も、その役者の身体の動きに共鳴し、吸い込まれるように陶酔感に陥っていく。そこに舞踊の祝祭性がある。模倣には深い意味があると言わねばならない」
続けて、著者は再びハリソンの『古代芸術と祭式』に触れ、述べます。
「ハリソンの言っているように、原始時代にも、シャーマンは毛皮や鳥の羽で仮装し、化身する動物たちの動作や叫びを真似て踊った。その踊りが過去の狩猟や戦闘を再現する踊りである場合でも、これらの戦闘や狩猟における成功を祈っての踊りの場合でも、どちらにも模倣という要素がみられる。しかも、そこには、再び提示するにしても、前もって指示するにしても、再現という現象がある。模倣とは再現であり、再提示なのである」
続けて、模倣について、著者は以下のように述べます。
「人間は、模倣されたものを見て喜ぶ。観客は、巧みに模倣されたものを舞台の上に見て楽しむ。わが国の古典芸能、人形浄瑠璃でも、人形が人間のしぐさを巧みに真似すると、観客は感動する。本物だけでは誰も褒めはしないが、本物をいかにも本物らしく真似ると褒められる。再現することは本質を表現することであり、そこにいわば〈もののあはれ〉がある」
ここで、芸術の本質について、著者は以下のように述べます。
「芸術は、神々の世界に遊び、神々と交わることなのだと言えよう。わが国の芸能の始原にも神楽があり、これを〈カムアソビ〉と言った。神々と一つになって遊び、また、神々を遊ばせることが、歌や踊りの原初形態だったのである」
そしてホイジンガの『ホモ・ルーデンス』をあげて、以下のように述べます。
「ヨハン・ホイジンガの言うように、祭祀は、聖なるものとして、極めて質の高い神秘さと真剣さによって営まれる反面、それは常に遊びである。ここでは、遊びと真面目の対立は消え去る。聖なるものと遊戯が一つになっているのが祭祀であり、祝祭であった。祝祭の場では、世界は神々のうちに場を占め、神々しい世界と化す。日頃のありふれたものも新しい意味をもち、光を当てられる。祝祭空間の中で、人々は、歌い、踊り、仮装し、遊び狂う。そして、人々は非日常的な世界へと脱出し、我を忘れる。このように、実際生活の合理性を超えて、人々を別の世界へと解き放ち、本来の人間存在へと回帰させるのが、祝祭空間であり、遊びの空間であり、芸術空間なのである」
「演劇のカタルシス」では、演劇の起源について、著者は述べます。
「一般に、わが国でも、ヨーロッパでも、演劇は宗教的起源をもつものが多い。神や仏の愛や慈悲を説く宗教伝説の地盤から、舞台芸術が生まれてくる。わが国の人形浄瑠璃も、本地霊験物を起源としている。神仏の加護による蘇生譚や神仏の身代わり譚を主題にした説教節が人形芝居に仕立てられ、それが神社や寺院の祭礼などで演じられた。 芸術作品を、美しいもの、偉大なもの、荘重なもの、崇高なものにするのは、その背景にある宗教性である。そのような芸術作品は、神仏との交渉の中で、神仏の前での人間の卑小さ、人間的悲しみを語り、常に人間を超えた大きな世界を見ている。そういう宇宙的広がりが、芸術作品を偉大なものとしているのである」
さらに著者は、芸術作品の起源について述べています。
「芸術作品は祭祀に起源をもつ。宇宙的出来事を再現し、目に見えない世界を目に見える世界に表現するのが祭祀であり、芸術である。芸術作品を祝祭空間が取り囲み、その祝祭空間はより大きな宇宙観に支えられている。どんな芸術作品も、人間を超える偉大なものに支持されていなければ、卑小なものになってしまう。大いなるものは、われわれの住む世界に意味を与える。芸術作品大いなるものの象徴であり、大いなるものの顕現である。われわれは、それを通して大いなるものとつながり、大いなるものに帰一する。芸術作品は宇宙的なものの表現であり、宇宙的なものの顕現でなければならない。われわれは、それを通して宇宙創世の力に与り、宇宙万物と一つになる。1つの芸術作品は、マクロコスモスを映すミクロコスモスなのである」
(2)「芸術は生命の表現」の3「表現される宇宙」では、いわゆる宗教建築物について以下のように述べられています。
「寺院や神殿など、聖なる建築物は宇宙の象徴である。その聖なる空間は宇宙の中心にあり、中心から広がる円形や方形の建造物は宇宙の似姿である。その建立は宇宙創世を象徴し、永遠の宇宙を象徴する。聖なる建築物の芸術性もそこに起源をもつ」
また、茶室についても、以下のように述べられています。
「わが国の特に室町時代から戦国時代にかけて完成された芸道には、一般に、極限された一点に全宇宙の働きを凝縮し、そこに美の表現を見ようとする傾向がある。茶道も、その1つである。特に、わび茶は、それまでの唐物荘厳の異国趣味を廃し、座敷飾りも最小限に圧縮し、格式も簡素化し、清貧の美を求めていった。茶室も、村田珠光、武野紹鴎、千利休へと降るに従って、ますます狭くし、四畳半から二畳にまで縮めた。そのため、茶室の空間は緊張し、清潔・静寂な空間を濃密な気がはしり、逆に無限の広がりをもつようになった」
(5)「現代芸術の行方―何が失われたのか」の1「神なき時代の芸術」では、「世界像の喪失」として、以下のように書かれています。
「ヨーロッパ各地に遺されている新石器時代の巨石建造物は、そこで祖霊を祀り死者の鎮魂の儀礼を行なった聖なる建造物であった。それらが広大な大地に根差し、天に向かって建てられているのも、そのような宗教的意味がある。それが、われわれ現代人から見ると偉大な野外芸術にさえ見えるのも、その背景に、コスミックな宗教的世界観があったからである」
新石器時代の巨石建造物とは死者のための建造物だったのです。 まさに『唯葬論』(三五館)でわたしが訴えた「人類の文明も文化も、その発展の根底には『死者への想い』があった」というメッセージを思い出しますが、続けて著者は次のように述べています。
「古代エジプトやメソポタミアの壮大な神殿の偉大さも、その神殿が天上・地下の神々と深くつながっていることからくる。古代の神殿は、天と地と冥界の交差する聖なる場所であった。人々は、神殿という聖なる空間で、天上・地上の神々に思いを寄せ、神々と交歓したのである。神殿を支える高く大きな柱は、天上と地上と地下を貫く柱であり、宇宙を支える宇宙樹の象徴である。それを通して、神々は降臨してくる。その柱の回りを廻って舞い、神々を迎える儀式が、舞踊の起源となった。芸術は、神々を祀る儀礼や祝祭から生まれたのである」
また、芸術が生まれる世界像について、著者は述べます。
「古来、天は崇高、無限、至上、永遠の象徴であり、大地は、永遠の生命、死と再生、豊穣の象徴であった。天と地は相合して万物を生み出し、その天地未分の宇宙の根源的力に与って、人は永遠の生命を得ることができると考えられていた。人々は、人間の力を越えた偉大な宇宙の力への畏怖の念をもち、その大いなるものへの畏怖の感情から、巨石を建て、神殿を造り、教会や寺院を建立し、神像や聖画を描き、塑像を彫った。芸術作品は、それを通して、われわれが永遠の深みへと導き入れられる象徴であり、大いなるもののシンボルであった。有限なものの中に無限なものを表現し、目に見えるものの中に目に見えないものを表現することが、芸術という人間の営みにほかならなかった。すぐれた芸術作品が生み出されるには、そういう世界像がなければならない」
5「現代芸術はどこへ向かうのか」では、「変質した祝祭」として、以下のように述べられています。
「現代では、芸術の本来の場所であった祝祭も大きく変質する。 芸術作品が美術館や博物館、演奏会場や劇場に移されるようになったのは近代になってからであるが、これらは、かつての聖空間の代用物である。これらの空間も一種の祝祭空間ではあるが、そこには聖なるものに通ずる場所がなく、芸術作品は孤立している。 現代の祝祭空間は、むしろスポーツ競技場や娯楽施設、イベント会場や博覧会などに見られるが、ここにも、かつて祝祭がもっていた聖なる世界がない。それどころか、国威発揚のために大がかりに企画されたオリンピックや万博、商業活動に組み込まれた巨大な遊園施設や百貨店のイベントなど、現代では、祝祭が巨大な産業技術文明に組み込まれてしまっている」
続けて、著者は現代の祝祭空間について、以下のように述べます。
「さらに、ラジオやテレビなど、現代のマス・メディアの発達によって、身体を運ばなくても、これらが映像や音声を通してリアルタイムで送られてくる。現代の祝祭空間は、このマス・メディアを通して巨大な広がりを見せるのだが、毎時間、そのような劇場空間を居ながらにして見せられていると、祝祭はその意味を失う。マス・メディアによる神聖さを失った祝祭空間、それが現代の祝祭空間である。ここでは、労働の時間と祝祭の時間、ケの時間とハレの時間の区別がなくなり、労働と祝祭の両方の意味が失われる」
そして「あとがき」では、著者は芸術について以下のように述べます。
「花にこそ春は宿るように、1つの芸術作品は根源的生命の象徴として現われ出るものであり、いわば宇宙生命の表現である。花の中に春を描く、それが芸術である。<人はなぜ芸術するのか>、その表現衝動の源泉にも、宇宙衝動とでも言うべきものがある。芸術は根源的生命から現われ出てくる出来事であり、再創造であり、再現前化である。芸術は、いわば命の輝きなのである」
