- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2120 社会・コミュニティ 『「利他」とは何か』 伊藤亜紗・中島岳志・若松英輔・國分功一郎・磯崎憲一郎著(集英社新書)
2022.04.13
『利他とは何か』伊藤亜紗・中島岳志・若松英輔・國分功一郎・磯崎憲一郎著(集英社新書)を読みました。「ケア」について考え続けているわたしは、「ケア」と「利他」は密接に関わっているととらえているのです。共著者ですが、伊藤氏は美学者で、『記憶する体』を中心とした業績でサントリー学芸賞受賞。中島氏は政治学者で、『中村屋のボース』で大佛次郎論壇賞受賞。若松氏は批評家・随筆家で、『小林秀雄 美しい花』で蓮如賞受賞。國分氏は哲学者で、『中動態の世界』で小林秀雄賞受賞。磯崎氏は小説家で、『終の住処』で芥川賞受賞。全員が、素晴らしい賞を受賞しています。この5人は、東京工業大学の中にある人文社会系の研究拠点「未来の人類研究センター」のメンバーとして、現在進行形で「利他」の共同研究を行っているそうです。
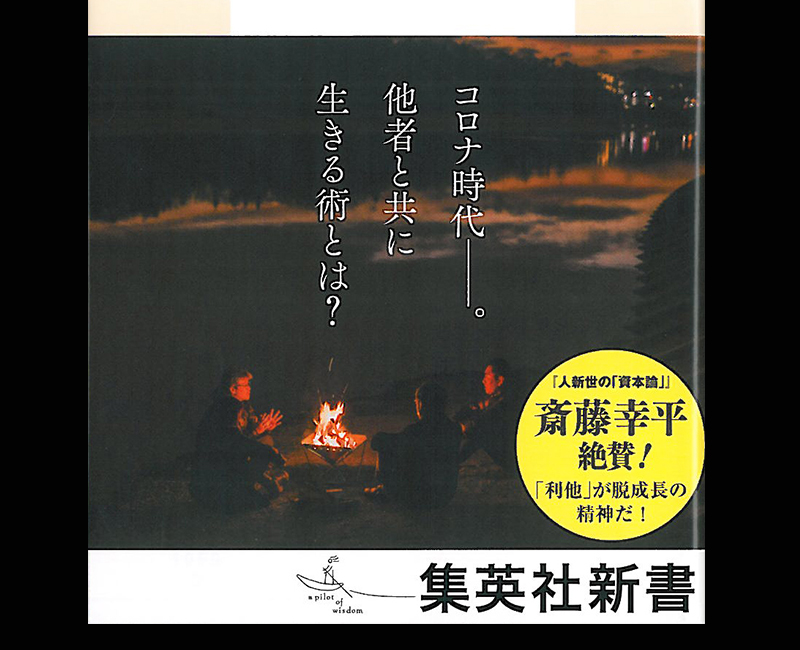 本書の帯
本書の帯
帯には焚火にあたる人々の写真が使われ、「コロナ時代――他者と共に生きる術とは?」「『人新世の「資本論」』斎藤幸平絶賛!」「『利他』が脱成長の精神だ!」と書かれています。カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「コロナ禍によって世界が危機に直面するなか、いかに他者と関わるのかが問題になっているそこで浮上するのが『利他』というキーワードだ。他者のために生きるという側面なしに、この危機は解決しないからだ。しかし道徳的な基準で自己犠牲を強い、合理的・設計的に他者に介入していくことが、果たしてよりよい社会の契機になるのか。この問題に日本の論壇を牽引する執筆陣が根源的に迫る。まさに時代が求める論考集」
 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
はじめに――コロナと利他(伊藤亜紗)
第1章:「うつわ」的利他――ケアの現場から(伊藤亜紗)
第2章:利他はどこからやってくるのか(中島岳志)
第3章:美と奉仕と利他(若松英輔)
第4章:中動態から考える利他――責任と帰責性(國分功一郎)
第5章:作家、作品に先行する、小説の歴史(磯崎憲一郎)
おわりに――利他が宿る構造(中島岳志)
「はじめに――コロナと利他」の冒頭を、伊藤亜紗氏は以下のように書きだしています。 「新型コロナウイルスの感染拡大によって世界が危機に直面するなか、『利他』という言葉が注目を集めています。たとえば、フランスの経済学者ジャック・アタリは、2020年4月11日に放送されたNHK番組『ETV特集 緊急対談 パンデミックが変える世界~海外の知性が語る展望~』に出演し、パンデミックを乗り越えるためのキーワードとして『利他主義』をあげています。深刻な危機に直面したいまこそ、互いに競いあうのではなく、『他者のために生きる』という人間の本質に立ちかえらなければならない、と」と
ビジネスの現場においても、利他という言葉を耳にする機会が増えてきたとして、伊藤氏は「ビジネスと利他というと稲盛和夫氏が有名ですが、最近では、やはりより若い世代のあいだで利他というキーワードが広まりつつあるようです。たとえば、ファッションの世界。ファッションというと自分を着飾る利己的なイメージがありますが、もはやそれだけではないのです。ファッション誌『Harper’s BAZAAR』の編集長、塚本香さんは、『今、ファッショナブルって何?」というコーナーで、ファッショナブルを定義するうえで「利他主義もこれからの重要なエレメントになる」と語っています(「Harper’s BAZAAR」2020年11月号)』と紹介します。
いまのファッションのあり方は、環境に対する負荷が非常に大きくなっているといいます。2019年にはついに、国連貿易開発会議で、ファッションは「世界で第2位の汚染産業」との汚名を着せられてしまいました。また、伊藤氏は「科学技術も、社会の営みも、本来は利他的なものであったはずです。にもかかわらず、私たちがこれほどまでに問題を抱えるようになったのはなぜなのか。そのためにはただ『利他主義が重要だ』と喧伝するだけでは不十分であるように思います。利他ということが持つ可能性だけでなく、負の側面や危うさも含めて考えなおすことが重要になってくるでしょう」と述べます。
第1章「『うつわ』的利他――ケアの現場から」の「利他ぎらいが考える利他」では、キリスト教の「隣人愛」や、浄土真宗の「他力」など、利他の考え方は伝統的に宗教的な価値観と密接に結びついていたと指摘しています。伊藤氏は、「現代における利他という言葉は、しばしば宗教的な文脈とは切り離されて流布するようになっています。その結果、『利他』の輪郭もかなり曖昧なものになっているように思います」と述べます。その流れの中で際立つアタリの利他主義の特徴は、その「合理性」です。件のNHKの番組で、アタリは「利他主義とは、合理的な利己主義にほかなりません。みずからが感染の脅威にさらされないためには、他人の感染を確実に防ぐ必要があります。利他的であることは、ひいては自分の利益になるのです。またほかの国々が感染していないことも自国の利益になります。たとえば日本の場合も、世界の国々が栄えていれば市場が拡大し、長期的にみると国益にもつながりますよね」と語っています。
このアタリの発言について、伊藤氏は「合理的利他主義の特徴は、『自分にとっての利益』を行為の動機にしているところです。他者に利することが、結果として自分に利することになる。日本にも『情けは人のためならず』ということわざがありますが、他人のためにしたことの恩恵が、めぐりめぐって自分のところにかえってくる、という発想ですね。自分のためになるのだから、アタリの言うように、利他主義は利己主義にとって合理的な戦略なのです」と述べています。
「私にできる最大の善――効果的利他主義」では、伊藤氏は以下のように述べています。 「自分にできる〈いちばんのたくさんのいいこと〉。ポイントは、『いちばんたくさんの』というところにあります。最大多数の最大幸福。つまりこれは『功利主義』の考え方です。効果的利他主義は、単に功利主義をとなえるにとどまらず、幸福を徹底的に数値化します。たとえば自分の財産から1000ドルを寄付しようとする場合、それをどの団体に、どのような名目で寄付をすると、もっとも多くの善をもたらすことができるのか。得られる善を事前に評価し、それが最大になるところに寄付の対象を定めることによって、効率よく利他を行おうとするのです」
「共感を否定する『数字による利他』」では、「効果的利他主義は、なぜここまで数値化にこだわるのか」という問いを提示し、伊藤氏は「それは、利他の原理を『共感』にしないためです。最近親戚ががんで亡くなったから、がん治療の研究をしている組織に寄付をしよう。職場に視覚障害者がいるから、盲導犬の育成を行っている団体に寄付しよう。こんなふうに考えるのが、共感にもとづく利他だ、と彼らは言います。日本風にいえば、『ご縁』があったもの、精神的物理的に近いものに対して、施しをしようとする。ところが、効果的利他主義は、こうした共感にもとづく利他を否定します。共感にもとづいて行動してしまうと、ふだん出会うことのない遠い国の人や、そもそもその存在を意識していない問題にアプローチできないからです」と答えます。
「ブルシット・ジョブ」では、一条真也の読書館『ブルシット・ジョブ』で紹介したアメリカの文化人類学者デヴィッド・グレーバーの著書が取り上げ、伊藤氏は「ブルシット・ジョブとは、実際には『完璧に無意味で、不必要で、有害』なのに、あたかも『意味があって、必要で、有用』であるかのように振る舞わなければいけない雇用形態のことです。なくても済むのに部下を監督するマネージャー職。リクエストを担当者に回すだけのコーディネーター職。グレーバーの本には、世界中から寄せられた『自分の仕事をブルシットだと感じている人』からの報告があふれています」と述べます。
新型コロナウイルスは、私たちの仕事のあり方に大きな問いを投げかけました。伊藤氏は、「医療従事者や物流業者といった、生活を支える『エッセンシャルワーカー』に光が当たる一方、在宅勤務を始めた人のなかには、これまで当たり前のようにやってきた業務のなかにも、必要なものとそうでないものがあることを自覚した人が多かったのではないかと思います」と述べます。わたしは、冠婚葬祭業もエッセンシャルワークに含まれると考えています。しかも、冠婚葬祭業は他者に与える精神的満足も、自らが得る精神的満足も大きいものであり、いわば「心のエッセンシャルワーク」「ハートフル・エッセンシャルワーク」とでも呼ぶべきでしょう。
ブルシット・ジョブではないかと疑問視されている仕事の1つに、はんこを押すことがあります。伊藤氏は、「はんこは日本のひとつの文化ではありますが、それによって手続きが理不尽なほど煩雑化し、さまざまな業務の障壁になってきたことも事実です。紙に出力することになるので、環境にも不必要な負荷がかかります。雇用形態そのものではありませんが、はんこは、私たちの身の回りにある典型的なブルシット的業務です。この点に関して見直しが進んだことは、コロナが仕事にもたらしたポジティブな効果ということができます」と述べています。
「ケアすることとしての利他」では、伊藤氏は「他者の潜在的な可能性に耳を傾けることである、という意味で、利他の本質は他者をケアすることなのではないか」という考えを示します。ただし、この場合のケアとは、必ずしも「介助」や「介護」のような特殊な行為である必要はないとして、「むしろ、「こちらには見えていない部分がこの人にはあるんだ」という距離と敬意を持って他者を気づかうこと、という意味でのケアであるといいます。耳を傾け、そして拾うことです。
ケアが他者への気づかいであるかぎり、そこは必ず、意外性があるとして、伊藤氏は「自分の計画どおりに進む利他は押しつけに傾きがちですが、ケアとしての利他は、大小さまざまなよき計画外の出来事へと開かれている。この意味で、よき利他には、必ずこの『他者の発見』があります。さらに考えを進めてみるならば、よき利他には必ず『自分が変わること』が含まれている、ということになるでしょう。相手と関わる前と関わった後で自分がまったく変わっていなければ、その利他は一方的である可能性が高い。『他者の発見』は『自分の変化』の裏返しにほかなりません」と述べます。
「うつわ的利他」では、利他についてこのように考えていくと、利他とは「うつわ」のようなものではないかというイメージが浮かぶとして、伊藤氏は「相手のために何かをしているときであっても、自分で立てた計画に固執せず、常に相手が入り込めるような余白を持っていること。それは同時に、自分が変わる可能性としての余白でもあるでしょう。この何もない余白が利他であるとするならば、それはまさにさまざまな料理や品物をうけとめ、その可能性を引き出すうつわのようです」と述べます。哲学者の鷲田清一氏は、患者の話をただ聞くだけで、解釈を行わない治療法を例にあげて、ケアというのは、「なんのために?」という問いが失効するところでなされるものだ、と主張しています。他者を意味の外につれだして、目的も必要もないところで、ただ相手を「享ける」ことがケアなのだ、と言うのでした。
「余白をつくる」では、再び『ブルシット・ジョブ』の著者であるデヴィッド・グレーバーに言及し、伊藤氏は「ブルシット・ジョブについて指摘したグレーバーは、あらゆる人間的な仕事は本質的にはケアリングであると指摘しています。川に橋をかけるのは、そこを渡りたいと思う人をケアするためでしょう。改札が自動化しても駅員が待機しているのは、重い荷物を持った人やその土地に不案内な観光客をケアするためでしょう。ところが、人々が数字のために働き、組織が複雑化して余白を失っていくにつれて、仕事からケアが失われていきます。「仕事のケアリング的な価値が、労働のなかでも数量化しえない要素であるようにみえる」(『ブルシット・ジョブ』)からです。その先にあるのは、自分がなんのために働いているのか、利他の宛先のない、虚しい労働でしょう。仕事は、ただ生活の糧を得るためだけの手段になってしまうでしょう」と述べます。
「利他の『他』は誰か」では、『荷を引く獣たち――動物の解放と障害者の解放』で種を超えたケアについて語ったスナウラ・テイラーが取り上げられます。彼女は画家であり作家、そして障害者運動と動物の権利運動の担い手です。同書は、「もし動物と障害者の抑圧がもつれあっているのなら、もし健常者を中心とする制度と人間を中心とする倫理がつながっているのなら、解放への道のりもさらに、交差しているのではないか」と問いかけ、「壊れやすく、依存的なわたしたち動物は、ぎこちなく、不完全に、互いに互いの世話をみる」ことを訴えた本で、アメリカン・ブック・アワード(2018年度)を受賞しています。伊藤氏は「テイラーの主張の根本にあるのは、自然は人間が思うよりずっと相互扶助的なものだ、ということです。これは、私自身、理工系の研究者と話していて、目を開かされた点でもあります」と述べています。
ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典氏は、「生物学の世界において、種を保存するために『利他』ということは、当たり前のこととしてたくさんあるんじゃないかな、という気がします」と語ったそうです。17世紀の哲学者トマス・ホッブズは、人間の自然状態を「万人の万人に対する闘争」と言いましたが、伊藤氏は「しかし本当にそうなのか。あまりに競争の側面にばかり気をとられてきたこれまでの人間のあり方を利他的なものにしていくためには、自然に対するとらえ方から考えなおしていかなければいけないのかもしれません」と述べるのでした。
第2章「利他はどこからやってくるのか」の「『小僧の神様』と利他」では、志賀直哉の短篇小説「小僧の神様」が取り上げられます。神田の秤屋で奉公をしている仙吉(小僧)は、番頭達の話で聞いた鮨屋に行ってみたいと思っていました。ある時、使いの帰りに鮨屋に入るものの、金が足りずに鮨を食べることができない仙吉を見かけた貴族院の男(A)は、後に秤屋で仙吉を見つけ、鮨を奢ります。鮨を奢られた仙吉は「どうして番頭たちが噂していた鮨屋をAが知っているのか」という疑問から、Aは神様ではないかと思い始めます。仙吉はつらいときはAのことを思い出しいつかまたAが自分の前に現れることを信じていた。一方Aは人知れず悪いことをした後のような変に淋しい気持ちが残っていました。中島岳志氏は、「この小説のテーマは利他という問題と深く関わっています。発表は、日本がスペイン風邪第2波に直面していた1920年1月。100年前のパンデミックのさなかに、志賀直哉は利他の問題を考えていたのです」と述べています。
「ポトラッチ――贈与と負債」では、一条真也の読書館『贈与論』で紹介したフランスの社会学者マルセル・モースの著書の内容に言及し、中島氏は「私たちは誰かからプレゼントをもらうと、『やったー! うれしい!』と感じるだけではなく、お返しをしなければならないという観念にかられる。相手から一方的にもらうばかりでこれがずっとたまってくると、両者のあいだに上下関係のようなものが生まれてくる。与える側ともらう側という、負い目をベースとした上下関係ができてしまう。贈り物を受け取った側は、貸し付けられたものというような認識を持ってしまい、いずれ子孫を含めて返済しなければいけないというふうに考えるわけです」と述べます。
 児童養護施設からの「こころの贈り物」
児童養護施設からの「こころの贈り物」
ちなみに、ブログ「こころの贈り物」に書いたように、わが社は児童養護施設のお子さんたちに七五三や成人式の晴れ着をプレゼントしましたが、わたしたちは、けっして一方的に児童養護施設のお子さんたちに贈り物をしたのではありません。わたしたちも素晴らしい「こころの贈り物」をいただきました。そして、お互いが「こころの贈り物」を贈り合う行為を「ケア」というのです。相手を支えることで、自分も相手から支えられることを「ケア」というのです。「ありがとう」と言ってくれた相手に対して、こちらも「ありがとう」と言うことが「ケア」なのです。そう、「サービス」は一方向ですが、「ケア」は双方向です。わが社は、サービス業からケア業へと進化したいと願っています。
中島氏は有名な「わらしべ長者」の話にも言及します。Wikipedia「わらしべ長者」の「あらすじ」にストーリーは紹介されていますが、中島氏は「これは仏教説話ですから、長谷観音の霊力というのを説いているのでしょう。利他や贈与という文脈からこの物語を読むとき、重要なポイントは最初の交換にあります。青年は、夢のお告げにしたがって手にした藁を、それを欲しがる子どもにあっさりとあげてしまう。この段階では、青年は長谷観音が物をどんどん大きな富へと変換してくれることに気づいていません。しかも、藁をあげたらミカンがもらえるとも思っていない。ものすごく不用意に、大切な物をぱっとあげてしまっている。つまり、この一箇所だけが、大切な物の一方的な贈与になっているのです」と述べています。
「結果としての間接互恵システム」では、青年がふいに藁をあげてしまうという行為に、中島氏はは、利他の根本にある非常に重要な問題があるとして、「この贈与には、いい人だから贈与という行為をするという、善と利他をつなげる問題を超えた何かがあります。青年の動機を合理的に説明することはできません。『思わず』とか『ふいに』としかいいようがないものによって行われる行為です。そこにはおそらく、後ろから押す力、あるいは意思に還元されない何かが働いている。人間の合理的な意思の外部によって起こされる力によって、この藁は贈与されたのだと思います。そして具体的な利益は事後的にやってくる」と述べています。
中島氏は、ポイントは結果としての間接互恵システムであると指摘します。間接互恵の非常に重要な本質は、不確かな未来によって規定されているという逆説にあります。つまり、かえってこないかもしれないし、どうなるか分からないけれどもやってしまうという行為によってこそ、間接互恵システムは成り立っているとして、「これは巨視的な観点で働いている、人知を超えたメカニズムであって、私がこれを『オートマティカルなもの』だと考えます。理系の研究者のお話ですとすごく感動を覚えるのは、植物の光合成や惑星の自転・公転などと、この『オートマティカルなもの』が何かつながるような感覚がああるからなのです」と述べます。
さらに、中島氏は以下のように述べています。
「ただ心臓が動いていることとか、免疫細胞の働きだとか、私たちの意思に還元されないものによってこそ、世界の大半のものが動いている、そしてその力を人間はもっとコントロールできる、あるいは、その力を認知できるという発想が強かった。けれども、そんなものをはるかに超えたところでいろいろなものがオートマティカルに動いていること、その大きな力自体を私たちが直視することから解体されていく世界があるのではないか。そこにあらわれているものこそ『利他』としか名づけようのないものではないでしょうか」「『聖道の慈悲』と『浄土の慈悲』」では、伊藤氏は、自分はオートマティカルなものを自然科学の話としてお話しすることはできないけれども、宗教の話でいえば、たとえば、伊藤氏が慣れ親しんだ親鸞は、「オートマティカルなもの」を「他力」という概念でとらえているとして、「親鸞は、『歎異抄』第四条で、慈悲にはふたつある、という言い方をしています。善いことをしようと思ってする聖者の行いが『聖道の慈悲』で、浄土からおのずとやってくるのが『浄土の慈悲』です。つまり、親鸞は『聖道の慈悲』を自力、『浄土の慈悲』を他力と考えているわけです」と述べます。
中島氏は、親鸞の「悪人正機」という概念にも言及し、「いろいろな説明の仕方があると思いますが、罪には英語でいうクライム(crime)とシン(sin)があるとすると、親鸞がとなえた悪あるいは罪には、人間のどうしようもなさという問題が含まれるので、親鸞が意味するところはシン(sin)の領域でしょう。クライム(crime)は犯罪ですけれども、シン(sin)には存在すること自体の罪の問題が含まれています。人間がどんな善行を行おうと、それでもなおどうしようもなさというものに支配されている。そんな私たち、煩悩具足の凡夫は、その支配の構造、つまり自分の無力を果たして認識することができるのか。もし、それを認識した人間であれば、人間の限界、自己の限界という無力に立つことができる。この無力を知ることができた人間にやってくるのが『他力』であるというのが、親鸞の思想構造です」と述べるのでした。
第三章「美と奉仕と利他」の「『利他』の原義――『利』とはなにか」では、若松英輔氏が、「『利他』はもともと仏教の言葉です。仏教で『利』という言葉は肯定的な意味を指すことが多い。しかし、儒教では必ずしもそうではありません。『利』は、目先の、そして自分だけの利益を指すことが少なくないのです」と指摘し、「仏教において『利』は、『利益』『利根』『利生』などよきものを示すときに用いられます。『利益』は、物心両面にわたって福利をもたらすことを意味します。現世利益という言葉があります。あまりよい意味では用いられませんが、そう感じるところには、現世で終わるものではなく、後の世でこそ花開くのが真の利益であるという認識があるからです。利益という言葉には、そもそも現世に終わらないよき働きが含まれています。『利根』は、宗教的、霊性的素質において優れていることを指しますし、『利生』は、衆生に利益を与えることを意味します。こうした数例を確かめるだけでも『利』が仏教のなかでいかに重要な言葉であるかが分かります」と述べています。
仏教には「自力」「他力」という言葉があります。「自力」とは人間が自分の力で何かをなそうとすることですが、「他力」は自分では何もせず、仏のちからによって何かが起こるのを呆然と待つことではないとして、若松氏は「人間と仏が、人と仏の二者のままでありながら、『一なるもの』になることです。仏教における『他』には『自他』を超えた『他』という意味があるのです。そう考えると、利他における『他』も、自分以外の他者ではなく、『自』と『他』の区別を超えた存在ということになります」と述べます。
最澄は、「他を利するには自己を『忘れ』なくてはならない」と述べ、空海は、「仏教は『自利』と『利他』の2つの支柱からなる」と書きました。若松氏は、「2人は近似したことを語っていると考えることもできますが、似て非なるものであるということもできます。最澄の志は高く、どこまでも透明です。真の意味で自己を手放せと促す最澄には、そこを仏がすくい上げてくれる、という絶対の信頼がある。しかし、空海は『自利』を否定しない。空海は自利と利他の『二利』がある、といいながら、それを超える真の『利』があることを暗示しているようにも見えます。最澄、空海は文字通りの意味で霊性の巨人ですが、1つの言葉をめぐる理解を見るだけでも、それぞれの特徴が浮かび上がってきます」と述べています。
「沈黙という秘義」では、利他は行為の中に顕現しますが、言葉によって説明した途端に本質が見えにくくなると指摘されます。利他が成就していても、それをめぐって語り始めたときに虚飾を帯びるといった現象はわたしたちが日々、目にするところであるとして、若松氏は「語らずに行う。あるいは人目に隠れたところで行うことを、陰徳を積むといいます。『新約聖書』や『論語』を読んでも陰徳を促す文言に出会うのは珍しくありません。イエスは、『右の手のすることを左の手に知らせてはならない』(『マタイによる福音書』6章3節フランシスコ会聖書研究所訳注)と述べたと記されています」と述べます。
また、『論語』には「徳は孤ならず。必ず鄰あり」という孔子の言葉が収められています。「徳ある者は、あえて声をあげる必要などない、必ず志を同じくする者に出会う」というのです。若松氏は、「こうした言葉は、言葉の限界と誤り易さを示す言葉であるとともに沈黙のちからを説く言説として読むこともできます。行いによって利他は始まり、沈黙によってそれは定まるという原理を先賢たちは説いているのです」と述べ巻ています。若松氏というとキリスト教を信仰されている方と思っていましたが、このように仏教や儒教にも通じておられるのは素晴らしいことだと思いました。
若松氏は、「利他」の問題を「美」にまで求めます。民藝運動を展開した宗教哲学者の柳宗悦の「芸術の理解がその民族を理解する最も根本的な道だと云う兼々の信念と、芸術が国の差別を越えて、吾々を結合の喜びに導く力だと云う信念とを、具体化せねば止まない決心でいる(『朝鮮を想う』)」という言葉を取り上げ、「柳宗悦にとって、人間の争いを食い止めるものが美でした。美は人を沈黙させ、融和に導く。さまざまなことについて対話し、その彼方に何かを見出していくというよりも、沈黙を経た彼方での対話ということを、彼は考えていたのでしょう。利他というものも、そういう枠組みの中で起こってきたし、起こっている。そして、これからも起こっていくのではないかと思います」と述べるのでした。
「おわりに――利他が宿る構造」の冒頭に、中島岳志氏は「『利他』の反対語は『利己』ですが、このふたつは常に対立するものではなく、メビウスの輪のようにつながっています。利他的な行為には、時に『いい人間だと思われたい』とか『社会的な評価を得たい』といった利己心が含まれています。利他的になろうとすることが利己的であるという逆説が、利他/利己をめぐるメビウスの輪です」と書いています。本書を読んで「利他」とは「ケア」そのものであると言うことが理解できました。また、「利他」が仏教だけではなく、儒教やキリスト教にも通じる人類の普遍思想であるという可能性が見えてきました。もっと「利他」について知りたいので、次は中島氏の単著である『思いがけず利他』を読んでみたいと思います。