- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.07.19
『黄金と生命』鶴岡真弓著(講談社)を読みました。
2007年に刊行された485ページの大著で、「時間と錬金の人類史」というサブタイトルがついています。農耕、神話、宗教、哲学、科学、国家、貨幣・・・・・・限りある命を乗り越えるための技と知=錬金術の軌跡を追い、一万年以上、魂を突き動かした光源=「万物の王」の正体に迫る力作です。「生命表象としての黄金」を鍵として人類史を俯瞰し、西洋文明の「邁進力」の謎を読み解く壮大なオデッセイとなっています。
美術文明史家の著者は、ケルト研究の第一人者です。また、ケルト芸術文化およびユーロ=アジア世界の民族デザイン交流史の研究者として知られます。立命館大学文学部教授を経て、現在は多摩美術大学・芸術人類学研究所所長・芸術学科教授を務めています。早稲田大学大学院修了後、アイルランド、ダブリン大学トリニティ・カレッジへ留学。処女作『ケルト/装飾的思考』(筑摩書房、サントリー学芸賞)で、日本で初めてケルト芸術文化史の全体を紹介し、ケルト・ブームを引き起こしました。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
プロローグ 黄金を射ぬく、または金属人類史
第一部 黄金の夜◎金属(メタル)篇
―「生命時間に協力する」農耕民へ
第一章 生命体としての金属―神話のなかの冶金術
第二章 「万物の王」の発見―大地から誕生する最強の王
第三章 「黄金の胎児」と農耕革命―女神と男権の戦火を超えて
第四章 農耕民のニュートンたち―「時間に協力する」知と技の誕生
第二部 黄金の夜明け◎錬金術(アルケミー)篇
―「生命時間を支配する」医者へ
第五章 時間を加速する技=冶金術―死に涙したアダムと金属民の溶鉱炉
第六章 『聖書』とギリシアの「知」の光 ―蛇、ヘルメス、イオニア派、アリストテレス
第七章 エジプトとイスラムの仲立ち―アレクサンドリア、グノーシス、イスラム
第八章 ヨーロッパ錬金術の誕生―金属と人間の「生命時間の統一」
第三部 黄金の真昼◎貨幣(マネー)篇
―「生命時間を克服する」経済人へ
第九章 巨龍の近代国家は黄金を求める―再来したリヴァイアサン
第十章 『ファウスト』と紙幣―「想像の黄金」の近代
第十一章 貨幣の魔術―未来という担保
第十二章 「万物の王=黄金」のゆくえ―生命なき金属、または聖なるものの成就
エピローグ 「時間の聖劇」と眠りについた黄金
「参考文献」
「あとがき」
プロローグ「黄金を射ぬく、または金属人類史」では、「太陽と黄金」として、著者は以下のように述べています。
「太陽は、その慈愛の光でヒトを幸せにしてくれる。なのに、その姿を直接に見ようとすると、目を焦がし、一瞬にして世界を奪う。
太陽があるからこそ、この青い惑星には生命が息づいている。大気を暖め、海を温め、水と空気の壮大な循環を引き起こす。そして光のエネルギーが、植物を繁茂させてくれる。あらゆる生命体に無尽蔵のエネルギーを惜しげもなく与えてくれる太陽は、古からヒトの最高に崇拝するカミでもあった」
続いて、著者は、「生命」と「輝くもの」の結びつきは、人類の始原からどうしても切ることのできないものだったとして、以下のように述べます。
「昔から、ヒトは黄金の装身具を身にまとってきた。なかでも指輪には特別な意味がある。ワーグナーのオペラ『ニーベルングの指輪』も、トールキンの『指輪物語』も、絶対的なパワーを与える黄金と指輪をめぐる神話を、強力に伝承している。なぜ、指輪には絶対的な力が宿ると信じられたのだろうか。指輪は太陽、日輪の象徴だからである」
また、「黄金、闇の太陽」として、著者は以下のように述べます。
「黄金は、『闇のなかでこそ輝く太陽』なのではないのか。
地上の輝きの王である黄金は、不死のシンボルとして、早くから奉られた。克服すべき死の、最も近くにいるものが、黄金だった。ツタンカーメンの黄金のマスクは棺に付けられていた。平泉の金色堂もまた藤原氏の亡骸を守っていた。地上の太陽である黄金が富の象徴であったことは間違いない。しかし同時に、死に最も近い存在でありつづけたのだ」
「太陽」と「黄金」について、著者は以下のように述べます。
「『太陽』は、ヒトの頭上に惜しげもなく降り注ぐ。けれども『黄金』は探し求めなければ、手に入れることはできない。この最高・最強・最輝の金属を、地中から取り上げたのは、『ヒト』だったのである。
ユーラシアの西に『王の中の王』と呼ばれたアーサー王がいた。輝く熊たるアーサー王を際立たせるのは剣である。彼をして王たらしめた剣がある。その剣は空から降ってきたのではない。王自身、ヒトみずからが、『鋳ぬいた』ものだった」
「鋳ぬかれた黄金」として、著者は以下のように述べています。
「人類は、およそ6000年前に金属・黄金に出会った。
ヒトは、黄金に、この地上の『時間』=『あらかじめ定められた生命時間』から、解き放たれているという『状態』を見た。死すべき運命を乗り越えている、至高の表現としての黄金に出会ったのである。以来、金属・黄金に、ヒトは2つの能動的な意味を与えることとなった。この地上で最高の金属『黄金』を、永遠に輝く『万物の王』として、これを生命の象徴的『光源』とした。黄金は、健康・希望・未来のシンボルとなったのである。そしてヒトは、黄金の特質を象徴的・科学的に探究することによって、ヒト自身が『生命時間を操作する』テクノロジーを開発しはじめたのだ。鍛冶師や錬金術師や医者、王、詩人、経済人のみか現代人も、地上に『黄金』の状態を実現しようと考えている」
さらに著者は、ヒトにとって、「黄金が永遠の生命を象徴する」ということは、比喩ではなく、哲学だったと指摘します。そして哲学は、行為を呼び起し、行為は哲学へとフィードバックされるとして、以下のように述べます。
「シバの女王が、黄金のソロモンの宮殿にさらに黄金を贈るアクションに出たのも、最強の龍が守る金羊毛をギリシアの勇士たちアルゴナウタイが奪取に出かけていったのも、中世の放浪のユダヤ人が黄金を商い、各地を転々と歩いたのも、すべて『黄金』に象徴された、最強最大の『生命=時間』を産出させる、命がけの行動だった。
『物質の黄金』に、ひれ伏したのではない。『黄金』の謎を追い求め、遂に自らその創造に挑む、闇の太陽への航海者となったのである。ヒトは英知と技術で、この最高・最強・最輝の金属を、みずから『射ぬく=鋳ぬく』ことになった。
本書は「黄金」についての本ですが、物質の黄金そのものというよりも、むしろ象徴としての黄金を語ってゆく内容となっています。
「黄金と生命」として、著者は以下のように述べます。 「ホモ・サピエンス・サピエンスの象徴的思考は、数万年前、洞窟の暗闇で、息絶えた、愛する仲間のために、最初の花(地上の太陽のかけら)を手向けた瞬間に始まった。ヒトの知的行動のはじまりには、すでに、『黄金』の探求は予見されていたと私は考える。
ミゼレーレ(哀しみ)、メメント・モリ(死を思え)。ヒトの生命への『思い』が、ヒトを成長させた。その成長の過程を『黄金』によって照らし出し、明らかにしていきたいと思う。太古から現代まで一気に―ユーラシア大陸と新世界を行き交ったインド=ヨーロッパ語族を主人公に―考えてゆきたい」
そして、著者は「黄金と生命」について以下のように述べるのでした。
「『黄金と生命』というテーマは、人間の『生』の証としての『心』、心の実としての『知』、知の実現としての『技』の連携を浮彫りにすること、それによって人間にとっていかなる最高・最強・最輝のものが、この地上にもたらされたかという、人類史の金山に問いかけるのだ。人類と金属の出会い。先史時代に起こった人類の移動、文明の発生と戦い、狩猟から農耕への移行、自然哲学者たちの世界観、錬金術師たちの格闘、ヘブライやインドやイランの宗教、近代科学、経済学、王や国家、貨幣・・・・・・」
第一章「生命体としての金属―神話のなかの冶金術」では、「金属文明」として、アジアは金属文明において明らかにヨーロッパの大先輩であったとし、著者は以下のように述べています。
「そもそもエジプトを含めて、世界の四大文明は、すべてオリエント(東洋)―『本当の文明人』の住み給う東洋―で生まれた。西アジアの考古学的資料や、中国の前漢時代に司馬遷によって編纂された『史記』(戦国時代以降の『本紀』や『列伝』)、あるいは『旧約聖書』(『列王記』『創世記』『詩篇』など)には、成熟した剣の象徴的用い方、考え方が語られ、そこに反映されている歴史的事実をみてもよくわかる」
「金も銅も生きていた」として、著者は、かつて、「金属の生きた時代」が、ヨーロッパにも、アジアにもあったとし、以下のように述べています。
「中国の鍛冶師が生贄を用いた神話が存在する意味や、あるいは紀元後1世紀のローマ帝国においては、立派な軍人や政治家だった大プリニウスが、金属を擬人化/生物化して記しても、まったく不自然とは思わなかった心性。これらが、当時の人々の間に共有されて存在した事実は、心に刻んでおいて欲しい」
著者は、「インド=ヨーロッパ世界」として、今日わたしたちが常用している英語の金属(metal)や黄金(gold)や貨幣(money)などは、元はインド=ヨーロッパ語族の言葉であると指摘しています。「ゴールド」はサンスクリット語で、「光り輝くもの」の意です。インド=ヨーロッパ語族という一大言語グループは、インドのサンスクリット、ヒンドゥー、イラン(ペルシア)語から、ギリシア、ラテン、ゲルマン、ケルトなど、大部分のヨーロッパの言語(ただしバスク語、フィノ=ウゴル語等を除く)までを含んでいます。現在20億人、世界人口の3分の1が、このグループの140ほどある言語を話しています。
第二章「『万物の王』の発見―大地から誕生する最強の王」では、「金と銀は寄り添う―『ヒトと金属の始原』」として、金と銀の関係について以下のように述べられています。
「金と銀の原始はどうだったのか? 有名なウィンナ・ワルツの『金と銀』を伴奏して踊るかのように、ゴールドとシルバーは、いつも寄り添ってきた。『金と銀が揃うと楽しい世界が現出し、あらゆるものが自由に手に入る』と『ファウスト』の第2部で天文博士も言っている。いかにも金と銀は、一緒に説明できる金属である。何より金と銀は大自然において共存して、金銀鉱を成す場合が多いからである」
続けて、銀と金について、著者は以下のように述べています。
「銀は、広く分布するが多種多様な鉱石に含まれ、いわゆる自然銀は少ない。したがって最初は、銅などの卑金属を製錬する際に、副産物として手に入れられたようだ。古代ローマ人が言うように、『銅の(かいた)汗』を溜めるようにして、銀はヒトに獲得されただろう。
一方、金は、腐食しないため、自然界では希少な元素でありながら、人目を引き、自然金の形で見つかることが多い。ただし自然金というものの、厳密に言えば合金であり(純度99~65%位)、銀や銅などを含んでいる。主には、銀との合金である。金と銀はアマルガム(合金)を作りやすい。だからこの時代の人々が目にしたのは、純粋の金や銀ではなかった。金と銀の区別が、それほど厳密でなかったことがみえてくる」
著者は、「大地母神と生きていた金属」として、方向をもった変化は「成長」であると指摘し、以下のように述べています。
「金属は、あのディアナ女神の司る月が満ちて、地上に誕生する日を夢見て、大地の子宮のなかに息づき、成長していた。緑(酸化銅)や紫(紫水晶の入った石英含銅鉱)など、この規則に従わぬ輩もいたが、母胎(大地)から取り上げ(鉱石の採取)、羊膜をはがすと(採取した原石の加工分割)、変身した。通過儀礼(製錬)をすると、光沢を放つ身体となった。(それでも規則に従わぬ者は、見捨てられた[脈石の廃棄])。そのなかにただ1人、最初から変わらず、火や水に腐食することもなく、最も明るく、最も黄色に輝く光を放つ生き物もいた」
また、大地にかかわりながらも、限りある時間を生き抜くヒトは、生命としての大自然のなかに、最も強く最も輝かしい存在とシンボルを求めたとして、著者は以下のように述べます。
「彼らは万物の王を求めた。生き抜くなかで、石などのモノをシンボル化してきた彼らは、大自然のなかにあるモノ、万物にも、『王』を求めた。ヒトの王を求めるように、彼らの神話的な思考は『モノの王』を求めたのである。それが、『万物の王』という最も強く最も輝かしく永遠であるシンボルの探求であった」
約1万2000年前に氷河期が終わると、磨製石器を使い始め、農耕と牧畜で生活する新石器時代を迎えます。第三章「『黄金の胎児』と農耕革命―女神と男権の戦火を超えて」では、農耕が始まる前の狩猟採集の時代、時間は、ヒトと共生する生命のなかに組み込まれていたとして述べます。
「たしかに、狩猟採集民族による星(天体)に関する神話伝説は、少ない。彼らは農耕民に比べ、天を観測する必要性が低かったからだと説明されている。だが、記録が残らなかっただけで、旧石器時代のヒトは、太陽と月の運行をよく知っていた。太陽によって1年を知り、月によって週を知る。太陽と月は、彼らの時計だった。その時計は、正確で見やすかったが、単純だった。が、しかし、それで十分だった。彼らにとって時間とは、まず季節であった。獲物や収穫を得るための指標は、それだけではなかったし、最大の指標でもなかった。すあわち、動植物自身が―俳句の季語のラインナップよろしく―時や季節やさまざまな頃合いを示してくれたからだ」
また、著者はヒトが時間を意識した経緯を以下のように説明します。
「天球を戴く大地の上に住むあらゆるものも、また時間の運行に、参加・協力していた。もっとも、それは形式(時間の規則)を完全に体得した星ほど、完璧でも不変でもなかったが・・・・・・。天球は、読めば読むほど、精妙さと正確さを増していく不思議な暦だったのだ。そうしてヒトは、自分たちが、皆、意識しないままに、この世の万物、すべての生きとし生けるものとともに、時間の運営という壮大な活動の一員であったことに気がついた。それは、世の始まりから続く、終わることのない聖なる劇であり、祭式であった。農耕民は、もはや単なる聖劇の観客ではいられなかった。この時代になって、ヒトは初めて時間を意識したのである」
「『文明』とは何か―四大文明だけが大文明なのか?」として、著者は「文明とは何か?」という問いに対して、以下のように答えています。
「結論から言えば、明確な定義はない。文明を文化と明確に区別する傾向は、ドイツの学者、たとえば歴史哲学者ディルタイ(1833~1911)に強いが、英米の学者は、それほど明確な区別はしていない。強いて言えば、どちらの学者も、物質的な領域に属するものを指して『文明』と呼び、『文化』を精神的領域のものとするようである。ただし、今日、文明と文化を、対立してとらえる見方は、ある意味で無用化している。事典類のなかにも、『文明』の項目を独立させずに、『文化』の項目に含めて、説明しているものがある」
「女神と男神の世界―古ヨーロッパの女神崇拝社会」として、著者は、神話のテーマとして、重大な関心を引いたのは、妊娠・出産であり、おそらく神話劇で、繰り返し演じられたのは、新生児誕生の祝儀であったと指摘し、以下のように述べています。
「神話劇で、赤子は熊や蛇に育てられ、男神と大女神と関連づけられた。これらの神々は、すべてが『死と再生』に関わり、自然生命の周期を支配し、満ち足りた生命の象徴として、崇められた。古ヨーロッパの神話世界は、女性的なものを崇拝する社会を反映している。女性は、男性に従うものではなく、人間の本質、つまり、女性的なものと男性的なものとに潜んでいる、すべての根源的な要素が、生命や世界を創造する力とみられている」
また著者は、古ヨーロッパ文明社会の異質性(四大文明と古ヨーロッパ文明の相違点)とは、古ヨーロッパ社会が「女神崇拝社会」だったということであるとして、以下のように述べています。
「この人類最古の文明は、女性(のシンボル)が主導して成立し、女性(のシンボル)が運営していた。四大文明のうち、メソポタミア、エジプト、中国の文明社会は、男権社会で、メソポタミアとエジプトの神話世界の主神も、男神(シュメールの三主神アヌ、エンリル、エンキやバビロニアのマルドゥク、エジプトのラー等)である。神話がないと言われる中国でも、三皇五帝(古代中国の神話的名君)の初代、最古の皇帝である伏犠は、男性である。インダス文明は、その支配体制も、神話世界も不明であり、確認できない。そのなかで、古ヨーロッパは、明らかに男権的ではない観念が確認できる稀有な文明なのである」
「ゾロアスターと『アヴェスター』の火と溶鉱炉」として、著者は「拝火教」として知られるゾロアスター教の開祖の名前をあげ、述べています。
「ゾロアスターの名は、古代ローマ人にも有名だった。プリニウスが『博物誌』に引く、エウドクソスの『世界周航記』によると、プラトンの死(紀元前347年)の6000年前だと言う。プルタルコスの『イシスとオシリスについて』は、ゾロアスターを、トロイア戦争の5000年前の魔術師としている。現代の研究者の間でも、紀元前1500年頃から紀元前600年頃と、確定していない」
続けて、著者はゾロアスター教の聖典について述べます。
「このゾロアスター教の聖典が、私たちの求めるペルシアにおける最古の宗教文献で、きわめて重要であり、この人類最古の創唱宗教の聖典は『アヴェスター』と呼ばれてきた。現存するものは、原典の一部にすぎない、膨大なものである。『アヴェスター』を記した言語は、古代イラン語の一種のアヴェスター語と呼ばれるもので、その最古層は、紀元前1500年頃の言語を含んでいるとも言う」
「拝火教」とも呼ばれる通りに、ゾロアスター教の神話世界では、火を最重要視しました。そして、溶鉱のイメージが重要な意味を持っていました。 火と溶鉱について、著者は以下のように述べています。
「火や溶鉱は、世界や人を成熟、完成させるものでもあった。それは、『光輝』の神アフラ・マズダーを至高神とする、この宗教の性質からして当然のことであった。これは、現代のインド=ヨーロッパ語族の黄金観とも無関係ではない。なぜなら、英語のgoldもドイツ語のGoldも古代インド・イラン語のなかのサンスクリット語の『輝くjvalita』の語に由来し、金、黄金を意味するフランス語のorも、『光』を意味するヘブライ語のorに由来するからである。金の元素記号Auは、ラテン語のaurumから来ているが、この語もヘブライ語のorに由来すると言う。Aurumとは、古代ローマ語、つまりラテン語で『灼熱の夜明け』を意味する。やはり金は、天上界や天球とも関係しているのだ」
さらに「黄金は万物の王の影―インド=ヨーロッパ語族の天と地」として、著者は、インドに確立した、「光輝」というものが世界の原動力であるというイメージは、この時代のバラモン教だけでなく、後に成立するヒンドゥー教の神話世界にも影響を与えたことを指摘し、以下のように述べます。
「『リグ・ヴェーダ』では、独立賛歌を5つしか持たない神ヴィシュヌが、ブラフマー、シヴァに並ぶ、ヒンドゥー教の3大神の1つとして、世界を維持する神として、人々に信仰されるのだ。太陽の光輝を神格化した、この神は世界(天、空、地)を3歩で踏破する」
続けて、著者はゾロアスター教の神について述べます。
「ペルシアの光明神アフラ・マズダーは、このインドの光明神と協力して、毘盧遮那仏を生み出す。太陽の一族、シャカ族出身のゴータマ・シッダールタは、ヒンドゥー教では『光明神ヴィシュヌ』の化身の1つとされる。遍く世界を照らす毘盧遮那仏はアフラ・マズダーと無関係ではないともいう。わが奈良の大仏は、毘盧遮那仏の像である。
ちなみに、ヴィシュヌの胸の旋毛は、『卍(まんじ)』の形をしているらしい。『太陽の光輝』を象徴化したと言われるこの形は、インド=ヨーロッパ語族侵入以前の時代のインダス文明の印章にも使われていた。あるいは、草原の十字軍、インド=ヨーロッパ語族の持つ十字架も、インドに入ってからは、少し先端が曲がったのかもしれない」
第四章「農耕民のニュートンたち―『時間に協力する』知と技の誕生」では、「自然現象として現われた『時間』」として、著者は述べます。
「天上の星々の複雑かつ正確な移動は、時間を、精確さを誇る『舞台俳優』のように現象化している。しかもそれは、地上の生命(生物)や自然の活動(潮の干満や気温、降水量の変化等)にも、正確に対応していた。『天上と地上』。この気の遠くなるほど隔たった2つの世界に密接な関係があることに、彼らも気づいた。この関係を説明するため、ヒトは天上と地上の世界に、『神秘的結合(ウニオ・ミステイカ)』を想定した。そしてこの発想法は、現代のロマンティストの夢想とはまったく違う、きわめて合理的なものであった」
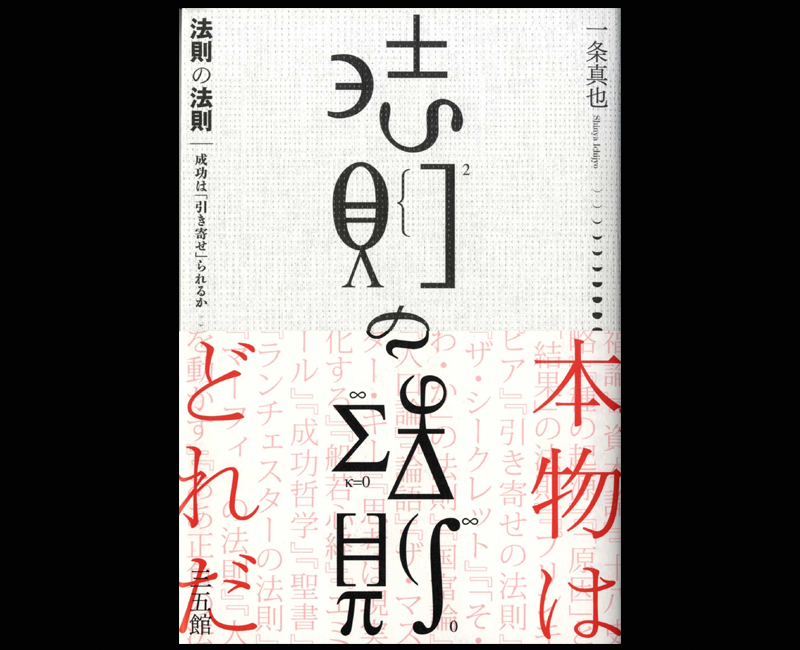 『法則の法則』(三五館)
『法則の法則』(三五館)
また、「天上と地上の2つの世界を同一の法則で説明する」という一点において、近代の天文学も先史時代の「天文学」も同じということであるとして、著者は以下のように述べています。
「ニュートンが天才ならば、先史時代にも、多くの天才たちがいたのである。彼らはニュートンのように、天上と地上の『2つの世界』は、神秘的に関連する『1つの世界』であり、天上だけでなく、世界全体で展開する森羅万象は『リズムのある聖劇』(ニュートンでは法則)であるという発見をした。この時、ヒトにとって世界は、文字通り『劇的な』変化をとげたのである。世界を『聖なる演劇のリズム』として、ヒトが意識した時、ヒトは、それまでとは異なる態度で『時間というリズム』を意識し始めたのである」
このあたりは、ニュートンを「法則王」としてとらえた拙著『法則の法則』(三五館)でも詳しく述べました。
著者は人類の文明史上における一大事件として農耕の発明をあげ、「遷移系列に干渉する営み」として、以下のように述べています。
「農耕は、『生命の時間の自然な流れ(正常遷移系列)』を、一時的に『停滞させる技術』(焼畑による作物の耕作期間は、5年程度が限界である)として生み出された。のちにヒトは、長期的に『時間を停滞させる技術』も生み出した(稲の水耕栽培等。これは連作障害を防ぎ、水管理は、田の長期的利用を可能にした)。動物に協力してもらう場合もあった(ヨーロッパの三圃式農業のように、動物の糞を連作障害に対処するために利用する)。
つまり農業は、ヒトの望む植物の集団(栽培植物の純系群落)を生み出すだけではない。ヒトの活動で、遷移の方向を変化させ、特殊な群落を生み出すこともある。例えば、火入れによってカシワ林を出現させることも行ってきた。つまり『時間の方向を変化させる』こともできたのである。生命の時間の『異なる流れ(偏向遷移系列)を生む技術』でもあったのだ!」
農耕民は、「時間の流れ」に「干渉」し、それを「操作」することに踏み出したのです。さらに、「農耕のヒトによる『時間』の観念と『生長』への手助け」として、著者は農耕について以下のように述べます。
「ヒトは生態系のなかでは『二次生産者』なのであり、植物の作る栄養に従属して生きる、『従属栄養生物』である以上、植物と無縁の生活はありえず、農耕は、今もヒトの生命線なのである!
彼ら農耕民の大部分は、農業の本質を表現するのに、難解な数式や、厳密で一義的に定義された科学用語の代わりに、複雑な儀式や神聖で多義的な神話を使って、私たちにその本質を語りかけてくるのだ。時間の壁を超えて、歴史の闇の彼方から・・・・・・。
これは筆者の単なる思い込みではない。例えば、民俗学では、儀式や神話を総称して、民間伝承あるいはフォークロア(英語では『民俗学』も意味する)と呼ぶが、フィールドワークで得る同時代の民間伝承と文字資料を利用すれば、紀元前3000年頃まで遡って検証することができるゆえんである。そしてこの農耕民の民間伝承、例えば農耕儀礼の目的は、基本的に、自然の運行や作物生育にとって、正常な時間の運行が維持され、妨害されないように手助けをするという共通性を持つのだ」
続けて、著者は以下のように具体的に説明しています。
「例えば、豊穣と生殖の女神イシュタルで有名な、古代バビロニアの農耕社会の神話と儀礼を例にすれば、『正常な時間の運行』が維持されてゆくように願い、植物が枯れて死ぬ夏の盛りに、定期的に儀礼を行なった。女神の夫で穀物の神タンムズは、穀物としてひき砕かれ死にながら、数日後に再生する、その祭を行なうのである。これは穀物が、毎年『正常な時間』の運行に沿って死に(夫婦が冥界に降り)、再生する(再び地上によみがえる)ことが、破綻なく行われるという、正常な周期とリズムの維持に、人間たちが手助けをする、典型的な祭なのである。この人間側からの手助けは、地球上のほとんどの農耕社会で行われて来たであろう」
ヒトは農耕をとおして、この宇宙全体の、「時間という聖劇」に協力するのです。そして、その壮大な運営に携わるスタッフ、つまり壮大な聖劇の参加者となったとして、著者は以下のように述べます
「もはや、彼らは時間を遠くから観ているだけの傍観者・観客ではなくなったのである。ここに、現代人につながる時間が、萌芽したのである。いわばこの農耕のニュートンたちの時間観は、彼らのみか、私たちの時間観の、第一歩でもあったのだ」
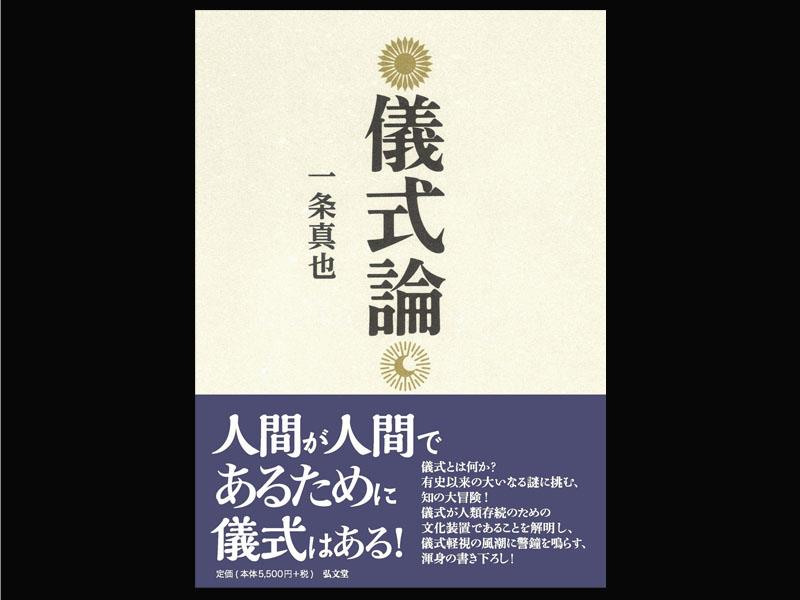 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
拙著『儀式論』(弘文堂)では、「時間」を操作するさまざまな農耕儀礼について考察していますが、本書の著者は「言葉で語るのではなく、儀式で演じる」として、儀式について以下のように述べています。
「力を補給してやれば、世界は、再活性化あるいは再生するのである。すなわち農耕のヒトにとっては、生き抜くために、世界を維持すること、すなわち、『時間を動かす世界』に『力を供給する実際の方法』を、次の世代に伝えることの方が、世界の終わりを語ることよりも、当然、はるかに重要だったのだ。そして、活動が、即、技術であるかぎり、この観念や願いは、言葉よりもむしろ象徴的行為や生活の場で示されたであろう。実際の行為や実演された演技、つまり儀式、儀礼、習俗などに彼らの時間観を表わし、次世代が受け継ぐという形式をとったのだ。これは儀式のみならず、生活のすべてが、彼らにとっては、演劇にあったことをも意味している。お祭や儀礼は生き抜くヒトの、生命の闘いの実践だった。現代人の祭は、そのことを忘れていられる祭に過ぎないと、地に足がついた論理を生きた彼らは、不思議がるに違いないのである」
たとえばヨーロッパでは、古くから、最後に刈り取った穂麦を「麦の母」「麦の祖母」などと呼びました。そして、その内側に麦霊と見立てた人間を入れて包み込みました。それから、その首をはねる所作をして、麦霊の再生を祈る祭を行ったのです。または、「最後の麦束」で人形を作って着物を着せて、担いで練り歩いたりしました。最後には川に投げ込んで豊穣を約束させるという祭です。このような農耕儀礼は、現代人にとっては迷信や、科学を知らない蒙昧の呪術としてしか映らないかもしれません。しかし、著者は以下のように述べています。
「これらはすべて、麦を最も重要な穀物として生活する人々が、つつがなく時間の維持を願い図るための、とびきり知的な、しかし、命がけの、儀礼=演劇だったのである。その意味で、ヒトにとって、農耕そのものが、ヒトによる壮大な聖なる演劇であった。つまり農耕とは、宇宙と大自然、季節や天体が演じる演劇(変わらぬ時間の運行)が終わらぬことを願っておこなう、演劇であったのだ」
「時間の正常な運行に協力者が必要だった」として、著者は「時間」について以下のように述べています。
「現代人は、時間の流れを、いわば宇宙がひとりでに、おこなっていると思っている。しかし農耕のヒトは、時間は自動的に流れるものだとは考えなかった。つまり外から力を与えてくれる協力者を必要とし、万一、その外力が絶えてしまえば、途端にバランスを崩し、流れなくなってしまうのが時間である、といつも心配を抱いていた。彼らにとって、時間の流れは、保証されてはいなかったのだ。言い換えれば彼らにとって、時間は、何者かによって運動する力が与えられ、維持されているがゆえに、かろうじて流れるものであったのである」
続けて、著者は時間について以下のように述べます。 「だから、この時間に力を与え、それを維持する何者かは、同時に自然すなわち宇宙に力を与え、それを維持する者でもあると考えられた。なぜなら、この時代の農耕民たちは、天球(月と星)という暦だけでなく、動植物の姿や声の変化など、地上の自然現象も時計として利用していた。現代人のように機械が無機的に示す時刻・暦ではなく、自然/環境の只中に有機的に顕われてくる時間という観念を、狩猟採集民から受け継いでいたのである」
「人間の協力によって維持される『第一動因』の力」として、著者は、圧倒的大多数のヒトは、天上界の時間の流れを、さまざまな方法で、積極的に支えようとしていたとして、以下のように述べています。
「ヒトの側からも、地上からも協力しなければ、時間の変わりない運行は保てないと思っていたからである。近代以前、世界各地の農村で行われた、『冬至の祭』は、そのよい例である。衰えた冬の太陽に再び、何者かが力を与え、太陽の生命力を復活・再生させねばならない。それを促すためにヒトの側からも祭を行う。この冬至の祭は、後にクリスマスと習合するが、ゲルマン民族のユール祭などにその名残がみられる」
続けて、著者は「冬至の祭」について以下のように述べます。
「現代の私たちは、非ユークリッド幾何学や偏微分方程式等を駆使して表わした、苦心の成果である宇宙像の真の姿も知らずに、冬至と習合したクリスマスのディナーショーに参加し、初日の出を恋人と楽しんでいる!祖先たちと同じく、積極的に! いにしえの冬至の祭では、ヒトは『(太陽の)生命時間は宇宙の時間の一部』であると考えていたゆえに、ヒトは、短くなってしまった日照時間を取り戻すため、宇宙に向けて、祭で協力した。いつ何時、天上界の時間の流れも、永遠不変でなくなるかもしれないと考える、ヒトの大いなる不安によって、その祭は欠かせなかったのだ」
第一部の最後にあたって、著者は繰り返して述べています。
かつての祭や儀礼は、けっして迷信で行われたのではありません。
それは、経験則から推し量られた「知性の命令」によって、行われていたのです。
第五章「時間を加速する技=冶金術―死に涙したアダムと金属民の溶鉱炉」では、「仲立ちの知と技」として、著者は以下のように述べています。
「今日私たちが使っている錬金術という概念は、卑金属を変成させて金を造りだす技のことだ。しかし私たちは、錬金術をそのように狭くとらえるのではなく、生命時間を支配する技を錬金術と呼ぶのである。その歴史は、文明の黎明期から始まっていた。そして今日地上で最強の存在を自任するところの西洋人のベースとなった、ヨーロッパという時空でひとつの到達点に至る」
 『唯葬論』(三五館)
『唯葬論』(三五館)
「『赤い土』のアダム―石器人の無念」として、著者は各地でみられる「赤い土の葬礼」に言及し、それが生命力の付与が目的だったと推測しています。
「現生人類(ホモ・サピエンス・サピエンス)は、それ以前のヒトより『心優しいヒト』であるという。より正確には生死に直面した経験や感情を、なにかで表現・表象することを営み始めていたヒトであるということだ。すなわち愛する人の死に臨んで涙し、『生命時間』の限りあることへの無念を、何とか行為で表わしたいという心を宿したヒトだった。『死』(『生』)を、身の回りにある印象的で特別と思えた色彩ある物質によって、意味づけしよう、徴づけようとしたのだ。実際、このようなヒトの本格的な『象徴的表現の営み』は、数万年前に始まっていた手向けの花からさらに進んで、およそ3万5000年前のこの後期旧石器時代に始まるとされる。それはいいかえれば、ヒトの心に『他者に対する共感と想像力』が、より強く育まれたことを意味している」
このあたりは、拙著『唯葬論』(三五館)のメインテーマです。
また、著者は「死者を想う」という心を宿したヒトについて述べます。
「私たちの前に横たわる仲間の身体は、生命を失うと同時に、唇や頬、手のひらや足の裏等の皮膚から赤い血色が失われていくのを見たはずだ(視覚)。その身体に触れれば、熱(体温)が失われていくのを、感じるに違いない(触覚)。さらに時間がたてば、その身体が腐敗臭を放つことに気づくだろう(嗅覚・味覚)。
だが、これらに先立って、決定的に感じられるのは、仲間から「息」が失われたという事実だろう。耳をそばだてても、呼吸音は聞こえない(聴覚)。目を凝らしても、胸は上下しない(視覚)。手を寄せても、熱い吐息は感じない(触覚)。顔を近づけても、息は匂わない(嗅覚・味覚)。息の有無は、まず、五感に感知されるのだ。ヒトが死ぬということは、息を失うことだった。仲間想いのヒトが、失われていく血色に対して、赤い土で生命力を付与しようとしたことは、当然だったのかもしれない」
さらに著者は、仲間の死を経験したヒトについて述べています。
「この経験は彼らにある重要な真実を確信させた。すなわちヒトの生命の本質とは、息であるということである。いかにも『創世記』(2の6)にも、その真実が示されている。最も劇的なシーン。そう、あのミケランジェロがシスティーナ礼拝堂に描いた『創世記』のなかでおそらく最も有名な、『アダムの創造』の場面である。神は、アダムに鼻から、息(プネウマ)を吹き込んで、生命(霊)を与えたのだった。それが人間の誕生だった。しかし死は、その人間の生命の根拠を奪う」
続けて、著者は以下のように述べるのでした。
「死の絶望は、ヒトの心に『時間を支配するという欲望』を生み出した。 なぜなら、自身の死への恐れのみならず、愛する仲間の死ということ以上に、世界の無常さ、時間の流れの残酷さを痛感させるものはないだろうからだ。仲間の息の喪失への絶望と死への無念は、彼らをして赤い土を手に取らせた。これが後期旧石器時代頃のヒトに起こった心の決定的事件だった。この絶望は、現在の私たちまでの、生命時間を乗り越えようとする営み、『黄金の生命』の探求の遥かな始原となったのだ・・・・・・」
「鍛冶師という『媒介者』の出現―農耕定住民の金属使用」として、著者は、鍛冶師は、金属を変化させることにより、人を教化する文化人だったともいえると述べます。その理由は、文化とは、混沌とした世界と自己に「形」を与えるものなのだからというのですが、さらに以下のように述べています。
「イニシエーション(加入・仲間入りの儀式)という語は、人間を変化させるという意味に置き換えられるのである。また彼らは、究極的にはシャーマン(霊媒)と同一視されたかもしれない。いわゆるシャーマンとは、神々の世界に自分の魂を飛ばして、その知識をヒトの世界にもたらす人間である。自分の身体を媒体として、神や霊と合一し、神の言葉を伝えるため、神に変身する。シャーマンは神々とヒトの世界の仲立ち、異能の媒介者であった」
「人工的に時間を生み、時間を加速する技術」として、著者は「冶金儀礼」から見て、「金属の製錬作業」と「宇宙における生命の成長過程」が見事に同一視されていたことが分かると指摘し、つまり冶金術は、「生命の時間を操作する」(エリアーデ)という点においては、農耕と同じ技術であったと喝破します。しかし、宇宙=生命(農耕民の神話世界では、宇宙も生きていた)の時間の流れに協力する農耕に対して、冶金術には異なる点があったとして、以下のように述べています。
「それは、冶金術が、時間の流れを『加速する技術』であったという点である。鍛冶師は、大地のなかから取り出した胎児(鉱石)を、人工の子宮(炉)の中に入れ、火(熱)と水と風(生命の仲立ち)、さらに、天体の力を借りて、短時間で新生児(金属)に成長させる。これは、自然の子宮(大地)のなかでは、気が遠くなるほどの時間がかかると考えられた、生命育成の時間を、溶鉱炉という小宇宙のなかで、再現・加速する作業であった。冶金術の発明によって、ヒトは『人工的に時間を生み出し、時間を加速できる』ようになった。すなわち、時間を征服・支配する道が拓けたのだ」
著者は、流産や早産のイメージが、冶金術につきまとうのは当然であると言います。なぜなら、金属民が大地から取り上げる「胎児」は、必然的に説きならず生まれし胎児だったからです。そして、著者は以下のように述べるのでした。
「この技術にもまた、仲間の遺体をみつめながら、時間の残酷さに涙した『原始人の思い(哀しみ)』が反映しているのが分かるだろう。時間を支配する技術=冶金術は、生命の条件、すなわち風(呼吸)と熱(温かさ)を必要とした。彼らの思いは、ついに時間を征服する技術を、生み出したかに見える。がしかし、彼らの哀しみは、『冶金術』では、癒されない。その哀しみを、本当に解決するには、『錬金術』の完成が必要だったのである」
第六章「『聖書』とギリシアの「知」の光―蛇、ヘルメス、イオニア派、アリストテレス」では、「画家のパレット」として、著者は「色とは、不死を求めるヒトにもたらされる光であった。愛するヒトの遺体に塗った、あのアダムの赤い土は、いかにして金属だけでなく人間の生きる時間を支配する技である錬金術へと変容していったのか」と述べています。
また、以下のように「赤い土の葬礼」を連想させています。
「『聖書』の『楽園追放』から、ヨーロッパ16世紀の錬金術誕生までを辿っていくと、それが人間のからだと生命に作用する力と、その媒介を発見しようとする、人間の知と理論の探求であることが浮かび上がってくるのである。それはなんと、花や赤い土をシンボル化した、原始のヒトたちの、自然観察の経験の理論化にほかならないのである」
第七章「エジプトとイスラムの仲立ち―アレクサンドリア、グノーシス、イスラム」では、中世の錬金術師たち、そして現代の科学史家の多くが、錬金術の発祥の地と考えるのが、エジプトのアレクサンドリアであることが紹介されます。著者は、「技術と理論の『仲立ち』=エジプト―アレクサンドリア」として、以下のように述べます。
「そもそもマケドニアは、各文明の成果が複雑に習合していた土地だった。王は、そこから遠征し、ナイル川とチグリス・ユーフラテス川、インダス川という、世界四大文明の源泉のうち、3つの大河を手にして、ヨーロッパ、アフリカ、アジアの3大陸の支配者となったのだった。思えば、この王こそ、まさにアリストテレスのいう「金属変成や物質変成」に見紛う文明の変成をもたらす大いなる仲立ちとなった存在であった。アリストテレスの教え子は、いわば現実の世界で、錬金術師の使う還流装置(ケロタキス)となった」
また、「グノーシス、『蛇』の知―アレクサンドリア」として、著者はグノーシス主義について以下のように述べます。
「人々に真の知恵の自覚(認識)を促し、重視する思想を、グノーシス(真知)主義という。エデンの園で神に呪われ、そこを追放された人間の子孫から、世を救う福音をもたらす救世主イエスが、紀元1世紀に出現した。その同時代の同じ地域に、同じようにエデンの園で神に呪われた蛇もまた、世を救う福音をもたらす救世主として、人間の前に姿を現していたのである。つまりグノーシス主義は、エジプトとともに、紀元1世紀のシリア、パレスチナ地域にも存在した」
第八章「ヨーロッパ錬金術の誕生―金属と人間の『生命時間の統一』」では、「ファウストとゲーテ」として、著者は以下のように述べています。
「ドイツ文学史上、いや世界文学史においても、屈指の巨人ゲーテ、彼もまた、このルネサンス期のファウスト博士と同じ魔術師・錬金術師だったのかもしれない。なぜなら、彼は、文学はもとより、動物学、植物学、解剖学、光学等の自然科学研究者であり、歴史論や絵画も創作する美術研究家にして、学芸、建設、兵制、さらには、財政を司る政治家と、多彩な才能を見せたのだから。彼の思想については、次の第3部で、もう一度、触れることになる。なぜなら、ゲーテこそ、歴史上、最強かつ最大の錬金術にして、万物の王の生涯を終了させる究極の錬金術を理解していた人物の1人かもしれないのだから」
また、「『自然錬金術』と治療の発想―パラケルスス」として、著者は以下のように述べています。
「ファウストを生んだドイツ語の文化圏(当時ドイツに属していた巡礼地で知られるアルプス山脈の地、チューリヒ南東のマリア・アインジーデルン)に生まれたその人は、私たちの提起する観点からいっても、紛れもない錬金術師と呼びうるヒトであった。なぜなら彼は、金属のみならず、人間の病気を治療し、不死化するために錬金術を研究し、治療活動をした錬金術師であり、医師だったのだから。このヨーロッパで、世界と人間の生命の時間を操作し、完成する技術、すなわち、西ヨーロッパで錬金術を完成させたヒトは、今日、一般に、パラケルスス(1494頃~1541)と呼ばれている」
第九章「巨龍の近代国家は黄金を求める―再来したリヴァイアサン」では、「解けない魔法」として、著者は以下のように述べています。
「近代産業社会が生み出す、多くの『富』を人間たちは所有してきた。お金や株券という黄金を空想させるお化けが、箒の魔法で溢れ出てくる。 しかし・・・・・・ミッキーのような魔法使いの弟子と同じで、この魔法をやめさせる力(つまり倫理)も、知恵(共産主義もうまくいかなかった)も、もっていない。近代経済システムという魔法は、止まらない商品(水)運びに似て、充足の限りを知らない。生産と消費の過剰さを呼び、『水』(自然・天然資源全体の象徴でもある)の利用と消費、それによる、廃棄物の『洪水』を前にして、ヒト自らが『死』の危機にさらされていく」
また著者は、「リヴァイアサンの身体と『政治経済の世界』の誕生」として、『リヴァイアサン』の著者であるホッブスの時代について、以下のように述べています。
「ホッブスが生きた16世紀から17世紀は、ガリレオやニュートンによる科学革命が起こり、近代科学が誕生した時代でもある。ニュートンに代表される近代科学によって、『天上界(天空界)と地上界(月下界)は統一された』世紀だった。中世の写本(『黙示録』を描いた劇的なスペインのベアトス本)にあるようにかつてははっきり色わけされ分裂していた天と地、2つの世界、2つの自然は、1つになった」
このあたりも、わたしは『法則の法則』に詳しく書きました。
続けて、著者は以下のように述べています。
「にもかかわらず、なぜ近代になっても、世界の分裂・混乱はおさまらないのだろうか? それは、中世的世界観にあった、天上と地上というこの2つの自然を統一することに、近代科学は成功し、『世界』は生み出されたが、その結果、1つになったはずの世界に、もう1つの異世界が、生み出されたからだと考えられる。つまり、その3番目に生まれた世界こそ、私たち、人間による、人間のための、人間の世界、すなわち近代人の『政治=経済の世界』であった」
そして、著者は「総合的自然科学者ゲーテ」として、ゲーテについて以下のように述べるのでした。
「詩人、人文学者、財務長官、イタリア紀行の古典主義者、『若きウェルテルの悩み』、疾風怒濤派の元祖、植物の変容や色彩や鉱物で世界をヴィジョンする自然哲学者、世界の根源を知ることに絶望した錬金術師ファウストを60年かけて生み出した親・・・・・・。ニュートンが『分析的自然科学者』とすれば、彼は、『総合的自然科学者』であった。ゲーテの武器は、ニュートンのような『科学的分析』ではない。世界に対する『想像力と共感』、世界の本質を見抜く『芸術的直観』である」
第十章「『ファウスト』と紙幣―『想像の黄金』の近代」では、「経済学的視点から読み解くゲーテ『ファウスト』」として、著者はゲーテが認識した「万物の王の錬金術」の正体は、「貨幣」を媒介として、「労働力」や「生産物」を売買し、「貨幣」を尺度とする利潤を求め、貨幣が示す価値を増大させる運動であると指摘し、以下のように述べます。
「これが、後に近代経済システム、とくに『資本主義』と呼ばれる運動と、事実上同じものである。しかしゲーテが認識した近代世界の本質は、今日の私たちの目から見れば、現代の思想家や学者がいう『資本主義』と、事実上同じではあっても、完全に同一のものというわけではない。私たちのイメージする『資本主義』ではないのである。実のところ、資本主義批判で有名な『資本論』の著者、1818年生まれのドイツのカール・マルクスは、ゲーテが死去した1832年、まだ少年であった。では、ゲーテの『近代世界の本質』とは何か? それは、『万物の王』の魔術、つまり『錬金術』である。これは比喩ではない。ゲーテ自身が、そう表現しているのである」
著者によれば、近現代の代表的な経済学者によって、いわゆる「ファウスト的な精神」が、「企業家の精神」とも呼ばれてきたといいます。そもそも、「資本主義」という観念を普及させたマックス・ウェーバーや、ヴェルナー・ゾンバルトは、その「近代的企業家」像を描き出したというのです。
それから著者は、以下のように述べています。
「そうした近代的企業家像とは、単なる合理的人間、計算高い人間ではなく、宗教的人間または冒険的商人、探検家や組織家を統合した人物像のことであった。つまり企業家精神とは、『宗教的精神』、あるいは『冒険的精神』のことであったことをしっかりと胸に刻もう。そうした資本主義の企業家像が、ゲーテの描く魔術師ファウストの人物像や精神に共通することは、『ファウスト』を読めばわかる。事実、ゾンバルトは資本主義の企業家精神を『ファウスト的精神』と呼んだのである」
また著者は、「『ファウスト』のストーリー―紙幣と『生命時間の錬金術』」として、以下のように述べています。
「『ファウスト』は、有限な人間の生命を黄金に変える「時間を乗り越える術」=「錬金術」の世界の物語なのである。すなわち第1部では、若返りと精力の復活(時間を取り戻す)、「生命時間を支配する技術」に基づく世界が語られた(本書第1部・第2部を参照のこと)。そして第2部では、『物質の黄金化による富の増大』、すなわち『物質の黄金への変容』が語られる。そして、これもまた『時間を支配する技術』に基づく世界の物語である。錬金術を『生命時間を支配する技術』と捉え、また『人間の生命時間とモノの時間』という2つの『時間を支配する技術』が揃ってはじめて『錬金術』とする、本書の私たちの観点からも、『ファウスト』は明らかに錬金術の物語である」
さらに著者は、「ゲーテの錬金術への直観―象徴文学『ファウスト』の意味」として、以下のように述べています。
「結論から言えば、『ファウスト』の作者ゲーテ自身は、物語のファウスト博士と同じく、魔術師・錬金術師の探求心を捨てない『オカルティストである近代人』であった。これは、今日のゲーテ研究者も認める歴史的事実である。そこにゲーテ研究者として著名なルドルフ・シュタイナー(1861~1925)の名があることも不思議ではない。オーストリアに生まれた彼は、ゲーテと同じ科学者であり文人、哲学者、オカルティストであるが、『新しい科学』を提唱し、実践した。そしてゲーテ自身もオカルティストの近代人であることを認めていた。自叙伝である『詩と真実』(1811~1833年刊)のなかで、自分の思想について『ネオプラトニズムがその基盤となっているにしても、ヘルメス主義、神秘主義、カバラも同様に貢献している』と告白している」
そして著者は、「紙幣とはなにか―国家の法制としての『紙のお化け』」として、以下のように述べるのでした。
「ゲーテの看破した『万物の王』の『錬金術』の正体、それは『紙幣』に基づく『近代経済システム』である。では、『紙幣』とは何か? 紙幣は『貨幣』の一種である。貨幣の起源に関しては、『交換説』、『装飾貨幣説』、『呪術説』、『宗教説』、『貨幣国定説』などがあり、現在でも、その答えは謎である。これからも謎のままだろう。なぜなら貨幣は単一の起源に帰せるものではなく、また無理に単一の起源を考える必要もないからだ。世界史上で最古の金貨発行は、前8世紀後半から前6世紀中葉にかけて、オリエント世界とギリシア世界を結ぶ政治・経済・文化の中心地としてアナトリア西部に栄えたリュディアの王によるというが、そこにも複数の目的があったようだ」
第十一章「貨幣の魔術―未来という担保」では、「生命時間の無常を克服する錬金術と芸術・科学」として、著者は以下のように述べています。
「錬金術における『時間の支配』とは、パラケルススが主張したように、金属の時間のみならず『人間の生命時間』を支配するもの、つまり、『ヒトやモノを不死化すること』であった。これは、言い換えれば、時間の『無常性』を克服、永遠化するということである。ゲーテも『ファウスト』で、『無常』なる時間を『永遠』に変える3つの方法を示している。それは『芸術』、『科学』、『経済』である」
著者は「『近代経済』と『錬金術』の共通性―信用と未来の前提」として、歴史上、最強、最大の錬金術である私たちの生きる世界の近代経済システムこそが「万物の王=黄金」の錬金術の正体だと指摘し、こう述べます。
「有限な人間の生命時間を支配して、『想像の金』を『現実の金』に変え(現金化)、世界中の『万物を金に換える』このシステムは、原理的には、最高の錬金術でなくて何であろう。なぜなら―ビンスヴァンガーにしたがって私たちはこう言うことができる―黄金のみならず、『想像の存在』を『現実の世界の存在』に変えてしまう魔術。つまり、紙幣や証券とは、かつて神にしかできなかった、無から有を創造するのだから!」
さらに著者は、「『黒』を見ることのできるゲーテ、見えないニュートン」として、ファウスト=「黒魔術師」の使う錬金術は、わたしたちの生きる現代社会の「近代経済システム」の術に似ていないだろうかと読者に問いかけ、以下のように述べるのでした。
「古のタレスたちのような素朴な自然哲学者たちや自然魔術師たちが用いた『魔術』は、天体等の自然界(現実の世界)に自然物の魔力を使う、自然魔術たる『白魔術』だった。それに対して『近代経済システム』の錬金術は、明らかに、魔術師ファウストのように、自然界(現実の世界)には本来存在しない―『魔界(想像の世界)』から召喚した、悪魔メフィストフェレスのような『人ならぬもの』や、巨龍(国家)や、お化け(貨幣)たちの魔力、国家権力や貨幣価値等を使う、『黒魔術』なのである」
第十二章「『万物の王=黄金』のゆくえ―生命なき金属、または聖なるものの成就」では、「『聖なるもの』の成就」として著者は述べます。
「『万物の王=黄金』は、成長・完成された。『万物の王=黄金』の運命は成就し、見えない姿となり、どこかへそっと『消える』のである。当然そこには、仰々しい謀殺の悲劇や暗殺のドラマなど、一切の歴史的事件との関わりは、この『皇帝』と人類との別れには、存在しないのである。したがって、彼が私たちの世界から、いつ、どのようにして、なぜ、消えたのか、私たちの世界の歴史的事実から、その日時や理由を特定することは不可能である」
続けて、著者は「万物の王=黄金」のゆくえについて述べるのでした。
「あえていうなら、筆者の考えでは、20世紀初めのロシアの社会主義者レーニンが、彼らが完全に勝利したあかつきには、『公衆トイレ』を作るために使用すること、それが、正当で、有益で、人道的な『金(黄金)』の利用法であるなどという、『冒瀆的な』意見を、この皇帝(黄金)に関して述べ、金の威光を否定した時か(『現在と社会主義の完全な勝利ののちとの金の意義について』1921年)。あるいは、1971年、アメリカ合衆国が金とドルの交換を停止した、『世界最強の超大国の金本位制が、事実上、終焉』を迎えた時か。または、20世紀の終わり、『デジタル・マネー化』が始まり、貨幣の素材価値が完全になくなる動きが生まれた時か。それとも、これらの何れとも、まったく関係のない『歴史的時点』なのか・・・・・・。いずれにせよ『万物の王』は、もう私たちの世界にはいない」
エピローグ「時間の聖劇と眠りについた黄金」では、「『万物の王』はいずこに?―聖なるものの成就のあとの世界で」として、著者は述べます。
「新しい生命の誕生には、古い生命の犠牲が必要であるという、古代人の想像力は、現代の映画にもよくあるテーマだ。『アルマゲドン』で地球を守るために、父が、娘のフィアンセになりかわって、自ら爆薬を抱えて死んでいく。そのうるわしき犠牲の精神に人は感動する。そして、数万年前に死者に花を手向けたヒトの涙と、現代人が身近な人の死に向かい合うときに流す涙に違いなどあるはずもない。絶対的な別れにどうすることもできない無力さ、人間を死に至らせる『時間の残酷さ』に対する無念の思いは、すべてのヒトに共通する最も深い『思い』であろう」
 『ハートフル・ソサエティ』(三五館)
『ハートフル・ソサエティ』(三五館)
続けて、著者は時代を超えて「変わらないもの」について述べます。
「技術や知の方法は変わっても、ヒトは変わらないのだ。もっといえば、人間のモノの感じ方、モノの考え方、つまり心の世界においては、前近代は終わってはいない。私たちの心のなかでは、『近代』はもちろん、『中世』も『古代』も『先史時代』も、さらには、象徴的思考の生まれた『後期旧石器時代』すら生きつづけ、今でも力を発揮しているのだ。
あたかも、ゲーテの『万物の範型(シェーマ=イデア)を生み出す世界』、時空を超越して存在する『戦慄すべき世界』のように」
この一文は、拙著『ハートフル・ソサエティ』(三五館)で、わたしが「人は、かならず『心』に向かう」と訴えた部分と共通しています。
エピローグの終盤では、著者は「輝き」について書いていますが、素晴らしい名文です。まずは「『時間』という名の聖劇―未生の花」として、著者は以下のように述べています。
「黄金郷を求め新大陸へ向けてスペイン人が船出したあの日、女神と聖牛が西に向かったあの夜、そして最初の花を手向けたヒトまで、私たちの祖先たちが見た時と同じ夜空の中心から、天の星は私たちを見守っている。そしてその星や月、太陽を、『輝き』としてみとめるのはヒトなのだ」
そして、「夢見る黄金の胎児―ライン・ゴールドのように」として、著者は「輝き」について以下のように述べるのでした。
「『輝き』とはなにか。それは人間にとっての『驚き(という歓び)』のことである。ラインの川底に潜む黄金が放つ異様な光、太陽、アーサー王の剣、ベルサイユ宮殿の鏡の間、金貨、蒔絵・・・・・・。
これらの圧倒的な光と美しさにはっとするとき、私たちの心に走る『驚き』という閃光が、『輝き』の正体なのだ。
ゲーテを引くまでもない。『人間の達しえる最高のものは、驚きである』。これが錬金術の奥義だったのだ。『驚く心』が生命の最高の瞬間である以上、それは、ある瞬間に思いがけずやってきて、私たちに『触れる』。そして、私たちが『触れる』ものでもある。錬金術が追求した『賢者の石』は、それが何かに『触れる』瞬間に黄金を生むものであることを、いま一度思い出そう」
この気の遠くなるような壮大な「知」の旅に読者を連れ出してくれた本書の「あとがき」を、著者は以下のように書きだしています。
「遠い昔、ヒトの『心に』燈された『思いとしての黄金』の、現在にいたるまでの長い航海を、描き出そうとしたのが、本書である。ヒトにとって、金属・黄金は、天上の星や太陽と照応し、生命の時間を永遠化する象徴としてこの世に生まれた。永遠の輝きと腐蝕しない若さを保ち続ける『黄金』は、この地上で最も生命的な『生き物』として、求められてきた」
黄金の心のヒトの命脈は尽きていません。20世紀以降にも、光る守り手、旗手は続いていますが、その1人として、著者はアイルランドの詩人であるイェイツの名をあげます。彼の膨大な「隠喩」の書物、『幻想録』の最後の数行には、ゲーテも膝を打って墓から起き上がるだろう、警句が書かれているというのです。その中から、著者は以下の言葉を紹介します。
私に必要なものはほかにない、
ミイラがミイラ布にくるまれているように
心の旅にくるまれているからは。
「あとがき」の最後で、著者は以下のように述べるのでした。
「心の旅は、終わることはない。私たちもまた、あのエジプトのミイラのように―錬金の知・技を握っていた最初のヒトのように―しっかりとその象徴の黄金布に、くるまれているかぎり、心(想像力)の旅は終わらないと」
最後に、本書の存在を某ブログで知ったのですが、一読して、その壮大すぎるスケールに魅了され、知的好奇心を嫌というほど刺激されました。まさに超弩級の書物とは、本書のような本であると思います。
わたしの ブログ記事「東京自由大学HPリニュアール」で紹介したように、今年の4月にNPO法人 東京自由大学公式ホームページがリニューアルされました。わたしは同大学の顧問を務めているのですが、新しくなった公式HPを見て、本書の著者である鶴岡真弓氏も顧問であると知って大変驚きました。
数ヵ月前に本書を読み終えたわたしは「世の中には凄い人がいるものだなあ」と思っていたのですが、まさかその凄い人と一緒の顧問だったとは! まことに光栄の至りであります。
