- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.06.08
『大分断』エマニュエル・トッド著、大野舞訳(PHP新書)を読みました。「教育がもたらす新たな階級化社会」というサブタイトルがついています。一条真也の読書館『自由の限界』、『新しい世界』で紹介した本に著者のインタビューが掲載されており、興味を持ちました。もっと著者の考え方を深く知りたいと思い、2020年7月に刊行された本書を手に取った次第です。著者は、1951年フランス生まれ。歴史家、文化人類学者、人口学者。ソルボンヌ大学で学んだのち、ケンブリッジ大学で博士号を取得。各国の家族制度や識字率、出生率、死亡率などに基づき現代政治や社会を分析し、ソ連崩壊、米国の金融危機、アラブの春、トランプ大統領誕生、英国EU離脱などを予言。著書に『経済幻想』『帝国以後』(以上、藤原書店)、『シャルリとは誰か?』『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』(以上、文春新書)、『グローバリズム以後』(朝日新書)など多数。
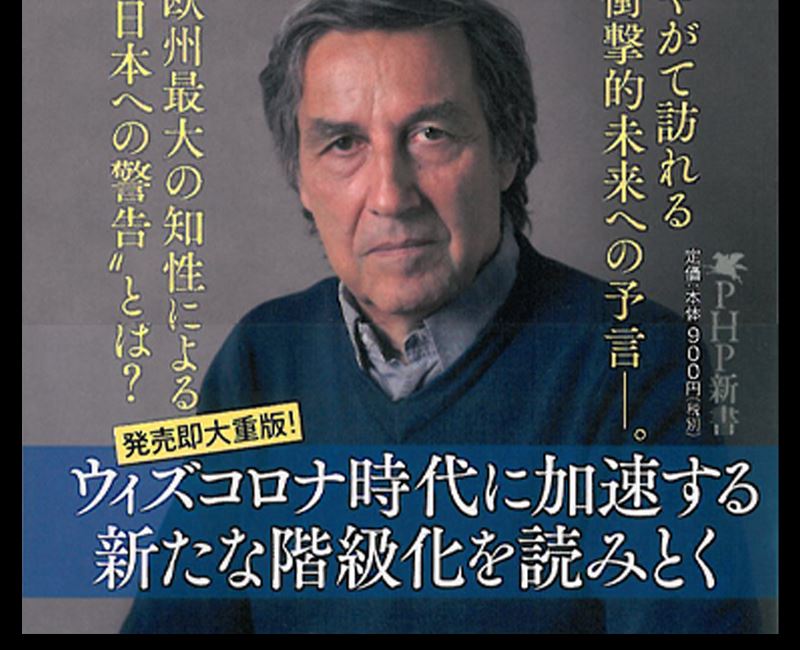 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、著者の顔写真とともに、「やがて訪れる衝撃的未来への予言――」「欧州最大の知性による”日本への警告”は?」「発売即大重版!」「ウィズコロナ時代に加速する新たな階級化を読みとく」と書かれています。帯の裏には、「トランプ大統領の誕生、ブレグジット……これまで数多くの予言を的中させてきた著者による4年ぶり待望の語り下ろし!」とあります。
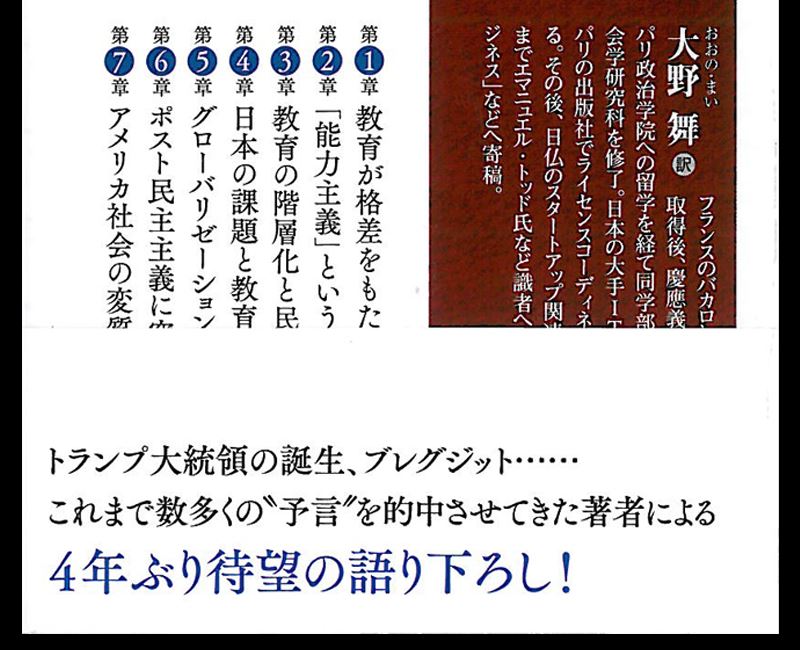 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また、カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「現代における教育はもはや、社会的階級を再生産し、格差を拡大させるものになってしまった。高等教育の階層化がエリートと大衆の分断・対立を招き、ポピュリズムを生んでいる――これまで、ソ連崩壊、トランプ大統領の誕生など数多くの『予言』を的中させてきた著者は、こう断言する。民主主義が危機に瀕する先進各国で起きている分断の本質を、家族構造が能力主義・民主主義に及ぼす影響や地政学的要素を鑑みながら、鮮やかに読み解いていく。日本の未来、そして変質する世界の行方は。欧州最大の知性が日本の読者のために語り下ろした、これからの世界情勢を知るために必読の1冊」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1章 教育が格差をもたらした
第2章 「能力主義」という矛盾
第3章 教育の階層化と民主主義の崩壊
第4章 日本の課題と教育格差
第5章 グローバリゼーションの未来
第6章 ポスト民主主義に突入したヨーロッパ
第7章 アメリカ社会の変質と冷戦後の世界
「訳者あとがき・解説」
「はじめに」の最初に置かれた「階級化した世界」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「今、我々は『思想の大いなる嘘の時代』に直面しています。先進諸国では、識字率が上がり、多くの人が民主主義について語れるようになり、あらゆる民主的な制度が存在し、投票制度も、政党も、報道の自由もあります。しかし、実際には社会はいくつものブロックに分断されてしまい、人々が『自分たちは不平等を生きている』ことを知っている状態にいます。構造としては、上層部に「集団エリート」の層があり、その下に完全に疎外された人々、例えばフランスでは国民連合(旧・国民戦線。反移民などを掲げる極右政党)に票を入れるような層があります。そしてその間には、何層にもなった中間層が存在しています」
このような構造の中で、民主主義のシステムは機能不全に陥ってしまったとして、著者は「民主主義に基づいて築かれた制度は問題なく機能し、国としては全ての自由を手にしている。にもかかわらず選挙そのものは狂っているとしか思えないものになっている。民主主義というのは本来、マジョリティである下層部の人々が力を合わせて上層部の特権階級から社会の改善を手にしようというものです。ですから、民主主義は今、機能不全に陥っている。私はそう考えるわけです。そしてこの機能不全のレベルは教育格差によって決まるのです」と述べています。また、「経済構造と教育の歪んだ関係」では、「私は学ぶという行為自体が目的になるべきだと信じています。学ぶことでより良い人間になれます。そして、知るということ、それ自体が良いことだと思うのです。ところが、次第に社会が複雑化し、ますますその深刻さが増している現代社会では、教育は経済的、社会的な成功を収めるためのツールとなってしまいました」と述べます。
「分断された世界はパンデミック以後にどう変わるか」では、2020年、新型コロナウイルスの世界的大流行(パンデミック)が猛威を振るい、多くの国はロックダウン(都市封鎖)を行ない、経済活動や人の行き来を停止したとして、著者は「コロナ以後(ポスト・コロナ)について、私は『何も変わらないが、物事は加速し、悪化する』という考えです。コロナ危機が収束の兆しを見せ始めた頃、アメリカでは、白人警官による黒人市民の殺害が社会的波紋を引き起こし、全米で黒人差別に反対する大規模なデモが起きました。このデモには、黒人のみならず、高等教育を受けた若い白人たち――主にバーニー・サンダースの支持層――が多数参加しました。コロナ危機後の最初の出来事がこのアメリカで起きたデモだとすると、実はコロナ以前のアメリカにすでに存在していた傾向と、今起きていることの本質は全く変わっていない、ということがわかるでしょう。というのも、コロナ以前から白人の若者も、高等教育を受けた若者も、非・特権階級化しているという傾向はすでに見られていたからです」と述べています。
そして、著者は「本書では、高等教育が引き起こした社会の分断と格差について主に論じています。さらに、それに関連してグローバル化疲れ(グローバリゼーション・ファティーグ)についても分析しました。私は、これまでの研究者人生の中で、ソ連の崩壊やアラブの春、トランプ大統領の誕生などについて予測し、それらは今日まで割と適切な予測であったと思います。ただ、私はアナール学派(フランス現代歴史学の学派の1つ)から教えてもらった変数を使い続け、それらを現代社会や社会の未来に当てはめて研究を進めただけなのです。アナール学派はそもそも社会のダイナミズムの本質を見抜いた人々だったため、それに続く私の分析も高性能なものとなりえた、ということを付け加えておきましょう」と述べるのでした。
第1章「教育が格差をもたらした」の「教育が社会を階級化し、分断を進めている」では、アメリカやフランスなどの国々では、全人口のおよそ3分の1が高等教育を受けるという比率に到達し、それ以降の伸び率は停滞し、教育の発展は壁にぶち当たっていると指摘し、著者は「もちろん、大学進学率でいえば日本ではおよそ50%、韓国では70%という数字がありますが、日本でも東京大学や慶應・早稲田大学を卒業するのと、地方大学を卒業するのとでは意味が異なると思います。つまりそこで注視しなければならないのは、大学の中でもトップレベルとそれ以外という区分がある点です」と述べています。
「エリート対大衆の闘争が始まる?」では、マルクスは『フランスにおける階級闘争』をまさしくフランスで書きましたが、そのフランスで2018年から起きていたのは、仏大統領マクロン派の権力側と「黄色いベスト」たちの対立でした(「黄色いベスト運動」。燃料税の引き上げ反対から始まったフランスの国民的デモ運動を指す)。著者は、「これは高等教育を受け、非常に頭が良いとされながら実際には何も理解していない人々と、下層に属する、多くは30代から40代の低収入の人々、高等教育を受けていないながらも知性のある人々の衝突でした。つまり、フランスのような国では学業と知性の分離というのはすでに始まっていることなのです」と述べます。
「20世紀の重要な思想の崩壊」では、著者は良いマルクス主義と悪いマルクス主義があると考えているとして、「悪いマルクス主義者は資本家階級を金持ちのロボットのように捉え、彼らが金儲けにしか目がなく、そこに喜びを見出していると捉えます。しかし、自らをヒューマニスト(人道主義者)と称する私は、 お金持ちも人間として捉えています。つまり、彼らも自分たちの人生を意味あるものにしたいと考えている。だから金儲けもある程度を超えたら重要ではなくなります。社会には、経済的に特権的な立場にある支配階級が存在します。そういう人々がいること自体は問題ではなく、もっと重要なことは、その支配階級の人々が人間として存在することの正当性を得るために、何らかの目的を持っているかどうかです」と述べています。
「教育の発展が道徳的枠組みを崩壊させた」では、今の時代の自己中心主義という側面について考え、著者は「まず道徳というのは個人レベルの話ではありません。良い行動をするためには、(自分が望ましい行動をした時に)それを好ましく受け取ってくれる周囲の人たちがいることが必要です。つまり道徳というのは個人のものであると同時に集団的なものでもあるのです。集団的な道徳観とはフランスだとカトリックの道徳だったり、別の社会ではプロテスタントのものだったりしました。国家的なレベルでは愛国心や共産主義、社会主義、そしてもちろんキリスト教による倫理観が存在しました。個人は道徳的な枠組みの中にいて、その行動によって道徳や倫理そのものを生かしてきました。しかし今日、高等教育の発展や不平等の拡大によって集団の道徳的な枠組みが崩壊してしまった状態にあります。共産主義も宗教も消滅してしまいました。国家的なレベルでの集団的な感情というものもありません。社会主義的な感情も崩壊し、個人しかいない社会になっているのです。そしてこの集団的な道徳の枠組みをなくしてしまった個人は、以前よりもずっと卑小な存在になってしまっています」と述べます。
第2章「『能力主義』という矛盾」の最初に置かれた「識字率の上昇がもたらした歴史のうねり」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「教育の運命というのは歴史そのものです。まず文字はシュメール(初期のメソポタミア文明)で紀元前に神殿の会計を担当していた人々によって発明されました。ほぼ同時かその少し後にエジプトでも文字文化が生まれ、それは主に表意文字と呼ばれるものでした。ただ、文字を書くという行為は、筆生の階級に限定されたものでした。つまり文字が生まれた時代には、いつの日か全ての人が読み書きできるようになるなどとは誰も想像していなかったということです。なぜならば、最初の文字のシステムは非常に複雑だったという点が挙げられます。もちろんその後、フェニキア人によってアブジャド(子音文字)が生まれ、ギリシャ人によってアルファベットも生まれましたが、それでもまだ、まさか全ての人が読み書きできるようになることなど、誰も考えていませんでした」
その後プロテスタントの宗教改革が起き、ようやく、全ての人々が読み書きできるようになるべきだという考え方が生まれたことを指摘し、著者は「私にとって近代社会の始まりはこのあたりです。北部、そして中央ヨーロッパ、つまりドイツや北欧の国々、オランダ、イギリスなど、プロテスタントの国々でようやく全ての人が読み書きを学ぶことが可能だと気づいたのです。中世の初期に一体誰がこんなことを想像できたでしょうか。そして、ヨーロッパ全体、全世界で現代に至るまで識字率は上昇していきました。これから10年も経てば地球上全ての人々が読み書きができるようになるでしょう。これに伴い、当然のことながら女性の識字率の上がり、地球上のあちこちで出生率が下がるという現象も起きました。このように、私にとって教育の発展というのは歴史そのものなのです」と述べています。
次に、中等教育の発展があります。全ての人が読み書きできるようになる世界を想像したプロテスタントの国々ですら、まさかある日、全ての人が中等教育を受けられるようになることは想像できなかったとして、著者は「最初にそれを実践に移したのは、第一次世界大戦後のアメリカでした。なぜならば国家がそれに反対しなかったからです。また、アメリカにはプロテスタントの信徒が多く、ハイスクールも設立され、第一次世界大戦後の時点ですでに中等教育を受けた子供たちの割合がとても高かったのです。アメリカでは、1929年の時点で実に人口の半数以上が中等教育を受けていました。それに続く形で高等教育の発展が始まり、それ以外の国々もアメリカに続きました。そして1965年頃、高等教育を受けた人々の割合が全人口の3分の1に達するあたりで停滞します。読み書きとは異なり、高等教育は複雑な問題です。生活水準や両親の学歴などとも複雑に絡み合っているのです」と述べます。
「世界的に学力が低下している?」では、今のフランスで問題だと思われるのは、計算力と読解力の低下が管理職の親を持つ子供たちにおいても起きているという点であるとして、著者は「この理由として、学校教育や教育法そのものが放任主義的になってきているという見方もあります。しかし私は、どちらかというと子供たちが読書をしなくなっているということに理由があると思っています。テレビやテレビゲームができる前の時代、子供たちは読書をしているか、そうでなければ退屈していたのです。私は退屈というのは進歩のための大切な要素だと信じています」
「エリートたちが愚か者ばかりなのはなぜか」では、15歳以上の思春期を迎える子供には、考える時間を与えるべきであるとして、著者は「考えるということは、自由な時間を持つことで自然と身に付きます。自由な時間で学校の課題図書以外のものもとにかくなんでも読んでみる。もしかすると、子供にはある時点で敷かれたレールから外れることが必要なのかもしれません」と述べ、さらに「親たちは子供の成績を気にして過ごします。そうして、成績によって区分けがなされ、子供たちも自分の能力によって定められたレベルを内面化していきます。しかし、このような教育は子供たちから何を奪っているのでしょうか。それは1人でじっくり考える時間です。本当に頭の良い人間になるためには、1人で考える時間が欠かせないのです。満点を取るということが究極の目的となれば、子供にとって考える時間がなくなることは間違いありません。社会が完璧さを要求しすぎるがために、結果的に教育や学力の低下を招いているのです」と述べています。
「能力主義が階級の再生産をもたらす」では、高等教育の発展は、メリトクラシー、つまり能力主義のプロセスの中核にあるものであると指摘し、著者は「能力主義の観念を編み出したイギリスの社会学者マイケル・ヤングは、それを非常に軽蔑的に見ていた人物です。教育によって人々が区分けされる世界では、実際に学業で失敗をした人々はそれを内面化し、自分は劣っている人間だという認識に至ってしまうからです。ですから学校教育の結果によって人々が選り分けられる社会という理想自体、どこかおかしなものなのです。本当にそうやって人々は共に生きていけるのでしょうか」と疑問を呈します。
「女性が男性より高学歴になるという新しい現象」では、国によってかなり大きな可変性を含むものの、わたしたちは人類史上初めて、先進国の教育において女性が高等教育を受ける比率が男性のそれを超えるという時代を迎えたことを指摘し、著者は「このような追い越しは、初等教育レベルではかつてカリブ海のアンティル諸島の社会か、ブラジルの黒人社会でしか見られなかったことです。これらの社会では、奴隷制度によって家族制度の崩壊が起き、男女間の識字レベルの不平等が生まれたのです。同様に18世紀から19世紀のスウェーデンでもこのような状況が見られました。しかし、今日、アメリカ、イギリス、フランスやスウェーデンで見られる、高等教育における女性の優位性は全く新しい現象であり、事実として間違いなく観察できることなのですが、どのように解釈をしたら良いのかはまだわかりません」と述べます。
フランス国立人口研究所(INED)の『Population(人口)』と題された雑誌の中に最近面白い記事を見つけたとして、著者は「そこでは、『女性が自分より社会的地位が高い男性と結婚をする』という従来のモデルが、崩壊していることが示唆されているのです。なぜならば若いカップルにおいては女性の方が男性よりも高学歴であるケースが増えているからです。そういう意味で、全く新しい現実が訪れていると言えます。あるいは、これを世代間の問題として議論を進めるのも面白いと思います。全ての世論調査結果から見えてくることですが、昨今見られる世代間の分裂は教育問題と同じくらい重要な社会の差別化の要素になりつつあります」と述べています。
第3章「教育の階層化と民主主義の崩壊」の「教育格差がトランプ大統領を生み出した」では、歴史のある時点で成熟した社会には民主的な時代が到来することを指摘し、著者は「読み書きの大衆化に続き、教育格差の時代がやってきます。まさしく現在、我々は初等教育だけでなく、中等・高等教育の発展が著しい時代に入りました。現代社会の特徴はこの高等教育のレベルがさらに何層にもなっていることです。その結果、お互いは不平等な関係である、という潜在意識が広がっています。社会の中でお互いを学歴や高等教育の種類などで判断するようになったのです。これが教育格差の時代です。例えば、2016年のアメリカ大統領選の際に最も注目された変数の1つが、教育レベルでした。高等教育を受けた人たちは、民主党の候補であるヒラリー・クリントンに、中等教育で止まっている人たちは共和党の候補であるドナルド・トランプに投票したと言われました。しかし本当に注目すべきは、高等教育の中でも、学部以上の学歴を有している人、あるいは有名大学出身者たち、文化的階層の最上部にいる人の多くがクリントン(左派政党)に投票したという点です。また、このような状況は世界のあちこちでレベルは違えど、見られるものです」と述べています。
「『集団エリート』という新たな現象」では、著者は「エリートとは何者なのか」と問いかけ、以下のように述べています。
「これは時代によって異なります。民主主義を機能させるエリートとして最初に思い付く人物は、古代ギリシャ・アテナイのペリクレスでしょう。ペリクレスは貴族階級を代表し、同時に大衆の民主的なものへの願いを汲み取った人物です。また、19世紀のイギリスで投票権の拡大に貢献した人々もまたエリートと呼べる人々でした。彼らは民衆を選挙システムに組み込むことを受け入れたのです。さらに、左派政党にも枠組みを与え、自由党が生まれました。のちに労働党の出現で勢力が衰退しますが、自由党は、例えばウィリアム・グラッドストンのような、教育を受けた伝統的にプロテスタント宗派の人々、つまりその時代の知識人やブルジョワたちで構成されていました」と述べるのでした。
第4章「日本の課題と教育格差」の「日本における『能力主義』」では、基本的に直系家族を基盤とする日本のような社会は、そもそもが身分制の社会であると指摘し、著者は「ここでは長男が重要とされてきました。それは徐々に男性全体が特権を持つ、つまり男性優位社会へと変化していきました。日本でももちろん、戦後には能力主義の発展が見られましたが、そこにはフランスで見られるような、平等に対する強いこだわりがないのです。日本にも奥深いところで、巧妙な形での平等主義が存在するとは思います。例えば、あるレベルにおいてはどの仕事も高尚であり、正しく為されるべき、といった考え方です。『馬鹿な人はいても馬鹿げた仕事はない』ということです。そしてきちんと為された仕事はそれがどんな仕事であれ評価されます。それぞれがある身分に属していて、そこで自分の仕事をきちんとこなすという社会です。もちろん、日本にも高等教育を受けたエリートが存在しますが、他国と異なるのは、人々がその身分の序列を認めているという点です。ここでは上層部の下層部に対する軽蔑、あるいは下層部の上層部に対する憎しみというものはないのです」と述べています。
「なぜ日本ではポピュリズムが力を持たないか」では、日本は身分制の社会ですが、明治の頃からすでに教育の重要性を認識してきたと指摘し、著者は「私が思うにこれもまた、国家が生き延びるためだったのだろうということです。日本人であると感じることや、西洋からの脅威に対抗し生き延びるために、日本社会は自分たちの価値観を超越し、階級化したシステムを残したままで大規模な民主化へ進んでいったのだと思うのです。なお、直系家族構造の社会の問題は、非常に効率的ではあるのですが、現状の形をそのまま繰り返すという傾向があり、無気力な社会になることと関係しているという点です。直系家族の罠は、自分と全く同じものを作り出そうとする点にあるのです。それと同時に、虚弱なシステムでもあるため外からショックを受けた時に再び活性化するという側面もあります」と述べます。
「日本は中国とどう対峙すべきか」では、「日本は核武装をしたら良い」と主張する著者が、以下のように述べています。
「もちろん、日本は被爆国として核保有に対する抵抗が強いこともよく理解しています。しかしあの時代はアメリカが唯一の核保有国で、また、アメリカ自体が非常に人種差別的な時代であったという背景も含めて考えるべきなのです。確かに日本では福島の原発事故がいまだ記憶に新しく、日本の核に関するリスクは地震と津波であるという点も理解できます。しかしそれでも、結果的に日本は国家の自立を守るために核エネルギーの利用を続けています。私からしてみたら、リスクの高い核の利用法(原発)を続け、一方で国の安全を確実なものにする方の核(兵器)を避けていると見えるのです。日本が核武装をすれば中国との関係は大きく変わり、この規模の異なる二国間の平和はほぼ永久的に約束されると思います」
一方で日本は、靖国神社とそれが象徴するもので周辺国と対立するのはやめるべきであるとして、著者は「靖国神社が象徴するものは、日本が本当はどんな国なのか、ということを隠してしまっていると思います。日本は17世紀から19世紀まで鎖国をし、外部と一切戦争をしなかった国なのです。にもかかわらず、靖国神社を巡って対立が起きることで、日本の歴史について間違ったイメージが広がってしまうのです。なお、ここから展開する見解は他の誰にも認められてはいないもので、むしろ私の日本に対する個人的な愛着心から出ているということをまずお断りしておきましょう。日本の歴史を見る限り、基本的に戦争にはあまり関心がない国だったということがわかります。だから、近代の植民地主義もある種の”勘違い”から端を発しているのではないかと思うのです」と述べます。
「人口減少解決のために不可欠なこと」では、たった一国のみで生き延びることはできないとして、著者は「米中覇権争いなど世界で国家間関係が再編されている今、日本の将来についても再考するべきでしょう。これは急務であると言えます。なにせ日本はこれから移民を受け入れなければならないからです。それは単純に国内のバランスを保つためでもありますが、老いていく社会の高齢者たちを支えるためにも必要でしょう。移民については、中国など隣国との関係性をしっかり把握した上で、インドネシア、ベトナム、フィリピンなどからの受け入れを優先する方法もうまくいくのではないでしょうか。ヨーロッパからの移民だってありえると思います。また、さらに言うならば、天皇陛下が移民についてスピーチなどをすることは非常にいいことではないかと思います。というのも、この移民の受け入れというフェーズは日本にとって明治維新ほどの重要性を帯びるはずだからです。明治維新は日本が植民地化されずに生き抜くために起きたわけですが、それと同じように、少子化は今後日本という国が生き延びられるかどうかという問題と深く関わっているのです。
「日本は少しばかりの『無秩序』を受け入れよ」では、日本で話をする時に、よく半分冗談として言うのは「日本にとっていいモデルとなるのは、江戸時代の日本だ」ということであるとして、著者は「19世紀の直系家族システムの最盛期ではなく、むしろ江戸時代を参考にしたらいいと思うのです。移民政策は政府がしっかりと管理して行なうべきではあるのですが、それと同時に日本人は『無秩序』を学び直す必要があると確信しています。例えば、日本では学校で子供たちに掃除の仕方を教えるといいます。また、スポーツ選手たちのクロークは試合後も非常に綺麗だそうです。それらは非常な美点であり、維持するべきです。しかしそれと同時に『多少秩序が乱れていても世界は崩壊しない』ということを学ぶべきではないでしょうか。
第5章「グローバリゼーションの未来」の「グローバリゼーションは終わるが”世界化”は終わらない」では、「グローバリゼーション」と「世界化(Mondialisation)」を区別しておく必要があるとして、著者は「世界化というのは、インターネットにより世界中とコミュニケーションを取ることが可能になった状態、英語の世界共通語化、人々の国家間移動が強化されたことなどを指します。今やほぼ世界中の人々が読み書きができるようになり、発展途上国でも西洋の夢を自分たちのものにすることが可能になっているのです。それは、19世紀、より良い世界の夢を農民たち自身が描けるようになり、都市への流入が起きたことと同様です。一方でグローバリゼーションというのは、モノと資本の自由な流通という点に限ります。私たちはグローバリゼーションの終焉を迎えようとしているのかもしれませんが、それは世界化が終わるということではないのです」と述べています。
「移民と民主主義の関係――民主主義には『外国人嫌い』の要素がある」では、民主主義というのは最初から普遍化を目指すものではなかったことを指摘し、著者は「民主主義とは、ある土地で、ある民衆が、お互いに理解できる言語で議論をするために生まれたものでした。民主主義の思想には、土地への所属ということと、外から来るものに対する嫌悪感が基盤にあるのです。歴史を侮ってはいけません。ギリシャのアテネ、人種差別主義のアメリカ、フランスのナショナリズム的な革命。ですから、ブレグジットやポピュリズム運動など、今起きている民主主義への復活の裏にはこの『外国人嫌い』の要素が含まれていることはある意味当たり前なのです。これは半分冗談として聞いていただきたいのですが、『もし大規模な外国人嫌いの思想が民主主義を崩壊させるとしても、少しだけであれば逆に民主主義を到来させるだろう』ということです。民衆の自己意識は、ある程度の社会的な団結と集団行動を可能にするための『必要悪』なのです」と述べるのでした。
第6章「ポスト民主主義に突入したヨーロッパ」では、人類学的かつポスト宗教の大陸ヨーロッパのポテンシャルを鑑みると、地政学上で昨今実際に起きたイギリスとアメリカの撤退の後、この地域において真の民主主義が持続されると考えるのは愚かだと言わざるをえないとして、著者は「今日表出してきていることは(権威主義的価値観という)大陸ヨーロッパの伝統であり、それはリベラル民主主義にとって決して好都合なものではないのです。フランスならば民主主義的な価値や平等の価値をそこにもたらすこともできたのかもしれませんが、そんなフランスも今や自立した国ではなくなってしまっています。さらに言えば、EUは、抽象的な政治哲学の観念が現実の壁にぶち当たっている場所でもあります。民主主義の考え方、つまり「人はみな平等で自由」という理想は素晴らしいですし、私自身も大賛成です。しかしながら、それがうまくいくためには人々の教育レベルが均一でなければならず、お互いに理解し合えて、そして時には衝突し合うことも可能でなければいけません。今のEUではそれは不可能なのです」と述べるのでした。本書を読んで、著者が訴える「教育がもたらす新たな階層化社会」の姿がおぼろげに見えてきたような気がしました。
