- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2217 宗教・精神世界 『現代スピリチュアリティ文化論』 伊藤雅之著(明石書店)
2023.03.02
『現代スピリチュアリティ文化論』伊藤雅之著(明石書店)を読みました。「ヨーガ、マインドフルネスからポジティブ心理学まで」というサブタイトルがついています。著者は、1964年名古屋市生まれ。1998年、米国ペンシルバニア大学大学院社会学部博士課程修了(Ph.D.)。専門は宗教社会学。おもな著書に『現代社会とスピリチュアリティ』(単著、渓水社、2003年)、『スピリチュアリティの社会学』(共編著、世界思想社、2004年)、訳書に『宗教社会学』(メレディス・B・マクガイア著、共訳、明石書店、2008年)など。
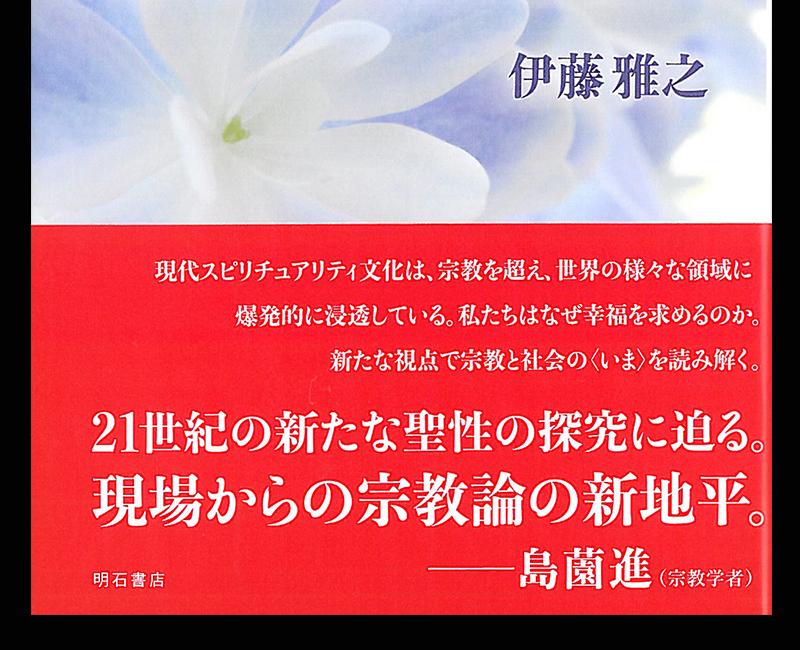 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「現代スピリチュアリティ文化は、宗教を超え、世界の様々な領域に爆発的に浸透している。私たちはなぜ幸福を求めるのか。新たな視点で宗教と社会の〈いま〉を読み解く」「21世紀の新たな聖性の探求に迫る。現場からの宗教論の新地平。――島薗進(宗教学者)」と書かれています。
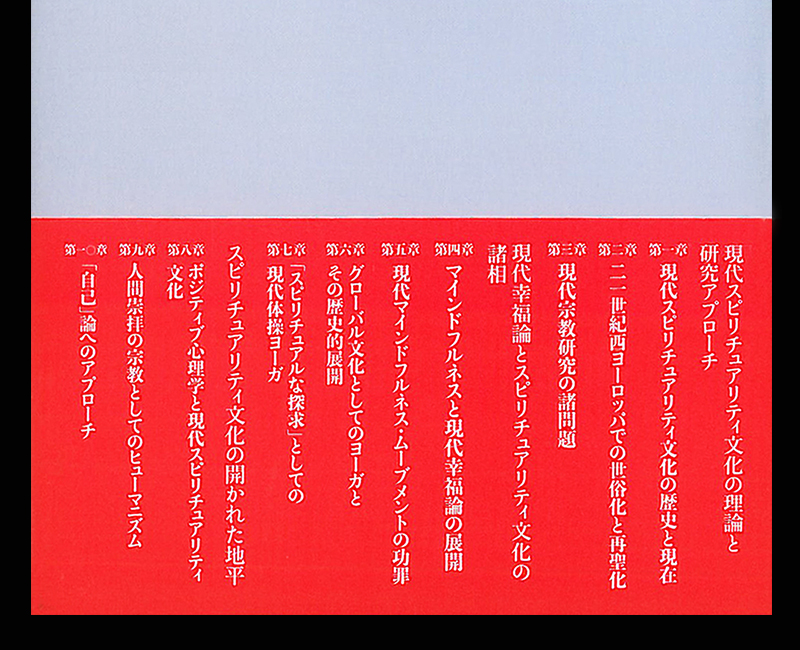 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1部 現代スピリチュアリティ文化
の理論と研究アプローチ
第1章 現代スピリチュアリティ文化の歴史と現在
――対抗文化から主流文化へ
第2章 21世紀西ヨーロッパでの世俗化と再聖化
――イギリスのスピリチュアリティ論争と現在
第3章 現代宗教研究の諸問題
――オウム真理教とそれ以後
第2部 現代幸福論と
スピリチュアリティ文化の諸相
第4章 マインドフルネスと現代幸福論の展開
第5章 現代マインドフルネス・ムーブメントの功罪
――伝統仏教からの離脱とその評価をめぐって
第6章 グローバル文化としてのヨーガとその歴史的展開
第7章 「スピリチュアルな探求」としての現代体操ヨーガ
第3部 スピリチュアリティ文化
の開かれた地平
第8章 ポジティブ心理学と
現代スピリチュアリティ文化
第9章 人間崇拝の宗教としてのヒューマニズム
――ヒューマニストUKの活動を手がかりとして
第10章 「自己」論へのアプローチ
――エックハルト・トールと
ネオ・アドヴァイタ・ムーブメント
「おわりに」
「初出一覧」
「参考・引用文献リスト」
「索引」
本書の帯に推薦文を寄せている島薗進先生はわたしのグリーフケア研究の師です。日々、わたしたちは、さまざまな情報交換を行っています。その流れの中で、わたしは一条真也の読書館『死は存在しない』で紹介した田坂広志氏の著書を島薗先生にメールで紹介しました。すると、島薗先生から「田坂さんの本は読んでいませんが、ご紹介くださっている内容は、1980年前後から、いわゆる『ニューサイエンス』(ニューエイジサイエンス、ニューフィジックス)などで唱えられてきた内容と重なるとことが多いように思います。カプラ『タオ自然学』が早い時期のもので、私はそれなりに妥当性があるものと思っていました。現在の「新霊性文化」(ニュースピリチュアリティ)の動向にそったものと思います。伊藤雅之さんが『現代スピリチュアリティ文化論』で示している動向と共通のものでSBNRの動向にそっています。私は共鳴するところが多いですが、『限界意識のスピリチュアリティ』にも関心をもつべきだという立場です」という返信メールが届きました。ちなみに「SBNR」とは「Spiritual But Not Religious」の頭文字をとったもので、特定の宗教への信仰を持たないが、スピリチュアルに関心があり精神的な豊かさを求める信仰的スタンスのことです。現在、主に欧米を中心にSBNR層が拡大しています。
「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「1960年代後半以降、北アメリカや西ヨーロッパ、日本を含む東アジア諸国などにおいて、『宗教』を補完し、代替するものとしての『スピリチュアリティ』への関心が多くの人びとの間で高まった。宗教研究者からすれば、世界の諸宗教の形態は歴史的に見てもきわめて多様であり、スピリチュアリティは宗教のなかに含まれる、あるいはこの二つの概念は同義語であり相互に置き換え可能だと長らく考えられてきた。しかし20世紀後半になると、一定の割合の人びとがこれら二つの概念を明確に区分し、一方の宗教は諸制度や教義、儀礼という形式上はっきりと組織だっているものを指し、他方のスピリチュアリティは個々人による通常の自己を超えた何ものかとのつながりの経験を表すようになってきている。本書では、1960年代以降に発展した、こうした自己を超えた何かとのつながりを強調する一連の思想や活動、実践を『現代スピリチュアリティ文化』と呼ぶことにする」
スピリチュアリティとは、さまざまな思想や活動、実践を対象とする包括的な概念であり、一般の人々にとってもこの語についての理解は大きく異なります。しかし、大まかに言えば、現代スピリチュアリティ文化の典型は、ホリスティック(全体論的)な世界観を持ち、ゆるやかなネットワークでつながり、自らが選択した実践を通じて自己実現を求める人びとから構成される諸現象と捉えることができるといいます。この文化では、個人をこの上なくかけがえのない存在として捉える「自己の聖性」をとりわけ重視し、スピリチュアルな体験をする個人の感性や直感、「本当の自分」の探求などに力点が置かれる傾向があるようです。歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリによれば、20世紀後半には、1人ひとりの「内なる声」や真正性を強調する自由主義的ヒューマニズムという人間崇拝の宗教が繁栄しましたが、著者は現代スピリチュアリティ文化が発展した社会的背景にはこうしたヒューマニズム思想の広がりが影響していると考えています。
1960年代から現在までの約60年にわたる現代スピリチュアリティ文化は、(1)対抗文化(カウンターカルチャー)の中での意識変容の試み(1960年代から70年代半ば)から、(2)ニューエイジを典型とする私的空間での「自分探し」といった下位文化(サブカルチャー)の確立(1970年代後半から90年代半ば)を経て、(3)全体社会の各制度領域において自己のスピリチュアリティを高めようとする主流文化(メインカルチャー)への浸透(1990年代後半以降)に移行してきていると捉えられます。幅広いアプローチやメッセージを包括的に捉えるためのキーワードとなるのが「ウェルビーイング(持続的幸福)」です。心とからだのつながり、ありのままの自己の受容、自然との調和、超越的な存在とのつながりなどを通じて、身体的健康だけでなく、心の平安がもたらされるという意味をこの語は含んでいます。著者は、「ウェルビーイングは『幸福』と同義であるが、長期的な心身の健康を指すため、本書では『持続的幸福』と表記することにしたい」と述べます。
「ウェルビーイング」をキーワードとするこの文化的潮流において、著者はとくにマインドフルネス(瞑想)、ヨーガ、および心理セラピーの3つの実践に注目しています。この3つの実践形態は、マインドフルネスのなかにヨーガが含まれたり、その逆だったり、また心理セラピーの一貫としてヨーガや瞑想をしたりと重なりあうところが多いです。2000年代以降に興隆したマインドフルネス・ムーブメントは、今日では医療、心理療法、教育、スポーツ、企業にも広がり、定着してきています。従来は特定の修行の一環として、ヨーガのアシュラム(道場)や仏教寺院で行われていたこれらの実践は、伝統文化を離れ、幅広い社会・文化領域で一般の人々により行われてきています。心理セラピー関連としては、1998年に創始されたポジティブ心理学は注目に値します。著者は、「この新しい心理学の分野は、人間のポジティブな側面(喜び、感謝、充足感など)を強化し、人びとの幸福度(ウェルビーイング)の向上をめざす科学として確立し、学校や業、軍隊でもその介入調査は導入されている。これもまた、現代スピリチュアリティ文化の一環として理解できる現象である」と述べるのでした。
第一章「現代スピリチュアリティ文化の歴史と現在――対抗文化から主流文化へ」の1「グローバル化とスピリチュアリティ文化の広がり」では、グローバル化は、世界各地の人々のものの見方、考え方、感じ方を均質化する役割を果たしたことが指摘されます。世界中で同じ映画やテレビ番組、ネット配信動画などを視聴し、同じファストフード店で食事をし、巨大企業の同一製品を使用し、さらにはインターネットで国境を越えた交流をすれば、世界各地の人びとの価値観が類似することは当然のように思われるからです。しかしながら、グローバル化は同時に価値観の差異化をもたらすと指摘し、著者は「なぜならば、世界的な物的、人的、および情報の交流によって、人びとが以前は意識することのなかった自分たちの容認できないような別の地域や国の人びとがおこなう社会的・文化的相違を発見し、伝統的価値観を強化するケースが増えるからである。なかには、伝統を新たに創造して、自分たちの文化的アイデンティティを強化する場合もある」と述べています。
現代世界におけるさまざまな宗教現象もこのグローバル化の影響を逃れることはできません。世界各地での原理主義の台頭(キリスト教福音派など)は、差異化の表れです。他方、グローバル化がもたらす宗教文化の均質化は、先進諸国、特に都市部を中心に世界各地で広がっています。その典型は「スピリチュアリティ」をキーワードとする一連の思想や実践の発展です。4「スピリチュアリティ文化の変遷Ⅰ(1960年から90年代前半)では、著者は、1960年代以降の現代社会、とりわけアメリカや西ヨーロッパ諸国、日本、韓国などの東アジアにおいては2つの価値体系、すなわち、未来志向で理性を重視し業績主義的な「近代的志向性」、および現在志向で表現主義的、感性を重視し自己肯定を掲げる「脱近代的志向性」のせめぎ合いが起こっていると指摘します。1960年代の高度経済成長期の「追いつけ、追い越せ」といったメッセージは前者の典型であり、ビートルズの「Let It Be」やSMAPの「世界に一つだけの花」、映画『アナと雪の女王』の「Let it Go ~ありのままで~」の歌詞にある、ありのままの自己肯定を主張するメッセージは後者の好例であるといいます。
「対抗文化のなかでの意識変容の試み」では、1960年代から70年代半ば頃までのスピリチュアリティ文化は、対抗文化(カウンターカルチャー)、すなわち現状の社会体制や価値・規範に異議申し立てをする社会・文化運動として特徴づけられます。その主な担い手となったのは、第二次世界大戦後に生まれた「ベビーブーマー」と呼ばれる世代でした。彼らは、物質的な豊かさに恵まれ、戦後民主主義教育を受けて育った世代である。この世代が青年期を迎え、欧米や日本などで開花させたのが対抗文化である。イギリスでは、音楽、ファッション、映画産業などが一気に花開いた50年代後半から70年代前半までを長期の60年代と捉え、「文化革命」と呼んでいます。スピリチュアリティ文化の発展は、まさに若者たちによる文化革命の一環として発展していったのです。
1960年代後半、アメリカの学生にはじまり全世界に広がったベトナム戦争に反対する平和運動は、対抗文化のなかでのスピリチュアリティの重要性を喚起する大きなきっかけとなった出来事の1つでした。たとえば、現代スピリチュアリティ文化において多大な影響力をもつベトナム人禅僧、ティク・ナット・ハンの活動は、自国でのベトナム戦争がきっかけとなっていると指摘し、著者は「彼は、社会と隔絶した僧院での修行ではなく、民衆の救済活動と仏教修行を同時に実践する『行動する仏教』を掲げた。アメリカのマーティン・ルーサー・キング牧師とともに反戦運動をおこなうなかで、ティク・ナット・ハンは戦争という社会問題の根は人間一人ひとりの心にあるとして、マインドフルネスを広める活動を展開していく」と説明しています。
ベトナム戦争に反対し、南北ベトナムのいずれの立場とも距離をおいたため、ティク・ナット・ハンは亡命を余儀なくされました。亡命先のフランスに開いた「プラムヴィレッジ」と呼ばれる共同体は、その後の数十年間の彼の活動拠点となっていきます。著者は。「ティク・ナット・ハンのアプローチは、社会変革と個人のスピリチュアリティの探求の関係について問題提起するものであり、反戦平和活動を支持する当時の若者たちにも影響を与えることになった。こうした活動に賛同する担い手は、『意識が変わらなければ世界は変わらない』というスローガンを提唱し、社会運動への積極的な参加と同時に、身近な生活世界の問い直しを通じて自己変革へのはたらきかけも実践した。反戦平和運動以外でも、ドラッグによる意識変容の試みや自然農法をおこない自給自足をめざすコミューン運動がその具体例である」と述べます。
若者たちは、ティク・ナット・ハン以外にも多くの東洋思想やグル(精神的指導者)たちに傾倒していきました。その1人に、リチャード・アルパートがいます。彼は、(幻覚や恍惚状態を引き起こす麻薬である)LSD体験によってこの世界は作り出された虚構にすぎないとの理解に至り、その体験の意味を求めてインドを放浪しました。彼はそこでヒンドゥー教のグルであるニーム・カロリ・ババ(通称マハラジ)に出会い、彼の弟子となります。その後、アルパートはラム・ダスと名乗り、アメリカ帰国後に自らの体験をまとめた『ビー・ヒア・ナウ』(1970年)を出版し、多くの若者たちから絶大な支持を得ました。また1968年、ビートルズのメンバーたちは、インドのリシケーシュにあるスワミ・シバナンダによるヨーガ道場やマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーのもとを訪れています。マハリシは、「超越瞑想」と称する独自のヨーガを展開していた。ジョージ・ハリスンらがヒンドゥー教の聖地リシケーシュなどを訪れ、ヨーガや瞑想に親しむ姿が世界に伝わりました。著者によれば、ビートルズによる「Let It Be」(1970年)はこの時代を代表する曲として理解できるといいます。
また、スワミ・シバナンダの弟子であるスワミ・サッチダーナンダは、ヨーガの思想、アーサナ(体操)、呼吸法、マントラ、瞑想などをバランスよく体系的に学ぶ「インテグラル・ヨーガ」を掲げました。彼のヨーガは欧米の若者を中心に広がることとなりました。1969年にニューヨーク郊外で開催されたウッドストック・フェスティバルでは、40万人の聴衆を前に、「物質的にもスピリチュアルな面でもアメリカが世界平和に対して重大な役割を担っている」というオープニングのメッセージを伝えています。著者は、「こうした歴史的な一大音楽イベントにおいて、インドの聖者が招かれてオープニングを飾るというのは、スピリチュアリティ文化の対抗文化的特徴を如実に表していると言えるだろう。この時期には、マハリシやサッチダーナンダ以外にも、バグワン・シュリ・ラジニーシやジドゥー、クリシュナムルティなどによる多くの東洋的思想が流布したり、インドやチベットへの放浪が一部の若者の間でおこなわれたり、ヨーガや瞑想といったアジア系の身体技法への関心が高まったりしていった」と述べています。
スピリチュアリティ文化の潮流とも密接に関連するものとして、自己実現や創造性の開発を重視する心理学の発達が挙げられます。アブラハム・マズローやカール・ロジャーズらは、一般の人たちを対象にした人間性心理学を発達させました。また人間性心理学を応用する形で、ヒューマン・ポテンシャル・ムーブメント(人間性回復運動)が展開されました。1962年にはこの運動の最大規模の拠点となるエサレン研究所がカリフォルニアに誕生しました。著者は、「この研究所では、エンカウンターグルやボディワークといった心理セラピーや身体技法とともに、瞑想やヨーガも自己変容のための技法として教えられるようになっていく。エサレン研究所がスタートしたのと同じ1962年には、サンフランシスコ禅センターもオープンしている。インドの瞑想やヨーガだけでなく、日本や韓国の仏教も欧米に伝わるが、その当初から心理学との相性はよかったと思われる」と述べています。わたしは、日本における心身医学の創始者であった池見酉次郎氏にエサレン研究所のことを教わり、拙著『リゾートの思想』(河出書房新社)の中で詳しく紹介したことがあります。
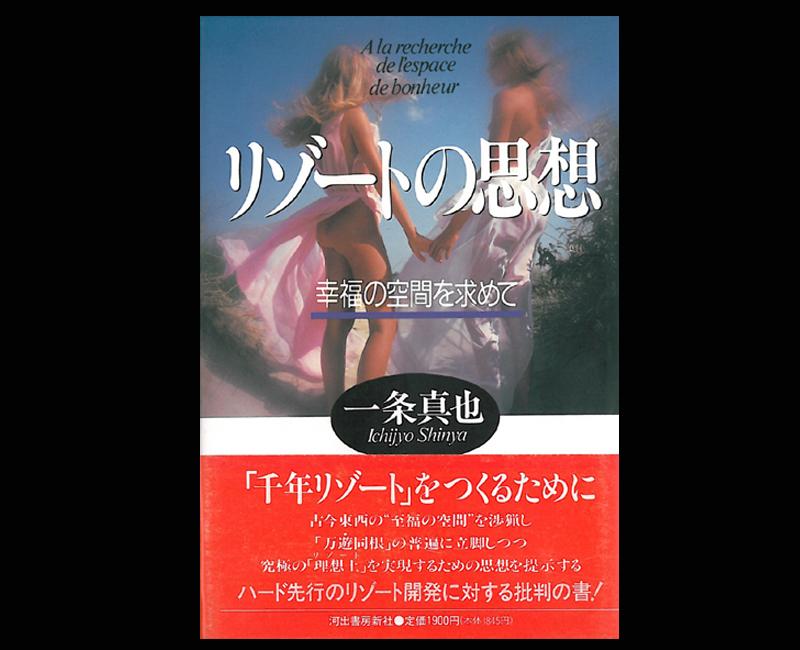 『リゾートの思想』(河出書房新社)
『リゾートの思想』(河出書房新社)
著者によれば、欧米人が東洋思想や新しい心理学に魅力を感じた背景には、科学的テクノロジーを重視し自然との共存を軽視した西洋物質文明への批判や、人間の心とからだを分離したものとして捉える心身二元論への懐疑があったといいます。カウンターカルチャーの中で支持を得た禅や瞑想は、うつ病の再発予防や一般の人たちの持続的幸福のために実践される西洋式のマインドフルネスにつながっていくことを指摘し、著者は「マハリシやサッチダーナンダらのヨーガは、90年代以降のスピリチュアリティを重視するヨーガ・ブームの土壌となる。そして、マズローらによる人間性心理学は21世紀に入ってから急激な発展をして今日に至るポジティブ心理学の源流になっている。さらに、ラジニーシやクリシュナムルティ、ラム・ダスらの思想と活動は、のちのネオ・アドヴァイタ・ムーブメントが発達する基盤となっていく。このように、1970年代中頃までには、21世紀になってから急速に広がる主要なタイプのスピリチュアリティ文化の基盤が確立したのである」と述べています。
「精神世界/ニューエイジという下位文化の生成」では、 1970年代後半から90年代半ばまでのスピリチュアリティ文化は、全体社会における下位文化 (サブカルチャー)として位置づけられるといいます。5「スピリチュアリティ文化の変遷Ⅱ(1990年代後半から2020年まで)の「洗練されたスピリチュアリティ」では、現代世界において、おそらくもっとも影響力のあるスピリチュアル・ティーチャーとしてエックハルト・トールが紹介されます。彼の思想と活動は、スピリチュアリティ文化とは明らかに異なる洗練された内容となっているといいます。トールの最初の本である『パワー・オブ・ナウ』(1997年)は300万部、『ニュー・アース』(2005年)は500万部以上売れています(それぞれ英語版)。著者は、「彼の書籍は発行部数のみでなく、包括的な内容も注目に値する。彼の本のなかには、キリスト教(旧約聖書、新約聖書、マイスター・エックハルト)、仏教(ブッダ、禅僧)、インド哲学(『ウパニシャッド』『バガヴァッド・ギーター』、ラマナ・マハルシ)などさまざまな宗教・哲学思想にふれつつ、自我のメカニズムについて、また思考と本来の自己を一体化してしまう問題点などを詳しく語っている。彼の書籍には現世利益的な内容や疑似科学的な技法などは一切語られていない」と述べます。
「非宗教領域でのスピリチュアリティの展開」では、スピリチュアリティ文化の非宗教制度領域への広がりは、教育においては、ホリスティック教育の重要性の指摘や、学校教育における「いのち」の重視、心を扱う学問としての臨床心理学やセラピー文化の人気に見いだされると指摘しています。また、ポジティブ心理学は、人間の持続的幸福を向上させる基盤となる美徳(「勇気」や「感謝」「スピリチュアリティ」など)を養うための介入調査を実施しているとして、「具体的に、ポジティブ心理学は特定の私立学校のカリキュラム全体に導入されたり、地域全体の教育プロジェクトに採用されたりしている。また、企業やアメリカ陸軍などでの研修にも使用されている」と述べています。
医療・社会福祉においては、死生学の発展、ホスピスやスピリチュアル・ケア(終末期医療)への関心が挙げられます。健康の分野でも、心身二元論への批判は高まっており、WHO(世界保健機関)が従来の「健康」の定義である「肉体的、精神的、社会的に幸福な状態」にスピリチュアルな次元も含める試案づくりをしたこともこの流れを示しています。この試案は1999年に総会で提案されましたが、さまざまな宗教伝統全体の意思統一には至らず、現在は保留となっています。著者は、「仏教に起源をもつ西洋式のマインドフルネスは、一般の人びとのストレス軽減や心の健康の維持・発展のために用いられている。その効果に関して科学的な根拠を強調し、指導者を養成し実践する拠点が大学や医療機関である場合も多い」と説明します。また、気功やヨーガ、太極拳のプログラムが各種のスポーツジムやカルチャーセンターで増えています。これらはホリスティックで心身一元論的な諸実践の現代社会への広がりを示す事例と言えるでしょう。
かつて大流行した「ロハス」という言葉は2010年代中頃になるとあまり使用されなくなりますが、それに代わるように2015年からは、国連サミットで採択されたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)が新たな標語になっていきます。著者は、「SDGsでは、17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169の目標が定められているが、そのなかにはロハスと共通する健康志向や自然との共生の理念が含まれている。ヨーガやマインドフルネスなど、心とからだのつながり、人間社会と自然とのつながりを強調し、自然にもやさしく、地球温暖化対策などを意識した商品が売れる時代になってきたのである」と説明しています。
ロハス、SDGsとも関連するスピリチュアリティ文化を包含するキーワードとして、「持続的幸福」やそれに類する用語(「ウェルビーイング」「ハピネス」など)が用いられるようになってきているとして、著者は「ヨーガやマインド・フルネスは心身の健康、それを通じての持続的幸福を育成するためのきわめて有効な手段として発展してきたと言ってよいだろう。またポジティブ心理学は、人びとの幸福度を高めるメカニズムの解明と実践方法を主目的とした応用心理学であり、その内容は『ウェルビーイング』や『幸福』と題された大学の講義科目として教えられるようになってきている。世界幸福度ランキングが各種の調査手法により公表されるようになったのも21世紀に入ってからである」と述べています。
6「現代スピリチュアリティと『宗教』概念の再考」では、宗教研究者はまず、宗教を広義に捉え、現代スピリチュアリティ文化を研究射程に入れることが不可欠となるとして、著者は「そこで注視すべき重要な点は、このスピリチュアリティが思想的には雑種性を帯び、世界各地で共通する現象となり、従来の宗教集団と異なる独自のネットワークをもつということである。このようなスピリチュアリティ文化の特徴は、グローバル化による単一の場所としての世界において、脱ローカル化したシンボル、儀礼、世界観が混じり合う状況が生まれたこと、またそこで生みだされる文化資源に、一般の人たちが比較的容易にアクセスできるようになったことと密接に結びついている」と述べるのでした。
第二章「21世紀西ヨーロッパでの世俗化と再聖化――イギリスのスピリチュアリティ論争の現在――」の1「社会学におkる『宗教』の位置づけ」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「欧米の社会科学、とりわけ社会学におけるほとんどすべての諸理論は、近代化と宗教との関係をきわめて重要な問題として扱ってきた。宗教が社会変動を促進するのか、あるいは阻害するのかに関しては、多くの異なる見解がある。しかし、現代社会におけるさまざまな変化が宗教に対して大きな影響をもたらすことに研究者たちは同意している。さらに言えば、社会学者のなかには、近代化による社会変動が宗教の社会的影響力を衰えさせる、場合によっては喪失させると主張する者もいる。これは広く『世俗化(secularization)」や「脱聖化(desacralization)」と呼ばれるものである」
19世紀末から20世紀初頭に活躍した社会学の巨人たちも、宗教の世俗化に関してくの議論をしていると指摘する著者は、「たとえば、エミール・デュルケム(1858-1917)は、社会秩序の必要性を主要な関心として、宗教がその秩序の重要な一部をなすとしている。デュルケムによれば、宗教には普遍性があり、それが完全に時代遅れになることはないという(Durkheim 1912)。しかし、社会的分業が高度に発達した産業化社会においては、宗教がもっていた社会全体を統合するという意義をいくぶん失うことになると予見していたのである(Durkheim 1893)」と述べています。
マックス・ウェーバー(1864-1920)もまた、現代社会において宗教の重要性は徐々に失われていくという見解を提示した1人です。ウェーバーによれば、現代社会は合理化と合理的知識、そしてとりわけ世界の「脱魔術化」によって特徴づけられるとして、著者は「一般の人びとは、伝統的な慣習や自らの感情よりも、目的的な合理性に基づいて行為するようになる。この合理化が宗教の影響を徐々に奪うことになる、というのがウェーバーの主張である。脱魔術化により、世界はもはや神秘や呪術による拘束を受けることがなくなる。そして超自然的なものは社会から徐々に失われていく。こうした事態をウェーバーは悲観的に捉え、不安に包まれた未来を予期していた」と述べます。
2「1960年代以降の世俗化論の成立と展開」の「社会の多元化と宗教の関係」では、1960年代以降、西洋社会において、キリスト教系の新宗教が発展し、またアジアの宗教伝統に由来する多くの宗教が伝播したり、出現したりしました。それらは総称して「新宗教運動(New Religious Movements)」と呼ばれるようになります。アンドリュー・グリーリーは新宗教運動の興隆が社会の再聖化を示すものであると捉えています。他方、新宗教運動の発展こそが世俗化を示す根拠であるとする立場もあるとして、著者は「価値観の多様化により、宗教が競合するようになった結果として生じた現象と理解できるからである。多元化社会とそこでの宗教の衰退をはっきりと論じるのがピーター・バーガーである。バーガーは、個々人の人生における意味付与の問題にとりわけ関心をもっていた。宗教は、このプロセスと密接にかかわる。個人が人生のなかで葛藤し、折り合いをつけていく際に必要な文化資源を提供すると考えられるからである」と述べています。
3「イギリスの世俗化論争」の「消費文化としての宗教」では、社会全体にかかわるより広い文脈から見ると、西洋社会の宗教風景は、チャールズ・テイラーが「現文化の大規模な主観的転回」と呼ぶものに呼応しているといいます。テイラーによれば、現代人はますます自らをユニークで隠れた深みをもつ存在として捉えるようになってきています。その傾向は消費文化の発展と結びつくものです。消費者として、個人は相当な選択肢をもち、自分たちは自己の人生を自らの選択を通じて形成することが可能だと感じる傾向があります。著者は、「宗教においても、『内なる声』の重要性、『自己の真正性』『内なる神』といったキーワードが現代文化では重要であり、『われわれの宗教』など気にかけられることはあまりない。むしろ、『唯一無二の私』が聖なるものにふれる経験をすることが不可欠なのである」と述べます。歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリもテイラーと同様に、自己の聖性を強調する一連の思想や活動に着目すると指摘し、著者は「ハラリは、『人間至上主義(humanism)』、すなわち人間がもつ神聖性は一人ひとりに宿るとする世界観を20世紀に栄えた宗教であると捉える。この人間崇拝の宗教は、20世紀後半になると、1人ひとりの『内なる声』や真正性、個人の直感や感性の探求を重視する自由主義的ヒューマニズムという形で繁栄してきたと論じている」と述べます。
4「宗教の世俗化と社会の再聖化」では、現代スピリチュアリティ文化が主流文化化すると、聖性は、宗教領域の枠内のみならず、非宗教領域にも浸透していく傾向が見られることが指摘されます。こうしたスピリチュアリティの主流文化化を示す具体例として、著者は「たとえば、仏教に起源を持つマインドフルネス(瞑想)は、今日では医療、心理療法、教育現場でも宗教の文脈を離れて活用されはじめている。うつ病の再発を防いだり、ストレスの低減に役立ったりするだけでなく、人びとの幸福感の向上によい影響のあることがわかってきたからである」と述べています。ここでは、ニューエイジ・スピリチュアリティの大きな特徴の1つである疑似科学的傾向は見られず、逆に科学的な根拠に基づく実践がなされていると指摘するのでした。
第二部「現代幸福論とスピリチュアリティ文化の諸相」の第四章「マインドフルネスと現代幸福論の展開」の1「幸福論の過去と現在」では、幸福(happiness,well-being)の探求は、人類史上、きわめて多くの宗教者、哲学者、文学者、政治家などの関心を惹きつけてきた普遍的テーマであるとして、著者は「ギリシャの哲人アリストテレスも中国の聖人孔子も、また偉大なる宗教者ブッダも、よりよく生きること、幸福に生きること、またその妨げとなっている苦しみの原因やその解決法を示すことが思索や教えの主要テーマだったと考えられる」と述べています。
こうした有史以来、今日に至るまで続いてきた人びとの幸福への関心ですが、以前とは異なる現代的特徴も浮かび上がってきています。現代における幸福論の特筆すべき点の1つは、科学者たちが幸福に直接関連する研究を積極的にはじめたことであると指摘し、著者は「1990年代中頃以降の過去30年間において、幸福に関する科学的研究は、とりわけ心理学、神経科学、精神医学といった人間の精神衛生にかかわる専門領域で顕著な発展を遂げている。また、それに関連して、人びとの幸福度の向上のために、従来は宗教的あるいはスピリチュアルなものとして捉えられていた実践や技法(瞑想やヨーガなど)がそうした特定の枠組みを超えて、医療や心理療法や教育の現場で普及してきていることも、見逃せない特徴であると筆者は捉えている」と述べます。
2「世界幸福度地図の作成と幸福経済の確立」の「世界幸福度地図とその社会的影響」では、2006年9月、イギリス・レスター大学の社会心理学者であるエイドリアン・ホワイトは、世界初の試みとなる「世界幸福度地図(World Map of Happiness)」を作成し、心理学の専門誌に発表したことが紹介されます。その結果は研究者のみならず、多くの国のマスコミならびに政府関係機関に大きな影響を与えることになりました。著者は、「ホワイトによる幸福度地図の発表後、世界一となったデンマークやGDPが世界で150位以下にもかかわらず、幸福度ランキングでは8位となったブータン王国に関して、国の幸福への取り組みや歴史、宗教、社会制度や教育、人びとの日常生活などについて、新聞、雑誌、テレビ番組での特集や多くの書籍を通じて紹介されている」と述べています。
ブータンが以前から掲げるGNH(国民総幸福量)という考え方が広く知られるようになったのも、この幸福度地図が作成されたことが大きなきっかけの1つとなっています。グローバルな視点から主観的幸福度を客観的に示す世界地図が作成されたことの意義はきわめて大きいと言えるとして、著者は「ホワイトの分析によれば、各国の幸福度は、人びとの健康、経済的豊かさ、そして教育の順で密接な関連が見出された。これら健康、富、教育の三要因にも相関関係のあることが判明している。世界全体で見たときに、医療・福祉サービスが充実し、国民一人あたりのGDPが高く、教育へのアクセスが高い国で生活する人びとのほうが、幸福である可能性ははるかに高いということになる。現代的生活にともなう不安やストレスは、世界全体で考えると健康や経済的水準、教育の必要性に比べると影響力は小さいようだ」と述べます。
ホワイトは自国イギリスの状況について、調査した178カ国中41位であり、「比較的よい」位置にあると評価しています。しかし、イギリスのマスコミや政府関係機関は、かならずしもホワイトのような肯定的な評価をしているわけではありません。2010年には、年間予算200万ポンドのウェルビーイング・プロジェクトの一環として、キャメロン首相により英国国立統計局に対して、幸福度の本格的調査に着手するよう指示がありました。それを受け、英国国立統計局は、国民の生活の質や満足度を測定する手段としての「幸福度指数(happinessindex)」をまとめています。2011年にまとめられた幸福度指標には、「1 個人の幸福/2 人間関係/3 健康/4 仕事/5 居住地域/6 個人の資産/7 教育と職業の技術/8 国の経済状況/9 国の統治に関する状況/10 自然環境」という10項目が挙げられています。
「幸福経済の確立」では、世界全体で見たとき、人びとの幸福度は、経済が発達し、医療・福祉が充実し、教育制度が整った国々で高いことを指摘しながらも、こうした条件が整備されている国々の間でも、国民の幸福度には違いがあるといいます。また同じ国の中でも、当然のことながら、個々人の幸福感には大きな差があります。著者は、「各国間での、また個々人による幸福感のちがいは何によって生じるのだろうか。幸福度ランキング、それをふまえての幸福度指数の作成の延長線上に、こうした諸課題に対処する形での社会政策の提案がなされている。このような取り組みは、人びとの幸福(well-being)実現のための社会・経済政策であることから、幸福経済と呼ばれることが多い」と述べるのでした。
3「1960年代以降のマインドフルネスの広がり」の「「マインドフルネスとは何か」では、現在のアメリカ、イギリスをはじめとする多くの社会において、「マインドフルネス」と呼ばれる瞑想法が広く普及していることが紹介されます。そもそもマインドフルネスとは何であり、どのように広がったのだろうかとして、著者は「さまざまな瞑想やヨーガの実践においてしばしば使用されているmindfulnessという語は、原始仏典のなかにあるパーリ語の『サティ(sati)』、サンスクリット語の『スムルティ(smrti)』を英訳する際に用いられたものである。イギリスの仏教学者、ルパート・ゲティンによれば、現在のマインドフルネスの起源は、テーラワーダ仏教の僧であるニャーナポニカ・テラ(Nyanaponika Thera)の考えに依拠しているといいます。彼が1954年に著した『仏教瞑想の真髄(The Heartof Buddbist Meditation:Satipatthna)』では、仏教瞑想の中核にマインドフルネスを位置づけ、その解説のなかで、マインドフルネスとは「正念」そのものではなく、「最小限のありのままの注意」であり、なんら神秘的なものではないと断っています。
1960年代以降、現代スピリチュアリティ文化の展開のなかで、タイ、ミャンマー(ビルマ)、スリランカなどに広がったテーラワーダ仏教(上座部仏教)の僧侶たちが主催する仏教の瞑想センターがアメリカやイギリス国内で開かれ、対抗文化の影響を受けた若者たちは瞑想実践に参加するようになりました。日本から伝わった禅仏教も欧米での瞑想への関心に大きく影響したと思われると推測し、著者は「1980年代に代になると、タイやミャンマーなどで本格的な瞑想修行をしたアメリカ人やイギリス人が自国に戻り、洞察瞑想やヴィパッサナー瞑想と呼ばれるセンターを開設する」と述べています。ミャンマー仏教は瞑想の本場だとされますが、わが社がサポートしている日本で唯一のミャンマー式仏教寺院「世界平和パゴダ」も「マインドフルネス・センター」として位置づければ大きな話題を呼ぶかもしれません。また、ベトナム人僧侶で世界的に著名なティク・ナット・ハンは、1991年に『マインドフルネスの奇跡』を出版しています。著者は、「彼は今日に至るまで、西洋世界において、ダライ・ラマ法王と並ぶもっとも影響力のある精神的指導者であり、彼の著作、講演、ワークショップでのマインドフルネスの実践は、このことばの英語圏における定着と普及に多大な貢献をしたものと思われる」と述べます。
マインドフルネスでは実際に何をするのでしょうか。マインドフルネスの実践的な技法には、ヨーガの動きをともなうもの、呼吸を観察するもの、歩く瞑想、座る瞑想などいくつかのものがあるとして、著者は「それらの技法のちがいは注意を払う対象がからだの感覚、呼吸、歩く動作(足裏の感覚)、座っているときの呼吸によるお腹の膨らみやへこみ、鼻先に感じる息、あるいは心の変化などの異なるポイントに向けられることにあると捉えれば理解しやすい。私たちは、通常移ろいゆく思考の波に支配されている。頭のなかのおしゃべり(思考)に翻弄されないための軸となるのが、呼吸や音や身体感覚などといったマインドフルネスの対象である。ただし、その対象が細やかなもの(鼻先にふれる息など)のほうが、粗雑なもの(身体感覚、マントラの音など)より注意を払いつづけることは困難となる。反対に、微細なものを対象としつつも、思考の波に巻き込まれないようになることは、いま、ここにただあることにつながるのである。こうした瞑想実践の原理は、古典ヨーガの経典『ヨーガ・スートラ』の内容ともほぼ完全に一致している」と説明しています。
「医療、心理療法としてのマインドフルネス」では、マインドフルネスの医療、心理療法の現場への普及は、ジョン・カバットジンによる功績が大きいことが紹介されます。彼は仏教の伝統に基づく瞑想の実践者であり、アメリカ・マサチューセッツ大学の医療センターに勤務していました。自らの瞑想体験に鼓舞されたカバットジンは1979年に医療センターにストレス低減クリニックを創設し、マインドフルネス・プログラムを導入。その後、マインドフルネス・ストレス低減法(Mindfulness Based Stress Reduction:MBSR)として確立し、瞑想の理論と実践にかかわる8週間の体系だったトレーニング・プログラムを開発します。著者は、「このプログラムが当初対象としたのは、リウマチなどの疼痛(うずくような痛み)ケアの患者であったが、それが次第に精神疾患やストレスへの対処法へと応用範囲を広げていく。カバットジンとその同僚たちは、心臓病、ガン、(高血圧、糖尿病などのよくない状態が長期にわたって改善されない)慢性病、睡眠障害、不安、パニックなどを含むさまざまな状態にある2万人以上を援助してきている」と説明します。
4「現代幸福論と新しいスピリチュアリティ文化のゆくえ」では、インドで2500年以上前から実践されていたディヤーナまたはジャーナ(瞑想)は、中国において(ジャーナが漢字で音写されて)禅那となり、やがて13世紀以降の日本において禅として花開くことになったことが紹介されます。また、上座部仏教の国々である、タイ、ミャンマー、スリランカなどにおいても、この瞑想の伝統は、ヴィパッサナー瞑想として仏教的修行の中核をなしています。著者は、「1960年代以降の欧米諸国における、現代スピリチュアリティ文化の誕生とその後の発展において、こうした瞑想の伝統は西洋人によって実践され、やがて宗教の文脈を離れて、医療や心理療法の手法として、また教育の一環として実践されて今日に至っている」と述べています。
アジアで生まれた精神・身体的技法であるマインドフルネスだからこそ、医療や教育現場への導入が容易だったという面はあるだろうという著者は、「仮に、西洋世界でキリスト教に依拠する、たとえば『祈り』を同じように導入しようとしたとき、既存の土着文化(伝統的キリスト教)との摩擦が生じた可能性は十分ある。他方、瞑想や坐禅に関する伝統文化がある日本においては、グローバル化のなかで生まれたマインドフルネスの普及により多くの時間と労力がかかるように思われる」と述べます。マインドフルネスを医療現場に導入したカバットジンは、「マインドフルネスはスピリチュアルか?」としてまとめられた一節で、「スピリチュアル」という言葉がはらむ問題性に言及しつつ、スピリチュアリティとそうでないものとの区別へ疑問を投げかけています。彼はまず、「マインドフルネスの作業とは、わたしたちが手にするすべての瞬間において、活力に目覚めることです。覚醒状態のかでは、すべてがインスピレーションを与えてくれます。スピリット(精神、精霊)の領域から除外されるものなどありません」としています。
第五章「現代マインドフルネス・ムーヴメントの功罪――伝統仏教からの離脱とその評価をめぐって――」の1「マインドフルネス・ムーヴメントの到来」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「21世紀以降、仏教瞑想に起源をもつ『マインドフルネス』と呼ばれる精神・身体技法は、アメリカ、イギリスをはじめとする多くの社会の医療、心理療法、企業、教育などのさまざまな分野で用いられてきている。わたしたちの心のあり方を判断することなく、『ありのままに注意する』ことを意味するマインドフルネスは、ストレスを軽減し、うつ病の再発を予防し、仕事やスポーツでの能力を発揮し、さらには生徒の集中力を高めることが明らかとなってきたからである。特定の宗教伝統に由来する実践が、現代社会では非宗教領域、しかもそのなかの主流に浸透してきている。こうした動向は、現代のスピリチュアリティ文化の特徴を考えるうえで大きな手がかりとなる」
人類史上、長らくの期間、宗教とスピリチュアリティは相互に代替可能な概念として用いられていましたが、1960年代後半以降の欧米では、一般の人々が明確な教義や組織がある「宗教」と対置する形で「スピリチュアリティ」の語を使用したり、自己規定したりするようになります。この新しいスピリチュアリティと呼べる現象は、社会文化状況の変化に呼応して、1960年代の対抗文化(カウンターカルチャー)から70年代半ば以降の下位文化(サブカルチャー)を経て、1990年代後半以降になると主流文化(メインカルチャー)としての特徴を持つようになってきたといいます。宗教学者の島田裕巳氏によれば、現代スピリチュアリティ文化が主流文化化すると、聖性は宗教領域の枠内のみならず、非宗教領域にも浸透していく傾向が見られる。これはやや誇張した表現を使えば、社会全体の聖化、あるいはそれ以前に世俗化の時代があったとする立場からは再聖化、ポスト世俗化として理解できる側面を持つといいます。著者は、「仏教に起源をもつ瞑想法が、医療、心理療法、教育現場でも宗教の文脈を離れて活用されている状況は、まさにスピリチュアリティ文化の主流文化化を示している。スピリチュアリティ文化として明らかに捉えられる実践を、意図的に『スピリチュアリティ』という語を避け、科学的に実証された方法であることを強調するところは、スピリチュアリティ文化の現代的なあり方を示しているようにも思われる」と述べています。
2「マインドフルネスの起源と発展」の「『マインドフルネス』瞑想の創造」では、現在、さまざまな社会領域で用いられる「マインドフルネス」という語は、原始仏典のなかにあるパーリ語の「サティ」、サンスクリット語の「スムルティ」を英訳する際に用いられたものであることが紹介されます。1881年刊行の『ブッディスト・スートラ』を翻訳するときに、ウィリアム・リース・デービッズが使用したのが最初であったといいます。その後、多くの研究者が「サティ」に関して、仏教のテキストを読み、それぞれの文脈において多様な解釈を示した。それというのも、「マインドフルネス(サティ)」には、「特定の事実を記憶すること」「想起すること」「心にとめること」「意識すること」など多くの意味が含まれるからです。1950年代以降になると、マインドフルネスをめぐる定義の一部は、瞑想実践から得られた知見を含むようになっていくと指摘し、著者は「現代のマインドフルネスの定義にもっとも大きく、そして決定的な影響を与えたのが、ドイツ人の仏教僧、ニャーナポニカ・テラ(Nyanaponika Thera)である」と述べます。
「対症療法としてのマインドフルネス」では、いくつもの社会領域において急速にマインドフルネスが普及した背景には、現代社会の直面する問題やそれに対応するための社会政策の変化が明らかに関連しているとして、著者は「WHO(世界保健機関)によれば、現在、うつ病は心臓病、がんに続く第三の主要な健康を害する問題となっているが、2030年には第1位となることが予想されている。うつ病をはじめとする精神疾患は、先進諸国においてはとくに深刻な問題であり、国家にとっても大きな経済的負担となっている。たとえばイギリスにおいて、メンタルケア関連の支出はきわめて大きく、抗うつ剤の費用だけで毎年約5000万ポンド(約18億円)かかっている。その負担額は今後増大していくことが予想される」と述べています。
3「仏教の断片化、あるいは再文脈化」の「仏教における改革運動」では、20世紀前半の仏教改革運動と21世紀のマインドフルネス・ムーブメントには多くの共通点があるとして、著者は「いずれも、僧院での出家生活に関心をもたず、仏教経典にほとんど馴染みのない一般の人たちを対象としていたことは偶然ではないだろう。またこれらの運動は、驚くほど即効性があることを約束している点でも共通している」と述べます。また、5「薄れゆく宗教・スピリチュアリティ・科学の境界」では、著者は「マインドフルネスというスピリチュアリティに密接にかかわる精神・身体技法が実践され、しかしそれが『宗教』や『スピリチュアリティ』と関連づけられることなく、科学的手法として理解され、実践されているところに今日的特徴があると言えるだろう」と述べています。
マインドフルネスの広がりは、科学や教育のあり方そのものを根底から変容させる可能性を持っているといいます。神経科学、心理学、認知科学、教育学におけるマインドフルネスの実践といった科学的研究が増加することによって、科学の世界が根底から揺らいでいる側面があるからです。なぜなら、マインドフルネスの実践が、科学は第三者の立場から客観的にアプローチすべきであり、研究対象に直接かかわる一人称の主体となるべきではないという「主観性のタブー」に異議申し立てをしていることになるからであるとして、著者は「現在、さまざまな領域で『内省的探求』と名づけられる一人称の調査方法を受け入れるようになってきていることは科学的潮流、ひいては教育のあり方にも大きな影響を与える可能性があると言える」と述べるのでした。
第六章「グローバル文化としてのヨーガとその歴史的展開」の2「近代ヨーガから現代体操ヨーガの発展へ」の「近代以前のヨーガ」では、ヨーガの起源は、紀元前2600年頃のインダス文明の時代にさかのぼるとする説があることが紹介されます。遺跡からヨーガのポーズをとっているとも解釈できる多数の(一辺2〜5センチほどの石に刻まれている)印章が見つかっているからです。また、紀元前500年頃のゴータマ・ブッダにヨーガの源流を求める人たちもいます。瞑想するブッダに真のヨーガ行者の姿を見出すからだろうとして、著者は「少なくとも、紀元後4-5世紀頃には古典ヨーガが成立したと考えるのが一般的である。この頃、パタンジャリによって195の章句から成る『ヨーガ・スートラ』経典が編纂されたためである。この経典では、『心のはたらきを止滅させること』をヨーガの最終目的とし、人間が煩悩から開放されて真の幸福へと至る道が示された」と述べています。
「1960―80年代におけるヨーガの発掘」では、反戦平和や既存の価値観に異議申し立てをする対抗文化を支持する若者たちの一部は、東洋思想だけでなく、呼吸法や瞑想などの身体実践を通じて意識変容に強い関心を示していったことが紹介されます。著者は、「こうした潮流なかで、たとえばカリフォルニアにあるエサレン研究所では、エンカウンターグループやボディワークといった心理セラピーや身体技法とともに、瞑想やヨーガも自己変容のための技法として教えられるようになっていく。またヨーガの思想、アーサナ、呼吸法、マントラ、瞑想などを体系的に学ぶ『インテグラル・ヨーガ』を掲げたスワミ・サッチダーナンダの教えが欧米の若者を中心に広がる。彼は、1969年にニューヨーク郊外で開催され、3日間で40万人以上が参加したウッドストック・フェスティバルのオープニングにおいて、物質的にも精神的にも重要な役割を担うアメリカへのメッセージを集まった聴衆に伝えている」と述べます。
3「日本におけるヨーガの展開」の「ヨーガの黎明期から1960年代の第一次ヨーガ・ブームへ」では、近現代の日本において、本格的なヨーガの伝播は、1919年に中村天風が天風会を設立したことに始まることが紹介されます。天風は、ヨーガの呼吸法を取り入れ、人間が本来生まれながらにもっている「いのちの力」を発揮する具体的な理論と実践を「心身統一法」として各界で説法をしました。その後、1940-50年代には、神智学者の三浦関造が竜王会を主宰し、「綜合ヨーガ」の研修会でアーサナや呼吸法を指導しました。著者は、「この2人は、日本のヨーガの草分け的存在であるとされている一般の人びとにヨーガが広がる大きなきっかけとなったのは、1950年代後半より活動をはじめた2人の人物による」と述べています。1人は、沖ヨガの創始者、沖正弘です。もう1人は、大学でインド哲学を長らく教え、60歳を過ぎてから本格的なヨーガの実践を始めた佐保田鶴治です。
ヨーガが一般の人々に急速に普及していた1995年、オウム真理教による地下鉄サリン事件をはじめとする一連の事件が発生しました。オウム真理教は、もともと「オウム神仙の会」と名乗るヨーガ道場を前身としていました。また、その思想がインドやチベットの宗教伝統の一部を基礎にし、この団体の活動においてはヒンドゥー語やサンスクリット語に起源をもつ用語が多用されていました。著者は、「結果として、聖なる音『オーム』や瞑想、また『ヨーガ』ということば自体にも、この教団のイメージがつきまとうことになる。オウム事件が日本のヨーガ界に与えた影響はきわめて大きかった。ヨーガ教室の多くは廃校となり、個人経営のヨーガ道場では、看板から『ヨーガ』の文字を外す所さえあった」と述べるのでした。
第七章「『スピリチュアルな探求』としての現代体操ヨーガ」の2「古典ヨーガからハタ・ヨーガへ」の「古典ヨーガの成立」では、「ヨーガ」とは、サンスクリット語で「軛(牛馬の首の後ろにかける横木)をかける、結びつける」という動詞から派生した名詞であり、「結合」「統合」を意味することが紹介されます。ヨーガの起源は数千年前にさかのぼるとする説もありますが、紀元後4-5世紀頃になると、パタンジャリが『ヨーガ・スートラ』を編纂したとされています。そこでは、さまざまな欲望や怒りや不安により私たちを揺り動かし、落ち着きなくさせる、「心のはたらき」を「止滅」することを最終目的とし、心を静めるための心的技法が重視されています。この経典に示された内容は「古典ヨーガ」と呼ばれています。著者は、「この心のはたらきを止滅させることは、人間が究極的な幸福に至る道とヨーガでは理解されている」と述べます。
第三部「スピリチュアリティ文化の開かれた地平」の第八章「ポジティブ心理学と現代スピリチュアリティ文化」の1「心理学とスピリチュアリティ文化のかかわり」では、現代スピリチュアリティ文化においては、自己の存在をかけがえのないものとして崇敬する「自己の聖性」をとりわけ重視し、スピリチュアルな体験をする個人の感性や直感、「本当の自分」の探求などに力点が置かれる傾向があると指摘されていることが紹介されます。20世紀後半には、1人ひとりの「内なる声」や真正性を強調する自由主義的ヒューマニズムが繁栄していましたが、現代スピリチュアリティ文化発展の社会的背景はこうした思想の広がりが基盤となっていたと言えるだろうとして、著者は「個人の創造性や自己実現にも密接に関連し、SBNRを自らのアイデンティティとする人びとを中心に支持されている心理学の分野の一つにポジティブ心理学という領域がある。ポジティブ心理学では、伝統宗教や現代スピリチュアリティ文化で重視される美徳(感謝、慈悲、自制心、超越性、スピリチュアリティなど)が持続的幸福の基盤となると捉えている。そのため、この領域ではこうした感情や価値観を科学的技法により発展させるための調査や介入を試みている」と述べています。
2「ポジティブ心理学の誕生と発展」では、マーティン・セリグマンがアメリカ心理学協会の会長に選出された1998年、従来の心理学を拡張し、病理学や心理的障害といった人間のネガティブな側面と同様に、ウェルビーイングと幸福に焦点を当てるよう明確な呼びかけをしたことが紹介されます。セリグマンのこの呼びかけに続く心理学的な潮流は、「ポジティブ心理学」と呼ばれています。ただし、この名称自体は1954年、アブラハム・マズローによる造語だそうです。著者は、「ポジティブ心理学は、1950、60年代に展開したマズローやカール・ロジャーズらによる従来の心理学が扱うことのなかった自己実現、創造性、至高体験などといったテーマを扱う人間性心理学の流れを汲んでいる。しかし、ポジティブ心理学は経験的アプローチを採用しているという点で、それとは大きく異なると主張する」と述べています。
3「ポジティブ心理学における美徳研究」の「ウェルビーイング理論とその主要概念」では、セリグマンの当初使用していた幸福(happiness)は、ギリシャ語の「ヘドニア(hedonia)」に近く、快楽志向の活動から得られる幸福の側面を指すという印象を持たれる傾向にあったことが指摘されます。これに対して、のちにセリグマンが強調したウェルビーイングは、アリストテレスの「ユーダイモニア(eudaimonia)を念頭に置き、人間としての私たちの可能性の実現を指します。セリグマンは、短期的なポジティブ感情にすぎないと考える幸福から、徐々に美徳(virtue)の強化に力点を置くようになります。1998年の創設当初、セリグマンは「本物の幸せ」(authentichappiness)に至る道筋を描くことを目指していましたが、彼はその方向性を修正し、幸福が以前考えていたような人間存在の唯一の目標ではないと主張するようになりました。そのため、happyでなく、flourish(繁栄、持続的幸福)やwell-beingという語を意図的に使用するようになったといいます。
「徳性と美徳の内容」では、徳性(あるいは美徳)は、宗教や哲学の主題であると同時に、健康や回復力、意義のある人生など、心の健康にも密接に関わることが指摘されます。ポジティブ心理学は、アリストテレスの倫理学から影響を受け、個人や共同体の繁栄に貢献すると考えられる人間の普遍的な徳性に着目しました。著者は、「セリグマンとクリストファー・ピーターソンは、アリストテレスのみでなく、プラトン、トマス・アクィナス、聖アウグスティヌス、ブッダ、孔子、老子、『ウパニシャッド』『バガヴァッド・ギーター』『武士道』など200冊に及ぶ哲学書や教典を読み、そこで強調されている美徳について探究した。それを通じて、ユダヤ・キリスト教、イスラーム、仏教、ヒンドゥー教などのいずれの文化圏においてもきわめて貴重な人間的性質として扱われ、世界の哲学や倫理体系における普遍的な原則とされている徳性を確認した」と説明しています。
4「ポジティブ心理学による介入調査の事例」の「日常への新たなまなざしと感動」では、ポジティブ感情を長年研究してきたバーバラ・フレドリクソンは、わたしたちが日常味わうポジティブ感情(感謝、喜び、愉快、勇気、安らぎなど)とネガティブ感情(怒り、憎しみ、恐怖など)の頻度において、前者の比率が3対1を上回る場合、人生は繁栄(持続的幸福)に向かうとする実証的研究成果を報告したことが紹介されます。著者は、「彼女が挙げているポジティブ感情は、ポジティブなことについて考える思考様式ではなく、繊細でかき消されてしまうエネルギーの質のようなものである。それに対するネガティブ感情は人間が生存し、よりよく生きるために必要不可欠なものを含むが(たとえば、外敵の恐怖、不正義に対する憤りなど)、反すうする(繰り返し立ち表われる)という性質をもつ。そのため、このネガティビティに支配される頻度が高くなることがいろいろな問題を生じさせていると論じている」と述べます。
5「科学性をまとったスピリチュアリティ文化の発展」では、ポジティブ心理学が美徳を促進するためのプログラムの目的について批判があることが指摘されます。アリストテレスとポジティブ心理学とでは、美徳に対する捉え方が大きく異なることが明らかだからです。著者は、「たとえば、勇気ある人びとは、持続的幸福(ユーダイモニア)を望んでいるために、そのように行動するわけではないとアリストテレスは慎重に説いている。むしろ、その美徳を達成した後に、人びとは勇気のために勇気をもって行動するにすぎない(アリストテレス『ニコマコス倫理学』第三巻六章)。したがって、勇気という徳の実現が個人の快適さにつながらない場合もある。これに対して、ポジティブ心理学によって開発されたエクササイズを用いて、勇気を養う努力をしている人は、自分自身を改善し、それがもたらすと感じる個人的な利益のために、その訓練に従事しているのである。言い換えれば、ポジティブ心理学における美徳の促進は、個人の持続的幸福のための手段となっていると言えるだろう。同様の批判は、マインドフルネスの功利的特徴に対してもなされており、両者には共通する傾向があることがうかがえる」と述べています。
ポジティブ心理学は、価値中立的な専門科学の1つであるとはっきりと表明しています。セリグマンらは心理学的な研究調査に基づき、持続的な幸福の向上をめざす技法を提示しています。しかし、ポジティブ心理学は、人々の精神的健康だけでなく、道徳的およびスピリチュアルなウェルビーイングにも密接に関係する科学であると指摘し、著者は「それは私たちがどのように生きるべきかという根源的な意味の問題にかかわっている。さらに、個人の選択、意思決定を重視する現代社会に適合的な規範的な側面をもつ。そこでは、セリグマンというカリスマ的なリーダーと熱狂的な支持者を擁し、感謝、寛容さ、超越性といった特定の価値を個人の持続的幸福のために促進しつつ、明るい未来を約束する」と述べるのでした。
第九章「人間崇拝の宗教としてのヒューマニズムーーヒューマニストUKの活動を手がかりとして――」の1「生命の尊さの意味基盤をもとめて」では、ヒューマニズムこそが20世紀に繁栄した「宗教」であると論じる歴史学者ハラリの議論を紹介し、この思想・実践の現状と今後の課題について考察しています。著者は、「ヒューマニズム思想は、一見すると『自己を超えた何ものかとのつながり』を強調する現代スピリチュアリティ文化とは無関係なように見える。しかし、両者が自己の聖性をとりわけ重視し、『本当の自分』を実現しようとめざす点では共通するところがある。現代スピリチュアリティ文化が発展するための土台は、このヒューマニズムの現代世界への広がりが前提になっているように思われる」と述べています。
2「ヒューマニズムの誕生と発展」の「ヒューマニズムの語源」では、ドイツ語の造語humanismusから派生したヒューマニズム(humanism)という名詞が最初に使われたのは1808年のことであると紹介されます。ヒューマニズムは明確に区別できる2つの意味を持っていました。一方で、ヨーロッパのルネサンス期に発展した古典研究の復興やそれに触発された思想的伝統、すなわち「教養」を指します。他方、いまだ体系だってはいませんが、非宗教的、非神学的、非キリスト教的な人生態度に幅広く言及する語として使用されたのです。著者は、「20世紀になると、後者の意味合いが強まり、ヒューマニズムはおもに神や宗教の代わりに、人間とその文化に価値を置く人生態度を示す語として用いられるようになる」と述べています。
4「人間崇拝の宗教」では、ヒューマニズムも実は新しいタイプの宗教であるとする有力な議論が紹介されます。世界的ベストセラー『サピエンス全史』『ホモ・デウス』の著者である歴史学者ハラリによるものです。ハラリによれば、キリスト教とヒューマニズムの攻防は、宗教と非宗教ではなく、伝統宗教と新しい宗教との対立ということになります。まずハラリは宗教を「超人間的な秩序の信奉に基づく、人間の規範と価値観の制度」と定義します。宗教であるためには、「超人間的な秩序」と「人間の規範と価値観の制度」という2つの要件を満たす必要があります。著者は、「たとえばサッカーには、多くの決まりごとや習慣、奇妙な儀式があり、『人間の規範と価値観の制度』となっている。しかし、それが人間自身の発明であることを誰もが承知している点で『超人間的な秩序』という条件を満たしていない。したがって、サッカーは宗教に含まれない。また、死者の霊や妖精の存在、生まれ変わりは、西洋人の多くが信じており、『超人間的な秩序』の要件を満たす」と説明します。
この2つの要件を満たすものが宗教となるわけです。ハラリによれば、20世紀以前には、人間の外部に存在する神への崇拝に焦点を合わせる「有神論の宗教」がヨーロッパにおいて支配的でした。しかし、このタイプの宗教は科学の発達にしたがって、次第に重要性を失っていきます。科学が解き明かす現実(リアリティ)とキリスト教的世界観とに大きな矛盾が生じたことに原因があります。これに代わって発展してきたのが、自然法則に基づく宗教であり、そこでは人類は独特で神聖な性質をもつとして崇拝されています。ハラリはこれを「ヒューマニズム(人間至上主義)の宗教」と呼びます。著者は、「伝統社会において、宇宙的意味が付与されるのは神によってであった。ところが近代は人間が力(科学)を手に入れた時代であり、聖なる個人の側が宇宙秩序に対して意味づけするという反転が生じている。つまり、現代は神の信仰から人間崇拝へと転換したのである」と説明します。また、「ヒューマニズムはまさに人間至上主義であり、20世紀を代表する「宗教」である。とくにそのなかの一分派である三つめのリベラリズムは、1989年に冷戦が終結された以後の現代社会でとりわけ支配的な宗教であるとハラリは捉えている」と述べます。
5「21世紀の生命観の課題と展望」では、21世紀の科学技術のさらなる発達により、人間を聖なるものとするヒューマニズム思想の基盤が根底から揺らぐことになるというハラリの考えが紹介されます。ハラリがそのように考える理由は、生命科学、遺伝子工学、人工知能の発達により、ヒューマニズム=人間至上主義が前提とする神話が崩壊するからです。著者は、「その神話とは、自由意思を有する意識をもった主体的個人という人間のイメージである。最先端の科学的成果によって、人間の自己決定は自由意思によるものとは言いがたく、人間の知性によってのみ創造できると信じられていた芸術活動が人工知能によっておこなわれるなど、従来の人間にまつわる信仰がつぎつぎと否定されている。その結果、人間存在の聖性イメージを保持することが困難になってきたと言えるだろう」と説明します。
第一〇章「『自己』論へのアプローチ――エックハルト・トールとネオ・アドヴァイダ・ムーブメント――」の1「1960年代以降の現代スピリチュアリティ文化」の冒頭を、著者は「21世紀に入って20年が経った現在、現代スピリチュアリティ文化は先進資本主義諸国の主流文にますます深く浸透してきているように思われる。たとえば、1990年代後半以降に起こった現代体操ヨーガの発展は現在に至るまで続いている。身体や呼吸に注意を向けるエクササイズにより、多くの人びとがスピリチュアルな体験をする機会となっている」と書きだしています。また2000年代以降に興隆したマインドフルネス・ムーブメントは、今日では医療、心理療法、教育などにも広がり、定着してきていることを指摘します。そして、従来はヨーガのアシュラム(道場)において、あるいは仏教の寺院において特定の修行の一環として行われていた実践は、伝統文化を離れ、幅広い社会・文化領域で一般の人々により行われてきていることが紹介しています。5「『自己の聖性』神話の終焉?」では、著者は「20世紀においては、有神論の宗教と人間崇拝の宗教とがともに存在していた。21世紀において、自己の聖性を強調する従来型のスピリチュアリティは、単一の自己を否定しつつも、意識の聖性を強調するネオ・アドヴァイタとともに、どのように共存していくことになるのだろうか。自己をめぐる言説に着目しつつ、今後のスピリチュアリティ文化の動向を注視することにしたい」と述べるのでした。
「おわりに」では、もともと「精神世界」への個人的関心の強かった著者が、現代スピリチュアリティ文化を研究する大きなきっかけは、島薗進氏の『現代救済宗教論』(青弓社、1992年)と出会ったことだったと紹介されます。著者は、「早いものでそれから30年近くになる。この本に所収されている『新宗教と新霊性運動――日本の新宗教とは何か』では、新宗教、呪術的大衆文化とともに、日本やアメリカにおいて展開する『精神世界』やニューエイジを現代宗教における第三の道として論じていた。その後に刊行された同氏による『精神世界のゆくえ』(東京堂出版、1996年)では、この社会・文化的潮流を宗教文化史のなかに位置づけ、本格的な議論が展開される。これらの考察により示された研究成果は、宗教社会学を専門とする筆者にとってとても大きな知的刺激となり、また転機となったことはまちがいない。島薗氏による先駆的研究以外にも、2000年代以降になると国内外において数多くの重要な研究がおこなわれてきている。こうしたスピリチュアリティ文化の研究領域に対して、本書が何らかの学術的貢献ができることを願うばかりである」と述べるのでした。わたしも島薗先生に私淑する者として、『現代救済宗教論』や『精神世界のゆくえ』は何度も読みました。もちろん宗教学者として圧倒的な学問的業績を誇る島薗先生ですが、本書の著者のような後進の学者を生み、育ててこられたことも偉大な業績であると思います。