- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.12.25
もともとクリスマスはヨーロッパの「死者の祭り」ですが、『死は存在しない』田坂広志著(光文社新書)を読みました。サブタイトルは「最先端量子科学が示す新たな仮説」。著者は1951年生まれ。1974年東京大学卒業。1981年同大学院修了。工学博士(原子力工学)。1987年米国シンクタンク・バテル記念研究所客員研究員。1990年日本総合研究所の設立に参画。取締役等を歴任。2000年多摩大学大学院の教授に就任。現名誉教授。同年シンクタンク・ソフィアバンクを設立。代表に就任。2005年米国ジャパン・ソサエティより、日米イノベーターに選ばれる。2008年世界経済フォーラム(ダボス会議)のGlobal Agenda Council のメンバーに就任。2010年世界賢人会議ブダペスト・クラブの日本代表に就任。2011年東日本大震災に伴い内閣官房参与に就任。2013年全国から7300名の経営者やリーダーが集まり「21世紀の変革リーダー」への成長をめざす場としての「田坂塾」を開塾。著書は100冊余。
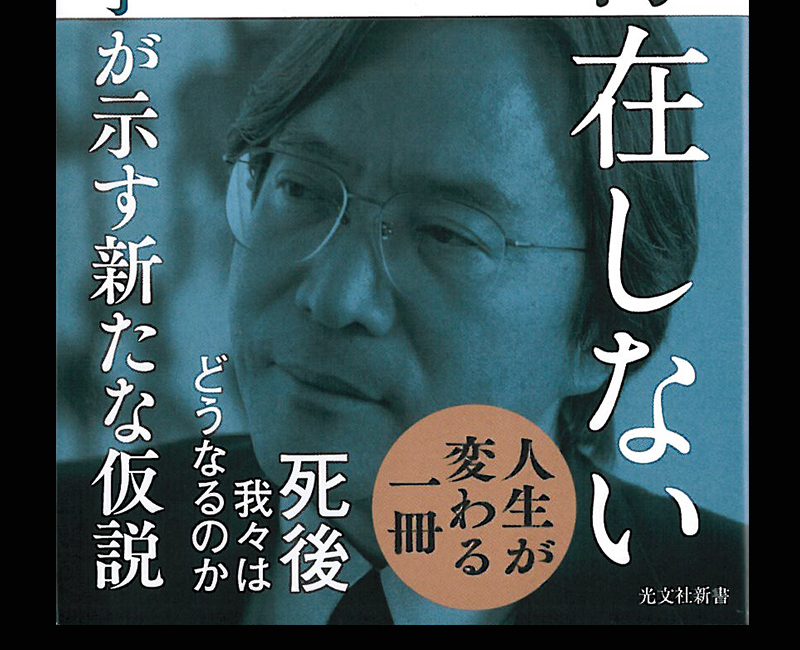 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、著者の顔写真ととともに「死後 我々はどうなるのか」「人生が変わる一冊」と書かれています。また、帯の裏には、「かつて『死後』についてこのように語った本があっただろうか」「この宇宙のすべての情報を記憶する『ゼロ・ポイント・フィールド』」「そこからこの壮大な物語は始まる」「――人類数千年の謎 その答えを求め――」と書かれています。
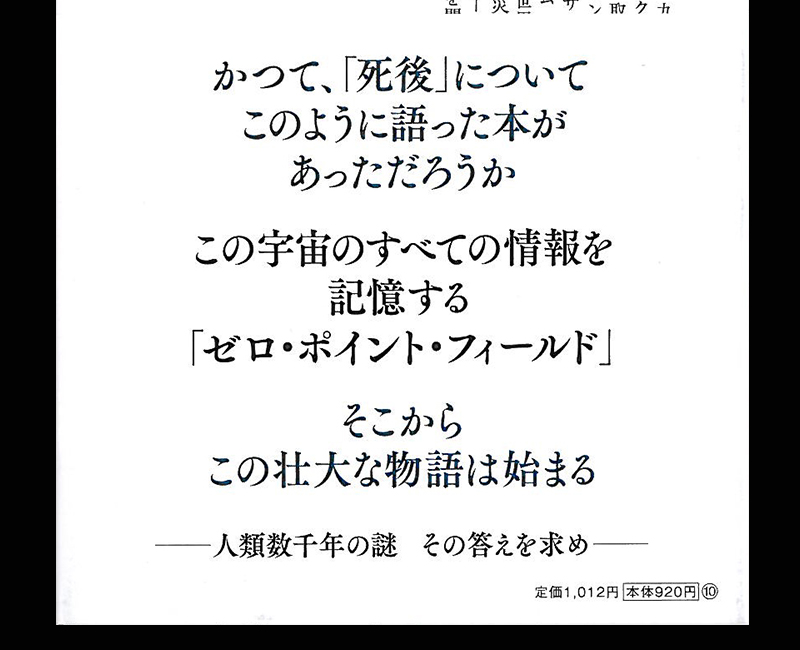 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには、「筆者は、本書を、次のような『問い』を抱かれた方々に読んで頂きたいと思い、書いた」として、以下のように書かれています。
・「死」を直視すべきときを迎えている方々
・「科学」にも「宗教」にも疑問を抱かれている方々
・最先端量子科学の「仮説」に興味を持たれている方々
・人生で「不思議な体験」が起こる理由を知りたい方々
・肉親の「死」について切実な思いを抱かれている方々
・「死」についての思索を深めたい方々
カバー後そでには、「最先端科学が示唆する『死後の世界』の可能性」として、「これまでの『科学』は、『死後の世界』の存在を、否定してきた。それゆえ、『死後の世界』を肯定する『宗教』とは、決して交わることが無かった。しかし、近年、最先端量子科学が、一つの興味深い『仮説』を提示している。その『新たな仮説』は、『死後の世界』が存在する可能性を、示唆している。では、その『仮説』とは、どのようなものか、どのような科学的理論か。もし、その『仮説』が正しければ、「死後の世界」とは、どのようなものか。この『死後の世界』において、『我々の意識』は、どうなっていくのか。もし、その『仮説』が正しければ、それは、この人生を生きる我々に、何を教えるのか。もし、この『仮説』が正しければ、『科学』と『宗教』は、融合していくのか」とあります。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序 話 この本を手に取られた、あなたへ
第一話 あなたは、「死後の世界」を信じるか
第二話 現代の科学は「三つの限界」に直面している
第三話 誰もが日常的に体験している
「不思議な出来事」
第四話 筆者の人生で与えられた「不思議な体験」
第五話 なぜ、人生で「不思議な出来事」が起こるのか
第六話 なぜ、我々の意識は
「フィールド」と繋がるのか
第七話 フィールド仮説が説明する
「意識の不思議な現象」
第八話 フィールド仮説によれば
「死後」に何が起こるのか
第九話 フィールド内で我々の
「自我」(エゴ)は消えていく
第一〇話 フィールドに移行した
「我々の意識」は、どうなるのか
第一一話 死後、「我々の意識」は、
どこまでも拡大していく
第一二話 あなたが「夢」から覚めるとき
終 話 二一世紀、「科学」と「宗教」は一つになる
「謝辞」
「さらに学びを深めたい読者のために」
序話「この本を手に取られた、あなたへ」の「最先端科学が示唆する『死後の世界』の可能性」では、著者は「これまでの『科学』は、『死後の世界』の存在を、否定してきた。それゆえ、『死後の世界』を肯定する『宗教』とは、決して交わることが無かった。しかし、近年、最先端量子科学が、1つの興味深い『仮説』を提示している。その『新たな仮説』は、『死後の世界』が存在する可能性を、示唆している。では、その『仮説』とは、どのようなものか、どのような科学的理論か。もし、その『仮説』が正しければ、『死後の世界』とは、どのようなものか。この『死後の世界』において、我々の『意識』は、どうなっていくのか。もし、この『仮説』が正しければ、それは、この人生を生きる我々に、何を教えるのか。もし、この『仮説』が正しければ、『科学』と『宗教』は、融合していくのか。本書は、そのメッセージを語ったものであるが、本書で述べる『最先端量子科学が示す新たな仮説』とは、『ゼロ・ポイント・フィールド仮説』と呼ばれるものである」と述べています。
著者は、永年、科学者と研究者の道を歩んできており、本来は「唯物論的思想」の持ち主でした。しかし、自身の人生において、「不思議な体験」、例えば、「直観」や「以心伝心」、「予感」や「予知」、「シンクロニシティ」や「コンステレーション」などの体験を、きわめて象徴的な形や劇的な形で、数多く与えられたために「死後の世界」が存在すると考えるようになったそうです。著者は、「なぜ、我々の人生において、『不思議な出来事』が起こるのか」「なぜ、世の中には、『死後の世界』を想起させる現象が存在するのか」「もし、『死後の世界』というものがあるならば、それは、どのようなものか」を解き明かしたいと考えたそうです。そして、永年の探求と思索の結果、たどりついたのが、先端量子科学が提示する、この「ゼロ・ポイント・フィールド仮説」だというのです。
第二話「現代の科学は『三つの限界』に直面している」の「いまも『意識の謎』を解明できない現代の科学」では、現代の科学が、決して「万能」でもなく、「無謬」でもなく、解き明かせない「謎」を数多く抱えた「限界」のあるものであることが理解できるだろうとして、著者は「そうであるならば、我々は、現代の科学の主張を無条件に信じ込み、『現代の科学が否定しているのだから、神秘的な現象や死後の世界は存在しない』という固定観念は、一度、取り去って、まずは、虚心に、我々の生きているこの世界を見つめてみる必要があるだろう。特に、現代の科学が直面する最大の問題の1つは、『意識の謎』を解明できないという問題であると指摘します。
続けて、著者は「その『意識の謎』のうち、最も根源的な問題は、そもそも、現代の科学は、『物質』か『意識』というものが、どのようにして生まれてくるのかを、説明できないのである。現代の脳科学は、そのことを、『脳神経の作用で、意識が生まれてくる』と説明するが、この説明そのものに、多くの科学者や哲学者が疑問を抱いている。むしろ、現在、最も注目されているのは、『そもそも「物質」そのものが、極めて原初的な次元で「意識」を持っているのではないか』という仮説である。すなわち、ルネ・デカルト以来、当然と考えられてきた、『物質』と『意識』というものを対立的に捉える考え方ではなく、むしろ、『物質』の根源的構成要素である、量子や素粒子そのものに、極めて原初的な次元の『意識』が備わっているという考えである」と述べるのでした。
「『説明できないものは、存在しない』とする頑迷な立場」では、「視線感応」や「以心伝心」、「予感」や「予知」や「占い的中」、「既視感」や「シンクロニシティ」といったものは、わたしたちの誰もが日常に体験するといいます。そして、古今東西、無数の人々が体験し、報告されてきましたが、こうした「意識の不思議な現象」を、現代の科学は説明できないと指摘し、著者は「現代の科学は、『説明できないものは、存在しない』という立場をとるため、これらの『意識の不思議な現象』を、すべて、『単なる偶然』『ただの錯覚』『何かの思い込み』『一種の幻想』『脳神経の誤作用』といった理由で説明しようとするのである」と述べています。
第三話「誰もが日常的に体験している『不思議な出来事』」の「筆者が永く抱いてきた『唯物論的世界観』」では、著者が1970年に東京大学に入学し、科学技術を学ぶ工学部に進学の後、先端科学である原子力工学の専門課程で博士号を得た人間であると自己紹介し、「その後、米国の国立研究所で研究に従事し、原子力関係の国際学会でも委員を務めた人間である。従って、『科学者』としての訓練を受け、『研究者』としての道を歩んできた人間であり、基本的には、現代の科学、すなわち『唯物論的科学』や『物質還元主義的科学』の立場に立ってきた人間である」と述べています。すなわち、著者は、唯物論的思想から、「死とは、無に帰することである」との信念を持って生きてきたのでした。そして、さらに言えば、「無に帰すること」を恐怖と捉えることもなく、むしろ、「無に帰することは、やすらぎである」との思想さえ抱いて、30歳過ぎまで生きてきたのです。
「筆者に与えられた数々の『意識の不思議な体験』」では、現在の著者は、現代の科学では「単なる偶然」「ただの錯覚」「何かの思い込み」「一種の幻想」「脳神経の誤作用」として切り捨てられてきた「意識の不思議な現象」が、厳然として存在することを信じるようになったとしながらも、「ただし、それは、決して、すぐに『超能力』や『霊的世界』を信じる神秘主義的・オカルト的な思想に向かったのではなく、あくまでも、1人の科学者として、これらの不思議な現象を説明できる『科学的根拠』があると、信じるようになったのである。そして、永年の探求の結果、その『科学的根拠』として、現代の最先端量子科学が示す『1つの仮説』にたどり着き、この仮説が、多くの謎を解明できることを確信した」と述べています。
第五話「なぜ、人生で『不思議な出来事』が起こるのか」の「最先端量子科学が示す『ゼロ・ポイント・フィールド仮説』」では、「ゼロ・ポイント・フィールド仮説」について言及しています。もし、この仮説が正しければ、著者が体験したさまざまな「不思議な出来事」や「意識の不思議な現象」の正体が、科学的に明らかになるだけでなく、さらには人類の数千年の歴史の中で、多くの宗教家によって語られ、無数の人々によって信じられてきた、「神秘的現象」や「神秘的体験」の正体もまた、明らかにされるのではないかとの予感を抱いたといいます。「ゼロ・ポイント・フィールド仮説」とは、一言で述べるならば、この宇宙に普遍的に存在する「量子真空」の中に「ゼロ・ポイント・フィールド」と呼ばれる場があり、この場に、この宇宙のすべての出来事のすべての情報が「記録」されているという仮説です。
「無限のエネルギーが潜む『量子真空』」では、「量子真空」の中には、壮大な宇宙を生み出せるほどの莫大なエネルギーが潜んでいると述べ、著者は「現代科学の最先端の量子物理学においては、何もない『真空』の中にも、莫大なエネルギーが潜んでいることが明らかにされているのであるが、このことは、「真空」を「無」と考える一般の常識からすると、なかなか理解できないことであろう。なぜなら、密閉された容器の中から空気を含むすべての物質を外に吸い出し、容器の中を完全な『真空』の状態にしても、なお、その『真空』の中には、莫大なエネルギーが存在しているのである。そして、このエネルギーのことを、量子物理学では『ゼロ・ポイント・エネルギー』と呼んでいるのである。これは、たしかに、我々の常識を超えている」と述べています。
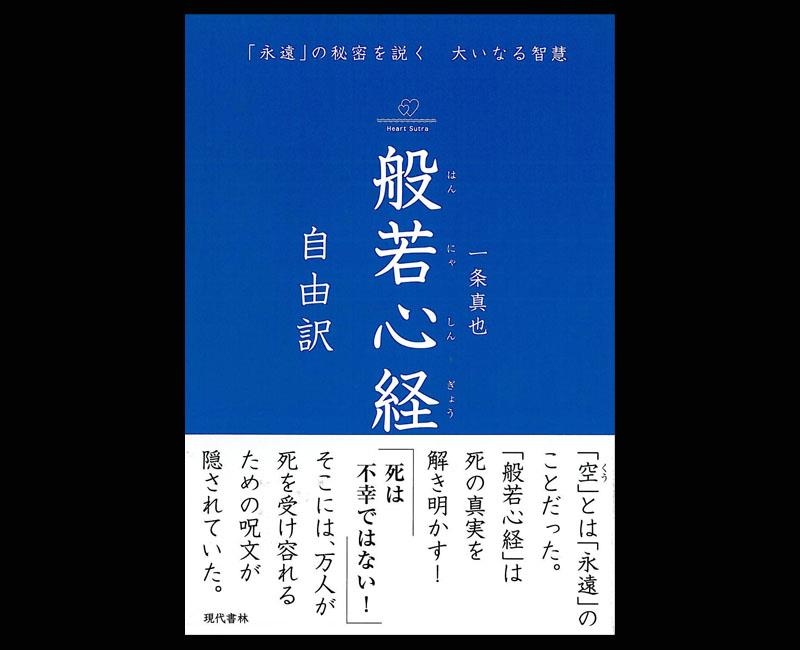 『般若心経 自由訳』(現代書林)
『般若心経 自由訳』(現代書林)
この「量子真空」に無限のエネルギーが潜んでいるという考え方は、「空」とは「永遠」のことであるという拙著『般若心経 自由訳』(現代書林)のメッセージにも通じますが、同書では空海の『般若心経秘鍵』にならって色即是空の色を「波」、空を「海」に例えました。本質は海であり、波とはあくまでも現象に過ぎないということです。すると、本書『死は存在しない』でも、著者は「この世界に『物質』は存在しない、すべては『波動』である」として、「いま、静かな湖面の上を吹きわたる風を想像して頂きたい。この場合、風は『空気の波動』であり、それが、湖面に『水の波動』である波を生み出す。それは、言葉を換えれば、『風』という波動エネルギーの痕跡が、『湖面の波』という波動情報として『記録』されるということである。そして、湖面の上を、様々な『風』が吹きわたるならば、そのすべてが、『湖面の波』して『記録』されるだろう」と述べているので驚きました。
これが、現実世界(湖面の上)での「出来事」(風)を、ゼロ・ポイント・フィールド(湖面)が、「波動情報」(湖面の波)として記録するということのイメージであるといいますが、著者は「ただし、現実の風や湖面では『波動のエネルギー』が減衰してしまい、この波動の痕跡は、時間とともに消えてしまう。しかし、ゼロ・ポイント・フィールドは『量子的な場』(Quantum Field)であるため、『エネルギーの減衰』が起こらない。そのため、このフィールドに『記録』された『波動情報』は、永遠に残るのである」と述べます。
「『ゼロ・ポイント・フィールド仮説』は荒唐無稽な理論ではない」では、「宗教」の世界では、不思議なことに「ゼロ・ポイント・フィールド」と極めて似たビジョンが、遥か昔から語られているとして、著者は「例えば、仏教の『唯識思想』においては、我々の意識の奥には、『末那識』と呼ばれる意識の次元があり、さらにその奥には、『阿頼耶識』と呼ばれる意識の次元があるとされており、この『阿頼耶識』には、この世界の過去の出来事のすべての結果であり、未来のすべての原因となる「種子」が眠っているとされている。また、『古代インド哲学』では、『アーカーシャ』の思想が語られており、この『アーカーシャ』とは、宇宙誕生以来のすべての存在について、あらゆる情報が『記録』されている場であるとされている」と述べます。ゼロ・ポイント・フィールドからは、神智学や人智学でいう「アカシックレコード」を連想しました。
「フィールドに『ホログラム原理』で記録される『すべての波動』」では、わたしたちの生きるこの宇宙や、この世界は「ホログラム的構造」であるといいます。著者は、「すなわち、『部分の中に、全体が宿る』という不思議な構造については、これも、昔から、古い宗教的叡智や詩人の神秘的直観が、その本質を洞察している。例えば、仏教の経典『華厳経』においては、『一即多 多即一』の思想が語られており、英国の神秘詩人、ウィリアム・ブレイクは、『一粒の砂の中に、世界を見る』という言葉を語っている」と述べるのでした。
「我々の『未来』と『運命』は、すでに決まっている」では、「ゼロ・ポイント・フィールド」には、「過去から現在に至る様々な出来事」の情報が存在し、それらの組み合わせから生まれてくる「起こり得る様々な未来」についての情報も存在するとして、著者は「それゆえ、もし、我々の意識が、この『ゼロ・ポイント・フィールド』に繋がることができるならば、『未来』を『予感』したり、『予知』したり、『占い』を行ったりすることは、ある程度、できるのである」と述べています。
「『相対性理論』では、過去、現在、未来は同時に存在している」では、実は、現代物理学の世界では、「過去」「現在」「未来」は、「同時に」存在しているものとされているとして、著者は「実際、アインシュタインは、歴史的な業績である『相対性理論』において、我々が生きる三次元の『空間』に、第四の次元として『時間』を加え、四次元の『時空連続体』(Space-Time Continuum)という考え方を提唱しており、この『時空連続体』においては、『過去』『現在』『未来』は、同時に存在するものとして扱われている」と述べます。
また、現代の最先端物理学者、ポール・デイヴィスは、「時間」というものを「タイムスケープ」(Time-Scape)として捉えています。それは、丁度、「ランドスケープ」(Land-Scape)、すなわち「風景」と同様、地図を広げると、すべての山や河や地形が一目で見て取れるように、この宇宙の空間的な広がりのすべてと、宇宙の時間的広がり(歴史)のすべてが、一目で見て取れるものです。この「タイムスケープ」においても、「過去」「現在」「未来」は、同時に存在するものとして捉えられており、「ゼロ・ポイント・フィールド」の中では、「過去」「現在」「未来」の情報は、おそらく、こうした「タイムスケープ」のような形で存在していると、著者は考えます。
この「タイムスケープ」のイメージを見事に語ったのが、一条真也の映画館「インターステラー」で紹介したクリストファーノーラン監督のSF映画です。この映画において、俳優のアン・ハサウェイが演じる、科学者であり宇宙飛行士である主人公、アメリア・ブランドは「五次元の存在は、谷を下るように過去へ、山を登るように未来へ行ける」という言葉を語っています。また、アインシュタインが、友人との書簡の中で、「我々物理学者にとっては、過去、現在、未来というものは幻想なのです。それが、どれほど確固としたもののように見えても、幻想にすぎないのです」という言葉を残していることは良く知られています。
第六話「なぜ、我々の意識は『フィールド』と繋がるのか」の「ノーベル賞学者ペンローズの『量子脳理論』が解き明かす『意識の謎』」では、著者は、「なぜ、我々の意識が、この『ゼロ・ポイント・フィールド』に繋がることができるのか。そして、そこに記録されている『宇宙のすべての出来事の情報』や『過去、現在、未来の出来事の情報』に繋がることができるのか。その理由は、我々の『意識の場』である脳や身体は、この『ゼロ・ポイント・フィールド』と量子レベルで繋がることができるからである。そのため、脳や身体の、ある特殊な状況においては、我々は、『ゼロ・ポイント・フィールド』から情報を受け取ることができ、このフィールドに情報を送ることができるのであり、その特殊な状況において、我々の脳や身体は、『宇宙のすべての出来事の情報』や『過去、現在、未来の出来事の情報』に繋がることができるのである」と述べています。
第七話「フィールド仮説が説明する『意識の不思議な現象』」の「なぜ、フィールドでは『類似の情報』が集まってくるのか」では、古今東西の「運気論」で「引き寄せの法則」というものが共通に語られていることが紹介されます。著者いわく、その理由は、「無意識」の世界では、ゼロ・ポイント・フィールドを通じて、「類似の情報」が集まってくるからであるからだといいます。では、なぜ、フィールドに繋がると、「類似の情報」が集まってくるのか。それは、「無意識」の世界で、何かを「想う」ということは、その「想念」に関連した情報を「探す」ことや、「集める」ことに他ならないからであるといいます。
「なぜ、天才は、アイデアが『降りてくる』と感じるのか」では、天才たちは、おそらく無意識の世界でゼロ・ポイント・フィールドに繋がり、そのことによって、フィールドから創造的なアイデアや発想を引き出していると考えられるといいます。すなわち、それらの創造的なアイデアや発想は、古今東西の天才や賢人たちの「該博な知識」や「深遠な叡智」が、ゼロ・ポイント・フィールド内で縦横に結びついて生まれたものであろうと推測し、著者は「言葉を換えれば、『天才』と呼ばれる人々が発揮する直観力や創造力、発想力や想像力といったものは、実は、彼らの『脳』が生み出すものではなく、彼らの『脳』が『ゼロ・ポイント・フィールド』と繋がることによって与えられるものであると考えられる」と述べます。
著者は、過去25年間に、100冊余りの著書を上梓してきました。そのテーマは、生命論パラダイム、複雑系科学、弁証法哲学、ガイア思想、未来予測、資本主義、知識社会、情報革命、経営とマネジメント、戦略思考、人生論、仕事論、プロフェッショナル論、意思決定、企画力、営業力など、多岐にわたっています。著者は、「正直に言えば、なぜ、こうした幅広いテーマで著書が執筆できるのか、自分でも不思議に思うことがある。ただ、1つ言えることは、こうした著書を執筆するときには、いずれも、何かに導かれるように、様々なアイデアや発想が降りてきて、自然に必要な情報が集まり、そこに一冊の本が生まれてくるのである。そのため、書棚に行き、過去の自分の著作を読むと、しばしば、『これは、自分が書いうか…』という不思議な感覚に囚われることがある」と述べます。すなわち、著者の無意識がゼロ・ポイント・フィールドに繋がり、その著書の執筆に必要な、様々な情報や知識や叡智が、「直観」という形で「降りてくる」ことによって、著書が生まれてきたものであると感じるというのです。わたし自身、100冊余りの著書がありますが、著者と同じことを感じることもあります。
「昔から無数の人々が信じてきた『神』や『仏』の実体は何か」では、「神」や「仏」や「天」とは「ゼロ・ポイント・フィールド」に他ならないとして、著者は「すなわち、その『神』や『仏』や『天』とは、宇宙の歴史始まって以来の『すべての出来事』が記録され、人類の歴史始まって以来の『すべての叡智』が記録されている、この『ゼロ・ポイント・フィールド』に他ならない。なぜなら、無数の人々が『神秘的な出来事や体験』と感じてきた、不思議な『直観』や『以心伝心』、『予感』や『予知』や『占い的中』、『シンクロニシティ』や『コンステレーション』などの現象は、これらの人々の無意識が『ゼロ・ポイント・フィールド』と繋がることによって、起こってきたからである。そして、もし、そうであるならば、昔から、世界の様々な宗教において『祈祷』や『祈願』、『ヨガ』や『座禅』や『瞑想』と呼ばれ、実践されてきた諸種の技法は、実は、この『ゼロ・ポイント・フィールド』に繋がるための『心の技法』に他ならない」と述べるのでした。
第八話「なぜ、子供たちは『前世の記憶』を語るのか」では、「前世の記憶」や「転生」や「生まれ変わり」といった事例が世界中に無数にあるとして、それらを客観的にまとめた有名な書籍に米国ヴァージニア大学の精神科教授、イアン・スティーヴンソンが書いた『前世を記憶する子どもたち』や、彼の後継者であるジム・タッカー教授の書いた『リターン・トゥ・ライフ』などを紹介。著者は、「これまでは、こうした事例は、『転生』や『生まれ変わり』を信じる人々からは、『人間は、死んだ後、他の人間に生まれ変わる』ということの明確な証拠として語られてきたが、『ゼロ・ポイント・フィールド仮説』の立場に立つならば、これらの子供たちは、何らかの理由で、その意識がゼロ・ポイント・フィールドに繋がり、そのフィールドに記録されている、ある過去の人物の情報を語っているのであろう。すなわち、子供たちが『前世の記憶』を語るということは、必ずしも『転生』や『生まれ変わり』が存在する証拠ではない。実際、この子供たちは、皆、成長するにつれて、そうしたことを語らなくなるという事実を見ても、子供たちが語ったのは、ゼロ・ポイント・フィールドから伝わってきた『ある人物の人生に関する情報』であると考える方が、合理的であろう」と述べています。
「なぜ、『死者との交信』が起こるのか」では、「霊媒」や「死者との交信」も、「ゼロ・ポイント・フィールド仮説」の立場に立つならば、「霊界」から故人を呼び出したのではなく、「霊媒」とは、ゼロ・ポイント・フィールドに繋がる能力の高い人物であり、フィールドから、その故人に関する様々な情報を受信し、それを、家族の前で語っているのではないかと推測します。また、言葉づかいや仕草についても、フィールドからの情報に基づいて無意識に真似をしているのであろうと推測し、著者は「さらに、会話についても、フィールドから故人の存命中の考えや思いを感じ取ったならば、当意即妙に、家族の質問にも答えることができるだろう。『ゼロ・ポイント・フィールド仮説』に立つならば、それが、『霊媒』や『死者との交信』の実体であると考えられる。そして、同様に、世の中で語られる『背後霊』についても、それが『見える』という人は、その背後霊になったとされる故人の様々な情報を、ゼロ・ポイント・フィールドから受け取って、語っているのであろう」と述べます。このあたりは心霊現象の原因を「死者の仕業」とするか「生者の超能力」とするかで議論した19世紀の心霊科学論争を連想させます。
「現実世界の『自己』が死んだ後も、深層世界の『自己』は生き続ける」では、米国の発明家であり、未来学者でもあるレイモンド・カーツワイルが紹介されます。彼は人工知能研究の世界的権威でもありますが、著書『シンギュラリティは近い』において、人類は、将来、脳内の情報をすべてコンピュータ内の人工知能に移植する技術、「精神転送」(マインド・アップローディング)を実現し、それによって、肉体は死を迎えても、意識は生き続けることが可能になると予想しています。そしいぇ、このカーツワイルのビジョンには、多くの科学者や技術者、識者が関心を示し、この「マインド・アップローディング」をテーマにしたSF映画が製作されていることが紹介されます。その映画とは、一条真也の映画館「トランセンデンス」で紹介した俳優ジョニー・デップの主演作品です。
「フィールドは『情報貯蔵庫』ではない、『宇宙意識』と呼ぶべきもの」では、著者は、ゼロ・ポイント・フィールドとは単なる「情報貯蔵庫」のようなものではないと指摘します。そうではなくて、この宇宙で起こったすべての出来事のすべての情報を「記憶」していく「超越意識」のようなものであり、これを敢えて命名するならば、この宇宙のすべてを記憶している意識、すなわち、「宇宙意識」と呼ぶべきものであるといいます。そして、ゼロ・ポイント・フィールドの性質について、「記録」から「記憶」への動詞の転換、「情報貯蔵庫」から「宇宙意識」への主語の転換を訴えています。
第九話「フィールド内での我々の『自我』(エゴ)は消えていく」の「なぜ、臨死体験では『幽体離脱』が起こるのか」では、幽体離脱のような体験が報告されるのは、死後も、我々の「自我意識」が、しばらく、ぜロ・ポイント・フィールドに残り、現実世界を見つめているからであるとして、著者は「それゆえ、世界の様々な宗教においては、誰かが亡くなったときに行われる、共通の風習がある」と述べます。例えば、日本では、「通夜」や「夜伽」と呼ばれる風習があり、故人の棺の傍に、一晩中、遺族や近親者が添い続けることを大切にします。それは、まさに、肉体は死んでも、「自我意識」は、ゼロ・ポイント・フィールドから、その自分の肉体や遺族の姿を見ているからである。そのため、遺族や近親者が、棺の傍に居て、故人が寂しさを感じないようにするためであるというのです。
続けて、著者は「近年、こうした風習の真の意味は忘れられ、儀式だけが粛々と行われているが、本来、こうした宗教的儀式には、そのような意味があった。また、日本では、『初七日』や『四九日』などの法要の儀式があり、死後、一定の期間、遺族が喪に服する。これも、肉体を離れ、ゼロ・ポイント・フィールドに移った故人の『自我意識』が、まだ、その遺族や、自分の現実世界での人生に思いを残しているからであり、世界の宗教に共通にある、『喪に服する』という風習は、その故人の『自我意識』が、次の変容を遂げる前に、その寂しさや不安に添い続けるためである」と述べています。
その人生の在り方、死に際の在り方によっては、死後も、ゼロ・ポイント・フィールドに移った「自我意識」が苦しみ続けることは、大いにあるだろうという著者は、「だからこそ、遺された人々は、故人に対して、『供養』『慰霊』『鎮魂』といった儀式を行うのである。特に、戦争や大災害、大事故などで、苦しんで亡くなった人々や、悲惨な最期を遂げた人々に対しては、我々は、こうした儀式を、多くの遺族や近親者が集まって行う。そのことによって、故人の『自我意識』が、苦しみから解き放たれ、慰められ、鎮められることを、我々は願うのである。
さらに著者は、「ただ、改めて言うまでもないが、こうした宗教的儀式は、そうした故人の意識に働きかけることを目的としているのであり、儀式そのものが豪華であることや、特定の様式に従っているということには、実は、あまり大きな意味はない。むしろ、遺族の心のこもらない儀式を、どれほど盛大に行っても、故人の意識は救われず、逆に、どれほどささやかな儀式でも、遺族の心がこもっているならば、故人の意識は深く救われるだろう。されば、経済的理由がゆえに、故人に立派な葬儀を行ってあげられなかった方々も、そのことを悲しまれる必要はない」と述べるのでした。
 『唯葬論』(三五館)
『唯葬論』(三五館)
「『幽霊』や『地縛霊』という現象の正体は何か」では、「古城の幽霊」や「地縛霊」と呼ばれるものは、その城や場所に行くと、その場が、ゼロ・ポイント・フィールドに記憶されている「その死者の情報」に繋がりやすくなるため、その場を訪れた人々の意識に、そうした情報が流れ込み、死者の姿の幻影を見たり、死者の声を聴いたりする幻聴が生じているため起きている現象であろうと述べています。すなわち、そうした現象は、その場に、死者の「自我」としての意識がとどまり続けているために起こっているわけではないというのです。地縛霊という考え方は、イギリスの民俗学者トム・レスブリッジが生み出したとされています。レスブリッジの地縛霊論については、拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)の「幽霊論」で詳しく紹介しましたが、ゼロ・ポイント・フィールド仮説の適用に、わたしは違和感をおぼえません。
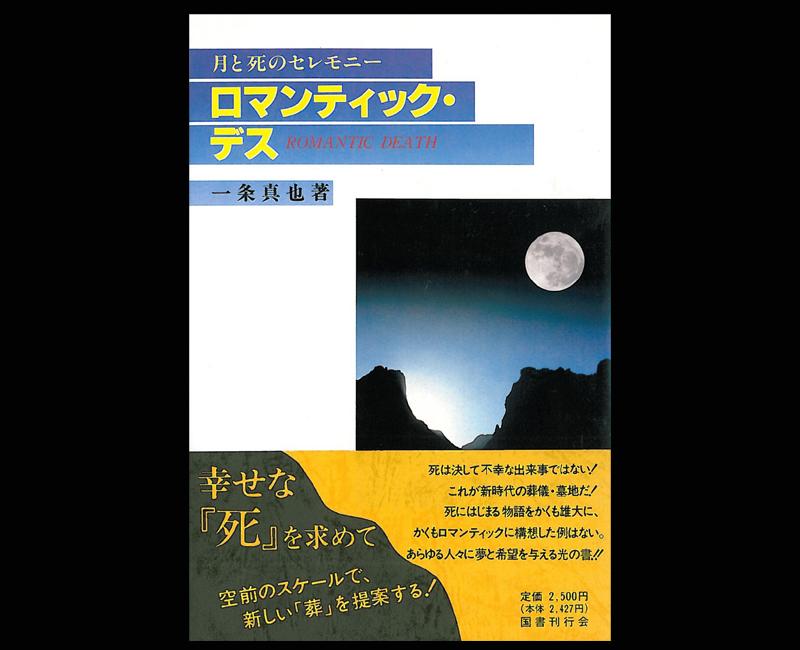 『ロマンティック・デス』(国書刊行会)
『ロマンティック・デス』(国書刊行会)
著者によれば、フィールド内で、わたしたちの意識は「私」を忘れ、「すべて」を知るといいます。また、「なぜ、臨死体験では、『光の存在』に会い、『至福』に満たされるのか」では、「私」を忘れて「すべて」を知ることを、臨死体験から戻った人々は、異口同音に、「あの死後の世界では、すべての叡智が自分の中に流れ込んでくる感覚に包まれた」と述べていると指摘します。そして、この体験を擬人的なイメージで語ったのが、「死後の世界では、光の存在に出会った」「神のような存在に迎えられた」といった体験談であり、このイメージも、臨死体験から戻った人々が、異口同音に語っていることであるといいます。このあたりの考察は、拙著『ロマンティック・デス』(国書刊行会、幻冬舎文庫)の中で詳しく書きました。同書で、わたしは「『死』とは『私』がなくなること」と表現しました。臨死体験だけでなく、本書全体と通じて『ロマンティック・デス』と共通のテーマを扱っていると言えるでしょう
 『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)
『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)
第一〇話「フィールドに移行した『我々の意識』は、どうなるのか」の「死後、我々は『肉親』と再会できるのか」では、「我々の意識が、死後、ゼロ・ポイント・フィールドに移行した後、そこで、『故人』と再会できるのか? 特に、すでに他界した『肉親』と再会できるのか?」という疑問が取り上げられます。著者は、「この疑問は、『死後の世界』について、多くの人々が抱かれる疑問であろう。なぜなら、誰といえども、大切な『肉親』を失った後は、深い喪失感と孤独を感じ、その悲しみと寂しさの時期を経た後、その『肉親』と、いつか『遠い世界』で再会できるのではないか、との思いを抱くからである」と述べています。これは、拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)に書いたグリーフケアの問題そのものです。
では、死後、わたしたちは肉親と再会できるのでしょうか? 著者は、「ある意味で、我々は、肉親と『再会』できる。しかし、それは、ゼロ・ポイント・フィールド内での『再会』であり、この現実世界での『再会』とは異なったものである。すなわち、我々が、ゼロ・ポイント・フィールドで再会するのは、『自我意識』が消えていき『超自我意識』となった肉親である。それゆえ、その肉親は、かつて現実世界で触れ合ったような、明確なエゴを持ち、喜怒哀楽を表し、愛情と葛藤を共にした肉親ではない。すでに、そうしたものを超越した意識状態の肉親、文字通り『超自我意識』の肉親である」と述べています。
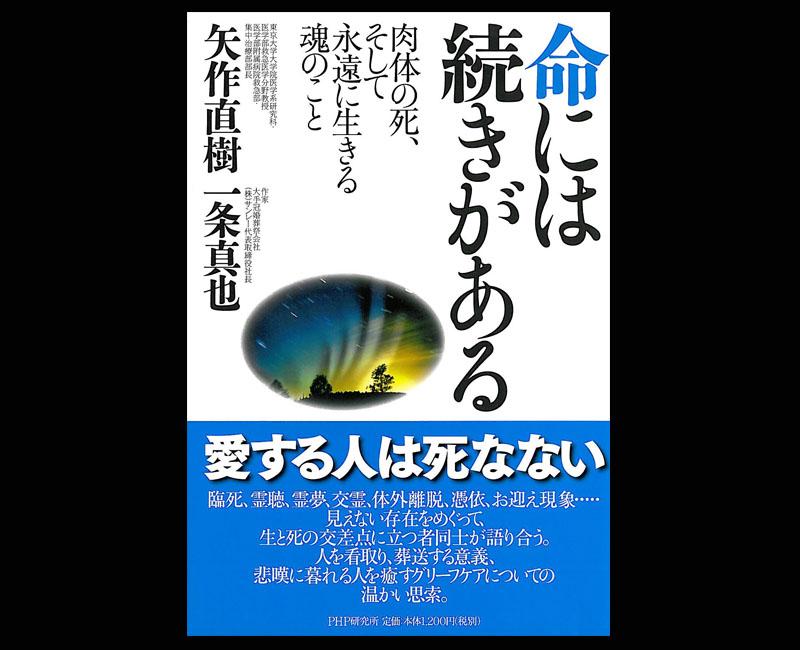 『命には続きがある』(PHP研究所)
『命には続きがある』(PHP研究所)
「なぜ、『祈り』を捧げると、故人は、我々を導くのか」では、「超自我意識」は、「自我の障壁」を作らないがゆえに、ゼロ・ポイント・フィールド内の様々な情報に、容易に触れることができるといいます。そのため、肉親の「超自我意識」は、我々の願いに応える「必要な情報」や「良い情報」を、容易に引き寄せることができるというのです。著者は、「我々の無意識が『肉親の超自我意識』に繋がることが大切な意味を持つと述べるのは、それが理由である。筆者は、そう考えているがゆえに、父母を亡くされた遺族の方には、必ず、『お父様は、天界から導いてくれていますよ』や『お母様は、天界から守ってくれていますよ』と語りかける」と述べます。このあたりは、東京大学名誉教授の矢作直樹氏とわたしの対談本である『命には続きがある』(PHP研究所)の内容にも重なります。
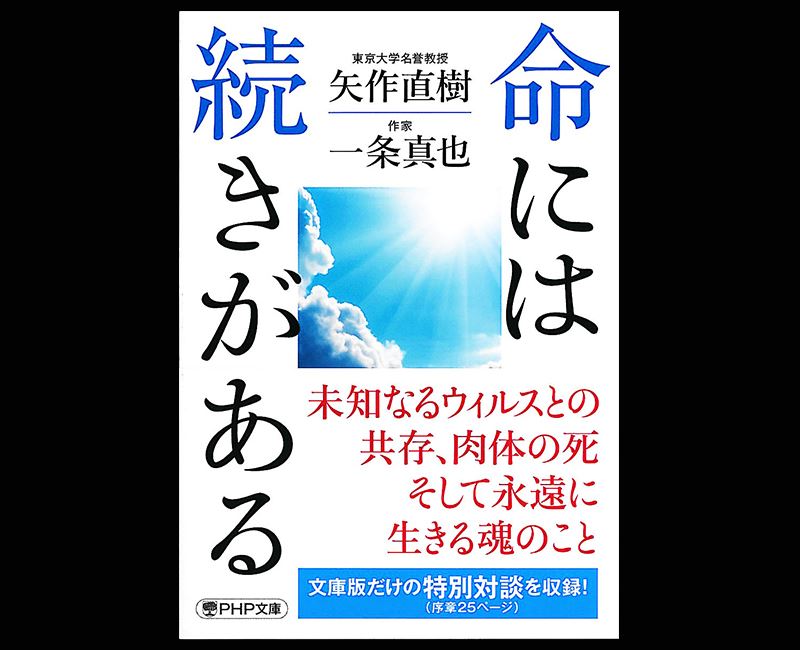 『命には続きがある』(PHP文庫)
『命には続きがある』(PHP文庫)
それは、慰めとして語りかけるのではないといいます。もし、その遺族が、本当に「両親は、天界から、自分を導き、守ってくれている」と深く信じるならば、その想念が、実際に、その「天界」(ゼロ・ポイント・フィールド)から、両親の「超自我意識」を通じて、「必要な情報」や「良き情報」を引き寄せるからだというのです。「祈り」とは、ゼロ・ポイント・フィールドに繋がる最良の方法であり、深い祈りの中で、肉親に対して「問い」を投げかけ、「導きたまえ」と語りかけるならば、しばしば、何かの「答え」が聞こえてくるという著者は、「それは、決して『思い過ごし』ではなく、我々が深い『静寂意識』の中にあるならば、不思議なほど、必要なときに、何かの『声』が聞こえてくるのである」と述べます。
 『ロマンティック・デス』(幻冬舎文庫)
『ロマンティック・デス』(幻冬舎文庫)
第一一話「死後、『我々の意識』は、どこまでも拡大していく」の「138億年の旅路、そして、大いなる帰還」では、著者は「我々の意識は、いつか、『宇宙意識』へと戻っていくのである。なぜなら、この『私』という存在は、138億年前に『量子真空』が生み出した、この『宇宙』が、その138億年の旅路の果てに、地球という惑星の上に生み出したものだからである」と述べ、「『私』とは、宇宙意識の見る『夢』」では、著者は「もし、あなたが、『私とは、この肉体である」と信じるかぎり、死は明確に存在し、そして、それは、必ずやってくる。もし、あなたが、「私とは、この自我意識である」と信じるかぎり、あなたの意識がゼロ・ポイント・フィールドに移った後、いずれ、その『自我意識』は、消えていく。そして、『超自我意識』へと変容していく。それゆえ、その意味において、『自我意識』にとって『死』は存在し、それも、必ずやってくる」と述べます。このあたり、『ロマンティック・デス』のメッセージと重なる部分が多いです。
さらに、もし、わたしたちが「私とは、この壮大で深遠な宇宙の背後にある、この『宇宙意識』そのものに他ならない」ことに気がついたならば、「死」は存在しないといいます。「死」というものは存在しないというのです。なぜなら、この現実世界を生き、「肉体」に拘束され、「自我意識」に拘束された「個的意識としての私」は、この「宇宙意識」が、138億年の悠久の旅路の中で見ている、「一瞬の夢」に他ならないからだというのです。そして、その「一瞬の夢」から覚めたとき、「私」は、自分自身が「宇宙意識」に他ならないことを、知るというのです。ここまでくると、宗教あるいはSF小説のようにも思えますが、著者の壮大な「死」をめぐる考察は「宇宙意識」にまで到達しました。
終話「二一世紀、『科学』と『宗教』は一つになる」の「『科学的知性』と『宗教的叡智』が融合した『新たな文明』」では、著者は「科学者の方々には、かつて、『沈黙の春』の著者、レイチェル・カーソンが語った『センス・オブ・ワンダー』(不思議さを感じる力)を大切にして頂きたい」と述べ、「宗教者の方々には、それぞれの教義の原点となる経典や聖典を、新たな目で『読み解いて』頂きたい。『読み直して』頂きたい」と述べています。
また、著者は「もし、本書で示した『ゼロ・ポイント・フィールド仮説』の観点から、それぞれの経典や聖典が語っている『真理』を読み直し、読み解かれるならば、そこに、このフィールド仮説が述べる世界の姿と『不思議なほどの一致』を、数多く見出すだろう」とも述べ、さらに「もし、経典や聖典の『読み解き』や『読み直し』をされたならば、その新たな理解と解釈を、『誰にも分かる易しい言葉』で、語って頂きたい。なぜなら、古い経典や聖典は、素晴らしい真理が語られているにもかかわらず、言葉が固く、難解であるため、多くの人々を『宗教』から遠ざけてしまっているからである」と述べます。
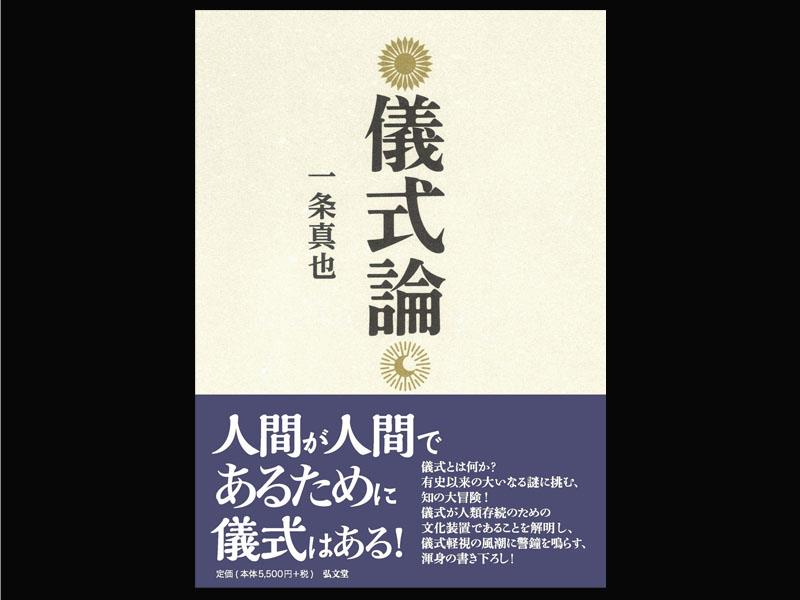 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
著者は、「それぞれの宗教が営む『儀式』についても、現代の人々の心境に合わせた『簡素化』を試みて頂きたい。『過度に様式化された儀式』もまた、人々を『宗教』から遠ざけてしまっているからである。いずれ、最も深い真理は、『簡素な言葉』で語られるものであり、最も大切な祈りもまた、『簡素な技法』で行われるものだからである」と述べるのでした。儀式についてはわたしの専門ですが、著者の言う通りであると思います。わたしの本業である冠婚葬祭業は儀式産業そのものです。結婚式も葬儀も、単なる形骸化したセレモニーではありません。それは社会を安定させ、人類を存続させる重要な文化装置です。冠婚葬祭が変わることはあっても、冠婚葬祭がなくなることはありません。儀式もアップデートするのです。その考えで、わたしは『葬式不滅』(オリーブの木)を書きました。
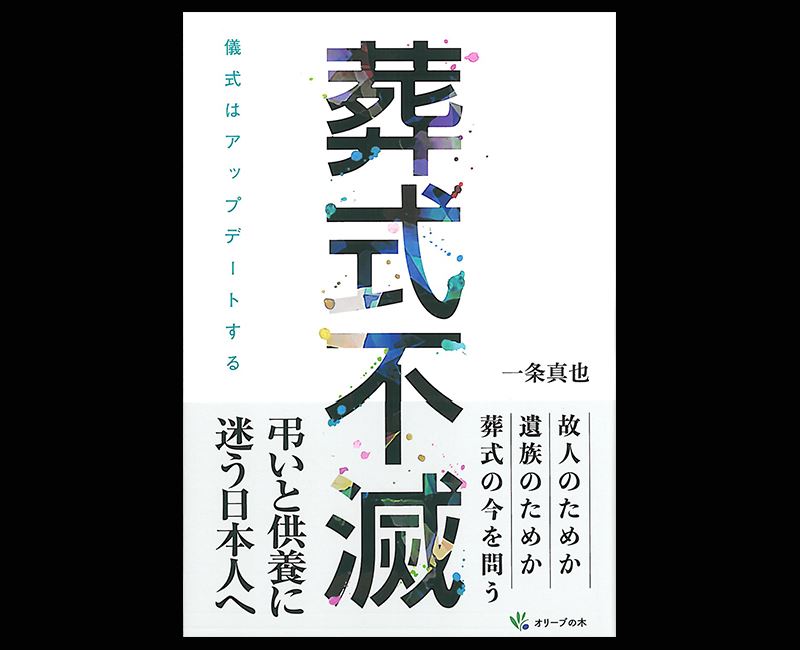 『葬式不滅』(オリーブの木)
『葬式不滅』(オリーブの木)
といったふうに、本書の内容はわたしがこれまで書いてきた著書との関連も深く、非常に興味深く読みました。一言でいって「ニューエージ」系の本だなと思いました。また、旧来のオカルト思想である「神智学」に近い考えであるとも思いました。要するに精神世界の本であるわけですが、このような本が光文社新書から刊行されたことに驚きをおぼえています。なお、本書の内容で個人的に気がかりだった点ですが、まずは、ゼロ・ポイント・フィールド仮説に対して科学的な側面から証明が行なわれていないこと。「仮説」でしかも十分な検証が行なわれていないため、折角の視点が仮説の重層構造になっており、説得力を損なっているように感じました。またこれに伴い、事実と仮説が混同されやすく記述されている箇所(世界が波動で出来ていること)(事実と波動がゼロ・ポイント・フィールドに記録されること)などが散見される点は論説として問題だと思います。
また、著者が体験、あるいは提示している不思議な現象についての数量の問題があります。著者が提示している実例の絶対数が少ないため、偶然であることを否定できません。また、科学的な視点を謳うのであれば、偶然でないことを統計学等を用いて証明してほしかったです。さらに、「死」に対する定義が不明確(p.232など)なことです。著者が「死」をどのようにとらえているかについて明確に提示されていないことは、本書の論題を考慮すれば問題であると考えます。一応、著者は「死をどう定義するかは私という存在を顧みれば良い」という認識であると思われますが、このような不明確な定義のまま「死が存在しない」と論を進められても説得力に欠けます。
さらに、アインシュタインの手紙に関して(p.150)、スッキリしませんでした。「過去」「現在」「未来」が幻想だとするアインシュタインの手紙は、相対性理論においては絶対時間が存在せず、「ある者にとっての現在は他者にとっての過去である」というような状況が成立することから、ここを指しての表現でないかと思われます。そのため、これがタイムスケープの論理的裏付けとなるかについて、個人的に大きな疑問を感じます。そして、わたしの専門である儀式の意義について(p.226)です。著者は、「供養」「慰霊」「鎮魂」のために儀式を行なうと述べていますが、(当該箇所の論旨があるとは言え)グリーフケアの視点が欠如していることには違和感をおぼえますし、著者の理論でいうならば、究極的には葬儀が不要とも言える(葬儀の有無にかかわらず死者は救済される)ため、この箇所については言及が必要かと思います。
著者の「ゼロ・ポイント・フィールド仮説」はまだ提唱されたばかりで更なる検討の必要があるかと思いますが、科学的な研究を続けてこられた方が、科学の限界を感じ、宗教的な側面からも研究を進めようとされた点、そして「無に帰することは、やすらぎである」と考えていた著者が、そのままでは精神的な安らぎを得られなかった、すなわち、やはり唯物的な価値観以外に、人々の心を安定させるカタチが必要であることが明確に示された点について、きわめて意味のある本であると感じました。「科学と宗教の融合」といったようなテーマは陳腐といえるほどに語られてきましたが、わたし個人の立場としては、宗教と科学の間に矛盾があることは別に問題はないと考えています。
しかし、たとえ矛盾があったとしても、その矛盾をそのまま飲み込み、複数の理論を自己の中で並立させることができることが、他ならぬ日本人の「強み」であると考えているため、どちらが正しいと断定すべきものであるとも思いません(むしろ、これまで神道・儒教・仏教といった相互矛盾を含む宗教・論理を享受してきた日本人が細かい矛盾を云々ということはナンセンスとも思えます)。その大らかさが、現在の世界の閉塞感を打破する素材なのではないかとも思えますので、宗教・科学と言った本来矛盾するものの橋渡しを企む本書は大きな価値があると思います。
何よりも、「直観」「以心伝心」「予感」「予知」「シンクロニシティ」「コンステレーション」といった不思議な現象、さらには「臨死体験」「霊媒」「地縛霊」「背後霊」「転生」といったオカルト的な現象までをすべて説明できる統一理論の試みというのは壮大なロマンがあります。一条真也の読書館『黎明』、『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」』、『シンクロニシティ』といった本を連想しました。いずれも科学と宗教を横断した内容で総合性がありました。正直この上なく面白い本であり、知的好奇心を刺激される読書体験を与えられました。
 『満月交心 ムーンサルトレター』(現代書林)
『満月交心 ムーンサルトレター』(現代書林)
ここまでの内容をブログにUPしたのですが、それを京都大学名誉教授で宗教哲学者の鎌田東二先生が読んで下さいました。鎌田先生は、本書で扱われているような諸問題、特にアカシックレコードなどに代表される神秘主義思想研究の第一人者です。『満月交心 ムーンサルトレター』(現代書林)をはじめとして、わたしとも「死」や「死後」について多くを語り合って下さいました。その鎌田先生は、わたし宛のメールに「長文ブログ、大変興味深く拝読しました。わたしの昔からの考えはおおむね田坂氏と似ていますので、特に違和感はありません。また、文末の佐久間さんの批判的吟味の論点もよく理解できます。ともあれ、科学者でこのような考えを持つ人は昔からいつも少数ですがいました。が、今はこのような方の登場が絶対少数ではなく、一つの科学的な知見や見解や立場ということになりつつあるということでしょうか? そのような科学シーンの展開そのものがおもしろい現象ですね」と書かれていました。鎌田先生も、田坂広志氏も、1951年生まれの卯年です。科学から宗教への橋渡しを本書が、宗教から科学への橋渡しを鎌田先生が行うことで見えるかも知れない新たな地平の姿がどのようなものか。今から楽しみでなりません。ちなみに、わたしは、お二人よりひと回り下の卯年です。同じウサギ年のよしみで、いつか、田坂氏にもお会いしたいと願っています。

 『
『