- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2136 書評・ブックガイド 『教養脳』 福田和也著(文春新書)
2022.05.29
『教養脳』福田和也著(文春新書)を読みました。
「自分を鍛える最強の10冊」というサブタイトルがついています。著者は、文芸評論家。慶應義塾大学環境情報学部教授。1960(昭和35)年東京生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。同大学院修士課程修了。1993年『日本の家郷』で三島由紀夫賞、2002年『地ひらく』で山本七平賞を受賞。著書に『日本の近代(上・下)』『昭和天皇』など多数。
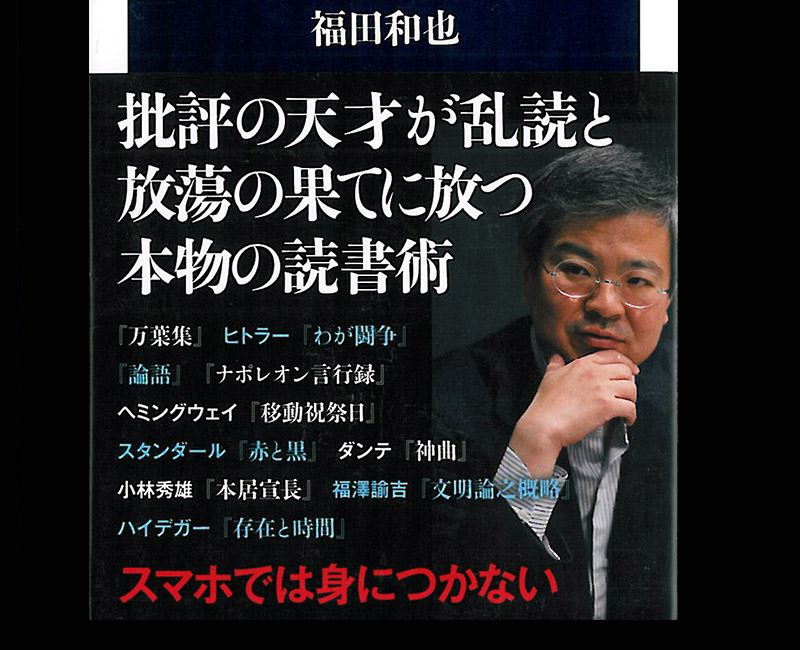 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、著者の写真とともに「批評の天才が乱読と放蕩の果てに放つ本物の読書術」「『万葉集』ヒトラー『わが闘争』『論語』『ナポレオン言行録』ヘミングウェイ『移動祝祭日』スタンダール『赤と黒』ダンテ『神曲』小林秀雄『本居宣長』福澤諭吉『文明論之概略』ハイデガー『存在と時間』」「スマホでは身につかない」と書かれています。
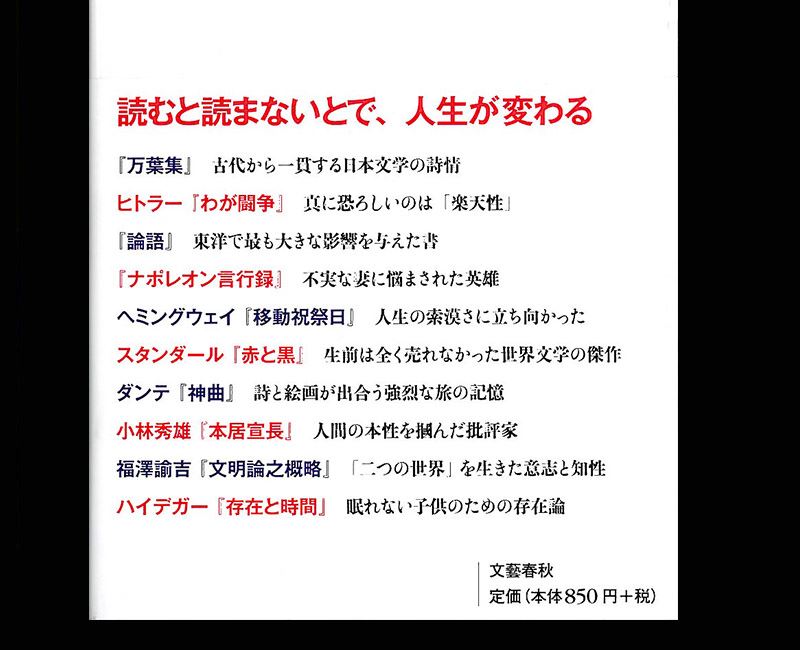 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には「読むと読まないとで、人生が変わる」として、本書で取り上げられる10冊の書目が以下のように並んでいます。
『万葉集』
古代から一貫する日本文学の詩情
ヒトラー『わが闘争』
真に恐ろしいのは「楽天性」
『論語』
東洋で最も大きな影響を与えた書
『ナポレオン言行録』
不実な妻に悩まされた英雄
ヘミングウェイ『移動祝祭日』
人生の索漠さに立ち向かった
スタンダール『赤と黒』
生前は全く売れなかった世界文学の傑作
ダンテ『神曲』
詩と絵画が出会う強烈な旅の記憶
小林秀雄『本居宣長』
人間の本性を掴んだ批評家
福沢諭吉『文明諭之概略』
「二つの世界」を生きた意志と知性
ハイデガー『存在と時間』
眠れない子供のための存在論
カバー前そでには、以下のように書かれています。
「教養とは何か? 単なる知識・情報ではない。自分の世界を拡げる『知』である。その最強の武器こそ、歴史の過酷な淘汰に耐えた書物にほかならない。『批評の天才』が、世界を動かした10冊をどう読めばよいかをレクチャー。本物の読解力が身につく!」
「まえがき」では、1人1人が個々の世界に閉じこもってしまったのでは、社会は発展していかないと指摘して、著者は「よりよく社会を発展させるためには、人が広く学問、芸術、宗教に触れて自分の人格を養い育てていくことが必要であり、そうした努力や成果がそもそも『教養』の意味であって、語源はラテン語の『cultura(耕す)』である。ところが現代社会においては、その目的が置き去りにされ、「一般教養」という言葉が象徴するように、文化に関する広い知識ととらえられるようになった」と述べています。
肝腎の目的を忘れてしまっては、いくら美術館を回って絵を見ても、オペラの公演を見ても、漢文の本を読んでも、教養は身につくものではないとして、著者は「しかも今やインターネットの発達で、美術館やコンサート会場に行く人も少なくなった。ネットを利用すれば有名絵画のほとんどは見ることができるし、様々な音源に接することもできるからだ」と述べます。
そして、著者は「確かにスマホで調べれば、この本で取り上げた10冊の本の内容はすぐ分かるだろう。しかし、そこで得られるのは情報に過ぎない。しかも数分後には忘れられている。そんなものは何の役にも立ちはしない。難しい本と長い時間をかけて対峙した結果、自分の中に生じる共感や反発は、他人に対する想像力につながる。これこそが教養の要なのだ。新型コロナウイルスの感染拡大で世界が分断された今、人間が自分のことしか考えられなくなっている今こそ、教養は必要だ」と述べるのでした。
最初に登場する名著は『万葉集』です。「なぜ古典を学ぶのか」では、今の自分たちの生活や利害、関心と全く関係のない時代の人々の言葉を学び、その発想や言動を理解しようとすることにこそ、古典教育の意味があるとされたと指摘し、著者は「自分と隔絶した他者を理解しようと徹底的に努力することにこそ、人間の人間としての力、つまりは利害、欲望、本能を超えた人間性の力があると、ヨーロッパ人たちは考えたのだ。この、自分とまったく違う時代、文明のなかにいる他者を理解する能力を、ドイツ人は『教養』と呼んだ。ドイツ語で『教養』は『Bildung』である。英語にすると『becoming』。『~に成る』『形成する』という意味だ。つまり、自分を人間として形成する、作り上げていく、ということである」と述べています。
また、教養について、著者はこうも述べます。
「教養というのは、オペラに精通しているとか、絵画に詳しいとか、仏像を見るのが好きといった類のものではない。もちろんそういうことが教養につながらないわけではないが、鑑賞体験やそのための周辺知識の習得が、人間らしい人間になる、つまり他者を理解する力をつけるという方向性に向かわないのならば、教養を身につけることにはならないのだ。教養というのは、知識とか経験の豊富さを人に誇ったり、それを何か実用的な目的で使うために身につけるものではない。ゲーテは、『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』のなかで、教養を定義して、『自身になるという目的以外の目的をもたない』営為、としている。つまり『教養』とはあくまで『自己目的』であって、自分を自分として形成することなのだ。そのような自己を人間らしい人間として作り上げるのに必要なのが、古典を通しての隔絶された他者を理解する試みなのである」
「日本文学の一貫性」では、日本の古典は、決して現在の日本の言葉とその情緒、表現、気分と隔絶していないと指摘し、著者は「きわめて根強い、詩情において一貫したものがあって、それが日本の文学を形作っている。つまり日本文学は『古事記』、『万葉集』の時代から一貫して日本文学として存在しているのである。あたりまえだと思われるかもしれないが、これは大切なことなのだ。ドイツのラテン文学者、クルツィウスやアウエルバッハらが指摘しているように、ヨーロッパ文学全体がギリシア、ラテンの地中海世界から派生した大文学圏であると考えることはできるが、国民文学的観点から見ると、話は違ってくる。フランス文学にしろ、イギリス文学にしろ、現在の国単位での文学系統が意識されるようになったのは、17世紀からせいぜい遡って15世紀にすぎないことを紹介し、著者は「イタリアはダンテやペトラルカらにより13~14世紀に国民文学の濫觴が見られるが、ドイツは18世紀を待たなければならない。その点、日本の場合、文学の一貫性とその意識は、『万葉集』が成立した8世紀にすでにあったと考えられる」と述べます。
「率直と寛容」では、「今、日本で文芸作品を作っている人はどれだけいるのだろうか」と問い、著者は「短歌と俳句の人口だけで、軽く1000万人を超えるのではないだろうか。昔から小説や評論を書いて雑誌に投稿したり賞に応募したりする人たちは多かったが、今やインターネットという場を得てその数はさらに拡大している。これは異様なことであると同時に素晴らしいことでもある。日本はまさに言霊の咲き栄える国だということになる。日本の文芸、文化において、もっとも貴重な性格の一つが、誰もが文化を創る側にたてるということにあり、その文化の基本的なあり方を決めたのが『万葉集』なのである」と述べるのでした。
2冊目は、アドルフ・ヒトラーの『わが闘争』です。「ヒトラーには2つの見方がある」では、ヒトラーの2つの見方が紹介されます。1つは悪魔的であり狂信的な計画を着々と進めていった一種の天才的陰謀家、もう1つは歪んだ世界観や、また野蛮な政治的手法を持っていたにしろ、結局は相対的な国際関係の中で、その時々の状況に応じて政策を打ち出した、他の大国の指導者たちと本質的には変わらない政治家です。
「ドイツ本国で発売禁止に」では、これまで世界で刊行されたヒトラーに関する本は軽く数万冊を超えていると思われますが、ヒトラー自身の著書はたった2冊であるとして、著者は「1冊は1925年に刊行された『わが闘争』、もう1冊はヒトラーの死の16年後に刊行された『ヒトラー第二の書』である。もっとも2冊目は1945年のドイツの降伏後、ベルリン総統府の地下壕から発見されたヒトラーの口述原稿を研究者が注釈をつけて出版したものであり、ヒトラー自身はこの原稿を極秘扱いにし刊行を禁じていた。よって、ヒトラーが自らの意志でこの世に送り出した唯一の書は、『わが闘争』ということになる」と述べます。
「『わが闘争』が誕生するまで」では、いわゆる「ミュンヘン一揆」でデモ行進をした罪でランツベルク刑務所に入れられるも、ヒトラーは特別待遇になったことが紹介されます。著者は、「広くて快適な部屋が与えられ、昼も夜も側近たちと一緒に食事をすることができた。所長の厚意によって誰とでも面会ができ、差し入れも自由で小包、新聞、手紙などは何の検閲もされなかった。あまりの快適さにヒトラーは刑務所を『国費で勉強できる大学だ』と言うほどだった。こうした中、ヒトラーは裁判の趣意書をまとめようと、側近のエミール・モーリスとルドルフ・ヘスに向かって語り始めた。自分の来し方について、自分の運動の目標について、自分の世界観について。やがてそれは趣意書の域を大きく超えるものとなっていき、最終的に上下巻、2冊の本にまとまった。『わが闘争』の誕生である」と述べています。
「恐るべき楽天性」では、ニーチェを愛読し、古今の哲学から文学に通じていたインテリのムッソリーニに対して、ヒトラーの知的素養は、まことに貧しいものだったと指摘されます。音楽、とくにワーグナーに対する熱狂と、一部の建築と美術に対する蘊蓄を除けば、ヒトラーは全く教養の世界とは無縁でした。著者は、「ヒトラーを恐れるとしたら、その楽天性ではないだろうか。種の保存をめぐる激烈な闘争の場である戦場において、ヒトラーは厭世的になることなく、『私はこの世界が好きだ!』と叫び、世界を肯定した。この楽天性こそが彼をして世界を震撼させる恐ろしい一連の事件の指導者としたのだ。『わが闘争』にはヒトラーの楽天性が充満している」と述べるのでした。
3冊目は『論語』です。著者は、「聖徳太子の時代から明治まで、日本の知識人たちは『論語』を読み、対話をすることで自分たちの思惟や解釈能力を鍛えてきた。そこから日本人の精神的営為の大きな部分が出てきたことは否定できない。ところが、その伝統が戦後半世紀にわたって途絶えてしまった」と述べていますが、これには大いに賛成です。「倉庫番や飼育係で生計を」では、おそらく孔子は幼い頃、母の家で育ち、少年になって父の家に移ったのではないだろうかと推測し、著者は「宗教者の母は、雨乞いなどの儀式の際には、祭器を用いてお供えをし、音楽を演奏し、祈りの言葉を捧げた。そうしたものに幼い頃から接していた孔子は遊ぶときに、祭器の俎豆を並べたのだろう。文字も母の家で習ったに違いない。当時、文字を読み、書ける人間は限られていた。文字を用いることのできる母親を持ったが故に、孔子は文字を習得することができた。それが彼の勉強への道を開いたのである」と述べます。
倉庫番や飼育係などで現実問題に対処し、自分で解決策を模索する、それこそが孔子の勉強だったと指摘し、著者は「これはある意味、デカルトに通じる。デカルトはラシーヌやパスカルと同じ法服貴族の出である。ラシーヌはきちんと勉強して法律家になり、パスカルも数学や神学の道に入っていったが、デカルトは博打ばかりしていて家を追い出され、世界中をうろつきまわった果てに、『われ惟う、ゆえにわれあり』という概念に至った。つまり、鄙事中の鄙事をさんざん歩いた人間が結局、抽象的な概念にたどり着いた。孔子もまた鄙事という勉強を重ね、最終的に物事を抽象的にとらえる域まで達した。その彼がとらえた概念が『論語』に集約されているのである」と述べます。
「老いと親しい者たちの死」では、70すぎまで生きた孔子は平均寿命が30歳のその時代においては超がつく長生きでしたが、それ故の哀しみもあったと指摘します。まずは、自身の衰えです。さらに、親しい者たちの死です。著者は、「孔子は19歳のときに幵官氏という女性と結婚しており、鯉という子供をもうけた。妻の詳細はほとんど分かっていないが、鯉は孔子が魯国に戻った年に、50歳で亡くなった。自分よりも子供が先に死んでしまったことを孔子は嘆き悲しんだ。さらに71歳のとき、最も信頼していた弟子の顔淵を亡くした。顔淵が死んだときの孔子の哀しみ様は尋常ではなかった」と述べています。このあたりは、加地伸行先生の『孔子』に詳しく書かれています。
「日本人と『論語』」では、飛鳥時代には斉明天皇が儒教に帰依し、平安時代になると官吏の養成に用いられるようになるなど、儒教は浸透していきましたが、その中心にあったのが『論語』だったと指摘し、著者は儒教の研究といえばもっぱら『論語』学であり、宮中での進講も『論語』が中心であって、五経に及ぶことはなかった。11世紀になると武士が台頭して地方の実権を握るようになり、やがて源頼朝が鎌倉に幕府を開いて日本最初の武家政権が確立された。王朝文化が武士社会に浸透することで、武士たちの間でも『論語』が読まれるようになった」と述べています。このあたりは、加地先生とわたしの対談本である『論語と冠婚葬祭』(現代書林)で詳しく語り合っています。
朱子学が日本にもたらされたのは鎌倉時代で、中国では元代の中期にあたっています。しかし、さかんになったのは、江戸時代に入ってからでした。著者は、「徳川幕府の下、朱子学が公式の学問として認定されると、『論語』は武士にとって必須の教養になった。何故朱子学が公式の学問として認定されたのかといえば、これほど支配者にとって都合のいい論理はないからだ」と述べています。朱子学に対して批判的であった伊藤仁斎や荻生徂徠といった日本の儒学者たちの考えの核心は「生きている人間の背丈で考え、生きている人間を抑圧するようなもの、つまり超越性などは解体していく」というものでした。
このような仁斎や徂徠の考えには日本的な儒教の特徴があり、またある意味で日本人の考え方の特鐵の一つが現れているとして、著者は「それは、人間の背丈を超えて君臨しようとする正義や理念を、自分たちの生きている感情や暮らしに引きずり降ろしていくということである。仁斎、徂徠の方法論を日本的な考え方として意識した時に、この朱子学批判の流れと後水尾院が始めた古典研究の流れが一つになる。これが、賀茂真淵から本居宣長に進んだ日本国学の道である」と述べます。
「川を見つめる孔子」では、著者は「『論語』は何故これほど長い間読み続けられてきたのだろうか」と問い、それは周の時代を理想とした孔子が74歳まで生き、人とつき合ったり、謀反の中にいたり、さまざまな渦中で見たり聞いたり、いろいろな経験をする中で培った確信が現れているからではないだろうかと推測しています。『論語』子罕篇に「子、川の上にありて曰く、逝くものは斯の如きかな、昼夜を舎かず」とあります。「孔子が川を見つめながら言った。時間の過ぎるのは、この水の流れのようなものだ。昼と夜とを問わぬ」といった意味ですが、孔子最晩年の言葉です。
そして、孔子は生涯を通し、普遍なるものを求めていたとして、著者は「高いところに行く道を求めていた。そのためにいろいろなことを働きかけてきたけれど、さすがに疲れてしまった。故郷に戻ったのは、理想の断念だった。そうした自分の人生を孔子は川の水の流れの中に見ていたに違いない。しかし、この断念があったからこそ、孔子は故郷で真の教育をすることができた。そしてその教えは『論語』という形になって、21世紀の現代でも読み継がれているのである」と述べるのでした。
4冊目は、『ナポレオン言行録』です。「幕末とナポレオン」では、幕府側はヨーロッパに一大変事が起きていることに気づいてはいたものの、その実態、つまりナポレオン戦争を察知することは出来なかったと述べられています。それをスクープしたのが頼山陽でした。著者は、「医師はナポレオンのロシア遠征の生還者だった。大軍が瞬く間に寡勢となり、馬を殺して飢えを凌いだその回顧談は、山陽には『史記』の世界の大叙事詩に思えた。ここに成立したのが、ナポレオンの一代記を詠んだ漢詩『仏郎王歌』である」と述べています。
山陽の文名が上がるとともに「仏郎王歌」は人口に膾炙し、ナポレオンの存在は知られていきます。著者は、「蛮社の獄に際して自殺した小関三英がリンデン筆の伝記を『那波列翁伝初編』として訳出して、ナポレオンとヨーロッパ情勢についての知識は飛躍的に進んだ。佐久間象山は自らをナポレオンに投影していたし、吉田松陰は萩の野山獄に収監された時に『那波列翁を起してフレーヘード(自由)を唱』えることを提議し(岩下哲典『江戸のナポレオン伝説』中公新書)、西郷隆盛は、ジョージ・ワシントンとナポレオンを崇拝した」と述べます。
『ナポレオン言行録』の特筆すべき点は、全てがナポレオン本人の言葉であるということだ。編者のオクターヴ・オブリが言うように、ナポレオンは偉大な文人であった。もしも彼が20世紀に生きていたら、ウィンストン・チャーチルのようにノーベル文学賞をとっていたかもしれない。我々はこの書を読むことによって、ナポレオンについて知るばかりでなく、彼の文章を堪能し、彼の呼吸を感じることができる。そもそもナポレオンの存在が世に知られるようになったのは、その文章がきっかけであった」と述べています。
ナポレオンが青春時代、、王立の士官学校は12ありました。特にソレーズにあるベネディクト修道院は、「近代的」な教育が定評であり、ラテン語を必修からはずしていました。著者は、「ヴァンドームの王立士官学校では自然科学の授業が行われていた。そうした中、ブリエンヌの教育課程は、ラテン語をみっちり教える伝統的なものだった。この旧弊な教程がナポレオンにとって、すこぶる有益なものとなったのである。タキトゥス、ウェルギリウス、キケロ、セネカといったラテン文学の古典に接したことは、文人ナポレオンを生むうえで決定的なことだったからだ。戦場で、議場で、歓喜の宴で、ナポレオンが自分の言葉で兵士たちを熱狂させることができたのは、古代ローマの雄弁家たちのレトリックを、ブリエンヌで叩きこまれたからだ」と述べるのでした。
5冊目は、アーネスト・ヘミングウェイの『移動祝祭日』です。『老人と海』『日はまた昇る』『武器よさらば』『誰がために鐘は鳴る』『エデンの園』、短編「蝶々と戦争」「キリマンジャロの雪」といった有名作品ではなく、『移動祝祭日』こそは文豪ヘミングウェイの代表作であるという著者は、その理由について「この作品に漲っている幸福感、充実感、これこそが文学の魅力の、最も分かりやすい、顕かな姿であるからだ」として、「『移動祝祭日』はヘミングウェイの若き頃のパリでの修業時代を綴った印象記である。20の掌編から成っていて、いずれも文庫本で10ページほどの長さだが、その凝縮力と完成度は素晴らしい。作家としての彼の資質の全てが込められていると言ってもいいだろう」と述べています。
6冊目は、スタンダールの『赤と黒』です。今から190年も前に書かれた『赤と黒』は21世紀の現代において、世界的に最も知られた小説の1つといっていいとして、著者は「フランスの偉大な作家の代表作なのだから当たり前だと思っている人は、生前のスタンダールについて知ったならば驚くだろう。何故なら、彼は職業作家ではなかったし、文筆家でさえなかったのだ。ただ自分で書きたいから書き続け、物好きな出版社が彼の書いたものを本にして出版してはくれたけれど、全くと言っていいほど売れなかった。1822年に出版された、恋の結晶作用の『ザルツブルクの小枝』で有名な『恋愛論』は、10年間で売れたのはたったの17冊。在庫が船の重石として量り売りされる始末だった。彼が死んだときに記事を載せたパリの新聞は二つだけ。葬式に立ち会ったのは、友人の作家メリメを含めたった3人だった」と述べています。
「幸福になることが難しい時代」では、著者は以下のように述べています。
「スタンダールは、青春の思い出、というよりも一瞬の恍惚に生涯忠誠を誓い、その忠誠によって、近代においては、いかに幸福が、恋愛が、官能と感傷が難しいかを身をもって明かした作家だった。大革命と前後して出生し、幼くして母を失い、父に反発し、革命期の理性への熱狂とともに教育を受け、17歳のときにナポレオンのイタリア遠征に参加し、ハプスブルク帝国の支配から北イタリアが解放される様を目の当たりにした。この歴史的な転変の中で、はじめて恋をし、女を知った。軍をやめると、恋愛遊戯とオペラ通いを繰り返し、劇作家になるべく戯曲の執筆を試み、女優と同棲するも成功を勝ち得なかった」
じつは、『赤と黒』は、スタンダールによるナポレオンへのラブレターであるという見方があります。ナポレオンが、その帝国を賭けた、もっとも大規模な征服を試みたとき、奇しくもスタンダールはその軍の中にいました。著者は、「皇帝の夢が、炎上するモスクワを背景として潰えた戦いを生き延びたスタンダールは、王政復古のもとで小説を書き始めた。小説は、すでに夢を夢として語ることを許さない社会において、偽善と屈託の中で生きることを余儀なくされた近代人の精神を捉える唯一のジャンルだと思われたからだった」と述べるのでした。
7冊目は、ダンテ・アリギエーリの『神曲』です。「旅に文学書を」では、著者は「海外旅行に行くとき、その土地にちなんだ、かかわりのある文学書を持っていくことを、私はお薦めしたい。というのは、名作と言われる文学作品は、その土地、その街や文化、気風、雰囲気などを、きわめて的確に切り取り、定着させているからだ」と述べていますが、これはわたしも実行していることです。「俗語で書かれた新しい文学」には、「復活祭前の聖金曜日に暗い森に迷い込んだダンテは古代ローマの大詩人ウェルギリウスに導かれて『地獄』で異教徒や罪を犯した人々の末路を見た後、『煉獄』で人々が罪を浄めるために苦行する姿を見、聖女ベアトリーチェに導かれて『天国』に行き、三位一体の神の姿を見る。ちなみに、ウェルギリウスはダンテが心酔し、尊敬し、私淑した詩人であり、ベアトリーチェは実在するダンテの憧れの女性である。ダンテが『神曲』で描いたのは、キリスト教世界を基軸とする、ギリシア、ローマの古代文学の伝統を踏まえた、『信仰による魂の救済』であった」と書かれています。
8冊目は、 一条真也の読書館『本居宣長』で紹介した小林秀雄の大著も取り上げられます。「人間の本性を摑む」では、著者は「小林秀雄で特筆すべきことの1つは彼の評論文が売れるということである。評論文が売れることで、作家なりジャーナリストなりから自立して、自分なりの立場を作ることができる。自分の読者を持つということを真剣に考えた批評家は、小林秀雄が嚆矢といっていい」と述べています。また、「彼の批評は人間の本性を摑んでいる。これは小説家にも必要な能力だが、批評家の場合、さらにそれが何を彷彿させるか、存在感の輪郭をいかに書くかを考えることが非常に重要である。『本居宣長』の前半で中江藤樹、伊藤仁斎について書いているが、小林の文章を読むと、彼らがそこにいることが厳然として分かる。その人間の本性の摑みが、時代を超えても読まれている理由なのだろう」と述べます。
「本居宣長」で自らのダイモンを追究する小林が思考の中心に据えたのが、「物のあはれ」であったとして、著者は「『物のあはれ』は外来の『唐ごころ』の理性や論理に把えられない、人の心を動かす、精霊、悪霊、森羅万象に開かれた情けが形として成されていく在り様である。小林はこの『物のあはれ』を一種の歴史的概念、つまり固有名詞として扱っている。紀貫之、藤原俊成、藤原定家を巡りながら、歴史的な意味を帯びた、知識階級の概念操作に捕らわれない、日本人の広い言語意識の背後にある詩情全般を反映した言葉として、『物のあはれ』をとらえている。『物のあはれ』は小林にとって、日本人と日本語に囁き続けるダイモンの声に外ならなかった」と述べます。
さらに小林は、文字導入以前の日本語の姿への拘りを見せていると指摘し、著者は「ここで小林が取り出しているのは、言葉が或る固有の言語、民族語として立ち上がっていく上での、抵抗と感触をもった、『形』の身もだえである。そのイメージを記録や理性によって整頓せずにありのままに見るという態度が、『物のあはれ』であり、『古事記』の編纂態度なのであった」と述べます。そして、『本居宣長』の持つ強い説得力は、これが思想でもなく、イデオロギーでもなく、まさに言葉の固有性、日本語という偶然で単独的な言葉のダイモンに耳を傾けたところにあるとして、著者は「そこにおいて、私たちを誘うのは、言霊の力でも、ナショナリズムでもなく、まぎれもなく個別性の魔としての、ダイモンそのものとしての批評にほかならない」と述べるのでした。
9冊目は、著者の母校である慶應義塾大学の創設者・福澤諭吉の『文明論之概略』。「二つの世界を生きた知性」では、「西欧化を進める中でいかにして日本は日本であり続けるか」という問いに対して近代の知識人は、西欧の論理と日本の伝統の結合を基盤とした価値や思想、文化の創出で応えたと指摘し、著者は「例えば正岡子規は、伝統的な風雅の道である俳諧を独立した文芸としての俳句へと転換論することで『文学』を発明し、岡倉天心は狩野派や大和絵の画工たちを『芸術家』にした。彼らは日本の伝統的な様式を、西欧近代の枠組みの中で再生して日本的でありながら西欧的であるような、日本にとっても西欧にとっても画期的な文化の創造を試みたのである」と述べます。
福澤諭吉の『文明論之概略』もまた、その問いに対する理論的解決の試みであったといえるとして、著者は「この書が19世紀前半に活躍したフランソワ・P・ギゾーの『ヨーロッパ文明史』および19世紀中葉に活躍したヘンリー・T・バックルの『イギリス文明史』に依拠したことはよく知られている。しかし、もちろん諭吉はギゾーやバックルの説をそのまま日本語にして紹介したわけではなく、内容を咀嚼した上で自身の論を展開しているのだ」と述べます。そして、諭吉をリスペクトする著者は、「現在、諭吉の提議を活かす時に問われるのは、諭吉の思惟が時代時節に適応しているか、否かといった事ではない。むしろ私たちが、すべてを呑み込み、包含していく単一的な文明の進攻とその野蛮に対して、批判的に対することができない、という欠落によってこそ、諭吉の思想はその、今日における活力が問われているのだ」と述べるのでした。
最後に登場する10冊目は、マルティン・ハイデガーの『存在と時間』です。「『死』から『存在へ』では、ハイデガーの人生について、著者は「1909年9月、20歳でイエズス会の修練士用宿舎に入った。教会の期待に見事応えたのである。ところが、たった2週間で除籍されてしまった。ハイデガーには心臓疾患があり、度々心臓発作を起こしていたからだ。聖職者の道を断たれたハイデガーは同年、フライブルク大学に入学。最初は神学を専攻したが、2年後には哲学に転じた。彼の病気は厄介なもので、ひどい発作が起きて死にかけても死なずに復活し、生きよう.と思うとまた発作が起きる。ハイデガーが子供の頃から死を恐れていたかどうかは分からないが、『死』というものに対して早くから意識的であったことは確かである。彼は『死』を通じて『生』を考えるようになり、『生』は『存在』へとつながった。ハイデガーは『死』から『存在』へと向かっていったのである」と述べています。
1927年、『存在と時間』はハイデガーの師であるフッサールの現象学研究年報の第8巻に掲載され、公表されました。当時、ハイデガーは38歳。マールブルク大学の教授であり、彼にとっての初めての主著でした。著者は、「この本は、ドイツの若きインテリたちに衝撃を与え、瞬く間に当時の思想界の形勢を変革し、その影響はドイツにとどまらず、ヨーロッパ哲学全般にまで及んだと言われている。何故それほどの衝撃があったのかといえば、まず時期ということがある。『存在と時間』が刊行されたのは第一次世界大戦が終結して9年後。第一次世界大戦は、4年3か月の長期間、25か国という参加国の多さ、毒ガス、戦車、航空機などの大量殺戮が可能な新兵器、その結果としての1000万人に近い戦死者……とどの要素をとってみても、これまでの戦争の常識を根底から覆すものだった」と述べています。以上、本書に登場した古今東西の名著を簡潔に解説していく著者の筆さばきは見事で、さすがに「批評の天才」と呼ばれるだけのことはあります。願わくば、著者の前に屹立する「批評の天才」である小林秀雄の伝記を書いていただきたいです。