- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2024 マーケティング・イノベーション | 社会・コミュニティ | 経済・経営 『ビジネスの未来』 山口周著(プレジデント社)
2021.04.08
『ビジネスの未来』山口周著(プレジデント社)を読みました。「エコノミーにヒューマニティを取り戻す」というサブタイトルがついています。著者は1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、組織開発・人材育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループに参画。現在、同社のシニア・クライアント・パートナー。専門はイノベーション、組織開発、人材/リーダーシップ育成。著書に一条真也の読書館『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』で紹介した本など。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には頬杖をつく著者の写真とともに、「新しい時代を創るために資本主義をハックしよう」と書かれています。また、カバー前そでには、「21世紀を生きる私たちに課せられた仕事は、過去のノスタルジーに引きずられて終了しつつある『経済成長』というゲームに不毛な延命・蘇生措置を施すことではなく、私たちが到達したこの『高原』をお互いに祝祭しつつ、『新しい活動』を通じて、この世界を『安全で便利な快適な(だけの)社会』から『真に豊かで生きるに値する社会』へと変成させていくことにあります」と書かれています。
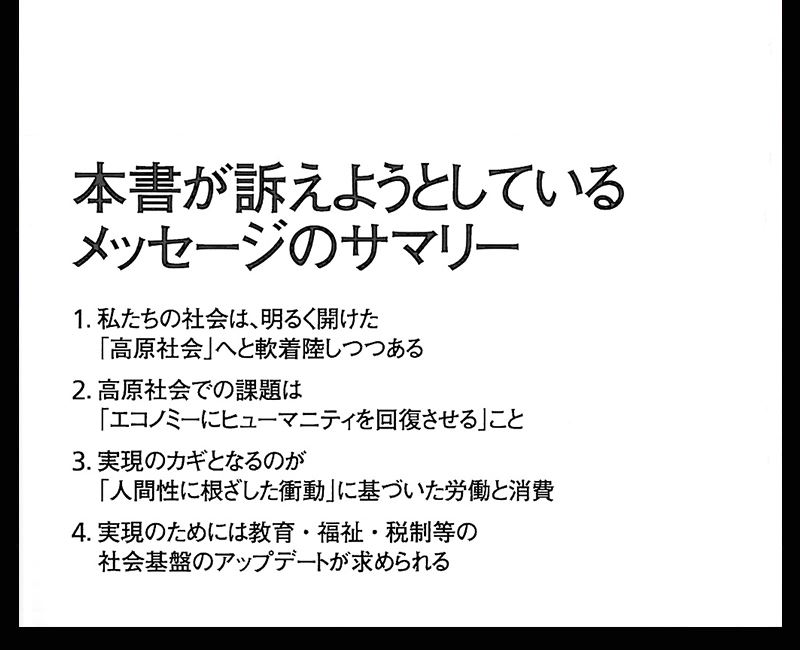 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「本書が訴えようとしているメッセージのサマリー」として、以下のように書かれています。
1. 私たちの社会は、明るく開けた「高原社会」へと軟着陸しつつある
2. 高原社会での課題は「エコノミーにヒューマニティを回復させる」こと
3. 実現のカギとなるのが「人間性に根ざした衝動」に基づいた労働と消費
4. 実現のためには教育・福祉・税制等の社会基盤のアップデートが求められる
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 私たちはどこにいるのか?
第二章 私たちはどこに向かうのか?
第三章 私たちは何をするのか?
イニシアチブ1:真にやりたいコトを見つけ、取り組む
イニシアチブ2:真に応援したいモノ・コトにお金を使う
イニシアチブ3:ユニバーサル・ベーシック・インカム
の導入
補論
1.社会構想会議の設立
2.ソーシャル・バランス・スコアカードの導入
3.租税率の見直し
4.教育システムの再設計
「おわりに」
「参考文献」
「はじめに」の冒頭で、著者は「ビジネスはその歴史的使命をすでに終えているのではないか? これが、本書執筆のきっかけとなった私の疑問です」と書き出し、続けて「答えはイエス。ビジネスはその歴史的使命を終えつつある。ということになると思います」と述べています。本書で示されるさまざまなデータは、人類が過去200年にわたって連綿と続けてきた「経済とテクノロジーの力によって物質的貧困を社会からなくす」というミッションがすでに終了していることを示しているとして、著者は「この状況は昨今、しばしば『低成長』『停滞』『衰退』といったネガティブな言葉で表現されていますが、これは何ら悲しむべき状況ではありません。古代以来、私たち人類はつねに『生存を脅かされることのない物質的社会基盤の整備』という宿題を抱えていたわけですから、現在の状況は、それがやっと達成された、言うなれば『祝祭の高原』とでも表現されるべき状況です」と述べています。
また、著者は「21世紀を生きる私たちに課せられた仕事は、過去のノスタルジーに引きずられて終了しつつある『経済成長』というゲームに不毛な延命・蘇生措置を施すことではなく、私たちが到達したこの『高原』をお互いに祝祭しつつ、『新しい活動』を通じて、この世界を『安全で便利で快適な(だけの)世界』から『真に豊かで生きるに値する社会』へと変成させていくことにあります」と述べ、この転換を前向きに乗り越えていくに当たって、大きく3つのポイントがあると指摘します。1つ目のポイントは「終焉の受容」です。2つ目のポイントは、この状況を「ポジティブに受け入れよう」ということです。
「低成長」は「文明化の終了」がもたらした必然的な状況だと考えられるとして、著者は「文明化が終了してしまえば、文明化の推進を担っていたビジネスが停滞するのは当たり前のことです。本書で後ほどあらためて指摘する通り、地球の資源と環境に一定のキャパシティがある限り、全ての国はいずれどこかで成長を止めざるを得ません。この『成長が止まる状況』を『文明化の完成=ゴール』として設定すれば、日本は世界でもっとも早く、この状況に行き着いた国だと考えることができないでしょうか。これを逆さまにして指摘すれば、『高い成長率』は『文明化の未達』を意味することになります。『進んでいる』のではなく、『遅れている』からこそ成長率が高い、ということです。このように『成長の意味』を捉え直せば、世界認識の絵柄は180度反転することになります」と述べています。
著者によれば最大の問題は、そもそも「どのような社会をつくりたいのか?」という構想が描かれないままに、単なる「変化率」を表す概念でしかない「成長」という指標だけが、独善的に一人歩きしていることだといいます。わたしたちが社会を評価する際にしばしば用いる「成長率」という概念は、社会の状態を表す指標ではなく「変化率」を表す指標であり、数字でいう「微分値」をあたかも状態記述の指標のように用いているのだとして、著者は「しかし、もし私たちが『目指すべき社会』の実現のために日々、働いているのだとすれば、それがどれほど実現できたかは『目指すべき社会』の『達成度』、つまり『積分値』で記述されなくてはなりません。そして、そのような『状態を表す指標』で現在の世界をあらためて振り返れば、私たち人類がここ100年のあいだに素晴らしい偉業を成し遂げてきたことが確認できるでしょう」と述べます。
さらに、この転換を乗り越えていくための3つ目のポイントとして「新しいゲームの始まり」という点を指摘し、著者は「端的に言えば、世界は大多数の人々にとって『便利で安全で快適に暮らせる場所』にはなりましたが、まだまだ『真に豊かで生きるに値すると思える社会』にはなっていないのです。これらの問題をどのように解決していくかは個別テーマによって異なりますが、いずれにせよ言えるのは『古いゲームが終わり、新しいゲームが始まる』ということです。なお、本書でたびたび用いられる『高原』という比喩をはじめ、私たちが生きている現代という時代を世界史上の『第二の変曲点』として捉える歴史観など、本書執筆の上では社会学者の見田宗介先生の著作『現代社会はどこに向かうか――高原の見晴らしを切り開くこと』において用いられたさまざまな比喩的表現、思考の枠組みを転用させていただいていることを見田先生への感謝の意とともにここに記しておきます」と述べています。
第一章「私たちはどこにいるのか?」では、現在のパンデミックの収束がいつごろになるのか、そもそも果たして根治的な収束が起こり得るのかについて、さまざまな議論が交わされています。しかし、いずれの議論においても前提になっているのが「世界はもう元の通りにはならない」ということであるとして、著者は「その変化が良いものであれ、悪いものであれ、私たちは不可逆な変化の最中にあります。この変化をどのようにして乗り切っていくのか、私たちはこれから長い時間をかけて議論しなければならないわけですが、その議論の大前提として、あらためて確認しておかなければならない重大な論点があります」と述べ、それは、「私たちは、どこにいるのか?」「私たちの社会はどのような文脈の最中にあるのか?」ということだといいます。
経済を語る際に、必ず言及されるのがGDPです。しかし、「GDPの発明に関する問題点」では、そもそもGDPは、100年ほど前のアメリカで、世界恐慌の影響を受けて日に日におかしなことになっていく社会・経済の状況を全体として把握するという目的のために開発されたものであると指摘し、著者は「当時のアメリカ大統領、ハーバート・フーバーには大恐慌をなんとかするという大任がありましたが、手元にある数字は株価や鉄などの産業材の価格、それに道路輸送量などの断片的な数字だけで政策立案の立脚点になるようなデータが未整備だったのです。議会はこの状況に対応するために1932年、サイモン・クズネッツというロシア系アメリカ人を雇い、『アメリカは、どれくらい多くのモノをつくることができるか』という論点について調査を依頼します」と述べます。
数年後にクズネッツが議会に提出した報告書には、現在の私たちがGDPと呼ぶようになる概念の基本形が提示されていました。つまり「測りたい問題が先」にあった上で「測るための指標が後」で導入されたのです。著者は、「本来、私たちがやらなければならないのは、そのような『GDPの延命措置』ではなく、『人間が人間らしく生きるとはどういうことか』『より良い社会とはどのようなものか』という議論の上に、では『何を測れば、その達成の度合いが測れるのか』を考えることでしょう。経済学者をはじめとした専門家の多くはこの種の議論を非常に嫌がりますが、理由は明白で、このように抽象的で哲学的な議論のプロセスでは『専門家としての権威』を発揮できないからです」と述べています。
また、「GDPという指標がもつ意味」では、1958年に、いたずらに経済成長率という指標だけを追いかけることの危険性を訴え、経済成長と医療・教育・福祉などの充実をバランスさせるべきだと訴えたガルブレイスの『ゆたかな社会』が世界的ベストセラーとなったことを紹介し、著者は「その後、半世紀を経て、物質的満足度がすでに飽和しているにもかかわらず、ガルブレイスの主張とは逆行するようにして、なぜGDPという指標が、他の指標に突出して重視されるようになったのか? おそらくは『それ以外の適当な目標がなかったから』というのがその理由でしょう。かつてモンテーニュが言ったように『心は正しい目標を欠くと、偽りの目標にはけ口を向ける』のです。私たちの社会が指標としてとうに賞味期限の終わった指標を使い続けていることは、とりもなおさず、私たちが新しい目標となる構想を描くことができていない、ということです」と述べます。
「新しい価値観、新しい社会ビジョンを再設計する」では、GDPという指標はもともとアメリカによって考案されたわけですが、この指標で国威を測るからこそアメリカがつねに優位な立場にある(ように見える)という点を忘れてはならないとして、著者は「アメリカの経済分析局はかつて『GDPは20世紀でもっとも偉大な発明の1つだ』と評しましたが、そう考えるのも無理はありません。なんといっても、この指標で測るからこそ『アメリカは世界一の覇権国』であり続けられるのです。そしていま、製造産業から情報産業へのシフトが大きく進むアメリカによって『非物質的な財=無形資産をGDPに算入しよう』という議論が主導されている」と述べます。
「『成長』のイメージは『幻想に過ぎない』」では、フランスの経済学者、トマ・ピケティは世界的なベストセラーとなった著書『21世紀の資本』において、わたしたちが一般に有する「成長」のイメージは「幻想に過ぎない」と一蹴していることを紹介し、著者は「成長というのは一種の宗教なのだな」ということをつくづく感じると述べています。また、「『成長・成長』は「信仰」と同じ」では、著者は2017年に上梓した『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』において、ビジネスにおける意思決定があまりにもサイエンスに傾斜するようになっていることで、かえってビジネスが矮小・脆弱になっており、人間性に根ざした感性や直感をビジネスに回復させることの重要性を指摘したことを紹介し、「こと経済・社会に関する認識については、この傾向が明らかに逆転していると感じています。理由はシンプルで、『無限の成長』という考えは『非科学的なファンタジー』でしかないからです」と述べています。
さらに、科学的にあり得ないことを信じることを「信仰」と言うのであり、「成長・成長」とひたすらに叫ぶ人たちというのは、これを一種の宗教として信じていると指摘して、著者は「アメリカの社会心理学者、レオン・フェスティンガーは、認知的不協和理論を提唱し、数々の例証から「自分の信念と事実が食い違うとき、人は『信念を改める』よりも『事実の解釈を変える』ことで信念を守ろうとする」と指摘しました。この現象が特にわかりやすく発現するのが信仰の現場です。フェスティンガーはカルト教団の内部に潜り込み、『UFOがやってくる』『大洪水が地球を襲う』といった教祖の予言が外れるという事実を眼前にしても、依然として帰依を解こうとしない信者を観察したことがきっかけとなってこの理論の着想を得ています」と述べます。
「枢軸の時代」では、人類史を4つのステージ、すなわち「文明化以前の時代」「前期文明化の時代」「後期文明化の時代」「文明化以後(高原)の時代」に分けて整理します。「文明化以前の時代」とは、今日の私たちの社会の基底をなすさまざまな抽象的な制度や仕組み、たとえば「貨幣」や「市場」や「宗教」などが考案・実装される前の時代ということです。人類の始祖がアフリカで誕生して以来、数万年にわたって続いたこの時代に転換点をもたらしたのが「枢軸の時代」でした。人類が向き合った「1つ目の変曲点」です。
「枢軸の時代」という言葉は、ドイツの哲学者・精神科医だったカール・ヤスパースが、紀元前5世紀を挟んだ前後の300年ほどのあいだに全地球規模で発生した思想史・文明史的な転換点を指して名付けたものだと説明し、著者は「一体、何が起きたのか?この時代、古代ギリシアではソクラテスやプラトンによって哲学が、インドではウパニシャッドや仏教が、中東ではゾロアスター教が、中国では諸子百家による儒教が、パレスチナではキリスト教の礎となる古代ユダヤ教が、それぞれ生まれました。不思議なことに、たった500年ほどの短い期間に、西はエーゲ海から東は中国まで、今日の私たちの精神・思想・科学の骨組みとなる考え方が全地球規模といってよい範囲で同時多発的に生まれたのです。一般に、歴史の文脈で『近代』というとき、それは16世紀のルネサンス以降、啓蒙時代が始まってから現代までのあいだということにされていますが、筆者はこの「枢軸の時代」が、近代の特徴とされる「人間主義」「合理主義」「自由主義」の萌芽であったことから、これを「長い近代の始まり」と考えています」と述べています。ちなみに、わたしは『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)において、「枢軸の時代」について詳しく書きました。
「文明化の終焉を生きる」では、一般に第1次産業革命のスタートは18世紀後半と考えられていますが、このタイミングから、人間がもつ問題解決能力は爆発的に増殖し、衣食住それぞれの物理環境の劇的改善という「文明化」が急速に進むことになり、その上昇カーブは20世紀後半に至るまで続くことを指摘し、著者は「しかしこの上昇カーブは、すでに見た通りさまざまな側面でその勾配をなだらかにしつつあり、以降は定常状態を前提とする『高原状態』に移行して『無限に続く幸福ないま』が循環する時代がやってくるのではないか、というのが私の仮説です。これが、人類が向き合うことになる『2つ目の変曲点』です。つまり私たちは、BCE5世紀の頃、『1つ目の変曲点』を通過してから、ほぼ2500年ぶりに、新しいモードに切り替える時期にきている、ということです。冒頭から記述してきた内容を受けてそれを表現すれば、私たちがいま生きているのは『文明化の終焉の時代』だということになります。そして、おそらくは2020年に発生したグローバルなコロナによるパンデミックが、この高原状態への移行を急速に推し進めることになることでしょう」と述べます。
「『グレートリセット』が意味するもの」では、2020年6月、著者自身も分科会のメンバーとなっている世界経済フォーラム(通称ダボス会議)は、2021年1月に開催される年次総会のテーマを「The Great Reset=グレートリセット」にすると発表しました。世界経済フォーラムを創設したクラウス・シュワブ会長は、この「リセット」が意味するものについて、「世界の社会経済システムを考え直さないといけない。第2次世界大戦後から続くシステムは異なる立場のひとを包み込めず、環境破壊も引き起こしている。持続性に乏しく、もはや時代遅れとなった。人々の幸福を中心とした経済に考え直すべきだ(日本経済新聞2020年6月3日記事より)」と語っています。ここでシュワブがかなりオブラートに包んだモノの言い方をしていますが、彼のこれまでの言説を踏まえて意訳すれば、「第2次世界大戦後から続くシステム」とは、これまでたびたび言及した「無限の成長を前提とするシステム」を指すことは明らかです。
では、この強迫的なシステムをどのように「リセットする」のか? シュワブはここで「人々の幸福を中心とした経済」という言葉を用いています。記者の「リセット後の資本主義はどうなりますか」という質問に対して、シュワブは「資本主義という表現はもはや適切ではない。金融緩和でマネーがあふれ、資本の意味は薄れた。いまや成功を導くのはイノベーションを起こす起業家精神や才能で、むしろ『才能主義(Talentism)』と呼びたい。コロナ危機のなか、多くの国で医療体制の不備が露呈した。経済発展ばかりを重視するのではなく、医療や教育といった社会サービスを充実させなければならない。自由市場を基盤にしつつも、社会サービスを充実させた『社会的市場経済(Social market economy)』が必要になる。政府にもESG(環境・社会・企業統治)の重視が求められる」と述べています。
また、「『資本の価値』も『時間の価値』もゼロに」では、わたしたちの社会システムは「時間によって資本の価値が増殖する」ということを前提にして構築されているわけですが、近代以降、長らく常識として考えられてきたことが、もはや成立しなくなってきていると指摘しています。これはいったい、どういうことなのか。著者は、「重要なポイントは『時間』です。『将来における資本の価格が利子』になるということはつまり『利子』と『時間』というものが不可分の関係にあるということです。『時間」によって「利子」の存在が合理化されるということは、逆に言えば「利子=資本の価値」がゼロになったということは、つまり「時間の価値」もゼロになったということです。いや、これはロジックが逆転していますね。実際に起きていることはむしろその逆でしょう」と述べています。
「『希望の物語』という幻想」では、「時間の価値の喪失」という状況は、わたしたちが人類史的な転換点に差し掛かっていることを示しているとして、著者は「人類の歴史に登場したイデオロギーにはしばしば『より良い未来のために、いまを手段化する』という考え方が含まれています。たとえばキリスト教に『最後の審判』という考え方があることはご存じでしょう。(中略)また、マルクス主義では、人類の歴史がすべて『階級闘争の歴史』であったと整理した上で、この歴史はやがて、労働者の団結によって資本家が打倒され、階級対立も支配もない共同社会が訪れることで完成する、としています」と述べます。
マルクスが「宗教は民衆のアヘンである」と指摘したことはよく知られていますが、著者は「だからこそ、実際にロシア革命以後、ソ連や中国などの共産主義国家において明確な政策的意図をもって宗教が弾圧されたわけですが、そのようなマルクス主義と、そのマルクス主義が強く否定した正典宗教とが実は同じ枠組みの物語を唱えており、数十億人というスケールの人々がその物語に陶酔したという事実は、私たちに大きな洞察を与えてくれます。それは、私たち人間は、そういう類の『いま頑張っていれば、いずれ良い未来がやってくる』という『希望の物語』が大好きだということであり、これを逆に言えば、そのような『希望の物語』がなければ、私たちは生きていけない、ということなのです。ところが、そのような物語を、ついに誰も紡げなくなってしまった世界が、いままさに訪れているのです」と述べます。
「成長の完了した『高原状態』の社会」では、著者は「では資本に変わるものはなんなのか?」と問い、シュワブが「資本主義から才能主義への転換」と記者に答えたことを紹介し、「『才能』とは言い換えてみれば『個性』ということです。いま、この世界に生きている人々が、各自の衝動に基づいて発揮する個性こそが、社会をより豊かで瑞々しいものに変えていく。そういう未来を『才能主義』と言っているのです。ここでもまた『経済発展』だけをいたずらに目指すのではなく、『より良い社会』の実現に、私たち人間のもっている才能や時間という資源を投入するべきだというアイデアが提示されています。シュワブはまさに『高原社会の高度をこれ以上高めようとするのではなく、この高原社会を、私たちにとってより幸福なものにする方向へ転換しよう』と呼びかけているのです。ここに『新しい人間観・社会観』が求められることになります」と述べています。
近代から続いている上昇の放物線の慣性のうちにあって、無限の成長が続くということを当たり前の前提として考えている人たちにとって、成長の完了した「高原状態」の社会は、刺激のない、停滞した、魅力のない世界のように感じられるかもしれないとして、著者は「ここに、私たちが向き合わなければならない本質的な課題があります。真に問題なのは『経済成長しない』ということではなく『経済以外の何を成長させれば良いのかわからない』という社会構想力の貧しさであり、さらに言えば『経済成長しない状態を豊かに生きることができない』という私たちの心の貧しさなのです」と述べていますが、これはまさに拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)のメッセージでもあります。
第二章「私たちはどこへ向かうのか?」の「『経済性から人間性』への転換」では、『心ゆたかな社会』に通じるメッセージがさらに展開されていきます。「高原への軟着陸」というフェーズにさしかかったわたしたちの社会は、これからどちらの方向へ向かうべきなのか。著者は、「便利で快適な世界」を「生きるに値する世界」へと変えていくと示し「これを別の言葉で表現すれば『経済性に根ざして動く社会』から『人間性に根ざして動く社会』へと転換させる、ということになります。私たちがこれから迎える高原社会を、柔和で、友愛と労りに満ちた、瑞々しい、感性豊かなものにしていくためには、この『経済性から人間性』への転換がどうしても必要になります」と述べています。そして、これを実現するために必要なのは、ここ100年のあいだ、私たちの社会を苛み続けてきた3つの強迫、すなわち「文明のために自然を犠牲にしても仕方がない」という文明主義、「未来のためにいまを犠牲にしても仕方がない」という未来主義、「成長のために人間性を犠牲にしても仕方がない」という成長主義からの脱却が必要になるといいます。
「『人間の条件』とは何か」では、フランスの文学者で飛行家でもあったアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリが著書『人間の大地』の中で述べた「人間であるということは、まさに責任を持つことだ。おのれにかかわりないと思われていたある悲惨さをまえにして、恥を知るということだ。仲間がもたらした勝利を誇らしく思うことだ。おのれの石を据えながら、世界の建設に奉仕していると感じることだ」という言葉が紹介されます。サン=テグジュペリは「人間の条件」として「おのれにかかわりないと思われていたある悲惨さをまえにして、恥を知る」ということをあげています。著者は、「もし私たちが『経済合理性』を理由にして、社会に残存する格差や貧困や虐待といった『悲惨さ』を放置せざるを得ないのだとすれば、もはや私たちは人間性を備えた存在=ヒューマンビーイングたり得ないと言っているのです。今日の日本の社会が抱えている悲惨さを思い返せば、実に耳の痛い指摘です」と述べています。
「人為的に問題を生み出す体系=マーケティング」では、経営思想家のピーター・ドラッカーが、企業の目的は1つしかなく、それは「顧客の創造」であるとした上で、さらにその活動は「マーケティング」と「イノベーション」の2つに支えられると言い切ったことが紹介されます。著者は、これを「問題の開発」と「問題の解消」という枠組みで考えてみれば、実は同じことを言っているということがわかるとして、「『問題の開発』がマーケティングであり『問題の解消』がイノベーションだということです。マーケティングという用語自体は20世紀の初頭で生まれていますが、今日の私たちが用いているのと同様の概念として定着したのは、1960~70年代のことです」と述べます。
今日でもビジネススクールのマーケティング科目の定番教科書として用いられているフィリップ・コトラーの『マーケティング・マネジメント』の初版がアメリカで出版されたのは1967年のことだと紹介し、著者は「この1967年という年に不思議な符号を感じないわけにはいきません。放っておいても社会が次から次へと『解いてほしい問題』を投げかけてくれているのであれば、マーケティングは必要ありません。マーケティングが体系的なスキルとして社会に求められるようになった、ということは、事業者みずからが問題を開発しなければ、新しい欲求を生み出すことができなくなったことの証左でもあるのです」と述べます。
「道徳か好景気か」では、具体的に、どのようにすれば「需要の飽和」を先送りできるのか? 著者は、1970年代において、広告代理店の電通でマーケティング戦略立案のために用いられていた「戦略十訓」の内容を以下のように紹介します。
1.もっと使わせろ
2.捨てさせろ
3.無駄使いさせろ
4.季節を忘れさせろ
5.贈り物をさせろ
6.組み合わせで買わせろ
7.きっかけを投じろ
8.流行遅れにさせろ
9.気安く買わせろ
10.混乱をつくり出せ
「戦略十訓」を紹介した後、著者は「たしかに、これらのことができれば「需要の飽和」は先送りにできるかもしれません。しかしおそらく、このリストを一読した人のほとんどは、内容に強い違和感を、あるいはもっと率直に言えば不快感を覚えたと思います。資源・環境・ゴミ・汚染といった問題が全地球的に議論されている現代の私たちから見れば、こういった意図をもって需要を誘起するのはあまりにも非倫理的だと思うかもしれません」と述べます。
「『欺瞞』の限界について」では、大規模な災害や戦争の後にはGDPが増大することが紹介されます。大きな破壊が起きるとその破壊を埋め合わせるための大規模な生産が必ず後で発生するからですが、著者は「これはつまり、経済成長というのはそもそも、その前提として破壊という営みを必要としているということですが、だからといって経済成長のために戦争を起こそう、災害を祈ろうということにはなっていません。なぜか? それがあまりにも非倫理的だということが誰にとっても明らかだからです。なので『破壊』という言葉を、当たり障りのない『別の言葉』に置き換えて、これを促進させることで経済を活性化させようということが、一種のまやかしとして行われることになります。この『別の言葉』が『消費』です。『消費』とはすなわち『廃棄してスクラップにする』ことですから『破壊』と同義なのです。そして、この『消費と呼ばれる破壊』を促進させるための知識・技術の体系が『マーケティング』なのであるとすれば、この活動が潜在的にいかに大きな問題に接続されかねない『倫理的にギリギリの活動』なのかが理解できると思います」と述べています。
社会におけるデザインの役割と責任について活発な提言を行ったオーストリアのデザイナー、ヴィクター・パパネックは著書『生きのびるためのデザイン』で、「多くの職業のうちには、インダストリアル・デザインよりも有害なものも有るには有るが、その数は非常に少ない。たぶん、たった1つの職業がいっそうといかがわしいものだといえよう。広告デザインがそれである。多くの人を説き伏せて、手元に金がありもしないのに、もっぱら人目を引きたいという理由から要りもしない品物を買ってしまうように誘惑する職業などというものは、おそらくいまの世の中に或る職業のうちで最もいかがわしいものだといえるだろう。そして宣伝・広告人の広めるあくどい白痴的な考えを商品へとでっちあげるインダストリアル・デザインは、すぐにその次にならぶものだろう」と述べています。このパパネックの言葉について、著者は「非常に辛辣な指摘ですが、これを広告・マーケティング関係者のみに向けられた批判と捉えてしまったらパパネックの本意を読み誤ることになります。ドラッカーが指摘している通り、企業活動のエッセンスが『マーケティング』にある以上、パパネックが指摘する原罪性から逃れられるビジネスパーソンはいません」と述べます。
このような経済のあり方はポトラッチを想起させる状況であるという著者は、「ポトラッチという『ゲーム』の勝者の末路」では、以下のように述べています。
「ポトラッチとは、文化人類学者のマルセル・モースが1925年に著した『贈与論』において紹介した、主にアメリカ先住民のあいだに見られる一種の儀式です。この儀式において、部族の酋長たちは『どちらがより多くの財産を蕩尽できるか』を競うことでお互いの立場の優劣を決めます。つまりポトラッチというのは、より気前よく、より大胆に財産をばら撒き、破壊した方が勝つという『ゲーム』なのです」
現代の文明世界におけるポトラッチがどのようなものか、なかなか想像できないかもしれませんが、著者いわく、映画には、このような「異常蕩尽」がしばしば印象的なシーンとして描かれています。著者は、「たとえばかつてはロバート・レッドフォードが主演し、近年、レオナルド・ディカプリオの主演によってリメイクされた『The Great Gatsby』の冒頭のパーティーシーンは、これこそ文明社会におけるポトラッチだ、と思わせるものですし、同じくレオナルド・ディカプリオの主演になる『The Wolf of Wall Stree』には、ウォール街で大成功した実在の投資銀行家、ジョーダン・ベルフォードのまさにポトラッチ的で破茶滅茶なライフスタイルを描き、それがあまりにも倫理的に常軌を逸したものだったので日本ではいわゆる『18禁』になってしまいました」と述べています。
また、「『必要』と『奢侈』のあいだの答え」では、ドイツの経済学者ヴェルナー・ゾンバルトの『恋愛と贅沢と資本主義』に言及した著者は、ゾンバルトの「奢侈には二種類ある」という指摘を取り上げ、「あらためて抜粋を引けば『壮麗な聖堂を黄金で飾って神に捧げる』のと『自分のためにシルクのシャツをオーダーする』のはどちらもともに『贅沢』には違いないが、両者には「天と地の差があることがただちに感ぜられるだろう」という指摘です。この2つの『消費行動』に私たちが感じる『天と地の差』は何に由来しているのでしょうか。ここでは2つの点を指摘したいと思います。それは『他者性』と『時間軸』です。『シルクのシャツ』が純粋に自己満足・自己顕示という『閉じた目的』に向けた消費である一方、『壮麗な聖堂』は自己だけに閉じることのない他者の救済という『開かれた目的』に向けた建設であるということです。そして『シルクのシャツ』が極めて短期間のあいだに、文字通り『消費』されてしまうのに対して、『壮麗な聖堂』は事実上、無限といっていいほどの長い時間にわたって、多くの人に『高い次元の悦び』を与えてくれます」と述べています。
このような喜びを、思想家ジョルジュ・バタイユは「至高性」と呼びました。「『至高体験』を味わえるかどうか」では、これらの欲求は人間性そのもの=ヒューマニティに根ざすもので、その衝動こそが人間を人間ならしめていると指摘し、著者は「しかし、こういった欲求が『実生活で必要なものか』と問われれば、それは『否』ということになります。一方で、これらの欲求が『奢侈』に接続されるかと問われれば、それもまた『否』ということになります。つまり、こういった『人生を生きるに価するもの』に変えてくれる重大な欲求が、ゾンバルトの指摘にも、ヴェブレンの指摘にも、ケインズの指摘にも含まれていないのです」と述べるのでした。ちなみに、拙著『儀式論』(弘文堂)でもバタイユの「至高性」について詳しく書きましたが、ここで著者が言う「『人生を生きるに価するもの』に変えてくれる重大な欲求」をわたしは「礼欲」と呼んでいます。礼とは神につながることであり、人と人が交流することでもあります。ポトラッチそのものが儀式的ですが、儀式とは究極の消費と言えます。
「インストルメンタルとコンサマトリー」では、著者は「私たち人間が『生の充実』をもっとも強く感じるのが『人間性に根ざした衝動』を解放した時なのだとすれば、すでに十分な文明化を果たした私たちの「高原社会」において、人々が、本質的な意味でより豊かに、瑞々しく、それぞれの個性を発揮して生きていくためには、各人の個性に根ざした衝動を解放しなくてはなりません。しかし、現在の社会では、このような『人間を人間ならしめる』衝動的欲求の多くが未達になっており、そしてより重大なことに、その『未達になっていること自体』にあまりにも多くの人々が無自覚です」と述べます。市場が「未達の欲求」があるところに生まれるのであれば、これまでの経済とは異なる位相の広大な市場が、潜在的には生まれることになります。著者は、まさにいま「高原」へと至りつつある社会において、このような「人間的衝動」に根ざした欲求の充足こそが、経済と人間性、エコノミーとヒューマニティの両立を可能にする、唯一の道筋なのではないかと考えていると告白します。この著者の考え方に、わたしは大いに賛同します。
第三章「私たちは何をするのか?」の「高原のコンサマトリー経済」では、わたしたちの社会は、200年にわたって続いた熾烈な文明化の競争、効率化への強迫から、ついに解放され、さらなる上昇を求められることのない穏やかな高原社会に到達したと指摘し、著者は「このような高原社会において、かつて私たちが経験したような高成長を志向すれば、それは必然的に非倫理的な領域への侵犯を伴うことになってしまいます。このような社会において、私たちの経済活動は、文明的な便利さを向上させることから、文化的な豊かさを向上させることへと転換し、経済活動と社会の豊かさの増進を同調させていくことが求められます」と述べています。
「イニシアチブ1:真にやりたいコトを見つけ、取り組む」では、著者は、あたかもアーティストやダンサーが、衝動に突き動かされるようにして作品制作に携わるのと同じように、私たちもまた経済活動に携わろうということを提案し、「20世紀後半に活躍したドイツの現代アーティスト、ヨーゼフ・ボイスは『社会彫刻』という概念を唱え、あらゆる人々はみずからの創造性によって社会の問題を解決し、幸福の形成に寄与するアーティストである、と提唱しました。世のなかには『アーティスト』という変わった人種と、『アーティスト以外』の普通な人種がいる、というのが一般的な認識でしょう。しかし、そのような考え方は不健全だ、とボイスは言っているのです」と述べています。
この「アートとビジネスの近接」は多くの場合、「ビジネス文脈にアートを取り込む=Art in Business Context」か、またはその逆に「アート文脈にビジネスを取り込む=Business in Art Context」という議論がほとんどで、「ビジネスとアートをまったく別のモノとして捉えている」という点で共通していると指摘し、著者は「このような枠組みを前提にした取り組みを続けている限り、アートはやがて、かつてもてはやされ、やがて弊履を捨てるようにして忘れ去られた数多くの経営理論やメソッドと同じように、ビジネス文脈での流行スキルの1つとして消費されて終わることになるだけだと思います」と述べます。
「根本的にそれは違うだろう」と思う著者は、「本質的に、いま私たちに求められているのは、ビジネスそのものをアートプロジェクトとして捉えるという考え方、つまり『Business as Art』という考え方だと思います。文明化があまねく行き渡り、すでに物質的な問題が解消された高原の社会において、新しい価値をもつことになるのは、私たちの社会を『生きるに値するものに変えていく』ということのはずです。そして、そのような営みの代表がアートであり文化創造であると考えれば、これからの高原社会におけるビジネスはすべからく、私たちの社会をより豊かなものにするために、各人がイニシアチブをとって始めたアートプロジェクトのようにならなくてはいけないと思うのです」と述べます。
「衝動で駆動するソーシャルイノベーション」では、「凍てつく真冬の夜に、屋台のラーメン食べたさに子供を連れて長い列に震えながら並ぶ人たちを見て『自宅で気軽に美味しいラーメンを食べさせてあげたい』と感じた安藤百福」や「ゼロックスのパロアルト研究所で『コンピューターの未来』を示唆するデモンストレーションに接して『これは革命だ!このスゴさがわからないのか!』と叫び続けたスティーブ・ジョブズ」などを例として取り上げ、著者は「このような『経済合理性を超えた衝動』は、アーティストの活動においてしばしば見られるものですが、同様の心性がアントレプレナーにもしばしば観察されるのです。現在、ビジネスの文脈においてしばしば議論の俎上に上る、いわゆる『アート思考』とビジネスとの結節点はここにあります。高原社会において、必ずしも経済合理性が担保されていない『残存した問題』を解決するためには、アーティストと同様の心性がビジネスパーソンにも求められる、ということです。
「文明的価値から文化的価値へ」では、価値創出の転換の成功事例として、あらためて参照したい人物として、著者は我が国の武将である織田信長を取り上げます。織田信長はおそらく、日本の戦国時代がいつまでも終わらない本質的な理由について気づいた、歴史上最初の人物であるとして、「戦国時代において、武将の格を決めるもっとも重要な指標は『石高』ですが、これは要するに『保有している耕作地の大きさ』のことを指します。なぜ、耕作地の広さが問題になるかというと、当時の経済規模は耕作地の面積にほぼ比例したからです。信長はこの点を治世上の問題として考えました。どういうことでしょうか。日本は島国で国土を容易に拡大することができない上、その国土の9割は山岳や丘陵地帯で耕作に適した平地は1割程度しかありません。つまり『耕作地の広さ』をめぐって争うと必ず『誰かが得をすれば必ず誰かが損をする』というゼロサムゲームにならざるを得ないのです。これが、信長だけが気づいた『戦国時代がいつまでも終わらない本質的な理由』でした」と述べています。
信長は、自分が仮に天下を統一することになったとしても、この問題から逃れることはできないということに気づいていたとして、著者は「自分の部下である武将が勲功をあげたとして、彼に領地を与えようとすれば、それは必ず、他の武将もしくは自分の領地が減ることを意味したからです。このような状況では安定的な統治など望むべくもありません。最終的に、信長はこの問題をきわめて鮮やかに解いてしまいます。いったいとうやって? 『茶道によって』です。信長は自身が茶道を嗜み、茶器などの茶道具を山や城と交換することで、巨大な価値空間を創出することに成功したのです。一種の貨幣を生み出したといっても良いでしょう」と述べます。
「消費されていないという『価値』」では、すでに需要・空間・人口という3つの有限性を抱えている世界において、大きな経済的価値を創出しようとすれば、それは「文化的価値」という方向をおいて他にないとして、著者は「文明化がすでに終了した世界にあって、これ以上の過剰な文明化が富を生み出すことはありません。一方で『文化的価値の創出』についてはその限りではありません。意味的価値には有限性がありませんから、無限の価値を生み出すことがこれからも可能です。そしてその価値は資源や環境といった有限性の問題から切り離されているのです。文明化の終了した世界にあって、人々が人生に求めるのはコンサマトリーな喜びであり文化的豊かさであると考えれば、これからの価値創出は『文明的な豊かさ』から『文化的な豊かさ』へとシフトせざるを得なくなります」と述べています。
「労働+報酬=活動」では、「畑仕事」といえばそれは「労働」になりますが、同じ行為を「ガーデニング」といえば「遊び」になるとして、著者は「これは魚釣りも狩猟も同じで、過去の社会においてど真ん中の『労働』であったものが、今日の社会において優雅な『遊び』に転じているわけです。一方でその逆に、かつて貴族にしかできない『余暇』の過ごし方だった、研究、創作、執筆、ガーデニング、スポーツといった活動のほとんどは、今日の社会において、何からの経済的価値を生み出す『労働』として認められるようになっています」と述べています。
「遊びと労働が一体化」では、遊びと労働が一体化するコンサマトリーな経済はすでに社会の一部には顕現していると指摘し、「これは前著『ニュータイプの時代』でも指摘したことですが、今日の社会において、最前線で活躍している人ほど『遊びと仕事』の境界が曖昧になっています。これはもちろん『遊びがお金を生んでいる』という意味でもあるのですが、それ以上に『仕事そのものが報酬となってその場で効用として回収されている』ということでもあるのです。労働と報酬が一体化すれば、労働そのものの概念が変わることになります。おそらく、これは人類史における革命的な転換となるでしょう」と述べます。
「昔話と『重要な忠告』の共通項」では、第2次世界大戦時に日本に滞在して諜報活動を指揮したソ連共産党のスパイ、リヒャルト・ゾルゲは日本への赴任が決まった際、真っ先に「日本の神話」を収集し、これを読み込むことで日本人の精神構造を理解しようとしたことを紹介し、著者は「イギリス大使のパークスなども同様のことを行っていますが、スパイ活動や外交交渉などのような、手続き上のルールだけに従っていてもコトが進まないような『一筋縄ではいかない』仕事に取り組む場合、相手の精神性を深いところまで理解するためのよすがとして、彼らはその国の文化が営々として築き上げてきた神話に頼るわけです」と述べます。
「生産者と消費者の顔の見える関係づくり」では、生産者と消費者が顔の見える関係にあれば、生産者は、自分の生み出したモノ・コトによって喜ぶ消費者を見て、喜びを感じるとして、著者は「しかし、それだけではありません。実はこの時同時に、喜ぶ生産者を見ることはまた、消費者にとっての喜びでもあるからです。そしてそのような関係性にある生産者と消費者を見ることは、枠外にいる他者にとってもまた喜びでしょう。喜びがエコーのように反射していくのです。現在の分断社会において、このような関係性がもっともわかりやすく成立しているのがレストランと常連客の関係です。シェフにとって、自分の労働から得られる最大の喜びは、支払われる代金などではなく、テーブルで顧客が交わす『美味しい!』という声であり、花のように咲く笑顔でしょう。そしてまた常連客にとっては『美味しい!』と伝えた時に見られるシェフが見せる喜びがまた、同時に自分にとっての消費の喜びとなっているのです。最終的にはもちろん、顧客は代金を支払ってその場の取引を閉じるわけですが、そこで支払われている代金は『等価交換によって関係をチャラにする』というよりは、むしろ『感謝のしるし』として、あるいはもっといえば多分に『贈与』のニュアンスを含んだものになります」と述べています。
また、「『責任ある消費』と『贈与』の関係」では、わたしたちの存在は「死者」と「自然」から贈与されているとして、著者は「贈与されたモノは贈与し返さないといけません。私たちもまたいずれ『死者』あるいは『自然』として未来に生きる私たちの子孫に対して贈与する義務を負っているからです。つまり、私のいう『責任消費』というのは、贈与された私たちの存在を未来の子孫に対して贈与し返しましょう、ということなのです。しかし、多くの人々は、私たちが『贈与された』ということを忘れてしまいがちです」と述べています。これは、まさに拙著『唯葬論』(サンガ文庫)で展開したわたしのメッセージと同じです。
「『消費』や『購買』は、より『贈与』や『応援』に近い活動へ」では、これからやってくる高原社会では労働と創造が一体化していくことになるとして、著者は「そのような社会においてはまた同時に、これまでの『消費』や『購買』は、より『贈与』や『応援』に近い活動になっていくことでしょう。そのような社会にあって『被贈与の感覚』を守り、育んでいくことは非常に重要です。しかし、このような指摘に対して『贈与が大事だということはわかったけれども、では具体的にどのようにすれば良いのか?』と思う人もいるかもしれません。なに、難しく考える必要はありません。大事なことは一点だけ、それはできるだけ『応援したい相手にお金を払う』ということを心がけるということです」と述べています。これを読むと、著者の言う「高原社会」とは、わたしの言う「ハートフル・ソサエティ」に限りなく近いことがよくわかります。
「『責任ある消費』で市場原理をハックする」では、わたしたちは日常生活の中で、特に意識することもなく、モノやサービスを購入するわけですが、この購入は一種の選挙として機能し、購入する人が意識することなく、どのようなモノやコトが、次の世代に譲り渡されていくかを決定することになることを指摘し、著者は「私たちが、単に『安いから』とか『便利だから』ということでお金を払い続ければ、やがて社会は『安い』『便利』というだけでしかないものによって埋め尽くされてしまうでしょう。もしあなたがそのような社会を望まないのだとすれば、まずは自分の経済活動から考え直さなければなりません。だからこそ、『責任ある消費』という考えが重要になってくるのです。なぜ『責任』なのかというと、私たちの消費活動によって、どのような組織や事業が次世代へと譲り渡されていくか、が決まってしまうからです。私たちが、自分たちの消費活動になんらの社会的責任を意識せず、費用対効果の最大化ばかりを考えれば、社会の多様性は失われ、もっとも効率的に『役に立つモノ』を提供する事業者が社会に残るでしょう」と述べています。
「おわりに 資本主義社会のハッカーたちへ」では、著者は「世界に満ちている不合理や不条理に憤っていて、それを変えたいと思いながらも、巨大な敵を前にしてどのように行動を起こしたらいいか、考えあぐねている人たち」に、「資本主義のハッカー」となることを提案し、「私たちが依拠している社会システムを外側からハンマーでぶっ壊すのではなく、静かにシステム内部に侵入しながら、システムそのものの振る舞いをやがて変えてしまうような働きをする静かな革命家たち。これから世界のさまざま箇所で、このような思考様式・行動様式をもった人々の台頭を私たちは目にすることになるでしょう。彼らこそ、21世紀の社会変革を主導する『資本主義社会のハッカー』です」と述べるのでした。
名著『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』のときもそうでしたが、本書を読み終えて、わたしは「こんなにも同じ考えの人がいるのか?」と驚くほど、著者との思想の共通性を痛感しました。エコノミーにヒューマニティを取り戻すことは、「礼経一致」を掲げるわが社のミッションだと思っているからです。そして、本書に書かれているビジョンが今後の社会を的確に予見していることを確信しました。ゆえに、わが社の経営における認識基準や意思決定は間違っていないことを再確認し、非常に心強く思いました。