- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1892 民俗学・人類学 『スリランカの悪魔祓い』 上田紀行著(講談社文庫)
2020.06.04
6月4日は、天安門事件から31年目となる日ですね。中国にとって「悪夢」と呼ぶべき忌まわしい事件でした。中国といえば、イタリアの有力政治家が「中国政府の新型コロナウイルスの隠蔽工作は全人類に対する犯罪だ」と糾弾したことが世界的なニュースになっています。
さて、今回は『スリランカの悪魔祓い』上田紀行著(講談社文庫)をご紹介いたします。「イメージと癒しのコスモロジー」というサブタイトルがついています。単行本は1990年3月に徳間書店から単行本として刊行され、わたしはそれを読みました。同書に加筆修正した『悪魔祓い』(2000年8月、講談社+α文庫)を再編集したのが本書です。鎌田東二先生に紹介され、著者とは何度もお会いしています。
著者は1958年東京生まれ。文化人類学者。東京工業大学大学院准教授(社会理工学研究科、価値システム専攻)。1986念より、スリランカで「悪魔祓い」のフィールドワークを行い、『スリランカの悪魔祓い』で、「癒し」の観点を最も早くから提示しました。一条真也の読書館『生きる意味』で紹介した著書が2006年度大学入試で出題率第1位になるなど、その日本社会変革への提言は大きな注目を集めています。
 本書の帯
本書の帯
本書のカバーには、スリランカの悪魔祓いの儀式を撮影したさまざまな写真が使われ、帯には「他者を癒す 世界を癒す 自分を癒す」「他者とのつながりの回復の中で、人は、はじめて、癒されていく」「『癒し』の原点の書!」と書かれています。
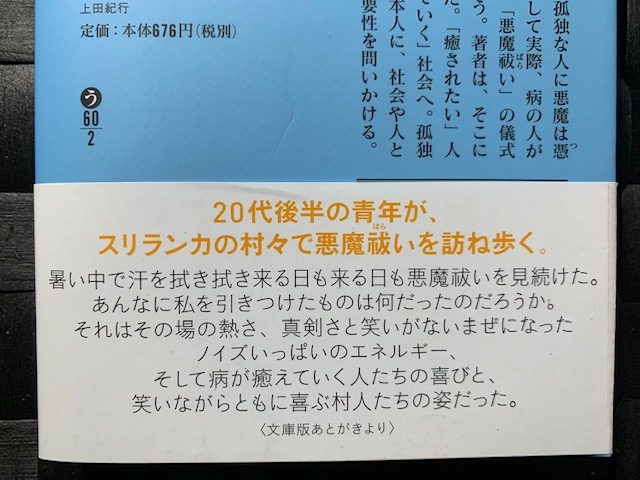 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「20代後半の青年が、スリランカの村々で悪魔祓いを訪ね歩く。」として、こう書かれています。
「暑い中で汗を拭き拭き来る日も来る日も悪魔祓いを見続けた。あんなに私を引きつけたものは何だったのだろうか。それはその場の熱さ、真剣さと笑いがないまぜになったノイズいっぱいのエネルギー、そして病が癒えていく人たちの喜びと、笑いながらともに喜ぶ村人たちの姿だった。――〈文庫版あとがきより〉」
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「スリランカでは、『孤独な人に悪魔は憑く』と言う。そして実際、病の人が出たら、村人総出で『悪魔祓い』の儀式を行い、治してしまう。著者は、そこに『癒し』の原点を見た。『癒されたい』人から、自ら『癒されていく』社会へ。孤独に陥りがちな現代日本人に、社会や人とのつながり、その重要性を問いかける」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「文庫版まえがき」
第一章 悪魔に出会う
第二章 悪魔に憑かれる
第三章 悪魔を祓う
第四章 悪魔と遊ぶ
「あとがき」
「参考文献一覧」
「文庫版あとがき」
「文庫版まえがき」で、著者はこう書いています。
「スリランカの悪魔祓いは、古より伝わる癒しの術である。そこには数千年かけて築きあげられてきた、人類の叡智が結晶している。試行錯誤を繰り返してきたその長い年月は、悪魔祓いの儀式を、人間の潜在力を揺り動かす、きわめて効果的かつ優美な体系へ導いてきた。それはわれわれの隠された力を掘り起こす仕掛けに満ちている」
続けて、著者は「緊張と弛緩、恐怖と安心、怒りと笑い、孤独とつながり、静寂と狂騒……、悪魔祓いは人間のすべての感情と意識を動員する。それはダンスや歌や華麗な衣装によってアートである以前に、われわれの意識の内奥のステージがひとつひとつ明るみに出される一大パフォーマンスであるという意味で、まぎれもないアートなのである。そしてそのアートの中心に悪魔がいるのだ」と書いています。
第一章「悪魔に出会う」では、アバマンガレ・リーリ・ヤカー(葬式の血悪魔)へ巨大な供えものをする儀式について、次のように書かれています。
「葬式の血悪魔は数ある血悪魔の中でももっとも強力で、人間の死体を好む。そのため呪術師は自ら死体の役となり、悪魔を呼び寄せるのだ。ここで奇妙なことが起こった。場内で見物していた村の男たちが、一斉に叫びだしたのだ。
『アーポー、アーポー、何で死んじゃったんだよう!』『戻ってきてくれよう、お父ちゃん。おれだけを置いてかないでくれよう!』『アーポー、アーポー、悲しいよう』
なんと悪魔祓いの場は、今度は葬式の場になってしまったのだ。しかし、その葬式は悲痛なものではない。あまりの迫真の演技に観客からときどき笑い声が洩れる。葬式のパロディーなのだ。こんな葬式でも、悪魔はだまされてほんとうに来るのだろうか」
また、著者はスリランカにおける信仰について、「スリランカの近代仏教は悪魔信仰をまったく否定するところに成り立っていた。スリランカの街を歩くと、いたるところで大きな仏像に出会う。それは多くは主要道路の脇や、交差点に立てられていて、われわれ外国人に強い印象を与える。さすが仏教国、古代からの仏教の流れが脈々と息づいているのだなと思うのだ。ところが、その仏像がじつは新しい。古代どころか、ほとんどが1950年代以降に建てられた代物なのである。そして、その仏像の立てられている場所の多くがキリスト教会の前だったり、その跡地だったりという事実を聞くと、われわれは当惑してしまう。現在の仏教は、植民地支配から独立後にキリスト教を打ち破って出てきた新しい宗教なのである」と述べています。
さらに、著者は「植民地統治への憤り、怒り、アイデンティティ・クライシス。しかし、そこに彗星のように登場したのが、スリランカ近代仏教の祖アナガーリカ・ダルマパーラ(1864~1933)だった。仏教徒の家に育ったものの、キリスト教教育を受けたドン・デイヴィッド・ヘーワヴィタラネが16歳のときに神智学協会のブラヴァツキー夫人とオルコット大佐に見いだされ、感化されて仏教の偉大な伝道者アナガーリカ・ダルマパーラとなり、スリランカに仏教の復興をもたらしていく過程は、それだけで1冊の本になってしまうほど劇的なものだ」と述べます。
続けて、著者は以下のように述べるのでした。
「けれど、アナガーリカ・ダルマパーラによって復興させられた仏教はそれまでの仏教とは決定的に違っていた。従来の出家者中心の仏教から在家者中心の仏教へ、またキリスト教への対抗意識をむきだしにしたナショナリズム的仏教へ。ダルマパーラはスリランカがシンハラ人の島であり、仏法の島であることを生涯を通じて説きつづけた。そしてそれは植民地統治下のシンハラ人に大きな力を与えた」
第二章「悪魔に憑かれる」では、「悪魔祓いの式次第」として、著者は「悪魔祓いを見ていくうちに、その進行がはっきりとした式次第を持っていることがわかってきた。同じ『演目』ならば、その進行はいつもほとんど同じである。ぼくははじめて悪魔祓いを見たときに若い呪術師のアリアダーサが言った言葉が正しかったことに気がついた。家族が貧乏だったためにひとつ規模の小さな儀礼にしたが、そのピデンナ(悪魔への供えもの)という儀礼には他の大規模な儀礼の基本がすべて入っている。まったくそのとおりだったのだ。大規模な儀礼がどんなに込み入った過程に見えようとも、それは基本的には悪魔への供えものの連続だ。いろいろな悪魔に供えものをして、それを取り去るようにと命令するのだ。それは悪魔よりもはるかに偉いブッダや神々の権威のもとでなされるのである」と述べています。
「どんな人に悪魔が憑くのだろう」と質問すると、呪術師も村人も「それは孤独な人だよ」と答えたことを紹介し、著者は以下のように述べます。
「孤独、タニカマという言葉だ。それは物理的な孤独でもある。たとえばひとりで川辺で水汲みをしているとか、誰もいない家でひとりでいるとか。そして心理的な孤独でもある。さびしい。家族がかまってくれない。兄弟の中でなぜ自分だけが冷遇されているのだろう。世間の風が冷たい。そんな疎外感だ。村の人々は孤独な人に悪魔のディスティが来るという。ディスティとは眼差しという意味だ。孤独な人が悪魔に眼差される。悪魔の力とは患者を眼差す力なのである。ディスティという言葉は悪い意味にだけ使われる言葉だけれども、それが眼差しだということは重要だ」
続けて、著者は「孤独でない人には悪魔の眼差しはこない。つまり、人が眼差し眼差されあうような温かい関係の中にあるとき、悪魔の眼差しはこない。しかしその温かい人の輪の外に投げだされてしまうと、人は悪魔に眼差されてしまうのである。そうだとしたら悪魔に眼差された人を癒すにはどうすればいいのだろう。その答えは明らかだ。悪魔の攻撃のもととなったタニカマ、孤独を癒せばいいのである。温かい人の輪の中で患者をもう1回取り囲むことが不可欠なのだ。そして、悪魔祓いの中で行われているのも患者の人の輪の取り戻しなのである」と述べます。
第三章「悪魔を祓う」では、「なぜ癒されるのか」として、著者は「儀礼の機能のうちもっとも重要なものは人間関係、社会関係を修復したり、調停したり、社会に統合をもたらしたりする機能である。たとえば結婚式という儀礼がある。好きなもの同士がただ一緒になる。あるいは結婚届を出す、それだけでいいはずなのになぜ人は結婚式をそれも盛大にするのか。それは結婚によってもたらされる社会関係の変化を調停するためだ、というのがこの考え方だ。ひとりの男とひとりの女が一緒になり、これからはひとつの夫婦という単位であつかわれるようになるためには劇的な社会関係の変化を必要とする。本人同士もそうだし、特に双方の親族にとっては、いままで親戚でもなかった人々がこれからは親戚になるわけだから重大な変化である。そのためには結婚式という場にともに集い、神様とか仏様の権威のもとで儀式をし、一緒に飲んだり食べたりしてその劇的な変化を調停しなければならないのである」と述べています。
結婚式に続いて、葬式ついても、著者は「葬式だってそうだ。ひとりの人間がこの世から突然いなくなる。彼の持っていたすべての人間関係から彼あるいは彼女だけが脱落するのである。そして家族にとっては父や母や息子や娘がぽっかりといなくなる。その穴をどう埋めていくのか、悲しみを乗り越えて新たな人間関係へどのように移行していくのか。葬式は、ひとりの人生の終わりであるとともに、その人間不在の新たな社会関係のはじまりの場なのである」と述べます。
さらに、祭りについても、「お祭りもまた儀礼だ。そして、それが社会の統合という機能を持っていることを疑う人はいないだろう。お祭りを一緒にすることで自分たちは同じ社会の一員なのだという一体感がもたらされる。結果、社会の統合が維持されるのである。そう考えていくと、どんな社会に存在する儀式や儀礼もみんな、ある社会的機能を持っている。スリランカの悪魔祓いだってそうだ」と述べています。
そのような儀礼について、著者は「たくさんのシンボルによって構成された儀礼が伝えるメッセージは究極のところ、その文化の世界観、コスモロジー(宇宙観)である。つまり、その文化が世界や宇宙をどう考えているかということだ。宇宙の起源は何か、人間の起源は何か、民族の歴史はどうはじまったか、天体の意味は、さまざまな植物や動物の意味は、そして社会のさまざまな役割の意味は……そうした情報がメッセージとして伝達されていると考えるのである。そうしたメッセージは多くの神話として伝えられてもいる」と述べます。
続けて、著者は以下のように述べています。
「だから多くの儀礼は神話の上演という形をとる。さまざまな社会で、学校という情報伝達の制度がなくても、その文化が考える世界の仕組みが子孫へと伝わっていくのは、神話と儀礼があるからなのだ、という流れで話は進んでいく。そして、このアプローチもあの悪魔祓いにぴったりだ。悪魔祓いの中で伝えられるメッセージがシンハラ民俗仏教のコスモロジーだということは明らかだ。そのコスモロジーとはブッダを頂点とし、神々が続き、底辺に悪魔や死霊が存在するピラミッド型のものだ」
「不思議なイメージ療法」として、著者は「アメリカの放射線医で癌の専門医であったカール・サイモントンが、後にたいへん有名になるサイモントン療法というイメージによる癌の治療法を開発するきっかけになったのは、彼の診療の中で生じた大きな疑問だった。それは、なぜ同じような癌を持ちながら、ある患者は健康を回復し、ある患者はまたたく間に死んでしまうのか、という疑問だ。サイモントンはそこに患者の精神状態と癌の進行との相関関係を発見した。強い生きる意志を持ちポジティヴな信念を持っている人のほうが、悲観的でネガティブな人よりもはるかに経過がいいというのだ。もしそうならば、患者の病気に対する態度をポジティブなものに変えれば治療の効果を高めることができるはずだとサイモントンは考えた。そして、その発想から主に生体フィードバックの原理とイメージ療法の技法に基づいて、彼はサイモントン療法を開発したのだ」と述べます。
また、「悪魔祓いはイメージ療法か?」として、著者は「癌は不治という社会通念のために、サイモントン療法の患者にとっては白血球を強力に、癌を弱くイメージすることが、ときに困難で、知らず知らずのうちに癌を強く白血球を弱くイメージしてしまう。しかしコスモロジーの中のブッダと悪魔に関しては、ブッダが悪魔よりはるかに強力であることを疑う者はいない。ブッダの偉大さは小さいときから繰り返し物語られ、体に叩きこまれている。寺の前を通れば自然に手を合わせ、バスにのっていても自然に腰を上げて敬意をあらわす。それを疑うものは仏教、いや宇宙全体を疑うことになり、自分の存在自身をも疑うことになってしまうのだ。つまり、悪魔祓いにおけるイメージはそれが伝統に基づき、共同体的に保持されていることで揺るぎない基盤を持っており、患者にとってもっとも強力なイメージなのである」と述べています。
なぜイメージは心身の不調を好転させることができるのでしょうか。著者は、「プラシーボの謎」として、「その出発点は心身医学と呼ばれる分野にある。「心」の働きを軽視し、「体」の治療に重点を置いてきた近代医学の中で、心身医学は心と体、人間の精神的な状態と身体的な状態の関係を追究してきた。そこでは、われわれが分けて考えがちな心と体が分けられるものではなく、一体であるということが明らかにされてきたのだ。身体を治療するシステムであり、人間の身体をあたかも悪くなった部品を取り替える物体のように取りあつかうような医学にとって、まず第一の謎は、プラシーボ(偽薬)効果と呼ばれる一連の現象だった。プラシーボとは、「人を満足させる」という意のラテン語だ。患者の治療に対する信頼が厚い場合には、投薬された薬がたとえ砂糖の丸薬のような不活性物質でも治療効果が認められるという現象がプラシーボ効果である」と述べます。
そして、「精神神経免疫学」として、著者は「人が最大のストレス状態になり、免疫力が最低になるのは、人がつながりを実感できずに孤独に陥り、その状態に対して無力感を感じて自暴自棄になるときだという。愛するつれあいの死がもたらす無力感がその代表だ。そして、免疫力が最高になるのは、人がつながりを感じ、生きる意欲に満たされているときである」と述べるのでした。
さて、「呪文は理解不能だから効く」として、著者は「『呪文』が効くのは、それがわけがわからず『理解不能』だからなのである。意味不明の言葉を発せられたときに、われわれの分析的左脳はパニックに陥る。それを『意味』として捉えようとしてもどうにも理解できない。しかし、その左脳のパニックこそが『呪文』の謎を解く鍵なのである。それは左脳をパニックに陥れ、左脳の働きを停止させる。そしてそのときに右脳のいきいきとした働きがあらわれでてくるのである」と述べています。
続けて、著者は「なぜ宗教的な儀式のはじまりには意味不明の呪文が置かれているのだろう。悪魔への供えものの段も意味不明の呪文からはじまっていた。そしてなぜ、古より人々は聖なる場所に入っていく前に呪文を唱えたのだろう。それは呪文によって左脳の分析的な流れを止めることで、感覚的な右脳の働きを活性化させるためではなかったか。そして呪文によって活性化された右脳は、ふだんは見えない悪魔を呼び寄せ、ふだんは感じられない聖域に漂う何ものかをキャッチするアンテナとなるのだ」と述べます。
また、「イメージとしての悪魔」として、著者は「儀礼にはやたら繰り返しが多い。何で同じことを何回も繰り返さなければならないのか。1回だけやればいいのに、それは無駄ではないかと思われていたのだ。しかし、それは効果的なイメージを描くには必須の方法である。繰り返しこそが、イメージを深く身体に、右脳に埋めこむ過程であり、イメージにリアリティを与えていく過程なのである。そのイメージの身体化の極限がトランス、『憑依』だ。役者が登場人物になりきるとき、登場人物にいのちが吹きこまれるとき。そして、そのときにはじめて悪魔はリアリティを持ってあらわれでるのだ。もう患者は悪魔と完全に一体だ。どこまでが患者で、どこまでが悪魔かはわからない。患者は狂ったように踊りまくり、そして悪魔の言葉をしゃべる」と述べます。
それは悪魔のイメージが左脳のブロックを越えて右脳に、そして身体全体に及び、患者を覆いつくした状態なのであるといいます。そして儀礼はそれから一転して、患者と一体となった悪魔が患者の外に出ていくイメージの身体化の場となるのでした。著者は、「悪魔の関与しているヒステリー神経症においては悪魔を祓うのがいちばんなのだという。患者を取り巻く全状況は悪魔に象徴化されているから、それが祓われ、いなくなるという暗示療法によって患者は回復するというのだ」と述べています。
そして、文化人類学者である著者は、自身の仕事について、「文化人類学者の仕事、それは文化の翻訳である。自分の文化とは異なる世界に住みこみ、彼はさまざまな『奇習』に出会う。どうにも自文化の論理では理解できない突拍子もないことに出会うのだ。それを彼はどうにか理解し、故国で待っている人たちにも理解できるように翻訳を試みる。しかし、それはある意味では幻滅のプロセスでもある。文化人類学者は湖の底に何か妖しく輝くものを見つける。何が輝いているのだろう。彼は魅せられて、なんとか湖底から引きあげようとする。そして引きあげてみると、手の中にあるのは何の変哲もない平凡な石ころなのだ」と述べるのでした。
第四部「悪魔と遊ぶ」では、「左脳的アイデンティティの罠」として、著者は「右脳的アイデンティティとはどんなものだろう。それが『つながりの中の自分』というアイデンティティだ。他のものとの差を見つけだし、その差を分析する左脳に対して、右脳は他との同一性を直観し、それと合一していこうという働きを持つ。だから、それは他との同一性に基づいたアイデンティティを導きだす。そして、他と共有する同一性として浮かびあがってくるのが『いのち』である。われわれはみな異なっている。だから差にこだわりだせば、いかようにも分断することができる。しかし、その差は、すべてが『いのち』を持っているという大いなる同一性の前では取るに足らないものだ。そして、同一性に焦点が合わされたとき、そこには『つながりあったいのち』いうもうひとつの世界が開けてくるのである」と述べています。
このあたりは非常にニューエージの影響も感じますが、著者の処女作である『覚醒のネットワーク』のメッセージを連想しました。さらに著者は「YESの世界、NOの世界」として、このような方程式を提示します。
YES+隠された力=癒し
NO+隠された力=呪い
「イメージは主客を超える」として、著者はこう述べます。
「右脳と左脳とのコミュニケーションは異なっている。左脳は言語というメディアを使い、右脳はイメージというメディアを使う。そして、その違いは、単に言語がイメージかという違いではなく、じつは対象との距離感覚の違いでもあるのだ。左脳が対象を分析しようとするとき、そこには分析する『私』と分析される対象との間の距離が必要だ。対象から離れていないと、ものごとの差は見えてこない。それがいわゆるデカルト的な『主客の分離』だ。しかし、右脳の世界の捉え方はまったく違う。ものごとの本質を直観するためには、対象との距離がなくならないといけないのだ」
続けて、著者は「その対象と同一化し、どこまでが私でどこまでが対象かわからなくなり、そのふたつが一体となったときにはじめて右脳的なコミュニケーションが可能になるのである。そして、その状態ではじめてイメージが成立するのである。悪魔祓いのとき、患者は悪魔に憑依され、悪魔になりきる。それがイメージ化の極限であり、そのときには主体と客体の区別はなくなってしまう。つまり、イメージとは『世界とのつながり』に基づいたメディアなのである。そして、イメージと言うときに問題になるのは、それがどんなイメージか、と言う以前に、世界とイメージする人との間の渾然一体となったつながりの関係なのだ」と述べています。
また、著者はコスモロジーについて、「いままでの文化人類学者はコスモロジーのことを宇宙「観」と言い、あたかも人々の宇宙の見方、知識というふうに考えてきた。けれど、それは宇宙に関する知識ではない。コスモロジーを持つというのは、知識を持っているのではなく、宇宙と私が特殊な関係のもとにあるということなのだ。つまり、ブッダという名前を聞くだけで思わず畏敬の念が湧き起こって手を合わせてしまう。ブッダのイメージで体内の免疫力が向上し、いきいきしてくる。そして、孤独を病むと悪魔のイメージが呼び起こされてくる。神話的宇宙のイメージはわれわれの身体のエネルギーと不可分に結びついている。そんな神話的宇宙と身体の抜き差しならぬ関係こそがコスモロジーを持つということなのである」と述べます。
さらに著者は、以下のように述べるのでした。
「ぼくたちはふたつのまったく異なる世界を持っているということになる。それは、いままで『俗なる世界』と『聖なる世界』と呼ばれてきたふたつの世界だ。俗なる世界、それは左脳的なコミュニケーションの世界である。そこではすべてがものとして存在している。ものとものとの間は明確に区切られ、われわれはそれらの差を分析し、ひとつひとつが別のものだと認識している。しかし、その『俗なる世界』の向こう側には『聖なる世界』が隠されている。それは右脳的コミュニケーションの世界だ。そこではすべてがエネルギーの渦巻きとして存在している。そしてひとつひとつの渦巻きは他の渦巻きとのエネルギーの交流で成り立っている」
さらに「霊は存在するのか」として、著者は「霊は存在する。それはイメージによって結びあわされ、あらわれでるエネルギーとして存在するのだ。しかし、忘れてはならないのは、そのエネルギーはそれ自体独立して存在しているのではないということだ。それはあくまでも結びあった関係性の中で存在しているのである。それは『聖なる世界』における右脳的コミュニケーションの中に存在していると言ってもいい。つまり、霊とはものではなく、『霊的関係』が結ばれたときにはじめてそこに立ちあらわれてくるエネルギーなのである」と述べます。霊はそれだけでは存在し得えず、対象と渾然一体となった霊的関係の中ではじめて霊が見えてくるというのです。それは自分が霊的状態になってはじめて、霊のエネルギーが感知されるということでもあります。
また、「悪魔遊び――悪魔との和解」として、著者は「悪魔祓いとサイモントン療法の関連を論じながら、ぼくにはいつも引っかかっていた一点があった。そのふたつは驚くほどよく似ている。しかし、明らかに異なる一点がある。それは、サイモントン療法の癌と悪魔祓いの悪魔の性格だ。どちらも患者の体から出ていくべき存在だけれども、そのふたつに対する見方は根本のところでまったく異なっている。サイモントン療法における癌は明らかに敵である。その敵は徹底的に攻撃し、殺戮し、滅ぼさなければならない。しかし、悪魔祓いの悪魔はそうではない。儀礼の最後で患者は悪魔と笑いあう。そして悪魔は殺されるのではなく、笑いながら去っていくのだ。そのふたつのイメージ療法はそのプロセスこそが同じだが、違う世界観の上に成り立っているのである。それは西洋のキリスト教文化の中の悪魔祓いと、東洋の悪魔祓いの違いであると言ってもいい」と述べています。
この儀礼はむしろ悪魔と出会い、悪魔と親しむ席なのである。そして、悪魔の存在を受容してあげるからこそ、悪魔もはじめて心を開くのだ。そのように断言する著者は、最後に「悪魔祓い、それは患者と悪魔が互いの存在を受容しあい、ともに心を開きあうことで、互いが敵として存在するのではなく、味方同士なのだということを確認する和解の場なのだ。それは、患者と悪魔の癒しあいであると言ってもいい。悪魔も自分の存在を認めてもらって癒され、患者はNOとして見えていた世界がじつはYESの世界であったことを知る。そして両者はともに満たされながら別れていくのである」と述べるのでした。
わたしは一昨年、上智大学グリーフケア研究所の客員教授に就任しました。上智といえば日本におけるカトリックの総本山です。カトリックの文化の中でも、わたしは、エクソシズム(悪魔祓い)に強い関心を抱いています。
なぜ、わたしが悪魔祓いなどに強い関心を抱いたのかというと、エクソシズムとグリーフケアの間には多くの共通点があると考えているからです。エクソシズムは憑依された人間から「魔」を除去することですが、グリーフケアは悲嘆の淵にある人間から「悲」を除去すること。両者とも非常に似た構造を持つ儀式といえるのです。本書を読んでその考え方との強い共通性を感じました。