- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.07.02
『ともに悲嘆を生きる』島薗進著(朝日新聞出版)を読みました。「グリーフケアの歴史と文化」というサブタイトルがついています。著者は日本を代表する宗教学者です。1948年、東京都生まれ。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業。主な研究領域は近代日本宗教史、死生学。東京大学名誉教授。現在、上智大学大学院実践宗教学研究科教授、同グリーフケア研究所所長。わたしは同研究所の客員教授を務めている御縁で、著者から本書を献本していただきました。
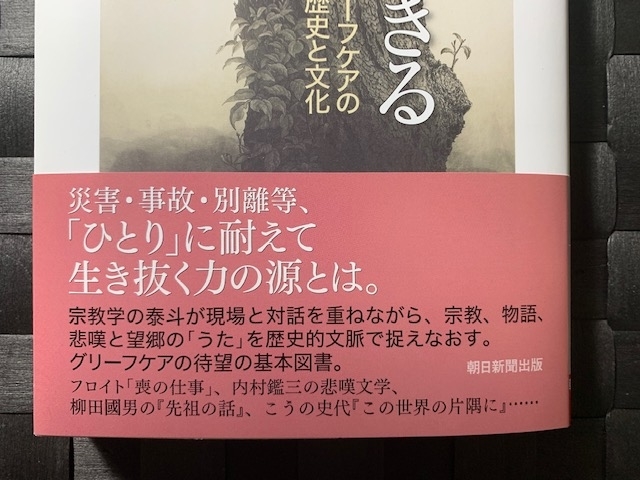 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には木の根に止まる小鳥を描い武田史子氏の絵が使われ、帯には以下のように書かれています。
「災害・事故・別離等、『ひとり』に耐えて生き抜く力の源とは。」「宗教学の泰斗が現場と対話を重ねながら、宗教、物語、悲嘆と望郷の『うた』を歴史的文脈で捉えなおす。グリーフケアの待望の基本図書。」「フロイト『喪の仕事』、内村鑑三の悲嘆文学、柳田國男の『先祖の話』、こうの史代『この世界の片隅に』……」
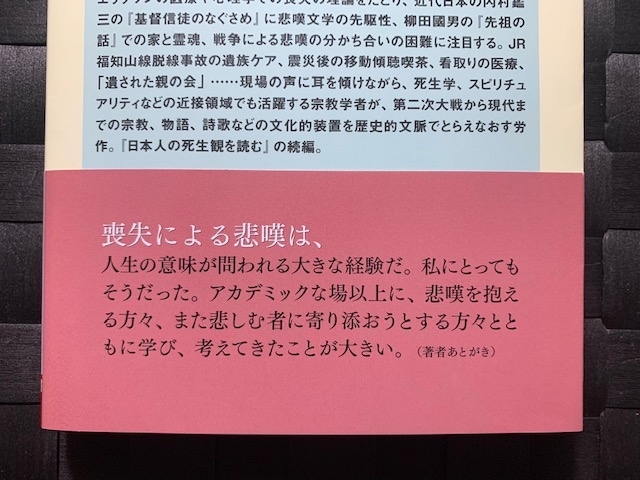 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には「喪失による悲嘆は、人生の意味が問われる大きな経験だ。私にとってもそうだった。アカデミックな場以上に、悲嘆を抱える方々、また悲しむ者に寄り添おうとする方々とともに学び、考えてきたことが大きい。(著者あとがき)」と書かれています。
さらにカバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「超高齢社会で大切な人を喪失する悲嘆は身近である。災害や事故による非業の死に向き合ってきた日本人。現代の孤独な個々人は、どのように生きる力をよびさますグリーフワークを行えばよいのか。フロイト、ボウルビィ、エリクソンの医療や心理学での喪失の理論をたどり、近代日本の内村鑑三の『基督信徒のなぐさめ』に悲嘆文学の先駆性、柳田國男の『先祖の話』での家と霊魂、戦争による悲嘆の分かち合いの困難に注目する。JR福知山線脱線事故の遺族ケア、震災後の移動傾聴喫茶、看取りの医療、『遺された親の会』……現場の声に耳を傾けながら、死生学、スピリチュアリティなどの近接領域でも活躍する宗教学者が、第二次大戦から現代までの宗教、物語、詩歌などの文化的装置を歴史的文脈でとらえなおす労作。『日本人の死生観を読む』の続編」
この最後に書かれているように、本書は一条真也の読書館『日本人の死生観を読む』で紹介した本の続編です。この本は大変な名著で、わたしは数えきれないほど読みました。拙著『死が怖くなくなる読書』(現代書林)の中でも取り上げています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章
第1章 悲嘆が身近になる時代
第2章 グリーフケアと宗教の役割
第3章 グリーフケアが知られるようになるまで
第4章 グリーフケアが身近に感じられるわけ
第5章 悲嘆を物語る文学
第6章 悲しみを分かち合う「うた」
第7章 戦争による悲嘆を分かち合う困難
第8章 悲嘆を分かち合う形の変容
「あとがき」
「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「愛する人との死別は悲しくつらい。子どもに先立たれた親の気持ちはとても察し切れるものではない。配偶者・パートナーの死も耐えきれないほどに感じられることもあるだろう。災害や事故・事件などの非業の死も、遺された者の思いは想像にあまりある。このような悲嘆はけっして新しいものではない。長寿が期待できなかった時代には、むしろ珍しくはないよく耳にする経験だったようにも思える」
著者は哲学者の西田幾多郎の「我が子の死」という文章を紹介し、以下のように述べています。
「日露戦争でただ1人の弟が戦死したが、1907年には西田は数え年6歳の二女と生まれたばかりの五女をあいついで喪っている。そして1920年には長男と、25年には妻と死別している。西田哲学は宗教的な基盤をもっているが、それはこうした死別の経験、悲嘆の経験(西田自身は「悲哀」とよぶ)と深く関わっていると捉えられてきている」
西田が「我が子の死」を発表した頃、日本では個人の悲嘆が文字で表現され多くの人に分かちもたれることはあまりなく、また、悲嘆が身近な者以外の者によるケアの対象と考えられることもありませんでした。著者は述べます。
「その時代からおよそ120年が経過した。この間に悲嘆を分かちもつあり方、分かち合うあり方に大きな変化があった。そして、多くの人たちは自覚的に悲嘆を経験すること、グリーフケアを受けること、あるいはグリーフケアに学ぶことが意義深いと感じるようになった」
死別や深刻な喪失の物語を聞く機会は増えており、悲嘆のために社会的な適応が妨げられるような事例も目立つようになっています。著者は「なぜ、そうなのか。この事態にどう向き合うのか」と問い、「悲嘆を分かち合うよき場、またよい関係が求められている。そして、そこでは『ともに生きる』力の源が探られている。宗教やスピリチュアリティが深い関わりをもつのもその故だろう」と述べるのでした。
序章では、一条真也の新ハートフル・ブログ「この世界の片隅に」で紹介した2016年の日本のアニメ映画、「おみおくりの作法」で紹介した2015年のイギリスとイタリアの協力によるウベルト・パゾリーニ監督の映画などを取り上げつつ、著者は悲嘆の文化の形を示します。そして「グリーフケアの歴史と悲嘆の文化」として、以下のように述べます。
「グリーフケアにあたるものは、これまでどのように行われてきたのだろうか。死別や喪失に伴う儀礼が重要な役割を担っていたことはまちがいがない。ともに悲嘆を生きるために、人々はさまざまな文化装置を作り、伝え、再創造してきた。宗教が重要であることは確かだが、加えてさまざまな物語や詩歌や造形物、うたやおどりや芸能等も力になった」
また、著者は「悲嘆が分かち合われる場・関係」として、以下のように述べます。
「グリーフケアとは何かを考えながら、悲嘆の文化の歴史を問い、悲嘆が分かち合われる場や関係に注目する。これが本書の主眼とするところだ。確かにグリーフケアが目指すのは、個々人が自らの悲嘆を奥深く経験していけるようにすることだろう。それは孤独な心の中の事柄として捉えることができる。しかし、そうした個人の内面の変化が生成してくるためには、よい交わりの場やよい関係が形成される必要がある。そしてそれは、カウンセリングのような一対一の関わりだけではない。遺族会や自助グループはそのよい例である」
続けて、著者は以下のように述べるのでした。
「よい交わりの場やよい関係が重要なのは、『ともに悲嘆を生きる』ことが人間の本来的なあり方に根ざしているからである。そのことをよく認識することによって、スキルやノウハウに還元されない、グリーフケアのより多面的な理解が可能になるだろう。また、私たちが継承してきた文化的資源を新たに活用していく道筋も見えてくるだろう」
第1章「悲嘆が身近になる時代」では、その冒頭を「グリーフケアの興隆」として、著者はこう書きだしています。
「グリーフケアという言葉が知られ、広まってきたのは2000年代に入ってからのことである。私が所長を務める上智大学のグリーフケア研究所は、後で詳しく述べるように、もともと2009年に聖トマス大学に設置されたが、聖トマス大学の事情もあって2010年に上智大学に移されたものだ。この設立に際しては、2005年のJR福知山線(宝塚線)の事故で多くの犠牲者を出したJR西日本の意向が大きく反映している。だが、このわずかな期間に、世間のグリーフケアの認知度はだいぶ高まったように思う」
続けて、グリーフケアの歴史を述べようとすると、精神医学や心理学の古典に出会うとして、著者は、ジークムント・フロイト(1856-1939)の「悲哀(Trauer、喪)とメランコリー」(1917年)という論文を紹介します。わたしも一条真也の読書館『人はなぜ戦争をするのか』の中でこの論文に言及しましたが、著者は以下のように述べています。
「これはヨーロッパで多くの死者が出た第一次世界大戦と関わりがあるかもしれない。とはいえ、その時期にグリーフケアが急速に普及したというわけではない。その後、50年の間に理論的には大いに発展し、精神医学や心理学の領域では認知度を増してきてはいた。第二次世界大戦、ユダヤ人大虐殺、原爆投下、朝鮮戦争、ベトナム戦争と戦乱が続き、20世紀には理不尽な死を経験する人々が膨大な数に上った。にもかかわらず、一般社会はグリーフケアにさほどの関心を向けてはいなかった」
続けて、著者は以下のように述べています。
「1967年にイギリスでシシリー・ソンダースが聖クリストファー・ホスピスを開設し、以後、ホスピス運動が世界に広がっていく。医療の周辺に位置すると同時に、宗教とも相接するスピリチュアルケアの領域に注目が集まった。それはまた、死生学(death studies,thanatology)とよばれるような学術研究分野、また生と死の教育(death education、いのちの教育、死の準備教育)といった教育分野の拡充をももたらした。こうした動きのなかで、『死別の悲しみ』という主題が次第に大きな位置を占めるようになってくる」
日本語には「悼む」という言葉があります。
「『悼む』とは何か?」として、著者は述べます。
「毎年、8月6日、9日、15日には多くの人が黙祷する。あるいは手を合わせる。では、そのことをどういう言葉で表せばよいのか。神仏や霊の存在を信じているなら『祈る』『念ずる』だが、苦難を負った人、亡くなった人のことを思いながら、神仏に思いが及ぶとは限らない。では、何に向かって『手を合わせて』いるのだろうか」
続けて、著者は「悼む」について述べます。
「昨今、私たちは『悼む』という言葉の意味を見直しているようだ。悼む相手は亡くなった人であって神仏ではない。神仏ではないが手を合わせるのは、そこに尊い何かがあるからだ。それを『死者の霊』とか『みたま』とよぶ人もいる。だが、『霊』とか『たま』『たましい』は実感がわかないという人もいる。ならば、『死者を悼む』で差支えない。そこに尊いものがある」
著者は、一条真也の新ハートフル・ブログ「悼む人」で紹介した2015年公開の日本映画も紹介します。この映画の主人公、坂築静人がものに憑かれたように続ける「悼む」行為が日本人にとっては見慣れたものであるとして、著者はこう述べます。
「無惨な死をとげたり、見捨てられて死んでいったり、無念な思いを残して死んでいった人を慰霊・追悼するのは、日本人にとってなじみ深い行為だ。政敵に追われ無念の死をとげた人物が祟り、後に御霊として祀られ救いの神になるという御霊信仰は、天神信仰を始めとして少なくない。
戦争の死者は敵味方を問わず供養するが、それは祟るのを恐れる気持ちも入っている。『怨親平等』とは、敵・味方の差別なく、恩讐を超えて平等に解脱や極楽往生を願うという仏教の思想だが、それは殺された者の恨みを前に供養せざるをえない思いに支えられている。13世紀に襲来した蒙古人兵士を慰霊する施設も各地にある」
続けて、著者は以下のように述べています。
「墓地に行けば、古くて置き場のない墓石が積み上げられていて、無縁仏を表すものになっている。ゴミソ、カミサマ、ユタ、稲荷行者などとよばれる各地のシャーマンは、不幸な死をとげた霊を慰める儀礼を行い、それによって生者が平穏に暮らせることを願う。近代の法華系の仏教団体では、先祖供養に力を入れるが、その『先祖』には祀られていない人びとが包摂され、『三界万霊』への供養という性格も込められている。1970年頃から広まった水子供養は、現代における怨霊供養の新たな様式と言えるだろう。第二次世界大戦で亡くなった方への慰霊や供養は現代日本の宗教文化の大きな一部をなしている」
また、著者は「公認されない悲嘆」として、グリーフケアの領域では「人知れず悼み弔う人たち」のことが注目され、「公認されない悲嘆」(disenfranchised grief)という言葉が用いられるようになったと紹介します。著者は以下のように述べます。
「1989年にケネス・ドーカが提示したもので(概要は、坂口幸弘『悲嘆学入門――死別の悲しみを学ぶ』5-6頁)、社会的に正当性が認められていない悲嘆を指す。たとえば、隠れた家族(同性愛カップルの相手)や恋人(不倫の相手)や友人の死、中絶や流産、幼い子どもの死、自殺やエイズ患者の死などに見舞われた場合だ。『公認されない悲嘆』は自らの胸の内にしまわれてしまい、他者と分かち合う機会がない、あるいは乏しい。そのことが生き残った者を孤立させ、悲嘆を厳しく、癒しの得られぬものにしてしまう。喪失による打撃から抜け出しにくい悲嘆を「複雑性悲嘆」と名づけて通常の悲嘆と区別することもあるが、『公認されない悲嘆』は『複雑性悲嘆』になりやすい傾向がある」
さらに、「悲嘆を分かち合う場と関係を求めて」として、著者はこう述べています。
「悲嘆のさなかにいる人々は、かつては家族・親族、あるいは地域社会といった共同性のなかにいた。重い喪失を経験する人々は『悲嘆をともに生きる』人々の実在を感じ取りながら、寂しさつらさを経過することが多かった。多くの人々は成長の過程で、悲嘆を抱える人々とともに悲嘆を分かち合う行事に参加し、それを見守る経験をもっていた。だが、現代社会ではそのような共同性が乏しくなっている。あるいは薄くはかないものになっている。そこで、他者が支援するなかで、悲嘆を分かち合う場や関係が求められるようになった。2011年の東日本大震災はそのことをわかりやすく示す機会となった。1995年の阪神・淡路大震災では、精神科医や臨床心理士による『心のケア』が注目された。しかし、その背後では、ボランティアによる寄り添いの支援活動が広がりつつあった」
グリーフケアが目指すものは何か。著者は述べます。
「個々人の悲嘆についての精神医学的・心理学的なケアであるとともに、こうした新たな場や関係の構築でもある。日本社会はますます孤立化が進む。高齢者だけではない。引きこもりの人、虐待される子ども、家庭を温かい環境にできない親たち、自殺を考える人たち、うつに苦しむ人たち等、共感し合う関係を求めて得られない人々が多い。悲嘆に苦しむ者と寄り添って他者を支えたいと思う人が重なり合っている。そこに生じる場や関係は、効率性や対価提供にしばられるふだんの社会生活では排除されがちなものである。グリーフケアはこのような社会のあり方を問い直す動きでもある」
第2章「グリーフケアと宗教の役割」では、「災害支援と仏教僧侶の活動」として、著者は以下のように述べています。
「1995年の阪神・淡路大震災の被災者支援では、『心のケア』という言葉がさかんに使われた。だが、『グリーフケア』という言葉を耳にした人はあまりいなかったはずだ。この時はまた、仏教界の支援活動が注目される機会も少なかった。『心のケア』というと精神科医や臨床心理士が思い浮かべられる。これに対して、『グリーフケア』というと宗教が関わるものというニュアンスが強まる。2005年のJR福知山線(宝塚線)の脱線事故では『グリーフケア』が注目されるようになっていた」
「死者を悼み生者に寄り添う」として、著者は述べます。
「若手僧侶がグリーフケアに携わる。東日本大震災ではそれが目立った活動となった。では、これは伝統仏教の僧侶にとってまったく新しい宗教活動の取り組みだったのだろうか。檀家制度のなかでは自覚されにくかったのかもしれないが、僧侶の葬祭への関わりは死者を悼み遺された人の悲しみに寄り添う慈悲の行としての側面が大きい」
また、著者は「悲嘆に寄り添う仏教の実践」として、「葬祭が仏教にとって本来的な営みであることを東日本大震災はよく思い出させてくれた。死者を、とりわけ親しい死者を前にし、また死別の悲しみに打ちのめされている人を前にするとき、多くの日本人は仏の慈悲を身近に感じるのだ」とも述べています。
また、「震災支援と平常の葬儀の共通項」として、著者は以下のように述べています。「東京で『人の苦に寄り添う』活動をしている『ひとさじの会』の若い僧侶たち、東日本大震災で死者を悼み、死別の悲しみに暮れる人たちを受けいれる僧侶たちは、日本中世に死の穢れを超えて死者を弔った僧侶たちの精神を引き継いでいる。そして、その精神は大乗仏教の根本に通じる何かでもあるだろう。『無縁社会』といわれる現代社会の困難、また東日本大震災を通してあらためて自覚した人間の弱さやいのちのはかなさ――つまりは人間の苦の現実によって、日本人は何ほどか仏教を身近なものに感じるようになっているのではないだろうか」
このあたりは、東日本大震災について書いた拙著『のこされたあなたへ』(佼成出版社)でも詳しく述べました。
さらに、著者は「震災で見えてきた伝統仏教の力」として、東日本大震災では日本仏教の力が見直されたと指摘し、苦難の中にある人々に手を差し伸べ、折れそうな心を支え沈みそうな心をすくい上げる働きが目立ったと評価します。
ここで、著者は「葬式仏教」についてこう述べています。
「『葬式仏教』という語は1960年代初めに使われるようになったもので、そんな伝統仏教への苛立ちが含まれていた。折しも新宗教は大発展期で、在家仏教を唱える霊友会、立正佼成会、創価学会などが急成長をとげていた。菩薩行としての苦の現場での助け合いは、これら新宗教教団においてきわめて活発になされていたが、伝統仏教教団の寺院は人々とふれる場が葬祭に特化して、いのちの通わないものになっている、そう感じられるようになった」
しかし、震災後の苦の現場に赴いて人々を支える伝統仏教の僧侶の働きは目を見張るものがあったと述べるのでした。
東日本大震災で仏教者や寺院が大きな役割を果たすようになる背景には、仏教が看取りの医療に関わっていく動きがありました。それはまた、宗教側の支援を求める医療側の姿勢の変化とも関わっているといいます。
ここで著者は、岡部健医師(1950-2013)が重要性を訴え続けた在宅の看取りについて言及します。在宅の看取りをよりよいものにするために、岡部医師が行ったことの1つは、共同で利用できるくつろぎのスペースを作るということでした。それも屋内ではなく、5000坪の森を安く買って、そこに小屋を建て、露天風呂を作り、調理場を作り、ピザ窯も買って、いわゆる「岡部村」を作り上げました。春には、「花見の会」、秋は「芋煮の会」を開き患者さんを招待します。著者は「患者さんにとってはあきらめていた希望の灯がともることになる。家族には大切な思い出の場ともなるだろう」と述べています。
岡部医師といえば、死の間際に今は亡き近親者がお迎えにくるという「お迎え現象」の研究で知られます。これについて、著者はこう述べています。
「『お迎え現象』が宗教と関わりが深いことは言うまでもない。『お迎え現象』に接することで、看取りに関わる医療者は宗教者の関与が欠かせないと感じることになる。岡部医師もそうだった。もとあと宗教に関心が深かった岡部医師だが、「お迎え」に関わる話をたくさん聞くようになって、ますます穏やかに死に、安らかに死者を送る上で、宗教が重要だとの思いを強めていった。
在宅の看取りに集中するようになって以後、岡部医師は「お迎え」を経験する患者の言葉に注目してリサーチもしてきました。在宅で世を去った682人の患者の家族にスタッフが行ったアンケート調査(回収数366)では、「お迎え」体験があったとの答えが42・3%に達したといいます。
岡部医師は「あの世があろうとなかろうと……あの世とつながった感覚」をもつことや「宗教側の知恵の蓄積をちゃんと受けとめる」ことの意義を問うてきたのです。つまり「宗教文化が伝えてきたことを現代的に引き継いでいくことを求めているのだ」と著者は述べています。
第3章「グリーフケアが知られるようになるまで」では、著者は「フロイトと『喪の仕事』」として、前述の「喪とメランコリー」を紹介し、以下のように述べています。「『喪』というのが外的な形にとどまらず、内面、つまり心の内側でも何かを行っているとすれば、それは何か。フロイトはそれを『喪の仕事』とよんだ。英語の『グリーフ』や『モーニング』にあたるドイツ語は『トラウエル Trauer』、『喪の仕事』にあたるドイツ語は『Trauerarbeit』だ。『喪の仕事』は『悲哀の仕事』『悲嘆の仕事』とも言える。英語に直すと『グリーフワーク』となる。さまざまな喪失に伴う悲嘆の仕事のうち、とくに死別による喪失の後のものが『喪の仕事』とも言える。大切な人を亡くした人は、その人に向けられた自分の心のエネルギーを捉え返しながら、その喪失を受け入れていく」
また著者は、「心にとっては『いる』が、現実には『いない』」として、以下のように述べています。
「愛の対象が失われる、自分が大事にしている世界が失われるというときに、死んだ人はいなくなるのだろうかと考えてもいいだろう。死んだ人は、残された人にとっては、ある意味ではたいへんリアルに存在している。死者は遺された者に語りかけてくるように思うし、自分の気持ちがそこへいつも向かっていく。死んだ人はいないとはなかなか言えない。でも、その人がこちらに働きかけてくることはない。心にとっては『いる』にもかかわらず、現実には『いない』ということが対象喪失ということの意味だ。そこで、現実には『いない』が心の中に今も『いる』他者との関わりが問い直される。だから、心の作業が続くのだ」
人が亡くなると、「ああ、あの人がいないなあ」とつくづく寂しくなりますが、夢の中とか、また物語の中では死んでいる人は語りかけてきます。著者は、「これは喪失された対象が新たな形で場所を得ようとする心の仕事の現れと見ることもできる。これは『モーニングワーク』や『グリーフワーク』、つまりは心のなかの『喪の仕事』、『悲しみの仕事』によって死者が新たな形で寄り添ってくれる存在に転形したものといえる」と述べています。
「葛藤を自覚し成熟していく過程」として、著者は「喪の仕事にはもっと苦しいものもある。大切な人が亡くなったことについて、自らに責任があるように感じてしまうことは少なくない」と述べ、さらに「そこには自分が愛する人に対してもっていた疎ましい思いの自覚も含まれている。愛の対象に対して、同時に憎しみや敵意がこもっているという洞察は『アンビヴァレンツ』(両価性)という言葉で表される。父に対して愛とともに愛を妨げる力の主として、ひそかに敵意をもつ。これがエディプス・コンプレックスだが、大切な他者の死によって、その対象に対して自らがもっていた敵意を直視し自らを責める気持ちが押し寄せてくる。心の内の葛藤を新たな愛へと昇華していけるかどうかが喪の仕事の課題でもある」と述べています。
さらに著者は、以下のようにも述べています。
「悲しむことは悪い反応ではない。喪われた尊いものを抱き直す『仕事』なのだ。その意味では、むしろよりよく生きていくために不可欠の『仕事』だ。悲しみを省いてしまうことは、心のなかの大切なものを切って捨てるようなことだろう。悲しみという心の仕事を時間をかけて行うことが成熟につながり、それまでにもまして奥深い生きがいを見出していくことに通じる」
著者は、フロイト自身の喪の仕事にも言及し、「子どもの愛着と喪失」として、以下のように述べます。
「フロイトの喪の仕事の理論はその後のグリーフケアの理論の基盤を作ったものだが、そこには大きな限界もあった。背後には自らの父の死後のグリーフの経験があり、父に対する息子の敵意といったモデルに大きく影響されている。フロイト以後のグリーフ(悲嘆)の研究では、もっと多様な喪失の経験に即して考察が進んでいく。父子関係と並んで母子関係が重要であることは、フロイト以後の発達心理の研究の1つの焦点だった。悲嘆と母親への愛着との関係についてはジョン・ボウルビィの研究がよく知られている」
自身も精神分析医であり児童心理の専門家であったボウルビィは、動物行動学の成果などを組み込みながら、小さな子供が大事なものを失ったときの反応について考察を進めました。著者は述べます。
「親がいなくなった子どもはどうするだろうか。これを身近で経験した人は少ないだろう。私は自分の家で飼っていた犬のことを思い出してみる。生まれてしばらくして我が家に連れてこられたその犬は、最初にくるまれていた布を一生大事にしていた。口にくわえて振り回したり、その布があると元気でいろいろなことをやる。けれども死ぬまでそれから離れなかった。ペットの多くは大きな喪失を経験して、飼い主のもとに来ているのだ。このような事例からも、悲嘆の原型を母親から切り離された子どもの反応に求めるのはもっともなアプローチであることが理解できるだろう」
さらには、「アイデンティティと悲嘆」として、著者は以下のように述べるのでした。「ボウルビィら発達心理学の専門家たちは、たくさんの子どもの反応を見ながら、愛着の対象の喪失と成長について考えた。フロイト以後の精神分析で次第に強調されていくことだが、人が育っていく際に、最初に母の愛に包まれていた経験がいかに大きな恵みであるか。エリック・エリクソンの言葉では、世界に対し、また生きていくことに対して『基本的信頼』をもつことがその後の成長を支える糧となる。それはまた、いのちの恵みの源への感受性を育むことでもある。日本人にとってのいのちの源、それは母でもあるが、また家族や地域の人々の愛でもあり、故郷の自然でもある。悲嘆とともに生きていくことは、いのちの源の感覚をもつことでもある。そう感じる人が少なくない」
第4章「グリーフケアが身近に感じられるわけ」では、ブログ『死と悲しみの社会学』で紹介したジェフリー・ゴーラーの名著が取り上げられます。グリーフケアが登場してくる前に「悲しみを分かち合う文化の後退」があったのではないかという問題について1960年代に正面から問うた書物です。「悲しみを分かち合う儀礼の後退」として、著者は以下のように述べています。
「ゴーラーは20世紀のふたつの大戦を経る間に、喪の儀礼が急速に失われていったと捉えている。その要因の1つとして、戦死者の妻たちへの配慮があったのではないかという。彼女たちが長い期間、喪に服しているよりも、新しい人生に向かっていくことを認めようとする考え方が作用したのではないかと推測している。(中略)当時のイギリスで医療関係者や知的な思考を重視する人々は、死に関わる儀礼を軽視し、結果的に死を隠すような文化傾向を後押しすることになっていったと捉えられている」
「悲しみを分かち合おうとする態度」として、著者は「なぜ悲しみを分かち合おうとする態度がこれほどまでに重要なのか」と問いかけ、以下のように述べています。
「悲嘆のさなかにいる人は、言わば悲嘆に閉じ込められ孤立している。悲嘆のさなかにいる人を『そっとしておいてあげよう』と思うのももっともなところがある。喪を過ごしている人は一人でいることを必要としていると感じられる。私には何もできることはないと、腫物にさわるような感じで引き下がるのが穏当と思う。だが、それは悲嘆の経験の一面だ。死者と孤独にやりとりをするような時を過ごしながら、悲嘆とともに生きる姿勢になっていく。その過程は長く続くがそこでは悲嘆を分かち合い、心の中の死者を他者とともに悼み、ともに悲嘆を生きる方向へと歩みだしていくことが必要なのだ」
これは、拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)で訴えたメッセージに通じます。
また、「グリーフケアが求められるようになるまで」として、著者は以下のように述べます。
「なぜ悲嘆への理解やグリーフケアの理解が20世紀の末から21世紀の初めにかけて急速に進展したのか、ということである。私の考えでは、それは悲しみを分かち合うことが容易でなくなってきたことと関わりがある。後に少し詳しく述べるが、かつては悲しみを分かち合う共同体があり、悲しみを分かち合う文化があった。たとえば、死者を弔うさまざまな儀礼があり、行事があった。だが、そうした集団で広く共有される悲嘆を分かち合う形が後退してきたという事実がある。たとえば通夜や葬儀、あるいは法事などが死者の追悼の集いとしての力を失ってきている」
このあたりは、『儀式論』(弘文堂)を書き、日々、葬送儀礼に取り組んでいるわたしの最大のテーマですので、儀礼および儀式の力を回復する方策を考え続けています。
続けて、著者は以下のようにも述べています。
「20世紀の末頃から、そうした近代的な悲嘆の文化も後退していくようになった。グリーフケアはそうした背景のもとに生じてきている。当初、悲嘆は病理として扱われた。そこでは悲嘆がない方がQOL(Quality of Life 生活の質)が高いとするような理解が生じがちである。しかし、心の豊かさということからすれば、それはむしろ逆である。悲嘆が継続すること、重大な喪失の経験を忘れないことは、むしろ心の豊かさを養うことにもなる。このような逆説的な事態が人間には起こる。QOLの数値的評価をするような場合には注意すべき事柄である」
わたしは「心の豊かさ」を形容するキーワードとして「ハートフル」という言葉を考案し、使い続けてきましたが、この「ハートフル」と「グリーフケア」が結びつくということを再認識しました。わたしはいま、拙著『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の増補改訂版として『ハートフル・ソサエティ2020』という本を書いていますが、同書の中では「グリーフケア」にも大いに言及するつもりです。
また、「死生学とホスピス運動(死の臨床)」として、著者は以下のように述べています。
「1960年代から現代社会で周辺化されがちな『死』をあらためて主題化する動きが起こってくる。ホスピス運動やそれと結びついて展開した死生学(death studies)の動向だ。医療現場はこうした動きの中心だった。科学的合理主義に権威を求めがちな現代の生物学的医療だが、そこでは死にゆく人間にどう対処するかに関わる方法が欠けていた。1967年、シシリー・ソンダースは、治療するためではなく死にゆく人をケアするための聖クリストファー・ホスピスを設立した。また、エリザベス・キュブラー・ロスは1969年、死にゆく人の心の動きを描き出す『死ぬ瞬間』を公表した。こうした『死の臨床』の新たな動向は、死をめぐる学知や思想を大きく展開させていくことになる。これが死生学の動きだ」
続けて、著者はグリーフケアに言及し、こう述べます。
「グリーフケアもまた、この『死の臨床』や死生学の動きに大きな影響を受ける。『死の臨床』や死生学においては『スピリチュアルケア』や『スピリチュアリティ』が中心的な主題の1つとなる。死に向き合うことは、生きる意味を問い直すことや死の不安や恐怖に耐える何かを求めることを含む。生きている意味が見失われ絶望に沈むような、スピリチュアル・ペインの経験に寄り添うようなケアが求められることにもなる。深刻な死別や喪失の経験も、生きる力を見失いそうなスピリチュアル・ペインをもたらすことがある。そもそも人生で痛切な喪失を経験することは『小さな死』を経験することだと解することもできる。死を迎えるときの寂しさは、死別の悲嘆の究極の形と捉えてもよいだろう」
また、「グリーフケアと文化」として、著者は述べます。
「実際的なグリーフケアの活動としても、たとえば東日本大震災後の寄り添いや傾聴活動について、グリーフケアという観点から学び考える姿勢が目立つ。また、この20年ほどの間に、自死遺族、子どもをなくした親たちの集い、がんサバイバーの集い、事故・事件の被害者の集い、さまざまな機縁による遺族会など、悲嘆や喪失をめぐる多様で自助的な集いが形成されてきている。グリーフケアの専門家がクライアントを癒す事柄としてではなく、お互いに悲嘆を経験する人々が他者を支え合うための何かとして学ばれるようになってきている。こうしたグリーフケアの実践や知識は、今、急速に発展する途上にあると言えるだろう。そこで大きな課題の1つとして浮上しているのが、死別や悲嘆をめぐる文化の違い、また文化の意義をどう捉えるかという問題である」
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「伝統的な葬儀や死者儀礼になじみにくいと感じる人は増えてきているだろう。だが、死者への追憶や、無常を嘆き死別の悲嘆を表現する伝統文化に対する親しみはさほど失われていないようにも思える。東日本大震災後には、鴨長明の『方丈記』がしばしば思い起こされ、宮澤賢治の詩歌や物語が読み返されもした。どちらも日本の仏教の伝統と深い関わりがある。他方、死者の霊と交流する民俗宗教的な伝統も話題に上る機会が多い。柳田國男が失われていく日本固有の宗教文化を考えて、記録に残そうとしてきたような死者との交わりの感覚が、新たにその意義を問い直されてもいる。現代においてグリーフケアに取り組む際、グリーフをめぐる文化の違いや、多様な悲嘆の文化を継承してきた人類社会の遺産について考えることも重要な課題の1つとなっている。グリーフケアは多くの課題をもつ豊かな学知と実践の領域に展開する途上にある」
第5章「悲嘆を物語る文学」では、その冒頭を、著者はこのように書きだしています。
「かつて人は喪の共同性を通して悲嘆から癒されていった。社会は悲嘆を抱える人を遇する儀礼や行事や生活様式をもっていて、死別による痛みを負った人々はそれらを経過することで、日常生活にもどっていくための力を回復していった。そうした共同生活に埋め込まれた儀礼や行事や生活様式を『喪』というが、今では喪の共同性は残っているとしても簡略化され、実質の薄いものになってきている。喪服や喪中の葉書は残っているが、喪に服している人を気にかける人は少ない。喪に服していることを門や玄関前に表示している家は少ない。葬儀や法事も簡略化し、新盆の行事といっても知らない人が多いだろう」
続けて、著者は以下のように述べています。
「このような『共同体的な喪の後退』を補うかのように、悲嘆を分かち合う場が広がってきている。『喪の後退』も長い時間を経て進んできていると思うが、悲嘆を分かち合う多様な様式も長い歴史をもつ。『喪の後退』によって、初めて生じたようなものもあるだろう。グリーフケアの集いはそのようなものの1つだ。だが、手厚い喪が行われていた時代から悲嘆の表出は行われてきた。それが新たな様態をもって展開する例もある。悲嘆の文学というのはこの後者に属する。たとえば、『挽歌』は『万葉集』の時代からある」
本書では「悲嘆の容れ物」として宗教や伝統儀礼について見てきましたが、文学や詩歌もまた「悲嘆の容れ物」としての機能を果たしてきたのです。20世紀の後半には「悲嘆を物語る物語」が数多く創作され、やがて、映画やコミックやアニメにも喪・失と悲嘆のテーマはあふれるようになりました。
第6章「悲しみを分かち合う『うた』」では、「古くなった『故郷』」として、著者は以下のように述べています。
「『悲嘆』と『故郷』、『悲嘆』と『望郷』には深い関わりがある。これは『国民』とよばれるような容易に連帯感をもつ公衆が実感されるようになったことと切り離せない。『故郷』では皆が一体になれる。しかし、今は孤独だ。孤独ではあるが『帰って行く場所』がある。それは生命の源であり、死んで帰ってゆくところでもある。このようなイメージを含んだ『故郷』という言葉が人々の心をつかんだ時代があった。そうした背景のもとで、孤独と悲嘆をかこち、『望郷』の思いを歌う。内村鑑三が若かった頃にはまだなく、高度経済成長以後の時代にも保持しにくくなった心情のあり方だ」
また、「復活した(?)『故郷』」として、著者は以下のようにも述べています。
「上智大学グリーフケア研究所の高木慶子特任所長によると、死が間近な人が枕元で聞きたいと願う曲のなかで、『故郷』は1、2を争うということだ。そういえば、と思って歌詞を見直すと、1番は自らのいのちの源である自然への感謝、2番は親や家族や同郷の人々とのつながりの確認と感謝と読める。そして3番目だが、『志をはたしていつの日にか帰らん』というのは、自分の一生を振り返り、自分の人生の総体を受け入れて、世を去る心を定めていくという意味で受け止めることができる。そして、高木慶子シスターは『いつの日にか帰らん』というのは、母のふところに帰るということかもしれないし、大いなるもののふところに帰るということかもしれない。いずれにしろ、この歌詞を聞きながら安らぎの場に行くと感じ取ることができるのだという」
ちなみに、わたしが編者となった葬儀のエピソード集である『最期のセレモニー』(PHP研究所)でも紹介したように、実際の葬儀の場では「故郷」や「赤とんぼ」といった童謡を流したり、参列者が合唱したりといったことがよくあります。
「赤とんぼと童謡」として、著者はこう述べます。
「童謡というジャンルは、1918年に『赤い鳥』が創刊されて生み出され、1920年代の終わり頃まで次々とヒット曲が生み出された。大正期と昭和初期が主な創作時期である。『上から教える』要素が色濃かった『唱歌』に対して、童謡は子どもたち自身が親しみやすい言葉で、また子どもたち自身がおもしろいと感じるような意味内容が語られていた(周東美材『童謡の近代――メディアの変容と子ども文化』)。唱歌は文語がしばしば混じり、子どもたちには意味がわかりにくい言葉も多いが、童謡では話し言葉に近く、擬態語・擬声語が多用され、言葉あそびも好まれた」
拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の「悲嘆論」で、わたしは童謡詩人の野口雨情について書きました。グリーフケアのことを考えるとき、いつも野口雨情の童謡が心に浮かんできます。わたしは、多くの名作童謡を書いた雨情の大ファンです。特に、「十五夜お月さん」「雨降りお月さん」「証城寺の狸囃子」「うさぎのダンス」など、「月」や 「うさぎ」をテーマにした歌が多く、うさぎ年で月狂いのわたしにはたまりません。また、横浜を舞台にした「赤い靴」と「青い眼の人形」を聴くと、たまらなくセン チメンタルな気分になります。わたしは、野口雨情の童謡には基本的に「グリーフケア」の要素があると考えています。
雨情の童謡作品はどれも、なんだか泣きたくなるような郷愁と哀愁が強く感じられます。それは、その歌の背景に、さまざまな現実のストーリーがあるからです。たとえば、「赤い靴」にはモデルとなった女の子がいましたが、彼女は渡米を果たさ ずに病気で夭折しています。「青い眼の人形」も実話に基づいてつくられた歌です。そして、「シャボン玉」は、雨情が幼くして逝った娘を歌った作品だとされています。「シャボン玉消えた 飛ばずに消えた 生まれてすぐに こわれて消えた」という歌詞は、雨情自身の亡き娘のことでした。彼は、自分の愛娘のはかない命を、すぐ消えてしまうシャボン玉に喩 たとえたのです。そして、雨情夫婦は、この歌によってわ が子を亡くした悲しみを癒したのであった。唱歌として名高い「シャボン玉」とは グリーフケア・ソングだったのです。
その哀しくも透明な美しさを備えたセンチメンタリズムは、東京専門学校(現在 の早稲田大学)で雨情の学友であった小川未明の「金の輪」や「赤いろうそくと人 魚」などに代表される童話の世界にも通じるように思えます。その未明もまた、幼いわが子を失うという経験を持っていました。根本的に「グリーフケア」の要素を持っている雨情の童謡は、愛する人を亡くし た人、特に幼い子を亡くした多くの人々の心を癒すことができるのではないでしょうか。著者は、雨情の先人としての小林一茶の存在をあげ、「雨情は江戸時代の俳人、小林一茶に強く惹かれていたようだ。一茶は満2歳で母親を失い、50歳で初めて結婚して、次々と4人の子どもが生まれては死んでいった。『おらが春』は長女さとと死別した悲しみを記した俳文作品である」と述べています。
また、「国民と故郷と悲しみ」として、著者は以下のように述べています。
「『ロンドンデリーの歌』や『アリラン』にはさまざまな内容を盛り込めるのだが、それは同じ仲間と感じ合う多くの人びとの共感が背後にあるからだろう。『さまざまな内容』と述べたが、そこにはまず温かい故郷や親子の情愛あふれる絆の像がある。他方、その絆から離れて去っていった、あるいは旅立っていった人の像がある。その人が帰ってくるのか、長い別離になるのか、永遠の別れになるのか、定かではないが、寂しさがあり、悲しさがある。去っていった者の方に身を置くなら、望郷の念があふれてくる。こうした像や悲しみや哀愁の情緒が大多数の人びとに共有されると感じられていた」
続けて、著者は以下のように述べています。
「こうしたことが可能だった1つの理由は、アイルランドや韓国・朝鮮が植民地状況にあったからかもしれない。日本の場合、『唱歌』や『童謡』や『歌謡曲』によって、多くの人びとが悲しみや望郷の念を分かち合うことはできたかもしれない。しかし、『ロンドンデリーの歌』や『アリラン』のような歌は思いつかない」
成田龍一氏の『「故郷」という物語――都市空間の歴史学』によると、「故郷」の概念が急速にゆきわたるようになったのは1880年代だといいます。この時期から、東京にいる同じ「故郷」の出身者が中心となり、ときに地元に留まっている者をも巻き込んで、「同郷」の人士が寄り集う機運が高まります。そして、90年前後に数多くの「同郷会」がいっせいに成立していったことを紹介し、著者は以下のように述べるのでした。
「各地の人びとが他の地域と張り合うかのように同志を募り合い、同郷会の設立という形で全国で同時的に故郷意識、同郷意識が顕揚されていく。この場合の『同郷』の範囲は市や町とその周囲の郡といったほどの広がりだ。メンバーは官吏、教育者、医師、軍人、村長、役場関係者、学生といったエリートや地域指導層が主体であり、もっぱら男がその担い手だった。日本という『国』への強い帰属感を前提に『故郷』の意義が強調されている」
第7章「戦争による悲嘆を分かち合う困難」では、「軍人・兵士の死をめぐる不協和音」として、著者は述べます。
「アジア・太平洋戦争の後期には多くの軍人・兵士が戦死した。この若者たちの中には、大学等で学問に取り組んでいるさなかに召集された者がおり、また特別攻撃隊の一員として最期を迎えた者も少なくなかった。将来、エリートとして日本社会で大きな役割を担うことが期待された者たちが早い死を余儀なくされたこと、また、確実に死ぬことを覚悟しながら最後の日々を過ごさねばならなかったことから、彼らの死に対する悲嘆は多くの人々の共鳴をよぶはずのものだった」
続けて、著者は以下のように述べています。
「靖国神社や各県の護国神社は、彼らに対する追悼と慰霊と祈りの場となるはずだった。ところが敗戦によって靖国神社や護国神社の威光は失墜した。また、敗戦が予想されるなか、彼らの死を避けられる可能性はなかったのかという思いが強まっていった。こうしたなかで、戦没した若者たちの手紙、日記、手記等が公表され、多くの人々の共感をよぶようになる。悲嘆を分かち合うメディアとなっていく。ところがそれとともに、それらに対する不協和音も響くようになる」
第8章「悲嘆を分かち合う形の変容」では、「葬送の宗教文化」として、著者は「日本で『ともに悲しむ』営みを支えてきた文化装置として、お通夜、お葬式や法事などの葬祭、また、お盆やお彼岸などの季節行事があることについては異論がないだろう」と述べ、さらに以下のように述べています。
「江戸時代以来、日本の葬祭は主に仏教寺院と僧侶を媒介としてなされてきた。キリシタン禁制とともに江戸幕府が定めた宗門改め制によって、ほぼ全国にわたって住民が寺院の檀家となることが強制された。それが行えるだけの仏教寺院が、すでに全国に分布していたという事態が前提となっている。この檀家制度によって、人々は葬儀や法事で、またお盆などの季節行事で、人が死ぬと僧侶にお経をあげてもらい、戒名や法名をつけてもらい、定期的に仏事(法事)に参加することが自然と感じるようになった。僧侶にとっては、葬祭や死者・先祖を対象とする季節行事で仏事を営むことが主要な寺院活動となっていった。死と死者をめぐる伝統仏教のこのような活動がグリーフワークの場として、あるいは人々の『喪の仕事』を助ける場として機能してきたことも確かなところである」
「葬式仏教の追善回向行事」として、著者は述べます。
「曹洞宗の寺院の出身で東京帝大で歴史学を学び、東京帝大史料編纂所や駒澤大学等で研究教育にあたった圭室諦成(1902-1966)という学者がいた。その圭室諦成が1963年に刊行した『葬式仏教』は『葬式仏教』という語に学術的な基礎づけを行った著作である。日本では、死者や祖霊への民俗信仰が仏教の追善回向の形をとるようになり、それが仏教の主要な活動の形態となっていったことを跡づけた書物である」
その『葬式仏教』142ページに、こう書かれています。
「日本においては、新亡の霊をアラミタマといい、たたりの可能性をもつ危険な霊と考えた。そしてそれがミタマという祖霊に帰一するまで、遺族は厳重なアライミに服する民俗があった。この民俗とむすびついて、仏教の中陰仏事は伸びている。また祖霊に帰一したミタマを、年2回まつる民俗があった。この民俗にむすびついたのが、盆行事である。現在、仏事・盆行事などに、仏教では説明のつかない部分がおおいのは、そうした民俗がつよく残っているためである」
「死霊・祖霊信仰こそ日本の固有信仰」として、著者は、圭室諦成の結論は「維新以後の仏教の活きる路は、葬祭一本しか残されていない。そして現在当面している課題は、古代的・封建的な、呪術的・祖先崇拝的葬祭を精算して、近代的な、弔慰的・追悼的な葬祭儀礼を創造することである」と紹介します。
そして、「あとがき」では、著者はこう述べるのでした。
「精神科医や臨床心理士が『心のケア』の専門家とみなされ、期待されるようになったのは近年のことだ。1995年に阪神・淡路大震災があって、『心のケア』という言葉が広まった。だが、それ以前からグリーフケアの機能を果たす文化装置があり、『ともに悲嘆を生きる』社会関係があった。それは『心のケア』の専門家に引き継がれただけでなく、新たに広範な人々によって受け継がれようとしている。グリーフケアという言葉が広まってきたのはこのためだ。そのことについてじっくり考えてみよう。それはまた、死や深刻な喪失を受け止める死生観やスピリチュアリティの歴史について、また死者とともに生きることについて考え直すことでもあるだろう」
本書は250ページほどのソフトカバー本ですが、そこに書かれていることには事典なみの情報量が詰まっています。また、グリーフケアについての問題点や今後の展望も述べられており、「グリーフケアの基本図書」と呼ぶべき一冊になっています。悲嘆のさなかにある人も、グリーフケアを学ぼうとする人も、まずは本書を一読していただきたいと思います。なお、もうすぐ、著者と鎌田東二氏(上智大学グリーフケア研究所特任教授)、小生の3人の共著である『グリーフケアの時代』(弘文堂)が刊行されます。こちらも併せてお読みいただければ幸いです。
