- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1659 経済・経営 『セゾン 堤清二が見た未来』 鈴木哲也著(日経BP社)
2019.02.15
『セゾン 堤清二が見た未来』鈴木哲也著(日経BP社)を読みました。一条真也の読書館『堤清二 罪と業』で紹介した本は西武帝国を築き上げた堤一族の悲劇を描き出していましたが、本書には経営者・堤清二の未来志向の経営の軌跡が綴られています。著者は1969年生まれで、現在は日経ビジネス副編集長です。
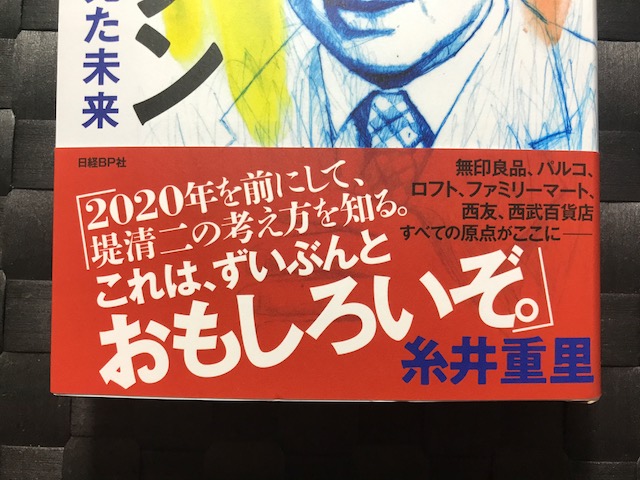 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、堤清二の似顔絵(山口はるみ画)が描かれており、帯には「無印良品、パルコ、ロフト、ファミリーマート、西友、西武百貨店、すべての原点がここに――」「『2020年を前にして、堤清二の考え方を知る。これは、ずいぶんとおもしろいぞ。』糸井重里」と書かれています。
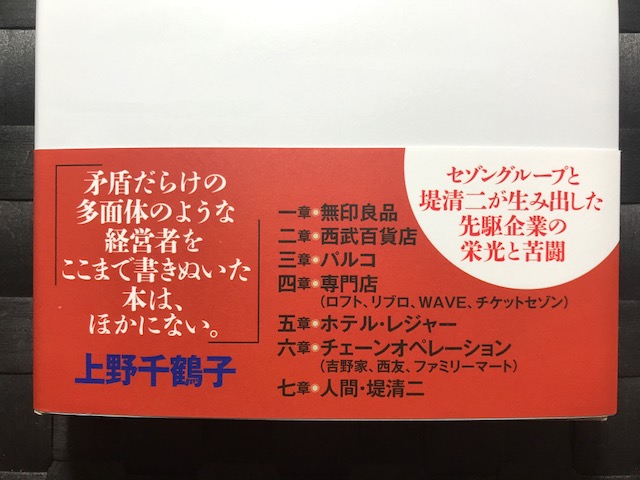 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には本書の構成が紹介され、「『矛盾だらけの多面体のような経営者をここまで書きぬいた本は、ほかにない。』上野千鶴子」「セゾングループと堤清二が生み出した先駆企業の栄光と苦闘」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「はじめに」
一章 無印良品
一節 ロンドンで感じた違和感
二節 西友と堤からの「独立」
三節 今は無印を、僕たちが解釈している
二章 西武百貨店
一節 革新は、いつも逆境から
二節 セゾンが文化を”民主化”した
三節 挫折の連続の中に先見性
三章 パルコ
一節 幻の「銀座パルコ」
二節 パルコの流転と堤の戦い
三節 アニメ文化に宿るDNA
四章 専門店
一節 ロフトを生んだ堤のひと言
二節 リブロの静かな誇り
三節 堤の理念、継承者たちの奮闘
五章 ホテル・レジャー
一節 異母弟・猶二が見た清二の夢
二節 「共犯」だった銀行が豹変
三節 西武の原点とグループ解体
六章 チェーンオペレーション
一節 吉野家買収の慧眼(けいがん)と矛盾
二節 西友、「質販店」の憂鬱(ゆううつ)
三節 ファミリーマート、誤算の躍進
七章 人間・堤清二
一節 「お坊ちゃん」が学んだ大衆視点
二節 避けられなかった「裸の王様」
三節 堤が遺したメッセージ
「あとがき」
「はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「無印良品、ファミリーマート、パルコ、西武百貨店、西友、ロフト、そして外食チェーンの吉野家――。いずれも日々の生活でなじみのある企業であり、知名度の高いブランドだ。これらの企業が、かつて同じグループに属していたことを、知らない世代が増えている。コンビニエンスストアの中で、なぜファミリーマートだけが無印良品の化粧品やノートを売っているのか。改めて指摘されなければ、普段の生活では不思議に思わない」
続けて、著者は以下のように述べています。
「これらはいずれも、堤清二という男が一代でつくり上げた「セゾングループ」という企業集団を構成していた。小売業にとどまらず、クレジットカードや生命保険、損害保険などの金融業、ホテルやレジャー、食品メーカーまで、多様な事業を展開してきた。ラジオ局のJ-WAVEも、いわゆるグループ企業ではなかったが、情報発信を重視する堤の戦略によって、開局から深くセゾングループが関与した。ほかにもセゾングループは、映画配給のシネセゾンやパルコ出版などのメディア関連事業、美術館や劇場といった文化事業を幅広く手がけたところに特色があった。一時はグループ約200社、売上高4兆円以上のコングロマリットを形成したセゾングループ。かつてはスーパーを軸としたダイエーと並んで、二大流通グループとされていた」
しかし、展開する事業の多彩さにおいては、セゾングループを超えるコングロマリットは日本に存在しなかったと指摘して、著者は述べます。
「セゾングループの存在感を高めていたのは、売上高4兆円を超える規模よりもむしろ、消費文化をリードする先進性にあった。1970年代から1980年代にかけて、セゾングループが手がける事業には、いつも何らかの新しさがあった。話題性に富み、高感度のセンスを備えていたのだ」
堤清二は、「商品を売るのではなくライフスタイルを売る」「モノからコトの消費へ」「店をつくるのではなく、街をつくる」などの考え方を全面に打ち出して、セゾングループを経営しました。著者は以下のように述べます。
「セゾン文化が全盛だった1970年代から1980年代のように、1つの企業が消費者を啓蒙できる時代では、もうない。堤のような経営者が消費文化を先導できるわけでもない。ただ、堤とセゾングループがかつて持っていた特有のエネルギーを検証することは、未来の消費の行方を知る上で、大きなヒントとなるはずだ。新たな価値を生み出す発想力や、現状を否定してイノベーションを起こす柔軟性――。閉塞感が漂う現代だからこそ、セゾングループのかつての哲学を掘り起こし、分析することに大きな意味があるのだ」
著者は、「現代の課題を先取りして闘っていた堤」として、以下のように述べています。
「ロボットやAI(人工知能)などの先端技術をどのように活用すればいいのか。技術の進歩によって各段に便利になる生活の中で、人間らしい働き方とは何なのか。堤は、1970年代から1980年代にかけて、こうしたテーマに対しても、事業を通じて『解』を見いだそうとしていた。今見ても、これらは極めて現代的な課題である。
もしかすると堤は、30年、40年先の未来から、昭和の日本にタイムワープをした異色の経営者だったのかもしれない。1990年代以降、グローバル資本主義が地球を席巻し、『数字化できる利益こそが至上の価値』という考え方が企業社会を支配してきた。消費文化もその影響を受けた。だが堤が提示したのは、数学だけで人間の幸福や楽しみ、よろこびを評価する価値観に対する明確なアンチテーゼである」
また、「人間が豊かに暮らし、働き、そして幸せを感じるとは、どういうことなのか」と読者に問いかけ、著者はこう述べます。
「セゾングループの歩みを通して堤が導きだそうとした『解』を探ることは、市場原理主義とも言える乱暴なグローバル経済が転換期を迎えた時代だからこそ、大きな意味を持っている。企業が社会に存在することの意義は何か。人々を豊かにすることが1つの役割だとすれば、今度は、豊かさとは何かという疑問が立ちのぼってくる。企業が、経済活動を通じて人と社会を豊かにすること。それは、ものに満たされることばかりではない。生活をより便利にすることだけでもない。むしろ今求められるのは、物質を超えた新しい豊かさではないだろうか。堤清二という経営者は、そうしたメッセージをセゾングループの事業に込めていた」
一章「無印良品」の冒頭には、こう書かれています。
「無印良品は、堤の思想の結晶なのだ。あるいは、堤の分身と言ってもいい。父・康次郎に命じられて、27歳で西武百貨店に入社した堤は、西友やパルコといった小売業のほかにも、外食、金融、不動産など、多様な事業を展開した。その先にたどり着いたのが、無印良品だった。堤は西武百貨店などの事業を急拡大する中で、自ら大資本家の役割を担い、欧州の高級ブランドを大衆に広める伝道師としても成功した。
無印良品は、そんな堤の過去の取り組みに対するアンチテーゼだった。現状を打破する自己否定の精神。矛盾を抱えながら、それを高い次元へ昇華させること。無印良品には、そんな堤らしい経営哲学が凝縮されている。そして堤の強いこだわりが、国内外約900店の無印良品の成功をもたらしている。無印良品の生い立ちと歩みを伝えること。それは堤清二という極めて複雑かつ矛盾を抱えた経営者の輪郭を、くっきりと浮かび上がらせることでもある」
二節「西友と堤からの独立」では、1985年に西友の中に新設された無印良品事業部の初代部長を務めた木内政雄に対して、堤は何度も「無印良品のコンセプトのホテルをつくれ」と伝えていたそうです。著者は述べます。
「セゾングループは1988年、約50ヵ国で約100のホテルを運営するインターコンチネンタルホテルを買収していた。投資額は2000億円以上。世界のホテル業界で最大級の買収と言われ、のちにセゾングループを苦しめる一因にもなった案件だ。同ホテルチェーンは最終的に、負債を減らしたい銀行団の圧力によって1998年に売却される。堤はその無念さを隠さなかった。それほどホテル事業に強い思い入れがあったのだ。おそらく堤は、自らの経営思想を隅々まで注ぎ込んだホテルを一からつくり上げたかったのだろう。『無印良品のホテル』というアイデアに強いこだわりを持っていた。そして、木内に「無印良品のコンセプトのホテルをつくれ」と繰り返していたのだ」
無印良品のホテルは最近になって実現しました。2018年1月18日、良品計画が中国・深圳に世界初の「MUJIホテル」を開業したのです。著者は述べます。
「堤が存命であれば90歳。もう少し生きて、自分の目でその出来ばえを確かめたかったに違いない。日本でも2019年春、東京・銀座に、無印良品の新たなフラッグシップ店に併設されるかたちで、MUJIホテルがオープンする予定だ。MUJIホテルは、運営を外部に委ねるものの、コンセプトは良品計画が策定。内装のデザインや家具の提供も手がける」
二章「西武百貨店」の二節「セゾンが文化を”民主化”した」では、「タレントは使わず、アートをつくる」として、著者は以下のように述べています。
「西武百貨店は、広告を文化にしたと言われる。
著名なコピーライターの仲畑貴志も、堤に誘われてセゾングループの仕事を始めた。『タレントを起用した広告を、堤さんは避けていました。既存のものをカネで買うんじゃなくて、自らつくろうという思いがあったんじゃないですか。アートをつくろう、と。堤さんならではの個性が非常に強く反映されています』」
続けて、著者は以下のように述べています。
「堤のキャラクターを語る時、『辻井喬』のペンネームで詩や小説を書き続けた作家としての側面は見逃せない。経済界からは皮肉交じりで『詩人経営者』とも呼ばれたが、堤は創作に対して並々ならぬ執念を注いでいた。1970年代から1980年代、セゾン文化が世の中を席巻する前から、堤は自らの感性を頼りに、美術や演劇、音楽というコンテンツを事業に取り入れていった」
三節「挫折の連続の中に先見性」では、「テクノロジーで人間性を回復する」として、著者は以下のように述べます。
「『メカトロ』とは、自動搬送システムを使って店内の物流を合理化するといったハイテク技術を駆使した店舗のこと。セゾングループでは、西友能見台店(横浜市)に続いて、西武筑波店でメカトロを導入していた。
セゾングループ全体の方針や企業姿勢を伝える広告にも携わっていた糸井重里は、ロボットを導入した堤の考え方を、直接聞いたことがあった。『初期のロボットをスーパーマーケットに導入するという議論でも、ゆくゆくはどういう時代が来るという話をこんこんとしていましたね。いずれは人がやらなくてもいいことを、ロボットがやってくれる。これから我々はそれを視野に入れて仕事をしていくべきだ、と。今も似たような話が実現しつつあって、よく話題になっていますね』」
続けて、著者は以下のように述べています。
「現代では極度の人手不足を背景に、製造業だけでなく、小売業やサービス業でもロボット導入の機運が高まっている。堤はそれを30年以上前に先取りしていた。それだけではない。『なぜロボットを導入するのか』という点にも、深い思想の裏づけがあった。堤は、ロボットなどの先端技術を駆使して、セゾングループの職場から、力仕事や単純作業を排除しようと考えていた。テクノロジーの進化が人間性を回復すると信じていたのだ」
三章「パルコ」の一節「幻の『銀座パルコ』」では、以下のように述べられています。「振り返れば、堤はその経営者人生で長く「銀座」という場所に執念を燃やし続けてきた。西武百貨店とパルコの両方で経営幹部を務めた森川茂治は、セゾングループにとっての銀座の意味をこう解説する。『西武百貨店もパルコも、フラッグシップ店は池袋と渋谷というターミナル駅に立地して、私鉄沿線の顧客をキャッチするビジネスモデル。沿線に住む団塊世代がつくった戦後の新しい「東京」とともには発展した新興企業です。だからこそ、元来の「東京」、つまり江戸の生活文化が残り、老舗が商売をしてきた銀座に、どうしても拠点が欲しかったのです』」
また、「堤が銀座に抱いた野望」として、著者は述べます。
「池袋から成り上がった新興百貨店が、普通の方法で老舗百貨店に挑んでも勝ち目はない。百貨店が持ち得ない若者を魅了する斬新なイメージ戦略と情報発信で、一発逆転を狙う――。これがセゾングループの成功の方程式だった。そのためには西武百貨店だけでは足りず、ファッションのテナントを集積した都市型ショッピングセンターの草分けであるパルコが不可欠だ。パルコこそが、老舗百貨店が持ち得ない有力な業態だからだ」
続けて、著者は以下のように述べています。
「1970年代から1980年代、パルコは西武線のターミナル駅である池袋の街のイメージを向上させた。さらには東急グループの拠点である渋谷の街の印象を刷新する力も持っていた。いずれも、ターゲットにしたのは団塊の世代より下の、当時の若い消費者だった。戦後、私鉄沿線に住宅地が広がり、そこに住む若者たちが消費者として台頭してきた。若い大学生など、地方から東京への流入も続いた。そんな新しい都市生活者を魅了して、池袋と渋谷という街をつくり変えたのがパルコだった」
四章「専門店」の二節「リブロの静かな誇り」では、「ニューアカブームをけん引したリブロ」として、著者は以下のように述べています。
「1980年代といえば、大学生の間でフランス現代思想などのニューアカデミズムがブームになった時代だ。既存の分類にとらわれない独自の本の並べ方が評判を集め、リブロの池袋本店は”ニューアカの聖地”と呼ばれるようになっていた。それまでは難解で縁遠い存在と思われていた哲学や思想が、一般の人にも手が届くようなイメージをまとって流行するという特異な現象が起こっていた」
続けて、著者は以下のように述べています。
「ここでもリブロは、作家などを招くイベントや独自の切り口のブックフェアを展開。浅田彰や中沢新一といった学者が1980年代の『知のスター』のような存在になる上で、リブロが果たした役割は大きい。西武百貨店によって、欧州の高級ブランドは一般消費者の身近な存在になった。同じように、リブロによって象牙の塔の中にあった知は民主化された。リブロがけん引したニューアカブームでは『知がファッションになった』と言われたほどだ」
堤清二自身も書店としてのリブロを愛していました。「辻井喬にとってのリブロ」として、リブロの取締役や池袋本店店長を務めた菊地壮一の「堤さんは本の表紙を見たり、立ち読みしたりしている時に、新しい事業のアイデアを思いつくようで、書籍売り場の事務所からいろいろなところに電話をしていました。例えば秘書に、『すぐに誰と誰を集めておくように』と会議の準備を指示していました」という言葉が紹介されています。これについて、著者は、「堤は、フランスの現代思想で話題を集めた『リゾーム(地下茎)』など、海外で話題になっている思想を、店づくりにも導入しようとしていた。社内会議で現代思想などの話題が出ることも日常茶飯事だったという。リブロの売り場を歩きながら、ビジネスのアイデアを膨らませていたのだろう」と述べています。
書店のイノベーションが「リブロ」なら、レコード店のイノベーションが「WAVE」でした。現在の六本木ヒルズの場所に建てられましたが、当時わたしは六本木に住んでおり、毎日のように通ったものです。著者は、「単なる物販にとどまらない文化の発信とライフスタイルの提案こそが、リブロやWAVEの強みだった。そこに足を運べば新しい発見があり、自分も変わることができる。そんな何かに出合える店を、リブロもWAVEも目指していた」と述べています。
そして現代、改めてリブロやWAVEのような取り組みが見直されはじめているとして、著者は以下のように述べます。
「米アマゾン・ドット・コムなどのインターネット通販が全盛になり、リアル店舗は、顧客に足を運んでもらえるかどうか、自らの存在意義を改めて問い直す必要に迫られているからだ。その中でも、例えばカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が運営する複合商業施設『代官山T-SITE』(東京・渋谷)などは、かつてのセゾングループのDNAを引き継いでいると言えるだろう。施設内にある大型書店『蔦屋書店』で書籍や音楽ソフトを販売しながら、遊歩道で結ばれた複数の専門店も含めて、全体でライフスタイルを提案している」
五章「ホテル・レジャー」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「戦後の大衆消費社会をリードしたセゾングループ。西武百貨店を母体に、コングロマリットの形成にまい進していた堤は、一体、どこでつまずいたのか。最大の挫折は、ホテルやリゾート開発といった領域にあった。堤の経営者人生には光と影が交錯するが、影の部分は、これらの事業を担った不動産会社の西洋環境開発に凝縮されていると言っても過言ではない。ホテルやレジャーはかねて、西武鉄道グループの主力事業だった。西武鉄道グループは、先代の堤康次郎が1964年に他界した後、清二の異母弟の堤義明が継承者となった」
続けて、以下のように書かれています。
「清二が1980年代、ホテルやスキー場、レジャー施設といった西武鉄道グループと正面からぶつかる事業を急拡大した背景に、義明に対する対抗心があったことは間違いない。ただし、単なる兄弟の確執によって、清二が多角化に走ったという一面的な理解も正しくはない。西武百貨店に入社して間もない1960年代、清二は早くも日本人にとって真の豊かさとは何なのかを考えながら、『生活総合産業』という理想を胸に抱いていた」
夢を追った結末は残酷でした。1990年代、セゾングループの負債は3兆円以上と言われ、西洋環境開発は2000年に経営破綻。グループ解体に至ったのです。
一節「異母弟・猶二が見た清二の夢」では、「若い頃にホテル事業を手がけていた清二」として、こう書かれています。
「1964年の東京オリンピック開催の直前、9月1日に『東京プリンスホテル』は開業した。港区芝公園にあるこのホテルは、もとは西武百貨店が開業準備の段階から担当していた。当時、西武池袋本店の店長だった清二は、東京プリンスホテルの事業責任者にも就いた。オリンピック開催に向けてホテル不足が国家的な課題となっていた時代である。政治家だった康次郎は、『自分が貢献しなくては』と考え、大型国際ホテルの建設に乗り出した」
続けて、著者は以下のように述べています。
「当時としては水準の高い設備を有し、客室のデザインやインテリアなどは、清二の母親で、『会長夫人』(会長とは康次郎のこと)と呼ばれていた操が選定した。開業を記念して、西武百貨店は同ホテルで『ダリ展』を開催。猶二は『西武百貨店でなくてはできないイベントでした。かなり大きな反響もありました。この時、清二さんはホテルに思い入れを持ったのだと思います』と振り返る。
ホテルの建設を急いだ康次郎だったが、その開業も東京オリンピックも見ることなく、1964年4月に急逝する。そして、グループのホテル事業は義明が継承することになり、東京プリンスホテルも、西武百貨店から西武鉄道グループに移管されることになった」
その後、セゾングループは国際的に知名度のあるインターコンチネンタルホテルを買収しましたが、結果は失敗でした。セゾングループ流の「生活総合産業」をビジネスとして成功させる難しさについて、猶二は「セゾングループは、消費者に新しいライフスタイルを提案するビジネスをずっとやってきたわけです。ライフスタイルが変わって市場が大きくなった時にそのビジネスを始めれば、確実に利益は出るでしょう。けれどセゾングループの場合、ライフスタイルが変わる前に、次の新たな価値観をどんどんと提案していました。利益の果実をつみ取る前に、新しい事業をスタートさせるのです。だから、なかなか利益が出なかったのです」と話しています。
清二にとって、ホテル事業はどんな意味を持っていたのか。
「ホテルは文化の中心である」として、著者は「清二さんは、ホテルは文化であるという感覚でした。地域に根ざした情報発信の拠点であり文化の中心である、と。1964年、東京プリンスホテルの開業時になぜダリ展を開いたのか、というところに戻っていきます。それもやっぱり文化の発信なんです」という猶二の言葉を紹介します。
また、「レジャーや観光にもアクセル」として、「清二は、セゾングループの主軸であった百貨店やスーパーなどの小売業に限界を感じていた。だからこそ『生活総合産業』を標榜し、ホテル以外にもレジャーや観光といった、現代で言う『コト消費』の分野に夢を抱いて、1980年代以降、アクセルを踏み込んでいった。セゾングループがホテルやレジャー、観光に力を注いだ裏側には、時代的な事情もあった。1987年、総合保養地域整備法(リゾート法)が施行され、国の施策に乗って、全国的にリゾート開発が加速していたのだ」と書かれています。
続いて、著者は以下のように述べています。
「企業に週休2日制が広がり、バブル景気の後押しもあって、消費者はモノの消費からレジャーなどのコトの消費へ、鮮明にシフトしていた。清二について、『1980年代のバブル経済の波に乗ってホテルやレジャーなどの事業を手がけた末に、失敗した経営者』というイメージを持つ人は少なくない。バブル経済の膨張に背中を押された清二が、にわかにホテルやレジャー事業に突き進んだ、という論調だ。だが、それは事実ではない。清二は事業家として歩みはじめた当初から、レジャー事業に強い関心を持っていたからだ」
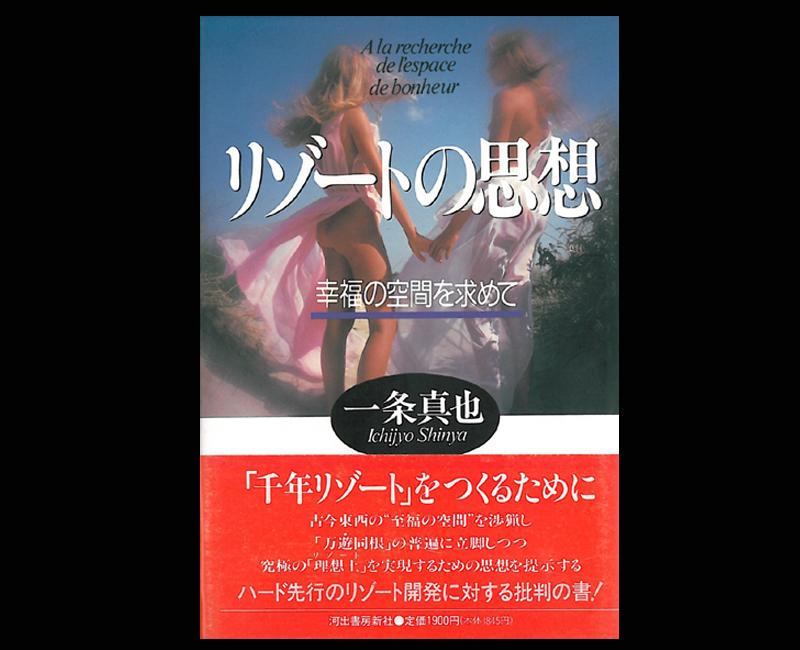 『リゾートの思想』(河出書房新社)
『リゾートの思想』(河出書房新社)
「レジャー産業に託した清二の思い」として、著者は、清二が35歳のときに編著として1962年に刊行した『レジャーの科学』(実業之日本社)という本を取り上げます。同書には「経営の理念は、消費者のレジャー活動に奉仕し、その人間的幸福の拡大に献身する具体的経済活動のなかから、私ども自身が創りあげてゆかねばならないと考えられる」という清二の言葉が書かれています。著者は、「レジャー事業で日本人の生活を豊かにしようという、若き清二の決意表明のようにも受け取れる。ここで『経営の理念』という言葉が登場しているが、実際に清二が順次手がけはじめたレジャーや観光事業は、文化を重視する清二の理念を色濃く反映したものになった」
なお、この『レジャーの科学』という清二の編著は、約30年後の1991年に刊行された拙著『リゾートの思想』(河出書房新社)の内容と重なる部分が多いです。
六章「チェーンオペレーション」の一節「吉野家買収の慧眼と矛盾」では、「流通革命論に疑問を抱いた堤」として、著者は以下のように述べています。
「堤が1979年に著した『変革の透視図』(改訂新版、トレヴィル)という経済書がある。東京大学での堤の講義をもとに編集したものだが、出版の動機として、ダイエー創業者の中内らが唱える『流通革命論』への疑問があった。流通革命とは、メーカーではなく小売業こそが、サプライチェーンの主導権と価格決定権を握るべきだという考え方で、1960年代以降に多くの信奉者を生んだ。これに対して、堤が提示したのは、『流通産業はマージナル産業だ』という主張だ」
何が「マージナル=境界」なのかというと、「資本の論理」と「人間の論理」の境界にあるというのです。資本と人間との接点にビジネスが存在する流通業は、規模の拡大や利益一辺倒ではなく、人間の本質を理解した事業展開が重要になるという論ですが、著者は「この趣旨に立てば、中内らの進める流通革命は、資本の論理に取り込まれていることになる。流通革命を実現するために、小売業が巨大になって、マニュアルに基づいたチェーンオペレーションを進める。そうした大量販売は、画一的な大量消費を前提にしており、消費者の本当の豊かさや幸福にはつながらない、という堤なりの異議申し立てだ」と述べるのでした。
七章「人間・堤清二」の冒頭で、著者は述べています。
「堤ほど毀誉褒貶の激しい経営者は、なかなかいない。
1960年代から若き異才の詩人経営者として注目を集めた。全盛期の1970年代から1980年代は、『セゾン文化』の主宰者として存在感を高め、時代を代表する経営者の1人となった。一方、堤の影の部分とされる複雑な家族関係や、父や異母弟との確執も、常に取り沙汰されてきた。1990年代にバブル経済が崩壊すると、飽くなき拡大戦略の末に、セゾングループを崩壊させたオーナー経営者として、世論の批判を一身に浴びることになった。堤に対する世の中の視線は交錯したまま、実像が定まらない。これは、堤がいかに多面性を持った人物かということの証左でもある」
一節「『お坊ちゃん』が学んだ大衆視点」では、「後天的に身につけた大衆に寄り添う目」として、清二の次男・堤たか雄が打ち明けた以下の思い出話を紹介します。
「唯一、父に怒られた記憶があるのが、小学生くらいの頃、父の運転手がいらして、私が『だって運転手なんだからいいじゃない』と言った時のことです。父は怒鳴るというよりも、理づめで私が泣くまで聞いてきました。『なんで運転手はダメなんですか』『あなたと運転手さんはどう違うんですか』『どういう点であなたが偉くて、運転手は偉くないんですか』と。『それは最もくだらない人間の考え方だ』というようなことを言われました」
「父はもともと社会主義者ですから、『つまらない人間』という表現はよく聞きました。つまらない男だとか、つまらない女だとか。そう思われるようなことをすると、本当に怒られましたね」
また、「人間が労働の主人公に」として、著者は述べます。
「仕事の場で人間を中心に考えるというテーマも、労働力が希少資源となった現代ならば、もっと自然に世の中に受け入れられたはずだ。AI(人工知能)の進化によって、人間が担うべき仕事は何かが改めて問われている。AIによって人間は幸福になれるのか。技術の進歩によって、働く人々は排除されてしまうのか。それとも、より人間的な仕事に集中できるようになるのか。こんな問いが真剣に議論されるようになった現代にこそ、堤の発想は改めて重要な意味を持ってくる」
続けて、「その分水嶺は結局、経営者がどんな理念を持つかということにかかっている」として、著者は「堤が伝えようとしたのは、そんなメッセージではないだろうか。現在は、政府が音頭を執る『働き方改革』の文脈の中で、どんな会社も、働き手を大切にする方針を打ち出さざるを得ないムードになっている。だが堤の理念を引き継ぐ者は、そうしたムードによって動かされるのではなく、自らの信念によって、ほかの会社とは違う踏み込んだ施策を打ち出している」と述べます。
二節「避けられなかった『裸の王様』」として、著者は堤清二の経営者としての人生について以下のように述べます。
「最初は望んで入ったわけではなかった小売業だが、堤はそこを足場にして、『生活総合産業』の実現に向けて走り続けた。『真の豊かさとは何か』という問いと向き合い、事業を通じて答えを出そうとした。そんな堤のロマンが、ホテルやリゾート、金融など、新事業へ進出する原動力となった。だが事業の幅が広がるに伴い、セゾングループは風船のように膨らみ、最後には巨額の負債とともに崩壊した」
続けて、著者は以下のように述べるのでした。
「成功と失敗はコインの表と裏のような関係なのかもしれない。何かに急き立てられるかのように攻めの経営を続けなければ、たった一代で約200社、売上高4兆円以上というコングロマリットは誕生しなかった。1980年代までのセゾングループの成功は、堤という個性が成し遂げたものである。同様に、1990年代以降のグループ崩壊の最大の要因も、堤自身にあったのだろう」
三節「堤が遺したメッセージ」では、ともに流通業界の両雄としてライバル視されたダイエー創業者の中内㓛が「いまとてもつらい状況にあります。しかし、もう一度、何か一緒にやりましょう」という内容の手紙を堤に送ったことが紹介されます。2005年に他界する数年前のことで、堤の側近によると、毛筆で書かれた長文の手紙だったといいます。著者は「巨額負債と本業の不振から、ダイエーは1990年代後半、深刻な経営難に陥った。中内は失意の中、2000年に会長を退任、翌2001年には取締役からも退いた。『つらい状況』というのは、血のにじむ思いで築き上げた自分の城が崩れかけ、銀行から経営責任を追及される屈辱を指す」と述べています。
続いて、著者は「この頃、堤も似たような境遇にあった」として、こう述べています。
「セゾングループの不動産会社の西洋環境開発が2000年に経営破綻した責任を取って、約100億円の私財を提供。グループの役職を退いた。2人の巨人はともに、流通業界で未踏のビジネスを切り開いた先駆者だ。年齢は堤が5歳下。ともに70歳を過ぎて、バブル崩壊後のグループ再建に苦闘した共通点もある。中内の手紙には、それでもまだ前に進もうという執念がにじみ出ている。かつてのライバルと手を携えて世の中に一矢報いたかったのだろうか。堤なら悔しい気持ちに共感してくれると思ったのだろうか」
堤清二について、著者は「実像が見えにくい、異能の経営者」として述べます。
「堤は決して、功成り名遂げた経営者ではない。一代でセゾンという巨大グループを築き上げた事実は揺るがないが、最後まで悪戦苦闘を続け、グループ解体に伴って何度も苦渋を味わった。それでも、堤が人間の真の豊かさとは何かを追求するために、セゾングループを土台に試行錯誤を続けた経験は貴重だ。新たなテクノロジーが次々に登場し、人々の描く理想のライフスタイルの形は揺らぎはじめている。私たちはこれから、一人ひとりが人間らしく生きることや豊かさの意味、幸福な人生とは何かということを、自分に問い、選択していかねばならない。その『解』を与えてくれるのは、国でも、経済でも、企業でもない。改めて自らに問いを投げかける時、堤が体を張って発したメッセージの数々が、私たちに大きなヒントを与えてくれるはずだ」
そして、著者は「一人の年寄りが死ぬことは、図書館が1つなくなるのと同じ」というアフリカのことわざを紹介します。
「あとがき」で、著者は以下のように述べます。
「企業経営では、世界的に新たな潮流が生まれている。これまでのように、ひたすら短期的な利益を追い求める姿勢を改め、事業を通じて社会にどんな価値を提供できるのかを重視しようとする考え方だ。『何のためにこの事業を展開するのか」「我々の会社は世の中に対してどんな価値を提供できるのか」。経営者には、単に経営の執行能力だけでなく、社会的な理念を持っているかどうかが問われはじめている。そう考えると、堤清二という人物の『今日性』が改めて鮮明に浮き彫りになる。『基本の論理』が力を増し続けている世の中に抗って、いかに『人間の論理』を打ち立てるかを、ライフワークとして考え抜いてきたのだから』」
また、著者は以下のようにも述べています。
「堤は理念がすべてに先行する経営者だった。リスクを冒して理想を追求した結果、多くの挫折を経験した。それでも、そんな堤の姿勢が事業を生み出すエネルギーとなり、日本人の消費生活の進化や文化の受容に、大きな役割を果たした。
現代、グローバル企業の経営者の多くが改めて『理念』や『思想』の重要性に気づきはじめている。それは、すべての価値観が揺らぐ世界では、強い理念こそが会社の軸となり、組織の求心力を生み出すからだ。高い給料だけでは、優秀な人材を集めることが難しくなっている」
続いて、著者は以下のように述べています。
「自分たちの事業が、社会にどんな価値をもたらすのか。誰を幸せにできるのか。こうしたメッセージを発信できない企業はこの先、消費者には選ばれなくなっていく。企業が掲げる理念やメッセージは、そのまま商品やサービスの個性としてもにじみ出し、ライバルが簡単にはまねできない強みとなる。日本の産業界に閉塞感が漂っているのは、もしかすると、このような個性を発する企業や経営者が減っているからかもしれない」
さらに、著者は以下のように述べています。
「堤清二という経営者は、事業を構想するスケールが大きく、思考も深かった。そして、それと比例するように、経営者としての短所も多く持ち合わせていた。独創的なビジネスを構想する力に秀でていた一方で、既に出来上がったビジネスで安定した利益を得る力、つまり持続力には問題があった。セゾングループ各社に対して自由なアイデアを認めたため、ユニークな事業が多数生まれたが、半面、グループの統治はおろそかになった。極めて多面的で矛盾を抱えていた堤は、成功に向かって突き進むよりも、破滅に至る宿命を内在させていたのかもしれない」
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「人間は誰しも長所と短所を備えている。功と罪、あるいは光と影、その両方を包含したものが人格だ。その個性が時代に合うこともあれば、裏目に出て苦しむ場合もある。バブル崩壊によってセゾングループは経営に行きづまり、解体に至ったことは紛れもない事実である。堤の支払った代償は大きかった。一方で、堤は日本社会の新たな地平を切り拓き、ほかの誰とも違う形で産業史に名を刻んだ。堤が生涯をかけて発したメッセージは、新しい生き方を模索する私たちの背中を押してくれるはずだ。歴史を振り返る意味が、そこにある」
 両雄の志を見直す
両雄の志を見直す
一条真也の読書館『闘う商人 中内㓛』で紹介した本を読んだときもそうでしたが、本書を読んだわたしは、深い感慨にとらわれました。わたしは、『孔子とドラッカー新装版』(三五館)の「志」の項で中内㓛氏と堤清二氏の2人について書き、「かつて、ダイエーとセゾンという企業集団があり、それぞれが日本人のライフスタイルをトータルにプロデュースする総合生活産業をめざしていました。ありとあらゆる業種に進出し続け、大きな話題を提供したが、結果はご存知の通りです。両者ともバブルの象徴とされています。しかし、わたしはダイエーとセゾンのすべてが間違っていたとは決して思いません」と述べました。
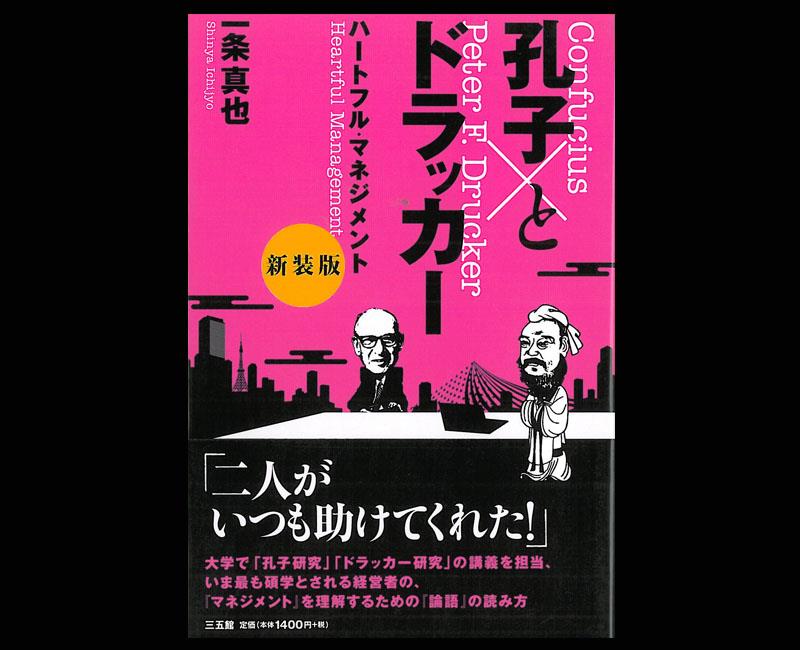 『孔子とドラッカー新装版』(三五館)
『孔子とドラッカー新装版』(三五館)
ダイエーとセゾンについては、佐久間庸和の天下布礼日記「総合生活産業の夢」にも書きました。「日本の物価を2分の1にする」と宣言して流通革命を推進した中内㓛氏。常に経済と文化のリンクを意識し、社会の中における美しい企業のあり方を追求した堤清二氏。両氏の心の中には「日本人を豊かにする」という強い想いがあったはずですし、それはやはり「志」と呼ぶべきものではないでしょうか。志なくして、両氏ともあれだけの大事業を短期間に成し遂げることは絶対に不可能であったし、逆にその志が大きくなりすぎた企業集団から乖離したときに凋落ははじまったのではないかと思います。ダイエーとセゾンは確実に日本人の生活を変えました。二人とも日本の経営史に名を残す巨人であることは間違いありません。栄枯盛衰が世の法則ですが、最終的な評価は歴史が下すのです。
特に、経営と執筆活動を両立しておられた堤清二の存在は、わたしの人生に多大な影響を与えて下さいました。その意味で、堤氏はわたしの恩人であると思っています。学生の頃、最も憧れた経営者は堤氏でしたし、わたしは「経営者でも本を書いていいんだ」ということを知りました。「二束の草鞋」を嫌う日本社会の中で、一時の堤氏の大活躍は歴史に残るものであると確信します。そして、堤氏の執筆活動を中心にした文化人としての感性が現実の経営の分野にフィードバックしていたことは間違いありません。まさに、堤清二氏こそは「文化」と「経済」をつなげた人であり、「未来」をしっかりと見ていた経営者でした。