- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.10.14
『しきたりの日本文化』神崎宣武著(角川ソフィア文庫)を読みました。
文化としての日本の「しきたり」についての民俗学からの知見が述べられていますが、大変勉強になりました。著者は1944年生まれの民俗学者です。旅の文化研究所所長、岡山県宇佐八幡神社宮司でもあります。
本書のカバー裏表紙には、以下のような内容紹介があります。
「喪中とはいつまでをいうのか。結納の本来の意味とはなにか。時代や社会の変化にともなって、もとの意義が薄れたり、変容してきた日本のしきたり。神棚と仏壇が同居するような神仏習合的な文化として培われてきたさまざまなしきたりを、『私』『家』『共』『生』『死』という視角から民俗学的に解明。なんのためにそうされてきたのかに焦点を絞り、言われてみればなるほどと納得がいく、日本文化としての『しきたり』を説く」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
1章 「私」のしきたり
1 縁起かつぎ
2 神だのみ
2章 「家」のしきたり
1 正月
2 盆
3 節供・節分
3章 「共」のしきたり
1 寄り合い
2 まつり
3 相互扶助
4章 「生」のしきたり
1 産のさまざま
2 名付けと初宮・食初め
3 七・五・三
4 年祝い
5章 「死」のしきたり
1 葬式組
2 通夜と葬送
3 喪・年忌
「参考文献」
「あとがき」
「はじめに」の冒頭で、著者は「おみくじと手水―作法の縮小化」として、おみくじについて以下のように述べています。
「おみくじは、護符でもあるのだ。吉が出たら財布にいれるか神棚に納めるかして、向こう1年間のお守りとしなくてはならないのだ。結ぶのは、凶が出たときにかぎる。それも、逆手 (右利きなら左手)で結ぶのである。結びにくいことだが、それゆえに、それを『行』とするのだ。つまり、行をもって身を祓い、再びおみくじを引くのである」
続いて、著者は手水についても以下のように述べます。
「おみくじと同様に祈願のおこないとしては、手水をとる。本来は水垢離をとるべきところを手水鉢の水を杓ですくって左手、右手と洗い、左手で水をすくって口をすすぐ。また百度石を踏む。本来は、そのつど家に帰って、潔斎をして宮参りや寺参りをするべきところを、最短の距離の往復ですませるのだ。さらに、賽銭箱に金銭を投じる」
よく「ご縁がありますように」と言って5円を投げ入れたりしますが、著者は「誰がいいだしたものか」として、以下のように述べます。
「これは、語呂合わせの遊戯にすぎない。投じる金銭に決まりはない。そもそもが、包み紙に入れて、表に『初穂料』とか『玉串料』と記して祈願を伝えるところを簡略化しているにすぎないのだ。なおいうと、初穂料とか玉串料そのものが、初穂(新米)を供えたり玉串を奉る手間を金銭に代替しているのである」
また、「戒律にはならなかった『しきたり』」として、著者は祈願の作法をも縮小化したことを重視し、「それによって、多くの人が平たく神仏と向きあうことができたのである。神さん、仏さんと、さんづけをしてなじんだように。こんなことは、世界でもまれなことである。そこでは、キリスト教やイスラム教の戒律にみるような厳重なしきたりは、ほとんど生じなかった」と述べます。
それがゆえに、祈願の作法も厳しくひとつに集約されることが少なくありませんでした。著者は述べます。
「本来ならこうすべきところを、ここではこうしてすませる。それも是とされ、結果として作法は、かぎりなく縮小化もした。それを許しあう、『融通』の文化土壌を伝えてきたのである。そして、それがゆえに、縮小や省略の理由もめいめいにいいわけをするようにもなってきたのである。戒律とはいえないしきたりだから、時折の変化もありうるし、時折の解釈もありうる。しかも、それが地方ごとに多様な展開をしてきたのである」
「混乱を招いた明治祭式」では、現在の神事では「二礼二拍手一拝」が一般的な作法となっていますが、出雲大社や宇佐八幡宮では「四拍手」が伝えられているのももう一方の事実であることを示し、著者は述べています。
「どちらが正統か、と問えば、両者に言い分がある。ここで二者択一を迫る必要はない。つまりは、それぞれの伝統にしたがって行えばよろしいのである。二礼二拍手一拝は、明治政府が神仏分離を強行し、神社神道を公的な宗教と定めたときに統一した作法である。いわゆる『明治祭式』のひとつで、たとえば、『御飯、御酒、御餅』が神饌の最上位に、魚が鯛に定番化するのも、明治祭式による統一である。それ以前は、各地でその土地土地の風土や歴史にちなんださまざまな祭式の作法や神饌があった。それが、近代国家のなかで統一がはかられたのである」
神仏分離ということでいえば、明治元(1868)年の明治政府による「神仏分離令」によって、神道と仏教は別な宗教となりました。神社と仏寺は表向きはそれぞれに独立したのです。しかし、めいめいには旧来の「神仏習合」の信仰形態をはばかることなく伝えてきたとして、著者は以下のように述べます。
「家に神棚と仏壇が同居し、正月には、宮参りをした足で寺参りもする。誕生は神式で祝った者が、死亡は仏式で葬られる。それを連綿と伝えてきているのである。このことは、簡単に世界に通じることではない。宗教の思想対立が戦争を引きおこすこともしばしばあるのだから、神仏の習合は理解されがたい不思議な構図なのだ」
1章「『私』のしきたり」の1「縁起かつぎ」では、日本人のカミ信仰、カミまつりのなかには、祓う要素がじつに多く存在するとして、著者は述べます。
「たとえば、神事のいちばんはじめに修祓行事がり、神主が大麻(木串や榊枝に切り紙を取りつけたもの)を振る。神輿渡御の先頭には、大麻や塩湯桶を持った先祓いが立つが、それが猿田彦や獅子に扮しての場合もある。また、神楽では、湯立て(湯祓い)とか榊舞・剣舞とかにその儀がある」
というと、いかにも神道に関係する行事のように思われがちですが、けっしてそうではありません。著者は述べます。
「仏教において香を焚き、その煙を浴びるのもそうである。もっとも身近なところでは、葬儀に参列したあとで塩を撤くのも、その儀にほかならない。また、修験において、水垢離をとったり火渡りの荒行を行うのもそうである。つまり、私ども日本人が宗閥を問わずもっている信仰の基本的な所作なのである。そして、それは、仏教が伝来、布教し、その仏教に影響を受けて神道が体系化する以前から、この列島弧に住む人たちが育んだもの、としなくてはならない。つまり、現在私どもが何気なく『お祓いでもしたら』という、その縁起かつぎの心象こそが祖型だ、としてよいのである」
このあたりは、わたしも拙著『知ってビックリ!日本三大宗教のご利益』(だいわ文庫)に書きました。
 『知ってビックリ!日本三大宗教のご利益』(だいわ文庫)
『知ってビックリ!日本三大宗教のご利益』(だいわ文庫)
また、「海水・塩水による禊祓い」として、沖縄では、葬式のすんだあとの満潮時に、家族が海や川に行って身を清める慣習があることが紹介されます。さらに、喪の忌明けの日にも海に入り、着物や布団などを洗ってくる習慣もみられるとして、著者は「死という強烈な穢れも、塩の力で除去される、と信じていたことがうかがえるのである。海辺ばかりでなく、山間の村々でも、わざわざ海辺に足を運んで、祭前の潔斎をするところが少なくない。これを、浜降り、浜行き、などという」と述べています。
著者は「変化する『清め』の習俗」として、葬式帰りに家の入口で塩を撤くのは、事後の清めということで、これまでの事前の禊ぎ祓いとは違うことを指摘します。しかし、塩を用いるということの伝統を継いでいるわけです。北九州の博多周辺では浜の砂を撒く慣習がありますが、この砂も「オシオイ」といいました。著者は「葬儀に参列したあとで、塩をつまんで『お清めをする』という。宗派によっては、そのかぎりではないとするところもある。が、一般的にはなじんで久しい作法である。では、どんな作法が妥当か、ご存じだろうか。自分の肩越しに、うしろに投じるのがよろしいのである」と述べます。
続いて、著者は、葬儀における「祓い」について述べます。
「かつて、一般に、葬儀の席には死霊のみならず、それをとりこもうとする悪霊が漂っている、とした。人びとは、それが背後霊のごとく依りついてくることを恐れたのである。それを塩で祓う。したがって、まず背後を祓ってしかるべきなのだ。むろん、身体の前のほうに霊が抱きつくかたちで憑いている、とお思いの方は、そのかぎりではない。前のほうも祓われるとよいだろう。さらにいうと、家の中に入る前に祓うのがよい。外の霊を家の内にもちこまない、とするのは、当然の作法というものである」
また、料理屋の店先での盛り塩について、著者は「これは清めの塩としないほうがよい」と断言し、さらに以下のように述べています。
「誰を祓うのか。『お客さは神さま』とすれば、客の来訪を塩を撤いて清めるとは、無礼千万なことになる。賓客を迎えるにあたって門先を清めるといえば、まだ理屈がたつだろうが。この盛り塩は、盛り砂の変化したもの、とするのがよいだろう。盛り砂とは、かつて道路が未舗装であったころ、雨が降ったあとのぬかるみに撒くために、料理屋や遊廓の店先に用意していたものである。それが、いつしか塩盛に縮小化されたものだが、いずれにしても近世以降のことである。現在は、凍結対応のために道路脇に塩袋が用意されているのは、周知のとおり。そのさらに古いかたちがそこにみられるのだ」
2章「『家』のしきたり」の1「正月」では、「神霊が宿る鏡餅」として、正月の鏡餅は単なる供えものではなく歳神の依代であることが紹介されます。古来、米粒にはイネの霊力(稲魂)が宿ると信じられてきました。もっとも、日本にかぎったことではなく、稲魂信仰は、古くから稲作が生活基盤となった東アジアの各地にみられるものですが、なかでも日本列島により濃厚に伝わるとして、その理由を著者は述べます。
「ひとつには、南方系の稲作の伝播の北限の地であるから、といえる。稲作の導入に、ひとかたならぬ先祖たちの労苦があった。そして、水田が開かれ、稲作を基盤にした定住生活が続くと、そこに祖霊信仰も強く根ざすことになる。その米粒を凝縮した餅や酒は、米のもつ神聖な力がとくにこもった食べものとみなされてきたのだ。そして、先祖たちがもっともあこがれた馳走であったのだ。それをカミに供え、そののちに人びとが食べることによってイネの霊力と先祖の霊力が人びとに移り宿る、とされてきたのだ。正月の鏡餅は、その象徴といってよい」
また、「御魂分けの『年玉』」として、著者は以下のように述べます。
「鏡餅は、歳神の依代である。神霊(御霊)が依り憑いたものを下げて、分けいただく。それが『おかげ』となる。ひとり鏡餅にかぎらない。カミへの供えもの(神饌)は、御飯も御酒もそうである。雑煮の本来の意味も、そこにあるのだ。つまり、歳神からの『御魂分け』。そして、歳神の御魂分けであるから、これが『歳魂』(年玉)なのである」
2「盆」では、半年を隔てて正月と対をなす「先祖まつり」と盆を位置づけます。つまり、盆も正月も、平たくいえば、カミ・ホトケ、それに祖霊を家に招いてもてなすまつりです。古くは、「盆まつり」という地方も少なくありませんでした。著者は以下のように述べます。
「古来、ヤマへの信仰が根強い。そのことは、すでに述べてきた。ヤマそのものがカミであり、ヤマにカミ・ホトケ、魑魅魍魎までが棲んでいる、とした。それは、天上の浄界と地上の俗界をつなぐ位置にある。修験道や神道が成立して以降は、カミ・ホトケが天降るときの中継点ともなったのである」
続けて、盆にも「ヤマから祖霊が降りてくる」とする観念が強く潜在すると指摘し、「ヤマからの祖霊を迎える『盆花迎え』」として、著者は「一般的には、墓地から祖霊を迎えるとして墓に供えた花を持ち帰って盆棚に飾る風がみられる。しかし、その花は、もともとはヤマからとってきたものである。野山の花を盆棚に飾る習俗を、『盆花迎え』とか『盆花とり』といった。正月の「松迎え」と対比されてよい習俗である」と述べるのでした。
また、「清浄な火―迎え火・送り火」として、著者は、カミやホトケを迎えるのに火を焚くという、その原理の普遍性に注目し、以下のように述べます。
「ひとり迎え火・送り火だけの問題ではない。神社や仏寺で篝火を焚く、灯籠や提灯を灯す、といったこととも関連する。それは、まず、灯を点して路を照らすことの意味をもつ。つまり、カミ・ホトケを誘導する路しるべとなる。そして、もうひとつ、精霊の『火への憑依』を期する意味がある。噴火を御神火といい、篝火を斎灯というように、火を清浄視する信仰心が反映されている、とみなくてはなるまい。日本のカミ・ホトケは、清浄な火に導かれ、依り憑くのである」
現在の盆行事は、一般的には仏教的な色彩を強めています。たとえば、祖霊にも大別して3種あるとし、本仏(祖霊)と新仏(新精霊)と無縁仏(餓鬼)とに分け、その扱いを違えます。これについて、著者は述べます。
「本仏は、年忌を重ねた先祖の霊のことで、これは直ちに仏壇に招聘する。新仏は、まだ成仏せず、この世とあの世の中間をさまよっている霊として、仏壇には招かない。座敷とか縁側に別の祭壇を設け、そこに祀るのである。このことは、各地で現在も行われている。が、本仏と混同して仏壇に招きいれるようになったところも少なくない」
さらに、「無縁仏」について、著者は以下のように述べています。
「無縁仏は、いわゆる餓鬼であり、血縁霊ではないから家には招き入れない。ただ、本仏や新仏についてくることもあり、しばしば悪しきとり憑きもするので、これも丁寧にもてなさなくてはならない、とする。そこで、庭に餓鬼棚を設ける習慣が、たとえば関東一円などに伝わる。しかし、一般には、餓鬼供養は、お寺さんまかせとして家々では行われなくなっているのである」
続いて、盆会の場合が取り上げられ、霊界と俗界をつなぐ存在として、長老が敬われることにもなると指摘し、著者は以下のように述べます。
「長老は、つまりはイキミタマ(生見玉=生御魂)である。いいかえるならば、カミ・ホトケを最上位とし、ご先祖さまが中間にあって、現世の人間社会とつなぐ役目をはたす。さらに、そのご先祖さまを、イキミタマといわれる老人たちが若年層とつなぐ図式がみられるのである」
そして、「盆の贈答習慣と『お中元』」として、著者は中元と歳暮の違いについて、以下のように述べています。
「中元が血縁的な贈答習慣にはじまるとすれば、歳暮は社会的なそれにはじまる、といってよい。もとは別々な理由からはじまったものが、今日では盆・暮の贈答習慣として対をなして伝わるのは、これは、近代以降の百貨店の商業戦略にあおられてのことだっただろう」
3「節供・節分」では、「折目・節目に『節季祓い』」として、著者は述べます。
「折目・節目は、いいかえると季節の隙間であり、邪気悪霊がしのびこみやすく、災いが生じやすいときである。現在でも、『季節のかわり目につき、一層のご自愛を』と手紙に書く。仏教や神道が成立する以前から、あるいは、宮中や幕府の公的行事が定まる以前から、人びとは、その過し方を大事にしてきた。古く、人びとにとっては、季節の循環がとどこおりなくすすむことが、農耕であれ狩猟・漁撈であれ、生活を営むうえで重要なことであった。であるから、それを防げる災いは、未然に防がなくてはならない。ゆえに、折目・節目の除災祈願が生まれ、それを行事化して大事に伝えてきたのだ。行事のはじめは、突発的な天変地異への異怖をのぞくと、折目・節目にあった、といってもよいのである」
3章「『共』のしきたり」の1「寄り合い」では、「『寄り合い』によったムラのしきたり」として、著者は、かつての日本のムラについて述べています。
「農繁期の労働力が足りない家も、作業がとくに遅れることがなかった。早くすませた家から夫役が加わったからである。ムラでは、むかしからのしきたりとして相互に助け合ったものである。たしかにムラは美しかった。道の草が生い茂ることもなかったし、側溝にゴミが溜まることもなかった。道路や人家から近い山の雑木の枝木もはらわれていたし、下草も刈りとられていた。春に秋に、そして冬にも、その作業が共同でなされていたからである」
続いて著者は、ムラのまつりに言及し、以下のように述べます。
「ムラのまつりは、老若男女が一堂に会し飲食を楽しむ場であった。いちばんの大役は、頭屋(当屋)である。ほぼ1年間、犠牲的につとめなくてはならないが、尻込みをする者はいなかった。たとえば、還暦になると、それを買ってでるのが一人前、とされていた。そして、頭屋が決まれば、同年輩の者や隣近所で頭屋組をつくり、細々と役割分担をした。それを実行委員会などとはいわなかったが、それと同等に、あるいはそれ以上に円滑に機能していたのである。
葬儀も同様であった。組内や講内が諸役を分担して進行するから、遺族は十分に別れをすることができたのだ。葬儀社は、長く不要であった。そうしたムラの運営は、『寄り合い』ではかられ、とり決められることが多かった」
 『隣人の時代』(三五館)
『隣人の時代』(三五館)
また、「血縁・地縁社会だったムラ」として、著者は以下のように述べます。
「ムラは、長く平和であった。なにごとにもかえがたい平和が維持されていた。共同作業もまつりも、そして寄り合いも、そのしきたりは平和を維持するための要素であった、とみるべきであろう。もちろん、それは、集団の単位が小さいからである。互いに言葉のあやを読みとる、それができる顔見知り社会だからである。いいかえれば、血縁社会、もしくは地縁社会ならではのことであった。そのところでは、都市における社縁社会では通じにくいしきたりかもしれない。かつて、日本のムラには活気があった。ムラが都市を支えていた。いや、人材も食料も、ムラが日本を支えていた、といっても過言ではない」
もちろん、このようなかつてのムラが実現していた血縁・地縁社会をそのまま現代に蘇らせることは不可能です。それでも、無縁化が進行し、孤独死が増え続ける現状が良いはずはありません。わたしは、『隣人の時代』(三五館)において、現代日本にふさわしい有縁社会のあり方とその再生方法について私見を述べました。
同書で示した有縁社会再生のための最大の方策が「隣人祭り」の開催でした。もともと、「祭り」とは血縁と地縁を強化する文化装置です。
2「まつり」では、「ムラのまつり、マチのまつり」として、著者は「ムラという共同体のなかで『まつり』も生まれた。そして、まつりを維持してきたのである。ひとり、ムラだけではない。ムラから出た人たちの集合体である『マチ』においても、まつりが生まれ、維持されてきた」と述べています。
日本の多くのマチは、近世の城下や宿場や門前からなるが、近隣の農山漁村と密接な関係を持続してきました。経済的な関係にかぎらず、通婚も不可分な関係にあったのです。著者によれば、そうしたマチでは、ムラのまつりの伝統をかなり色濃く継いできたといいます。
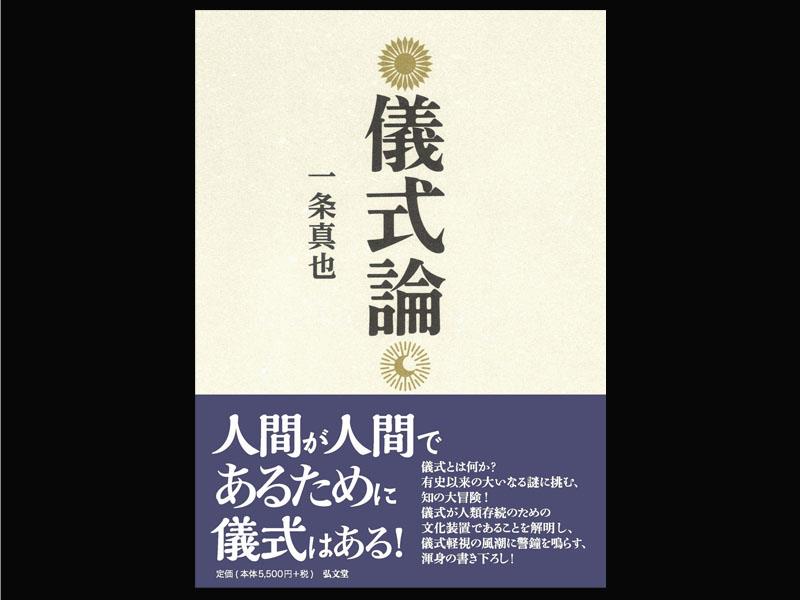 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
拙著『儀式論』(弘文堂)では、第3章「祭祀と儀式」において、「まつり」の本質を求めましたが、本書でも神崎氏が以下のように述べています。
「まつりは、もちろん信仰行事である。が、日本の場合は、宗派や宗旨を問わず、誰もが参加できる。とくにその土地に代々住む人は、ただの参加者ではなく、慣習にしたがっての実務分担者でもある。そこに、まつりを行い、まつりを伝承する本来の意義がありそうに思える。しかし、都市のまつりは、しだいにムラのそれとは離れていった。その運営や伝承のかたちが違ってきている」
続いて、都市におけるまつりのもっとも大きな変化は、まつりの実務参加者はかぎられており、見物参加者が多数を占めるようになったことであると指摘し、著者は以下のように述べます。
「そこでは、共同体への帰属意識は一般には広がりにくい。にもかかわらず、それぞれの都市でもまつりが維持されているのは、なぜだろうか。その実務的な中核部の人たちが、伝統的な町内会のしきたりにしたがっているから、というしかあるまい。ということは、そのところにおいては、ムラの伝統とも通じるところがあるのだ」
「まつり」といえば、この読書館でも紹介した柳田國男の古典的名著『日本の祭』がありますが、おそらく同書の影響を受けたであろう神崎氏は「なぜ、まつりを行うのだろうか。めいめいの信仰心はともかくとして、そこには『共』(共同体)の意義がある、とみるべきではあるまいか」と述べています。
また、著者は「まつりといえば、一般には神社の祭礼、仏寺の法会のように思われている。しかし、古くさかのぼってみると、ムラの行事が基盤にあって、その一部が神社や仏寺の行事に吸収された、とみるべきなのではあるまいか」とも述べています。
さらに「自然神・祖霊神を祀る」として、著者は述べます。
「まつりは、年中行事は、人びとがそこに集住したときから存在した。それには、イエの行事もムラの行事もあった。どちらが先に生じ、どちらに重きがあったかを問うことに、さほどの意味はない。ただ、古くさかのぼればさかのぼるだけ、共同体での結束を強くはからざるをえないところで、ムラの行事がさかんに行われただろう、と想像がつく。原始共産制という言葉にたよるつもりはないが、人びとのムラへの帰属意識は強かった。そして、人びとのカミを崇める信仰観念も強かった。この場合のカミとは、むろん神社に祀られている祭神ではない。ひとつは、山のカミ、水のカミ、火のカミなどの自然神である。つまり、天地間の森羅万象をつかさどる神々である」
「神道と仏教に吸収された土着の行事」として、著者は、仏教も神道も土着の信仰をたくみにとりいれて発達したことを指摘します。そして、仏教にも神道にも自然信仰と祖霊信仰が容認され、教義化されているとして、以下のように述べています。
「壇家寺が壇徒の祖霊供養を担当するようになったのは、歴史的にみると江戸中期以降のことである。だが、それ以前から、仏寺は、祖霊にかぎらず諸々の精霊を供養する場所であった。神社も、氏神が村落の守護神となるのは、同様に、江戸の幕藩体制下で国割りと村割りがなされてからのこと。しかし、さらに古く、小さな集落単位で産土神や株神が祀られていた」
これは、土地の開墾を共同で行った一族郎党の血縁神、あるいは血縁・地縁神の性格が濃く、祖霊の集合体ということができます。このように、土着の自然信仰と祖霊信仰をとりいれることで、仏教も神道も全国的に浸透することができました。そして、中世においては、「神仏習合」という日本独自の信仰形態を生みました。それぞれの土地で自然発生的に生じた行事が、神道行事の中にも仏教行事の中にも影響を及ぼしたり、吸収されたりしたわけです。
著者は「明治の『神仏分離』でさらに変容したまつり」として、以下のように述べています。
「明治政府における『神仏分離』は、日本のまつりを変容させた。神社神道を公的なものとしたところで、たとえば、宮中のそれにならって新嘗祭が大きな行事となった。それは、農村部での氏神まつり(秋まつり)に符合、複合するかたちで円滑な浸透をみた。が、一方で、秋まつりと同等に、あるいはそれ以上に重要であった春まつりが一部をのぞいて後退することになった」
「まつりは、葬送儀礼をのぞくオコナイ(行事)すべてがそうであったのだ」と喝破する著者は、さらに以下のように述べます。
「正月もまつりといった。盆もまつりといった。八朔も亥の子もまつりといった。現在、南九州に一部そのような呼称が伝わっている。が、歴史的には新しい呼称でも、雛まつりとか七夕まつりといい、昨今のイベントでも、ふるさとまつりとか開業まつりなどというではないか。そこに、まつりの本質をみなくてはならないのである。まつりは、ムラなりマチなりの共同体を維持するための、さまざまなオコナイを総称したものだったのである」
「近代化で失われる『きまり』『しきたり』」として、著者はかつての日本社会では、教育にあらざる教育がそこでなされたと指摘し、以下のように述べます。
「『大人の後姿』をみて、若者や子どもたちは自然に学んだのである。行事の由来や順序だけではない。挨拶の仕方、役割の分担と連携、そして飲食の作法など。それを毎年くりかえして覚えることで、人と人の関係がいかにあるのがよいかを自燃と学んだのである。それが、ムラやマチを安全に持続させることになったのであろう」
さらに、著者は「まつりで結束してきたムラ」として、ムラのまつりを執行する、その労働力として必要な戸数は3、40軒であり、寄り合いは、さらにそれを2分なり3分なりした少数であり、それを中国地方などでは「小部落」と呼び、当番組を「大部落」と呼んだことを紹介し、以下のように述べます。
「前者は、たとえば葬式講中ともいうように葬儀に必要な出夫をする。火事場の片づけにも出夫する。したがって、『ムラ八分』の単位もこの小部落であった。それに対して、大部落は、まつりの共同作業や小・中学校の通学班、青年団・婦人会の組織をつくるときの単位となっていた」
日本のまつりを、単に宗教的な行事ととらえてはならないとして、著者は以下のように述べます。
「宗教的な行事ととらえるから、忌み嫌うことにもなるのだ。日本の信仰は、先述もしたように自然や祖霊を祀ることに本来の基盤がある。カミを崇めるかたちで、人びとが集うのである。人びとが集まりやすいためにカミを崇める、とまでは言わないが、『何事におわしますかは知らねども』カミを崇めるのである。それで、人びとは集まりやすくなる。そこに、文律にあらざる、会議にあらざる共同体維持の機能がはたらく、とみてよかろう」
続いて、著者は以下のように述べるのでした。
「そこに、しきたりがあり、しつけがあった。これも端的にいってしまうと、次代の後継者たちを育てんがための制度であったのだ。まつり・行事をとおして、つまり共同作業をとおして教える。また、習う。学ぶ。しかし、それは、自らが体現して教えるのであり、それを見て習い、学ぶのである。『教わるより慣れろ』とか『聞くより見て盗め』、といった。いわゆる教育とは違った、『もうひとつの教育法』がはたらいていたのである」
 「サンデー毎日」2017年7月2日号
「サンデー毎日」2017年7月2日号
3「相互扶助」は、冠婚葬祭互助会のコンセプトである「相互扶助」について論じられます。わたしのブログ記事「冠婚葬祭互助会生誕の地を訪れる」にも書いたように、互助会の歴史は70年ほどですが、じつはきわめて日本的文化に根ざした「結」や「講」にルーツがあります。「結」は、奈良時代からみられる共同労働の時代的形態で、特に農村に多くみられ、地域によっては今日でもその形態を保っています。
神崎氏も「『お互いさま』が生んだ『結』のしきたり」として、「結」について以下のように述べています。
「結は、また、労働の交換というだけでなく、広く共同労働をも意味していた。ちなみに、婚礼を前にしての『結納』であるが、嫁という貴重な労働力をもらうために、婿が一定期間、嫁方に労働を返す、という慣行が、かつては西日本各地にあった。そこから、結を納めるという意味で生まれた言葉なのである」
また、著者は「火事と葬送のしきたり」として、以下のように述べます。
「結に代表される近隣組織の火事や葬儀への出夫は、労働をともなうものであった。火事でいうと、消火の手伝いもあるが、消火後の後始末に人手がかかった。近代以降、消防署や消防団の消火体制が整ってきたとはいえ、後始末まではしてくれない。それは、現代でも結の仕事なのである。そして、結の機能が後退したところで、業者が請負うということになるのだが、もちろんそれは金銭で精算されなくてはならない。結の出夫は、『お互いさま』であるので、当面の金銭負担が少なくてすむ、という当家にとっての有利があった。因ったときは、『遠い親戚より近くの他人』を頼ったのである。
葬儀についていえば、葬儀社の出現以前を想定してみればよい。現代の葬儀社が請負う作業の全部を、結、もしくは葬式組の組内で分担して行っていたのである。いや、まだ地方のムラでは、そうなのである」
著者は「葬儀は、あわただしく、会葬者が多ければその裏方作業もまた忙しい。かつては、結・葬式組が、現在は葬儀委員会と葬儀社がそれをとり仕切る。結は、葬儀委員会と葬儀社を合わせた機能といえばもっともわかりやすいだろうか」とも述べています。また、「いまや結・葬式組のしきたりはすっかり後退した。都市においては、崩壊して久しい。ムラでも、しだいに後退の傾向にある」と述べます。
そして、「都市では、相互扶助の制度は無用なのか」と問うた後、著者は以下のように述べるのでした。
「そうではあるまい。近年は、公民をとわず、さまざまな福祉制度や互助制度が新たに発達している。が、その多くは、金銭をもっての代替制度である。結のような相互扶助ではない。そこに、『お互いさま』『相みたがい』の精神は、ほとんど介在しない。そのことを批判するわけではないが、文化的な制度が文明的な制度に移行する、そのなかでの混乱がなおしばらく続くことだけは事実であろう」
ここで語られている互助制度こそ、まさに冠婚葬祭互助会です。
互助会は、「結」の流れを汲む近代的な相互扶助のシステムなのです。
4章「『生』のしきたり」の1「産のさまざま」では、「子どもの通過儀礼」として、著者は以下のように述べています。
「かつては『七歳までは神の子』といった。これは、幼児の無拓な性質を神性とみた、と一般 には解釈される。しかし、医療制度が整わない時代を考えてみると、病気に対しての免疫性が弱い幼児の健やかな成長は、人びとにとってカミの加護にすがらざるをえないほどの切実な願いというものであった。そこで、7歳までの折目・節目にさまざまな祈りと祝いの行事が派生したのである」
続けて、それらの行事について以下のように説明されます。
「それらは、七夜・名付け・宮参り・食初め・歯固め・初節句・誕生祝い・七五三などであり、現在も伝わっている。が、ずいぶんに簡略化されている。あるいは、変容している。漫然と行われているが、本義や作法は形骸化している。遊戯化している、といってもよい。それは、医療制度が整ったことで、出産の神秘性が薄らいだこと、幼児の死亡率が減ったことの影響であろう。カミの加護にすがらなくても、子どもは生まれ育つもの、という思いが大勢となって久しい」
また、著者はヤマの神を取り上げ、以下のように述べています。
「山のカミは、古くは諸神の根元にある。各地にオヤマ(御山)、ミヤマ(弥山)、オンタケ・ミタケ(御嶽)などという呼称が伝わるように、この日本列島には霊山信仰が根付いている。仏教の伝来、神道の形成以前からの自然信仰である、ということはすでに述べた。ゆえに、仏教が布教するときに寺院名の上に山号を冠したのであるし、神社が平地につくられても領守の森を必要としたのである。仏教も神道も『山』を遥拝し、山の力ミに敬意を表するかたちで浸透していったのである。
山のカミは、いくとおりにも分身する。正月には歳神(正月神)に、春先には田のカミになる。そうした伝承は、各地に通じる。したがって、もっとも古くさかのぼってみれば、産神にも転じた、とするのはしごく妥当である」
著者は「産屋での『別火』と禁制」として、出産の前後は、実母か姑か、あるいは姉妹などが食事を用意してくれるが、それ以外は自炊であることを指摘します。日常の生活とは火を分けるわけで、それがすなわち「別火」であったとして、以下のように述べています。
「『おべっか』、あるいは『おべっかい』も、その別火から派生した。ごきげんをとることにほかならないが、それは、産屋に入った女性に対してはだれもが丁寧な扱いをすることから生まれた俗語である。産屋における妊産婦は、産神のもとにあって、おかしがたい存在である。その認識が共通してあったのだ」
3「七・五・三」では、「ヒトとなる七歳の祝い」として、著者は七・五・三祝いについて以下のように極論します。
「七歳までは、いつでも、何度でも子どの成長を祝い、さらなる健康を祈願する行事を行ってもよろしいのである。それでは面倒だ、ということで、簡略化されたところで七・五・三祝いが残ったということができる。かつて、男女ともに7歳を盛大に祝ったのは、いうなれば、カミの子を経てヒトの子として認められる意味をもってのことだった。同時に、七歳の祝いをもって氏子入りするところも少なくなかった。事実、江戸期の氏子帳(人別帳)には、その事例が多かった」
そのことは、葬送の場合にも関係します。七歳に達する前に死亡した子どもは、葬儀も簡単にして墓石も小型にしました。カミの子は、すなわち社会的な人格を認められていなかったのです。「童子」あるいは「童女」と刻んだ小型の墓石を今でもよく見かけます。
そして、「子を思う習俗」として、著者はこう述べるのでした。
「現在、七・五・三や誕生日以外に、ともするとそのしきたりが簡略化されてきている。あるいは、形式的になぞるだけでとどまっている。たとえば、伝統的な行事食を子どもと一緒に家庭でつくるのを、どれだけ伝えているだろうか。一方で、最近は、肉親による子どもの虐待があとをたたない。親の子に対する自然の情愛が欠落したとは思いたくないが、これはゆゆしき現象である。そうした場合、あるいは、幼児期の通過儀礼もないがしろにされているのではなかろうか、と推測する。もしそうであれば、子どもの通過儀礼のもうひとつ別の意義もみえてくる。子どものうちに伝統的な行事を共有することは、生きるうえでの無形のちから、安心とか信頼とかの活力を導きだすことになるのではあるまいか」
4「年祝い」では、「失われた成人儀礼」として、著者は述べています。
「かつては、成人儀礼も重要な年祝いであった。その年齢を15歳とするところが多かったのは、武家社会における「元服」にならってのことだっただろう。事実、それをゲンプクイワイというところも少なくなかった。フンドシイワイというところも多く、親から贈られた白の六尺まわしを締めて祝ったものである。それが、若者組(若衆組)への組入りとなったところもある。とくに、西日本の海辺の村里ではその事例が多かった」
しかし、そうした習わしは、現在ではほとんど見なくなりました。昭和23(1948)年に、法令で満20歳をもっての成人式が定められてからは、1月15日に行政区分にしたがって一斉にそれを行うようになったからです。それによって、各地方で行われていたそれぞれの成人儀礼がなくなったわけです。
5章「『死』のしきたり」は、わたしの最も関心のある分野です。冒頭、著者は「葬儀社と葬式組」として、以下のように述べています。
「人生の通過儀礼のほとんどは、本人か家族が執りしきる。祝言(結婚式)のように当日の媒酌人ほかの諸役を他人に依頼することがあっても、準備万端は当家で整えるものである。ところが、葬儀については、そうはいかない。準備から儀式までの作業のほとんどを、他に委ねることになるのである。現在、都市においては、それを葬儀社に請負わせる。ほとんど丸投げ状態、といってもよい。もちろん、事前の確認は遺族が立会ってなされるが、あとは遺族の口出しは無用となる。それは、遺族は、周到な用意ができないままに混乱をきわめているところに、行事を手際よく進める必要に迫られるからである。自分たちの手にはあまるのであるから、葬儀社にゆだねるしかないのである」
また、葬祭業が本格的に成立、展開するのは、明治20(1887)年頃からのことであると指摘しつつも、著者は「ただ、それも東京や大阪などの大都市にかぎられていた。それも、特権階層の大規模な葬儀にかぎられていた。そこでは、専門の人足をつかった葬列が行われ、その人足手配が葬具の提供とともに葬儀社の業務の中心であった。納棺や葬儀の進行、会葬者接待などサービス業的な要素がでてくるのは、昭和初期のころである。それも、今日的な全面にわたっての代行請負が発達するのは、昭和30年代以降のことである。つまり、日本の都市化、経済の高度成長につれてのことなのである」と述べています。
さらに、「葬儀が遺族の手にあまるのは、今も昔も同じことである」として、著者は以下のように述べます。
「その場合は、『葬式組』が機能する。葬式組とは、便宜的な総称で、ところによって葬連組といったり葬式講中といったり、あるいは隣組といったり葬い組といったり、まちまちである。近隣の家々による相互扶助組織にほかならない。家数は、これもまちまちであるが、だいたい10軒以上、20軒ぐらいまでであろうか。これは、諸役を割りふったときに必要な数で、台所での賄い方もあるから1軒から男女ひとりずつの出夫例が多い。農作業での結や祭礼での頭屋組(当屋組)などの組織と重なるところもあるし、それとは別なところもある」
『古事記』(上つ巻)の天若旧子のくだりには、天若日子が高木の神が放った還し矢に当たって亡くなったとき、喪屋が作られましたが、その場面に青ヶ島のマツゲを想起させる掃(ほうき)が出てきます。また、哭女(泣き女)も出てくることから、著者は「青ヶ島の葬送儀礼の伝統は、遠く古代、あるいは神代にまでさかのぼれるのではあるまいか」と推測します。これは、青ヶ島の助役も務めた古神道研究家の菅田正昭氏の見解でもあるそうです。
2「通夜と葬送」では、「イエの観念と御魂移し」として、著者は述べます。
「昭和天皇が崩御されたときも『殯』という行事次第があった。詳しいことはわからないが、宮内庁に永く勤務し、昭和天皇の御葬儀でも端役をつとめた人に聞いたところでは、喪屋に安置された御遺体のおそばで当時の皇太子さまが夜籠りをされた、という。それによって天皇の御魂が生きたまま移譲される、とみるのは妥当であろう。そして、身分の上下なく、死者の『御魂移し』はイエの永続を願うところで共通する、とみるのも妥当であろう」
続いて、著者は「御魂移し」について以下のように述べます。
「その意義からしても、血縁の濃い者だけでの秘儀であるべきなのだ。イエの観念が強い民族社会なるがゆえに、根づいた通夜行事なのである。たぶん、これが共通するのは韓国ぐらいではあるまいか。韓国の葬儀習俗では、『泣き女』がことさら注目されるが、それは出棺前のこと。通夜儀礼は、血縁と近隣の者だけで行われる習慣が伝えられているのである」
「作法のおおもと」として、著者は「ひとつの作法にこだわるべきではない。我を通す余地もない」と訴え、さらに以下のように述べるのでした。
「『郷に入れば郷にしたがえ』、という諺もあるではないか。その地域やその社会の長老たちが先に進むはずであるから、それを見て習えばよろしいのだ。要は、追悼の気持ちをあらわすことにある。作法の細部に神経をはらうのも大事だが、それだけではすむまい。心のなかで『南無阿弥陀仏』とか『南無妙法蓮華経』とか『とう神えみ神、祓えたまえ清めたまえ』と、その式にあわせて唱えながら別れを次げる。あるいは、声にはださずとも、『ありがとう』とか『さようなら』を告げる。あとは全体の流れにしたがう。それが、もっとも丁寧な作法といえるのである」
この作法についての著者の考え方には、わたしも賛同します。
3「喪・年忌」は、本書の最後に取り上げられるテーマです。
著者は「かつて、まつりといったのは、葬送儀礼以外の行事すべてを指してのことであった。年忌もまた、まつりなのであった」として、さらに述べます。
「まつりを行い、まつりを伝える意義については、すでに何度か問いかけた。しかし、その意義をひとつにかぎって説くわけにはゆかない。日本の伝統的なまつりには、宗教的な規範や規制がきわめて希薄である。そこに祀られるカミやホトケの名前もわからないままに行事にたずさわることだって少なくない。が、それは『共』(共同体)のまつりでのこと。私的なまつりである年忌では、そうはゆかない。もとより、祀る対象は特定されている。それを戒名や位牌で、さらにたしかめることになる。と同時に、そこに参列する者は、自分との関係をもしかとたしかめることになる。年忌というまつりは、死者の霊をなぐさめるだけでなく、人びとが血縁的な系譜を共有する意義をもっているのだ」
本書は博学で知られる著者が「文庫書き下ろし」として上梓しただけに、非常に内容の濃い一冊となっています。身近なしきたりを民俗学的な見地から解き明かすことから始まり、冠婚葬祭や年中行事を「なぜ行うのか」「どのように行われてきたのか」「どう向き合えばいいのか」といった問題まで広げて考えています。冠婚葬祭を業にしているわたしは、本書を読みながら「なるほど」と納得することの連続でした。また、互助会の本来の意味や役割についても考えさせてくれる内容でした。これから、何度も読み返したい名著です。冠婚葬祭業界、互助会業界の方はぜひ一読をおススメします!
