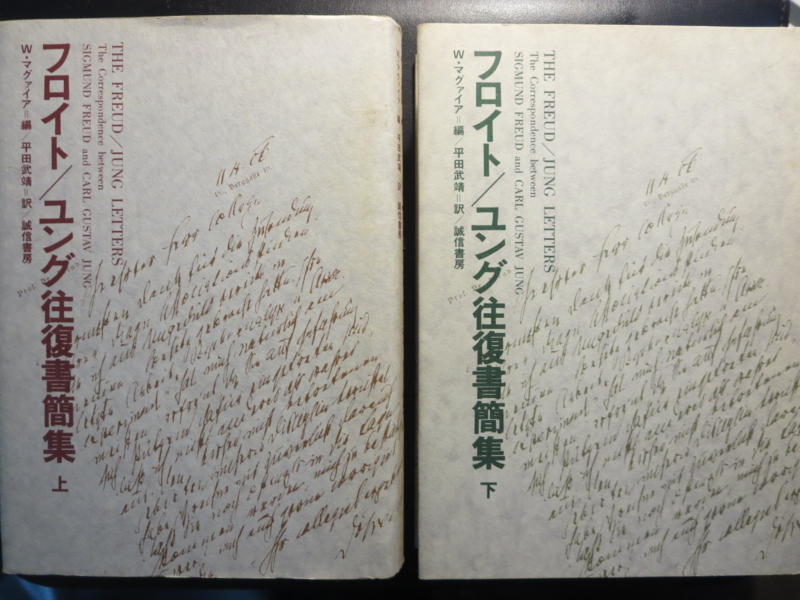- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1283 心理・自己啓発 『無意識の構造』 河合隼雄著(中公新書)
2016.07.22
『無意識の構造』河合隼雄著(中公新書)を読みました。 この読書館でも紹介した『コンプレックス』と並んで、著者の代表作です。 1977年に刊行された本ですが、今日まで版を重ねています。
著者は日本を代表する心理学者として知られ、京都大学名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授などを務めました。文化功労者であり、元文化庁長官でもあります。著者は1928年兵庫県に生まれました。52年京都大学理学部卒業。65年ユング研究所(スイス)よりユング派分析家の資格を取得。専攻は臨床心理学で、その立場から88年に日本臨床心理士資格認定協会を設立し、臨床心理士の資格整備にも貢献しました。2007年、脳梗塞のため、奈良県天理市内の病院で逝去。79歳でした。
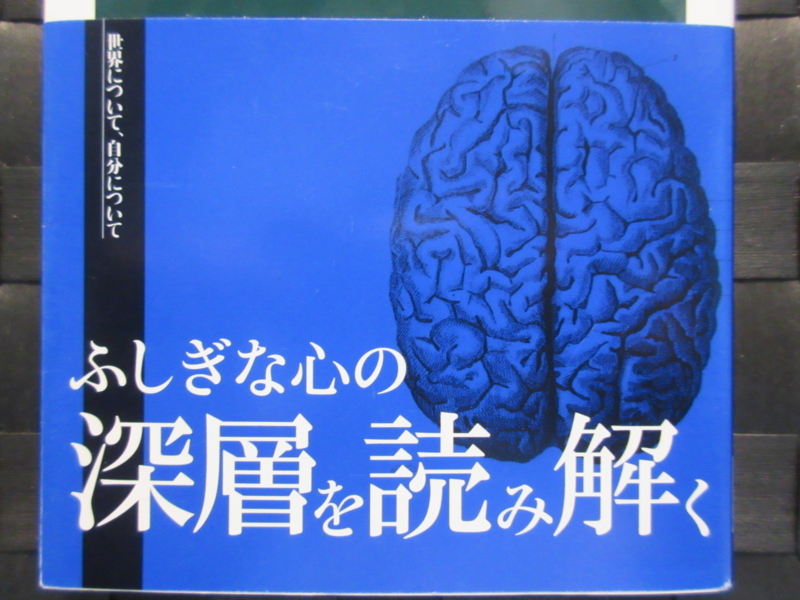 本書の帯
本書の帯
本書の帯には脳のイラストとともに、「世界について、自分について」「ふしぎな心の深層を読み解く」と書かれています。 また、カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「私たちは何かの行為をしたあとで、『われ知らずにしてしまった』などということがある。無意識の世界とは何なのか。ユング派の心理療法家として知られる著者は、種々の症例や夢の具体例をも取り上げながらこの不思議な心の深層を解明する。また、無意識のなかで、男性・女性によって異性像がどうイメージされ、生活行動にどう現われるのか、心のエネルギーの退行がマザー・コンプレックスに根ざす例なども含めて鋭くメスを加える」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
(1)無意識へのアプローチ
1 無意識のはたらき
2 コンプレックス
3 心の構造
(2)イメージの世界
1 イメージとシンボル
2 心的エネルギー
3 夢
(3)無意識の深層
1 グレートマザー
2 元型
3 影
(4)無意識界の異性像
1 ペルソナと心
2 アニマ
3 アニムス
4 男性と女性
(5)自己実現の過程
1 自我と自己
2 自己のシンボル
3 マンダラ
4 個性化の過程
「あとがき」
「参考文献」
(1)「無意識へのアプローチ」の1「無意識のはたらき」では、ヒステリーの治療を通じて、その心理的なメカニズムを明らかにしたのは、精神分析の創始者であるフロイトであることが示されます。フロイトが、当時ウィーンの開業医であったブロイヤーとともに『ヒステリー研究』を出版したのは、1895年のことですが、その中には5人の症例を通じて、ヒステリーの心理が解明されていることが紹介されます。
フロイトは、ヒステリーの原因となる体験を「心的外傷」と呼びました。それはあたかも古傷が痛みをもたらすように、本人の気づかぬ作用をとおして障害をもたらすからです。そして、このような外傷体験とそれに伴う情動を意識の外に追いやることを「抑圧」と名づけました。著者は「ヒステリーの治療は、抑圧されている外傷体験を見いだし、意識化することが大切なのである」と述べています。
フロイトは『ヒステリー研究』を出版した後、無意識の研究を続けました。そして、「無意識に到る王道」としての夢に注目し、1900年に『夢判断』という書物を出版します。この名著も出版された当時は誤解や反発に遭ったそうで、600部が売りつくされるのに8年もかかったといいます。 フロイトとユングの出会いについて、著者は以下のように書いています。
「そのころ、ユングはスイスのチューリッヒ大学の助手で新進気鋭の精神医学者として知られていた。彼もフロイトとは独立に、ヒステリーやその他の精神病の患者などと接することによって、無意識の心的過程の存在の重要性に気づき始めていた。そのとき、彼はフロイトの『夢判断』を読んですっかり感激したのである。その後、両者のあいだに手紙のやりとりがあり、とうとう、ユングは夫人と共にフロイトをウィーンに訪問した」
続けて、フロイトとユングの出会いが以下のように綴られます。
「1907年3月3日、日曜日(一説には2月27日とも言われている)、ユング夫妻はフロイトにウィーンの駅頭に迎えられた。ユングの思い出話によると、2人はただちに意気投合し、精神分析のことについて13時間も休みなしに話し合ったということである。ユングは学問的な話に熱中するあまり、フロイト夫人や子どもに社交的な話しかけをするのを忘れてしまい、フロイトの家族を呆れさせたという。先覚者に会ってユングの感激は大きかったし、質問したいことも山積していたであろう。フロイトは自分の業績について始めて、アカデミックな領域にいる、ユダヤ人でない人に認められた嬉しさでいっぱいであったろう」
このあたりは、わたしのブログ記事「危険なメソッド」で紹介した映画に詳しく描かれています。著者は、無意識研究の2人の巨人について、さらに述べます。
「フロイトもユングも初期の頃は催眠を治療によく使っていたが、2人とも、後にはこの療法をやめてしまっている。それは患者が分析家に依存心を起こしやすく、そのために多くの障害が生じることが解ったのと、たとい催眠によって心的外傷を想起できても、催眠が覚めると忘れてしまってなんの役にも立たぬことがあるためである。しかし、催眠は無意識の探究には大いに役立つものではあった。日常生活の中で、ひょっともの忘れをしたり、思いがけない失敗をしたりするが、ここにも無意識のはたらきが顕現されていることが明らかになった」
フロイトのもとに集った人々の中から、まず離反したのはアドラーでした。 アドラーもユダヤ人でしたが、フロイトの性衝動の重要視にあきたらず、人間の権力衝動のほうを重視して、異なる説を立てたのでした。フロイトの「構神分析学」に対して、アドラーは自分の説を「個人心理学」と呼び、ユングは自分のそれを「分析心理学」と呼んで、おのおの区別しています。
また、アメリカにおける深層心理学の動きについて、著者は述べます。
「アメリカにおいて特徴的なことは、それがアカデミックな領域に容易に滲透してゆき、大学内の精神科医や心理学者がその学説を大いに取り入れたことである。次に、アメリカにおける精神分析家の中で、フロイトがむしろ生物学的なモデルに頼ろうとするのに対して、文化・社会的な面を強調する、いわゆるネオフロイト派と称する人たちが出てきたことである。ホーナイやフロム、サリヴァンなどがこの中にはいる人たちである。 その他細かく分けると、いろいろな学派に分類できるが、人間の心を層構造的にとらえ、無意識の存在を重要と考える点を共通としていることから、それらは総称して深層心理学と言われることもある」
2「コンプレックス」では、フロイトがコンプレックスに注目していったことが指摘されます。フロイトは、あらゆるコンプレックスの中で最も根源的なものとして、エディプス・コンプレックスを仮定するようになりました。エディプスは有名なギリシャ悲劇の主人公です。主人公のエディプスがそれとは知らず、父親を殺害し、母親と結婚する物語です。この恐ろしい事実を始めて知ったとき、エディプスの母であり妻であるイオカステは自殺し、エディプスは自分の運命を呪って、自らの両眼を潰し、盲目となって放浪の旅に出るのでした。著者は以下のように述べます。
「フロイトは、この物語に示されているような、男性がその母親を愛の対象とし、父親を殺そうとするような願望が、人間の無意識内に存在すると考えたのである。女性の場合は、母親を殺して父親と結婚しようとする願望であり、これもギリシャ悲劇の主人公の名前をとって、エレクトラ・コンプレックスと呼ばれている。(エディプス・コンプレックスの名称の中に、広義にはエレクトラ・コンプレックスも含むことが多い。)」
フロイトはエディプス・コンプレックスを、もっとも根源的なものと考えましたが、これに反対したアドラーは彼独自の説を立てて、フロイトから離反して行きました。アドラーの周囲には社会主義者が多くいたこともあって、早くから、彼は社会的な観点を精神分析の考えの中に入れこもうとしたのでした。著者は以下のように述べます。
「アドラーは、人間にとって性の衝動よりも、権力を求める欲求のほうがより根源的であると考えた。彼は最初『器官劣等』という考え方を提出した。すなわち、人間は誰しもなんらかの劣等な身体器官をもち、それを補償して優越性を求めようとする衝動が、人間の心の中にはたらくと考えたのである。器官劣等の考えそのものは、アドラーは後年あまり強調しなくなったが、劣等感の存在は人間にとって根源的なものとして重要視した」
3「心の構造」では、「不可解なおそれ」として以下のように書かれます。
「朝起きて新聞を見ているうちに、何となくいらいらしてくるときがある。いくら考えても原因が解らないときもある。しかし、あとで反省してみると、新しく大臣になって騒がれている人の年齢が自分と同じであることを知った途端に、劣等感コンプレックスが刺戟されて、自我存在が多少おびやかされていたことが判明するときもある。われわれがいらいらさせられるとき、われわれはなにかを見とおせずにいるのだと考えてみると、まず間違いはない。自我の光のおよばないところで、なにかがうごめいているのである」
このような「不可解なおそれ」を解明すべく研究を続けたのが、ユングでした。彼は、フロイトと強調して精神分析学の確立のために努力したわけですが、のちに彼らは異なる学説を立てました。その理由の1つに、フロイトが神経症者の治療を主としていたのに対して、ユングは精神分裂病者に接することが多かったことが挙げられます。 ユングは分裂病者を理解するために、神話や伝説、宗教書などを読み漁りました。彼は、病者の語る妄想の内容とそれらの間に、何らかの類比性が存在すると感じたのです。
(2)「イメージの世界」の2「心的エネルギー」で、著者は以下のように、フロイトとユングの決定的な違いについて述べています。
「人間の仕事をみてゆくとき、そこに使用された心的エネルギーは結局のところ、性的なエネルギーに還元されるとし、それをリビドーと名づけたのが、フロイトである。彼が多くの著作によって明らかにしたように、たしかに人間の行う多くの仕事の背後に、性的なエネルギーが動いている。しかし、すべてのエネルギーの根源が性的なものであると考える必要は、ないのではなかろうか。物理学において、エネルギーという概念はあくまで量的なものとして用いられており、それはたしかに位置のエネルギー、熱エネルギーなどに変化してゆくが、どれが根源的であるなどと考えないところに、その特徴があると考えられる。心的エネルギーもむしろ、これと同様に考えるべきではないだろうか。ユングはこのような考えに立って、心的エネルギーを性的エネルギーも含めた一般的な概念とした。彼はそのような考えによって、1912年に『リビドーの変遷と象徴』という本を出版し、ここに彼とフロイトとの離別は決定的なものとなったのである」
ユングといえば、シンボルの問題が切っても切り離せません。 「シンボルの形成」として、著者は以下のように述べます。
「集団の中で創造的な能力のある個人が、なんらかのシンボルを見いだすと、集団の成員はそのシンボルによって新たなエネルギーを湧き立たせることになる。これは宗教におけるシンボリズムについて考えてみると真に明白である。初期のキリスト教における十字架のシンボルが、どれほど大量の心的エネルギーを民衆の中に動かしえたかは、誰しも知るとおりである。しかし、その反面、シンボルの恐ろしさもわれわれはよく知っている。戦争中の日の丸が、どれほど多くの民衆のエネルギーを、無意味なことに消費させるのに役立ったかを、われわれは体験を通じて知っているのである」
この読書館でも紹介した『人間』で、哲学者のカッシーラーは、「人間はただ物理的宇宙ではなく、シンボルの宇宙に住んでいる。言語、神話、芸術および宗教は、この宇宙の部分をなすものである」と喝破しています。 たしかに、わたしたちはシンボルやイメージの世界に生きていると言えるでしょう。それらの力は19世紀の合理主義によって弱められましたが、著者は以下のように述べます。
「20世紀後半に生きる現代人としての反省は、19世紀の合理精神が息の根を止めたシンボルやイメージを、いかにして再生せしめ、われわれの心の均衡を回復するかという点にかかっている。われわれはできるかぎり明確な概念をうちたて、それをうまく操作することによって自然科学の殿堂をうちたててきた。しかし、そこに生じてきたテクノロジーは最近になって、むしろ人間の生命を絶えさせるようなはたらきを示している。ここにおいて、われわれは概念化の際に無視され、背後に押しのけられた存在にも目を向け、世界をもう一度、トータルな存在として見なおす努力を傾けねばならないのではなかろうか。そのためには、われわれの内面に向けられたイマジネーションの力をもっと発揮させるべきであると思われる」
このような点について、宗教学者のエリアーデは、名著『イメージとシンボル』の中で次のように述べています。
「今日、われわれは、19世紀が予感すらできなかったあることを理解しつつあるのである。つまり、シンボル、神話、イメージが精神生活に必須な資であること、われわれはそれらを偽装し、ずたずたに切断し、その価値を下落させることはできても、根絶やしにすることはけっしてできないということを学びつつあるのだ」
このエリアーデの言葉を受けて、著者は以下のように述べます。
「かくて、われわれはシンボルの宝庫としての無意識の世界に興味をもち、そのことはわれわれ自身の全体性の回復へとつながってゆくのである。文化現象としてのシンボルに対して、われわれ個人のシンボルということも重要なこととなるが、そのためには、夢を観察することがもっとも適切な手段であると考えられる。夢は無意識界から意識へと送られてくるメッセージであり、まさにシンボルの担い手なのである」
3「夢」では、哲学者のショーペンハウエルの「夢においては、だれもが自分自身のシェークスピアである」という発言を紹介し、著者は「たしかに夢は自分自身によって演出され、演じられたドラマであると見ることができる」と述べます。そして、夢は劇と同じような構成をもち、次のような4段階に分けられるといいます。
(1)場面の提示
(2)発展
(3)クライマックス
(4)結末
著者によれば、夢で味覚や嗅覚がはたらくことは稀ですが、ときには存在するといいます。イメージがなくて声だけが聞こえるときもあるし、映画のナレーションのような形で「声」が聞こえることもあるというのです。全盲の人には触覚や聴覚による夢体験が存在するそうです。
(3)「無意識の深層」の1「グレートマザー」では、「母なるもの」として、以下のように書かれています。
「われわれ人間は、その無意識の深層に、自分自身の母親の像を超えた、絶対的な優しさと安全感を与えてくれる、母なるもののイメージをもっている。それらは外界に投影され、各民族がもっている神話の女神や、崇拝の対象となったいろいろな像として、われわれに受けつがれている。ユングはそれらが人類に共通のパターンをもつことに注目し、母なるものの元型が人間の無意識の深層に存在すると考えた」
グレートマザー像の典型として、著者は地母神を最初にあげていますが、それが崇拝の対象となるもっとも大きい要素は、それが持つ死と再生の秘密にありました。さらに著者は述べます。
「グレートマザーこそは、死と再生の密儀が行われる母胎なのである。そして、ある1人の女性が母性の体験をもつことの底には、この密儀が常に存在しているのである。ユングの高弟の1人ノイマンは、『グレートマザー』という大著の中で、女性の神秘が、初潮、出産、授乳を通じて体験されることを明らかにしている。その最初に存在する初潮ということは、まず自然に生じ、女性はそれを受け入れることによって体験される。それは、いつとなく、『やってくる』ものであって、自ら決意して行うものではない」
フロイトが個人的な親子関係を基にして、エディプス・コンプレックスを強調するのに対して、ユングが普遍的な母なるものの存在を主張し、フロイトから離別した根底には、このような考えの相異が存在していたのです。
2「元型」では、ユングが強い影響を受けた2人の人物が紹介されます。1人は、スイスの歴史家、文化史家であるヤーコプ・ブルクハルトです。バーゼルにある大教会の説教師の子として生まれた彼は、はじめは神学を学びますが後に歴史学に転じ、1840年からベルリンに滞在し、ランケ、ドロイゼン、ヤーコプ・グリムなどの大家に学びました。彼は人間の典型的なイメージを「原始心像」と呼び、ユングもこの言葉を使っていました。
もう1人は、スイスの文化人類学者、社会学者、法学者であるJ・J・バッハオーフェンです。本業は法学者でしたが、古代法の研究を通して古代社会についての造詣を深め、これをもとにした著作を発表して文化人類学に影響を与えました。特に、古代においては婚姻による夫婦関係は存在しなかったとする乱婚制論や、母権制論(1861年)を説きました。彼らは宗教や神話の研究に専念しましたが、明らかにユングに対して強い影響を与えています。ブルクハルト、バッハオーフェン、ユングの3人はいずれもイメージの世界への強い関心を抱いていました。彼らについて、著者は「概念を明確にして、それを組み立ててゆくことよりも、その背後に存在するイメージの生命のほうに心を惹かれてひかれた人である」と表現しています。
元型について関上げる際に、「文化差」というものが重要になります。 神話や昔話には、世界中に共通するパターンが存在しますが、国や地方による差も生じてきます。たとえば、小沢俊夫編『日本人と民話』には、いろいろと日本の民話の興味深い特徴が述べられているとして、著者は以下のような興味深いエピソードを紹介しています。
「ソ連の学者チストフが日本の『浦島太郎』の物語を、自分の孫に話してやった体験を述べているところが面白い。チストフが竜宮城の美しさを描写したところを話しても、孫は全然興味を示さず、なにか別のことを期待している様子であった。そこで彼は孫になにを考えているのかを尋ねた。『いつ、そいつと戦うの?』というのが孫の答だった。彼は竜宮城にいる竜と主人公の浦島の戦いが始まるのを、いまかいまかと楽しみに待っていたのである」
(4)「無意識界の異性像」の1「ペルソナと心」では、冒頭に「ユングは夢の中に現われる異性像の元型を、アニマ(男性の心の中の女性)、アニムス(女性の心の中の男性)と名づけている」と書かれています。また、2「アニマ」では、著者は以下のように述べます。
「男性は一般に男らしいと言われているような属性をもったペルソナを身につけねばならない。彼は社会の期待に沿って、強くたくましく生きねばならない。そのとき、彼の女性的な面は無意識界に沈み、その内容が、アニマ像として人格化され、夢に出現してくると、ユングは考える。女性の場合はこの逆で、女らしいペルソナをもつために、男性的な面はアニムスとして無意識界に存在するという。このように、男性であれ女性であれ、潜在的可能性としては両性具有的であると考えるところが、ユングの特徴である」
また、「アニマの投影」として、著者は以下のように述べています。
「一般に男性はアニマ像を投影した女性と結婚し、それによってある程度のバランスを得て、男性として必要なペルソナを築きあげることに専念する。そのようなペルソナが堅固になった中年の頃になって、アニマの問題は内面のこととしてふたたび持ちあがってくる。といっても、しょせん、それは何かに投影されて顕在化してくることが多い。 アニマはペルソナと対立するものであるだけに、それは男性に対して、弱さやばかげたことを開発することを強いる面をもっている。中年になってから、他人から見るとばかげたことをやり始める人はわりにいるものである。アニマは女性にのみ投影されるとはかぎらないので、趣味や娯楽の世界に、アニマ体験が求められ、そこに転落してしまう人もある。これらの危険に満ちた体験を、自分のものとして統合しえた人は、より豊かな人生を生き、他人との暖かい関係を確立できるようになるのである」
(5)「自己実現の過程」の1「自我と自己」では、著者は述べます。
「自己はユングがその生涯をかけて取り組んできた問題とも言えるものであるが、彼自身も述べているように、東洋の思想との結びつきが濃い。それだけに、われわれ日本人にとって、アニマ・アニムスよりも体験されやすいということもできる」 また、「心の全体性」として、以下のように述べています。 「自我と影、ペルソナとアニマ・アニムスなど、人間の心のなかに対極性が存在し、それらのあいだに相補的な関係が存在していることが明らかである。ユングは常にこのような人間の心のなかの相補性に注目してきた。本書では触れなかったが、彼の有名な内向―外向の考えも、そのような線に沿った考え方である。内向的な人と外向的な人が案外に良い友人であったり、夫婦であったりすることは多いのである」
2「自己のシンボル」では、「老賢者」が取り上げられます。
「自己が人格化されるとき、それは超人間的な姿をとり、老賢者(wise old man)として顕現する。このような人格像は昔話によく現われ、昔話の主人公が困り果てているときに、助言を与えたり、貴重な品を与えたりして消え去ってしまう。その知恵は常にまったく常識と隔絶しており、それに従ったものは成功するが、妙に人間の知恵をはたらかして疑ってかかったりしたものは失敗してしまう。 老賢者のイメージは東洋人には、むしろなじみの深いもので、仙人の話とか、あるいは老子などというのもその典型であろう。老子その人は実在したかどうか不明であるが、中国人や日本人のもつ老賢者のイメージが年と共に重積され、1人の人格像として形成されていったものとみることができる」
一方、ユングは「老賢者」とともに「始源児」にも注目しました。
「自己のシンボルとして老人と同じくらい、幼児の姿が用いられる。同じものが老人となったり幼児となったりするところに、その逆説性がよく示されているが、幼児の姿として現われるときは、その未来への生成の可能性、その純粋無垢な状態などに強調点がおかれていると思われる。これらの幼児のなかには、すでに内面には老人の知恵をもったものもいて、自己のシンボルにふさわしいものである」
さらに、著者は「始源児」について以下のように述べます。
「このような子どもの元型とも言うべき姿に、ユングは始源児という名を与えている。始源児は必ずしも知恵ばかりではない、超越的な力を有しているときもある。たとえば、ギリシャ神話の英雄へラクレスは幼児のときに、2匹の蛇を退治してしまう。わが国の昔話の英雄、桃太郎や一寸法師をこれらの中に数えてもいいだろう。夢にこのような超能力をそなえた幼児が出現するときがある。そのとき、その幼児は『小さい』ことを表わすのではなく、むしろ可能性の大きさを示すものであろう」
そして、「対立物の合一」として、著者は以下のように述べます。
「男性性、女性性といっても高いもの、低いものがあるので、それらの全体の結合という意味で、2組の結婚式が同時にあげられるというテーマもときに出現する。統合への努力がまだ不十分というわけで、花嫁、あるいは花婿の不在の結婚式というのが夢に生じることも、ちょいちょいある。あるいは結婚式をあげるはずで、相手を式場に待たしておきながら、自分は時間とか場所をまちがって、うろうろする夢もある。西洋の昔話に、結婚のテーマが多いと述べた。もちろん、わが国の昔話にもあるが、どうもその率が少ないように感じられる」
最後に、「共時性(シンクロニシティ)」の問題が取り上げられます。 ユングは「意味のある偶然の一致」を重要視して、これを因果律によらぬ一種の規律と考え、非因果的な原則として、共時性(synchronicity)の原理なるものを考えました。著者は、以下のように述べています。
「自然現象には因果律によって把握できるものと、因果律によっては解明できないが、意味のある現象が同時に生じるような場合とがあり、後者を把握するものとして、共時性ということを考えたのである。共時性の原理に従って事象を見るとき、なにがなにの原因であるかという観点ではなく、なにとなにが共に起こり、それはどのような意味によって結合しているかという観点から見ることになる。われわれ心理療法家としては、因果的な見かたよりも、共時性による見かたでものを見ているほうが建設的な結果を得ることが多いようである」
 わが書斎のユング心理学コーナー
わが書斎のユング心理学コーナー
以上、本書は200ページにも満たない新書本ですが、ユングの心理学を学ぶ上では恰好の入門書であると言えます。「あとがき」に、著者は「小冊子の範囲内で、相当深いところまで下降をこころみるので、読者が潜水病にかからないように、息抜きになるようなことも書いておいたつもりである」と記しています。こんな洒落たことを「あとがき」に書ける著者はなんてチャーミングな人だったのかと思いました。