- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.05.17
『儀式論』の参考文献として、『心理学と宗教』C・G・ユング著、村本詔司訳(人文書院)を読みました。この読書館でも紹介した『トーテムとタブー』、『幻想の未来/文化への不満』、『人はなぜ戦争をするのか』を読み、フロイトの儀式についての考え方を理解しましたが、今度はユングの儀式観を知るために、総計600ページ近い本書を読んだのです。
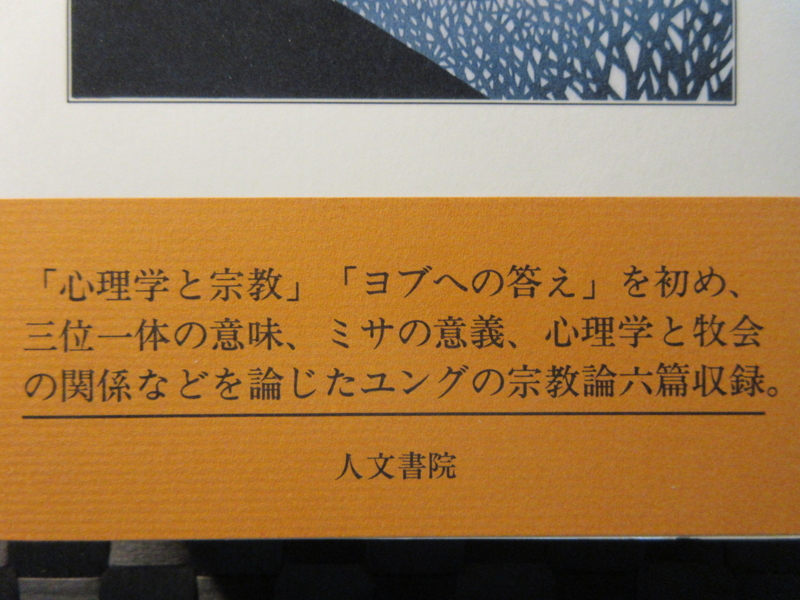 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「『心理学と宗教』『ヨブへの答え』を初め、三位一体の意味、ミサの意義、心理学と牧会の関係などを論じたユングの宗教論六篇収録」と書かれています。 本書は、フロイトと並んで20世紀を代表する心理学者であるユングが宗教を彼の心理学における主題とした著作です。もともとは『ユング全集』11巻に「東西の宗教の心理学」として収録されているものですが、そのうちの第一部「西洋の宗教」をほぼ収録したものである。紙数の関係で「V・ホワイト『神と無意識』への序文」「Z・ヴェルブロフスキ『ルシフェルとプロメテウス』への序文」「修道士クラウス」の論文は抜けています。このうち「修道士クラウス」は林道義訳『元型論』(紀伊國屋書店)に収録されています。
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
心理学と宗教
一 無意識的な心の自律性
二 教義と自然発生的象徴
三 自然発生的象徴の歴史と心理学
三位一体の教義にたいする心理学的解釈の試み
前書き
第一章 キリスト教以前において三位一体の観念に対応するもの
第二章 父と子と聖霊
第三章 信経
第四章 三つの位格の心理学的解明
第五章 第四のものの問題
第六章 結論
ミサにおける転換象徴
第一章 導入
第二章 転換儀礼の個々の部分
第三章 転換の神秘に対応するもの
第四章 ミサの心理学
心理療法と牧会の関係について
精神分析の牧会
ヨブへの答え
「注」
「訳者あとがき」
「人名・原典索引」
「事項索引」
「訳者あとがき」によれば、本書の内容は3つのカテゴリーに分けられます。第一は、心理学的宗教論とも呼ぶべきもので、心理学、特にユングの分析心理学の立場からすれば、宗教という現象はいかなるものとして理解されるかということを主題としています。「心理学と宗教」(1940年)がそれです。第二は、ある特定の宗教の教義や儀礼、教典を自分の心理学的立場から解釈したものです。「三位一体の教義にたいする心理学的解釈の試み」(1942年)、「ミサにおける転換象徴」(1942年)、「ヨブへの答え」(1952年)がこれに含まれる。ここで問題になっている宗教とは、もちろんキリスト教のことです。第三は、心理療法と牧会の関係を論じたもので、「精神分析と牧会」(1928年)と「心理療法と牧会の関係について」(1932年)がこれに当たります。
宗教、特にキリスト教は、ユングにとって大きな問題でした。 訳者の村本詔司氏は「訳者あとがき」で以下のように述べています。
「牧師の息子として生まれ育ったユングにとって、キリスト教は、父親を通じて耐えがたい幻滅の源泉であったにもかかわらず、あるいはそれゆえに、一生かかってその意味を追求しなければならない、いわば宿命のようなものであった。はじめにユング心理学があってそれがキリスト教に当てはめられたものではなく、反対に、はじめにキリスト教があってその謎を解明するためにユング心理学が生まれ、展開したといっても必ずしも言い過ぎではない。いわば、彼の心理学は、キリスト教に対する彼なりの応答なのである」
「心理学と宗教」の一「無意志的な心の自律性」で、まず、ユングは宗教の定義に言及します。そこで彼は、 この読書館でも紹介した名著『聖なるもの』を書いたルドルフ・オットーの説を紹介します。
「宗教はそれを表わすラテン語から明らかなように、ルドルフ・オットーがいみじくもヌーメン性 Numinosum と呼んだものを注意深く良心的にみつめることです。このヌーメン性とは力動的な存在もしくは作用で、意志の行為では惹き起こせません。反対に、その作用が人間という主体を捉え、支配するのです。人間は、その作用の創造主であるよりはむしろ犠牲になっています。ヌーメン性は、その原因が何であれ、主体の条件であり、主体の意志から独立しています。いずれにせよ、宗教の教え[と一般的合意]が常に、そして到る所で明らかにしているのは、この条件が個人の外にある原因に関係づけられなければならないということです。ヌーメン性は目に見える対象の属性か、それとも目に見えずに現存するものからの影響かのどちらかですが、それが意識にある特殊な変化を引き起こすのです」
しかしながら、実際の修行や儀式となると、ある種の例外があるとして、ユングは以下のように述べています。
「大部分の儀式が行われる理由はただ1つ、一定の呪術的な方策、たとえば、祈願、瞑想、呪文、犠牲、ヨーガ、苦行などによってヌーメン性の作用を意図的によびおこすことです。しかし外的で、客観的な[神的]原因への信仰は常にこのような行為から出発しているのです。たとえば、カトリック教会が秘跡を授ける目的は、信者に霊的な祝福を与えることです。しかしながら、この行為は結果として、疑いなく神の恩寵の現存を呪術的な手続によって強制するものであるので、次のように論じたとしてももっともだといえます。すなわち、誰も秘跡の行為によって神の恩寵が現存するように強いることはできないにもかかわらず、神の恩寵は必ずそこに現存しています。なぜなら、秘跡は神のつくられた制度だからです。神がこれを支持するつもりでなかったら、制定しなかったでしょう」
ユングによれば、無意識から生じる予測できない危険な傾向から身を護る呪術的な儀式は無数にあります。ユングは述べます。 「人類が現われて以来、抑制されない、勝手きままな、『超自然的な』影響に一定の形式と掟で制限を加えようという顕著な傾向が存在してきました。そしてこの過程は、儀式、制度、信念の増加という形で歴史において続けられてきました。最近の二千年では、キリスト教会の制度が、これらの影響と人間の間を媒介し、防御する機能を引き受けているのが分かります」
続けて、ユングは以下のように述べています。
「中世の教会文書では、時折、神の影響がたとえば夢において生じることがありうるということが否定されていません。しかしこの立場はそれほど強固には主張されず、教会は、個々の啓示が真正のものか否かを決定する権利を留保しています。事実、ある種の夢が神から出てきているのは否定できないということを教会は認めていますが、それにもかかわらず、教会は、夢に真剣に取り組むことにたいして気乗りがなく、露骨に反感さえ示しています。その一方では、直接の啓示を含んでいる夢もあるのを認めています。それゆえ、少なくともこの観点からすると、最近の数世紀に生じた精神的態度の変化は、教会にとってはまったく歓迎できないものではありません。夢や内的経験を真剣に考慮するのに相応しい以前の内省的な態度が効果的に抑圧されてきたからです」
ここでユングは、プロテスタンティズムに言及して述べます。
「プロテスタンティズムは、これまで教会が注意深く立ててきた多くの壁を取りこわし、個人の啓示が解体と宗派分立を促進する効果をもっているのを直接的に経験しはじめました。教義の棚が壊され、儀礼の権威が失われてしまうとすぐ、人は内的経験に直面しはじめました。その際、キリスト教でも異教でもその宗教経験の比類のない本質である教義と儀礼からこれまで与えられてきた保護と導きはもはや存在していませんでした。プロテスタンティズムは主として、[伝統キリスト教の]微妙な陰影のすべて、すなわち、ミサ、告解、典礼の大部分、聖職者の身代わり的意義を失ってしまったのです」
三「自然発生的象徴の歴史と心理学」では、宗教における象徴について、ユングは以下のように述べています。
「中世の教会の円花窓に勝利のキリストが見られたなら、これは、キリスト教の祭儀の中心的な象徴だと考えても間違っていません。同時に、人類の歴史に根ざしたどんな宗教も、たとえば、人類が発展させた政治形態と同じく、彼の心理の表現であるということも考えられます。もし、この方法を、人々が夢や幻で見たり、『能動的想像』によって発展させてきた現代のマンダラに適用するならば、マンダラは、『宗教的』と呼ばざるをえないある種の態度の表現だという結論に到達します」
続けてユングは、宗教や神の本質について述べています。
「宗教は、ポジティブであれ、ネガティブであれ、最高の、あるいは最強の価値への関係です。その関係は、非意志的であるとともに、意志的でもあり、つまり、わたしたちは、自分を無意識的に捉えている価値[それゆえ、エネルギーを負荷された心的要因]を意識的に受け入れることができるのです。わたしたちの体系の中で最大の力をもつ心理学的事実は神として機能しています。それは常に、神と呼ばれている圧倒的な心的要因だからです。神が圧倒的な要因であることをやめるとすぐに、それはただの言葉になります。神の本質は死に、神の力は消えてしまいます。どうして古代の神々は、その特権と人間の魂にたいする働きを失ったのでしょうか。それは、オリュンポスの神々の役目が終わり、新しい神秘が始まったからです。すなわち、神が人間になったのです」
「三位一体の教義にたいする心理学的解釈の試み」の第六章「結論」でも、ユングは宗教の本質についての自説を展開します。
「宗教は『啓示された』救済の道である。その観念は、いつでもどこでも象徴に表現されている前意識的な知の所産である。それらはたとえわたしたちの理性に把握されなくとも、それでも事実、働いている。というのは、わたしたちの無意識が普遍的な心的活動の表現として認めるからである。それゆえ、信仰だけで充分なのである。ただし、信仰があればの話ではあるが。しかし、合理的な意識を拡大し、強化すると必ず、わたしたちは象徴の源泉から離れてしまうことになる。合理的意識があまりにも強くなりすぎると、象徴の理解が妨げられる。これが今日の状況である。車輪を逆回転させて、『自分が知っているものは存在しない』というふうに無理して言い聞かせることはできない。だが、象徴が本来、何を意味しているかは、その気になれば、考えることぐらいはできよう。このようにして、わたしたちの文化のたぐいまれな宝が保存されるだけでなく、そのシンボリズムが異様であるためにわたしたちの『理性』から消え去っていた昔からの真理への新たな道がわたしたちに開かれるのである」
続いて、ユングはキリスト教にとっての最大の問題ともいえる点に言及し、象徴の意味について以下のように述べます。
「どうして一人の人間が神の子として乙女から生まれることができるのか。これは実際、理性にとって一種の侮辱である。だが、殉教者ユスティヌスは彼の同時代人たちに、彼らの英雄たちについてもまさに同じことが言えることを明らかにして、それによって多くの人々の耳を傾けさせたのではなかったか? このことが起こったのは、当時の意識にとってこのような教義が、今日とはちがって、それほど聞きなれないことではなかったからである。今日では、このような教義には誰も耳を傾けはしない。というのは、わたしたちが慣れ親しんでいる世界には、このような主張に対応するものが何もないからである。しかしこれらのことをあるがままに、すなわち、象徴として理解するのならば、わたしたちはその深淵のように深い英知に感嘆するよりほかなく、それらを保存してきただけでなく、教義としても発展させてきた直観に感謝したくなる。今日の人間には、自分が信仰するうえで助けになる理解が欠けているのである」
「ミサにおける転換象徴」の第三章「転換の神秘に対応するもの」では、ミトラス教の雄牛を運ぶ儀式を紹介し、これはその年の豊饒を祈願してなされる雄牛の供犠であり、供犠行為の典型的な表現であるとともに、キリスト教のミサとよく似ていることを指摘されます。そして、著書は以下のように述べています。 「夭折し、嘆き悲しまれ、復活する近東の神々の伝説や祭儀は数多く存在してキリスト教のミサに対応しており、ミトラ教の祭儀はその一例にすぎない。これらの宗教を少しでも知っている者なら誰にとっても、象徴タイプや観念がキリスト教のそれらといかに深く関わりあっているかは疑問の余地がない。原始キリスト教や初期の教会と時代を同じくする異教に充満していたのは、このような表象、およびそれらに関する哲学的思索であった。こうした背景のもとにグノーシスの哲学と思惟が繰り広げられるのである」
ここで、「グノーシス」という言葉が登場しています。 わたしは、、拙著『ユダヤ教vsキリスト教vsイスラム教』(だいわ文庫)の中でグノーシスについて説明しました。ギリシャ語の「知識」を意味するグノーシスとは、一言でいえば、「この世界は原理的に欠損を抱えている」という思想です。グノーシスは、究極の知識として現われ、人間の魂を根本から変えて、この世から永遠の光へ近づけることができるとされました。 歴史的に認められたグノーシスがキリスト教の登場に密接に結びついている一方、それより以前にユダヤ教の神秘的な思弁の中にグノーシス思想の萌芽が存在していることがわかります。それは後に、エッセネ派のようにカバラを生み出す一因となりました。イスラム教もまた、シーア派の思想やスーフィーに代表されるグノーシスを生み出しました。キリスト教と同じく、グノーシスはユダヤ教やイスラム教においても深い神秘主義を生み出しましたが、いずれも不信の目で見られました。いかなる宗教に関係するにせよ、グノーシスはある精神状態につながっています。グノーシス派の人々にとって、霊魂は肉体に閉じ込められており、したがって、彼は宇宙を闘争する二つの力に支配されたものと考えます。精神が物質に対立するように、光は闇と闘争する。善は悪と、生は死と、知識は無知と闘争します。人間の悲惨を生んだ最大の原因こそ無知だというのです。
第四章「ミサの心理学」では、ミサの祭儀で起っていることについて、ユングは以下のように述べています。
「ミサの祭儀で生起することには、人間的な側面と神的な側面の二重性がみられる。人間の側から見ると、供物が祭壇で神に捧げられるということになるが、この供物は同時に司祭と会衆が自らを捧げることをも意味する。典礼行為によって供物と供え手は聖化される。それは、主が弟子たちと祝った最後の晩餐、受肉、受難、死と復活を想いださせ、かつそれらを表現する。しかしこの擬人的行為は、神の側から見ると、外皮か容器のような何かでしかなく、そのなかで生じているのは人間のわざではなく、神のわざである。無時間性において永遠に現存していたキリストの生命が一瞬の内に目に見えるものとなる。そして、聖なる行為という凝縮した形においてであるが、時間的順序に従って展開する」
続けてユングは、ミサの具体的な流れについて述べます。
「キリストは供えられた実体の永遠の相のもとに人間として受肉する。彼は苦しみを受け、殺され、埋葬され、下界の力を破り、栄光の内に復活する。聖別 consecratio の言葉を発するおとによって神性が自ら行為し、現存しながら介入し、それとともに、ミサの本質的な出来事がすべて神性の恩恵のわざであることを証言する。その場合、司祭には奉仕者の意義しか認められていない。会衆や供えられる実体も同様である。それらはすべて、聖なる出来事の奉仕因である。神性の現存自身が、奉献行為のあらゆる部分を1つの神秘的統一へと集中させる。まさに神自身こそ、実体、司祭、会衆において自らを供物として供出し、人の子の形をとって父に対する贖いのために自己自身を捧げる者なのである」
ミサは宗教儀礼です。ユングは「儀礼行為においては人間は自律的な『永遠』、すなわち意識のカテゴリーの彼方に存在して『働いている者』の意のままになる―まるで卑しい者が集まって大いなる者を生ぜしめうるかのようである」として、さらに次のように述べます。
「ちょうど、すぐれた俳優が、単に演じるのではなく、その劇を書いた詩人の天才に魂を奪われるのと同じである。祭礼行為であるために欠かせない条件の1つは美しいということである。というのは、人は、美においても神に仕えるのでなければ、神に正しく仕えたことにはならないからである。それゆえ、祭礼には実際的有用性というものがない。実際的有用性は目的奉仕性であり、ただの人間的なカテゴリーだからである。だが神的なものはすべて、自己目的であり、わたしたちが知っている唯一の合法的な自己目的である。とはいうものの、永遠なるものがそもそもどうして『働く』ことが可能になるのかは、関わりあわないほうがよい問いである。それは答えることができないからである」
ユングは、供犠の心理学的意義についても以下のように述べます。
「生贄の供犠は象徴的なものである。すなわち象徴によって表現されるものすべてに関わっている。物質的な所産、調理された実体、人間の心理的業績、栽培植物に独特な、デーモン的な性質をもつ自律的な生命がそれである。生贄の供物の価値は、それが最善のものもしくは最初のもの(初穂)であることによってさらに高められる。パンと葡萄酒は農夫の生産する最善のものであることから、人間の努力が産み出す最善のものでもある。さらにこれに加えて、とくに麦は死んで復活する霊的なヌーメンの目に見える現われを意味し、また、葡萄酒は陶酔とエクスタシーを約束するプネウマの現存を意味する。古代人はこのプネウマをディオニュソスとして、とくに苦しみを受けるディオニュソス‐ザグレウスとしてとらえた。その神的実体は自然全体に広がっている。パンと葡萄酒の形で生贄にされるのは、要するに自然と人間と神であり、これらが象徴的供物の統一性において組み合わされるのである」
そして、「ミサにおける転換象徴」の最終部分で、ユングはミサの本質について以下のように述べています。
「ミサは、もともとはとくに才能に恵まれた個人が他の人たちと無関係に経験していたものが、意識の漸進的な拡がりと深まりとともに、しだいにより大きな集団の共通の財産になっていった何千年にわたる発展の集大成にして精髄である。しかしその根本に横たわっている過程は今もなお秘密である、これに対応する『密儀』や『秘儀』において具体的に、印象的に表現され、教義、修行、瞑想、奉献の行為によって強化されている。司祭はこれらによって神秘の領域にどっぷりと漬けられる。そのために彼は、神話的な出来事と自分が密儀に繋がっていることをある程度自覚することができるのである。それゆえたとえば古代エジプトでは、本来は王の特権であったオシリス化はしだいに貴族、そして古代エジプトの伝統が終わるころにはついに個人にも拡げられた。元来、秘教的で、沈黙を義務づけられていたギリシアの密儀宗教も同様に、しだいに集合的な体験へと拡大され、カエサルの時代にはいわば、スポーツのような気分でローマの観光客が異国の密儀へのイニシエーションを楽しむことになった。キリスト教はすこしばかりためらってから、さらに進んで密儀を公共の催しものにしてしまった。なぜなら、出来るだけ多くの人を秘儀の体験に誘うことこそ、キリスト教がとくに関心を払っていたことだからである」
「ヨブへの答え」では、ユングはキリストの本質にまで言及します。
「キリストはそもそも、ただの神話にすぎず、虚構でしかないと考えられることもあった。だが、神話は虚構ではなく、常に繰り返され、何度でも観察することができる事実にもとづいている。それは人間の身に起こるものであり、人間の運命も、ギリシアの英雄のように神話的なものである。それゆえ、キリストの生涯が相当程度において神話であるからといって、彼が歴史的に実在したということが全面的に否定されるわけではない。むしろ反対だとわたしは言いたい。というのは、ある一人の人生が神話的性格をもつということは、まさにその人生があらゆる人にも普遍的に妥当するものだということを表現しているからである」
続けて、ユングはいかにも著者らしい自説を述べるのでした。
「無意識、すなわち元型がある一人の人間の心を完全に捉えて彼の運命のあらゆる細部に至るまで支配してしまうということは心理学的にはまったくありうることである。その際、動揺に元型を表わしている客観的な、つまり心理的ではない対応現象が出現する。元型が個人における心理的なものであるだけでなく、わたしにはキリストがそのような人格であったように考えられる。キリストの生涯は、もし、それが同時に神にして人間の生涯であるならば、否応なくそうならざるをえないものである。それは、シンボルム symbolum 、すなわち異質な性質のものを寄せ集めたものであり、まるでヨブとヤハウェを1つの人格に体現させたような具合である。人間になろうというヤハウェの意図は、ヨブとの衝突から生じたものであるが、それがキリストの生涯と受難において成就されたのである」
わたしは、ユングのキリスト教についての考え方を非常に面白いと思いました。『モーセと一神教』でフロイトがユダヤ教の本質を解き明かしたように、この「ヨブへの答え」でユングはキリスト教の本質を解き明かしたのかもしれません。
