- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.03.09
『霊性の哲学』若松英輔著(角川選書)を読みました。 著者は1968年生まれの批評家で、『井筒俊彦 叡知の哲学』や『神秘の夜の旅』などの著書で話題を呼びました。 この読書館で著者の本を紹介するのは、『魂にふれる』以来です。
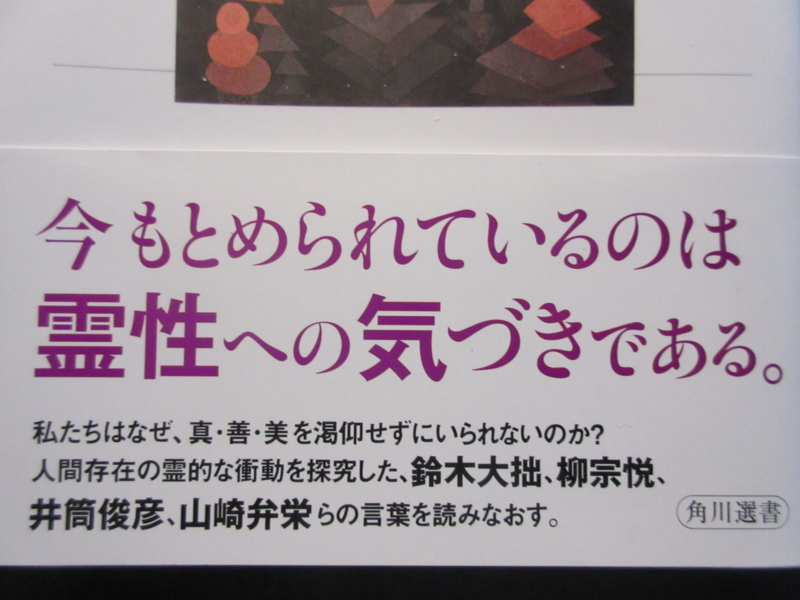 本書の帯
本書の帯
帯には「今もとめられているのは霊性への気づきである。」と大書され、続いて「私たちはなぜ、真・善・美を渇仰せずにはいられないのか? 人間存在の霊的な衝動を探求した、鈴木大拙、柳宗悦、井筒俊彦、山崎弁栄らの言葉を読みなおす」
また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。
「小さな自己を超え、永遠を希求する魂の衝動。この熱き働きを霊性と呼んで探究した近代日本の哲人達が現代に語りかけるものとは。霊性論の先駆者、山崎弁栄。日本的霊性を説いた鈴木大拙。民藝に美と平和の祈りを見た柳宗悦。カトリシズムを超えて霊性を問うた吉満義彦。人々への寄与を哲学の使命と信じた井筒俊彦。ハンセン病者の尊厳を詠った詩人、谺雄二―。日本思想の奥底に脈打つ命と霊性の哲学を探る」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
第一章 光の顕現 山崎弁栄の霊性
第二章 大智と大悲 霊性の人、鈴木大拙
第三章 平和と美の形而上学 柳宗悦の悲願
第四章 文学者と哲学者と聖者 吉満義彦の生涯
第五章 コトバの形而上学 井筒俊彦の起源
第六章 光と憤怒と情愛 谺雄二の詩学
「おわりに」
「文献一覧」
「ブックガイド」
「はじめに」の冒頭では、「精神史とは何か」として、著者は以下のように述べています。
「歴史とは、際限のない、ほとんど無限といってよい広がりです。その茫漠と拡がる時のうごめきを、何を基軸にして想起するかによって、『何史』であるかが定まってきます。文学史、美術史、外交史、あるいは思想史、精神史という表現もあります。文学史を書こうとするなら、何を文学であると考えるかによって、その姿が大きく変わってきます。 思想史と精神史は、似て非なるものです。思想史は、主に言語に結実した理念を軸に、そこに派生した出来事を追います。しかし、芸術運動のような思想のかたちをとらない「精神」潮流もある。精神史は、思想の姿をしていない、しかし、世界を揺るがすような言葉、人物、出来事からも目を離すまいとします」
また、「霊性の本意」として、著者は以下のように述べています。
「今日、『霊』という言葉が、何かいかがわしい様子を伴って認識されるのに根拠がないわけではありません。霊性論を長く展開している鎌田東二も指摘しているように、曹洞宗の宗祖道元(1200~1253)がすでに『霊性』という表現を用いています。『正法眼蔵』の序章ともいえる『弁道話』で道元は、『外道の見』、人を惑わす劣悪なる言説の例として、『霊知』とともに『霊性』という術語を用います。霊が目に見えないことに付け込む者の虚言として語られています。 一方、道元とは異なる意味での、近代につながる意味における、超越を求める働きとしての『霊性』という表記自体は、江戸時代からありました。その一例が平田篤胤(1776~1843)です。鎌田は篤胤の優れた読み手でもありますが、彼は霊性論における篤胤の再考を唱えます」
第二章「大智と大悲 霊性の人、鈴木大拙」では、「霊性―いのちの根源的な働き」として、著者は以下のように述べています。
「『霊性』という表現は大拙がはじめて用いたわけではありません。むしろ、戦前までの期間を考えるとき、霊性論の集大成を行った人物だったともいえます。大拙が『霊性』という表記を用いたのは1895年に刊行された最初の訳書であり、最初の刑行物であるポール・ケラスの『仏陀の福音』です。その次に刊行された大拙自身の処女著作『新宗教論』でもわずかながら『霊性』という表記を見ることはできます。しかしここでの『霊性』には、これまで見た『日本的霊性』で用いられているような意味は付されていません。『新宗教論』で大拙は、霊性を意味する表現として、『宗教的感情』あるいは『宗教的情感』と書いています。大拙における鍵言語としての『霊性』の発見には、18世紀にスウェーデンで活動したエマニュエル・スウェーデンボリ(1688~1772)の思想と出会ったことが決定的な役割を果たします」
さらに鈴木大拙における霊性論を探る著者は、「生ける実在としての霊性を語ること」として、以下のように述べています。
「『日本的霊性』で大拙は、『日本的霊性』と呼ぶべき姿が結実したのは鎌倉時代で、法然・親鷲による浄土教と禅の交差が決定的な契機になったと語りました。今日、この説をそのまま受け入れることは難しくなっています。大拙はさほど大きな役割を認めていませんが、聖徳太子―この人物の実在の是非の問題は別として―と飛鳥時代の仏教、最澄による天台宗、空海による真言密教の樹立、日蓮、道元など大拙が積極的にふれなかった鎌倉時代の宗祖たち、さらに、伊藤仁斎、荻生徂徠の日本における儒学、本居宣長や平田篤胤の国学に潜んでいる霊性の息吹を見過ごすこともできない」
続けて、著者は以下のように例を示しています。
「たとえば『仏教哲学』という視座で考えた場合、空海の業績には、日本の歴史だけではなく、世界史の次元で考えるべき問題があると井筒俊彦は考えていました。仁斎から宣長に至る思想の意味を語ったのが小林秀雄です。鎌田東二は、大拙の霊性論の意味を大きく認めつつ、『日本的霊性』の執筆当時、神道が政治利用されていたという時代環境をふまえてもなお、大拙の篤胤理解はあまりに局所的だったとそれを惜しむ指摘をしています」
第四章「文学者と哲学者と聖者の生涯」では、著者は近代日本を代表する哲学者である吉満義彦のお墓に行ったことを明かし、「亡くなった人がずっとお墓にいるということはないように感じています。ただ、墓所は生者と死者の待ち合わせ場所だと思うのです」と述べています。このお墓に対する考え方は、わたしにも共感できました。
それから、作家の遠藤周作が吉満義彦について書いたエッセイの一部が以下のように紹介されています。
「先生の机には若い、うつくしい女性の写真がおかれてあった。それは先生の若い頃、亡くなられた婚約者の写真だと寮生の1人が教えてくれた。この婚約者の女性は結核で早く亡くなられたが、臨終の時、先生は司祭をよんで2人だけの結婚式をあげられ、以来、先生は独身を守られたのである。いや、独身という言葉は間違っている。ある日、先生が一度、 『私は結婚をして妻が死んだのです』 きっぱり言われたのも憶えているからだ。 (「吉満先生のこと」『心の夜想曲』)」
この遠藤周作の文章に続いて、著者は次のように書いています。
「これはとても印象的な文章ですが、少し事実と違うことがあります。2人が結婚したのは臨終の際ではないのです。妻・輝子が亡くなったのは結婚から90日後です。ただ、吉満は輝子さんが遠からず逝くことを知りながら結婚しているのは事実です。そのあと吉満義彦は生涯独身を通します。彼がその後も1人だったというのは彼自身の問題ですが、ここで私たちが感じることができるのは、吉満が結婚をどのように考えていたかです。それはこの世で2人が出会ったことを神の前に証しし、感謝する行為だったのです。もちろん、吉満の墓石には輝子の名前も刻まれています」
また、著者は吉満が「文学とロゴス」の中に書いた「死者を最もよく葬る道は死者の霊を生けるこの自らの胸に抱くことである」という言葉を紹介し、続いて以下のように述べています。
「死者を弔うとは死者と共に生きることだと吉満はいうのです。さらにいえば、死者を弔うとは、死者を遠くに感じることではなく、限りなく近くに存在する者であることを忘れないことだというのです。ここでの『霊』とは、新生した死者の姿を指す言葉です。肉体から離れ、より高次な自由を得た、人間の像を語る言葉です。ここで語られていることが本当に行われるようになると、『遺品』というものはおそらくなくなります。なぜならば、亡くなった人は、この世に残された者のなかで生き続けているからです。死者は『生きて』いるからです。ある記念の物ではあり続けると思いますが、世にいう『遺品』ではなくなるのではないでしょうか」
さらに、著者は吉満が「神秘主義の形而上学」の中に書いた「されば最深の神秘的人間はまた最深の行動的人間である」という言葉の後に以下のように述べています。
「『神秘』とは、記されている通り、「神」が私たちに開示してくれる何ものかです。それをもっともよく眺めたるものは、もっともよく働くというのです。 働くとは、他者に向かって開かれて生きることです。本当の意味での神秘的人間というのは、神秘的経験というのを自らのためだけに用いることをしない。必ず他者に向かって開かれて、それが何であるかを他者に知らしめるのだというのです。同質のことを、ベルクソンが『道徳と宗教の二源泉』で、井筒俊彦は『神秘哲学』でプラトンにふれながら語っています」
続けて、著者は「神秘家」について以下のように述べています。
「『道徳と宗教の二源泉』も『神秘哲学』もそれぞれの神秘家論です。神秘主義者と神秘家という言葉を仮に使い分けるとしたら、何が神秘であるかを喋っている人が神秘主義者だとすると、神秘家とは、語ることなく働く人のことです。ベルクソンは、『道徳と宗教の二源泉』で真に『神秘』の境域にふれた者は、その身に受けた光を他者に分かち合わずにはいられないだろうと書いている。井筒は、プラトンのいうイデア界にふれた者は、その経験を現実世界で実現する「神聖なる義務」を持つ、と述べています。吉満がいう『神秘的人間』とはもちろん、『神秘家』のことです」
第五章「コトバの形而上学 井筒俊彦の起源」では、著者は「読む」という行為について以下のように述べています。
「ある文章を読んで感動して、その言葉をもう一度見つけたいと思って本をめくっても、同じ言葉が見つからないことがあります。小林秀雄も同じような実感を吐露していますが、『読む』という行為はじつに奥深いものです。現代人が感じているよりもずっと多層的な、また多次元的な出来事のように思われます」
続いて、著者は「読む」ということの意味について述べます。
「現代は『表現する』ということが重大な意味を持っていて、読むことはその準備に過ぎないとされていますが、井筒俊彦の認識は違います。読むことは書くことと同じくらい創造的な営みである、というのが井筒俊彦における哲学の根幹です。読むことこそ、テクストを新しく書き換える行為である。それが彼の思想経験の根本にあります。私たちはそういう世界観を取り戻していかなくてはならないのではないか」
さらに、著者は「主著『意識と本質』をどう読むか」で、次のようにとても大切なことを述べるのでした。
「そしてもう1つ大事なのは、読みっ放しにしないこと。読みという経験を深めるのは、書くということです。たくさん読んでばかりいても、たくさん書いてばかりでもだめです。書くという経験を深めるのは、読むということです。井筒俊彦の言葉を、一節を自分の手で書いてみる。そして、そこで想起されることを少しでよいので書いてみる。誰にも見せなくたってよいのです。感じたことを正直に書いてみる。 ただ、大切なのはそれが自分の書く最後の文章かもしれないと思って臨むことです。最後かもしれないというのは、けっして突飛なことではありません。それをまざまざと教えてくれたのは先の大震災でした。私たちが明日生きているというのは、それほど確実なことではありません。 井筒俊彦の言葉を前に、1人ひとりが自分の魂に正直になって、これが最後の文章だと思って書いてみる。それはかけがえのない経験になる。そうすることで、井筒俊彦という人は、もっともっと近い存在になるのです」
