- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.01.11
『宗教学』大田俊寛著(人文書院)を読みました。
「ブックガイドシリーズ 基本の30冊」シリーズの1冊です。 著者は、1974年生まれの気鋭の宗教学者です。 一橋大学社会学部を卒業、東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻宗教学宗教史学専門分野博士課程を修了し、現在は埼玉大学の非常勤講師を務めています。
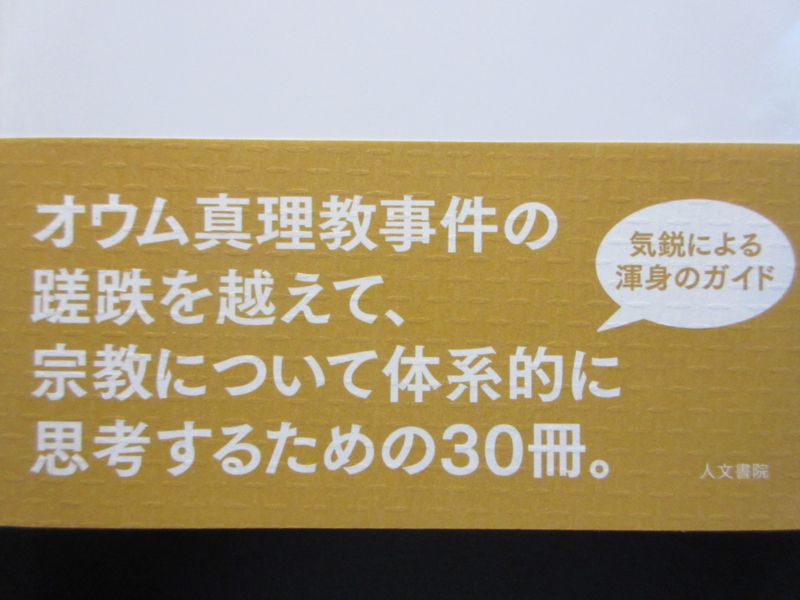 本書の帯
本書の帯
著者には、この読書館でも紹介した『グノーシス主義の思想』、『オウム真理教の精神史』、『現代オカルトの根源』といった著書があります。本書の帯には「オウム真理教事件の蹉跌を越えて、宗教について体系的に思考するための30冊。」「気鋭による渾身のガイド」と書かれています。
本書の目次構成および取り上げられている書籍は以下の通りです。
「はじめに―宗教の四段階構造論」
第1部 祖先崇拝の論理
フュステル・ド・クーランジュ『古代都市』
加地伸行『儒教とは何か』
柳田國男『先祖の話』
第2部 宗教の基礎理論
ロバートソン・スミス『セム族の宗教』
ジェイムズ・G・フレイザー『金枝篇』
エミール・デュルケム『宗教生活の原初形態』
ジークムント・フロイト『トーテムとタブー』
コラム(1)「フィクション」という概念
第3部 中世における政治と宗教
マルセル・パコー『テオクラシー』
エルンスト・H・カントーロヴィチ『王の二つの身体』
菊池良生『戦うハプスブルグ家』
井筒俊彦『イスラーム文化』
コラム(2)政治神学とは何か
第4部 近代の国家・社会・宗教
トマス・ホッブス『リヴァイアサン』
マックス・ヴェーバー 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
森孝一『宗教からよむ「アメリカ」』
村上重良『ほんみち不敬事件』
南原繁『国家と宗教』
コラム(3)キリスト教を理解するには
第5部 個人心理と宗教
フリードリヒ・シュライアマハー『宗教について』
ウィリアム・ジェイムズ『宗教的経験の諸相』
アンリ・エレンベルガ―『無意識の発見』
ラルフ・アリソン『「私」が、私でない人たち』
E・キュブラー・ロス『死ぬ瞬間』
第6部 シャーマニズムの水脈
ミルチア・エリアーデ『シャーマ二ズム』
I・M・ルイス『エクスタシーの人類学』
上田紀行『スリランカの悪魔祓い』
コラム(4)心霊現象と多重人格
第7部 人格改造による全体主義的コミューンの形成
ハナ・アーレント『全体主義の起源』
チャールズ・リンドホルム『カリスマ』
米本和弘『洗脳の楽園』
コラム(5)現代における究極的イニシエーション
第8部 新興宗教・カルトの問題
横山茂雄『聖別された肉体』
小川忠『原理主義とは何か』
大田俊寛『オウム真理教の精神史』
「はじめに・・・・・・宗教の四段階構造論」では、「理論と体系を欠いた危うい『学』―宗教学の再構築に向けて」で以下のように書いています。
「1995年3月20日に発生した地下鉄サリン時間を筆頭に、数々の凄惨な事件を引き起こした同教団に対して、当時の宗教学は、確固とした学問的立場や見識を示すことができなかった。それどころか日本の宗教学は、オウム真理教の成立と発展を、陰に陽に後押しさえしてしまったのである。いわく、『狂気がなければ宗教じゃない』(中沢新一)、『仏教の伝統を正しく受け継いでいる』(島田裕巳)と。日本の宗教学にとってオウム問題は、自身の存在意義や存立基盤に関わる水準の事柄であり、そのことは今でも、何ら変わっていない」
そもそも宗教学とは何か。著者は以下のように説明します。
「宗教学は、19世紀後半のヨーロッパで誕生した近代的学問の一つである。中世を支配したキリスト教的伝統の重圧や桎梏から解放され、宗教学は当初、数々の理論を積極的かつ大胆に展開した。しかしながら、およそ150年に及ぶその後の宗教学の歩みは、順調なものであったとは言い難い。宗教学は、一方で、西洋優越史観や科学万能論といった近代主義的潮流、また他方で、ロマン主義やニューエイジといった反近代主義的潮流により、自らの足場を絶えず揺るがされ続けた。そして今や宗教学は、宗教に関する一般理論の構築という当初の目的を、放棄・断念したかにさえ見える」
著者は、「宗教」とは、「虚構の人格を中心に掲げ、言語によって公示される法を紐帯とし、共同体を結成することを意味する」と述べます。そして、人類史の全体をマクロな視点から捉えた場合、「虚構の人格」を中心とする宗教的体制は、原始・古代・中世・近代という4つの段階を経ながら変化・発展してきたと見ます。またそれに応じて、宗教と呪術の各領域が機能分化してきました。すなわち、1)原始の祖霊信仰、2)古代の多神教(民族宗教)、3)中世の一神教(世界宗教)、4)近代の国家主権となります。
以下は、本書で取り上げられている本の解説文の中から興味深く感じた箇所を抜き書きします。 個人的な読書メモというか備忘録のようなものですが、将来の執筆などに活用するつもりです。 みなさんも関心を抱いてくれれば幸いです。
●フュステル・ド・クーランジュ『古代都市』
「『国家』と呼び得るような規模の共同体が未だ存在しなかった時代、ギリシャやローマの人々は、何を拠り所に生を営んでいたのだろうか。クーランジユによれば、それは『家族』であり、そしてその社会は、『死者の霊魂』に対する信仰の上に成立していた。後のヨーロッパでは、ギリシャ哲学やキリスト教神学に基づく複雑な霊魂観が発達したが、最古のそれは、きわめて素朴なものであった。すなわち古代の人々は、身内に死者が出ると、彼の遺骸を墓に葬り、そして彼の魂もまた、その場所で生き続けると考えたのである。彼らは墓に供物をささげ、霊魂の死後の幸福を祈った。祖霊を供養し続けることは子孫の義務であり、またその行為への参加によって、家族に属する者の外縁が決定された。他方、供養を受けない霊魂は、悪霊や怨霊と化し、社会に災厄をもたらすと考えられた」
●加地伸行『儒教とは何か』
「本来、儒教において礼とは、親に対する崇敬の態度であり、さらには、祖先を祀るための祭礼を意味していた。(中略)それは、しばしばシャーマン的狂乱状態を伴う招魂儀礼から成り立つものだったのである。 しかし孔子は、礼の根拠を、そうした粗野な儀礼にではなく、各種の古典文献に基づく教養に求めた(いわゆる「詩書礼楽」)。孔子によって儒教は、血縁共同体の結束を固めるための宗教儀礼から、より高度な政治的・学問的統治の技法へと脱皮したわけである。加地は、ここに儒教において『宗教性』と『礼教性』が明確に分離し始める端緒があると指摘している」
●柳田國男『先祖の話』
「日本仏教の葬礼においては、霊はあくまでも個人として扱われ、かつ、何十年にもわたって年忌法要が行われるが、柳田はこれを、日本の実情に合わない形式であると批判する。日本の霊魂観では、霊は死後次第に浄化され、個性を失ってゆく。そしてある年限を過ぎると、個人の魂は、『御先祖さま』や『みたま様』という一つの尊い霊体に融け込むものと思念されたのである」
●ロバートソン・スミス『セム族の宗教』
「供犠の分析を始めるに当たって、まずスミスは、教義や神話や信仰以上に、儀礼こそが宗教における中核的位置を占めるということを強調する。近代のキリスト教徒たちは、教義の内容や内面的信仰に宗教の核心を見出す傾向にあるが、原始的段階の宗教を対象とする場合、そうした考え方はまったく当てはまらない。原始宗教において、明確な教義や神話は未だ十分に発達しておらず、例えば人々は、神殿で行われている事柄に対して、相互に矛盾する見解を示すことさえ稀ではなかったのである。 宗教における最重要事は、教義や神話の内容を理解・説明することにではなく、儀礼に自ら参加することにあった。教義や神話はむしろ、儀礼という行為を説明するためにこそ存在し、その価値は二次的なものに過ぎない。神話が儀礼から引き出されたのであって、儀礼が神話から引き出されたのではないのである。スミスは、儀礼が義務的かつ固定的であったのに対し、神話は可変的であり、礼拝者個人の趣味嗜好にさえ委ねられていた、と論じている」
●ジェイムズ・G・フレイザー『金枝篇』
「人々が日々の糧を得るために厳しい生活を強いられるなかで、自然の神秘的な運行について研究することを許される一群の人々が登場したことは、人類にとって大きな前進を意味した。呪術師という『原始的哲学者』たちは、薬物や鉱物の性質、降雨と旱魃の法則、雷光の原因、月の満ち欠け、生命と死の神秘など、あらゆる事柄に驚嘆を覚えながらその法則性を探求し、そこから編み出した呪術を用いて、人々の願いを叶えようとしたのである」
●井筒俊彦『イスラーム文化 その根底にあるもの』
「井筒は、戦後日本におけるイスラーム研究の第一人者であり、なかでもイスラーム神秘思想への深い傾倒で知られる。世界中の名だたるロマン主義者たちの集会場と呼ぶべき『エラノス会議』(ルドルフ・オットーの呼び掛けに始まり、主な参加者は、カール・グスタフ・ユング、ミルチア・エリアーデ、ゲルショム・ショーレム、鈴木大拙らであった)に熱心に出席していたことからも分かるように、彼の宗教観は総じて、神秘主義やロマン主義の傾向を濃厚に帯びたものであった」
●ウィリアム・ジェイムズ『宗教的経験の諸相』
「ジェイムズの宗教心理学を含むロマン主義的宗教論は、その後、数々の新興宗教や、ユング心理学、トランスパーソナル心理学等の運動を通して発展していったが、そこに見られる問題点にも目を向けないわけにはゆかない。心理学に基づく諸種の宗教論が普及していった結果、宗教は所詮は『個人の内面』に関する事象に過ぎないという近代的見解が一層強化され、宗教の有する制度的・法的次元、ひいてはその根本的な社会形成力が、次第に考察の範囲外に置かれるようになった。また、アカデミズムの内外からは、自己啓発や成功哲学、ニューエイジなど、心理的操作によって『癒し』を実現しようという疑似宗教的な運動が、数多く出現するようにもなっていったのである。今後の宗教学においては、宗教の全体的な構造において心理的次元がどのような位置を占めているのかという事柄について、改めて慎重に問い直してゆく必要があるだろう」
●アンリ・エレンベルガ―『無意識の発見 力動精神医学発達史』
「ロマン主義とは基本的に、言葉で明晰に表現できない領域を対象とする思想であるため、その内容を正確に規定することは難しい。ともあれ本書でエレンベルガ―は、ロマン主義の全般的特色として、以下の六点を指摘している。1」『自然』への深い感情。啓蒙主義が人間理性と人工物を重視する一方、ロマン主義は自然を崇敬し、その内奥に分け入ろうとする。2)目に見える自然の背後にある『基盤』の探究。ロマン主義者の愛好する自然は、単なる物質的存在ではなく、自己の霊魂が由来する精神的故郷と見なされる。3)『生成』への思い入れ。啓蒙主義が理性の不変性を信奉するのに対し、ロマン主義は、個人・民族・言語・文化のすべてが有機的な生成発展の過程にあると捉える。4)『民族』の重視。啓蒙主義が、人類や社会の普遍的合理性を問題にするのに対し、ロマン主義は、個々の民族や文化に備わる独特の価値に力点を置く。5)新しい『歴史』感覚。啓蒙主義が未来志向であるのに対し、ロマン主義は、過去の世界に存在した精髄を呪術的方法によって呼び戻すことができると夢想する。6)『個人』の独自性の強調。啓蒙主義において、人間理性の普遍性・共通性が重視されるのに対し、ロマン主義では、人間一人一人に備わる還元不可能な固有性が強調される。 総じて言えば、啓蒙主義が、人間の理性によってすべてを明晰に照らし出そうとする『光の思想』であったのに対して、ロマン主義は、理性の外部に不分明な暗部が残り続けると考える『闇の思想』であったと位置づけることができるだろう」
●ミルチア・エリアーデ『シャーマニズム 古代的エクスタシー技術』
「シャーマンにとって、呪術飛翔はどのような意味を持つのだろうか。それは、病者の治癒や死者の魂の導きのために必要不可欠の能力であるが、エリアーデはそのもっとも主要な役割を、『始原の楽園への回帰』にあると見なす。オーストラリア先住民に伝わる『ドリームタイム』を始め、数々の神話で語られているように、原初的時代において人類は、動物たちと思うままに会話し、天と地を自由に行き来することができた。しかしその後、文明の発達とともに陥落が始まり、人類の超自然的な交流能力は失われ、始源の楽園は消え去ってしまったのである」
「宗教の中核がイニシエーションにあるという見解は、70年代以降、日本においても着実に広まっていった。本邦の宗教学における代表例としては、チベット密教の修行の過程を詳細に描いた中沢新一の『虹の階梯』(1981)、通過儀礼に伴う人間的成熟を宗教の中心的機能と見なした島田裕巳の『イニシエーションとしての宗教学』(1993)を挙げることができるだろう。同時にそれと並行して、日本の新宗教の一つであったオウム真理教においては、グルから弟子へと伝授されるイニシエーションを基盤とした宗教的実践が、次第に過激さを増していった」
●上田紀行『スリランカの悪魔祓い イメージと癒しのコスモロジー』
「スリランカの悪魔祓いの様相を詳しく描いた後、本書の後半では、このような儀礼によって人はなぜ癒されるのかということに関する考察が行われる。その際に最初に援用されるのは、機能主義と象徴論という、文化人類学における二つの基礎的な理論である。 まず機能主義によれば、さまざまな宗教儀礼は、社会を統合するという機能を有する。それはスリランカの悪魔祓いも例外ではない。機能主義によれば、『悪魔祓いは孤立した患者の共同体への再統合である。だから患者は癒されるのだ』(161頁)と説明される。 次に象徴論は、数々の宗教的象徴によって構成される体系やコスモロジーを重視する。その点から考察すると、スリランカの呪術師は、ブッダを頂点とし、悪魔たちを下層に配する神々の体系を構想している。ゆえに象徴論によれば、『悪魔祓いは神話の上演だ。そこでは悪魔はブッダの力の前では何ほどでもなく、去らねばならない存在だというメッセージがシンボルを介して伝達される。だから患者は癒されるのだ』(166頁)と説明されることになる」
●大田俊寛『オウム真理教の精神史 ロマン主義・全体主義・原理主義』
「ロマン主義的宗教論の初期の代表作としては、シュライアマハーの『宗教について』とウィリアム・ジェイムズの『宗教的経験の諸相』を挙げることができる。これらの著作では、内面で生じる神秘的現象こそが宗教の中核であり、それを経験した人間には、大きな人格的変容が生じることが論じられた。同様の構図は、ユング心理学にも見られる。彼はそこで、普遍的無意識の領野を探求することにより、真実の『自己』に到達し得ること、そして自己は、個人の生死を超越した永遠性を帯びることを主張したのである。 ロマン主義的な精神論や人格変容論は、20世紀後半、アメリカを中心とするニューエイジの思潮によって継承され、大衆的人気を博した。そしてその際には、ブラヴァツキー夫人の神智学において提唱された修行論や輪廻転生論もまた、積極的に導入・混淆されていった」
「ロマン主義・全体主義・原理主義という三つの潮流からオウムについて分析されるが、そのすべてが実は、『死』の問題と深い関連性を有する。すなわち、ロマン主義は、永遠に存続する不死の真我を、全体主義は、個人の生死を超越した共同体的生命力を、原理主義は、現文明の滅亡と神的ユートピアの樹立を希求することによって生じる幻想的思想法なのである。 麻原彰晃が好んで『人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ』と語ったように、オウムとは、現代社会の空隙として存在する死の問題を足掛かりとして急成長し、暴走した教団であった。われわれにとってオウム問題とは、究極的には、現代における死のあり方の特殊性や、それを再び公共化する方法について考えることに通じてゆくだろう」
最後のくだりは、『唯葬論』(三五館)のコンセプトにも関連します。 「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、」という文句でした。死の事実を露骨に突きつけることによってオウムは多くの信者を獲得しましたが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。言うまでもありませんが、人が死ぬのは当たり前です。「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」など、ことさら言う必要などありません。最も重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということなのです。問われるべきは「死」でなく、「葬」なのです。よって、拙著のタイトルは『唯死論』ではなく『唯葬論』とした次第です。
