- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.12.20
『死者の救済史』池上良正著(角川選書)を再読しました。
『唯葬論』(三五館)の参考文献として読みました。
「供養と憑依の宗教学」というサブタイトルがついています。
著者は1949年生まれの宗教学者で、駒沢大学文学部教授です。
東北大学卒。同大学院博士課程満期退学後、宮城学院女子大学、弘前大学、琉球大学、筑波大学などを経て 、1999年より現職。
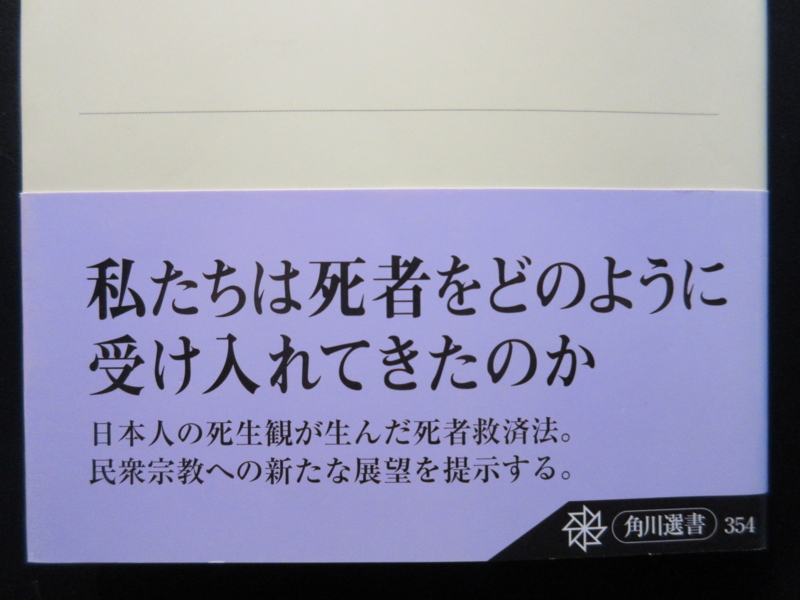 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「私たちは死者をどのように受け入れてきたのか」というリード文に続いて、「日本人の死生観が生んだ死者救済法。民衆宗教への新たな展望を提示する」と書かれています。
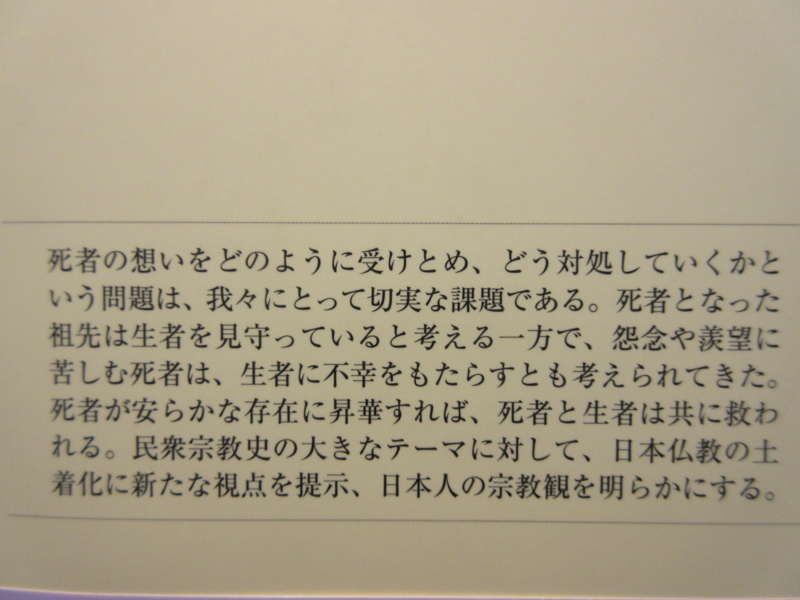 本書のカバー裏
本書のカバー裏
また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。
「死者の想いをどのように受けとめ、どう対処していくかという問題は、我々にとって切実な課題である。死者となった祖先は生者を見守っていると考える一方で、怨念や羨望に苦しむ死者は、生者に不幸をもたらすとも考えられてきた。死者が安らかな存在に昇華すれば、死者と生者は共に救われる。民衆宗教史の大きなテーマに対して、日本仏教の土着化に新たな視点を提示、日本人の宗教観を明らかにする」
本書の目次構成は以下のようになっています。
「はじめに」
第一章 苦しむ死者と日本の民衆宗教
第二章 仏教説話集に見る死者の救済
第三章 供養システムの深化と定着
第四章 比較死者供養論にむけて
第五章 憑依再考
第六章 仏僧と憑依
第七章 憑依から供養へ
「あとがき」
「はじめに」の冒頭には「日本の宗教史の根幹には『祖先崇拝』と『シャーマニズム』がある、とよくいわれる」と書かれ、次のように説明されます。
「一般に『祖先崇拝』『シャーマニズム』などと名づけられてきた思考・行動様式は、神仏・祖霊・死霊などとの直接的対話や個別的祭祀の体系であり、人々が神霊的な次元と交わす『個別取引』を重視するものであった。これに対して『世界宗教』とよばれてきた仏教・キリスト教・イスラームなどは、理念的にはこうした個別取引を抑制する教義を内包していた」
続いて、著者は以下のような例をあげます。
「たとえば仏教の高僧たちは、諸行無常・一切皆空・厭離穢土などの理想を高く揚げた。そこでは、死者の運命などは普遍的な理法の問題とされ、人間があれこれ思い煩うべきではない、と説かれる。キリスト教やイスラームのような一神教的な宗教では、個別取引とよべるものがあるとすれば、それは唯一神との『契約』の関係に限定され、雑多な霊的世界との取引を封じ込める圧力は、いっそう強かった」
さらに、著者は次のように述べています。
「とはいえ、これらの世界宗教が各地の文化へ定着する過程では、個別の霊的存在との直接交渉が全否定されることはなく、温存される一面も見られた。とくに日本に移入された大乗仏教は、むしろこれらを積極的に洗練・強化することによって定着に成功したともいえる。そこでは『輪廻転生』『追善廻向(供養)』などの理念が巧みに活用された」
第一章「苦しむ死者と日本の民衆宗教」の冒頭では「苦しむ死者たち」が取り上げられ、次のように「死者との多彩な交流」について述べられます。
「日本の民衆宗教史を見渡したとき、とりわけ注目されることのひとつは、生きている人間たちと個別的な死者たちとの直接的な交流・交渉が目立つ、という点である。亡くなった家族・親族や知人たちとの頻繁な交流の機会が、大規模で広範な制度的儀礼や慣習的実践として確保されてきたのである。たとえば『祖先崇拝』とか『先祖祭祀』と総称されてきたような、系譜上の死者を祀る行為がある。また、広く制度的な仏教諸宗派の管理下におかれた葬儀・年忌法要・盆や彼岸などの風習もある。これらは身近な死者や先祖たちが、生者や子孫たちと親密に交流する機会と考えられてきた。現代ではそれほど一般的とはいえないが、東北地方のイタコに代表されるような、霊媒的な宗教者を介して死者が直接に語りかけ、生者たちと対話するという習俗もある」
著者は、さらには御霊・怨霊・幽霊などの名で恐れられてきた死者たちの系譜があるとして、以下のように述べます。
「『祟り』『障り』『霊障』などとよばれるような、この世に未練を残した死者たちの働きと、それに対する生者たちの対処法は、日本の民俗・民衆的な宗教史の重要な部分を形づくってきた。身近な具体的な死者との直接交渉を基調とした儀礼や習俗が、生活文化の隅々にまで、多彩な広がりをもって浸透している」
著者が特に注目するのは、恨み・ねたみ・羨みなど、この世への強い未練や執着をもって死んだと考えられた「苦しむ死者」「浮かばれない死者」たちの系譜です。著者は以下のように述べます。
「彼らが放つと見なされた否定的な影響力は、多くの人々に脅威や気がかりとして受けとめられ、これを緩和するためのさまざまな対処法が開発されてきた。思いつくままに並べてみても、『祀り』『祓い』『浄霊』『鎮魂』『弔い』『供養』『追悼』『慰霊』などの言葉が浮かぶ。
これらの対処法には、それぞれに複雑な歴史的変遷があり、それぞれが微妙な性格の違いをもつ。とくに現代では、ある公的施設で行なわれる行事が『祭祀』か『追悼』か『慰霊』かといった違いは、深刻な論争の火種となる。それらは、ただちに宗教と政治をめぐるイデオロギー論争に結びついてくる。しかし、全体としてみれば、こうした行為は日本の民俗・民衆的な宗教文化の基底に、太く根強い流れとして今日まで存続してきたといえる。一般の民衆層にあっては、浮かばれない死者がもつ情念の力は、現在でも依然として高い潜在力を保っている」
苦しむ死者といえば「怨霊」ですが、著者は以下のように述べます。
「死者の祟りを恐れてこれを祀る、という行為に近いものが記録として出てくるのも、律令国家体制が完全に組み上がった奈良時代になってからである。一般に祟る死者の定番としてまず思い起こされるのは、平安時代の御霊信仰や、皇族・貴族たちを悩ました数々の怨霊たちであろう。その代表格をあげれば、早良親王、井上内親王、また貞観5年(863)の神泉苑での御霊会に早良親王(崇道天皇)とともに御霊に列せられた伊予親王、橘逸勢ら、それに誰よりも10世紀の菅原道真、平将門などであろう」
第二章「仏教説話集に見る死者の救済」では仏教説話が取り上げられ、著者は述べています。
「在来の〈祟り―祀り/穢れ―祓い〉システムの上に〈供養/調伏〉システムが寄生し、仏教的な教説にもとづく普遍主義的特性を発揮していく過程を探ろうとするとき、その実態を知るための貴重な資料として注目されるのが、一般に説話集とよばれる作品群である。とくに仏教説話集として特定されるジャンルの作品からは、多くの重要な手がかりを得ることができる」
このような観点から著者は、わが国初の本格的な仏教説話集とされる『日本霊異記』(正式名称は『日本国現報善悪霊異記』、以後『霊異記』と略記)を取り上げ、以下のように述べます。
「ここには、在来の〈祟り―祀り/穢れ―祓い〉システムの上に巧みに寄生していくことになる、〈供養/調伏〉システムの萌芽を見いだすことができる。知られるように、『霊異記』は薬師寺の僧、景戒によって8世紀末から9世紀初頭に編まれたとされる。内容的には、既存の民間説話のほか、『冥報記』『金剛般若経集験記』など唐代の仏教説話集からの影響が認められるほか、景戒自身の思想や政治的立場にもとづく解釈も目立ち、説話内容のすべてを歴史的事実として受け取ることはとうていできない。しかし、この『霊異記』にも強い唱導文学としての性格が読みとれる」
第三章「供養システムの深化と定着」では、「祟り物語の商品化」という興味深いテーマが扱われますが、その商品化のプロセスについて著者は以下のように述べます。
「為政者や社会的エリートたちが死者の祟りにおびえることは少なくなったとしても、一般の民衆層にあっては、ねたみ苦しむ死者がもつ情念の力は依然として高い潜在力を保ってきた。民俗・民衆的な宗教文化の系譜をたどるかぎり、死者との個別取引に頼る〈祟り―祀り/穢れ―祓い〉システムと、仏教的な理念を活用した〈供養/調伏〉システムとの競合・併存という関係は、近世から近代の激しい時代潮流にさらされながらも根絶されることなく、文化の中核に脈々と生きつづけたといえよう」
「死者の救済史」という本書のメインテーマを考察する手がかりとして、著者は近世以降に特徴的な2つの新たな展開を指摘し、述べます。
「まずその第一点目は、本格的な都市文化の繁栄、とくに版木印刷の普及や娯楽的芸能の大衆化などによって、上で述べたような〈祟り―祀り〉〈供養〉システムによる対処法が、ある定型的なスタンダードの物語として大規模に『商品化』されるようになった、という新展開である」
『怪異の民俗学(6)幽霊』には、怪談研究をライフワークとする京都精華大学文学部教授の堤邦彦氏の「禅僧と奇談文芸」という論文が掲載されています。それによれば、近世初期の霊験談として知られる『因果物語』は、鈴木正三の片仮名本では、まだ地域における布教活動に直結した唱導話材集という性格を保っていました。しかし、寛文年間に刊行された浅井了意の平仮名絵入本にいたって、近世出版文化の洗礼を受けた仮名草子作品としての娯楽文芸性が強く見られるようになっていくといいます。
以後、17世紀後半から18世紀にかけて、さまざまな『百物語』が流布しました。怪談・怪異文学は全盛期を迎えますが、1776年に書かれた上田秋成の『雨月物語』でひとつの頂点に達しました。池上氏は「『祟り』と『供養』の物語は、『売れ筋の』商品となったのである」と書いています。
19世紀に入ると、歌舞伎・講談などのジャンルで怪談物が一段と洗練され、技巧をこらした仕掛けによって大衆の人気を呼ぶ作品が続々と誕生しました。たとえば、累伝説というものがあります。実話に基づきますが、実際には近世初期の出来事でした。その後、祐天和尚の活躍を描いた『死霊解脱物語聞書』『祐天上人一代記』などで知られるようになり、さらには芝居・小説・狂言・舞踊・講談などの題材として江戸の庶民から絶大な支持を受けました。そして、約200年後の幕末の1959年に三遊亭円朝によって『真景累ヶ淵』(当初の演題は「累ヶ淵後日の怪談」)として脚色され、大ヒットしました。『真景累ヶ淵』は、同じく円朝の『牡丹灯籠』や、鶴屋南北の『東海道四谷怪談』とともに、日本を代表する怪談として今日まで広く知られています。
さて、近世以降に特徴的な新展開の第二点目は何か。著者は述べます。
「この時代以降、死者を祀るという風習に、『顕彰』という要素が強く表面化してくることである。ここで顕彰とは、もはや『浮かばれない死者』を『安らかな死者』に変えるのではなく、すでに功なり名をとげた人物の生前の徳を称えるという行為をさす」
死者顕彰の汎用化が大規模に適用されたのが、近代国家の『戦死者』たちでした。「戦死者の祭祀と供養」について、著者は次のように述べます。
「『顕彰』とはそれを誉め上げなければすまない、強固な社会集団の意志を背景にした行為である。顕彰を誇示し、あるいは誇示された顕彰を正当化する強い権威や権力が前提にあり、その権威や権力が高まることによって顕彰の信憑性も高まるという相乗的な関係がある」
本書では、〈祟り―祀り〉システムと〈供養/調伏〉システムという2つのシステムが論じられており、著者は以下のように述べます。
「〈供養/調伏〉システムでは、仏教の普遍主義的教説を触媒として、かえって死者との親密で個人的な交流の通路を開くことができるようになる。原理の個別主義は対応の主体性に結びつく、という逆説である。
〈供養/調伏〉システムがもつこの特性は、たとえば近代の戦死者への対応をめぐる興味深い対比としても見いだすことができる。死者の口寄せで知られる東北地方のイタコが最も繁盛したのは、第二次大戦中だったという証言は多い。
戦地から続々と帰ってくる戦死者たちに対して、全国の各地域では村や町をあげて「英霊奉斎」の式典がおごそかに行われました。
一方、ひそかにイタコを訪れた人々も多かったのです。
これについて、著者は以下のように述べています。
「『英霊奉斎』『英霊祭祀』が基本的に村や町という集団性、あるいは国家や天皇などの権威を前提にしなければ成り立たなかったのに対して、イタコの口寄せという『死者供養』の技法は、むしろきわめて個人的な死者との交流を可能にした。このことは、国家や行政が英霊の『祭祀』にこだわり、イタコがホトケ(死者)の『供養』にこだわったのはなぜか、という対比を考えたとき、きわめて示唆的である」
著者は、〈祟り―祀り〉システムと〈供養/調伏〉システムという2つのシステムは、新しい歴史的条件を組み込みながら、近現代のさまざまな現象として再生産されているとし、以下のように述べます。
「それは戦死者の追悼・慰霊はもとより、現代の新宗教や民間宗教者の活動、話題の怪奇小説、さらにはテレビの娯楽番組に登場する数々の怨霊話や幽霊談にまで及んでいる。『日本』という枠組みをいたずらに実体化する弊は避けなければならないが、この列島の民衆文化に刻みつけられた『苦しむ死者』への配慮と対処法の広がりは、同時にその歴史的な根深さの証でもあろう」
第七章「憑依から供養へ」では、著者は「憑依」を俯瞰的に述べます。
「初発の憑依の社会化において、普遍主義化への徹底を極限にまで推し進めたのは、いうまでもなく一神教的な世界宗教だった。そこでは神とサタン、聖霊と悪霊の二元論が憑依の解釈それ自体を二元論的に引き裂いた。絶対の神による心身の拘束は、もはや『憑依』とよぶことを許されなかった。それは神の『啓示』であり、『召命』であり、『導き』とされた。あるいは、『神秘体験』などの説妙な用語によって、体験の高雅な出自が保証された。モーセ、イザヤ、イエス、パウロ、そしてムハンマドに対して、『憑かれた』『神がかった』などの表現は絶対の禁句となった。
他方、悪魔・悪霊たちは、依然として人々に『取り憑く』霊威として残された。異教徒たちは、憑依のなかに生きていた。彼らは邪悪な霊に操られ、偽の神に仕える人々であった。唯一絶対の創造神を認めない異教徒が、何らかの「神」によびかけられたとき、それは『憑かれた者』となり、『シャーマン』とよばれた」
著者によれば、「シャーマン」や「シャーマニズム」といった概念は、こうした一神教的な伝統の文脈の中で鋳造され、保護され、やがて学術用語にまで押し上げられたそうです。そして、日本の制度的仏教も、この隔離の戦略によって、みずからの権威を維持しようとしたことに変わりはないとして、著者は「聖徳太子、弘法大師、明恵上人、親鸞聖人、日蓮聖人と尊称をもってよばれるようになった人たちの体験は、『憑依』の臭いのかからない言葉のなかで保護されていった。彼らは『示現』を受け、『夢』によって教えられ、『見仏』の体験はあっても、『憑かれ』たり、『神がかり』することは決してなかった」と述べています。
本書の内容は、「死者とのコミュニケーション」を考える上で非常に示唆に富んでいました。『唯葬論』を書く上でも大きなヒントをもらいました。〈祟り―祀り〉システムと〈供養/調伏〉システムという2つのシステムについては、自分でもよく考えてみたいと思います。
なお、本書は『唯葬論』でも紹介しています。
