- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.08.24
『寺院消滅』鵜飼秀徳著(日経BP社)を読みました。
今後25年のあいだに現在日本に存在する約7万7千の寺院のうちの約4割が消滅するという予測を統計的データの基に示す衝撃の書です。
著者は、日経BP社の記者であると同時に京都の某寺院の息子さんです。僧籍も持っており、盆には京都に帰って棚経を手伝うとか。
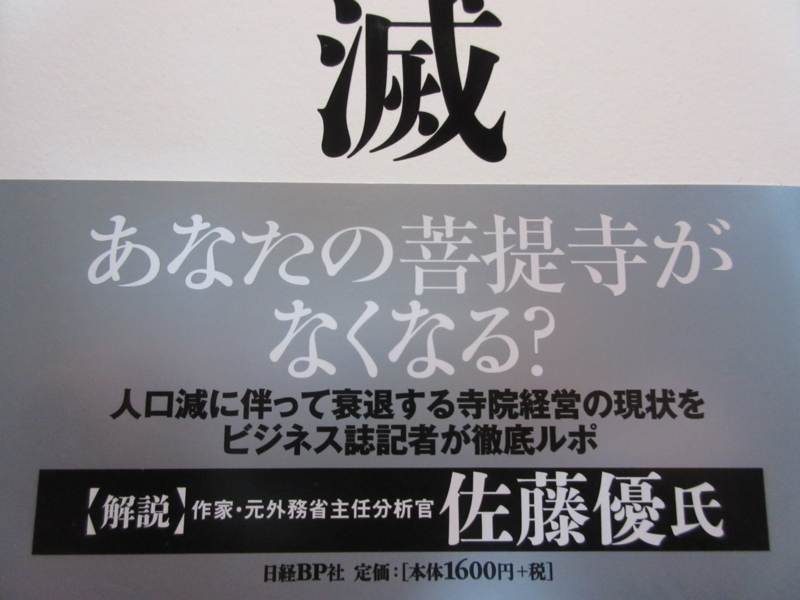 本書の帯
本書の帯
本書には「失われる『地方』と『宗教』」のサブタイトルがついています。
また、銀色の帯には「あなたの菩提寺がなくなる?」「人口減に伴って衰退する寺院経営の現状をビジネス誌記者が徹底ルポ」「【解説】作家・元外務省主任分析官 佐藤優氏」と書かれています。
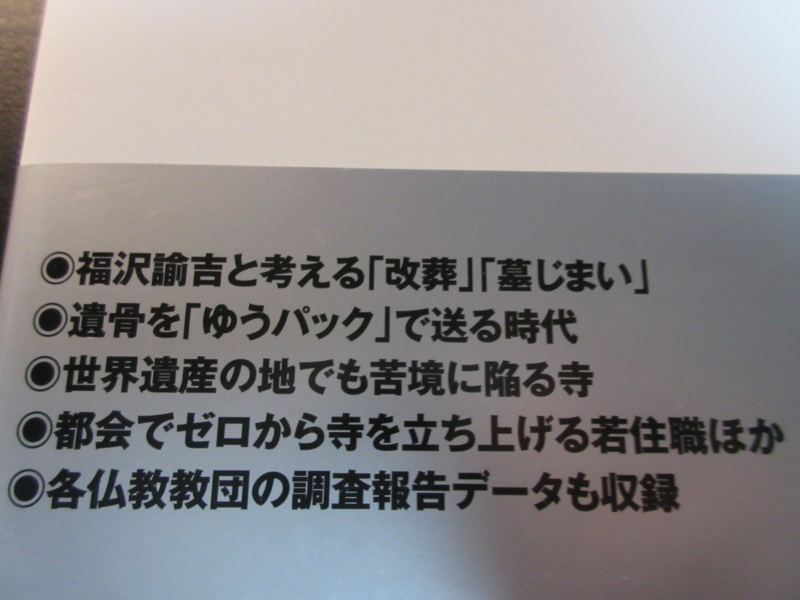 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には以下のように書かれています。
◎福沢諭吉と考える「改葬」「墓じまい」
◎遺骨を「ゆうパック」で送る時代
◎世界遺産の地でも苦境に陥る寺
◎都会でゼロから寺を立ち上げる若住職ほか
◎各仏教教団の調査報告データも収録
本書のアマゾン「内容紹介」には以下のように書かれています。
「『坊主丸儲け』『寺は金持ち』というイメージは強いが、日本のお寺は、かつてないほどの危機に瀕している。菩提寺がなくなり、お墓もなくなってしまった――。こんな事態が現実になろうとしている。
中でも地方のお寺の事態は深刻だ。高齢化や過疎は檀家の減少につながり、寺の経営を直撃する問題となっている。寺では食べていけないことから、地方の寺では、住職の跡継ぎがいない。しかし、寺は地域住民の大切なお墓を管理しなければならないため、簡単に廃寺にしたり、寺を移転したりすることはできないのが現実だ。
一方、都会で働くビジネスパーソンにとって、お寺やお墓は遠い存在であり、お寺との付き合いは『面倒』で『お金がかかる』ばかり。できれば『自分の代からはもう、お寺とは付き合い合いたくない』と、葬儀は無宗教で行い、お墓もいらない、散骨で十分という人も増えている。
経営の危機に瀕するお寺と、お寺やお墓はもういらないと言う現代人。この問題の根底には、人々のお寺に対する不信感が横たわっている。僧侶は、宗教者としての役割を本当に果たしてきたのか。檀家や現代人が求める『宗教』のあり方に応えることができているのか。
地方崩壊の根底に横たわる寺の消滅問題について、日経ビジネスの記者が全国の寺や檀家を取材し、徹底的にルポ。芥川賞作家の玄侑宗久氏らのインタビューを交えてこの問題に迫る。お寺やお墓、そして地域の縁を守ろうと必死で努力する僧侶たちの姿と、今だからこそ、仏教に『救い』を求めて集まる現代人の姿が見えてくる」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
一章 地方から寺と墓が消える
島を去る住職、来る住職
地方と都市を彷徨う墓地
世界遺産の恩恵はどこへ
もう住職はいらない
再建できない被災寺院
絶滅寸前の尼寺
【賢人に聞く 1】
宗教は「時代遅れ」でもいい(作家 玄侑宗久)
二章 住職たちの挑戦
「ゆうパック」で遺骨を送る時代
火葬場で読経10分、増える「直送」
「本当に感動する葬儀をやりたい」
多摩ニュータウンにできた”民家”寺院
企業人が仏教界を立て直し
【賢人に聞く 2】
25年後に35%の宗教法人が消える(國學院大學 石井研士)
三章 宗教崩壊の歴史を振り返る
寺は消えてもいいのか
鹿児島が迎えた寺院・僧侶の「完全消滅」
国家と宗教の争い
戦争に加担した日本仏教
農地改革に翻弄された寺
寺がサイドビジネスに手を出す理由
【賢人に聞く 3】
僧侶に「清貧さ」は必要か(全日本仏教会 戸松義晴)
四章 仏教教団の調査報告
序論
浄土宗 過疎地にある正住職寺院へのアンケート
曹洞宗 宗勢調査・檀信徒意識調査
浄土真宗本願寺派 宗勢調査
日蓮宗 宗勢調査
臨済宗妙心寺派 被兼務寺院調査
「日本仏教史」
「おわりに」
解説「消滅しそうで、消滅しない」 作家・元外務省主任分析官 佐藤優
「参考文献」「取材協力者」
「はじめに」で、いきなり著者は次のように書いています。
「折しも、日本創成会議(座長・増田寛也元総務相)が発表した『消滅可能性都市』が、話題になっていた。増田氏らは、このまま大都市圏への人口流出が止まらず、若年女性の減少などが進めば、2040年には全国の自治体の49.8%が消滅する可能性があると指摘している。例えば秋田県では大潟村を除いたすべての自治体が『消滅可能性』の範疇に入り、青森県や島根県でも多くの自治体が将来、『消えてなくなる』可能性があるという。地方都市が消滅するのに、そこにある寺が存続できるわけがない」
また、次のようなショッキングな事実が明かされます。
「現在、全国に約7万7000の寺院がある。そのうち住職がいない無住寺院は約2万カ寺に達している。さらに宗教活動を停止した不活動寺院は2000カ寺以上にも上ると推定される。無住寺院とはつまり空き寺のことであり、放置すれば伽藍の崩壊や、犯罪を誘引するリスクがある」
寺が専業で食べていくには、少なくとも檀家数は200軒なければ難しいと言われます。それも地域差があり、檀家が200軒以下であれば、住職が副業を持たない場合、生計を立てていくのは厳しいとされます。
後継者のいない寺や経済力のない寺は「消滅可能性寺院」と言えます。
消滅可能性寺院の中には、荒廃した庫裏に独居状態で老僧が暮らしており、孤独死を待っているような悲惨な状況も少なくなく、後継者探しを諦めている住職も多いといいます。
「はじめに」の最後に、著者は次のように書いています。
「昨今、家族葬や散骨、永代供養などにみられるように、寺との関わりが希薄になっている。田舎から都会への改葬(墓の引っ越し)も増えている。『失われる宗教』の背景には、法を説くことを忘れた僧侶への厳しい批判や寺院不要論があることは十分承知している。しかし、『寺が消えることは、自分につながる”過去”を失うことでもある』ことを、わずかでも感じ取っていただければ幸いだ。人は未来に希望を託さずには生きられないが、『過去』を振り返ることも時に必要だと思うからだ」
このような著者の見方について、著者の実家が寺院であることから、「本書にははじめから『寺院が消滅するのはいけない』というバイアスが存在する」などと指摘するレビュアーもいるようですが、わたしが見る限り、著者は寺院業界に肩入れすることなく淡々と書き進めていると思います。何かを論じるときに、その論者の素性に対して神経質になるのはナンセンスでだと思います。かくいうわたしも冠婚葬祭互助会の社長を務めていることから、「業界を救うために強弁をふるっている」などと揶揄されることもありますが、実際はそんなことはまったくありません。
一章「地方から寺と墓が消える」の「地方と都市を彷徨う墓地」が非常に興味深かったです。ここでは、「福沢諭吉のミイラと改葬」についてのエピソードが披露されており、著者は次のように書いています。
「福沢諭吉は1901年(明治34年)2月3日に脳出血が原因で死去したと伝えられている。享年67歳だった。葬儀は2月8日、福沢家の菩提寺である麻布十番の善福寺(浄土真宗本願寺派)で執り行われた。
通常、『葬儀』と『埋葬』が切り離されて、別々の寺で行われることはない。しかし、諭吉は生前、散歩の際に常光寺周辺の眺望が良かったことから、『死んだらここに』と、常光寺の墓地を手に入れていた。常光寺は善福寺からは約2.5km離れている」
続けて、著者は次のように書いています。
「最近では、寺檀関係が煩わしいと考え、『好きな場所』に『好きな埋葬法』を求める人が増えているが、地縁・血縁がしっかりと根付いていた明治期に、自由気ままに墓を求めたのはかなり珍しいケースではなかっただろうか。こうしたことからも、諭吉がなかなかの自由人であったことが読み取れる。
当時の埋葬法は、多くが土葬だ。土葬の場合、最初に墓に入る故人はなるべく地中深くに埋葬され、そしてその後に亡くなった配偶者や子供らの遺体を上に、上にと重ねていく。土に埋められた遺体は1年もすれば白骨化し、その骨もやがては土に還る。土饅頭型の墳墓の場合、盛られた土が次第に下がっていくことで白骨化したことが分かる。土葬は、執着を嫌う仏教の考え方に適った埋葬法と言える。諭吉は常光寺の地下で、76年間の永い眠りにつくことになった」
しかしながら、諭吉の墓はとんだ騒動に発展することになります。著者は、以下のように書いています。
「常光寺にしてみれば、『墓所を提供した』にすぎなかったが、諭吉の墓ができたことで、慶應大学を目指す受験生やその親が合格祈願に訪れる『受験の聖地』になってしまった。学生や大学関係者が毎年、墓参りに訪れ、寺は大いに賑わうことになった。常光寺が本堂を建てる際には、慶應大学による寄付の恩恵にもあずかった。
ところが、常光寺が本堂を構えるに当たって、寺を維持管理するための檀家の集まりである護持会組織が発足したことで、事態は動き出す。その会則に『常光寺に墓所を持つ檀家は浄土宗信徒であること』『信徒でなければ改宗すること』『改宗できなければ、墓を移転すること』などが明記された。決断を迫られた諭吉の遺族は常光寺からの撤退を決める」
1977年5月、諭吉の墓は常光寺から出て、本来の菩提寺である麻布十番の善福寺へ「改葬」されることになりました。改葬とは、「墓の引っ越し」のことです。「改葬」という言葉は1948年(昭和23年)にできた「墓地、埋葬等に関する法律」にも出てきます。しかし、諭吉の改葬が実施された当時は墓を動かすことはまだまだ一般的ではありませんでした。改葬が増えていくのは平成の時代になってからのことであり、諭吉の墓の引っ越しは、「改葬のはしり」と言えます。
諭吉の墓は76年の時を経て、掘り返されることになりました。ここで思いも寄らぬ事態となり、関係者は仰天しました。著者は、諭吉の亡骸について以下のように書いています。
「驚いたことに白骨化することなく、ついこの前に亡くなったかのような姿だった。遺体はミイラというより、屍蠟化していた。遺体が棺から出されると、大気に触れたことで急激に酸化し、みるみる緑色に変色していったという逸話も残っている。当時を知る関係者によると、諭吉の遺体には、大量の『お茶の葉』がまとわりついていたという。
『遺体が抗菌作用のある茶の葉と、冷たい伏流水に浸かった状態だったため、奇跡的に生身のまま残ったようです』(関係者)」
そして、この信じられない出来事について著者は次のように述べます。
「想定外の出来事に親族は対応について苦慮し、大学関係者とも話し合った末、結局遺族の意思を尊重し、諭吉は荼毘に付され(火葬され)た。そして、予定通り、錦夫人の遺骨や墓石とともに、善福寺に移された。
想像の域を出ないが、諭吉の墓の改葬が38年前でなく、現在であれば、どういう対応が取られただろう。ひょっとしてすぐに火葬されなかったかもしれない。奇跡的に良好な保存状態で見つかった諭吉の遺体からは、DNAが採取できた可能性がある。慶應大学医学部に遺体の一部でも保存することが真剣に検討されたかもしれない」
「地方と都市を彷徨う墓地」の最後では、日本宗教学会理事で淑徳大学兼任講師の武田道生氏の以下の言葉を紹介しています。
「今、団塊世代が田舎に住む親を、都会に呼び寄せています。そして両親が死んだ段階で墓も自分たちの生活圏に移す。それは地方から都市だけでなく、都市から地方への移動も含め、墓が日本全国を大移動するという”墓が彷徨う”時代が、この先20年くらいでやってきます」
「世界遺産の恩恵はどこへ」では、「葬儀相場のウソ」として、著者は葬儀費用について「葬儀の場合、東京ではスタンダードな額といわれる50万円を布施の1つの基準としよう。京阪神や名古屋などではその半分の水準(20万~30万円)とされ、地方都市だと10万円を切るところも多い。宝光寺のある石見地方では、先述のように3万~5万円という。東京の10分の1以下の水準だ」と書いています。
一方で県境を越え、広島市内に入れば20万円以上が貰えるといいます。
東京の布施の値段があたかも全国の寺のスタンダードであるかのように語られますが、著者は「お寺さんは裕福だ」「坊主丸もうけ」というのは誤解であると述べています。
また、「政教分離が阻む再建」として、著者は東日本大震災における被災寺院について次のように述べています。
「被災寺院―。東日本大震災における宗教施設の被害については、取り上げられることは少ない。しかしながら、寺や神社が津波にのみ込まれ、跡形もなく消えた施設は少なくない。伽藍や墓が流されただけでなく、住職やその家族が亡くなったケースもある。そうした宗教施設は、震災から4年以上が経過した今でも、ほとんど再建できていないのが実情だ。というのも、一般家屋であれば、被災の程度によって自治体などから住宅再建のための助成金を受けることも可能だが、宗教団体は公の支援を受けることはできない。いわゆる『政教分離の原則』があるからだ」
しかし、東日本大震災における被災寺院数は少なくとも287カ寺(全日本仏教会『東日本大震災支援中間報告書』における寺院支援先)にも及ぶそうです。到底、宗からの義援金ですべてが賄えるものではありません。
本書では、浄土寺という被災寺院の住職が「こんなこと言うのは、本当に嫌な気持ちになるんだけれど」と前置きしてから語った、震災後の寺院収入の原則が崩壊している実情が以下のように紹介されています。
「浄土寺では最初の合同葬儀は非常時であったため、1軒当たり一律5000円と供養料を定めた。だが、それがその後、『何かにつけて5000円』になってしまったという。本来であれば震災前のこの辺りの1軒の葬儀の布施相場は、20万~30万円の水準である。
布施の中身は『お気持ち』であることは確かだが、地域には『常識的な布施』の相場があって、寺院経営を維持してきた」
震災直後、一時的に布施や葬儀代の金額が下がるのは仕方ないにせよ、時間が経過した今でも元に戻っていないというのです。収入面が安定しなければ、寺院活動を維持するのは不可能です。この浄土寺のような問題は、東北沿岸の多くの被災寺院で見られるといいます。本書には「地域の氏子が支える神社の再建はさらに厳しいでしょうね」との住職の言葉も紹介されています。著者は「街は復興が進み活気を取り戻しつつある。しかし、宗教施設の復興は完全に置き去りにされている実情がある。東北沿岸の街から、物的にも精神的にも、宗教が消えようとしている」と書いています。
 玄侑宗久先生と
玄侑宗久先生と
さて、【賢人に聞く 1】では、わたしが親しくさせていただいている作家で現役住職の玄侑宗久氏が登場します。玄侑氏とわたしは、ともに京都大学こころの未来研究センターの連携研究員を務めています。玄侑氏は「宗教は『時代遅れ』でもいい」というタイトルで大いに語っていますが、まずは「経済」について次のように述べます。
「われわれは極めて純粋な『贈与』を受けながら生活を支えてもらっています。市場経済の原理でモノを見ている人は、僧侶は特権的だとか腹立たしく思う人もいるかもしれませんが、こういう経済の在り方が日本に存在するということを知ってもらいたい。
そもそも、『経済』の言葉の語源は『経世済民』です。『世を治め、民を救う』という意味です。『経済』とはもともと、非常に豊かな意味を含んだ言葉なんです。それが最近、『市場経済』だけに限定され、『経済』が含み持つ意味が細ってしまっています」
また、玄侑氏は寺院経営について次のように述べています。
「お寺が大きくなればなるほど、檀家さんの顔や生活が見えなくなり、葬儀や法事も事務的になってくる。寺も葬儀屋さんも変わらない状態になれば、一見限りの葬儀屋さんでもいいということになります。おらが寺の和尚さんに、『送ってもらいたい』と檀家さんに思っていただけるか。そこが寺の生命線です」
さらに「お布施」について、玄侑氏は次のように語ります。
「お布施とは何なのか。贈る側が金額を決める。これが布施なんです。頂く側が、決めるわけではない。
余談ですが私が書いている原稿は出版社が原稿料を決める。普通の商売はモノの値段は売り手が決めるのに、なぜか物書きの世界は、買い手が決めるという不思議な慣習があります。私の原稿料はいわば、お布施なんですよ。それに対してやはり私も、お布施の気持ちで原稿を書いています(笑)」
うーん、これはその通りですねぇ。それにしても、さすがは芥川賞作家、うまいことを言われますな!
それでは、寺院とは何か。玄侑氏は次のように語ります。
「バラバラになった人に対して再び、『集まろうよ』と言って、祭りや、正月、お盆、お彼岸などの年中行事を通して、きっかけを提供できるのは寺や神社だけです。そう思えば、地域の紐帯として、寺や神社の存在は本当に重要だと思います。残念なことに、そうしたことは人々が危機的な状況にならないと見えてこないんだと思います」
いわば寺や神社は「地縁」を強化する文化装置のようなものですが、玄侑氏は続けて述べます。
「地域独特の『余計なこと』ってありますよね。人付き合いとか、お墓参りとか、しきたりとか、季節の行事とか。われわれは合理的な考え方でどんどん『余計なこと』を省いてきたのでしょうが、浅慮だったとしか言いようがないです。地域の『余計なこと』こそ、深い意味合いを持っている。確かに地域の中で生活するのは厄介ですよ。隣近所と関わらないでやれるならそれに越したことはないという人も多いでしょう。現代人は面倒なお付き合いを避けがちですよね。でも考えれば面倒なお付き合いこそが、『絆』なんです。絆って、語源は馬の鼻づらをつなぐ綱のことですからね。絆は、束縛そのものなんです。その束縛を、面倒と考えるか、貴重なネットワークと考えるか。それはその人の考え方次第なんじゃないでしょうか」
そして「寺は社会の変動を受けてはいけない」として、玄侑氏は次のように語ります。
「自分の死後、どういう状態で、どこに埋葬されようが別に構わないというのは、こうした連続性が意識できなくなっているのかも。先祖や地域など、多くの連続性を感じるということを、生きがいとして感じてほしい。さらに言えば、寺や仏像はなぜ尊い存在なのか。それは何百年もの間、寺が修行の場であり、仏に対して僧侶や信者が仏餉をはじめとするお供え物を連綿と続け、手を合わせ続けてきたからにほかなりません。連続性さえ大事にすれば、『死後、自分がどこに埋まるのか』ということも含めて、理屈では説明しにくい安心感をもたらしてくれると思います。
最後に言葉の語義に詳しいことで知られる玄侑氏は「寺」の意味について述べます。
「『寺』という言葉の意味をご存じですか。『同じ状態を保つ』という意味です。『ぎょうにんべん』を付ければ、同じ状態で佇むことを意味する『待つ』。それが、主君を守備する『侍』の勤めでもあります。もっと言うと、『やまいだれ』を付ければ、なかなか治らない『痔』ということですよ(笑)」
こういうユーモアのあるお坊さんなら、檀家さんたちも楽しいでしょうね。
二章「住職たちの挑戦」の冒頭には「『ゆうパック』で遺骨を送る時代」というレポートが紹介されています。埼玉県熊谷市にある曹洞宗・見性院に毎週のように「遺骨」が宅配便で送られてきます。遺骨の配達は日本郵便の「ゆうパック」だけが「配達可能」だそうです。大手宅配会社のほとんどは受け付けていません。本書には次のように書かれています。
「見性院の住職・橋本英樹さん(49歳)が、ゆうパックを使った『送骨サービス』を受け付け始めたのが2013年10月のこと。寺に届けられた遺骨は本堂で供養した後、境内の永代供養塔に合同納骨という形で納められる。送骨による永代供養を希望する者は、見性院のホームページなどから申し込み、寺が用意してくれる専用の段ボール箱に骨壺を入れて送るだけだ。永代供養の基本料金は3万円(送料別)。月に遺骨3~5柱が見性院に届けられるという」
遺骨を宅配便で送るという手段さえ除けば、その後は一般的な永代供養と同じであるとしながらも、この行為に違和感を抱く人は多いようです。これについて、著者は次のように述べています。
「誤解を恐れずに言えば、この問題は、熊本県の慈恵病院が取り組んでいる『こうのとりのゆりかご(通称・赤ちゃんポスト)』の議論に似ている気がする。親の事情によって育てられない赤ちゃんの命を救うために、匿名で病院が引き取る仕組みだが、『生まれた子供を親は責任もって育てなければならない責任と倫理の崩壊を招く』『育児放棄や捨て子を助長する』などの批判意見も根強い。しかし、不遇な環境の下に生まれてきた命は、『受け皿』があってこそ救われることもある。ゆりかご(赤ちゃんポスト)と墓場(送骨)の問題はむしろ、『そうせざるを得ない』状況を生み出す社会構造にこそある。もちろん、いかなる事情であろうとも『命』や『骨』を託す人たちの責任は重い。1つ言えることがあるとするならば、赤ちゃんや死者に罪はないということだ」
ところで、この物議を醸している橋本住職は「葬儀を葬儀屋から取り戻す」ことを目指しているとか。本書には以下のように書かれています。
「葬儀のスタイルが大きく変化し始めたのは、1990年代以降だといわれている。かつて葬儀をする場所といえば、自宅や寺が多かった。しかしバブル期以降、全国的にセレモニーホール(斎場)が増え、近年は自宅葬や寺院葬がほとんど見られなくなった。現在、葬儀会場の大多数がホールである。そうなると葬儀の一切を葬祭業者が取り仕切り、僧侶は決められた時間に、決められた斎場で経を唱えればいいだけの存在になる。
『いわば、僧侶は”おがみ屋”になっているんです。今や、寺が寺としての役目を果たせるのは法事だけになっている。葬儀場所の”ホール化”は、お坊さんの存在が脅かされるだけではない。地縁の崩壊にもつながります。自宅や寺での葬儀には隣組の存在が必要でした。だから、地域から葬儀が失われるということは、隣組も失われることを意味します。失われてしまった寺院葬を取り戻すことは、地域社会を守ることにもつながるのです』(橋本さん)」
まあ、頑張っていただきたいものですね・・・・・・。
「本当に感動する葬儀をやりたい」では、東京都国立市にある日蓮宗・一妙寺という日本で最も新しい寺が紹介されます。まだ33歳という赤澤貞槙住職は、僧侶仲間から頼まれて、他の寺の葬儀や法事の手伝いをしているそうです。本書には以下のように書かれています。
「赤澤さんには、あたためていた腹案があった。それは『記憶に残る仏事』をすることだった。葬儀には、喪家や参列者の他にも葬儀業者や花屋、返礼品業者などさまざまな人が参加している。
『葬儀に関わるすべての人の心を打つ儀式をしようと思い、研究していました。葬儀にひと手間かけることで、とても感動的なものになると考えたのです。分かりやすいたとえで言えば、納豆を人に提供する時、パックのまま出すのと、美しい器に盛り直してネギを添えて出すのとでは、全く別のものになりますよね。要は、それと同じことです』」
続いて、赤澤住職の試みが次のように紹介されています。
「それは、葬儀会場で喪家と対面するところから始まる。控室で沈香を焚いて待ち受ける。戒名の授与の際には金襴の敷物を恭しく広げ、その場で墨書きして披露する。戒名の由来を文書にして添え、丁寧に説明する。戒名の授与一つとっても、厳かな空気がその場に流れる。
演出的、と言えばそうかもしれない。しかし喪家や関係者の目には、そうした手の込んだ『仕掛け』が新鮮に映る。なぜなら、これまでの寺檀関係者による葬儀が、マンネリとなっていたからだ。僧侶も檀家も、仏事を『こなしている』だけだった。だから『高いお布施を取って、大した葬式じゃなかった』と不満を口にする遺族が多い。『葬式仏教』と揶揄される原因も寺檀関係のマンネリズムにある。
『仏事の細部にこそ、仏教精神が宿ると考えたのです。葬式や仏事に熱心な僧侶には批判が集まりがちですが、私は仏事こそが一般社会と僧侶をつなぐ大切な接点だと考えています。「葬式坊主」と言われても、その場できちんと法を説けばよいことです』」
 石井研士先生と
石井研士先生と
【賢人に聞く 2】では、これまたわたしが親しくさせていただいている國學院大學副学長の石井研士氏が登場されています。石井氏とわたしは、ともに冠婚葬祭総合研究所の客員研究員を務めています。その石井氏は「25年後に35%の宗教法人が消える」として多くのデータをもとに意見を述べておられます。
インタビュアーの「仏教より神道の方が厳しい時代だと」という質問には、以下のように答えています。
「例えば急速に神棚を置く家庭が減っています。戦前戦中までは神棚と仏壇は、家庭に100%あったと言われていますが、今、全国平均で神棚がある家庭は40%ほど、仏壇は50%ほどです。東京だと神棚がある家の割合は、22%ほどです。これは、地縁が解体されてきている証しだと思うんです。地域共同体が解体し始めた。日本は昭和30年代から都市化が始まって、昭和40年代の冒頭から過疎化という言葉が使われ始めた。そうして『地縁の解体』が一般化してきています」
石井氏は、増加する「墓じまい」や散骨にも言及しています。
「お金の問題は報道ではしばしば取り上げられますが、もっと根本的なのは家族の問題でしょうね。民俗学者の柳田国男が言っていますが、日本人は『自分が祀ると同時に、祀られる存在になることを期待している』というのです。つまり死んだら『ご先祖様になる』ということです。しかしその構造が壊れつつあります。だって、祀り手がいないのですから。今後、独身の独居老人の孤独死者、つまり誰にも祀ってもらえない人が年間25万から30万人ぐらい現れ、その数はどんどん増えていくことが予想されています。最近になってそのことを多くの人が実感できるところまできてしまい、急に墓じまいとか自然葬とか散骨という言い方が増えているのだと思います」
「今から日本の宗教団体が取り得る対策はありますか」という質問に対しては「どうにもならないでしょう」と答えた上で、以下のように述べています。
「高度経済成長は日本人が望んだこと。その結果、都市に人が集まるということを政府は奨励し、われわれも享受した。その結果、過疎化が起こって既に50年です。そうした中で、地域の寺や神社は大切だから、存続させなければいけないという考えは成立しない」
それでは石井氏は島田裕巳氏と同じようなニヒリストであり、無縁社会を肯定しているのでしょうか。いや、そんなことはありません。
神道学の殿堂である國學院の神道文化学部長から副学長を務められた石井氏は以下のように述べます。
「昔は例えば氏神様にお参りをし、日頃のお礼、感謝、無病息災を、寺や神社にお祈りしてきたわけです。あるいは寺という存在が死後の世界観と非常に深く関わっていた。それは、日本人の持っていた祖先崇拝の考えをうまく制度化したものとも言えるわけです。家の中に神棚があり、仏壇がある生活をしていて、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんが神棚や仏壇に手を合わせている姿を、子供が見て日々を送っていたのは、恐らく30年前までくらいでしょうか」
また、石井氏は「墓じまい」についても以下のように危惧しています。
「急速な都市化の中で祖先崇拝の考えが壊れてきて、家の中に神棚も仏壇もない。寺に行くのはお盆の墓参りだけ。そのうちに故郷の墓は『墓じまい』して、墓と寺との関係を断ち、自分や伴侶を含めて、全部散骨にする、あるいは樹木葬にするとなってきている。そうしてわれわれ日本人がこの国の風土の中でつくってきた宗教的な情操というものが壊れてきている。これは怖いことです」
ちなみに、わたしは、もうすぐ『墓じまい・墓じたくの作法』(青春新書インテリジェンス)という最新刊を上梓します。ここで、自分なりに「墓じまい」についての考えを述べるとともに、新しい「墓じたく」についても提案しています。本が刊行されたら、石井氏にも献本させていただきます。
三章「宗教崩壊の歴史を振り返る」では、「寺は消えてもいいのか」として、以下のように書かれています。
「気づけば『死後』は、”誰でも買える”時代になっている。
仮に大切な人が亡くなったとしても、葬儀社に電話1本すれば、お墓の面倒まで見てくれる。そこに必ずしも寺や僧侶が、主体的に介入する必要はない。葬儀社の『雇われ僧侶』なるものが既に現れている。数年前から僧侶専門の人材派遣会社が存在し、そこに登録する僧侶が葬儀会場や墓地に派遣され、経を読んで、さっさと帰っていく。依頼主と僧侶とは1回限りの関係で、後の寺檀関係を構築することもない。
派遣会社に登録する僧侶の多くは、自坊の檀家が少なくて『食べていけない住職』や、一般企業に就職できない寺の子弟たちである。寺の貧困が、結果的に民間の葬儀業者を利し、さらに寺が困窮するという悪循環に陥っている。だが、『それはお寺さんが経営努力をしてこなかったから。寺がなくなっても困らない』という冷めた人は多い」
「おわりに」で、著者は本書の3つの側面をまとめています。
1.地方の困窮寺院の声を拾ったルポルタージュ。
2.伝統仏教の構造をひもといた歴史書。
3.菩提寺との付き合い方が分かる実用書。
本書では、全国の7万7000カ寺のうち3割から4割が消滅する可能性を指摘していますが、「寺院消滅」の原因には歴史的背景(過去的要素)と、昨今の社会構造の変化(現在・未来的要素)の2つがあると述べています。
さらに「おわりに」で、著者は以下のように書いています。
「寺は寺檀関係を足掛かりにして、地域の小作農地を次々と取得。経済基盤を固めていった。しかし、明治に入って『国家仏教』が『国家神道』へと切り替わる。いわゆる廃仏毀釈によって寺院が破壊され、仏教界は壊滅的打撃を受けた。同時に『肉食・妻帯の許可』が仏教の俗化に拍車を掛けた。
さらに『信教の自由』が宗教間の布教競争を誘い、新宗教やキリスト教が勢力を拡大。仏教教団間で熾烈な布教合戦が繰り広げられる。起死回生をかける仏教界は日本政府の植民地化政策に乗る形で、大陸への布教を強化。教義をねじ曲げてまで戦争に加担していった」
続けて、著者は以下のように書いています。
「敗戦は国家を解体したが、全国の寺院にも強烈な一撃を与えた。GHQが主導した農地改革だ。寺院の経済基盤だった農地がことごとく小作人に払い下げられ、寺は困窮した。しかし、にわかに到来した高度経済成長・バブル景気が寺院経営を下支えし、仏教界は生き長らえることができた。
だが、いわゆる『失われた20年』で寺院を取り巻く状況は一変した。地方から都市への人口の流出、住職の高齢化と後継者不在、檀家の高齢化、布施の『見える化』、葬儀・埋葬の簡素化など、社会構造の変化に伴う問題が次々に浮上。全国では空き寺が急増し、寺院の整理・統合の時代を迎えようとしている―」
本書の終りには「解説」として、作家・元外務省主任分析官の佐藤優氏が「消滅しそうで、消滅しない」という文章を寄稿しています。宗教に造詣が深いことで知られる佐藤氏ですが、以下のように述べています。
「最も強い宗教は、死のときに人びとの心をつかむ。シンクレティズム(宗教混交)が日本人の宗教性の特徴であるが、生まれたときはお宮参り、七五三でも神社のお世話になり、結婚式は神式かキリスト教式が多いが、葬儀は仏教というのが、一昔前までの多くの日本人の宗教との付き合い方だった。『葬式仏教』と揶揄されているが、少数派であるキリスト教から見るならば、葬式で人びとを惹きつける宗教が、もっとも強い宗教なのである。キリスト教が結婚式では優位性をもっているとはいえ、結婚は多い人でも3回くらいしかしない。2回目以後は結婚式をしないことが多い。それに対して、死に関しては、通夜、葬儀、初七日、四十九日、三回忌、七回忌、三十三回忌、五十回忌などさまざまな行事がある。また、春秋の彼岸、お盆など追悼の機会は毎年ある」
まったく同感ですが、さらに佐藤氏は以下のように述べます。
「宗教が衰退しているのは、死に対する意識が変化しているから、と私は見ている。葬儀を行わず、墓をつくらない人が増えているのは、死に対する意識の変化だ。生のみを追及して、死は無意味であるという発想は間違いだと思う。人間は必ず死ぬ。それだから、限界を意識し、充実した生を送ることができるのである」
そして、最後に佐藤氏は以下のように本書の解説を締めくくっています。
「死の現実を広く社会に認識させれば、宗教は復興する。ニーチェは神の死を宣言した。キリスト教の神が、死にそうで、なかなか死なない。それと同じように寺院は消滅しそうで、消滅しない。日本で1500年近くの伝統を持ち、明治維新直後の廃仏毀釈の危機を乗り切った既成仏教教団が、都市化や少子高齢化如きに負けることはないと私は確信している」
この佐藤氏の宗教観あるいは葬儀観については、拙著『唯葬論』(三五館)および『永遠葬』(現代書林)でも言及しました。「死の現実を広く社会に認識させる」ことにわたしも尽力する覚悟です。
ともかく本書を読んで大きな刺激を受けるとともに、大変勉強になりました。
25年後、本当に日本中の寺院の多くが消滅しているのでしょうか。
