- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.05.08
『物語 ビルマの歴史』根本敬著(中公新書)を再読しました。
「王朝時代から現代まで」というサブタイトルがついています。 約460ページと、新書にしてはなかなかのボリュームです。
中公新書の『物語 歴史』シリーズはアジア各国を中心に好著が揃っており、これまでに「中国」「韓国」「フィリピン」「ヴェトナム」「タイ」「シンガポール」「中東」「イラン」「イスラエル」「エルサレム」などの歴史本が刊行されています。最新刊として、今年の5月に「イギリス」も刊行されました。著者は1957年生まれ、国際基督今日大学大学院比較文化研究科博士後期課程中退、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授などを経て、現在は上智大学外国語学部教授。専攻は、ビルマ近現代史です。
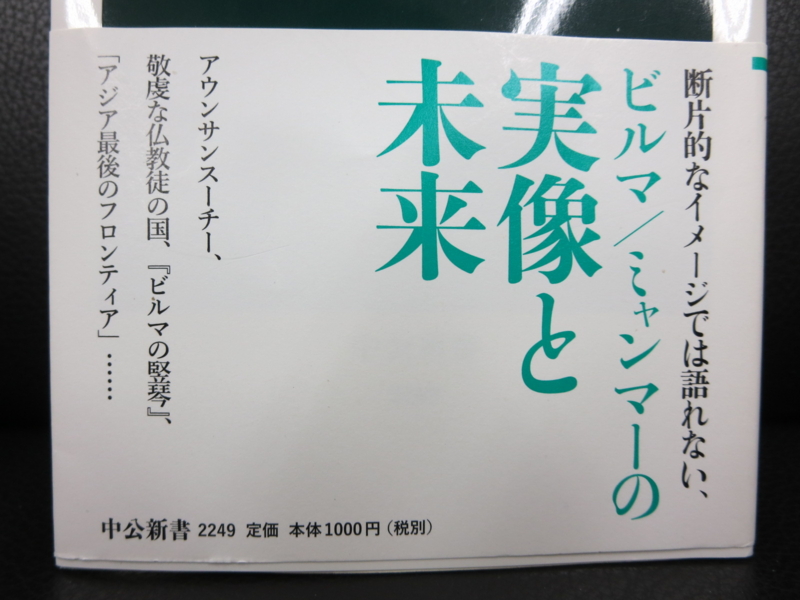 「ビルマ/ミャンマーの実像と未来」と書かれた本書の帯
「ビルマ/ミャンマーの実像と未来」と書かれた本書の帯
本書の帯には「断片的なイメージでは語れない、ビルマ/ミャンマーの実像と未来」「アウンサンスーチー、敬虔な仏教徒の国、『ビルマの竪琴』、『アジア最後のフロンティア』・・・・・・」と書かれています。
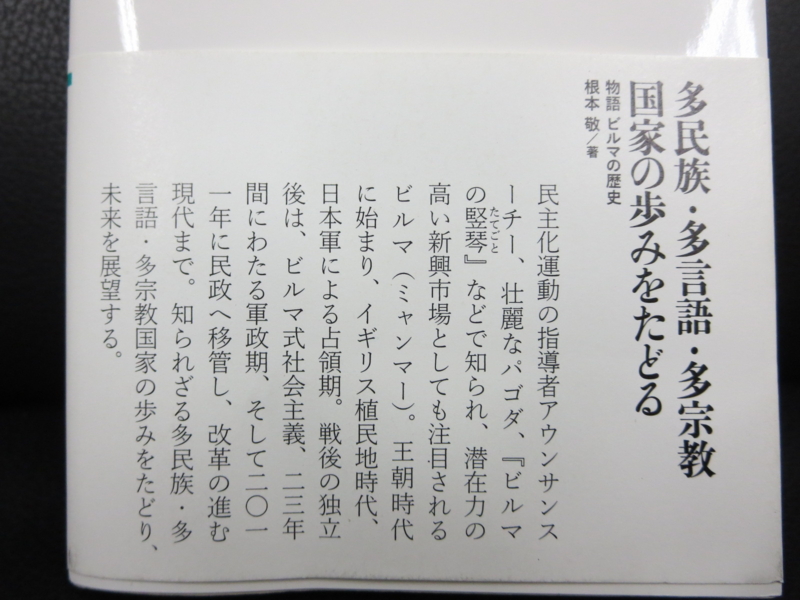 帯裏には内容紹介が・・・・・・
帯裏には内容紹介が・・・・・・
またカバー前そで、および帯裏には、「多民族・多言語・多宗教国家の歩みをたどる」として、以下のような内容紹介があります。 「民主化運動の指導者アウンサンスーチー、壮麗なパゴダ、『ビルマの竪琴』などで知られ、潜在力の高い新興市場としても注目されるビルマ(ミャンマー)。王朝時代に始まり、イギリス植民地時代、日本軍による占領期。戦後の独立後は、ビルマ式社会主義、23年間にわたる軍政期、そして2011年に民政へ移管し、改革の進む現代まで。知られざる多民族・多言語・多宗教国家の歩みをたどり、未来を展望する」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
序章 ビルマ(ミャンマー)という国
第1章 王朝時代のビルマ
第2章 英国植民地下のビルマ
第3章 ビルマ・ナショナリズムの擡頭
第4章 ビルマ人行政エリートの世界
第5章 日本軍の侵入と占領
第6章 独立への最短距離―対英独立交渉
第7章 独立後の現実―ウー・ヌ首相の時代
第8章 ビルマ式社会主義の時代―国軍による統治(1)
第9章 軍事政権とアウンサンスーチー―国軍による統治(2)
第10章 軍政後のビルマ―2011年以後
終章 ビルマ・ナショナリズムの光と影 「あとがき」 「参考文献」 「関連年表」
序章「ビルマ(ミャンマー)という国」では、まず「ビルマかミャンマーか―国名をめぐる基礎知識」という問題が取り上げられ、以下のように書かれています。 「この国のビルマ語名称は1948年の独立時からずっと『ミャンマー』である。一方、英語名称のほうは『バーマ(Burma)』が公式に使われ、国際社会でもその名前で知られてきた。日本でも『ビルマ』という呼称が用いられてきた。ところが、1988年9月に民主化運動を封じ込んで登場した軍事政権は、翌1989年6月に突然、英語の国名を『バーマ』から『ミャンマー』(Myanmmar)に変更すると宣言した。すなわち、英語の国名もビルマ語の『ミャンマー』に統一すると決めたのである」 著者によれば、ビルマでは王朝時代(11~19世紀)から、書き言葉(文語)では「ミャンマー」が使われ、しゃべり言葉(口語)では「バマー」が使用され、今でもビルマ人同士の会話(とりわけ年長者のあいだ)では「バマー」がよく使われるそうです。
さらに国名の呼称について、著者は次のように述べています。 「国連ではすぐに英語名称を『ミャンマー』に切り替え、現在に至っている。日本政府も国会の承認を得て日本語呼称を『ミャンマー』に変更した(1989年)。日本のマスメディアも一部を除いて『ミャンマー』表記に変えた。文部科学省の検定を受ける学校の教科書も同じである。世界の多くの国々も、米国や英国などの例外を除き、21世紀に入るころまでには『ミャンマー』(ないしはそれに近い発音表記)を使うようになった」
しかし、著者は次のようにも書いています。
「一方、『バマー』『バーマ』『ビルマ』を使いつづけたほうがよいとする見解も根強く存在する。これを一番強く主張しているのは、ビルマの国内外で反軍政側に立ってきた人々、すなわち民主化運動を支持してきた人たちである。彼らは『クーデターで登場した軍事政権が国民の合意を得ずに英語呼称を一方的にミャンマーに変えた』ととらえ、その命令を非民主的と断じ、従うことを拒絶してきた。彼らは現在でも『バーマ(ビルマ)』を使いつづけている。民主化運動指導者のアウンサンスーチーも同じ理由に基づき、英語で発言するときは『バーマ』を使いつづけている」
北九州市の門司には日本で唯一のビルマ式寺院である「世界平和パゴダ」がありますが、サンレーグループでは支援活動を続けています。 佐久間進会長が世界平和パゴダ奉賛会の会長を務め、わたし自身も「日緬仏教文化交流協会」の理事を務めています。その関係で、わたしのブログ記事「仏教文化交流シンポジウム」で紹介した、2013年9月21日に世界平和パゴダ建立55周年を記念して開催された「仏教は世界を救う」をテーマにしたパネルディスカッションに出演し、『ミャンマー仏教を語る~世界平和パゴダの可能性』(現代書林)という共著も上梓しました。
このようにビルマ(ミャンマー)は上座仏教の国ですが、じつは多様な宗教が共生する多宗教国家でもあります。根本氏は次のように書いています。
「人口の89パーセントを上座仏教徒が占めるとはいえ、残りの10パーセント強はキリスト教徒、イスラム教徒(ムスリム)、ヒンドゥー教徒、精霊信仰の人々から成る。ただ、イスラム教徒の人口比率は政府が示す数字よりも多いという指摘がビルマ研究者のあいだでは強い。国家が意図的に彼らの数値を低く発表している可能性がある。ビルマ政府は独立以来、『上座仏教を信仰し、ビルマ語を母語とする人々』(すなわちビルマ民族)を中心に国民統合を推し進めてきた。インド系のムスリムやヒンドゥー教徒は王朝時代からビルマに存在した人々であるが、英領植民地期になってから英国の政策で入ってきたインド系移民が目立ったため、のちに『招かれざる』移民として彼らをとらえる排他的ナショナリズムが反英独立運動のなかで生じるようになった。その影響から独立後もムスリムを『少なめに』カウントしようとする国家の意思が働いている可能性は否定できない。 ちなみに、現在の憲法(2008年憲法)では信仰の自由を認めながらも、上座仏教に『特別に名誉ある宗教』としての地位を与えている。そのうえで、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、精霊信仰の4つをビルマに存在する宗教としてわざわざ名指しで公認している(同時に宗教の政治利用の禁止も謳っている)」
昨今、あたかも最後のフロンティアのようにメディアを賑わすビルマ。かつては戦中派の思い入れの強い地として、そして現在はアジアの新市場としての印象が深い。「ビルマの竪琴」「インパール戦」「泰緬鉄道」「軍政」「アウンサンスーチー」「仏教」などキーワードは多く耳にするが、一般的にその実像が知られているとは言い難い。最近のブームでも専らマーケットや投資としての案内は多いが、歴史に焦点をあてて、その国の姿を説明したものは少ない。本書は、「ビルマ」と「ミャンマー」の違いなどの説明からビルマの歴史に焦点をあて解説された、ビルマを学ぶために非常に便利な一冊となっている。ビルマのことをこれから学ぼうとする人にも、既に有る程度関わりを持っている人にも一読の価値が高い。自分はビルマに少し関わっているが、こうして簡潔、かつビジネスチャンスという部分から離れてその国のことを説明した本をもっと早くに欲しかったと感じている。外交上も親日国として認識されているビルマ。ビルマの人は意外と(と言っては失礼だが)私達日本のことを知っている。私達も有る程度知っておくのは礼儀としても必要かもしれない。
さて、ビルマといえば、多くの日本人には竹山道雄の名作『ビルマの竪琴』を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、本書に収められた「『ビルマの竪琴』という幻想」には次のように書かれています。
「『ビルマの竪琴』は名作とはいえ上座仏教をまったく理解していない作品である。この作品に基づいてビルマのイメージをつくりあげるのは問題である。英国との戦争に負けた日本軍の兵士が、修行も行わずにいきなり比丘(正規の出家僧)になるという設定からして問題だが、この際それは横に置く。より深刻な問題点は、僧侶になった主人公が竪琴を奏でながら戦友の供養を行うことにある。日本では琵琶法師のようなイメージで受けとめられるかもしれないが、ビルマでは上座仏教の十戒に含まれる『歌舞観聴の禁』(音楽に親しんではならない)を犯す行為とみなされ、この僧侶は破戒僧ということになってしまう。戦友の遺骨を拾って供養するという行為も、日本では理解されやすい宗教的行為だが、ビルマの上座仏教から見れば何の意味があるのかわからない不思議な行いに映る。 上座仏教では遺骨に執着しない。なぜなら人間は死ぬとその大切な魂は肉体を離れ来世にいくと考えられているからである。残された遺体に特別の意味は見出されず、遺体の焼き場でもお骨を残していく遺族が多いのが現実である」
第9章「軍事政権とアウンサンスーチー」では、ノーベル平和賞を受賞した民主化運動の指導者アウンサンスーチーの思想の特徴が以下の3点にまとめられています。
(1)恐怖からの自由 アウンサンスーチーの思想と行動の基盤は「恐怖からの自由」という言葉で表現される。ただしそれは。世界人権宣言などの精神に含まれる「誰でも恐怖から自由に生きる権利を有する」という「権利」としてよりも、「一人ひとりが恐怖に打ち勝つ努力を行うべきである」という「義務」として強く語られる。彼女は「恐怖」こそ、あらゆる人々を堕落させ、社会を腐敗させていく根源であると断言し、人間はこの「恐怖」を克服して自ら自由になろうとしない限り、自分や自分の属する社会を改革することはできないとみなす」
(2)正しい目的と正しい手段 アウンサンスーチーの思想のもうひとつの特徴は、「正しい目的は、それにふさわしい正しい手段を用いない限り達成できない」という考え方に見られる。これは言い換えれば、目的と手段における「正しさ」の倫理的基準の一致を意味する。インド独立運動の指導者ガンディーが「良い木は良い種しか育たない」と言ったことと深く通じる考え方である」
(3)真理の追究 彼女によれば、真理とは「自分がどちらの側につくかによって、脅威になったり味方になったりする存在である」とされる。それは常に到達目標であり、有限の人生においてけっして到達することも完全に把握することもできないが、自分自身と自分が置かれている状況の「自覚」と「客観視」という自己努力を通して、常に追い求めるべき存在として語られる。そこでは「主観性を克服する闘い」として「偏見から自由になること」が求められ、常にその実践を通じて真理が追究される」
このようなアウンサンスーチーの思想の特徴である「恐怖からの自由」「正しい目的と正しい手段」「真理の追究」は、いずれもビルマ(ミャンマー)が民主化する上で必要不可欠なおのでしょう。しかし、それを国民全体が共有するには教育の問題が大きく立ちはだかります。著者は終章「ビルマ・ナショナリズムの光と影」の「教育改革―従順な人間から自分で考える人間へ」で、以下のように述べます。
「義務教育が実施されていないことも、ビルマの教育問題を考えるうえで避けて通ることのできない大きな問題である。ビルマでは、これまでに一度も義務教育が実施されたことがない。独立運動のころからその必要性が訴えられてきたにもかかわらず、予算不足や教員養成機関の不足などを理由に、政府によって常に先送りされてきた。小学校1年生への就学率は高くても(実際90パーセントを超える)、毎年実施される進級試験に落ちて落第すると、義務教育ではないため、その子供は学校に来なくなってしまうことが多い。結果的に落ちこぼれが増え、中学校進学の段階で就学率は50パーセントまで下落することになる。これに付随して、英領期に導入された10年制という中途半端な教育制度の問題も指摘しておきたい。『小学校4年→中学校4年→高校2年』というこのシステムは、国際標準の12年制システムより2年短いため、十分な基礎教育と中等教育を受けられないばかりか、ビルマ人が海外に留学するとき不利に作用する(高卒扱いされないことが多い)。12年制システムに切り替えることが現実的課題となっている」
わたしのブログ記事「安倍昭恵総理夫人講演会」で紹介したように、安倍晋三内閣総理大臣夫人である安倍昭恵氏は、僧院の教育施設をサポートするという形でビルマの子どもたちの教育支援をされておられます。 また、世界平和パゴダ奉賛会でも、ビルマに新しく学校を建設する運動を進めています。「アジア最後のフロンティア」として、ビルマ(ミャンマー)に熱い視線が集まっています。しかし、単なる消費経済の市場、安価な労働力の供給源、はたまたエネルギーの宝庫といった見方だけでなく、ビルマの国が築いてきた文化を見つめた交流が必要であると思います。 本書の内容は「ビルマの歴史」というよりも「現代ミャンマーの課題」といった印象を受けましたが、いずれにせよ、世界平和パゴダの支援をさせていただくうえの良い勉強になりました。
