- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0943 宗教・精神世界 『世界は宗教で動いてる』 橋爪大三郎著(光文社新書)
2014.06.23
『世界は宗教で動いている』橋爪大三郎著(光文社新書)を読みました。
著者は、この読書館でも紹介した『ふしぎなキリスト教』の共著者で、日本を代表する社会学者の1人です。1948年神奈川県生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。1995年から2013年まで、東京工業大学教授を務めました。日本人が宗教を論じた本としては小室直樹著『日本人のための宗教原論』という大変な名著があるのですが、在野における「知の巨人」として知られた故・小室直樹の弟子が橋爪氏です。
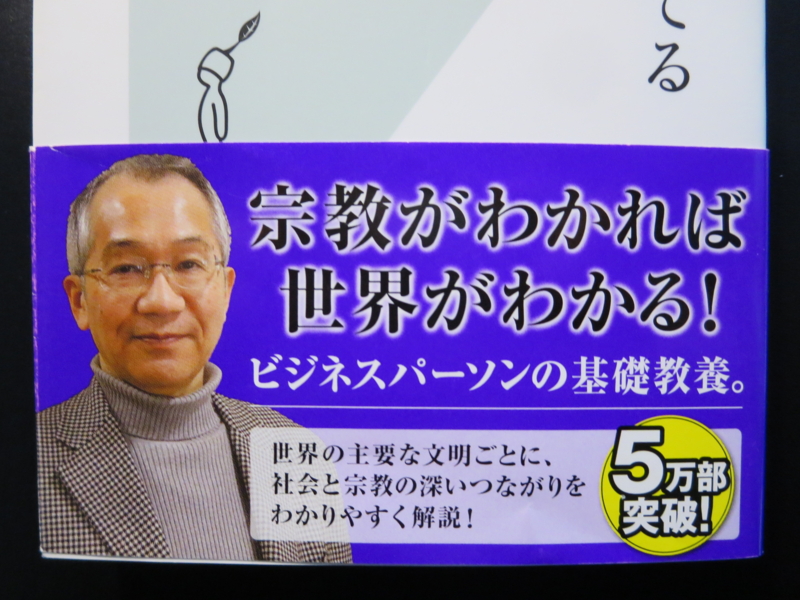 宗教がわかれば世界がわかる!
宗教がわかれば世界がわかる!
本書の帯には著者の写真とともに「宗教がわかれば世界がわかる!」「ビジネスパーソンの基礎教養。」「世界の主要な文明ごとに、社会と宗教の深いつながりをわかりやすく解説!」と書かれています。
また、カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「キリスト教はウォール街の”強欲”をどう考える?
イスラム教は平和のための宗教?
ヒンドゥー教のカースト制は本質的に平等?
世界を読み解くには、宗教が最大の補助線になります。ヨーロッパ人もインド人も中国人も、当人たちは意識していなくても、長い歴史をへたキリスト教、ヒンドゥー教、儒教の発想や行動様式に支配されています。宗教を理解すれば、グローバル世界を読み解く最大の鍵が手に入るのです。
―世界の宗教について比較研究を行ってきた著者が、主要な文明ごとに、社会と宗教の深いつながりをわかりやすく解説!」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」
第一講義 ヨーロッパ文明とキリスト教―イエスの父はヨセフか、それとも神か
第二講義 宗教改革とアメリカの行動原理―ウォール街の”強欲”をどう考えるのか
第三講義 イスラム文明の世界―イスラム教は平和のための宗教
第四講義 ヒンドゥー教とインド文明―カーストは本質的に平等
第五講義 中国文明と儒教・仏教―儒教はなぜ宗教といえるのか
第六講義 日本人と宗教―カミと人間は対等の関係にあり
「参考文献」
「まえがき」の冒頭には、「『ビジネスマンなら、宗教を学びなさい。』ビジネスマンの皆さんには、こう言うことにしている」と書かれています。そして、著者は以下のように述べています。
「宗教を、経済・政治・法律・科学技術・文化芸術・社会生活と、別ものと思っていませんか、あなたは。
たしかに日本では、それはそうかもしれない。ふつうに日本人として生まれ、学校教育を受け、社会に出ても、宗教と正面からぶつかる機会は多くない。葬式や結婚式か、初詣、さもなければ、突然押しかけてくる新興宗教。宗教とほぼ無関係に、一生を送ることができてしまう。
でもそれが、大きな間違い。日本以外のたいていの国では、経済・政治・法律・・・・・・社会生活を、まるごとひっくるめたものが『宗教』なんです。キリスト教がかつてそうだったし、イスラム教ではいまもそうである。ゆえに。『宗教』を踏まえないで、グローバル社会でビジネスをしようなんて、向こうみずもはなはだしい」
本書は、慶應丸の内シティキャンパスで行われた「宗教で読み解く世界」の講義(3時間×全6回)をもとにしています。講義ではユダヤ教・キリスト教・イスラム教・ヒンドゥー教・仏教・儒教・道教・神道と、数多くの宗教が順番に論じられていますが、著者は次のように述べています。
「世の中には専門家という人びとがいて、とれかひとつの宗教についてなら詳しく教えてくれる。だが、多くの宗教の関係を教えてくれるひとがいない。いま、グローバル世界で必要なのは、異なった信仰やちがった文明に属する人びとが、どういう国際社会(コミュニティ)をつくって行けるか、という構想である。それには、さまざまな宗教の『相互関係』を考えなければならない」
一連の講義を通して、明らかになることは何か。著者は述べます。
「宗教には、『自分とは何なのか』という問いが、凝縮されている。人間として生まれた誰もが、避けて通ることのできない問いである。だからこそ世界のどの文明も、宗教を核にして、その社会のまとまりをつくった。そのつくり方にはいろいろ違いがあるが、人類の知的遺産とはすなわち、宗教のことだと言っていい。『宗教のリテラシー』は、だから、複数の文明圏が並びたつ現代世界を生きるわれわれにとって、不可欠のものなのである」
そこで、著者はビジネスマンでない人々に対して、「人間なら、宗教を学びなさい。」と言うことにしているそうです。
第一講義 「ヨーロッパ文明とキリスト教」は、『ふしぎなキリスト教』の内容と重なっています。「Godは『怖い』」と言う受講生に対して、著者は以下のように述べています。
「ユダヤ教の神ヤハウェ(エホバともいう)が、まさにそういう怖い神、強い神です。
そこにイエス・キリストが現れて、別の神のスタイルを提示しました。神が人間の主権者であるという点はまったく変わらないのですが、人間に対する神の態度が変わった。
イエスは、神が怖く思えるのは、神がじつは人間を大事にしているからだ、とした。神が人間を大事にすることを愛と呼び、神の厳しさは愛なのだ、と言ったのです。愛とは、手助けをしたい、救いたいということ。神は人間に対してこういう態度を取っているというふうに、神を考え直した。これがキリスト教なのです。
こうしてキリスト教は愛の宗教になるのですが、それには、まず神は『怖い』という感覚があり、そのうえで『愛されている』と言われる。人間は、『ああ、よかった』となる。こういう順番になります。愛の中に怖さが隠れているとも言えるし、怖さの中に愛が隠れているとも言える。怖さと愛のサンドイッチです」
ユダヤ教では、モーセに代表される預言者が重要な役割を果たします。
著者によれば、預言者はおおむね以下の3つの条件を満たすことで人々に認められていきます。第1に、それまでの預言者の語る神の言葉を踏まえていること。第2に、先輩の預言者から「おまえはほんとうの預言者だ」とお墨付きをもらうこと。第3に、ニセ預言者を論破すること。著者は、預言者について次のように述べています。
「結局、誰がほんとうの預言者か、その時どきの事情に応じて人びとが適当に決めることになるのですが、もともと人間にそんなことを決める権利はない。だから間違う。その間違いの最たるものは、神が送ったイエス・キリストを拒否して、処刑してしまったことです。キリスト教からすれば、そういう言い分になる。これにまさる人間の罪はない。
イエスがほんとうに神の子なら、なんでもできたはずですが、抵抗らしい抵抗もせず、イエスは十字架にかかって死んでしまう。これ以上大きな愛はない。という話を信じるかたちで、キリスト教はできあがっているのです」
さて、キリスト教は死についてどう考えるのか。この問題について、著者はわかりやすく説明しています。
「キリスト教では、人間が死んだあと、霊魂がフワフワ漂っているというような考え方を認めない。霊魂の存在を認めないのですが、それなのに、個々人の人格は永遠不滅だと考えます。なぜか。個々人の人格をそのつど、Godが造り、そしてGodが死なない(永遠である)からです」
そして、著者は以下のような比喩を用いて説明します。
「人間がバイオコンピュータで、人格がカスタマイズされたソフトみたいなものだとすると、そのデー夕が全部、Godのもっているメガディスクに保存されている。コンピュータのハードウェアが壊れても、そのうち、新しい上級機種のコンピュータを与えられ、データがインストールされて動き出す。これが、復活ですね」
これは非常にわかりやすいアナロジーであると思います。
ここで受講生が「キリスト教においては、医療などの救命はどういうことになるのか」という質問をします。これに対して、著者は次のように答えます。
「聖書には人間の寿命について、興味深い記述があります。ヤハウェが人間の寿命を、120年とした、と書いてあるのです。したがって、120年より前に死ぬのは早すぎる、のです。この考え方だと、キリスト教徒の医療の目的は、人間を、その寿命である120歳にまで生き長らえさせることである、ということになる」
そして、「以上をまとめて、結論。」として、以下のように述べます。
「キリスト教徒は、人間が死ぬのは間違いだ、と考えている。人間は罪の結果死ぬのですが、それは、人間とGodの関係が正しくないことの結果。かりそめの、不正常な状態です。イエス・キリストが復活したのは、すべての人間が将来、確実に復活するという意味です。したがって人間の生死を思い煩うべからず、ということになる。それよりも、現在を大切にしてしっかり生き、Godに救われることのほうがはるかに重要なのです」
第二講義「宗教改革とアメリカの行動原理」では、「宗教的寛容とはにか」という問題が取り上げられます。宗教改革によってプロテスタントが起こりました。以来、カトリックとプロテスタントの対立構造が生まれましたが、著者は次のように述べています。
「互いに相手は、悪魔みたいなもの。悪魔なら早く殺したほうが、罪が少なくなるので、悪魔にとってもよいことである。相手を抹殺することは、神のためであり、自分の安全のためであり、悪魔自身のためでもある。そういう理屈になります。そう信じているのだから、殺し合いは容赦がない。これが宗教戦争の恐ろしさで、カトリックとプロテスタントは、延々と殺し合いを続けて、果てしない。結局、気がついてみたら、100年以上にもわたって、宗教を理由とする殺し合いが続いた」
「キリスト教は経済をどう考えるのか」という問題では、神の業(ネイチャー)と人の業(カルチャー)という興味深い視点が以下のように示されます。
「神の業はネイチャーです。それに対して、人間のやることはカルチャーです。カルチャーはもともと『土を耕す』こと。農業です。では神は、農業をやるか。やりません。必要ないからです。農業を始めたのは人間です。エデンの園では、農業は必要なかった。食べ物はなんでもあった。でも、追放されたので、額に汗して日々の糧を手に入れなければならなくなった。これが農業と牧畜で、人間の業なのです。そのほかにも人間がやるものとして、アート(技術、芸術)がある。これにも、良い場合と悪い場合がある」
第四講義 「ヒンドゥー教とインド文明」では、イスラムとの関係を論じた以下の部分を興味深く読みました。
「インドのカースト制に、反対する宗教があります。イスラム教です。
イスラムはカースト制を認めません。イスラムの場合、アッラーの前では、すべての人間は平等です。だから、どんな職業に就いてもいいし、誰と誰が一緒に食事をしてもいい。礼拝のときも社会的地位と無関係に、みんなが横一列に並びます。これは人びとの平等を示している。こうしたイスラム教に魅力を感じて、改宗したインド人も大勢います。けれども、インドの人びとの大部分は、ヒンドゥー教を続けることを選んだ。イスラム教とヒンドゥー教は、水と油のようで、混じり合わないまま併存している」
インド人の宗教で重要なキーワードは「輪廻」です。著者は、以下のように「輪廻」について述べています。
「カースト制のいっぽうで、インド人は輪廻という考え方にこだわります。これもインド人だけの考え方です。カーストと輪廻は表裏の関係で、現世で低いカーストであっても、死んで生まれ変われば違うカーストになる可能性があると考えます。
輪廻と対照的な考え方が、祖先崇拝です。中国は祖先崇拝なので、仏教を導入したけれど輪廻は理解しがたいものでした。儒教には、輪廻はありません。結局、中国でもかたちだけ仏教は残っていますが、輪廻は無視された。輪廻の考えは、中国人の発想のなかにほとんど残っていません。
日本人は、祖先崇拝をしているつもりかもしれませんが、本場の中国、韓国にくらべると、こんなものは祖先崇拝のうちに入らない。外国でもやっているからと、気休めのようにかたちばかりを取り入れただけです」

わたしはアジア冠婚葬祭国際交流研究会でミャンマーについて講演を行い、そこでミャンマー仏教などの「上座部仏教」と日本仏教などの「大乗仏教」との違いについて説明しました。また、『ミャンマー仏教を語る』(三五館)でも、ミャンマー仏教と日本仏教との違いを大いに論じましたが、そこでの最大のキーワードは「輪廻」と「先祖供養」ということです。著者いわく、日本人は「輪廻を信じているわけでもないし、かといって、祖先崇拝をまじめにやっているわけでもない」ということになります。
ここで「日本にも生まれ変わりの考え方はあります」との意見が出されますが、著者は以下のように述べます。
「生まれ変わりと輪廻は違います。日本では大昔、幼い子どもが死ぬと、正式の墓に葬らずに、家のそばに埋める習慣がありました。生まれ変わってほしいという親の思いです。これなども輪廻とは関係ありません。輪廻だったら、何に生まれてくるかはわからないのです。ほかの動物になったり、ほかのカーストになったりしているはずで、もとの家に生まれてきたりはしない。
輪廻は、おもしろい考え方で、人間と動物のあいだに境がありません。動物と人間は同類、という考え方です。これは一神教と大変に違う。一神教だったら、サルと人間はまったく違うものであって、同類だなどとは考えない。それぞれの種は、神によって別々に造られたと考える。
いっぽう輪廻では、生命体としては同じですから、ほかの動物に生まれ変わるのがふつうなのです」
「仏教はヒンドゥー教とどう違うか」という問題も興味深いです。著者は「仏>神」と明快に断じ、「これが仏教のいちばん大事な不等式です」として、以下のように述べます。
「この右辺の神とは、インドの神々、ヒンドゥー教の神々です。左辺の仏とは、とりあえずゴータマ・シッダルタのことですが、仏とは『覚った人』のことだから、人間でもある。したがって、『神より仏が大事』ということは、『神より人間が大事』と言っているに等しいことになる。そういう意味で、仏教は、人間中心主義です。人間の能力を極めて高く評価する」

第五講義「中国文明と儒教・仏教」では、「諸子百家」と呼ばれた数多くのグループの中でなぜ儒教が勝ち残ったのかが論じられます。著者は、中国の農業が家族経営であることに注目します。そして「農業は、命令に従うだけの奴隷制では、うまくいきません。農民の自発性を引き出す必要がある。骨身を惜しまぬ労働と工夫は、農民がまったく利己的に行動するのではなく、家族や子どものことを考えて利他的に行動するほうが、うまく引き出せる」と指摘します。これは、『孔子とドラッカー』(三五館)で初めて示した、わたしの「ハートフル・マネジメント」にも通じる考え方です。
「家族道徳は農業の基本」と考える著者は、次のように述べます。
「家族道徳と農業の家族経営は一体の関係にあり、それを重視する点が、儒家の非常に現実的なところです。中国の社会構造の基本は、中央政府は官僚制、底辺のグループは宗族(父系血縁集団)という二層構造。この中国社会の骨格は、儒教がつくったものです。中華人民共和国も、この構造を踏襲している。その意味では、現在でも、中国の基本は儒教です。ということは、中国共産党も儒教的システムなのです」
著者いわく、儒教はなかみが政治学なのに、「祖先を崇拝して、祖先を基点に自分たちを定義する」という考え方があるために宗教といわれます。自分たちが立派なのはまず祖先が立派だからであり、その立派な祖先を祀っている自分たちは、よそのグループより立派なのだという自己意識を持ちます。そうやって人々が、父系の血縁集団をつくって結束するわけです。
そこで「天」というものが大切になります。著者は「天」について述べます。
「天は、昔から存在し、歴代の政権に正統性を与えてきた。天を祀ることができるのは、皇帝だけですから、自分が政権を担当するにふさわしいことのパフォーマンスになる。そこで、この儀式をこれ見よがしに行なう。
天は、目にみえない。天を祀る儀式は、目にみえる。儀式を行なうかぎり、天は存在することになる。このように、天を祀るのは、宗教的行為です。
天を祀るのも、祖先を祀るのも、宗教的行為。これをしっかり組み込んでいる儒教は、だから、宗教ということになるのです。でもその機能は、政治と教育なのです」
第六講義「日本人と宗教」では、神道における「カミ」が論じられます。著者は、「カミ」について以下のように述べます。
「神社はもともと、カミを拝む場所。拝む場所だから、神社はからっぽで、そこにはカミはいない。この点、モスクと似ています。ところが、しばらくするうちに、神社にカミがいるかのように、信じられるようになった。カミがやってくる場所として、依代(鏡など)が置かれるようになり、それが『神体』とみなされていく。その結果、神社にカミが幽閉されたかたちになります。本来は自然現象で、自然の中でのびのびしていたものが、建物の中に人間の都合で閉じ込められ、窮屈このうえない。そこでダンス(神楽)を見せたり、格闘技(相撲)を見せたり、カミが退屈しないようにする。たまには、リムジン(神輿)に乗って、近所に散歩に出たりする。これが、お祭りです」
「お祭り」について、著者は以下のように述べています。
「お祭りの大事な点は、カミと人間が一緒に食事をすること。このときには、人間が食べるものをカミも食べます。ごちそうをつくって、供応する。いっしょに食事をすれば、仲良くなる。日本のお祭りの本質は、カミと人間が仲良くすることなのです」
東京オリンピックの開催決定以来、「おもてなし」が時代のキーワードになっています。この「おもてなし」のルーツはまさに「お祭り」にあります。カミと人間が仲良くするから、「おもてなし」という日本的ホスピタリティが生まれ、育っていったのです。
最後に「国家神道とはどのような考え方か」という問題を取り上げます。そこで重要になるのが「英霊」という考え方ですが、著者は国学者の平田篤胤が「英霊」の発明者であると指摘し、次のように述べています。
「平田篤胤は、どうやって英霊の考えを思いついたのか。
有力な研究によると、平田篤胤は、長崎経由で漢訳の聖書を入手し、読むことができた。そして、キリスト教の『聖霊』の考え方をしり、それをアレンジして『英霊』とした可能性が高い。キリスト教に由来することは伏せて、あたかも神道の古い考え方であるかのように粉飾して、『英霊』の説を唱えた」
続いて、著者は神道における「死」の考え方を紹介します。
「神道には古来、死の穢れの考え方があり、死者は黄泉におもむく、などと考えられた。黄泉におもむいたのでは、神社に祀ることはできない。例外として、菅原道真や徳川家康など有力な政治家の場合は、神社に祀られる場合があった。宣長は、死者がどうなるかはわからない、と言った。それに対して平田篤胤は、死者は黄泉に行かないで、霊となる。とくに国事殉難者はすぐれた霊、『英霊』となって、国の行く末を見まもっている、と言い出したのです」
さらに、著者は以下のように国家神道の本質を解き明かします。
「どの家にも宗旨があり、仏壇も墓地もあって、仏式で葬儀や法事を行なう。官軍の戦死者は、家族に引き取られ、ばらばらに儀式が行なわれた。軍として、国として、儀式を行なうことができない。この点、平田篤胤の『英霊』の考え方はじつに便利だと、陸軍は思った。戦死者が全員、英霊になるのなら、仏式の家ごとの葬儀と別に、家族の許可なく神道のやり方で、招魂祭や合祀を行なうことができる。国家として、戦死者を祀ることができる。徴兵制の軍隊をもつ近代国家として、国家が戦死者のような国事殉難者を祀ることができるのは重要なことでした。これが、国家神道の存在理由です」
この「英霊」の考え方のルーツは、じつに興味深かったです。
また、招魂祭や合祀などを行うにも、その考え方に筋が通っていないといけないというのも大いに納得しました。儀式にはロジックとストーリーが必要なのです。そして、国家神道に限らず、すべての宗教というものはロジックとストーリーによって織り成されているのでしょう。本書は、世界の宗教を気軽に俯瞰できる好著だと思いました。