- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2106 死生観 『もしも一年後、この世にいないとしたら。』 清水研著(文響社)
2022.02.08
『もしも一年後、この世にいないとしたら。』清水研著(文響社)を読みました。著者は1971年生まれ。精神科医・医学博士。金沢大学卒業後、都立荏原病院での内科研修、国立精神・神経センター武蔵病院、都立豊島病院での一般精神科研修を経て、2003年、国立がんセンター東病院精神腫瘍科レジデント。以降一貫してがん患者およびその家族の診療を担当している。2006年、国立がんセンター(現:国立がん研究センター)中央病院精神腫瘍科勤務。現在、同病院精神腫瘍科長。日本総合病院精神医学会専門医・指導医。日本精神神経学会専門医・指導医。
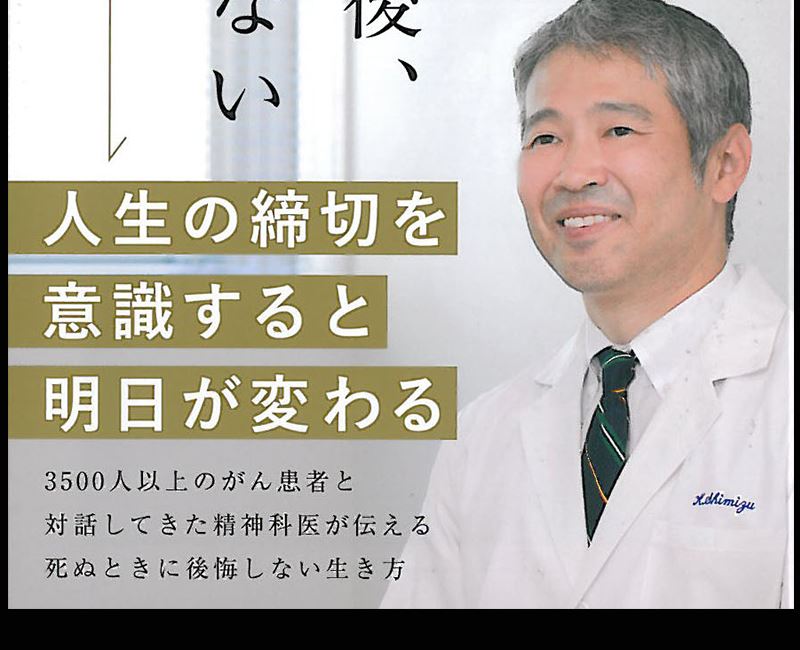 本書の帯
本書の帯
本書の帯には著者の近影とともに「人生の締切を意識すると明日が変わる」「3500人以上のがん患者と対話してきた精神科医が伝える死ぬときに後悔しない生き方」と書かれています。また、カバー前そでには「精神腫瘍医とは、がん患者さん専門の精神科医および心療内科医のことです」と書かれています。
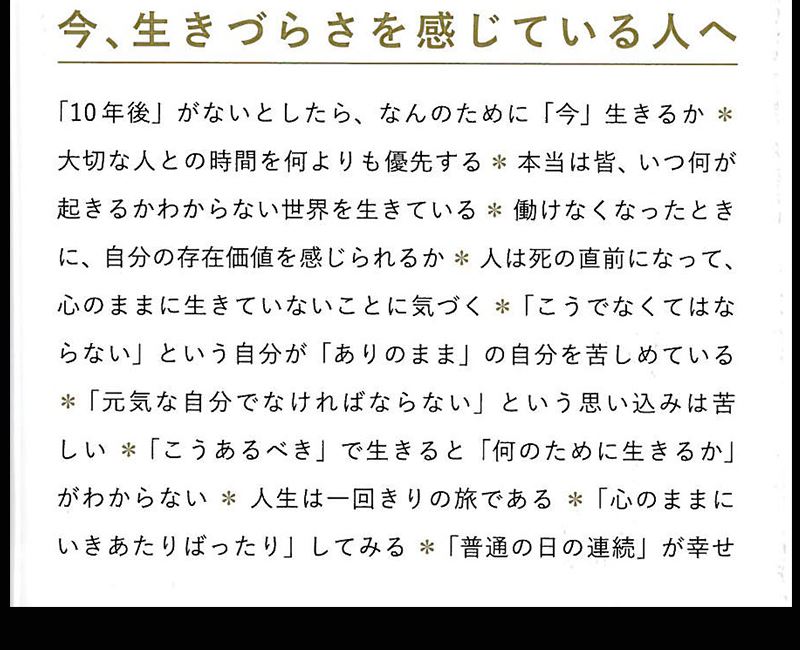 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「今、生きづらさを感じている人へ」として、「『10年後』がないとしたら、なんのために『今』生きるか*大切な人との時間を何よりも優先する*本当は皆、いつ何が起きるかわからない世界を生きている*働けなくなったときに、自分の存在価値を感じられるか*人は死の直前になって、心のままに生きていないことに気づく*『こうでなくてはならない』という自分が『ありのまま』の自分を苦しめている*『元気な自分でなければならない』という思い込みは苦しい*『こうあるべき』で生きると『何のために生きるか』がわからない*人生は一回きりの旅である*『心のままにいきあたりばったり』してみる*『普通の日の連続』が幸せ」と書かれています。
 アマゾンより
アマゾンより
アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。
「国立がん研究センターで、がん患者さん3500人以上の方の話を聞いてきた精神科医が伝えたい死ぬときに後悔しない生き方。今、生きづらさを感じているすべての人へ。人生の締切を意識すると、明日が変わる。
『もしも1年後、この世にいないとしたら――』
そう想像したとき、今やろうとしていることを変わらずに続けますか。それとももっと別のやりたいことをやりますか。がん告知後にうつ状態になる人の割合は5人に1人、がん告知後1年以内の自殺率は、一般人口の24倍。『告知後のショックは計り知れない大きさですが、それをきっかけに、残された時間を前よりも自分らしく生きるように変わっていく方が多くいらっしゃいます。そんな方々のお話を伺う中で、逆に医師である私が人生について教えてもらうことが山ほどありました』」
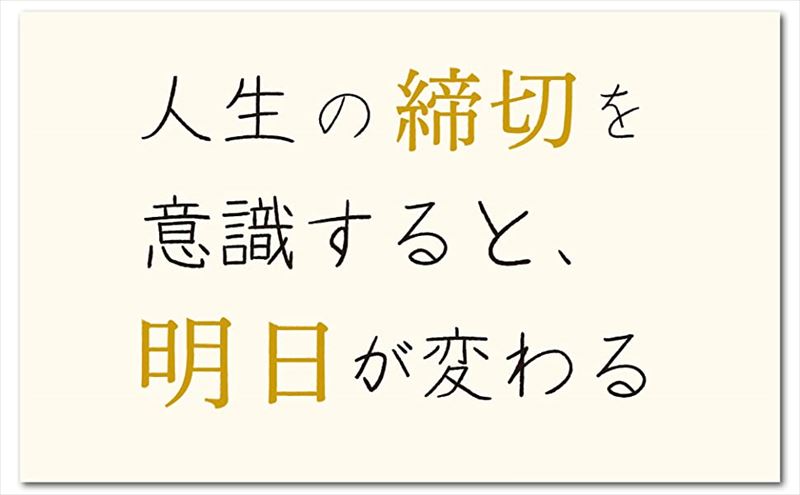 アマゾンより
アマゾンより
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに――大切なことを先延ばしにしていませんか」
序章 がんは体だけでなく心も苦しめる
第1章 苦しみを癒すのに必要なのは、悲しむこと
第2章 誰もが持っているレジリエンスの力
第3章 人は死の直前になって、
心のままに生きていないことに気づく
第4章 今日を大切にするために、
自分の「want」に向き合う
第5章 死を見つめることは、
どう生きるかを見つめること
「おわりに――『死』を意識して初めて
生きることの『光』に気づく」
「はじめに――大切なことを先延ばしにしていませんか」の冒頭で、著者「自分の人生がいつ終わりを迎えるのかは誰にもわからない。だからこそ、今生きている瞬間をかけがえのないものとして大切にしてほしい」という言葉を紹介します。これは、27歳でがんによりこの世を去ったオーストラリア人女性の最期のメッセージで、『ABC』『The Independent』『Mirror』など各メディアが伝え、瞬く間にFacebookで世界中に拡散されたといいます。著者は、「なぜこのメッセージは多くの人の心に届いたのでしょうか」と読者に問いかけています。
序章「がんは体だけでなく心も苦しめる」の「がんと無関係でいられる人は少ない」では、最新の統計(「がんの統計17 公益財団法人がん研究振興財団」)では、生涯においてがんになる確率は、男性では62%、女性では47%と報告されており、「2人に1人はがんに罹る時代になった」と言われていることが紹介されます。著者は、「2人に1人ということは、もし自分ががんにならなかったとしても、自分の家族ががんを体験するかもしれませんし、大切な友人ががんになるかもしれません。そう考えると、すべての人にとって他人事ではない病気と言えるでしょう。また、がんは年配の方だけの病気かというとそうとも限らず、がん患者の3人に1人は生産年齢と言われる15~64歳です」と述べています。
「『家族は第二の患者』といわれる」では、大切な人ががんになることで家族の人生も様変わりするとして、著者は「『かけがえのない人がこの世からいなくなってしまうかもしれない』ということは、受け入れ難いことでしょう。また、その人を支えるために家族が負わなければならない物理的、心理的な負担を並大抵のものではありません。ですので、家族は第二の患者と言われ、精神的な苦痛の程度は、患者本人に勝るとも劣らないと言われています」と述べています。
第1章「苦しみを癒すのに必要なのは、悲しむこと」の「柳のようにしなやかに立ち上がる力を人は持っている」では、著者は「大きな恐れや悲しみから、子供のように泣きじゃくる方もいらっしゃいますが、そのような姿の奥にこそ、大きな喪失と必死に向き合おうとしている力強さを私は感じます」と述べています。この、さまざまな喪失を認め、新たな現実と向きあう力を「レジリエンス」というそうです。もともとは物理学などの用語で、日本語に訳すと「可塑性」という意味になり、「元に戻る」ことを表します。それが心理学の世界でも使われるようになり、「柳」のようなイメージのこころの在り方を指すようになったそうです。
「苦しみに向き合う際の道しるべがある」では、突然のがん告知を受けると、それまでは当たり前であったこと、つまり「健康で平和な毎日が続く」と思っていた世界が突然変貌し、その人の目の前には様変わりした世界、つまり、さまざまな喪失や、死の予感を伴う現実が姿を現すことを指摘し、著者は「世界が様変わりしたことに対して、心理的な観点から2つの課題に取り組むことになります。1つ目の課題は、『健康で平和な毎日が失われた』という喪失と向き合うことです。最初はその事実を認めたくないという気持ちが働くでしょうし、圧倒的な現実の前に茫然自失になるのも無理がないことです。悔しさが溢れ、果てしない悲しみ湧いてくることもあるでしょう。この喪失と向き合うという課題に取り組む際には、負の感情がとっても大切な役割を果たしますので、しっかり悲しんで、しっかり落ち込むことが必要です」と述べています。
2つ目の課題とは、「様変わりした現実をどう過ごしたら、そこに意味を見出せるのか」を考えることです。著者は、「嵐のような悲しみや怒りは簡単にはやまないし、完全になくなることはないでしょうが、「残念ながらこの事実は変えられないんだ」というあきらめや絶望に近い感覚がうまれたとき、2つ目の課題への取り組みが始まります」と述べます。1つ目の課題と2つ目の課題は同時に進行しますが、徐々に悲しみや怒りが弱まっていき、新しい人生を考えるという方向にシフトしていくそうです。著者は、「切り替わるのではなく、少しずつ、グラデーションのように移っていく感じです」と説明しています。
第2章「誰もが持っているレジリエンスの力」の「『喪失』を受け入れるには時間とプロセスが必要」では、人間は想定をはるかに超える衝撃的な出来事に出会うと、心の機能がバラバラになってしまい、目の前で起こっていることを認識はできても、それが現実とは思えなかったり、記憶に定着しなかったりということがあるそうで、これを専門的には「解離状態」というとか。著者は、「がん告知に限らず、心のショックが大きかった場合にはよく経験される状態です。解離状態は、一気に激しい衝撃を受けることからこころを守るために、必要な機能なのかもしれません」と説明しています。
「今日一日があることに感謝する」では、「様変わりした現実をどう過ごしたら、そこに意味を見出せるのか」という2つ目の課題に取り組んだ先には、どういう世界があるのかを見ていきます。心理学領域における心的外傷後成長に関する研究から、その人の考えには「①人生に対する感謝」「②新たな視点(可能性)」「③他者との関係の変化」「④人間としての強さ」「⑤精神性的変容」の5つの変化が生じうることが明らかになっているとして、「人間は、希少であるものに価値をおく習性があります。貴金属のゴールドも、そこらへんに転がっていたら、だれも見向きもしなくなるでしょう。同じように、時間が永遠に続くと錯覚していると一日を粗末にしてしまいがちですが、時間が限られているとすると、一日一日がとても貴重に思えてくるわけです」と述べています。
第4章「今日を大切にするために、自分の『want』に向き合う」の「死ぬとわかっていても、どうして人は精いっぱい生きるのか」では、あまりにも多くのがん患者と向き合ってきた著者が医師として目標を見失い、苦しい時間が長く続いた時期があったことが告白されます。しかし、結局がん患者との臨床現場にその後も居続けている著者は、「なぜ辞めなかったのか。それは、残された時間が限られていることは十分にわかっていながら、精いっぱいその時間を生きようとされる患者さんの姿を知り、衝撃を受けたからです。マルチン・ルターによると言われる『たとえ世界の終末が明日であっても、自分は今日リンゴの木を植える』という言葉がありますが、そのころの自分には『もうすぐ人生が終わりになることがわかっているのに、なぜそんなに真剣に毎日を生きられるのか』ということが謎でした。そして、この仕事を続けることでその謎が解けるのではないのか、と思うようになったのです」と述べています。
第5章「死を見つめることは、どう生きるかを見つめること」の「死をないものとしてしまう世界はいつか破綻する」では、「死」については考えないようにしようという風潮が現代にはあると思うとして、著者は「たとえば最近は人生100年時代と言われます。そうすると高齢者の入り口と定義されている65歳もまだまだ通過地点であり、『どうやって長い老年期を生きようか』ということをまず考える方も多いでしょう。このこと自体はとても良いことだと思いますが、その一方で、人生100年時代という言葉には、『死』について考えることは後回しにしようという思惑が透けて見えます。また、アンチエイジング(=不老)という考えがあります。元気で若々しく生きようということは結構ですが、このなかには非現実的な不老不死を求める人間の志向性が如実に表れています」と述べます。
「『人間は死んだらどうなるのか』という問いにどう答えるか」では、なぜこのように「死」は現代社会の中で避けられ、隠されてしまうようになったのかと読者に問いかけた後、著者は「私はその理由について、次のように考えています。人間は動物としての生存本能を持っているので、自らの死を予感させるものには強い恐怖を感じるようにできています。例えば高所に立つとか、どう猛な動物に遭遇するとか、ピストルを突きつけられるとか、そんなときは強い恐怖感に襲われ、動悸や震えが起こるなど、心も体も強い反応を起こします。一方で人間がほかの動物と明らかに異なるところは、『未来を予測できる』というところです。死に対する恐怖を持ちつつも、自らの人生には限りがあり、いつか必ず死がやってくることを知っています。これは、人間が進化したために生じた葛藤とも考えられます」と述べています。
そして、「『普通の日の連続』が幸せ」では、著者は「もし1年後に自分が病床に伏していると仮定したら、1年後の自分が今の自分を振り返る際に、今の自分をうらやみ、あれもしておけばよかった、これもしておけばよかったと後悔するかもしれません。私の場合はあえてそう考えるようにします。『今日一日をこの様にすごせることは当たり前ではない』ということを意識することは、『今、ここにある自分』を大切に生きることにつながるでしょう」と述べるのでした。本書は具体的な事例と平易な言葉から読者を深遠な「死」の思想へと導き、穏やかな「死ぬ覚悟」を持たせる良書でした。わたしには『死ぬまでにやっておきたい50のこと』(イースト・プレス)という著書がありますが、その内容にも通じる部分が多々ありました。