- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2085 芸術・芸能・映画 『それでも映画は「格差」を描く』 町山智浩著(集英社インターナショナル新書)
2021.11.29
『それでも映画は「格差」を描く』町山智浩著(集英社インターナショナル新書)を読みました。一条真也の読書館『「最前線の映画」を読む』、『映画には「動機」がある』で紹介した本の第3弾です。わたしは映画評論家としての著者のファンであり、その独特の視点にはいつも刺激を受けています。この最新刊は、グローバル化とコロナ禍でますます加速する「格差」と「貧困」についてを考える映画を取り上げています。マスメディアが伝えない「真実」を世界の名監督はどのように描いたかを探り、「世界と映画」を熱く語っています。
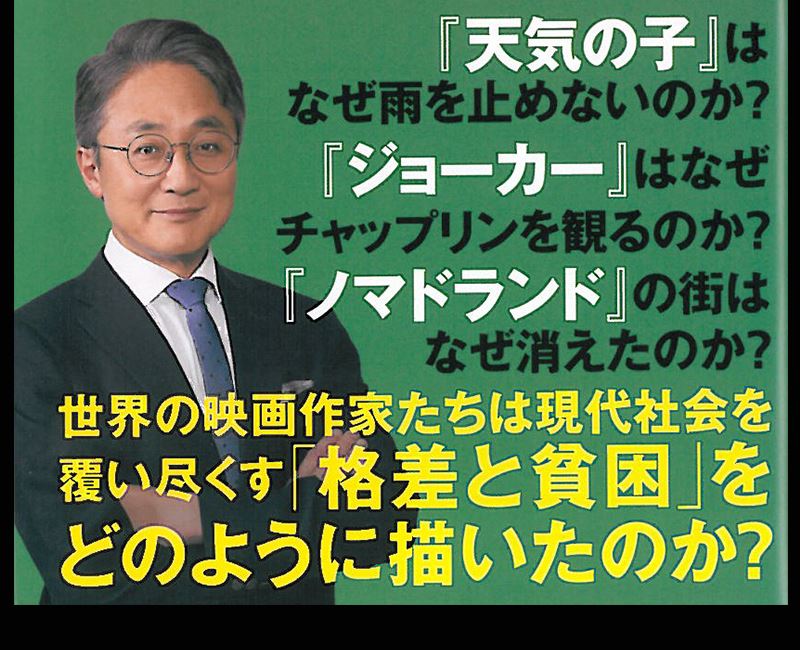 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、腕組みをした著者の上半身の写真が使われ、「『天気の子』はなぜ雨を止めないのか?」「『ジョーカー』はなぜチャップリンを観るのか?」「『ノマドランド』の街はなぜ消えたのか?」「世界の映画作家たちは現代社会を覆い尽くす『格差と貧困』をどのように描いたのか?」と書かれています。カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「映画は世界を映す窓だ! ギグワーカー、非正規雇用、ワーキングプア……言い方はさまざまだが、その実態は世界中、みな同じ。労働者から人権を奪い、生活限界まで搾取する。その傾向は突如襲ったコロナ禍によってますます拍車がかかっている。このディストピア的な状況を前に、世界の映画作家たちは各々のアプローチで「現代の資本主義」を描こうとしている。『パラサイト 半地下の家族』『天気の子』『万引き家族』などを徹底解剖!」
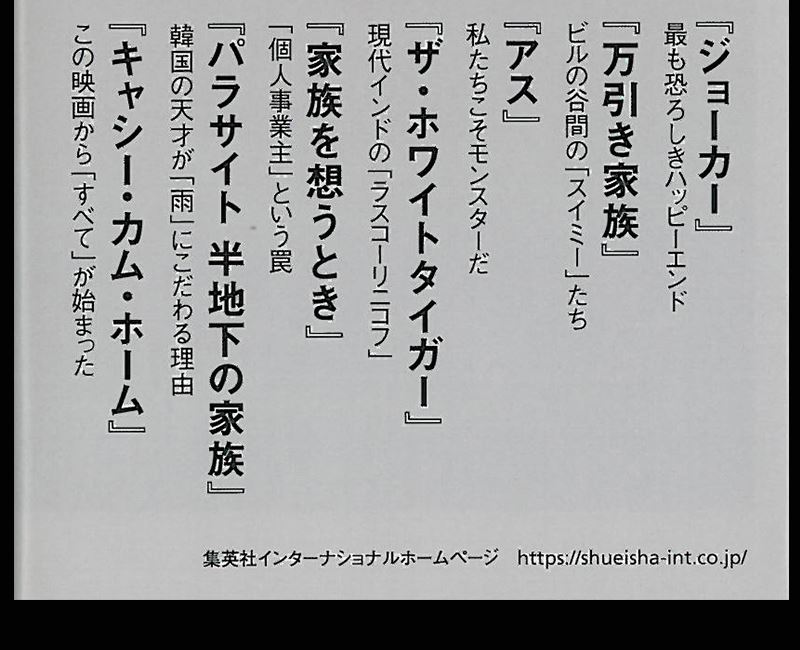 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の通りです。
「はじめに」
#1『パラサイト 半地下の家族』
――したたり落ちるのは雨だけ
#2『ジョーカー』
――最も恐ろしきハッピーエンド
#3『ノマドランド』
――映画が与えた「永遠の命」とは
#4『アス』
――私たちこそモンスターだ
#5『ザ・スクエア 思いやりの聖域』
――「善きサマリア人」は、どこだ?
#6『バーニング 劇場版』
――格差が生んだ「大いなる飢え」
#7『ザ・ホワイトタイガー』
――インドのラスコーリニコフ
#8『ロゼッタ』
――格差と貧困を描く
「ダルデンヌ・スタイル」とは
#9『キャシー・カム・ホーム』
――世論を動かした、ケン・ローチの「原点」
#10『わたしは、
ダニエル・ブレイク』
――貧しさは罪なのか?
#11『家族を想うとき』
――「個人事業主」という罠
#12『万引き家族』
――ビルの谷間の「スイミー」たち
#13『天気の子』
――愛にできるものはまだあるよ
「あとがき」
「はじめに」では、「グローバル世界の中で、今、起きていること」として、著者は以下のように書いています。
「ここ数年、世界各国で、経済格差を描く映画が増えています。本書はそこに反映された現実、込められたテーマを体系的に横断的に論じていきます。たとえば、カンヌ映画祭の最高賞パルム・ドールの受賞作品をご覧ください。16年はイギリスのケン・ローチ監督『わたしは、ダニエル・ブレイク』、17年はスウェーデンのリューベン・オストルンド監督『ザ・スクエア 思いやりの聖域』、18年は日本の是枝裕和監督『万引き家族』、19年は韓国のポン・ジュノ監督『パラサイト 半地下の家族』(以下、『パラサイト』)でした。『パラサイト』は翌年のアカデミー作品賞も受賞しています。さらにその翌年のアカデミー作品賞は中国系アメリカ人のクロエ・ジャオ監督『ノマドランド』でした。どれも、経済格差と貧困をテーマにしています」
「『自己責任』という名の弱肉強食」として、80年代以降、アメリカ、英国、日本、韓国などの国で経済格差が広がり続けていることを指摘し、著者は「それは偶然ではありません。これらの国の政府はいわゆる『新自由主義』的経済政策をとったのです。具体的には、富裕層の所得税率や大企業の法人税率を大幅に下げました。株や不動産取引の規制を緩和し、資本家たちのマネーゲームを活性化させました。雇用の規制も緩和し、解雇をしやすくし、非正規雇用を増やし、企業の人件費を軽減しました。これで企業の利益も株価も不動産価格も上昇し、豊かな者はもっと豊かになりました。だが、それ以外の人たちはどうなったでしょう? 税率が下がった分、福祉や公共事業は削減され、富の再分配は抑えられました。リストラが増え、非正規雇用が増えて、雇用は不安定になり、昇給や昇進も少なくなりました。不動産価格だけが上がって給料が追い付かなくなりました。貧しいものはもっと貧しくなったのです」と述べます。
「自己責任」を訴える新自由主義者たちは経済格差を肯定し、貧困を描いた映画をバッシングします。「チャップリンもまた石を投げられた」として、著者は「喜劇王チャーリー・チャップリンの名作『キッド』(1921年)が今、公開されたら、何と言われるでしょう。チャップリンはボロボロの服を着て、スラム街の屋根裏でなんとか暮らしている失業者。道端に捨てられた赤ん坊を拾って育て始めます。その男の子が5歳になると、ふたりで商売を始める。男の子が石を投げて民家の窓ガラスを割ります。家の人が出てくると、そこにチャップリンがガラスを背負って通りかかります。こんにちは、通りがかりのガラス屋ですが、お困りのようですね。『これは詐欺ではないか』『子どもを犯罪に加担させるなんて』そんな批判が浴びせられるに違いありません」と述べます。
「弱者と子どもへの共感」として、現実を描かれるのを嫌がる人々はいつもどこの国にもいることを指摘し、著者は「デ・シーカもケン・ローチもポン・ジュノもそれぞれの国で『左翼』『国辱』と攻撃されました。彼らはみんな、チャップリンを継ぐ者たちかもしれません。『キッド』に影響されて、デ・シーカは『自転車泥棒』を作りました。アントニオとブルーノが路上に並んで座るシーンは『キッド』へのオマージュです。そして、『自転車泥棒』に影響されてケン・ローチやダルデンヌ兄弟は映画を撮り始めました。是枝監督もまた『キッド』やケン・ローチに影響されて映画を撮っています」と述べます。
そして、本書でこれらの映画を論じていくうちに、いつの間にかチャップリンの血をたどる作業になっていたという著者は、「弱者への共感以外に、これらの映画を貫くものがもうひとつあります。子どもです。『ジョーカー』も含めて、本書で扱った映画はどれも貧しさの中に生まれてしまった子どもたちの物語です。貧しさを選んで生まれてくる子どもはいません。子どもには何の責任もありません。貧しい子どもの存在は、自己責任論に対する最も根源的な反論です」と述べるのでした。
「#1『パラサイト 半地下の家族』――したたり落ちるのは雨だけ」では、ソウル市内の半地下の部屋に住む貧しいキム家の奇想天外な物語が展開されますが、著者は「キム家のように半地下に住む人が、ソウルでは約23万世帯、69万人もいる。それはソウル市民の6%にあたる。『半地下』はもともと、北朝鮮の攻撃に備えた防空壕だった。68年、北朝鮮の武装ゲリラが、ソウルの青瓦台にある大統領府を襲撃してパク・チョンヒ大統領を暗殺しようとした事件がきっかけになって、ソウルの住宅には地下シェルターが義務付けられた」と説明します。
最初は物置きとして使われていた地下シェルターですが、70年代から、住居用に改造して賃貸されるようになりました。その理由は、ソウルに人口が集中して、安いアパートが不足したことです。著者は、「半地下の家賃はソウル市の普通のアパートの半額で、そこに住む世帯の平均年収も、ソウル市民の平均の約半分という。しかし、1日中薄暗く、風通しも悪く、湿気がひどく、ゴキブリも多い。だからキム一家は路上に撒かれた殺虫剤を部屋に取り入れようとすする。それにカビ臭い。その臭いは住人の服や体に染み込んで取れない」と書いています。
「#2『ジョーカー』――最も恐ろしきハッピーエンド」の冒頭を、著者は「ジョーカーがトランプで最強のカードなのは何にでもなるからだ。そして、ジョーカーがバットマンにとって最強の敵なのは、何も持たないからだ。ジョーカーには人並外れた能力は何もない。しかし、弱みもない。自分の命すら惜しいと思っていない。護べきものがない者は最強で最凶だ。そのジョーカーが何もかも失って、最強になるまでを描いたのが、トッド・フィリップス監督、ホアキン・フェニックス主演の『ジョーカー』(2019年)だ」と書きだしています。
「ロンリー・チャップリン」として、『ジョーカー』の中で、ゴッサムシティの金持ちが『モダン・タイムス』を観て笑うことが指摘されます。『モダン・タイムス』は、ベルトコンベアーによる流れ作業が導入されて、チャップリン演じる主人公の男が機械のように働かされるうちに精神を病む様子が描かれています。まったく笑い事ではない貧困層の悲劇をチャップリンは喜劇として描いたのです。チャップリンは、「人生はクローズアップで撮れば悲劇だ。だが、それをロングショットで撮ればコメディになる」と言いました。著者は、「バナナの皮で滑って転ぶ人を遠くから見れば笑ってしまうが、腰を打ったその人の歪む顔を近くで見れば苦痛と屈辱が見る者の心にも浸みる。つまりクローズアップはそのキャラクターの内面に観客を引きずり込む。『ジョーカー』はクローズアップで撮った『モダン・タイムス』だ」と述べるのでした。
「#3『ノマドランド』――映画が与えた『永遠の命』とは」では、フランシス・マクマーランド演じるファーンという主人公の物語が取り上げられます。ファーンは、30年以上前に夫とともにネバダ州の砂漠の中の街・エンパイアに住み始め、夫が亡くなった後も住み続けましたが、電気もガスも水道も止まったので、価値がゼロになった家を捨てて、キャンピングカーで寝泊まりしています。著者は、「アメリカン・ドリームとは本来、自分の家を持つことだった。ヨーロッパの貧しい小作人たちが、自分の土地を持つ夢がかなう国、それがアメリカだった。彼らは移民として大西洋を渡り、幌馬車で荒野を旅して約束の地を求め、どこかにたどり着いて家を持った。だが、すべては奪われた。ファーンが夫と住宅ローンを払い続けたであろう家は、ただの廃墟になった。画面に登場しない夫ボーは死んでしまったアメリカン・ドリームを象徴している」と述べています。
「#4『アス』――私たちこそモンスターだ」では、アメリカの平凡な一家が、囚人服のようなツナギを着た、彼らそっくりのドッペルゲンガーたちに襲われるホラー映画が取り上げられます。襲撃者たちは自らをデザード(縛られた者たち)と呼びます。なぜなら、彼らは地下の刑務所のような施設に閉じ込められていたからです。著者は、「実際、アメリカでは200万を超える人々が刑務所に収監されている。その数はやはり80年代から急激に増加した。その圧倒的多くが大麻所持罪だった。レーガン大統領が『ドラッグとの戦い』を宣言し、路上の職務質問で大麻所持者を片っ端から逮捕したからだ。この約40年間に全米の収監者数は4倍に増え、全人口に対する収監者の率は世界一になった。そのうち3人にひとりが黒人、6人にひとりがラテン系だ」と述べます。
「#6『バーニング 劇場版』――格差が生んだ『大いなる飢え』」では、村上春樹の短編小説「納屋を焼く」を原作とする韓国映画について語られます。若い女性が消えるという奇妙な物語ですが、現代の韓国を反映しているとして、著者は「韓国では女性に過剰に美しさを求める。だから、いい服や、化粧品や、整形に金がかかる。それに韓国の女性差別は日本と同じように過酷で、男性に比して就職先も限られ、賃金も低い」と説明します。「女三界に家なし」という言葉がありますが、「三界」は社会全体を意味します。かつて中国、韓国、日本の家父長制度の下では、女性は子どもの頃も差別されて、結婚して旦那が死んでも財産を相続できませんでした。自分の息子よりも地位が低かったのです。
そんな韓国では、キャンギャルなどで必死に稼いでも支出に収入が追い付かなくなる女性も多く、消えた女性のキャンギャル仲間は「だから女の子は突然消えちゃうんだよ」と言うのでした。著者は、「クレジットカードの破綻で夜逃げしたかもしれない。夜逃げならまだいい。00年代に日本でも報じられたが、クレジットカードのローンを抱えた女性たちが、サラ金などに手を出し、海外に送られて売春をさせられていた。その頃、日本で韓国系デリヘルが大量に発生したのはそのためだ。アメリカではマッサージパーラーの地下に不法に入国した女性たちが監禁されて売春を強制されており、国土安全保障省が全米で一斉に摘発して女性たちを救い出した」と述べています。
「#7『ザ・ホワイトタイガー』――インドのラスコーリニコフ」では、イギリスで最も栄誉ある文学賞ブッカー賞を受賞したアラヴィンド・アディガのベストセラー小説を映画化したネットフリックス作品が取り上げられます。インドの貧困層出身の青年が、裕福な一家の使用人として働く中で理不尽な現実に直面する物語です。主人公バルラムは貧しい村の貧しい家に生まれましたが、学校では飛び抜けた頭の良さを示します。教師からは「君はホワイトタイガーだ」と呼ばれますが、それは「極めて珍しい」という意味でした。インドの政治家は「我が国は世界最大の民主主義国家」と自慢しますが、実態はいまだ身分制度に支配され、最下層の者は生まれてから死ぬまで、地主たちに徹底的に管理され搾取されるのでした。
しかし、バルラムはそこからの脱出を図り、村を支配する地主の運転手になろうとします。著者は、「この部分は、99年のインド映画『Minsara Kanna』(K・S・ラヴィクマール監督。日本未公開)にヒントを得たのではないか。娘に恋をした男が運転手として入り込んで、それから自分の家族をどんどんその富豪の使用人にしていくというコメディで、『パラサイト 半地下の家族』の元ネタとも言われた。だが、バルラムは弱肉強食のホワイトタイガーだ。彼は前任の運転手を尾行して彼がイスラム教徒だと突き止め、イスラム嫌いの地主に密告して解雇させ、その後釜に座る。バルラムは、のし上がるためなら何でもするインドのラスコーリニコフ(『罪と罰』の主人公)なのだ」と述べています。
「#11『家族を想うとき』――『個人事業主』という罠」では、ケン・ローチの映画で描かれる現代の雇用問題が浮き彫りになります。著者は、「必要な時だけ呼び出される雇用状況は世界に拡がっている。一般人によるタクシー・サービスのウーバーや、料理の出前のウーバーイーツもそうだ。これはギグ・エコノミーと呼ばれている。たとえばウーバーイーツの賃金は、1回の配達ごとに計算されるから、待機中は無給だ。だから、1日働いても、時間で割ると最低賃金を下回ってしまうことが多い。明日の仕事もわからないゼロアワー契約は限りなく失業状態に近いが失業状態ではない。だから失業手当は請求できないし、失業者数にも算入されない。いわば見えない失業者が500万人以上いるわけだ」と述べています。
「#12『万引き家族』――ビルの谷間の『スイミー』たち」では、東京の下層社会で生きる家族を描いた是枝裕和監督の代表作が取り上げられます。高層マンションの谷間にポツンと取り残された今にも壊れそうな平屋に、治と信代の夫婦、息子の祥太、信代の妹の亜紀が転がり込んで暮らしています。彼らの目当ては、この家の持ち主である初枝(樹木希林)の年金でした。足りない生活費は、万引きで稼いでいました。著者は、「初枝は死んだが、葬儀など出せない。治も信代も初枝の血縁ではないのだから。しかたなく、治たちは初枝の遺体を床下に埋めます。初枝の死を隠した信代たちは初枝の年金を受け取り続けますが、これは実際の事件に基づいています。
一条真也の新ハートフル・ブログ「万引き家族」にも書きましたが、わたしはこの映画を認めません。この映画に登場する人々は本物の家族ではありません。いわゆる「疑似家族」です。彼らは情を交わし合っているかのように見えますが、しょせんは他人同士の利益集団です。もちろん、家族などではありません。家族ならば樹木希林扮する初枝が亡くなったとき、きちんと葬儀をあげるはずです。それを彼らは初枝の遺体を遺棄し、最初からいないことにしてしまいます。わたしは、このシーンを観ながら、巨大な心の闇を感じました。1人の人間が亡くなったのに弔わず、「最初からいないことにする」ことは実存主義的不安にも通じる、本当に怖ろしいことです。初枝亡き後、安藤サクラ演じる信代が年金を不正受給して嬉々としてするシーンにも恐怖を感じました。
そもそも、「家族」とは何でしょうか。哲学者ヘーゲルは、一条真也の読書館『精神現象学』で紹介した主著において、「家族の最大の存在意義とは何か」を考察しました。そして、家族の最大の義務とは「埋葬の義務」であると喝破しました。家族は、死者を埋葬することによって、彼や彼女を祖先の霊のメンバーの中に加入させるのです。これは「自己」意識としての人間が自分の死を受け入れるためには、ぜひとも必要な行為なのであると、ヘーゲルは訴えました。わたしも同意見です。「万引き家族」を批判する者が多いそうですが、万引きや年金の不正受給が「アンモラル」だからのようです。しかし、わたしは家族を弔わなかったことを認めるという最悪の「アンモラル」映画であると思います。この映画の評価だけは、著者の町山氏と大いに異なります。絶対に認めるわけにはいきません。
「#13『天気の子』――愛にできるものはまだあるよ」では、大ヒットしたアニメ映画が取り上げられます。「雨のディストピア」として、著者は「『天気の子』は、新海誠監督の作品の最大の魅力だった青空をほとんど封じて、雨か曇天ばかりにすることで、逆に空の美しさ、雲の美しさ、晴天の美しさを強調している。雨の描写も素晴らしい。アニメーションの最大の魅力は、あたりまえすぎて人々が見過ごしているものをアニメとして意図的に描くことによって、その美しさに気づかせる効果があるが、『天気の子』では、たとえば、窓についた雨のひとしずくひとつひとつの中に映る逆さまの小さな風景までも描き尽くす。さらに、その美しい自然描写と対置されるのが、猥雑な東京の描写。ここまでリアルに東京を描き尽くしたアニメがかつてあっただろうか」と述べています。秀逸な感想であると思います。
「貧しい豊かさ」として、著者は「今の日本では数百円あれば、コンビニやファストフードでアメリカやヨーロッパの高級レストランよりもおいしいものが食べられてしまう。酒場になんか行かなくても200円のストロングゼロをっ買えば、充分酔っ払って浮世を忘れられる。100円ショップでたいていのものは手に入る。何でも買える。困らない」と述べ、『天気の子』の主人公である陽菜の部屋にもモノが溢れていることを指摘します。また、著者は「モノや情報やノイズやちょっとした食べ物に囲まれていれば寂しくない。24時間営業のコンビニ、100円ショップ、歌舞伎町のネオンサイン、バニラバニーラ、携帯、ネット……たいていのものは安く簡単に手に入る。『天気の子』の壮絶な量の看板、ネオン、社名、商品名は、そんな安っぽいものなら何でもある日本の現状を示している。でも、そこには大事なものがない。未来だ」と述べます。この練りに練られたコメントはシビレます!
「あとがき」で、戦後30年間、日本人は力を合わせて働いてきたこと、最高税率は75%だったので、富は集中せずに公共事業や福祉、教育で国民に再配分されたこと、そして雇用は法律で守られ、給料は毎年上がり、国民全体の底が上がって「一億総中流」と呼ばれたことなどが紹介されます。著者は、「でも、それから40年あまり経った今、豊かな者の年収はビルのようにどんどん高さを増していきますが、その足元には切り捨てられた焼野原が拡がっています。自然にそうなったわけではありません。富裕層の税率を下げ、大企業の利益を上げるために非正規雇用を増やし、賃金を抑え、簡単に解雇できる社会にする政策を政府が採ってきたからです」と述べるのでした。
本書には、「格差」と「貧困」の現実を伝える、あるいはその解決方法を考える映画が13本紹介されています。「映画で世界を変えることができるか」は永遠のテーマです。総合芸術である映画には、観る者の心にメッセージを届ける大きな力があります。そして、社会をより良き方向に変えていきたいというメッセージを伝える映画は、これまでも、これからも存在します。最近、人間にとっての真の幸福とは、他者の幸せを願う「志」からしか生まれてこないような気がしてなりません。その意味では、「万引き家族」を除いて本書に登場する12本の映画には志があるように思います。わたしは、今度、『心ゆたかな社会』『心ゆたかな読書』(ともに現代書林)の続編として『心ゆたかな映画』という本を書こうと考えているのですが、本書はそのための有益なヒントに溢れていました。