- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.11.13
『若い読者のための 第三のチンパンジー』ジャレド・ダイアモンド著、レベッカ・ステフォフ編著、秋山勝訳(草思社文庫)を読みました。「人間という動物の進化と未来」というサブタイトルがついています。著者は、1937年ボストン生まれ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授。進化生物学者、生理学者、生物地理学者。アメリカ国家科学賞受賞。著書『銃・病原菌・鉄』でピュリッツァー賞、コスモス国際賞受賞。同書は朝日新聞「ゼロ年代の50冊」第1位に選ばれました。
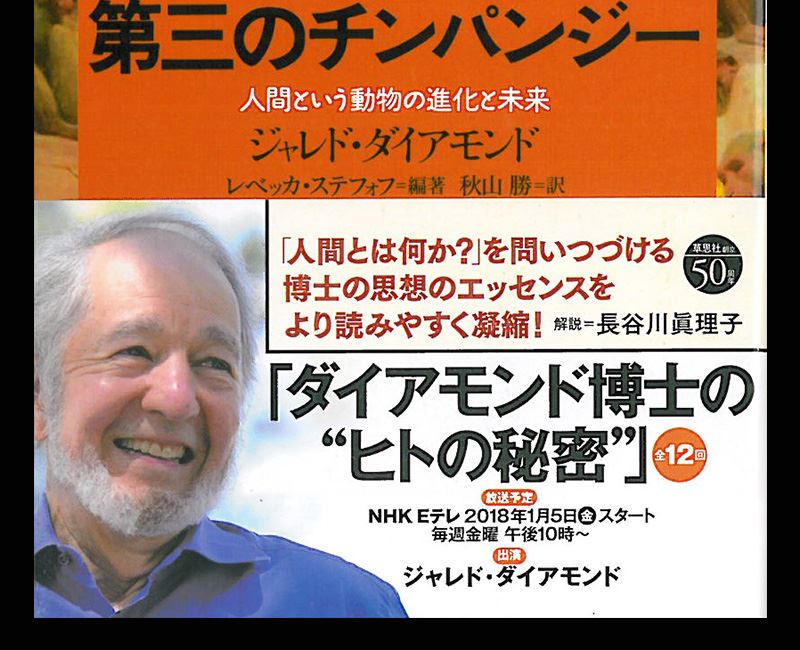 本書の帯
本書の帯
帯には著者の笑顔の写真が使われ、「『人間とは何か』を問いつづける博士の思想のエッセンスをより読みやすく凝縮!」「解説=長谷川眞理子」「『ダイアモンド博士の‟ヒトの秘密”』全12回」「NHK Eテレ2018年1月5日(金)スタート 毎週金曜 午後10時~」と書かれています。
カバー裏表紙の裏には、以下の内容紹介があります。
「チンパンジー(コモンチンパンジー)、ボノボ(ピグミーチンパンジー)と人間の遺伝子はじつに『98.4%』が同じ。つまり人間は三番目のチンパンジーともいえるのだ。たった『1.6%』の差異が、なぜここまで大きな違いを産み出したのか? 分子生理学、進化生物学、生物地理学等の幅広い知見と視点から、壮大なスケールで『人間とは何か』を問いつづけるダイアモンド教授の記念すべき第一作『人間はどこまでチンパンジーか?』を、より最新の情報をふまえて約半分のボリュームに凝縮した。名著『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』で展開されるテーマが凝縮された、より広い読者のための『ジャレド・ダイアモンド入門書』」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
はじめに「人間を人間であらしめるもの」
第1部 ありふれた大型哺乳類
第1章 三種のチンパンジーの物語
第2章 大躍進
第2部 奇妙なライフサイクル
第3章 ヒトの性行動
第4章 人種の起源
第5章 人はなぜ歳をとって死んでいくのか
第3部 特別な人間らしさ
第6章 言葉の不思議
第7章 芸術の起源
第8章 農業がもたらした光と影
第9章 なぜタバコを吸い、酒を飲み、
危険な薬物にふけるのか
第10章 一人ぼっちの宇宙
第4部 世界の征服者
第11章 最後のファーストコンタクト
第12章 思いがけずに征服者になったヒトたち
第13章 シロかクロか
第5部 ひと晩でふりだしに戻る進歩
第14章 黄金時代の幻想
第15章 新世界の電撃戦と感謝祭
第16章 第二の雲
おわりに
「なにも学ばれることなく、すべては忘れさられるのか」
「訳者あとがき」
「解説」長谷川眞理子(総合研究大学院大学学長)
第1部「ありふれた大型哺乳類」の第1章「三種のチンパンジーの物語」では、「霊長類の系統樹」として、ヒトと他の霊長類との差について、「ゴリラとは2.3パーセント、コモンチンパンジーおよびボノボとは約1.6パーセント。つまり私たちヒトは、チンパンジーとは98.⒋パーセントのDNAを共有し、チンパンジーこそヒトにもっとも近い種にほかならない。そして、見方を変えれば、チンパンジーにとって、彼らにもっとも近縁の種とはゴリラなどではなく、遺伝的には私たち人間なのである」と説明され、著者は「霊長類の遺伝的距離を分子時計で測ると、ゴリラがチンパンジーやヒトへと続く系統から分岐していったのは約1000万年前のことだった。ヒトの祖先はいまからおおよそ700万年前にチンパンジーの系統から分かれた。つまり、ヒトは約700万年の年月をかけて独自の進化を遂げてきたのだと言えるだろう」と述べます。
第2章「大躍進」では、もしも、わたしたちが人間になった瞬間と呼べる時があるとすれば、それは6万年前にさかのぼるこの「大躍進」の瞬間にほかならないとして、著者は「おそらく大躍進は、アフリカや中東で起きていた、同様な躍進のもうひとつの結果だったのだろう。このときの躍進は、大躍進に先立つ数万年のあいだにわたって続いていた。もっとも数万年といっても、人類が類人猿の歴史を分岐してからたどった長い歴史からすると、それは1パーセントにも満たないつかの間の出来事にすぎない。人類が野生動物を家畜化し、農耕と冶金を手がけ、文字を発明するのは、大躍進からわずか数万年後のことである。そして、『モナ・リザ』が描かれ、ベートーベンの交響曲が誕生し、エッフェル塔が建設され、さらに国際宇宙ステーション(ISS)、大量破壊兵器などの発明といった文明の記念碑のかずかずが登場するのは、あと数歩のことにすぎないのだ」と述べます。
「ヒトになる」として、地球上に生命が誕生したのが数10億年前のことで、恐竜が絶滅したのはおおよそ6500万年前だったと紹介し、著者は「私たち人類の祖先がチンパンジーの祖先から分かれたのはほんの1000万年から600万年前のことにすぎない。生命の歴史において、ヒトの歴史の割合はごくごくわずかなパーセンテージしか占めていないのだ」と説明。また、ゴリラとチンパンジー、そしてヒトの共通祖先はアフリカに住んでいたとして、「ゴリラとチンパンジーは現在でもアフリカにしか生息していないが、数100万年前までは人類もアフリカから足を踏み出すことはなかった。もともと、人類の祖先も類人猿の一種にすぎなかったが、しかし、あいついで起きた3つの変化をきっかけに、現在の人類にいたる方向へ向かっていく」と述べます。
その3つの変化とは何か。1番目の変化は約400万年前に現れていました。著者は、「化石の様子から、人類の祖先は2足歩行を常におこなっていたことを示していたのだ。これに対してゴリラやチンパンジーは通常、4足で歩行して、2足で立ち上がるのはときどきのことでしかない。ヒトの祖先が2足歩行を始めるようになると、両手は自由に使えるようになっていく。とりわけ大きな意味を帯びていたのが、その手で道具を作れるようになったということだった」と述べています。
2番目の変化は約300万年前に起きていました。著者は、「現生人類のすべては、ホモ・サピエンスという同一の種に属しているが、人類の系統――人類の祖先から現在の私たちへと連なる流れは、過去においておそらく数度、少なくとも2種に分かれて同時期に生息していた。そして、人類の系統が2つの種に分岐したのが、おおよそ300万年前のことだったのである。ひとつは厚い頭蓋骨と大きな臼歯をもつ猿人だった。猿人はおそらく繊維質の多い植物を食べていたのだろう。この猿人はアウストラロピテクス・ロブストゥス(Australopithecus robustus)と呼ばれ、「頑丈な南の猿」という意味だ」と述べます。
もう一種は、もっと軽くて薄い頭蓋骨と小さな歯をもつ猿人です。おそらく、食性の幅はもっと多彩だったのでしょう。アウストラロピテクス・アフリカヌス(Australopithecus africanus)、「アフリカの南の猿」と呼ばれています。そして、わたしたちの先祖から類人猿的な様子が薄れ、より人間らしいものへと変わっていったのが第3番目の変化とは何か。その正体を、著者は「恒常的に使われるようになっていた石器の存在だった。道具の使用は、動物界に明らかな起源をもつヒトの特徴にほかならない」と明かします。
「アフリカで起きたふるいわけ」として、50万年前起きたこのホモ・サピエンスの登場こそが大躍進だったのではなく、ホモ・サピエンスの登場とともに、特筆するような事件がただちに起きたわけではないことが明かされます。著者は、「洞窟の壁画、住居、弓と矢が登場するのはまだまだ数10万年先の話である。その石器はホモ・エレクトゥスが約100万年にわたって作っていたものと同じように荒削りなものだった」と述べます。
また、初期のホモ・サピエンスが備えていた余分な脳の大きさは、私たちの生活のあり方について劇的な変化を決してもたらすものではなかったとして、著者は「私たちが人間へと上昇していくことは、遺伝子の変化にただちに関係するものではなかったのである。つまり、第3のチンパンジーが「モナ・リザ」を描こうという考えを抱くようになるまでには、さらに決定的な要素をいくつかつけ加える必要があったのである」と述べています。
ここで、コラム「人類は有能なハンターだったのか」では、初期人類が肉を口にしていたことに言及し、動物の骨の化石には祖先が使った道具の痕跡が残っているし、骨から肉を切り落とした跡が石器にも残されていることが紹介されます。しかし、問題は、私たちの祖先が大型獣の狩猟で得た肉をどれだけ食べていたかで、すでに死んでいた動物の体からどれほどの量の肉をあさっていたかだとして、著者は「人類が狩りをしていたことを確かに示す最古の証拠は約10万年前にさかのぼるものの、当時の人類は、狩人としてまだそれほど上手ではなかったのは明らかである。とすれば、何10万年前の人類は、狩猟技術の点でさらに劣っていたのはまちがいないだろう」と述べます。
また、現代の狩猟採集民を対象にした研究では、家族が摂取するカロリーのほとんどは女性が集める植物性の食物によってまかなわれていることがわかっています。しかも、これらの人たちは初期のホモ・サピエンスよりもはるかに優れた武器を使っていることを指摘し、著者は「時には男たちも大型獣をしとめ、タンパク質の摂取に大いに貢献する場合もあるが、しかし、大きな獲物がおもな食料供給源であるのは唯一北極圏に限られている」と述べています。
さらに、大型獣の狩猟が人間の食料獲得に果たしていた役割はごくわずかで、それは人類が解剖学的にも行動面においても、現代の人間と変わらない進化を果たしたあとでも違いないと考えているとして、著者は「人類の歴史の大半を通じ、私たち人間は有能な狩人などではなく、石器を使い、植物性の食物や小動物を手に入れて処理していた、手先の器用なチンパンジーにほかならなかった。大きな獲物をしとめていたにせよ、それはごくたまのことにすぎなかったのである」と述べるのでした。
「氷河期を生きたネアンデルタール人」として、いくつかの点からネアンデルタール人に人間性を認めることができるだろうとして、著者は「ひとつは、火を恒常的に使っていたことをはっきりと示す証拠を残した最初の人間がネアンデルタール人にほかならない。保存条件に恵まれたネアンデルタール人の住んでいた洞窟内部には、灰と木炭を含んだ一角があり、簡単な暖炉として使われていたことを示している。さらにもうひとつ、遺体を埋葬する習慣を最初にもつようになった人間がネアンデルタール人かもしれないのだ。ただし、この点については、まだきちんと立証されているわけではない」と述べます。
しかし、病気になった仲間、年老いた仲間のめんどうをみていたのは明らかだとして、著者は「年老いたネアンデルタール人の骨を見ると、萎えた腕、歯の欠損、治りはしたものの不自由を残した骨折など、大半が深刻な身体的ハンディを負っていたことがうかがえる。このような不自由を抱えていれば、若い仲間の世話に頼ることなしに、年老いたネアンデルタール人は命をつないでいけなかったはずである。そう考えれば、最終氷河期を生きていたこれら奇妙な生き物――つまり、人間とよく似た姿をしていながらも、その精神はまだ人間とは言いがたい生き物に対して、私たちは自分の同族であるという印をまちがいなく見てとることができるはずだ」と述べるのでした。
第2部「奇妙なライフサイクル」の第5章「人はなぜ歳をとって死んでいくのか」では、「寿命をめぐる問題」として、ある意味で進化とはエンジニアのようなものであると指摘し、著者は「進化もまた、動物のほかの部分を切り離して個々の特質に限っていじり回すことはできない。器官、酵素、DNAなど、いずれもほかのものに使えたかもしれないエネルギーとスペースを使って作り上げたものだからである。個別にいじるかわりに、自然淘汰が選んだのは、その動物が繁殖成功度を最大化できる特質の組み合わせだった。エンジニアも進化生物学者も、なにかを増大させるなら、そこにはトレードオフ(差し引き関係)がかかわっている点を踏まえたうえで考えなければならない。変化がもたらす利益とともに、それにともなう損失の両面から評価しなくてはならないのである」と述べています。
第3部「特別な人間らしさ」の冒頭、人類を真に脅かしているのは、わたしたちの2つの文化的な習性であるとして、著者は「ひとつがジェノサイド(大量虐殺)であり、ある集団に属している人びとをことごとく殺し尽くす。もうひとつは他種の大量絶滅であり、環境破壊を決まってともなうが、その環境とは人間が暮らしていく場所でもあるのだ」と述べています。また、「最古の芸術」として、著者は「人類がチンパンジーから分かれて約700万年、最初の696万年を私たちは芸術とは無縁に生き抜いてきた。初期の芸術はおそらく木彫りやボディーペインティングだろうと思われるが、それがよくわからないのは、こうした造形は化石として残らないからである」と述べます。
化石として今日まで伝わり、ヒトの芸術ではないかと思わせる最初のものに、ネアンデルタール人の遺骨の周囲に残されていた花(手向けの花なのだろう)と、そのキャンプから発掘された削りあとがかすかに残る動物の骨があると紹介し、著者は「花が意図して置かれたものか、骨の傷もわざとつけられたものかどうかは判明していない。これらは芸術かもしれないし、単なる偶然の結果、そうなったのかもしれない」と述べています。わたしは、それを偶然の結果とは見ません。「ホモ・フューネラル」であるヒトが死者を弔うために行った行為であると考えており、拙著『唯葬論』(三五館・サンガ文庫)を書きました。
 『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)
『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)
第8章「農業がもたらした光と影」では、農業のおかげで食料の生産量は蓄えておくことができるほど飛躍的に増えたことを指摘し、著者は「つまり、より多くの人間が生き延びていけるようになったのだが、その一方で疫病を引き起こし、男女間や社会的な階級間に不平等を生み、強権的な支配者による専制という害悪をもたらしたのが農業である。ヒトの文化的特徴のなかで、よくもあり悪しくもあるのが農業なのである。農業は、言葉や芸術といった人間の高貴な特徴と、薬物乱用、大量虐殺、環境破壊などの悪徳とのちょうど中間に位置するものなのだ」と述べます。
現在でもなお猛威を振るっている伝染病や寄生虫は、農業に移行するまでは確たる勢いをもっていなかったと指摘し、著者は「こうした病気がはびこるのは、人口が密集し、栄養不良の定住者の住む社会に限られ、住人は互いのあいだで、あるいはみずからの排泄物を介して絶えず病気をうつしあっていた。集団感染する伝染病の場合、規模も小さく、人数もまばらで、たびたびキャンプを移動する狩猟民の集団では長生きすることはできない。結核やハンセン病、コレラの発生は農村が勃興してからのことで、天然痘、腺ペスト、麻疹は、都市に人が集中して人口密度が高まったわずか数千年前になってから出現するようになったのである」と述べます。
そして、「先史時代の交差点」として、「24時間が表示できる時計を想像してみてほしい」と読者に提案し、「この時計が示す1時間はそれぞれ10万年の時を表している。午前0時に人類の歴史が始まったとすれば、いま私たちは1日目の終わりを間もなく迎えようとしている。真夜中から夜明けまで、正午から日暮れまで、私たちは終日のほとんどを狩猟採集民として生きてきた。そして、午後11時54分、私たちはついに農業を採用した。もう後もどりすることはできないのだ。2度目の午前0時をまさに迎えようというとき、農業がもつ呪わしい面に制限をかけ、祝福にあふれた農業の恵みを実現する方法を私たちは見つけ出すことができるのだろうか」と述べるのでした。
第4部「世界の征服者」では、わたしたちの文化的な特質の中でも、言葉と農業と高度な技術の3つによってヒトの存在はきわめてユニークなものになりえていることが指摘され、「地球上に人間が広がり、世界の征服者になりえたのもこうした特質のおかげだ。そして、この世界征服の過程において、異なる集団同士の関係をめぐり、ヒトという種は基本的な変化を遂げていった」と書かれています。また、「最後に人間性に宿る暗黒の一面、すなわち『よそ者嫌い』という、自分と異なる人間に対して恐怖を覚えるヒトの性向についても考えてみよう」と呼びかけ、著者は「動物界において、よそ者嫌いはごくありきたりの競争に根差すものだが、同じ種である相手を大量に殺戮できる遠隔兵器を生み出したのは唯一ヒトに限られる。人間のジェノサイドの歴史をふりかえれば、恐怖に満ちた現代の戦争を引き起こした人間の醜い伝統が浮かび上がってくるだろう」と述べています。
第13章「シロかクロか」では、「動物界の仲間殺しと戦争」として、ジェノサイドの起源を理解する上で、特に興味を覚えるのは人間にもっとも近縁の種であるチンパンジーやゴリラの行動だと指摘して、著者は「人間には道具を操る能力と集団で計画を立てられる能力があるので、類人猿よりもはるかに殺人的である。1970年代ごろまでは生物学者なら誰もがそんなふうに考えていた。もっとも、これは類人猿が残忍であればという話だ。しかし、その後の発見から、チンパンジーもゴリラも人間の平均値と同程度には仲間に殺されていることが指摘されるようになった」と述べています。
「倫理規定とその破綻」として、つきあげてくる殺意をつねに抑制するのが倫理観で、すなわち何が過ち(この場合では人を殺害すること)であり、何が非道徳であるかということに対するわたしたちの理解だと指摘し、著者は「だが、なぜその衝動が解き放たれてしまうのか。そこが謎なのだ。この謎に対するひとつの鍵は、私たちが『我ら』と『彼ら』の観点から考えるように進化したという点である。チンパンジーやゴリラ、ライオンやオオカミといった社会性の高い肉食獣のように、初期の人類も集団を組み、互いに狭いなわばりのなかで暮らしていた。このころ、世界はいまよりもずっと小さく、そしてシンプルなものだった。1人ひとりの『我ら』が知っていたのは、ごく限られた『彼ら』であり、間近に住むものたちだった。ある人間集団にとっては、これは現在にいたるまで変わらない現実である」と述べます。
ジェノサイドの首謀者は、自らの行動と現代の理想たる世界共通の倫理の間に生じる対立から、どうやって身をかわすのか。それは、以下の3つの正当化のうちから、そのうちの1つか2つを駆使して、被害者に罪をなすりつけるといいます。第1に、世界的な規範を心から信じている人であっても、いまだに自己防衛には問題がないと考えています。第2に、「正当な」宗教、人種や政治的信条をもつことで、進歩やよりレベルの高い文明を代表するものだと主張します。最後に、わたしたちの倫理規範は人間と動物とは別のものだと見なしています。現代においてジェノサイドを引き起こした当事者は、殺戮を正当化するために被害者をいつも動物になぞらえようとするのです。
また、「ナチスはユダヤ人を人間以下の『シラミ』だと見なし、アルジェリアに入植したフランス人は地元のイスラム教徒を『ネズミ』と呼んだ。ボーア人(南アフリカに入植したオランダ人の子孫)はアフリカ人を『ヒヒ』と言っていた。アメリカ人はアメリカ・インディアンの扱いを正当化するために、こうした3つの言い訳のすべてを用いた。世界的な倫理規範を信じようと主張しているが、私たちの伝統的な姿勢とジェノサイドをめぐる物語は、白人は自己防衛のためにインディアンを殺してきたのであり、文化は白人のほうが優れていて、この大陸をさらに前へ前へと突き進んでいくように運命づけられている、そして犠牲者は野蛮な動物にすぎないというものだった」と述べます。
「未来を見つめて」として、ジェノサイドの可能性はわたしたちすべての人間の中に宿っていることを指摘し、著者は「世界の人口が増えていくにしたがい、社会間や社会内でのせめぎあいはますます激しいものになっていくだろう。互いに殺しあおうとする人間の衝動はさらに高まり、それを実現するための武器も性能を向上させていく。ジェノサイドをめぐる物語に耳を傾けることは耐えがたい痛みをともなうが、しかし、人間の本性に宿る破壊的な部分から目をそむけ、理解しようという試みを拒んでしまえば、いつの日か私たち自身が殺人者になるか、あるいは犠牲者になってしまうのかもしれないのだ」と述べます。
第5部「ひと晩でふりだしに戻る進歩」の第14章「黄金時代の幻想」では、有名なイースター島の石像が取り上げられます。「イースター島の謎」として、著者は「未完成のままの石像、うち捨てられたままの石像もあるが、その様子はまるで石工と運搬担当者が突然仕事を放りだし、持ち場を立ち去ったようである。オランダ人の探検家がやってきたときには石像はまだ立っていたが、1840年までには石像は島民によってひとつ残らず倒されていた。いったい、巨大な石像はどのようにして作られ、どうやって運搬されたのだろう。そして、島民はなぜ像を彫ることをやめ、最後には引き倒してしまったのか」と述べます。
第一の疑問について、自分たちの先祖は丸太をころとして使って石像を運んだと、20世紀の研究者トール・ヘイエルダールに対して島民が答えています。第二の質問に対する答えは、この島の容赦ない歴史を示すものであり、考古学者と古生物学の研究者によって明らかにされました。著者は、「ポリネシア人がイースター島に入植したのは西暦400年ごろであり、当時、島は森林でおおわれていたものの、木材を得たり、菜園を作ったりするために森林は徐々に切り開かれていった。西暦1500年ごろまでには、島の人口はおよそ7000人にまで増えていた。島民が彫った石像は約1000体、このうち少なくとも324体が立てられていた」と述べます。
また、「幼年期に起きた文明の生態学的破壊」として、古代都市ペトラが取り上げられます。ここには「失われた都市」と刻んだ岩が残されているのですが、映画「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」が撮影されたことでも知られます。著者は、「ペトラもまた、世界中に残る数多くの古代都市のひとつにすぎず、みずからの生存手段を破壊した国をまつる記念碑として今日に伝わっている。中央アメリカのマヤ文明、インドやパキスタンのハラッパ文明など、文明のことごとくが没落したのは、増えつづける人口がそれぞれの環境を圧倒してしまったせいなのだろう。歴史の本では王たちと蛮族の侵入について長々と語られている場合が少なくないが、結局は、森林破壊や浸食のほうが、人間の歴史を形づくるうえでははるかに重要な役割を果たしていたようである」と述べています。
おわりに「なにも学ばれることなく、すべては忘れさられるのか」では、人類に大躍進が起きたという確かな証拠が6万年頃のヨーロッパに突然出現したことを指摘し、著者は「この躍進を促したものがなんであろうと、それにかかわった遺伝子はごく一部だったのはまちがいないはずだ。現在でも人間とチンパンジーの遺伝子の違いは全体の1.6パーセントにすぎず、しかもその違いの大部分は、行動面において大躍進が起こる以前に刻み込まれていた。私自身は、言語能力を得たことを引き金にして大躍進は起きたにちがいないと考えている」と述べています。
最初の現生人類は、高貴な特徴を備えていましたが、著者は「彼らは現在私たちが抱えている問題の根底に横たわる2つの特徴も背負っていた。そのひとつこそ、互いに大量の人間を殺しあうという私たちの性質である。そして、もうひとつは、環境と資源基盤を破壊しようとする性質である。もしも、ほかの太陽系で勃興した高度な文明においても、自己破壊の種子が根深く関連しているのであれば、空飛ぶ円盤がなぜ私たちのもとを訪れてこないのかという事実もすんなり納得がいくだろう」と述べるのでした。
「訳者あとがき」で、秋山勝氏は本書の魅力について、「人間とはなにかという根源的で哲学的な問いについて、”若い読者”も強い好奇心に駆られながら、科学的に考えを深めていける点につきるだろう。鳥類学、進化生物学、生物地理学、人類生態学、古環境学、古病理学、言語学などの幅広い学識が縦横に駆使され、学際的に考えることの豊かさと興奮が堪能できる。また、生物学的な進化にとどまらず、言語、芸術、農業といった文化的な進化という推力についても本書は詳しい。農業の発展につれて階級分化が始まり、〈支配者―被支配者〉が分離していったことはよく知られている。だが、農業の誕生以前、狩猟採集民族の生活のほうがはるかに健康的で、生きることの豊かさを謳歌していたという点にまで指摘がおよぶのは、古病理学や育種学を踏まえたうえで語る博士ならではの知見だろう」と述べています。
「解説」では、総合研究大学院大学学長の長谷川眞理子氏が、「この本のテーマは、人間とはどんな動物か、ということです。人間は動物だけれども、ほかのいろいろな動物とは違って特別に偉いのだという考えは、かなり多くの人々が持っているようです。なぜなら、コンピュータやロケットなどを発明し、大きな都市に住み、言語を駆使して哲学的なことを考え、宗教を持ち、芸術を楽しむような生物はほかにいない(ように見える)からです。その一方で、人間が自分たちを特別な存在だと思うのは、人間の自己中心的な思考のせいであって、ミミズだろうがイチョウだろうが、どんな生物もそれぞれに特別なのだ、という考えもあります」と述べています。
その昔、哲学は、「人間はどんな動物か?」を追求する学問的広がりを持った探究でした。だからこそ、長年にわたって、人間とは何かという探究は、哲学の主たるテーマだったのだと指摘し、長谷川氏は「現代では、人間のいろいろな側面に関する研究が、それぞれに大変に深く専門化されてしまっているので、本当の人間の哲学をやろうと思えば、これほど多岐にわたる学問分野に踏み込まねば、できなくなってしまっていると言えるでしょう。でも、だからと言って、人間とは何かを探究することが、ソクラテスの時代よりも格段に難しくなってしまった、ということはないと思います(一見するとそう思えるけれども)。古代ギリシャのソクラテスでも、現代の私たちでも、からだと脳の基本的構造に変わりはありません。つまり、今の私たちも、紀元前4世紀のソクラテスも、ハードの面では同じ脳を使って考えているのです」と述べます。
現代では、この2000年の学問の発展の成果として参照するべき情報が、ソクラテスの時代に比べて格段に増えたとしながらも、長谷川氏は「いろいろな研究が進んだ結果、もう解決してしまったこともありますし、その方向で考える必要はないことがわかったということもあります。そして今ではコンピュータやインターネットがありますから、ソクラテスの時代よりも格段に多くの情報を各段に速く処理することができるはずでしょう。何も、それぞれの学問領域の細部にわたって知る必要はないのです。ソクラテスと同じ構造の頭を使って、ことの真髄だけを掘り出してつなげていけばよいはずです。確かにそれは難しいことではありますが」と述べます。
そして、「ジャレドの人間探求」として、長谷川氏は「本書は、私たち人間とはどんな生き物なのかについて科学的に考察したものです。しかし、それは単に人間の生物学的な組成や進化の道筋を科学的に解説したということではありません。人間という生き物が、この地上で現在行っていることは何なのか、この先、人間はどうなっていくのかという、私たち1人1人の生き方に思いをはせる、いわば哲学的な考察に導くものです。自然科学の探究そのものは、価値観や哲学とは異なる舞台で、客観的な検証に耐えるものとして進んでいきます。しかし、その結果は、私たち自身がどのように生きていくべきかについて、大いに示唆を与える材料となるでしょう。その意味で、そういう含意を意識して書いたという点で、この著作は非常に大きな視野を持っていると私は思います」と述べるのでした。
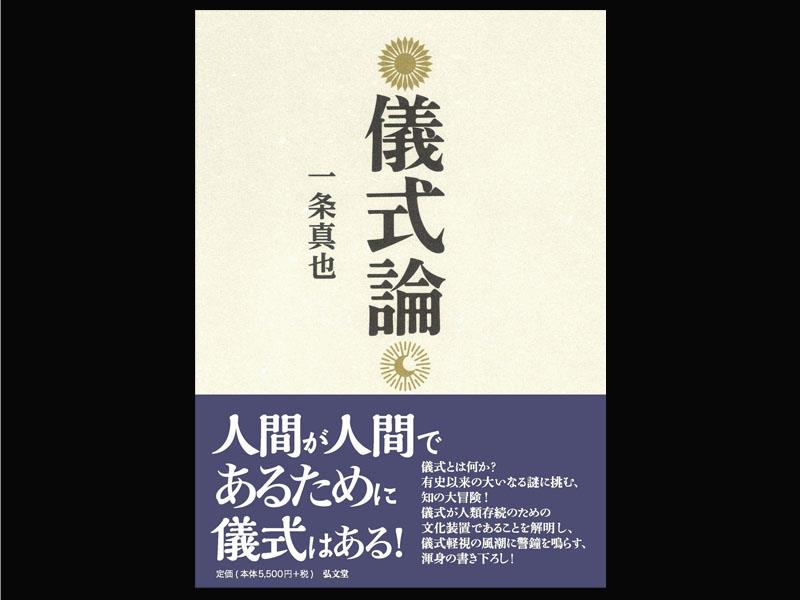 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
本書は、平易な言葉で書かれていますが、長谷川氏の言うように「人間はどんな動物か?」ということを考えさせてくれる良書でした。ちなみに、拙著『儀式論』(弘文堂)で、わたしは「人間は儀式的動物である」と訴えました。結婚式、葬儀といった人生の二大儀礼から、成人式、入学式、卒業式、入社式といった通過儀礼、さらには神話や祭り、オリンピックの開閉会式から相撲まで、あらゆる儀式・儀礼についての文献を渉猟したわたしは、「儀式とは何か」をテーマ別に論究。「人類は生存し続けるために儀式を必要とした」という仮説の下、儀式の本質に迫りました。第三のチンパンジーは儀式的動物なのです!
