- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.04.22
『老後レス社会』朝日新聞特別取材班(祥伝社新書)を読みました。サブタイトルは、「死ぬまで働かないと生活できない時代」です。朝日新聞特別取材班は、格差と超高齢化によって、人生後半の生き方、そして働き方が大きく変わろうとしている現在地を報じようと、各部の一線記者が集まった取材班だそうです。未曽有の少子高齢化・人口減少問題に取り組む長期企画「エイジングニッポン」の一環として、2019年に「老後レス時代」シリーズの取材を開始。就職氷河期世代を「ロストジェネレーション」と名付けた同紙の企画とも連動。執筆陣は総勢9名。
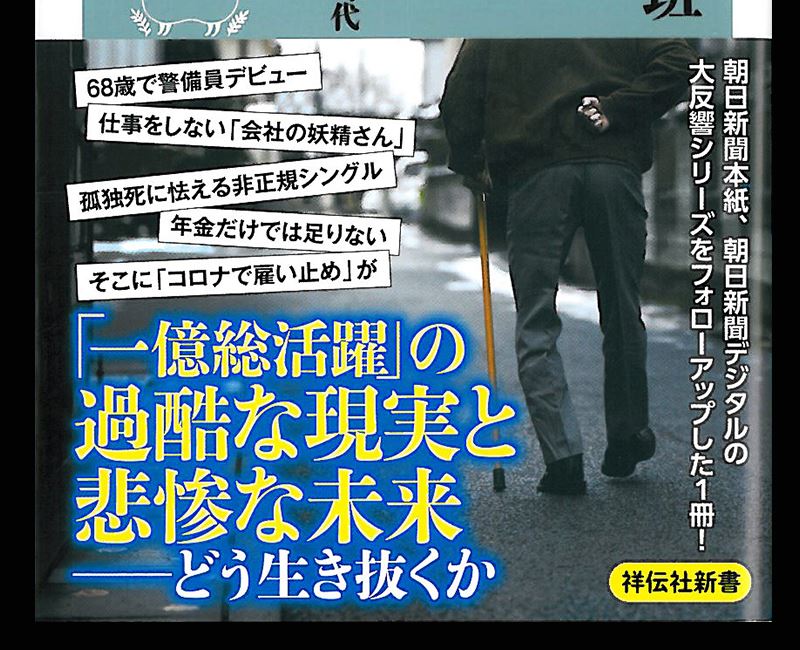 本書の帯
本書の帯
帯には杖をついて歩く老人の後ろ姿の写真とともに「68歳で警備員デビュー」「仕事をしない『会社の妖精さん』」「孤独死に怯える非正規シングル」「年金だけでは足りない」「そこに『コロナで雇い止め』が」「『一億総活躍』の過酷な現実と悲惨な未来――どう生き抜くか」「朝日新聞本紙、朝日新聞デジタルの大反響シリーズをフォローアップした1冊!」と書かれています。
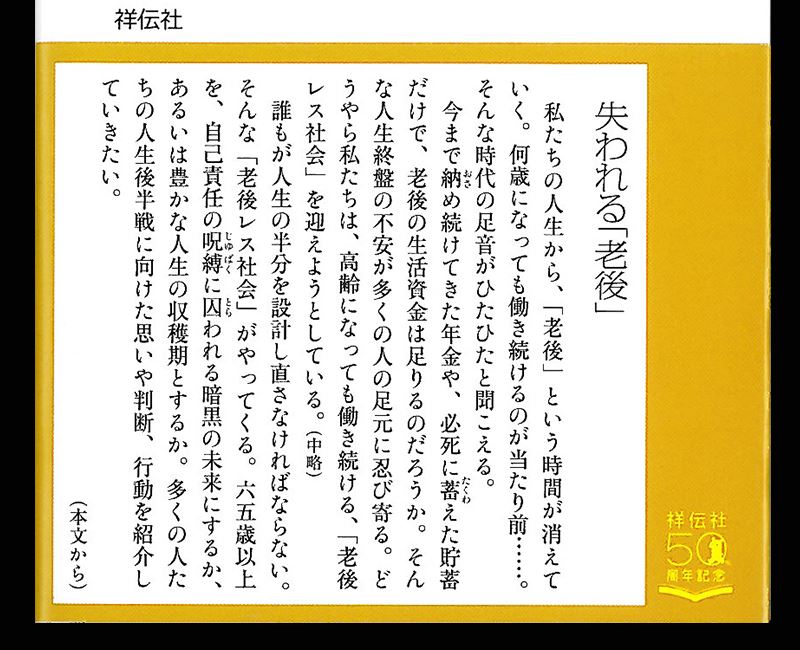 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「失われる『老後』」として、「私たちの人生から、『老後』という時間が消えていく。何歳になっても働き続けるのが当たり前……そんな時代の足音がひたひたと聞こえる。今まで納め続けてきた年金や、必死に蓄えた貯蓄だけで、老後の生活資金は足りるのだろうか。そんな人生終盤の不安が多くの人の足元に忍び寄る。どうやら私たちは、高齢になっても働き続ける、『老後レス社会』を迎えようとしている。(中略)誰もが人生の半分を設計し直さなければならない。そんな『老後レス社会』がやってくる。65歳以上を、自己責任の呪縛に囚われる暗黒の未来にするか、あるいは豊かな人生の収穫期とするか。多くの人たちの人生後半戦に向けた思いや判断、行動を紹介していきたい。(本文から)」とあります。
カバー前そでには、「待ち受けるのは暗黒の未来(ディストピア)か」として、以下の内容紹介があります。
「2040年問題―一九年後、日本の人口は六五歳以上の高齢者が35%を占めると推計されている。社会保障費が増大する一方で、労働力不足は深刻化。政府は『一億総活躍』と称し、高齢者の就労促進を謳うが、そこには公的支援を抑えようとする意図が透けて見える。70歳を過ぎてもハローワークに並ぶ。もはや『悠々自適の老後』はなくなった。死ぬまで働かなければ生きていけない『老後レス社会』が到来する。朝日新聞本紙と朝日新聞デジタルで好評を博したシリーズに、新たな取材による加筆を全面的に施し、『老後のなくなった日本の現実』と、避けられない未来をどう生きるかを考える」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章 消える「老後」
1章 高齢警備員
―過酷な現場でも「死ぬまで働く」理由
2章 会社の妖精さん―働かないおじさんたち
3章 ロスジェネたちの受難―私たちは、のたれ死に?
4章 定年前転職の決断 ―妖精さんとは呼ばせない
5章 死ぬまで働く ―前を向いた高齢者たち
6章 老後レス社会を生きる―定年延長、再雇用、
そして年金。近未来へのヒント
「おわりに」
「はじめに」には、「この国で、『少子高齢化』と『人口減少』という言葉を聞かぬ日はありません。加えて、経済的格差は広がるばかりで、それにコロナ禍による景気低迷や失業の増加が追い打ちをかけている。『老後への不安』は、すでに日本社会の通奏低音となっています。このまま高齢者が増加し、現役世代がさらに減り続ければ、私たちの人生の終盤は大きく変わらざるを得ないだろう……。意識する、しないにかかわらず、多くの日本人は薄々そう感じているのではないでしょうか」と書かれています。
また、工事現場で車や歩行者を誘導している警備員や、オフィスを清掃している作業着姿の人が、どう見ても70代以上だと気付くことが増えたとして、「高齢者を積極的に雇用する企業も現われ、定年退職後に新たに別の仕事を始めたり、地方へ移住して第2の人生を歩んだり、という選択もよく耳にします。そうかと思えば、高齢期を前に企業内で居場所を失った中高年のサラリーマンや、数十年先の老後への不安に苛まれる単身で非正規雇用の若い男女もいます」と書かれています。
本書は、2019年から2020年にかけて、日本の少子高齢化と人口減少をめぐるさまざまな問題を特集した朝日新聞の企画「エイジングニッポン」の一環として生まれました。参加した記者たちは30代から50代まで幅広い世代にまたがっており、当人たちもまた、自らの人生後半戦について思い惑いながら、取材を進めたそうです。「老後レス社会を生きるヒントを見つけたいという思いは、この本を手に取ってくださった方と共通しています」と述べられています。
2020年は世界中が新型コロナウイルスに翻弄されましたが、「コロナだけではありません。市場のグローバル化と日本経済の低迷、地球温暖化による気候変動、東アジアの安全保障環境の変化など、国内外の情勢は予測不可能なことばかりです。こんな確定的なことが何も言えない現在の日本で、確実に予想できる事象が1つあります。近い将来に高齢者人口が激増するということです。そして、どんなに時代が変化しようと、人間は必ず年を取るという事実もまた、変わることがありません。1人の例外もなく、すべての人が自分ごととして考えなければならないのが、老後レス社会なのです」と述べられています。
そして、「医療技術の進歩は目覚ましく、とりわけ世界有数の長寿国である日本では、今後も平均寿命が延びると予想されています。これは、あえて皮肉な表現をすると、『簡単には死ねない時代』がやってくるということでもあります。人生100年時代の到来を、『長寿の夢の実現』と見るのか、それとも『長生きリスクの増大』と考えるのか。それは、これからの私たちの選択と行動にかかっています」と述べられるのでした。
序章「消える『老後』」の冒頭の「忍び寄る不安」では、「私たちの人生から、『老後』という時間が消えていく。何歳になっても働き続けるのが当たり前……。そんな時代の足音がひたひたと聞こえる。いままで納め続けてきた年金や、必死に蓄えた貯蓄だけで、老後の生活資金は足りるのだろうか。そんな人生終盤の不安が多くの人の足元に忍び寄る。どうやら私たちは、高齢になっても働き続ける、『老後レス社会』を迎えようとしている」と書かれています。
また、「老後が怖い」と考える人がじわじわと増えているとして、「日本社会は戦後一貫して平均寿命を延ばし続け、世界に冠たる長寿国となった。100歳以上の人口は増え続け、2020年には8万人を超えた。人類史上、誰もが望んだ『長生き』という幸せを真っ先に手に入れた国で、老後に不安を募らせている人々が増えているというのは、何という皮肉だろう」
「生活の足腰が弱まる人々」では、所得の落ち込みにとどまらず、さまざまなかたちで「生活の足腰」が弱まっている人たちも増えているとして、「象徴的なのが、就職氷河期に社会に出た氷河期世代『ロストジェネレーション』(ロスジェネ)である。90年代半ばから2000年代半ばまで、企業が業績悪化のために新卒採用を極端に絞り込むと同時に、政府は規制緩和として派遣労働を多くの業種で解禁した。このタイミングで就職活動をしたロスジェネたちは非正規雇用に多く就き、雇用も収入も社会的地位も不安定なまま、中年になった人が多い。中高年の引きこもりや、高齢の親と同居の子の危機、いわゆる『7040問題』『8050問題』も、この世代の不遇が深く関わっている」と述べられています。
家族のかたちも変わり始めています。世帯類型を見ると、「単身世帯」は2015年で約35%に上り、「夫婦のみの世帯」や「夫婦と子からなる世帯」を超えて多数派となりました。50歳時点での未婚の人の場合、いわゆる生涯未婚率は男性がほぼ4人に1人、女性が7人に1人で、今後も上がり続けると推計されています。男性よりも平均寿命の長い女性は、将来的に高齢単身世帯となる可能性が高く、貧困に陥りやすいそうです。
「有史以来の転換点」では、日本が直面する危機について、国立社会保障・人口問題研究所の前副所長で明治大学特任教授を務める金子隆一氏が、「有史以来の大きな転換点」と形容しています。日本の人口は2008年頃にピークを過ぎ、これから徐々に加速しながら、最後はつるべ落としに減っていきます。この国の人口が1億を突破したのは戦後の高度成長期の1967年であり、今後は2050年を過ぎた頃に逆に1億人を切ると見込まれていますが、金子氏によれば「1億という同じ人口規模でも中身はまったくと異なる」といいます。
「2040年問題という『時限装置』」では、この人口オーナスのピークが日本を直撃するのは、いつかという問題が提起されます。いま、研究者や政府関係者の間で最も懸念されているのが、「2040年問題」であるとして、「この頃、団塊ジュニアという大きな人口の塊が高齢世代入りし、老年人口が最多となる。先に述べたように、この世代はロスジェネとして経済基盤も弱く、単身率も高い。日本社会そのものの持続可能性が大きな危機に瀕する年、それが2040年だ」と書かれています。
昭和と令和の高齢者像の違いを分かりやすく示しているのが、昭和の国民的漫画「サザエさん」に登場する一家の大黒柱、磯野波平です。「昭和と令和、それぞれの『波平さん』」では、「頭髪はかなり寂しくなり、趣味は盆栽で、家ではいつも和服姿でくつろいでいる。まだ会社勤めをしているが、すでにシルバーの雰囲気を漂わせている波平さん。長男のカツオ、次女のワカメはまだ小学生ではあるものの、長女のサザエは結婚して、孫のイクラにも恵まれた。現代の都市部の感覚では、波平の年齢は60代半ばか後半ぐらいのイメージだろう。しかし、作中では、まだ54歳とされている。朝日新聞で四コマ漫画の連載が本格的に始まった1950年代は55歳定年が一般的であり、まさに定年直前という設定だった」と書かれています。
「『一億総活躍社会』の本音」では、「現役世代が減っていく以上、高齢者の力を生かすことの重要性は否定しがたい。その一方で、政権の姿勢には危うさも感じられる。高齢者の増加に伴って必然的に増える公的支援を、できる限り抑えることに力点を置かれているように見えるからだ。コロナ禍では『ためらわずに申請を』と呼びかけているが、これまで国は、国民が貧困に落ち込んだ際の最後の切り札である生活保護を、できるだけ絞り込もうとしてきた。疾患に対する抵抗力や基礎体力が落ち、健康状態も急変しやすい高齢期は、いざという時に確実に受け止めてくれるセーフティーネット(安全網)がなければ、安心して働くことはできない」と述べられています。そして、「ディストピアか、人生の収穫期か」では、安倍氏を継いだ菅義偉首相が、目指す社会像として「自助・共助・公助」を掲げたことが紹介され、「一見、当たり前のようにも思えるが、重要なのはそのバランスである」と指摘されます。
1章「高齢警備員」の「職場は『70歳以上が8割』」では、「警備会社で働いてみて驚いたのは、働く高齢者の多さだった。なかには80歳を超えた人も。いまの勤務先では、70歳以上が8割を占めている。そう社長が教えてくれた。『超高齢化社会に進む現代日本の縮図がここにある』。そんな思いが日増しに強くなった。交通誘導で道行く車のドライバーに罵声を浴びせられ、警備員自身が「最底辺の職業」と自嘲する。そんな現場の実態と、人間臭いドラマを描けば面白いのではないか――。薄れていた出版の仕事への意欲がまたよみがえってきた」と書かれています。こうして書き上げたのが『交通誘導員ヨレヨレ日記』(三五館シンシャ)でした。
『交通誘導員ヨレヨレ日記』は「当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます」というコピーをつけられ、2019年7月に出版されました。初版は5000部でしたが、その後の増刷で7万6000部(2021年4月時点)のスマッシュヒットになったそうです。この本、わたしは版元の三五館シンシャから献本を受けました。じつは、同社の中野長武代表が「出版界の青年将校」と呼ばれた三五館の編集者時代にわたしの担当だったのです。無縁社会を乗り越えるための方策を書いた『隣人の時代』をはじめ、多くの一条本を編集して下さいました。三五館は残念ながら倒産しましたが、それらの本は、三五館シンシャからオンデマンドで発売されています。
「『働きたい』のか、『働かざるをえない』のか」では、本来、喜ぶべきことであるはずの長寿化が不安をもたらし、人生最大のリスクとなると指摘し、「そんな社会に私たちは生きている。2019年の国民生活基礎調査によると、全世帯5178.5万(2019年、総務省統計局)中、年収300万円未満の世帯が全体の3分の1を占めている。2019年度の内閣府の世論調査では、『日頃の生活で悩みや不安を感じている』と回答した人に理由を聞いたところ、『老後の設計』を挙げた人が56.7%(複数回答)で最も多かった。そんな中、安倍首相は在任中、『一億総活躍』というスローガンを掲げ、高齢者らの就労を促す方向に舵を切った」
また、「65歳を超えて働きたい。8割の方がそう願っておられます」「(高齢者の)豊富な経験や知恵は、日本社会の大きな財産です。意欲ある高齢者の皆さんに70歳までの就業機会を確保します」という総理の発言にネットはざわついたことが紹介され、「働かなきゃ食えないんだよ!」「大半の人は『働きたい』じゃなくて、『働かざるを得ない』ですよね」という反発が書き込まれたそうです。内閣府によると、この「8割」という数字は2014年度の「高齢者の日常生活に関する意識調査」をもとにしたものでした。ただし、これは仕事をしている人に分母を限定した数字で、回答者全体では約55%だとか。これを受けて、本書には「自分の意思として働きたいのか、生活のために働かざるを得ないのか。多くの人が感じる老後不安は、派手なスローガンで覆い隠すには、あまりに大きすぎる」と書かれています。
「『新しい生活困難層』が出現した」では、「なぜ、いま、『働かなくては生きていけない』高齢者が増えているのか?」という疑問について、福祉政策を専門とする中央大学法学部教授の宮本太郎氏は「生涯現役で元気に働き続けましょう、と上から号令をかけるだけでは、老いに関わるさまざまな困難を忘れた空想論になってしまいます。老後もばりばり働いてコロリと死ぬ『ピンピンコロリ』が理想だと圧力をかけるような空気はおかしいでしょう。老後を人生の付録のように考えないという意味での『老後レス』だったらいいのですが、実生活の厳しさを忘れた『人生レス』の施策は困ります」と答えています。
3章「ロスジェネたちの受難――私たちは、のたれ死に?」の「失われた世代(ロストジェネレーション)」では、日本において65歳以上の人口がピークを迎えるのはいまから約20年後の2042年で、高齢者の数は3935万人まで膨れあがることが紹介され、「同時に高齢化率も高まり、2036年には3人に1人、2065年には2.6人に1人が65歳以上となる。そんな時代に高齢者デビューするのが、主に団塊世代の子どもとして1971年から74年に生をうけた第2次ベビーブーマー、いわゆる団塊ジュニア世代なのだ。現在は40代後半にあたるが、生産年齢人口のうちで最大の人口ボリュームを持ち、世代全体の人口は800万人近くにも上る」と説明されています。
この世代を特徴づけるのは、人口規模が大きいことに加えて、バブル崩壊後の深刻な景気低迷期に社会に出ることになった、という歴史的背景です。本書には、「1990年代後半から2000年代前半、業績が低迷し、過剰な社員を抱えた企業の多くが採ったのは、社員のリストラではなく、新卒者の採用を極端に絞り込むという方策だった。この戦後最悪の『就職氷河期』と、大学や専門学校、高校を卒業するタイミングが重なったのが、1970年前半から80年代前半にかけて生まれた人たちであり、団塊ジュニア世代をまるまる含んでいる」と説明されています。
2000万人規模ともいわれるロスジェネは、いまや30代後半から40代となっているとして、「いまだ少なくない人々が不安定雇用にとどまり、低賃金にあえぎ、親と同居し、家族を持てず、将来展望に不安を抱いている。メディアでは『アラフォー・クライシス』や『中年フリーター』といった新たな呼び名もついた」と説明されています。このロスジェネは、「妖精さん」と呼ばれる企業の余剰人員と対極に位置する存在とも言えるとして、「企業内で居場所を失いながらも安定した収入が保障されている妖精さんたちと比べて、希望通りの職に就けず、低収入で、社会での居場所すら見つけられない人が、ロスジェネには多いのだから」と述べられています。
「不安定な雇用の先頭走者」では、「なぜ、この世代は落とし穴から抜け出せないのか」と問いかけ、2つの理由を示します。1つ目は、「非正規雇用の拡大だ。バブル崩壊後の規制緩和で派遣労働の対象職種が広げられ、正規、非正規という身分制度のような分断が労働市場に生まれた。雇用の不安定化は、その後の世代にも及んでおり、ロスジェネはその先頭走者となった」。2つ目は、「最大の原因は、日本独特の雇用慣行である。新卒時の一括採用、年功序列、終身雇用は、戦後の高度成長を支えてきた。まっさらの若者を会社が丸抱えして職業教育を施し、労働力を確保する。右肩上がりの時代には一定の効用があっただろう」と書かれています。
しかし、バブル崩壊後の長期不況で、この雇用システムは矛盾を露わにします。年長世代の雇用を守ろうとする日本企業の多くは、世代間のバランスを顧みずに新規採用を絞り込みました。その後に景気回復しても、新卒の採用が優先され、この世代は見捨てられた。いわば、「妖精さん」を守るために正社員から弾き出されたのが、ロスジェネたちだとも言える。いまになって経済界は新卒一括採用や終身雇用の廃止を唱え始めているが、中年になったロスジェネを救済するには、もはや平時の雇用改革では遅すぎる。
4章「定年前転職の決断」記者コラム「コロナは『日本人の老後』をどう変えた?」では、2021年春に卒業予定の大学生の就職内定率は69.8%(2020年10月現在)だったことが紹介されます。前年同期からの下げ幅7ポイントは、2008年のリーマン・ショックが直撃した2010年卒に比肩します。コロナ禍が就職活動期と重なってしまった世代が、「ロスジェネ世代」の再来となりかねません。
前年の最終的な就職内定率は過去最高の98%で、東京大学教授の本田由紀氏によれば、「どのタイミングで新卒就職するかによって明暗がはっきりと分かれてしまう」という事態が繰り返されれば、新たな生活不安定層が生まれることになるといいます。本書には、「若い世代の生活が不安定だと出生数に影響する。2020年の出生数は85万人を割り込む見通しで、翌21年は80万人を下回る可能性もある。コロナ禍により、日本の人口ピラミッドがさらに不安定化しかねない」と書かれています。
そして、「いくら元気に長く働けていても、誰もがいずれは年老いる。ロスジェネ世代や、コロナ禍で脆弱さがあらわになった非正規雇用の人たちは、『自助』による備えには限界がある。強制加入だが、本質は『共助』である年金や医療の社会保険、最後のセーフティーネットである『公助』の生活保護や福祉で何とか支え続けるしかない。特に、死ぬまで受け取れる公的年金は重要だ」と述べられるのでした。本書を読んで、わたしは暗澹たる気分になりました。特に、失われた世代(ロストジェネレーション)の人々が置かれた過酷な境遇に言葉を失いました。しかし、当然ながらロスジェネの人々の中には優秀な人材も多いはずであり、会社の経営者としては、そういう人材のわが社への中途入社をぜひ促進したいと思いました。また、「老後レス」で長生きがリスクとなる時代における互助会の在り方も考えたいと思いました。
それにしても、日本はどうしてこんな国になってしまったのでしょうか? 「老後レス社会」の他にも「無縁社会」という大きな問題があります。2010年、NHK「無縁社会」キャンペーンが大きな話題となりました。身元不明で「行旅死亡人」となった男の意外な人生、家族に引き取りを拒否された遺体の行方、孤独死の現場を整理する「特殊清掃業者」。年間32000件にも及ぶ無縁死の周辺を丹念に取材し、血縁、地縁、社縁が崩壊した現代社会へ警鐘を鳴らしました。番組は菊池寛賞を受賞し、「無縁社会」という言葉は同年の流行語大賞にも選ばれました。
「老後レス社会」を連載した朝日新聞紙上で、2010年末には「孤族の国」という大型企画がスタートしました。「家族」という形がドロドロに溶けてしまいバラバラに孤立した「孤族」だけが存在する国という意味だそうです。「孤族の国」の内容はNHK「無縁社会」とほぼ同じです。NHKへの対抗心から朝日が連載をスタートさせたことは明白ですが、「無縁」とほぼ同義語の「孤族」という言葉を持ってくるところが何とも情けないと思いました。
なぜならば、「無縁社会」キャンペーンに対抗するならば、「有縁社会」キャンペーンしかありえないからです。ちなみに、「有縁社会のつくり方」として、わたしが書いた本が『隣人の時代』(三五館)です。現在は、『交通誘導員ヨレヨレ日記』の版元の三五館シンシャの代表である中野長武さんが編集してくれました。日本の高齢者の多くが「老後レス社会」と「無縁社会」から挟み撃ちを受けている現在、改めて『隣人の時代』を多くの方々に読んでいただきたいと心から願っています。
