- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2265 オカルト・陰謀 『現代怪談考』 吉田悠軌著(晶文社)
2023.08.28
『現代怪談考』吉田悠軌著(晶文社)を読みました。この手の本には目がないわたしですが、本書は説得力に富んだ久々の名著でした。著者は、怪談研究家。1980年、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、ライター・ 編集活動を開始。怪談サークル「とうもろこしの会」の会長をつとめ、 オカルトや怪談の研究をライフワークに。テレビ番組「クレイジージ ャーニー」では日本の禁足地を案内するほか各メディアで活動中。 著書に『一生忘れない怖い話の語り方』(KADOKAWA)、『オカルト探 偵ヨシダの実話怪談』シリーズ1~4巻(岩崎書店)、『怖いうわさ ぼくらの都市伝説』シリーズ1~5巻(教育画劇)、『恐怖実話 怪の残香』(竹書房)、『日めくり怪談』(集英社)、『禁足地巡礼』 (扶桑社)、『一行怪談(一)(二)』(PHP研究所)など多数。
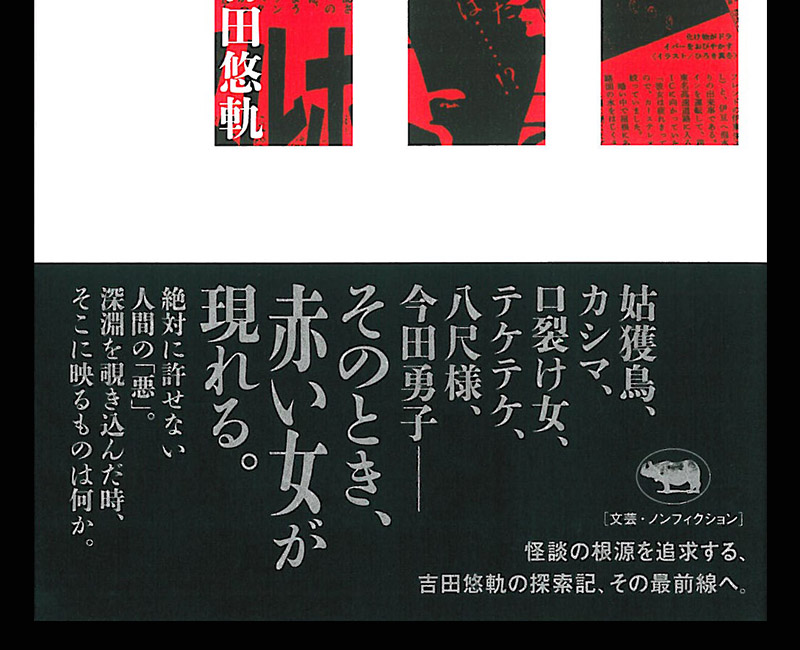 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「姑獲鳥、カシマ、口裂け女、テケテケ、八尺様、今田勇子――そのとき、赤い女が現れる。」「絶対に許せない人間の『悪』。深淵を覗き込んだ時、そこに映るものは何か。」「怪談の根源を追求する、吉田悠軌の探索記、その最前線へ。」と書かれています。
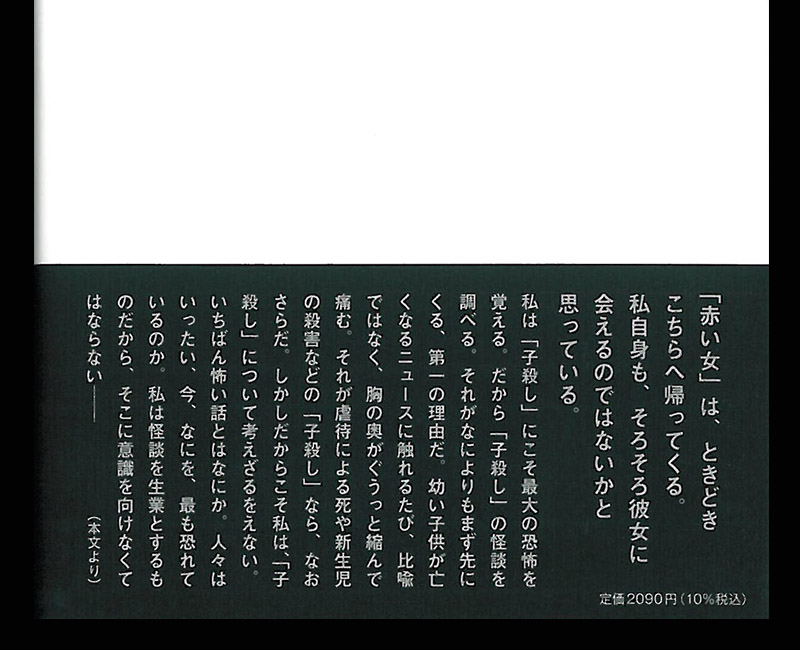 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「『赤い女』は、ときどきこちらへ帰ってくる。私自身も、そろそろ彼女に会えるのではないかと思っている。」として、「私は『子殺し』にこそ最大の恐怖を覚える。だから『子殺し』の怪談を調べる。それがなによりもまず先にくる、第一の理由だ。幼い子供が亡くなるニュースに触れるたび、比喩ではなく、胸の奥がぐうっと縮んで痛む。それが虐待による死や新生児の殺害などの『子殺し』なら、なおさらだ。しかしだからこそ私は、『子殺し』について考えざるをえない。いちばん怖い話とはなにか。人々はいったい、今、なにを、最も恐れているのか。私は怪談を生業とするものだから、そこに意識を向けなくてはならない――(本文より)」と書かれています。
本書のカバー前そでには、こう書かれています。
「現代怪談に姿・形を変えながら綿々と現れ続ける『赤い女』。そのルーツとは。現代人の恐怖の源泉を見据えることで明らかになる『もう一つの現代史』。赤い女の系譜を辿りつつ、その他重要な現代怪談のトピックについても探索していく。浮かび上がる『ミッシングリンク』とは。」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
怪談の深層に眠るもの「子殺し」怪談 section1
1 イタリア公園へ
2 こんな晩
3 ザシキワラシ
現代怪談の最前線①歩く死体を追いかけろ!
怪談の深層に眠るもの「子殺し」怪談 section2
4 現代怪談の幕開け
5 夕焼けの人さらい
〈付1〉赤い女前史
6 口裂けの系譜
現代怪談の最前線②牛の首
怪談の深層に眠るもの「子殺し」怪談 section3
7 子殺しの罪と罰
――コインロッカーベイビー
としての「コトリバコ」
8 欠損する下半身の意味するもの――カシマさん
現代怪談の最前線③人面犬
怪談の深層に眠るもの「子殺し」怪談 section4
9 「大流行」以前の口裂け女
10 変容する口裂け女
11 潜伏するカシマ・ウイルス
〈付2〉テケテケ
現代怪談の最前線④岐阜ポルターガイスト団地
怪談の深層に眠るもの「子殺し」怪談 section5
12 「感染」を拡大させる赤い女
――アクサラ、泉の広場の赤い女
13 「白い女」の系譜
――サチコ、ひきこさん、八尺様
14産みなおし、生まれ返りを希求する存在たち
〈付3〉MOMOチャレンジ
現代怪談の最前線⑤樹海村
怪談の深層に眠るもの「子殺し」怪談 section6
15 なぜ多くの人々が「赤い服を着た大きな女」
を見てしまうのか?
16 怪談とはなにか、恐怖とはなにかを探ること
「おわりに」
「怪談の深層に眠るもの『子殺し』怪談 section1」の1「イタリア公園へ」では、著者は「私は『子殺し』こそが現代怪談の最重要テーマではないか、と考えている。また実際、ここ数年間は、そうした主張をたびたび発信するようにこころがけてもいる」として、「赤い女」と著者が分類する怪談群を紹介します。インターネットの怪談でいえば「八尺様」「アクロバティックサラサラ」なども有名で、最近では「窓から首ヒョコヒョコ女」などという話もあります。著者は、「いうまでもなく、これらはすべて女性の怪人たちである(カシマだけは過去に男タイプもあったのだが、そちらは時とともに駆逐された)。彼女たちの多くは赤い服を着ているか、血にまみれた『赤い女』だ。白い服の場合もあるのだが、その理由も後で説明する。そして体に傷を負っていたり、程度の差はあれど異様な高身長であるケースが多い。またその名前を聞いたり、彼女についての話を知ると、自分のところに彼女たちがやってくる、との特徴があったりもする」と述べています。
著者の脳内には、ある予感がこだまするといいます。現代怪談にちょくちょく登場する「赤い女」たちはバラバラに存在しているのではなく、一人の同じ女ではないのかという予感です。著者は、「私はこうした『赤い女』が本当に実在するかどうかとの真偽を問う気はいっさいない。ともかくここでは、都市伝説にせよネット怪談にせよ実話怪談にせよ、『赤い女』にまつわる言説や体験談が、現代日本にそれなりに広く流布している、という事情だけ伝わればよい。そして私が彼女ら『赤い女』たちに惹かれる理由も、だんだん判明してきた。この『赤い女』もまた、現代怪談における『子殺し』から発生してきたものだからだ。つまり『赤い女』とは、『子殺しの母』のイメージが投影された存在なのだ」と述べます。
日本の近代化とともに、怪談の質が変わりました。その変質の根本には「子殺し」への恐怖が渦巻いており、「子殺しの母」のイメージがちらついていたのではないかと推測する著者は、「戦後から高度経済成長期にかけて、怪談と恐怖の文化はどのように発展したか。水木しげるや楳図かずお、稲川淳二らの『恐怖』の出発点もまた『子殺し』『子殺しの母』だったのではないか。そしてオカルトブームが巻き起こったとされる1970年代は、また同時に『子殺し』『子殺しの母』という言説が盛んに議論された時期でもあった。『口裂け女』とともに70年代は終わり、『今田勇子』とともに80年代が終わる。バブル崩壊から現在まで続く経済不況の時代は、しかし同時に、怪談文化が花開く時代でもあった」と述べるのでした。
2「こんな晩」では、日本において「子殺し」怪談が本格的に語られるようになったのは明治近代に入ってからだとして、著者は「明治20年代初頭、新生児を殺す様子を描いた『間引き絵馬』に戦慄した少年時の記憶が、後の柳田國男の農政学・民俗学へと続く経歴に影響したのだろうか」と述べます。ただどの時世においても、流産死産および乳幼児死亡率は我々の常識より圧倒的に高く、子供の成長前の死亡は珍しくありませんでした。「七つまでは神のうち」という有名なフレーズどおり、多産と多死の中で、乳幼児たちの命は「授かりもの」であり、死ぬのはもと来た場所へ「カエル」ことであったのです。
著者は、「こちら側に寄せては(生まれては)あちら側へと返し(死に)また寄せる(生まれる)波のような移ろう存在と見なされていた。埋葬も簡単に済ませたし、むしろ丁寧に葬ると再び生まれ変わってこないとまで考えられた。だから出産直後の赤子を殺す『間引き』は、『子返し』『カエス』とも呼ばれ、バースコントロールの一方法として行われた。もちろん罪悪感がなかったわけではない。ただし飢饉などの極限状態だけではなく、もっと緩やかな経済的事情や、男ではなく女が生まれたから、などの理由でも殺された。当時の医療技術からして、出産後の処置の方が、堕胎するよりもずっと母体に安全だったとの理由もある。その場合、新生児を殺すのは取り上げ婆(産婆)が多かった。臼を使って押し殺す、菰にくるんで川へ流すなどしていようだ」と述べています。
ただし間引き絵馬の場合、「子殺し」を行うのは産婆ではなく、分娩直後の母親ばかりだとして、著者は「首を絞めている時もあれば、立て膝による圧殺も多い。これは当時主流だった座産の姿勢のまま、『産む』行為の直後に『死なせる』行為へとタイムラグなしに移る場面を表している。啓蒙広告なので実情をそのまま反映しているかは疑わしいものの、こうした図像から当時の感覚をうかがうことはできる。すなわち、『産』と『死』は分断されておらずシームレスに繋がっている。それぞれは『生命を授かる』という1つの現象の異なる側面を見せているに過ぎない。そして産婦である母親は、『死』の側面についてもある程度は主体的に関わっている。つまり現代人の感覚と同じニュアンスでの『子殺し』とは捉えていない。なにも幼年期を超えて人間となった我が子を殺しているのではないのだから」と述べます。
さらに、著者は以下のように述べています。
「現代怪談へ繋がっていく端緒――仮に『近代怪談』とでも呼ぼうか――は、やはり自身の根源を脅かすような恐怖としての『子殺し』を語るところから始まったはずだ。怪談史の近現代とそれ以前は、どこで区切られるのか。この分岐点を、私はラフカディオ・ハーンの怪談に求めたいと思う。西洋から来て、アンチ西洋文化めいた視線を持ちながら日本を見つめた小泉八雲の仕事に。より精密に言うなら、彼が小泉節子(セツ)と結婚し、日本の怪談を取材しはじめた1891(明治24)年の、とある夏の盆の月夜に」
ハーンが日本の怪談を採集・記述しはじめた様子は『知られぬ日本の面影』(1984年)に記されていますが、その中に「持田の百姓」という六部殺しの話があります。著者は、「近世から近代にかけて、日本各地の農村では、裕福な家に対して次のような噂がよくささやかれていた。あの家が成功したのは、昔、一宿を求めてきた旅の六部を殺して金品を奪い、それを元手に財を成したからだ……と。六部とは諸国を巡礼する僧なので、旅費としてそれなりの金銭を持っていただろう。また共同体の外から来た六部ならば、殺して死体を隠蔽すれば、誰にも悪事を気づかれることはない。たとえ同じ村の人々に怪しまれたとしても、決定的証拠など出てきようがないのだ。とはいえ、もちろん日本全国の金持ち一家が、こぞって六部を殺していたはずがない。証拠のない殺人事件とはむしろ、外部の人々がありもしない悪事を噂するためのエクスキューズである」と述べています。
つまり「六部殺し」とは、成功者に対するやっかみのゴシップとして機能していたのです。貨幣経済の流入にうまく対応できた新興の大農家が、よくその標的になってしまったのです。また多くの場合、殺された六部は殺人者の子として転生し、親の罪を暴き、断罪するとして、著者は「溺愛する自分の赤ん坊や幼児が、ある日いきなり、告発の言葉を投げつけてくるのだ。『お前が俺を殺したのは、ちょうどこんな晩だったな……』と。いわば因果応報の教訓話でもある。そのため『こんな晩』という題で分類されることもある同型の話は、宗教者たちの唱導説話を通じて、近世に各地へ広まっていったとも考えられる。ただし元々あった金持ちへのゴシップ譚に、後から因果応報の怪談要素が付け足されたのではなく、初めからこうしたオチありきの物語構造だったと考えるべきだろう。なぜなら『六部殺し』伝承は、古くは9世紀から中国に伝わる『討債鬼故事』が輸入されたもののようだからだ」と述べます。
また著者は、「私という個人の存在が揺さぶられる脅威でいえば、やはり『六部殺し』に材をとった夏目漱石『夢十夜』(1908)第三夜を思い出す。ただ、あの幻想譚と『持田の百姓』とでは、なにに恐怖するかの視点・ポイントが決定的に異なっている。私という存在のありようが否定され、だからこそ私が最も恐れること。それは我が子を殺すことだ。近代人であるハーンや現代人である我々は、子殺しこそが人間存在の全否定にあたるような究極の罪だと考える。全面的に愛すべき・庇護すべき存在を排除してしまう、まぎれもない絶対悪の行動だ、と」と述べています。
ただ近世以前の人間は、少なくとも新生児の間引きについては、そこまでの重罪とは考えていなかったと指摘し、著者は「出産直後の赤子を殺すことは、出来れば避けるべき悪事には違いないが、生活のための仕方ないバースコントロールとも捉えていただろう。私たち現代人が21週までの胎児の中絶手術をすることと、それほど意識の差はなかったはずだ。母に庇護されるべき子供を殺す、という恐怖。それが高まれば高まるほど、裏返しに『子殺しの母』という恐怖イメージが形成されていく。なにしろ人間は、自分が最も恐れるものを想像してしまうものだから。『母性神話』と表裏一帯の『子殺し怪談』。それはハーン版『水飴を買う女』からの『持田の百姓』において、日本で初めてストレートかつ端的に提示された。だからこの話は、現代怪談へと続く『近代怪談』の嚆矢と見てもよいだろう」と述べるのでした。
3「ザシキワラシ」の冒頭を、著者は「日本では昔から、親の累が子に及ぶ因果応報譚がいくつもある。だが、それらの多くは、愛すべき大切な子供が亡くなる恐怖に根ざした物語とは限らなかっただろう。たとえば『日本霊異記』『今昔物語集』の行基の説話における『子殺し』は、むしろ悪しき因縁を断つための解決策であり、まったく非道な行為として描かれてはいない。つまり『子殺し』にそれほど重きを置く感覚はなかった。もちろん時代が進むにつれ、このような意識に変化が生じ、明治・大正となると『持田の百姓』の他にも、『こんな晩』と子殺しが結びつくような話がいくつか登場するようになっていく」と書きだしています。
家に利益をもたらした存在が、まったくの外部から来た異人を殺害したのが近世の「六部殺し」であり、それに反して、まさにその家に生まれた子供を殺すことで利益がもたらされたとの発想が、日本でもある時期から見られるようになっていくと指摘し、著者は「そのもっとも明確な例は、ザシキワラシについての、ある仮説だ。ザシキワラシは、現代日本では全国どこでも現れる「福をもたらす子供の霊」として扱われるが、元来は岩手県を中心にした東北地方ローカルの妖怪/怪談である」と述べています。まず、柳田國男『遠野物語』(自費出版、1910)にてザシキワラシが「紹介」されたのは周知のとおりです。
その『遠野物語』の話者を務めた佐々木喜善も、10年後に『奥州のザシキワラシの話』(玄文社、1920)を刊行しています。佐々木は同書にて、ザシキワラシの正体は間引きにより殺され、床下に埋められた子供(=若葉の霊魂)の場合もある、との仮説を述べました。南方熊楠は、この説をさらに広い地域に敷衍するかのような見解を『人柱の話』(『変態心理』第一六巻三号、1925)で表明。折口信夫もまた『座敷小僧の話』(『旅と伝説』七巻一号、1934)で六部殺しとも絡め、『若葉の霊』とザシキワラシの関係を示しています。柳田國男、南方熊楠、折口信夫という日本民俗学の草創期における三大巨人がいずれもザシキワラシに関心を示していたわけです。
間引きや堕胎や捨て子は、昔の日本でも良きことではなかったにせよ、現代人が想像するほどには罪悪感をひきずりもせず、悪事としての衝撃性もなかったことを指摘し、著者は「つまりいちいち特定の怪談が生成され、語り継がれるほどの大事ではなかった。あるいは怪談が生成されるには、一定のタイムラグが必要とされるせいもある。江戸後期に行われていたような間引きは、維新から時を経るにつれて姿を消していく。そのような時代になって初めて、時をさかのぼって間引きを怪談に仕立て上げようとするメカニズムが動き出す。とはいえ明治には『継子いじめ』が、大正には『母子心中』が、昭和の戦前戦後にかけては『貰い子殺人』が……というように、どの時代にもさまざまなタイプの『子殺し』現象は存在した。しかしそれらの事件が熱く社会問題化している最中に怪談化することはあまりない。間引き子の霊が着目されたのは明治であり、継子いじめ譚『継母の化け物』が広まったのはおそらく明治末から大正にかけて、そして貰い子殺し事件の『西郷山』が怪談となったのは1950年代で……。というように時が経ち、世相が移り変わったところで、過去の『子殺し』にまつわる怪談が生まれてくるものなのだ」
「現代怪談の最前線①歩く死体を追いかけろ!」では、「歩く死体」の物語が取り上げられます。いくら死体を遺棄しても、眠りから覚めたら傍らに死体があったという怪談で、日本では1980年代半ば頃から「実話怪談」ではなく「都市伝説」として、細々と若者たちに囁かれていたようです。90年代に入ると、テレビ番組『世にも奇妙な物語』の一篇「歩く死体」(1991年3月14日放送)として実写ドラマ化されました。同回は好評だったようで、その後の映画版でも「雪山」としてリメイクされました。雪山に墜落した飛行機事故の遭難者たちが体験する一夜、という筋立てです。著者は、「同じ雪山の都市伝説『スクエア』が組み合わされていたり、どんでん返しのラストがあったり、なかなか凝った構成の秀作である。ここにおいて『歩く死体』を主題としたストーリーテリングは、完成の域にまで達したといえよう」と述べています。
「歩く死体」の話は日本だけでなく世界中で語られましたが、その下敷きになったのはポーランドのノーベル賞作家ヘンリク・シェンケヴィチの代表作である小説『クオ・ヴァディス』(1896年)のようです。この中には古代ローマの聖ペトロが「死んだはずの人間と再会する」話が紹介されています。著者は、「この話が人々を惹きつけるポイントは、おどろおどろしい怪奇色や、謎解きミステリーめいたオチではない。隠したはずの罪が、死者=超越的な視線によって暴かれてしまう恐怖にこそあるのだ。その点は、キリスト教に馴染みの薄い日本人にしても変わらない。『お天道様』や『閻魔大王』『三尸の虫』に悪行を見抜かれるという罪の意識、たとえ他人に目撃されずとも超越者の眼差しを気にしてしまう心情は、じゅうぶん理解できるものだからだ。『歩く死体』においては、神様・お天道様の視線が『無意識』にとってかわっている。ここで罪を暴くのは神ではなく、無意識の中にいる「自分の知らない自分」である。1890年前後といえば、ようやくフロイトが精神分析治療を行いだした時代。しかし当時、けっして都会とはいえないニューヨーク州の山間の街でさえ、すでにこのような都市伝説がささやかれていたのだ」と述べています。
「歩く死体」のストーリーには、「無意識」とは別にもう1つ罪を暴くものがいることを指摘し、著者は「なにしろ罪人と裁判官を一人二役で行っているのだから、真相解明にはもう一つ別の『他者の視線』が必要だ。言わずもがな、客観的記録を残すための諸々のツールである。それはテクノロジーの進化にともない、手書きのメモから写真機、そしてビデオカメラへと変遷していった。『自分』の罪を暴く『自分の知らない自分』。そんな『自分の知らない自分』の行為を暴く『記録媒体』……。どこまでも追いかけてくる『他者の視線』からは、もはや逃れようがない。ここで再び、『歩く死体』の語られた時期に注目しよう。1960年代に一部で知られていたこの都市伝説が、また復活し広まっていったのは、1980年代後半だった。当時の日本では世界に先駆け、家庭用ビデオカメラが普及しはじめていたのである」と述べるのでした。
「怪談の深層に眠るもの『子殺し』怪談 section2」の4「現代怪談の幕開け」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「『現代怪談』のスタート地点をどこにするかは、いくつかの考え方があるはずだ。まずは平成改元の後、1990年代の始まりに置いてみるのが、わかりやすくはあるかもしれない。1990年には扶桑社版『新・耳・袋』が刊行、1991年には『「超」怖い話』シリーズが開始している。文学史・芸能史における『怪談実話』の枠組みの中から、『実話怪談』がジャンルとして胎動してきた時期なのだ。それはまた、J・H・ブルンヴァン『消えるヒッチハイカー』(新宿書房、1988)や、常光徹『学校の怪談』(講談社、1990)が刊行されたタイミングでもある。両書ともシリーズ続刊を順調に重ね、『都市伝説』および『学校の怪談』という枠組みが日本に完全に定着していった」
現代では「児童虐待」の一形態にあたる「継子いじめ」が、はたして江戸時代より明治以降にこそ増加・悪質化したかどうか。この問題について、著者は「私の浅薄な知識では断定しかねる。とはいえ明治期、武士階層に限られていた『家父長的家制度』が戸籍制度とともに国民全体に広まり、いわゆる『近代家族』が形成され、義親・継子関係が近世とは異なる状況に置かれたこと。あるいはもっと単純に、工業化の進んだ都市部において共同体の連携が緩み、児童虐待が隠蔽されやすかったことなどは想像に難くない。少なくとも昔話で語られるものとは様相の違う『継子いじめ』譚が、当時の大メディアたる新聞を通じ、一種のメロドラマとして大衆の耳目を集めていたことは確かだ」と述べています。
「継子いじめ」からやや遅れ、大正末年頃~昭和初期にかけて大きく社会問題化するのが「親子心中」です。覗きからくりの中でも口上資料が残っている演目、つまり覗きからくり最終期の演目を眺めてみれば、やはり「継子殺し」と「親子心中」のテーマが多く目立つとして、著者は「1931(昭和6)年、柳田國男は『明治大正史 世相篇』にて、明治以降、『家』が『親子』だけに小規模化され大量生産されたありようを分析していく。それに伴う親子関係の変化から、『この頃頻々たる親子心中の報道』を嘆きつつ、『これとても慈愛の遣瀬ない一破綻とも見られる』と同情も示す」と述べます。
恋人同士の同意による心中ならまだしも、我が子を道連れにする「親子心中」はまぎれもない殺人であり、「子殺し」に他ならないとして、著者は「血の繋がらない継子をいじめ抜いて殺すのと、我が子を執着から自殺に連帯させるのは、真逆のようであっても同じコインの裏表だ。それはつまり、親と子の『一体化』である。私という存在と、子の存在が不可分に癒着する(と幻想する)。だからこそ我が子でない子供は非情に殺害し、我が子は自身の命の終焉に付き合ってもらわなければならない。ハーンが『持田の百姓』に覚えた、自らのアイデンティティを揺るがす『子殺し』の恐怖は、日本人にもすっかり根付いたのだろう。とはいえそれは『子殺し』の根絶ではなく、間引きとはまた異なるタイプの『子殺し』事件(=親子心中)への変換を意味していたのだが。そして戦後、稲川の母は息子たち兄弟への寝物語に、『継母の化け物』を語った」と述べます。
5「夕焼けの人さらい」では、「貰い子殺し」が取り上げられます。明治から戦中まで、国民国家形成・富国強兵を目指す日本では国民の生殖管理を重視、間引きはもちろん堕胎=人工中絶の取り締まりも厳重化していきます。「堕胎罪」は1880(明治13)年に旧刑法、1907(明治40)年には現刑法として制定。さらに1929年の昭和恐慌が追い討ちをかけるかたちで、子を出産するも育てられないという社会状況が悪化すしました。著者は、「自宅分娩が主流の中、貧困層や私生児の出産が集中した民間の「産院」では、養育を見込めない、または遺棄された乳児が多数集まった。その対策として行われたのが「貰い子斡旋」だったが、これもまた悪用されてしまう。養育料のみを詐取した後、引き取った乳幼児を虐待死または直接に役害するものたちが現れたのだ」と述べています。
1930(昭和5)年、乳幼児41人が殺害されたという「板橋貰い子殺し事件」(岩の坂事件とも)が世間の注目を集めました。事件を受け、東京府産婆会による組織だった貰い子斡旋が行われるようになったのですが、悲劇はまだ続いていきました。それが「西郷山の貰い子殺し事件」です。ところで、戦前に「殺人者の男」だったものが、戦後に「人さらいの女」になるという転換が起こりました。この転換は、この後、日本全体で発生したと指摘し、著者は「戦前までいた人さらいの『赤マント』は、戦後、高度経済成長期を経て、子供を襲うヘビ女、カシマ、口裂け女その他へと連なる『赤い女』へ姿を変えたではないか」と述べます。
稲川淳二が「西郷山の貰い子殺し事件」を語る短い思い出話の中には、非常に多くの要素がちりばめられているといいます。そしてこの怪談を語る時、必ず最初に地形を説明する稲川のセンスはさすがだとして、著者は「西郷邸のような高級住宅が並ぶ高台と、いきなり断層の下へと落ちこむ目黒川と渋谷川。こうしたアップダウンの激しい立地は、そのまま高低の激しい社会格差を象徴する。高級住宅地のお屋敷で自宅分娩できる女性と、自ら産んだ赤子と離れ離れにならざるを得ない女性。その背景が貰い子殺し事件へ、そして西郷山の怪談へと結びついていく」と述べています。
稲川淳二は、母親から「貰い子殺し」の怪談を聴きました。稲川の母親たちは、犯人である川俣ではなく、やむなくではあるが我が子を棄てた(そして結果的に死なせることになった)母親たちの方をこそ、化け物としてイメージしました。人さらいとして、子殺しの犯人として、真っ赤な夕焼けとともに現れる女として語り直したのです。著者は、「そのイメージは後に、コインロッカーベイビー事件にて『母性崩壊』を糾弾される母親たちとも重ねられた。そしてカシマさんや口裂け女となり、アクロバティックサラサラとなった。『赤い女』は、1950年代半ばの、真っ赤な夕焼けの中から生まれたのだ」と述べます。
戦後、稲川少年たちが西郷山で遊んでいた時期であろう1954年(昭和29年)、親から棄てられ殺されたはずの子どもが甦るというストーリーの紙芝居が、戦争帰りの男によって描かれはじめました。著者は、「男の名は水木しげる、キャラクターの名は『鬼太郎』である。いつも目玉に体のはえた父親だけが傍にいる、母なし子のヒーローだ。生まれてすぐに母親から引き離され、西郷山に埋められた赤子たちは、ふたたび空を見上げることはなかった。しかし同年、彼らの怨念を背負うかのように土中からはいでた『ハカバキタロー(墓場奇太郎)』は、後に現代妖怪文化のシンボル『ゲゲゲの鬼太郎』へとのぼりつめる」と述べます。
「〈付1〉赤い女前史」では、重要な存在っとして「ウブメ」が取り上げられます。妊娠中あるいは難産で死んだ女性は「産女」となって化けて出ます。著者は、「つまり子を産めずに亡くなった、母になれなかった母の霊であり、女・性・子・産・死がメビウスの輪のようにねじれて繋がる複雑さを持つ。昔から各地にさまざまな伝承が残るが、特に近世から現代においては日本の幽霊・妖怪の中でも特権的な扱われ方をしている」と説明します。また、「昔の日本では、新生児の霊が一個の人格としてクローズアップされることはないのだ。とはいえ『子育て幽霊』『飴買い幽霊』と同一視される場合(たとえば『奇異雑談集』など)では子だけが生き延びており、高名な僧になった後日談などが語られる。中国の古典籍に出て来る子をさらう鳥『姑獲鳥』が日本に伝わり、近世以降、産女と同一視されるようになったことも有名だ。夜に干してある子どもの服があれば、”血”をつけて印とし、その子を取っていくのだという」と述べます。
また、著者は「赤い女」の赤という色について考察します。5~7世紀頃の日本での喪服は「白」であした。平安時代より上流階級の喪服はいったん「黒」に傾きますが、また室町時代から明治まで「白」に回帰します。日本人にとって「白」はずっと、死や異界に近く、神聖にして穢れなき色だったのです。「剣巻」成立時には百度参りの作法もあったので、神への正式な祈願には「白装束」という常識はあったと推察されます。「丑の刻参り(時参り)」という儀式は、江戸時代の人も現代人も、白装束で行うイメージを持っています。お百度参りなど神への願掛けに際しては、精進潔斎してのぞむものだからです。しかし、この儀式の開祖である橋姫は、おそらく意図的に神の指示に逆らい、「白」ではなく「赤」で身を包みました。著者は、「だから本来あの儀式は、白装束ではなく赤装束で行うべきなのだ」と述べるのでした。
6「口裂けの系譜」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「怖ろしい女のイメージといえば、日本では昔から『口の裂けた女』が定番として登場します。狼や蛇のような大きな口は最もわかりやすい怪物アイコンであり、それが『女』に付与されると鬼女や山姥になる。『橋姫』は宇治川に浸かる前から、顔も体も真っ赤に塗り、鉄輪や松明を装着した時点で、すでに本物の鬼そのものとなった。吉崎御坊『嫁おどし肉付きの面』もそうだが、鬼の仮装をした女たちは、仮装だけのつもりであっても、ついには心身ともに鬼へ変化してしまうのだ。怪物化の行き着く先はどこか。能の演目『鉄輪』『葵上』『道成寺』『黒塚』では、嫉妬や怒りに狂う女たちの顔は、口の裂けた『般若』の面で表される。そして『般若』をさらに怪物化したものが『真蛇』。もはや耳も消え(”聞く耳もたず”の象徴)、無情な瞳と般若以上に大きな口が強調される。口の裂けた女の最終形態は、鬼より非人間的な『蛇』なのかもしれない」と述べています。
ここで、著者は漫画家・楳図かずおが1961年~1968年に発表した「ヘビ女」ものの連作を取り上げます。「ヘビ女」シリーズ各話はパターンがおおよそ決まっており、(1)継母であるヘビ女が、継子である主人公への子殺し(or子喰い)を目論む。(2)継母は元は人間だが、精神異常や悪意から、ヘビ女の仮装をして主人公を脅すうち、本当の怪物へと変化してしまう。彼女たちもまた、苦しい情念に心を病み、怪物の仮装をしながら、本物の蛇(鬼)となった女なのだと紹介し、著者は「『ヘビ女』シリーズは、貸本マンガから大手マンガ雑誌へと転身するタイミングの楳図の出世作である。ただそれだけでなく、日本における『恐怖マンガ』の元祖と捉えてもよい」と述べます。
著者によれば、1961年の「口が耳までさける時」において、楳図自身が本作を宣伝するにあたり、それまで「怪奇」と呼ばれたジャンルと区別するため「恐怖マンガ」の呼称を発案したのだといいます。「幻想と怪奇」ではなく、より怪談めいた「ゾッとする恐怖」へ。著者は、「ともかく、母の大きく裂けた口は、そのまま子供を呑みこもうとしている。月並みな例えだが、膣から出た子をまた膣へと取り込もうとする怖ろしい母、再び子宮の中で我が子を孕みなおそうとするユング的『太母(グレート・マザー)』を重ねることも可能だろう」と述べています。
「現代怪談の最前線②牛の首」では、星野之宣『宗像教授伝奇考』の一篇「贄の木」が取り上げられます。丹波山地の某村では昔、「猪の頭」をかぶった神事が行われていたといいます。しかし現代の村人たちは、その歴史についてなぜか口をつぐみ、語りたがらない様子。物語が進み、主人公・宗像教授が調査を重ねるにつれ、隠された闇の歴史が明かされていくのでした。著者は、「かつて飢饉に苦しんだ村の祖先たちは、人肉を食らうことで命を繋いでいたのである。その際、少しでも罪悪感を減らそうと、猪の頭をかぶせた人間を狩り、死体を猪の肉として扱っていた。これこそが、封印された儀礼の正体だったのだ……。というのは、もちろん作者・星野之宣による創作である。しかしこの話が、いつしかれっきとした事実として扱われ、『牛の首』に紐付けられていくようになる」と述べています。わたしは、この話から「鬼滅の刃」の嘴平伊之助を連想しました。
「怪談の深層に眠るもの『子殺し』怪談 section3」の7「子殺しの罪と罰――コインロッカーベイビーとしての『コトリバコ』」では、日本初のコインロッカーが新宿駅地下に設置されたのが1964年12月であることが紹介されます。それから数年後、生まれてすぐの新生児を駅のロッカーに遺棄してしまうコインロッカーベイビー事件が連続することとなります。(68年にも1件あったものの)70年に渋谷駅コインロッカーで嬰児が捨てられていた事件を皮切りに、渋谷駅、新宿駅、大阪駅などのターミナル駅で同様の手口が多発。特に、それまで一桁台で推移していた年間件数が46件へと激増した1973年の前後は、大きな社会問題として扱われました。著者は、「当時のマスコミは、これを『母性崩壊』の象徴と受け取った。現代の母親は、自然と女性に備わっているはずの、我が子を無条件かつ絶対的に愛するという本能および精神=『母性』が崩壊(喪失)している――といった論調が過熱していったのだ」と述べています。
1960年代、ベビーブーマーの進学に伴って誕生した「教育ママ」という概念は、70年代に入っても引き継がれたと指摘し、著者は「立身出世のための学歴志向はむしろ加速し、受験対策のための大手進学塾が普及したのも70年代だ。外で働く父親、子供の世話と勉強を担当する母親、といった二極化の進行は、そのまま大正期から問題視され始めた『母子一体化』の進行でもあった。となれば必然的に『母性信仰』は肥大化していかざるをえない。こうした傾向はついに、母子関係が子供の病気や身体能力の根本原因でもあるという『母原病』なる疑似科学にまで行きつく。その後の反動や修正はあるにせよ、『母性信仰』神話は基本的に現代日本社会へと引き継がれている、と私は感じている」と述べます。
70年代前半の「母性崩壊」は、肥大化する「母性信仰」に伴って生じた言説であると指摘する著者は、「こうした時代状況を鑑みれば、むしろコインロッカーベイビー事件が世間の注目を集めないはずがないとすら言える。さらに1970年代は『オカルトブーム』に象徴されるように、霊的・精神的なものに注目が集まったタイミングでもあった。中絶した胎児を供養しなければ、さまざまな祟りにあう、と提唱する現代版『水子供養』もまた同じ文脈で捉えられるだろう。埼玉県秩父に紫雲山地蔵寺が開山したのが1971年。大がかりな商業的成功もあり、70年代半ばから80年代にかけて『水子供養』は多くの寺へと広がり、時ならぬ水子ブームとなる。『子殺し』の罪と罰は、ついに子宮内の胎児にまで及んだのだ」と述べます。
続いて、著者は「コトリバコ」に言及します。コトリバコが隠岐から伝わったという明治元年は「産婆取締規則」が制定され、産婆による堕胎が禁じられた年です。もちろんその法的効果は地方まで充分に及ばなかったものの、なんら制限がかからなかった訳でもありません。そして島根エリア(というより西日本)では江戸時代から、間引きではなく堕胎処置の方がメインだったとして、著者は「コトリバコのために殺していたのは出産直後の嬰児だけではなく『7歳まで』『10歳まで』の幼児・少年だったというのだが、これは間引きとはまったく異なる事態で、当時の常識からしても重大な殺人行為だ。これらの子を『口減らし』するなら奉公や養子に出せばよく、実際、そうしたことは江戸でも明治でも日本各地で一般的に行われていた」と述べています。
8「欠損する下半身の意味するもの――カシマさん」では、カシマという女怪人の出現は、現代怪談史における最重要トピックであるとして、著者は「『子殺し』のテーマを背負う現代怪談において、さまざまなキャラクターとして表現されてきた口裂け女、ひきこさん、八尺様などの『子殺しの母』=『赤い女』たち。その遠い源流は『ウブメ』や『橋姫』だとしても、70年代以降、次々に生まれた彼女たちの直系に連なる開祖、まさに赤い女たちのビッグ・マザーこそが、『カシマ』だからである」と述べます。
カシマはほぼ必ず、片足か両足を失った女の霊とされます。そのルーツは「下半身欠損伝説」かと思われるが、この噂が70年代初期にはカシマを産み、80年代初期に「テケテケ」系の怪談(旭川の「シャカシャカ」など)に繋がったと思われるとして、著者は「カシマもテケテケも、発生初期においては男パターンが混在してはいるものの、やはり時間経過につれて女パターンが圧倒的優位となる。下半身を失うのは、いつも女ばかりだ。この場合の下半身の欠損とは、つまり子宮と膣の欠損である。堕胎や産褥死あるいは妊娠中の死といった、間引きの一歩手前の『子を産めなかった女』の死へと繋がる。イメージを遡れば、下半身が『真っ赤』な血まみれのウブメ、あるいは火の神カグツチを産んだ際に女陰を――おそらく『真っ赤』に――焼かれて死んだイザナミへと辿り着く」と述べるのでした。
「現代怪談の最前線③人面犬」では、人間の顔をした犬という人面犬伝説の誕生について、著者は「深夜ラジオや若者雑誌といった『投稿』による参加型メディアは、インターネット以前の時代におけるサブカルチャー形成を担っていた。特に血気盛んだった若者雑誌では、編集部←→読者投稿のインタラクティブな誌面づくりへの熱が高まっていた。そうした流れと相性がよく、人気も獲得しやすかったのは、怖くて怪しげな噂の類。雑誌編集者たちは、若者・子供たち独自の文化圏で流通するネタを『噂(うわさ・ウワサ)』といった呼称でカテゴライズ。一般名詞としての『噂』とはやや異なるニュアンスで(今の「都市伝説」に近いノリで)扱っていたのである」と述べています。
「怪談の深層に眠るもの『子殺し』怪談 section4」の9「『大流行』以前の口裂け女」では、1970年代後半(75年以降)には日本各地に広まっていた口裂け女の噂の出所として、「精神病院からの脱走患者」説が紹介されます。この説は、79年「大流行」前の日本各地で広くささやかれていた設定ですが、特に発祥地の岐阜県ではこの噂が根強く、具体的な病院名が出ることも多いことを指摘し、著者は「やはり『大流行』前の口裂け女は都市中心部ではなく郊外、特に山を切り開いたニュータウンで流行していたのだ。都心では忌避される精神病院が建設されるのも、その近隣に接するかたちで子供を含めたファミリー層が入居するのも、まさに山林を開発した新興住宅地だったからである」と述べています。
日本の精神病床数の多さ、長期入院の割合は、ともに世界でも群を抜いていることは周知のとおりであるとして、著者は「呉秀三らの提言によってかねてより問題視されていた『私宅監置』が禁じられ、精神衛生法の施工、入院措置への移行がなされたのが1950年。そして1950年代~70年代にかけて日本の精神病床数は激増し、口裂け女『大流行』の79年に30万床に到達して以来、現在まで同規模水準を維持している。この状況が高止まりで固定されたのが、まさに1970年代後半だったのだ」と説明します。
10「変容する口裂け女」では、口裂け女の噂とは、人々の恐怖や願望を反映し、ものすごいスピードで変化してしまうものである点を強調する著者は、「たとえば60年代の山姥めいた『子供をさらい、子を喰らう口の裂けた女』の噂であれば、秋山の深層心理学的な分析や、(これも木下が批判する)民俗学的視点も、それなりに妥当な視座として適用できるだろう。しかしそこからイメージがどんどん流転する。飯能や名古屋で流れた口紅メーキャップによるイタズラ説、やや遅れて登場した『精神病院の脱走患者』説、その他、多種多様なローカルの噂が生まれつつ、79年『大流行』時の過熱報道によるキャラクター化へ……。口裂け女は、わずかな時期・場所の違いにより、さまざまなイメージが仮託され、万華鏡のごとく変化する存在だったのである」と述べています。
結局のところ、我々は「母性」のネガティブな表れを期待し、「子殺しの母」の恐怖を求めているのだとして、著者は「ユング心理学における太母(グレート・マザー)といったような、手垢のついた説明概念によりかからずとも、こうしたイメージが世間にありふれていることは、現代のあらゆる娯楽作品のストーリー展開を見れば明らかだ。近年のアメリカで製作される娯楽映像作品を例に挙げるのが、最もわかりやすいだろう。映画やドラマに出てくる『敵』『乗り越えるべき障』」の多くが、象徴的な役割としての『子殺しの母』『子殺しの父』であり、この父母を(象徴的に)殺す解決こそが物語のカタルシスとなる」と述べます。
現代人にとっての最大の恐怖は、子供が死ぬこと、子供が殺されること。だから「子殺しの親」こそが敵・障害の典型となるとして、著者は「あるいはもっと広くとって、『子の成長を拒否する親』までを範囲とすれば、より伝わりやすいだろうか。これと匹敵する絶対悪は『不老不死』しかないが、結局のところ『不老不死』『子の成長の拒否』『子殺し』はいずれも同根の悪なのである。そして日本ではアメリカほど『子殺しの父』の存在が大きくないので、代わりに「子殺しの母」がクローズアップされる。とりあえず、近年の日本ホラー文化を代表する作品として澤村伊智『ぼぎわんが、来る』(2015)を挙げておくが、他にも『子殺しの母』がモチーフとなるホラー作品は枚挙に暇がない」と述べるのでした。
11「潜伏するカシマ・ウイルス」では、70年代後半という時代は、怪談や恐怖にもこうしたリアリティを求める時代だったのだと指摘し、著者は「それは当時のオカルトブームの諸相を眺めてみれば明らかで、『ネッシー』『UFO』『超能力』そして『心霊』などへの注目は、けっして脱・科学としての、オルタナティブとしての『霊性文化』そのものへの注目ではなかった。あくまで『それまで非科学的・オカルトと考えられていた事象が、実は科学的に(定量的に/映像的に/再現可能な/データを明示できるかたちで)証明できるかもしれない』というその期待が寄せられたのであり、どこまでも近代自然科学の枠組みの中での、オカルト的事象の再設定の試みに過ぎなかったのだ」と述べています。
また、著者は以下のようにも述べています。
「ネッシー探索とは『ケルト文化における水の精霊への信仰を見直そう』といった発想ではけっしてはなく、『ネス湖に巨大生物が棲息しているか調査し、実物を発見するか映像におさめよう』というひたすら現実的なチャレンジだった。心霊写真とはまさしく、霊体が物質として存在すること、観測可能であると証明するための手段だった。だから霊が物理的に存在するかにこだわらない、一回性の個人体験を重視する『実話怪談』は、『心霊』と『都市伝説』から決別することでジャンルを確立した」と述べます。
その初期においては男女が並列され中性的だったカシマは、1999年にネットで提示されてからスタンダードとなった「鹿島さん」では、性的な面が強調されることとなると指摘し、著者は「下半身の欠如はレイプされ壊された膣と結びつく。男たちに犯されて妊娠した可能性を残したまま、彼女は殺されるのではなく、自死を選ぶ。米兵の銃弾に撃たれたまま死んだとしても、昔ながらの怨霊譚としては成立したはずだろう。しかし彼女は手足を切断しながらもみごとに生き延び、自分の意志によって自殺しなくてはいけなかった。そうでなくては母子心中による「子殺しの母」になれないからだ。『鹿島さん』という物語は、ネット怪談の普及発展と足並みを揃えて広まっていった。そして『鹿島さん』の直系にあたる『子殺しの母』たちが生まれていく」と述べます。
「現代怪談の最前線④岐阜ポルターガイスト団地」では、2000年に全国的な話題となった岐阜の団地でポルターガイスト現象が起きたという騒ぎについて、著者は「意外に思われるかもしれないが、私をふくめ現在の『怪談』文化に携わる人間は、霊的な事象の実在を証明せんとする『心霊』とはスタンスが異なる。『怪談』界隈の人々は、『心霊』に対してやや醒めた距離感で臨んでいる場合がほとんどだ。私は『怪談』を生業とし『怪談』そのものに興味を持つ人間なので、科学の立場から心霊現象の有無を問う人々とは別の立場で動いている。幽霊や祟りが『あるかないか』つまり『自然科学として実証可能であるかないか』を問うのは、私の仕事ではない。ひたすら怪しい談(はなし)を聞き、それを談(かた)る人々の方に思いを巡らせるだけだ」と述べています。
1995年のオウム事件ショックは、メディア全体にオカルト・アレルギーをひき起こしました。著者は、「事件前、あの団体をさんざん面白おかしく取り上げていたことの反動から、オカルト全般に対する強烈な自粛ムードが、しばらく世の中を覆っていた。我々の日常会話・世間話においても、よほど気安い仲でなければ、宗教や心霊にまつわる話題がためらわれるような空気感だった。少なくとも私個人は、そのように記憶している」と述べます。2000年とは、ようやく過敏なオカルト・アレルギーが緩みだし、いわゆる「スピリチュアル」ブームが台頭しはじめた時期でもあったのです。
「現代怪談の最前線⑤樹海村」では、 一条真也の映画館「樹海村」で紹介した清水祟監督の2021年の映画がヒットしたことを取り上げ、現在はホラー・コンテンツとしての「怖い村」が求められている時代であると指摘し、著者は「こうした欲求は、なにも今に始まったっことではない。たとえば、民俗学の著作として日本一有名だろう柳田國男『遠野物語』。遠野地方の民俗を聞き書きしたあの本にしても、俗っぽい『怖い話』『怖い村』的な興味を少なからず見いだせるではないか。また、その『遠野物語』が再ブームとなった1970年代半ばには、期を一にして国鉄ディスカバー・ジャパン・キャンペーン、横溝正史『金田一耕助』シリーズのリバイバル・ブームが起きていることも興味深い」と述べます。
また、著者は「現代人が求める『怖い村』をイメージするには、映画も含めた『金田一耕助っぽい世界観』を例に出すのが、もっともわかりやすいだろう(というより、「金田一」シリーズが我々の恐怖イメージに大きな影響を与えているのかもしれないが)。『犬神家の一族』『八つ墓村』のような、因縁と因習と祟りがどろどろに渦巻く閉鎖空間。そうした前時代的な集落が、近代化されたはずの日本国内に並列している怖さ」と述べています。さらに著者は、「ただし言うまでもなく、小説や映画ではない現実世界において、我々が求めるような『怖い村』など、どこにも存在しない。そんなものは実際とかけはなれた、一種の幻想郷だ」とも述べます。
それでも2000年前後までは、各地のローカル怪談として「怖い村」の噂はかろうじて残されており、その実在を信じる人々も多少は存在していたと指摘しつつ、著者は「しかしインターネットの普及・発展(特にGoogleの台頭)は、誰でも簡易にリアルタイムの地域情報や地図情報へのアクセスを可能にしてしまう。噂の場所を衛星写真でいくらでも確認できてしまうのだから、「怖い村」が実在するという幻想など粉々に打ち砕かれてしまう。ちなみにその前夜、パソコン通信からインターネット黎明期のアングラ文化が、各地でささやかれていたローカル怪談と化学反応を起こし、まさに『伝説』と呼ぶべき盛り上がりを見せた。そう、あの『杉沢村』『犬鳴村』こそが、『怖い村』をめぐる最後の巨大打ち上げ花火だったのだ……」と述べます。
「怪談の深層に眠るもの『子殺し』怪談 section6」の16「怪談とはなにか、恐怖とはなにかを探ること」では、著者は「子供の死」にこそ最大の恐怖を覚えると告白し、自分の子であろうと、他人の子であろうと。そして「子殺し」を怖れ、憎み、絶対悪だと感じていると述べます。そして、「子供の死」を最大の恐怖とし、「子殺し」を現代社会の絶対悪とする感情は、他の多くの人々も同じではないかと思っているとして、著者は「インターネットを眺めていても、児童虐待や子殺しのニュースが流れた時の人々の反応は、明らかに他の事件と異なっている。皆が皆、犯人への心底からの怒り、胸がしめつけられるような哀しみを、ストレートに表現する。『5ちゃんねる』やTwitterのような、他のネット空間よりも冷笑や逆張り、別視点からの穿った見方やひねくれた面白さを基調とするような場においても、そこだけは変わらない」と述べています。
最後に、著者は以下のように述べるのでした。
「『母性』とは、もちろん動物的本能の一部ではあるだろう。特に哺乳類は、胎内で成熟しきらないうちに子を産み、外の世界で成長させる生殖戦略をとった。だから「哺乳をはじめとして身体をきれいに保つ、保温する、外敵から守るといったさまざまな親からの養育(子育て)を受けなければ成長することができない。そのため親の脳には養育行動に必要な神経回路が生得的に備わっている」。ましてやヒトは脳=頭部を肥大化させたため、動物としては非常な未熟児を『早産』せざるをえず、より『子育て』の必要性が増してしまっている。ただ現状、本能としての『母性』が拡大解釈され、肥大化したイメージで捉えられていることもたしかだ。それは社会や家庭や親子関係が変化し、『子供』の貴重性が高まった結果である。乳幼児死亡率が高く、多産多死を基本とした時代とは、やはり一人ひとりの『子供』に対する捉え方、『子供の死』に対する捉え方は異なってくる」
日本民俗学を創始した柳田國男は「子殺し」の問題に関心を示しましたが、彼はまた冠婚葬祭や年中行事にも多大な関心を示しました。特に、冠婚葬祭には初宮祝い、百日祝いなど子どもの成長儀礼が存在しますが、その代表が七五三です。拙著『決定版 冠婚葬祭入門』(PHP研究所)にも書きましたが、古来わが国では「七歳までは神の内」という言葉がありました。また、七歳までに死んだ子どもには正式な葬式を出さず仮葬をして家の中に子供墓をつくり、その家の子どもとして生まれ変わりを願うといった習俗がありました。子どもというものはまだ霊魂が安定せず「この世」と「あの世」の狭間にたゆたうような存在であると考えられていたのです。さらに、七五三には「間引き」や「子殺し」を防止する機能がありました。
 「朝日新聞」2021年12月28日朝刊
「朝日新聞」2021年12月28日朝刊
七五三は、不安定な存在の子どもが次第に社会の一員として受け容れられていくための大切な通過儀礼です。そして、親がわが子に「あなたが生まれたことは正しい」「あなたの成長を世界が祝福している」と言うメッセージを伝える場にほかなりません。親がいない子の場合は、周囲の大人がそれを行うべきではないでしょうか。「人間尊重」を掲げるわが社では、児童養護施設のお子さんたちにも七五三祝いを贈る活動を行っています。具体的には晴れ着を無料レンタルし、プロのカメラマンが写真を撮影してプレゼントするのです。施設で成人となる方には、成人式の晴れ着を無料レンタルし、写真をプレゼントします。万物に光を降り注ぐ太陽のように、わが社はすべての人に儀式を提供したいという志を抱いています。