- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2175 芸術・芸能・映画 『ハリウッド映画史講義』 蓮實重彦著(ちくま学芸文庫)
2022.09.28
『ハリウッド映画史講座』蓮實重彦著(ちくま学芸文庫)を読みました。サブタイトルは、「翳りの歴史のために」です。著者は1936年東京生まれ。60年東京大学仏文学科卒業。同大学大学院人文研究科仏文学専攻修了。65年パリ大学大学院より博士号取得。東京大学教養学部教授(表象文化論)、東京大学総長を歴任。東京大学名誉教授。仏文学にとどまらず、映画、現代思想、日本文学など多方面で精力的な評論活動を展開し続けています。
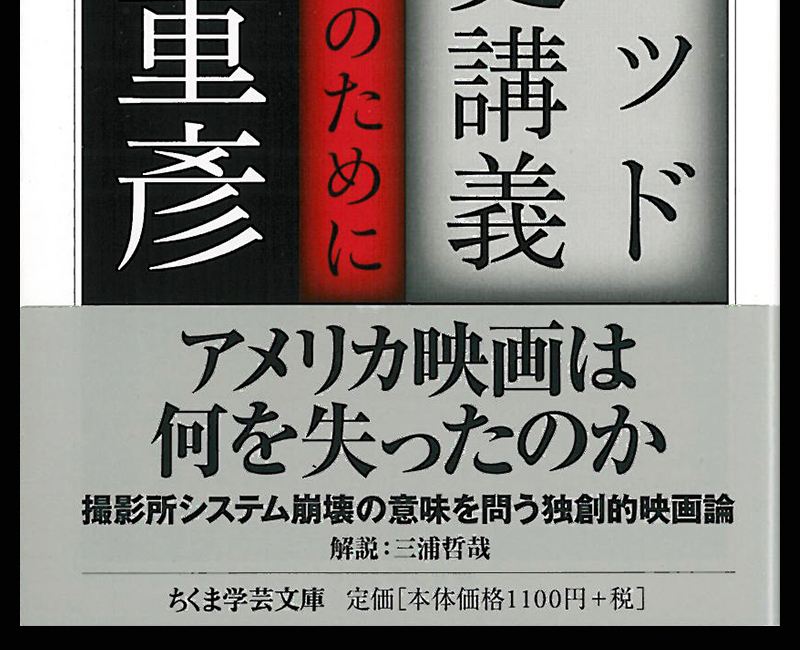 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「アメリカ映画は何を失ったのか」「撮影所システム崩壊の意味を問う独創的映画論」と書かれています。カバー裏表紙には、「『絢爛豪華』な神話都市ハリウッド。その栄光を支えた撮影所システムは、第二次世界大戦後、不意に崩れ始める。アメリカ合衆国との闘いをはじめ、時代と不幸な関係を結んだ『1950年代作家』たちが照らし出すものとは何か――。いまや映画批評において不可欠となった諸概念とともに描かれる歴史は、ハリウッドにおける決定的な変容を浮き彫りにする。アメリカ映画が抱え込んだ問題を剔抉し、作品を見定める視界を開く独創的映画論」とあります。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章
第一章 翳りの歴史のために
ーー「50年代作家」を擁護する
第二章 絢爛豪華を遠く離れて
ーー「B級映画」をめぐって
第三章 神話都市の廃墟で
ーー「ハリウッド撮影所システム」の崩壊
終章
「あとがき」
「文庫版のためのあとがき」
「解説」三浦哲哉
「参考文献」
「索引」
序章では、映画の歴史にあって真に「悲劇的なるもの」は、ことによると、ハリウッドにのみふさわしい概念なのかもしれないとして、著者は「この書物を支えているのは、まさしくそうした予感なのである。実際、1940年代の後半から50年代にかけてハリウッドで起こったほどの大がかりで『悲劇的』な撮影所システムの崩壊を、20世紀の人類は、いまだに他の領域では体験していないといってよい。事実、ほんの10年前ならごく当然と思われていた映画づくりのシステムが、第二次世界大戦の翌朝、映画の都とすら思われていたハリウッドから不意に崩れ始めるなどと予測しえたものなど、誰ひとりとしていなかったはずである」と述べています。
にもかかわらず、事態はそのように進行してしまいました。そこで、この神話的な都市がある時期に蒙った決定的ともいえる変容の実態を、ひとまず鮮明な輪郭で視界に浮上させておく必要があるだろうとして、著者は「映画がやがて100年もの歴史を刻もうとしているとき、1910年代の初めから映画にふさわしい都市としておのれを組織してきたハリウッドが、いまなお一貫して同じ機能を演じ続けていると信じることは、いくらなんでも不可能なはずなのである」と述べます。
第一章「翳りの歴史のために――『50年代作家』を擁護する」のⅠ「1935~1944」の「ニューヨークvsハリウッド」では、 映画が農民や労働者階級の啓蒙にもっともふさわしいメディアだと共産党によって判断されていたことはいうまでもないと述べられます。しかし、資本主義の矛盾にもっとも敏感だった東部の知識人がハリウッドに標的を定めたとき、その尖兵として撮影所に乗り込むことになったのは、演出家志望の若者ではなく、ニューヨークの舞台で名声を博した戯曲の作者たちでした。事実、『ウェイティング・フォー・レフティ』の成功の直後にハリウッドに招かれたクリフォード・オデッツは、リュイス・マイルストンの『将軍暁に死す』(36)で、脚本家として華々しくデビューしています。
『ボディー・ビューティフル』の作者はロバート・ロッセンも脚本家としてワーナー・ブラザーズと契約し、ラオール・ウォルシュの『彼奴は顔役だ!』(39)のクレジットに名をつらねることになります。著者は、「すでに20年代にブロードウェイからハリウッドに招かれていたジョン・ハワード・ローソンは遥かに上の世代に属しているが、若者たちに劣らず政治意識の強いシナリオライターとして、すでに1933年に、脚本家たちの組合『スクリーン・ライダーズ・ギルド』を創設している。のちに赤狩りの犠牲となる脚本家たちは、すでに30年代の中頃からローソンのまわりに結集していたのである」と説明します。
「アメリカにさからって」では、『ウェイティング・フォー・レフティ』の成功によってクリフォード・オデッツがハリウッドに招かれたとき、無法者による社会的なプロテストを描いたギャング映画というジャンルは、「ヘイズ・コード」の実施によって過去のものとなろうとしていたことが紹介されます。著者は、「その種の犯罪映画は、ほぼ10年後に、いわゆる『フィルム・ノワール』となって異なる意匠のもとによみがえるのだが、少なくとも30年代の中期においては、アメリカ共産党の方向転換もあって、社会主義的な姿勢の持主たちの関心は、階級闘争から人民戦線的な反ファシズム闘争へと移行していたのである」と述べます。ちょうど「ヘイズ・コード」がアメリカ映画を画一化しようとしているとき、ハリウッドはさらに新たな反アメリカ的な要素を抱え込むことになります。ヨーロッパにおけるナチズムの興隆に伴い、ドイツからの亡命者たちがやってきたのでした。
『ウェイティング・フォー・レフティ』がニューヨークで好評を博した直後に、フリッツ・ラングはアメリカ市民権を獲得し、MGMと契約します。彼のアメリカ第一作は集団的な暴力を題材とする『激怒』(36)でしたが、ドイツ時代の『M』(31)の試写に立ち会った社長のルイス・B・メイヤーは「これは何だ」と絶叫したといいます。著者は、「さいわいなことに、若いインデペンデント・プロデューサーのウォルター・ウェンジャーがその第二作『暗黒街の弾痕』(37)の製作を担当する。これらの作品の成功が、このドイツ人監督を20年間ハリウッドにとどまらせることになるだろ」と書いています。
Ⅱ「1945~1946」の「大作家の復帰」では、戦後のハリウッドにふさわしい現象はむしろビリー・ワイルダーの『失われた週末』(45)だろうとして、著者は「『深夜の告白』(44)もそうだがどこか異常さの影を宿すこの種の心理的スリラーは、プレミンジャーの『ローラ殺人事件』(44)など、大戦末期からの閉鎖的状況を戦後まで生きのびさせた。犯罪の香りと悪への誘惑を主題とした不安定な精神を描く一連の作品としては、ラングの『スカーレット・ストーリー』(45)、ジオドマークの『殺人者』(46)、ガーネットの『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(46)、チャールス・ヴィダーの『ギルダ』(46)などがすぐさま思い浮ぶ。40年代の後半にかけて、暴力の気配を漂わせたこれらの「フィルム・ノワール」はハリウッド映画の主流をかたちづくりさえするだろう。オーソン・ウェルズが『上海から来た女』(47)を撮るのもそうした風土の中でだが、それにくらべるとカザンの処女作『ブルックリン横丁』は、いかにも普通の映画にすぎない」と述べています。
Ⅳ「1948~1950」の「あるスターの死」では、メジャー系による直営館が独占禁止法によって独自のプログラミングを余儀なくされたことと、何よりも国内製作本数の低減によって、ニューヨークを中心にアートシアター的な小屋が出現し、イタリアのネオレアリズモのインパクトのもとにヨーロッパ映画の上映が盛んになったことが紹介されます。著者は、「やがて全米の保守的な組織からその不道徳ぶりを非難されることになるロベルト・ロッセリーニとイングリッド・バーグマンとの不倫の恋も、そうした背景と無縁ではない。48年のアカデミー作品賞をローレンス・オリヴィエ監督・主演の『ハムレット』が獲得したことや、キャロル・リード監督によるアレクサンダー・コルダ製作の映画『第三の男』(49)にセルズィニックが出資していることなども、アメリカ映画界の目をヨーロッパに向けて開かせることになる」と述べています。
Ⅵ「1954~1958」の「新しいスターたち」では、著者はさまざまなスターの名前を挙げて、「優雅さよりはスポーツ選手的なエネルギーを基本に据えたジーン・ケリーに、あくまで洒落た身軽さで対抗しようとするアステアは、マーロン・ブランド的な生臭さにはとうていたちうちできないだろう。まだジーン・ケリーも、ブラック・リストに載って自由な動きを奪われているかにみえるとき、バート・ランカスター、カーク・ダグラス、ポール・ニューマン、ウィリアム・ホールデンらの新スターを自由に使いこなしうる監督は伝統的な作家の中には見当たらない。ランカスターはアルドリッチ、ブランドはエリア・カザン、ホールデンはワイルダー、ポール・ニューマンはリチャード・ブルックス、そしてジェームズ・ディーンはニコラス・レイと組んだときに最も輝くことになるだろう」と述べています。
1951年の『欲望という名の電車』出演時は傍若無人な侵入者と思われたマーロン・ブランドも、54年の『波止場』でアカデミー賞を獲得したときには、ハリウッドには欠かせないスターとなりました。カザンとリー・ストラスバーグの指導するアクターズ・ステューディオ出身の役者たちが、エヴァ・マリー・セイント、キャロル・ベイカー等々、女優にいたるまでハリウッドに進出しました。著者は、「スターとしての肉体的な魅力にとぼしいオードリー・ヘップバーンの登場も、そうした変化の一端を告げるものだろう。『バンド・ワゴン』のシド・チャリシーが相手役のアステアより背の高いことが映画の中でギャグとされねばならぬ時代が到来していたのだ」と述べます。
Ⅶ「1959~1960」の「伝統と継承」では、著者は以下のように述べています。「いま、われわれは確信をもって断言することができる。ヌーヴェル・ヴァーグは、決してホークスやヒッチコックのような映画を撮ろうなどと思いはしなかった。ジャン=リュック・ゴダールが処女作『勝手にしやがれ』(59)をモノグラム・ピクチャーに捧げたとき、彼がモデルに選んでいたのはまぎれもなくジョゼフ・H・リュイスのような自由闊達な映画作りの姿勢なのだ。彼が範としたのは、エンタープライズ流の仲間意識であり、ニコラス・レイの『夜の人々』(48)のような精神的なA級性を、サミュエル・フラー的なインデペンデントの簡潔さで実現するのがその野心だったのだ。ゴダールがその『メイド・イン・USA』(66)を「音響と映像とを深く敬愛する方法を教えてくれたニックとサミュエル」に捧げたのはそのためだ」
第二章「絢爛豪華を遠く離れて――『B級映画』をめぐって」のⅠ「Poverty Row またはなぜ『B級』なのか」の「ハリウッド、その豊かさと貧しさ」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「ハリウッドという20世紀の神話的な地名から、『絢爛豪華』といった豊かさのイメージしか連想できない人は、アメリカ映画に対する途方もない誤解に安住しているといわねばなるまい。『絢爛豪華』であることは、その特性のほんの一部にすぎず、名前さえ知られていない役者たちが、安っぽい装置の中を冴えない顔でうろつくだけの映画が、ハリウッドでも大量に生産されていたからである。『絢爛豪華』な作品ばかりを送り出していたのでは、システムとしての撮影所は機能するはずがないのであり、そうした現実に視線を向けずにおくと、映画をめぐる思考はたちどころに抽象化してしまうだろう」
映画には、人を理由もなく楽天的な風土へと誘う麻薬のようなものが含まれています。華麗な銀幕とやらに視線を向けていると、政治的=経済的な現実はたちどころに遠ざかり、すべてが甘美な夢へと変容してゆくような気がしないでもないとして、著者は「この抽象的な濾過装置がうまく作動しなければ、夢の工場としてのハリウッドが、その独特な映像と音響とで世界を征服することなどありえなかったはずである。あのメロドラマ、あのミュージカル、あの西部劇、あの犯罪活劇の一景が、大スターたちの表情とともに華麗な忘れ難い記憶としていまも脳裏を横切ったりするのは、そのためである。実質的にはいまや廃墟と化したことを知っていながら、なお、ハリウッドの一語に胸をときめかせずにはいられないのも、そうした理由による。にもかかわらず、ハリウッドが、『絢爛豪華』な人工都市としてのみあったのではないという苛酷な現実は残る。そもそもアメリカ映画の歴史は、その発生いらい20年近くをハリウッドなしですませてきたのだし、東部の映画人にとっては植民地にすぎなかった合衆国の西海岸に生まれたこの神話的な都市には、すでにサイレント時代から、貧民街とも呼ばるべき一画がまぎれもなく存在していたからである」と述べています。
「歴史的な概念」では、『フランケンシュタイン』や『ドラキュラ』といったホラー映画がB級映画として見られることについて、著者は「『フランケンシュタイン』をイギリス・ロマン派の詩人シェリーの妻メアリーの原作小説に結びつけたり、東欧の伝説だといい張ってみたり、そのハリウッド版の第一作の監督がジェームズ・ホエールだと断言してはばからぬ精神がまぎれもなく存在している。そうした文化的な姿勢によって映画はいまもなお抑圧されているし、ケン・ラッセルといった程よく文化的な精神の持主も、その種の抑圧に快く手を貸しているのだといえる。原題にあえてブラム・ストーカーのと謳った『ドラキュラ』のフランシス・フォード・コッポラでさえ、心ならずもこの抑圧に加担している。われわれが、いまあえて『B級映画』を語ろうとするのは、その種の無意識の抑圧にさからう必要を感じているからだ」と述べています。
Ⅱ「Frankensteinの誕生」の「ユニヴァーサルのフランス人」では、ジェームズ・ホエール監督の『フランケンシュタイン』(31)が、怪優ボリス・カーロフを一躍世界的に有名にしたことはよく知られていることが紹介されます。しかし、カール・レムレにシナリオと詳細なカット割りとを提出したフローレーにとって、真のフランケンシュタイン役者はボリス・カーロフではありませんでした。著者は、「事実、彼は、いま1人の怪優ベラ・ルゴシを主演に使って2巻ほどのフィルムをテスト版としてまわしているのである。だが、結局のところ会社が採用したのはシナリオだけで、ホエール=カーロフのコンビで映画は製作されてしまう。フローレーの名前はシナリオライターとしてもクレジットされることはないだろう。真のフランケンシュタインの生みの親ともいうべきロバート・フローレーが得たものは、いま1つの企画だった『モルグ街の殺人』(32)を監督するチャンスのみである。これに主演するベラ・ルゴシが第2代目のフランケンシュタイン役者となることはいうまでもない」と述べます。
Ⅲ「Pictures of the B lot 語源探索」では、読まれるごとく、「B級映画」と訳されている作品は、ハリウッドでその言葉が発生した当初は、純粋に地理的な区別にもとづく分類法に従うものであったと説明されます。もちろん、その分類法の根底には、経済的な要請が働いていました。1本の作品に投資される金額を低く押さえ、売上げ額との差を大きくするというのがその要請でした。「安定した商品としての『B級映画』」では、著者は「かくして『B級映画』は、投資された資本の少なさとそれにみあった見かけのみすぼらしさにもかかわらず、安定した商品となる。ユニヴァーサルにおいても、伝統の怪奇映画にとどまらず、すでに1936年からシリーズ化されていたバスター・クラブ主演の『B級映画』である『フラッシュ・ゴードン』ものの成功がそれに貢献していたことは、いかにも象徴的である。出演料を低くおさえるという目的で、無声時代のスターや、他の作品では脇役しか演じない個性的な俳優を主役に迎え、『A級』の豪華さとは異質の世界を構築し、一方では先述のピーター・ローレやジョン・キャラダイン主演といった演技力の楽しみを観客に提供すると同時に、新しいスターの養成所としても『B級映画』が利用されることになる」と述べます。
Ⅶ「Welles,Godard そして『B級』の精神」の「『B級』的な輝きのまわりを旋回しながら」では、かつて「A級」のインデペンデント・プロデューサーとして活躍し、フォードの『駅馬車』を製作したことで記憶されているウォルター・ウェンジャーは、51年に妻ジョーン・ベネットのマネージャーを狙撃して投獄されるというセンセーショナルな事件を起こしたことが紹介されます。著者は、「これは、いかにも『50年代』ハリウッドを象徴するできごとだといえようが、出獄直後に彼がプロデュースすることになる作品にも、『B級』的な精神ともいうべきものがみなぎっている。いずれもドン・シーゲルに演出を任せているが、『第11号監房の暴動』(54)や『ボディ・スナッチャー 恐怖の街』(56)などは、簡潔さが大スターの不在を補い、単純であることの美徳が画面ごとに輝いている」と述べます。
時代の変化を敏感に察知して低予算の地味な作品で勝負するところなど、さすがにウェンジャーだと思わせはしましたが、その数年後に『クレオパトラ』(63)を企画し、これが悲惨な結果に終わったことは誰もが知っているだろうとして、著者は「それは、『非情の罠』(55)と『現金に体を張れ』(56)という2本の小品で登場したスタンリー・キューブリックが、その数年後には超大作『スパルタカス』(60)を撮らされてしまうという事情とも共通しているといえようが、いまや、「B級映画」は贅沢品にすぎず、映画産業そのものが、誰にもそんな贅沢を許してはくれなくなっていたのである。かつてなら「B級」にふさわしいと思われていた題材でも、いまでは社運を賭けた大作として撮られねばならなくなっているからである」と述べています。
そうした事業は、撮影所システムが機能しえなくなった70年代に入ってから、「B級映画」の黄金時代を築くきっかけとなった「キング・コング」や「スーパーマン」などが、大作としてリメイクされ始めたことによって証明されています。著者は、「スピルバーグの『インディ・ジョーンズ』シリーズもあからさまに『B級』的な題材なのだが、それを『B級映画』として簡潔に消費しうる余裕を、映画産業はとうのむかしに失ってしまっている。コッポラの『ドラキュラ』(92)さえ、『B級』の美徳にほかならぬ単純さには背を向けた作品として撮られているのである。多くの製作費をかけていながら、精神として『B級』性をとどめているのは、ティム・バートンの『バットマン』シリーズぐらいかもしれない」と述べています。
確かなことは、デヴィッド・リンチの『ブルーベルベット』(86)よりも、デヴィッド・クローネンバーグの『デッドゾーン』(83)よりも、ニール・ジョーダンの『モナリザ』(86)よりも、コーエン兄弟の『バートン・フィンク』(91)よりも、ティム・バートンの『シザーハンズ』(90)よりも、ハル・ハートリーの『シンプルメン』(92)よりも、『ゴダールのマリア』(83)の方が遥かに「B級映画」に近いということだと指摘し、著者は「62分というその上映時間の短かさにおいて、撮影スタッフの少なさにおいて、予算の低さにおいて、そして何よりもまず、その呆気ないほどの単純さにおいて。『マリア』から『ゴダールのリア王』(87)を通過して『新ドイツ零年』(91)にいたるまで、ゴダールは一貫して『B級』の単純きわまりない鈍い輝きのまわりを旋回している」と述べるのでした。
第三章「神話都市の廃墟で――『ハリウッド撮影所システム』の崩壊」のⅠ「MGMのタッグマッチ」では、しばらく前から、アメリカ映画といえば、誰もが清涼飲料水と石油とテレビネットワークと保険会社と不動産業界の支配をごく自然に思い浮かべるようにさえなってしまったことが指摘されます。また、近年では、映画とは縁もゆかりもない日本企業の名前がそこに顔を出し始めています。著者は、「こうした凋落の歴史の象徴的な引き金として、超大作『クレオパトラ』(63)の壮大な失敗が、60年代初頭のハリウッドを暗い色調に塗りあげていた事実は、多くの人が記憶にとどめているだろう。『クレオパトラ』は、何人もの製作者や監督や俳優たちの首がすげかえられていったことでも『風と共に去りぬ』(39)を想起させる20世紀フォックス社の社運を賭けた作品でした。
『クレオパトラ』は、途中から陣頭指揮に戻ったダリル・F・ザナックとジョゼフ・L・マンキーウィッツの「屈辱的な」努力によって数年越しの撮影を何とか終えたとき、2600万ドルの興行収入を収めながら、なお6000万ドルという記録的な赤字を出しました。ハリウッドが、もはや自社の商品をその製造過程で管理しえないさまを業界に印象づけることになったのです。著者は、「『サウンド・オブ・ミュージック』(65)の世界的な成功で一時的には体面を保てたものの、ザナックが最終的に辞任する1970年には、フォックスは7700万ドルの負債をかかえこむことになってしまうだろう。その後、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』シリーズによって70年代を何とか乗り切ったものの、80年代に入ると、フォックスはデンバーの石油王マーヴィン・デーヴィスに買収されてしまう」と説明します。
Ⅱ「双頭の鷲は死んだ」では、著者はこう述べています。
「監督になる人間などはどこにもころがっているが、アメリカと映画との間に通訳として位置しうるようなプロデューサーは、そう簡単に作れるわけではないからである。たとえば、老舗のユナイテッド・アーティストがマイケル・チミノ監督の『天国の門』(80)の製作に関わることで消滅してしまった事件などが、そのことを雄弁に証明している。グリフィスとチャップリンとダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォードという神話的な名前と深くむすびついていた名門ユナイテッド・アーティスト社は、予算を大幅に超過したこの大作の処置をめぐって窮地に陥り、不動産業者のカーコリアンによって買収され、MGMの傘下に入ることになったからである」
Ⅳ「物語からイメージの優位へ」では、70年代のアメリカ映画が、SFXと特殊メーキャップの濫用によって、サスペンス映画をホラー映画へと変質させたことを指摘し、著者は「たとえば日本では46年遅れで初公開されたジャック・ターナーの『キャット・ピープル』(42)とポール・シュレイダーによるそのリメイクとを比較してみれば、その変化はただちに納得されよう。その点をめぐってはすでに多くの指摘もあるが、オリジナルでは暗示的なショットの効果的な連鎖によって雰囲気として語られていた変身過程が、シュレイダー版では見えるものとして示され、視線いがいの諸々の感性を刺激する前者の修辞学は、後者では、もっぱら瞳ばかりに働きかけるイメージに置き代えられている」と述べています。
また、1982年のリメイク版「キャット・ピープル」について、著者は「露呈された性器そのものをスクリーンに映し出す権利を獲得した映画は、それと同じ水準で、狼へと変身する少年の顔のクローズアップや、からだから切り離される悪魔憑きの少女の首や、孵化する地球外生物の幼虫や、斧で割られる若い娘の頭蓋骨を特殊効果で視覚化する権利を獲得したのだが、それと交換に、肝腎なものを絶対に見せないことで成立するサスペンスという形式を放棄してしまったのである。もはや扉の蔭の秘密や影なき恐怖は語られえず、ドアーは見世物的にたたき割られ、怪物が視界の前面をわがもの顔に跳梁するのみだ」と述べます。
いわゆるハリウッドの撮影所システムは50年代に崩れ始め、60年代の終わりに完全に崩壊しますが、そのとき、ハリウッドとは異なるたんなるアメリカ映画が、ときならぬ視覚性の優位とともに形成されたとして、著者は「撮影所システムが有効に機能していた時期のハリウッド映画と、70年代以降のアメリカ映画とは、構造的にもイデオロギー的にもまったく種類を異にする商品なのだ。まず、このことを認識しなければならない。だが、それに劣らず重要なのは、この非連続性がアメリカ映画から西部劇を完全に追放し、サスペンスがホラーという後継者をかろうじて持ちえたような意味で、その系譜をたどることさえできなくなってしまったという点である」と述べます。
「死のスペクタクル化」では、一般に、人は、サム・ペキンパーの『ワイルドバンチ』(69)や『砂漠の流れ者』(『ケーブル・ホーグのバラード』)(70)にいたる一時期に、失われた西部への挽歌が奏でられたのだと思いこんでいるとして、著者は「だが、ここで見落としえないことは、西部劇が題材として不可能になったのではなく、活劇にふさわしい物語の形式そのものが、暴力描写を禁じていた『ヘイズ・コード』の消滅以後、銃撃戦の視覚的スペクタクル化によって死滅したという事実だろう。被弾した瞬間に噴出する血液も、もんどりうって倒れる馬も、落馬するカウボーイも、逃げまどう群衆も、すべてスローモーションによって『華麗』に引き伸ばされ、それにふさわしいものが構図=逆構図による切り返しショットであったはずの対決までが、緩慢な宇宙遊泳に似た「見世物」と化してしまったとき、もはや誰も西部劇は撮れなくなってしまったのだ。『ワイルドバンチ』が感動的なのは、もはや誰にも西部劇は撮らせまいとするペキンパーの狂暴な意志が、『死』そのものをスペクタクル化した最後の銃撃戦を「華麗」さ以上の不吉なまがまがしさで彩ってみせたことにある。西部劇は曖昧に消滅したのではなく、あくまでも意志的な自死を体験した高貴なジャンルというべきだろう」と述べています。
アメリカ映画は、ハリウッドの崩壊とともに、西部劇を永遠に失ってしまったのでしょうか。インディアンを悪役として描けないことが決定的だったのでしょうか。著者は、「コッポラとルーカスとスピルバーグがこの不吉なジャンルを聡明に回避し続けていることが何やら象徴的に思われもする。『あまりに静かすぎる』と低くつぶやきながら見えない敵に対して本能的に身がまえるガンマンの反応を、有効なショットの連鎖で物語ってみせるフィルム的言説を担いうるのは、やはりクリント・イーストウッドしかいない。われわれは、ヒッチコック流のサスペンス映画が二度と蘇ることがないように、フォード流の西部劇が再び復活しえないことを知っており、そのことをとりたてて悲しく思う気持はない。だが、『ダウン・バイ・ロー』(86)のジャームッシュや『エル・スール』(83)のビクトル・エリセに西部劇の呼吸といったものをまぎれもなく感じとって奇妙な戦慄を覚えなかった人がいるだろうか」
意識的であると否とにかかわらず、西部劇の神話は最良の作家たちのフィルムに脈搏っていると指摘し、著者は「最良の作家とは、瞳だけに働きかけるイメージのスペクタクル化の全盛期に、その風潮になじめず、物語の簡潔さに貢献するショットの可能性を確信しつつ、たんなるハリウッド映画のパロディとは異なる語り方を発見した人たちのことにほかならぬ。事実、アレックス・コックスの『ウォーカー』(87)にはそんな気配が感じとれるし、20世紀フォックスのザナック傘下で撮られたならより簡潔なものとして仕上ったろうにと惜しまれるジョン・セイルズの『メイトワン1920』(87)にもそうした雰囲気がわずかながら漂っているような気がする。だが、そこになにがしかの新しさが認められるかといえば、否定的な言葉を口にせざるをえない」と述べるのでした。
Ⅴ「反時代的な作家の系譜」の「バズビー・バークレーとオーソン・ウェルズ」では、ジョン・フォードが『駅馬車』(39)で獲得しえた大衆性とは、ともすれば物語に対する視覚の優位に惹かれがちだった彼の無意識の前衛的な資質が、ここで決定的に編集による説話論的な構造の簡潔な運動感へと変質をとげたからにほかならないと指摘し、著者は「もちろん、才能ある監督たちは、それぞれに個性的な構図によっておのれの映画的想像力を物質化する術を心得てはいたのだが、とりわけ個性的な作家たち、たとえばハワード・ホークスにしてもラオール・ウォルシュにしても、彼らの才能は、むしろキャメラの存在を意識させないまでにショットの独走を禁じることに発揮されていたのだといってよい」と述べています。
多くの人が口にするハリウッドの「絢爛豪華」さとは、個々の作品を見終わったあとで誰もが想像する「夢の工場」でのスターたちの生活の質にかかわるものであり、それはいつでもスクリーンとは無縁の世界に拡がり出す見えてはいない世界の形容にほかならなかったと指摘し、著者は「華麗な衣裳も壮大な装置もことさら視覚的に誇張されることなく、呆気ないほどの慎ましさで物語に奉仕するというのがハリウッドのイデオロギーにほかならず、ヨーロッパ系のアルフレッド・ヒッチコックやフリッツ・ラングさえもが理解したその倒錯性に同調しえず、ショットそのものに『絢爛豪華』な輝きをこめてしまったが故に、オーソン・ウェルズはアメリカから受け入れられなかったのである」と述べます。
ハリウッド映画は、50年代から徐々に変質しつづけながら、最後の超大作『クレオパトラ』(63)によって象徴的に終焉し、66年から70年にかけて、政治的かつ経済的な要因によって実質的に変質しました。著者は、「そうしたハリウッド神話の消滅は、アメリカ映画に、ほぼ3つの変化を導入したということができる。まず、70年代以後のアメリカ映画は、瞳を抑圧していた修辞学的イデオロギーから解放され、『見世物』にふさわしくイメージをスペクタクル化することで、物語の簡潔さを抹殺することになる。この傾向は、ロナルド・ニームの『ポセイドン・アドベンチャー』(72)などのパニックものや、ウイリアム・フリードキンの『エクソシスト』(73)などのホラー映画を生みだし、ほぼ10年にわたって流行するだろう。それと同時に、2番目の変化として、見ることで納得する観客と、見たものについて語り、かつそれをめぐって想像をめぐらせねば気のすまない『シネフィル』という、記号の享受層の二分化が否定しがたく進行してゆくことになる」と述べています。
また、著者は「だがそれにもまして重要なのは、オーソン・ウェルズ的な反時代性の系譜を体現するものが、いまやスタンリー・キューブリックではなく、視覚的な効果よりもいまだに物語の優位を確信しているかにみえるクリント・イーストウッドのような、むしろ反動的ともいえる作家の側に移ったという点である。これが、第3番目の変化である。『ハートブレイク・リッジ/勝利の戦場』(86)と『フルメタル・ジャケット』とを見くらべてみれば、そのことは誰の目にも明らかだろう。キューブリックのいくぶんか軽薄ともよべそうな時代との同調ぶりのかたわらに置いてみると、イーストウッドの倒錯的なまでの時代との行き違いがきわだち、むしろ貴重な試みのように映ってさえしまうのだ。実際、70年代以後、『許されざる者』(92)の監督ほど、画面の視覚的な効果を禁欲し続けた作家も稀なのである」とも述べています。
Ⅵ「ユニヴァーサルをめぐる決裂」の「「ハリウッドを遠く離れて」では、『波止場』(54)以後の全作品はニューヨークの撮影所で仕上げたというエリア・カザンの言葉通り、すでに50年代から、ハリウッド以外の場所でいくらでもアメリカ映画は撮れるようになっているとして、著者は「人件費が安いという理由で西部劇のロケ地にメキシコが選ばれた50年代の半ばから、マドリッドやローマで撮った方が遥かに安あがりだという時代が始まっていたのである。また、海外にまで足を伸ばさずとも、ニューヨークにはアストリア・スタジオという由緒正しい撮影所が復活しており、コッポラの『コットンクラブ』(84)はそこで撮られたことを宣伝材料の1つにしていたほどだ」と述べています。
続けて、著者は「さらには、ハリウッドのステージでのセット撮影よりも、ロケーションによる撮影の方がより効果的だという方法の簡易化のために、大型トラックによる機材移動のシステムを企業化した「シネ・モビール」方式も60年代の終わりから大幅に活用されているし、人工光線よりは自然光線での撮影に秀でたキャメラマンたちがヨーロッパから招かれたり、ヴィルモス・スィグモンドやラズロ・コバックスのようなその専門家たちが、アメリカ映画の画質を完璧に変えてしまってもいる。ゴードン・ウィリスと組んだウッディ・アレンのこの時期の作品も、映画にカリフォルニアの晴天など必要としないといい続けているかのようだ」とも述べています。
Ⅶ「誰がハリウッドを必要としているか」の「虚構都市ハリウッド」では、イメージの安易なスペクタクル化にさからう『タッカー』の反時代性は、それにふさわしく正当に評価されねばならないだろうとして、著者は「だが、スピルバーグがプロデュースを担当した『ドラキュラ』(92)となると、コッポラはふたたび視覚的な効果のために物語を犠牲にしているかのようにみえる。色彩、装置、衣装、メーキャップがことさら重視された映画だという意味では、コッポラのフィルモグラフィーにあっては、これはむしろ『ワン・フロム・ザ・ハート』の系譜に属する作品だといえる。そうする以外に、いま『ドラキュラ』を撮る理由は見いだしがたいだろうし、コッポラがある程度までそれに成功しているのも確かだとはいえ、その出来栄えをみるにつけ、決して才能を欠いているわけではないコッポラという監督をいかに活用すべきかについて、現代のアメリカ映画はいまだ明確なイメージをいだくにいたっていないとつぶやかざるをえない」
数多くの超大作を世に送り出した「ハリウッドの巨匠」であるフランシス・フォード・コッポラについて、著者は「ストーリー・テリングと視覚的な効果の追究との間に引き裂かれたコッポラのこうした分裂症的な資質こそ、すでに崩壊していながらも神話としてはそれなりに機能し続けているハリウッドの曖昧さを象徴するものにほかなるまい。フランシス・フォード・コッポラとは、おそらく過渡期的な作家なのであり、そのこと故に、かつてのハリウッドの巨匠のようなステイタスを獲得するにいたらず、また、ハリウッド崩壊後のアメリカ映画の安易さに徹することもできないのである」と述べます。
ハリウッドについて、著者は「ハリウッドとは、多少とも名の通った合衆国西海岸のたんなる土地の名前以外のなにものでもない。それに、マウント・リーの山頂につらなるHOLLYWOODの巨大な文字は、もともと不動産業者によって土地開発の目的で立てられたものでしかなかったのである。晴天の日には25マイルの距離からも鮮明に望まれるものだというが、その巨大な文字も風雪に耐えかね、撮影所システムが崩壊した70年代を通じて、あたかもその事実を反映するかのように、1つ2つと崩れ落ちてゆく。1964年から70年までの間に最も破損が激しかったというのは、どこかしら象徴的だといえよう。アメリカ映画の興行収入が記録的な落ち込みを体験した72年に市の文化史跡の1つに指定されながら、当然のことながら、補修のための資金は集まらない。77年には、改めてDの文字が欠け落ち、続いてOのひとつが崩壊する。再建計画のためにTシャツまで売られ、テレビスポットが流されても、映画産業の側からの資金提供の申し出はない。まがりなりにも潰れずに残っていた撮影所は、1つとして積極的に動こうとはしなかったからである」と述べています。
再建されたハリウッド・サインを犯罪解明の小道具に使った「フィルム・ノワール」の商品が存在するとして、著者は「ジム・ジャームッシュの『ストレンジャー・ザン・パラダイス』(84)のニューヨークが、ヌーヴェル・ヴァーグの監督たちの目に映ったパリのなまなましさに匹敵しようとする試みであったように、この映画に描かれたロサンジェルスとハリウッドの光景もまた、妙に新鮮で見る者の心を躍らせる。監督は、香港系のウェイン・ワン。題名は『スラムダンス』(87)。主演がトム・ハルスとヴァージニア・マドセン。助演がミリー・パーキンスとハリー・ディーン・スタントン。『アマデウス』(84)のトム・ハルスが売れない劇画作家を演じ、知らぬまに犯罪に捲きこまれるという犯罪映画の筋立てを、たぶん亡命イラン人であろうキャメラのアミール・モクリが小気味よくフィルムにおさめている。ここには、俊才と呼ばれるわりには脚本の処理に大胆さを欠くことが多いロジャー・コーマン門下には撮れそうもない「B級」的な犯罪映画の香りが漂っており、無国籍的なアメリカ映画の臆面のなさが見るものに快い驚きをもたらす」と述べています。
そして、初めてビヴァリー・ヒルズにロケーションを敢行したジム・ジャームッシュの『ナイト・オン・ザ・プラネット』(92)の冒頭の挿話で、ハリウッドの町は、まるで外国人によって撮られた土地のような表情におさまっていることを指摘し、著者は「もちろん、これはアメリカ映画ではあるがハリウッド映画ではないのである。ハリウッド以外の場所でいくらでもアメリカ映画が撮れることが当たり前になったいま、ハリウッドという虚構を必要としているのは、いったい誰なのだろうか」と述べるのでした。
青山学院大学文学部准教授(映画批評・研究、表象文化論)の三浦哲哉氏は、「解説」の冒頭を「1936年生まれの蓮實重彦が同時代的に愛好し、他の誰よりも見たという『自負』のもとで書かれたというハリウッド『B級映画』の歴史書である。ジョン・フォードやハワード・ホークスやアルフレッド・ヒッチコックといった偉大な作家の名がほぼ登場せず(しかし完全に、ではない)、映画の『翳り』の側面――いわば「B面」に焦点を置いた、きわめて独創的な映画論である」と書きだしています。また、三浦氏は「本書によってきわめて見事な定式が与えられた映画批評の鍵概念――『ありきたりな映画』、『映画の保護機能』、『スペクタクル化』、『説話論的な経済性』、そして『B級映画』は、まさに映画の『B面』に丹念なまなざしを注ぐことによってはじめて明瞭に示されえたものだ。これらはいまもなお映画の思考において欠かせないものでありつづけており、その意味でも本書は、映画入門のための必携書であると言える」と述べています。本書を読んで初めて知ったことは多いですが、特に「B級映画」についてのくだりが印象的でした。映画と共産主義の関係についても勉強になりました。