- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2154 オカルト・陰謀 『陰謀論はどこまで真実か』 ASIOS著(文芸社)
2022.07.26
『増補版 陰謀論はどこまで真実か』ASIOS著(文芸社)を読みました。著者のASIOSとは、2007年に日本で設立された超常現象などを懐疑的に調査していく団体で、名称は「Association for Skeptical Investigation of Supernatural」(超常現象の懐疑的調査のための会)の略です。海外の団体とも交流を持ち、英語圏への情報発信も行うそうです。メンバーは超常現象の話題が好きで、事実や真相に強い興味があり、手間をかけた懐疑的な調査を行える少数の人材によって構成されているそうです。ASIOSの本には、一条真也の読書館『UFO事件クロニクル』、『UMA事件クロニクル』、『超能力事件クロニクル』で紹介した本などがあります。
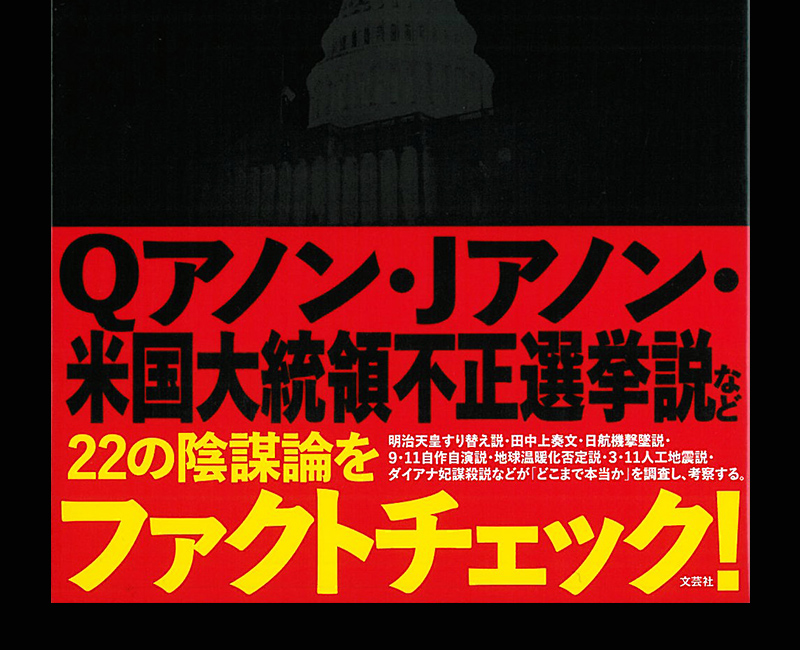 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙の下部には、「Qアノン・Jアノン・米国大統領不正選挙説など22の陰謀論をファクトチェック!」「明治天皇すり替え説・田中上奏文・日航機撃墜説・9・11自作自演説・地球温暖化否定説・3・11人工地震説・ダイアナ妃謀殺説などが『どこまで本当か』を調査し、考察する」と書かれています。
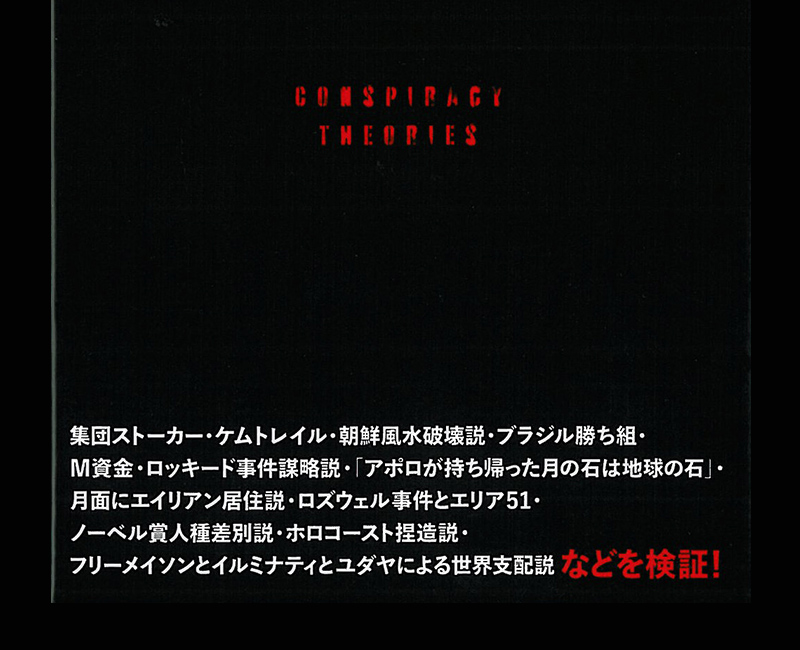 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏表紙には「CONSPIRACY THEORIES」「集団ストーカー・ケムトレイル・朝鮮風水破壊説・ブラジル勝ち組・M資金・ロッキード事件謀略説・「アポロが持ち帰った月の石は地球の石」・月面にエイリアン居住説・ロズウェル事件とエリア51・ノーベル賞人種差別説・ホロコースト捏造説・フリーメイソンとイルミナティとユダヤによる世界支配説などを検証!」と書かれています。なお、 本書は、2011年に文芸社から発刊された『検証 陰謀論はどこまで真実か』をリニューアルしたものです。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
まえがき――増補版の発刊によせて(本城達也)
第1章 Qアノンとアメリカ大統領選挙をめぐる陰謀論
第2章 私たちの生活に関わる陰謀論
第3章 日本史の中で語られた陰謀論
第4章 アポロとUFOをめぐる陰謀論
第5章 世界史の中で語られた陰謀論
「まえがき――増補版の発刊によせて」では、ASIOS代表の本城達也氏が「ここでいう『陰謀論』とは、『ある出来事や事件に対し、常識や通説とは大きく異なる陰謀があったとする主張』です。『陰謀』には『ひそかな悪だくみ』といった意味がありますから、もっと簡単に別の言い方をすれば、『あの事件や出来事の裏では、常識では考えられないひそかな悪だくみが行われていた』というものです」と述べています。近年、陰謀論が盛んになっています。なぜ、こうした変化が起きたのでしょうか? 本城氏によれば、考えられる要素は主に2つあるそうです。
1つは、2016年のアメリカ大統領選挙で、積極的に陰謀論を利用するドナルド・トランプが当選したことです。アメリカ大統領は絶大な発信力と影響力を持ちますから、当時の現役大統領としてトランプが発信する陰謀論の情報は、注目を集めないわけがないというのです。もう1つは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用者が増えたことです。ドナルド・トランプ前大統領が情報発信の手段の1つとして、SNSのツイッターをよく利用していたことは知られています。そうしたSNSを利用する人が、この10年ほどで増えているのです。
本書のスタイルは、最初に個別の陰謀論が紹介され、続いて「陰謀論」で詳しい内容を紹介し、さらには「真相」が語られるというものです。第1章「Qアノンとアメリカ大統領選挙をめぐる陰謀論」の冒頭に置かれた「Qアノン信奉者は、トランプとともにアメリカ再生のために戦っている(Qアノン陰謀論)では、「陰謀論」として、文学修士でAISOS運営委員のナカイサヤカ氏が「2017年、何でもありの4chan(フォーチャン)というアングラの電子掲示板で、『Q』というアカウントが、アメリカ政府の内部情報だと称する書き込みを始めた。軍関係の高官だと自称する『Q』が書く情報は、断片的な予言のような謎めいたものだった。だが、掲示板ユーザーの努力で解読が試みられると、だんだんとアメリカ政府の内部で大変な事態が起こっていることが明らかになってきた。掲示板ユーザーによる『解読』によると、民主党議員たちは実は小児性愛者で、日々子供たちに性的虐待を加えるという享楽にふけっている。虐待する相手の子供たちは人身売買組織から買っている」と書いています。
こうした「Q」が発信する情報を信じて活動する人々は、「Qアノン」信奉者と呼ばれています。「アノン」は匿名を意味する英語の「アノニマス」(anonymous)に由来するとして、ナカイ氏は「彼らが唯一の希望をつないだ存在がドナルド・トランプだ。長年民主党にやりたい放題やられてしまっている共和党大物議員たちと違って、トランプなら真実を暴き出してくれるだろう。『Q』が知らせようとしているのは、ドナルド・トランプがまもなくストーム(大変革)を起こし、すべてが変わるということだ」と述べます。
Qアノン陰謀論の「真相」の「『Q』の登場とQアノンの誕生」では、陰謀論の骨子に、「アメリカ政府を裏から操り、悪魔を崇拝する秘密結社ディープステート」という悪役が加えられたことが指摘されます。そして、悪役に対峙するヒーローには、「政治のしがらみとは無縁の庶民派大統領ドナルド・トランプ」が「神に選ばれた人」(ザ・チョーズン・ワン)として置かれ、そのトランプが「民主党議員たちの悪逆非道な行いを白日の下にさらし、アメリカに大変革(ストーム)をもたらす」という物語が付け足されたことを指摘し、ナカイ氏は「こうして誕生したのがQアノンである」と述べています。
また、「アメリカの分断の象徴となったエスタブリッシュメント」では、植民地時代のアメリカが本国イギリスの植民地政策に反抗して独立戦争を起こしたのは、植民地にやってきた財産も教育もあるイギリス人の子孫たちだったとして、ナカヤ氏は「さらにその子孫たちが東部に都市を作って、世界で初めて王様のいない共和国の舵を取る『アメリカのエスタブリッシュメント』となる。WASP(白人でアングロサクソンでプロテスタント)という呼び名も、同じような人々を違うカテゴリーで呼んだものである。一方で、同じヨーロッパ出身でも、身一つでアメリカにやってきた人たちがいた。ピルグリム・ファーザーズたちと同じように信仰の自由を求めるプロテスタント信者たちである。彼らはヨーロッパの祖国では得られなかった夢を実現しようとして移住してきた人々で、新天地で生きていこうとして、自作農として農園を開いたり、鉱山を探したり、小さな事業を始めたりした」と述べます。
「小児性愛者への敵意と『子供を救え』というキャッチフレーズ」では、陰謀論では、魔女や悪魔崇拝者は善良なキリスト教徒に対する不道徳の象徴として定番の存在であるとしながらも、著者は「だが、かつては不道徳の極みであり、悪魔と契約した人でなしの所業とされてきた離婚や未婚者の出産、同性愛や同性婚までがアメリカで認められるようになると、そうした行為をする人々が普通に社会的地位を獲得するようになる。それどころか、信仰の自由の名の下で、魔女の宗教ウィッカや悪魔教まで信者を集めているのが現代アメリカである。悪魔崇拝や魔女だけではもう敵としてのインパクトが弱い。そのような風潮にあって、道徳的な価値観が違う人でも一致して糾弾するのが、子供を傷つける行為だ。Qアノンが敵と見なす人々が小児性愛者という想定になっているのはこのためだろう。アメリカで子供を傷つけた人々への反感や反発は日本の比ではない。2003年に子供に性的虐待を行った罪で服役中だったカトリックの神父が刑務所内で殺された」と述べます。
このような背景がある中で、Qアノン信奉者は仲間を増やすためにSNSで拡散されやすい「子供を救え」(セーブ・ザ・チルドレン)というキャッチフレーズを考え出しました。このフレーズに興味をひかれ、クリックすると、そこには子供たちが酷い拷問を受けているという、おぞましい話が書かれています。ちなみに、「子供の血を使った悪魔の儀式が行われている」といった話は、12世紀から存在していたことがわかっています。それが「ブラッド・リベル」(血の中傷)といわれるもので、昔はユダヤ人たちがキリスト教徒の子供の血を使って悪魔の儀式をしているとされていました。ナカイ氏は、「これは、やがて20世紀になると、ナチスによってユダヤ人の迫害に利用され、ホロコーストにもつながっていく」と述べています。
「共通の敵を持つことで結びつく、コミュニティ型の陰謀論」では、Qアノン陰謀論にはSNSの仕組みも一役買っていると指摘し、ナカイ氏は「SNSで連絡し合っている仲間が陰謀論系の情報をシェアし始めると、『エコーチェンバー』(仲間内で同じような情報だけが繰り返し交換される状態)ができやすく、別の角度からの意見が届きにくくなる。また、仲間に勧められて、動画サイトでQアノンを解説している動画を見ると、次々と『お勧めの動画』として同じような動画が再生され続ける。気がつけば頭の中はQアノン情報で一杯になっているわけだ」と述べます。
イギリスのケント大学心理学教授カレン・ダグラスは、人々がそのように怯えてしまう内容の陰謀論に惹かれる理由は3つあると述べました。以下の通りです。
(1)人々は自分にとって理不尽で重大な出来事が起こったときに、自分が納得できる理由を求める心理が働く。
(2)さらに真実を知る自分は優位な立場にいると感じることで、重大な事件で感じた無力感から抜け出せる。
(3)次に、仲間に支持されていたいという心理が働いて、陰謀論に惹かれる。
つまり大事故が立て続けに起こってたくさんの人が死ぬのも、世界各地でずっと悲惨な内戦が続いているのも、「秘密結社による世界人口半減計画」が実行されているからだとなれば、原因があって起こってるのだと安心できるわけです。それに、そのような信じがたいことが実際にあると知っている自分は優位に立てると感じることもできます。さらに、同じことを知っている仲間を得られればもっと安心するといいます。ナカイ氏は、「このように陰謀論を信じる人は、理不尽で不安を煽るようなことばかり考えては怯えているように見えるかもしれないが、上記のように考えれば安心できるのが、陰謀論の魅力だというのだ」と説明します。
Qアノン内部には様々な矛盾した物語も共存しているため、ジャーナリストたちはQアノンを、様々な物語を中に入れる「大きな陰謀論のテント」と呼ぶようになっていると指摘し、ナカイ氏は「Qアノン信奉者たちが共有しているのは、彼らが敵と考えるディープステートの手先となっているエスタブリッシュメントへの怒りと、自分たちは正義を実行して国や家族を守らなくてはならないという自負であると言ってよい。Qアノン信奉者たちは共通の敵を持つことで、ゆるく結びつき、共存する。教祖的な存在を持たない彼らにとって大事なのは、自分の信じる筋書きに対して仲間同士の支持を得ることなのだ。Qアノンはいわば、コミュニティ型の陰謀論とも言える集団なのだろう」と述べます。
「そして議会議事堂乱入事件へ」では、陰謀論の世界にはまり込んでしまうことを、『不思議の国のアリス』に登場するアリスが白ウサギを追って落ち込んで不思議の国に行くことになるウサギの穴に例えて、『ウサギ穴に落ちる』というと紹介し、ナカイ氏は「穴の先には幻の陰謀論の世界があって、そこでさまよい始めると出口は見えず、脱出は難しいわけだ。Qアノン信奉者は自分で自分好みの幻想を作り出し、幻想の世界にはまってしまう。現実と切り離されて、適切な判断ができなくなってしまう状況をうまく表した例えと言える」と述べています。
そして、「反ワクチン運動との合体に警戒を」では、今最も警戒されるのは新型コロナウイルス流行でやや劣勢となっている反ワクチン活動家たちと合体することだろうとして、ナカイ氏は「反ワクチン運動は、もともとワクチンの副作用とされる薬害被害の補償を政府に求め、危険な副作用があるものを拒否する権利を認めてほしいという主張をしていた。だが、安全で効果が高いワクチンが普及して運動の存在価値が薄れるにつれ、だんだんと科学や医療を否定することが目的になってきている」と述べるのでした。
「Qアノンは日本人にも大事な真実を伝えている(Jアノン陰謀論)」の「陰謀論」では、「Qアノンの影響を受けた日本への陰謀論者『Jアノン』」として、アメリカには悪魔を崇拝する小児性愛者たちの秘密結社が存在し、それがディープステート(影の政府)として政府を支配しているという陰謀論の具体的内容を紹介します。カルト宗教研究家で「やや日刊カルト新聞」主宰者の藤倉善郎氏は、「リベラル的な政府高官や米民主党の政治家、ハリウッドスターたちはこの結社に属しており、こうした影の勢力と闘っているのがトランプ大統領(当時)なのだという」と述べています。
悪魔崇拝や小児性愛といった類の主張は前面に出てはきませんでしたが、アメリカを牛耳るディープステートは中国共産党と結託しており、バイデンもその一味だという説を紹介し、藤井氏は「それらと闘うトランプは神に選ばれた大統領であり、中国共産党の脅威を退けるためにはトランプが再選されるべきだ。そんな主張を掲げるデモや街宣が日本全国(主に東京都内)で2020年11月から翌年1月までの間に少なくとも十数回も展開された。Qアノンの影響を受けた日本の陰謀論者『Jアノン』たちである」と述べます。
Jアノン陰謀論の「真相」の「路上の主力は2つの宗教勢力」では、Jアノンには多くの団体が入り乱れていてわかりにくいのですが、大まかに2系統に分けることができるといいます。1つは、サンクチュアリ協会系。サンクチュアリ協会とは、霊感商法や正体を隠していの偽装勧誘が問題視されている統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の分派で、「7男派」とも呼ばれます。2012年に死去した統一教会の教祖・文鮮明の7男・亨進氏を直接の指導者として設立された教団です。亨進氏は2021年1月6日の連邦議事堂襲撃事件の日にも、連邦議会を取り囲むトランプ支持者たちの抗議活動に参加しているそうです。そして、もう1つの宗教勢力は、大川隆法氏が主宰する「幸福の科学」を中心とする幸福の科学系です。
サンクチュアリ協会が統一教会から離脱するより前の2010年、幸福の科学・大川隆法氏は、当時存命中だった統一教会教祖・文鮮明の守護霊を呼び出したと称してその言葉を記録し、書籍『宗教決断の時代 目からウロコの宗教選び(1)』として出版しました。藤井氏は、「文鮮明を地獄に住む蜘蛛であるかのように扱う等の内容を含んでいたことから、統一教会は幸福の科学に対して2度にわたって抗議文を送り、謝罪と訂正を要求。幸福の科学はこれを拒否し、2014年にも大川隆法氏が別の著書『忍耐の法』で、文鮮明がイエス・キリストについて『偽物である』としているかのように述べたとして、統一教会は3度も幸福の科学に抗議書を送りつけた。ここでも幸福の科学は謝罪と訂正を拒否している」と述べます。
「2020年アメリカ大統領選挙で民主党側が大規模な不正を行った」の「真相」では、米国現代史研究家の奥菜秀次氏が「なぜ2020年になったら突然空前レベルの選挙不正システム構築が可能になったのか。全米で数千人いる選挙管理人(公務員でもある)の目を盗んで、バイデン派はどうやって不正準備を行ったのか。トランプ派が言う不正が事実なら、とんでもない規模の準備が必要だが、なぜ事前に陰謀の計画が漏れなかったのか」」という疑問について、「郵便局員から選挙管理人までというと、全米各州に渡っており、地域的に東西南北に散らばっている。職種も統括も管理も異なる数多くの組織の上から下まで、バイデン派の息がかかるようにしないと、隠蔽もうまくいかない。そんな陰謀は現実的に不可能だ」と述べています。
第2章「私たちの生活に関わる陰謀論」では、世に流通しているさまざまな陰謀論が取り上げられていますが、「東日本大震災は『人工地震』によって起こされた!?」の「陰謀論」では、「日本攻撃のための人工地震・津波実験が行われていた」として、「例えば、日本では、昭和初期から人工地震が何度も起こされており、その様子が新聞記事でも報じられていた。また、人工地震を起こすことが可能な、いわゆる『地震兵器』も、1976年にはその使用を禁止する条約が国連総会で採択されている。日本も1982年にこの条約に加入しており、外務省のウェブサイトでは条約文を確認できる」と述べています。
さらに2005年にはアメリカ軍から機密文書が公開され、第二次世界大戦中の1944年に、アメリカ軍とニュージーランド軍が共同で行っていた人工地震・津波実験が明らかになったといいます。これは「プロジェクト・シール」と呼ばれるもので、当時、アメリカの敵国であった日本を攻撃するため、密かに行われていた実験であると指摘し、奥菜氏は「同プロジェクトの文書によれば、爆弾を爆発させることで、地震と30メートル超の大津波を発生させることに成功。爆弾は海底プレートから8キロ以内に仕掛ければ、1年以内に狙った場所で地震と津波を起こせるという。日本人は知らなかったが、昔から日本は人工地震や人工津波の標的にされていたのだ」と述べます。
「私たちは『思考盗聴テクノロジー』を使った『集団ストーカー』に狙われている」の「陰謀論」では、「集団ストーカーの犯人は宗教団体や警察か」として、エレクトロニック・ハラスメントとかマイクロウェーブ・ハラスメントと呼ばれるものがあることを紹介し、SF作家の山本弘氏が「ある集団が最新の『思考盗聴テクノロジー』を用いて、特定の市民を攻撃し、苦しめているというものだ。彼らは被害者の心の中を遠隔から読み取る一方で、下品な内容や中傷するような内容の声を、被害者の頭の中に『放送』する。『殺す』『死ね』などと脅迫してくることもある。また、被害者の肉体を操って、痛み、かゆみ、めまい、心臓の動悸、下腹部への異常な感触を起こしたりもする。こうした集団は、いわゆる『集団ストーカー』と同一視されることが多い」と述べています。
「真相」の「『思考盗聴』の訴えは1930年代から存在していた」では、何者かに心を読まれているとか、電波が聞こえるという訴えは、近年になって生まれたものではなく、1930年代からすでに存在していたのだ。CIAもまだない時代であると指摘し、山本氏は「ラジオのなかった時代には、頭に響く声は神や悪霊のものと解釈されただろう。牧師のジョージ・トロスは、1714年に出版された自伝の中で、自分が20代から無数の幻影や声につきまとわれてきたことを語っている」と述べるのでした。
第3章「『M資金』はGHQが接取した財産などをもとに運用されている秘密資金」の「陰謀論」では、「日銀のダイヤ34万カラット以上が消えた!」として、その行方に関連して1960年代からある噂がささやかれており、それが「M資金」と呼ばれる闇の超巨大融資システムであると紹介されます。歴史研究家の原田実氏は、「M資金の『M』はGHQの経済科学局長として資産を管理していたウィリアム・マーカット少将の頭文字をとったものとする説が有力だが、アメリカの隠し資産として『メリケン・ファンド』の隠語で呼ばれたからという説などもある」と述べています。また、「西ドイツのマルク債や米ドルも利用された」として、「ウィリアム・マーカット少将は旧日本軍が隠匿していた資産の一部(もしくは大部分)をストックした。そして財閥解体で宙に浮いた資本やアメリカ政府の反共産主義諜報活動予算からの出資などと併せ、日本の戦後復興(ひいては日本の共産圏入り阻止)のための秘密予算を組んだ」と書かれています。
「ロッキード事件はアメリカが仕組んだ田中角栄つぶしの謀略だった」の「真相」では、原田氏が「ロッキード事件発覚当時のマスコミはほぼ一致して、田中角栄は金権の権化たる巨悪、検察はその巨悪と戦う正義というわかりやすい図式で事件を報じた。庶民は検察およびその図式を作ったマスコミを支持し、巨悪の逮捕に溜飲を下げたわけである。その先例が以後の政治・経済犯罪疑惑においてもマスコミ報道の定番を形成し、今にいたっているというわけだ。その説に基づくなら、検察による冤罪を生みかねないスタンドプレーのきっかけを作ったという意味で、ロッキード事件をめぐる『陰謀』は今もなお悪弊を残し続けているということになる」と述べています。
また、「通常の外交手順だけで米国の主張が通る」では、日本は安全保障だけでなく食料・エネルギーなど国民生活の根幹までアメリカと、アメリカを中心とする「国際社会』に依存していることが指摘されます。さらにいえば日本は戦後いきなりアメリカ頼みになったわけではなく、近代化以降、ほぼ一貫してアメリカとの交易は日本経済の基幹となっていたとして、原田氏は「1941年から1945年にかけて、アメリカと交戦状態だった時期の日本が、民需・軍需ともあっさり物資欠乏に陥ってしまった原因は輸入・輸出ともアメリカに依存する貿易構造にあったのである」と述べています。
もちろん、田中角栄を含む歴代の総理大臣は、その力関係の中でできるかぎり日本側の要望を通すために努力してきました。しかし、日本がアメリカに頭を押さえられているという事実は覆しようがないとして、原田氏は「その閉塞感ゆえに、日本国民の間には、日本史の中に、アメリカと果敢に戦った英雄を見出そうとする心理が生じやすいのかもしれない。山本五十六しかり、戦艦大和しかり……。田中角栄は、かつて日本で最も人気があった政治家の1人であり、失脚後にアメリカとの関係で叩かれた人物でもあった。だからこそ、彼は陰謀の犠牲者と噂されることで、一部の日本国民の胸中においてアメリカと戦った英雄の列に加えられたのかもしれない」と述べるのでした。
第4章「アポロとUFOをめぐる陰謀論」の「アメリカ政府は『月面に異星人が住んでいる』という事実を隠蔽している」の「真相」では、「大気の状況や光学的現象で、奇妙な地形に見えただけ」として、AIOS創設会員で超常現象情報研究センター主任研究員の羽仁礼氏が「月面にある、建造物にも見えるような物体の目撃報告は、グルイテュイゼン男爵の発見をはじめとして無数にある。しかし、地上からの望遠鏡を用いた観測については、望遠鏡の精度が低かったため画像がぼやけた、あるいは大気の状況やレンズの反射などによって生じた光学的現象により、普通の地形が奇妙なものに見えたのだとも考えられる。さらに、観測者の先入観によって、自然の地形を人工物として認識することもある」と述べています。
第5章「世界史の中で語られた陰謀論」の「ナチスによるガス室でのユダヤ人虐殺はなかった(ホロコースト否定論)」の「真相」では、「群の到着時に遺体は残っていなかった」として、奥菜秀次氏が「〈ガス殺〉遺体の解剖・検死云々だが、ガス室稼働中にソ連軍が到着し施設を占領したなら解剖や検死もできたかもしれない。だが、運営役の親衛隊がソ連軍の侵攻を察知して証拠隠滅を図り、ガス室の稼働を停止し破壊した。つまり、軍が到着した時点で〈ガス殺〉遺体は焼却され残っていないため、検死も解剖も不可能だったのだ。ただし、〈ガス殺〉された女性囚人の毛髪が生地作成用に残されており、そこから青酸が検出されていて〈ガス殺〉の証拠となっている」と述べます。
また、「命令書が存在しない例は多い」として、アドルフ・ヒトラーによる〈ガス殺〉命令書が存在しないのは事実だが、ソ連のスターリン首相やカンボジアのポル・ポト首相、中国の毛沢東主席ら、数百万人の自国民の大量虐殺や処刑、大量殺人につながった武装闘争等を行った国のトップの命令書や指示書が存在しない例は珍しくはないとして、奥菜氏は「また、強制収容所の運営は、ガス室ができる前にヒトラーの元警護隊で私兵でもある親衛隊が統括運営することになったため、命令系統が軍とは異なる。親衛隊はヒトラーの指示書がなくとも命令で動けたため、『指示書がない行動をしたら違反』という概念は元からないのだ」と述べています。
さらに、「焼却炉におかしなところはなかった」として、「陰謀論」の「大量殺害に続く大量火葬をするには火葬炉が少なすぎる。連続火葬に必要な燃料もない」に言及する奥菜氏は、「通常の火葬場では一度に1人焼却する。だが、それは慣習に基づく使用法である。ガス室近くの火葬場では複数遺体を一度に焼却するので、『火葬炉が少なすぎる』ことも『必要な燃料がない』こともないのだ。また、通常の火葬場で焼かれる遺体は脂肪分の少ない老人や病死者が大半だが、アウシュヴィッツでは〈ガス殺〉直後の脂肪分の多い遺体が大半だった。それで、燃えやすく、燃料は少なくて済んだのだ。過剰な肥満体が多いアメリカで、遺体焼却時に大量の脂肪が燃焼し、火葬炉が過熱状態となって炉から火が噴き出したことがあった。だが、アウシュヴィッツでは焼却炉から流れ出た脂肪を燃料に使用するケースもあった。ナチス側の焼却炉設計時の機能算定書類では、実際の稼働推定より多い焼却可能数が出ていた。つまり、ナチスの焼却炉にはおかしなところは何もなかったのだ」と述べるのでした。
「米国同時多発テロは自作自演によって引き起こされた(9・11テロ陰謀論)」の「真相」では、「爆弾炸裂なら、数万人が証言するはず」として、奥菜氏が「世界貿易センタービル付近で本当に爆弾が炸裂したなら、『爆弾炸裂音を聞いた』という証言がマンハッタン島全土の住民の数万人から出てくることは間違いない。しかし証言は消防士やレポーター、地下にいたウィリアム・ロドリゲスも含め、ビルの近くにいた人たちからしか出ていない。しかもわずか100人足らずだ。そのことこそ、爆弾炸裂がなかった証拠だと言っていいだろう。要は、爆破解体時の爆音を聞き慣れた人でないと、轟音が爆弾炸裂かどうか判別するのは無理なのだ。さらに言うと、爆弾炸裂時には閃光が発生し空気振動も起きるが、世界貿易センタービル崩壊時にはそれもなかった」と述べています。
また、「『ペンタゴンの壁の穴』は最初にぶつかった部分の大きさ」として、「ボーイングが突入したというが、ペンタゴンの壁に開いた穴が小さすぎる」という、理解しやすい話は9・11陰謀論を蔓延させたことを紹介しつつも、奥菜氏は「だが、航空機の機体は飛行のため空気抵抗を減じる必要があり、水平尾翼は(垂直尾翼も)機首に近い方が短く(低く)デザインされている。そのため、ぶつかる相手が機体より柔らかくない限り、最初に短い(低い)部分がぶつかり、壁が機体より硬く尾翼では壁を砕けないため、穴は機体の左右の大きさにはならないのである。事実、目撃者によれば航空機は尾翼が折りたたまれる形で建物内に突入していったという」と述べます。
最後に、「ダイアナ妃はイギリス王室に謀殺された」の「真相」では、「有名人が死ぬと陰謀を信じる人が増える」として、ナカイサヤカ氏が「ダイアナ妃殺害陰謀説は、愛するダイアナを突然失った人々が味わった大きな喪失感を背景にして、生まれてきたことがわかってきた。人は喪失による衝撃には、まず否認することで対処しようとする。夭折した有名人が実は生きているという伝説は、大概この否認によって生まれる。『こんなに重要な人がただの事故や、そのような犯罪で死ぬはずがない』と思う人は、陰謀を疑う」と述べるのでした。世に陰謀論を真に受けて信じる頭の悪い人は多いですが、そういった困った人たちを論破のに本書は最適のテキストだと言えます。