- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2138 読書論・読書術 『人生の土台となる読書』 pha著(ダイアモンド社)
2022.05.31
『人生の土台となる読書』pha著(ダイアモンド社)を読みました。「ダメな人間でも、生き延びるための『本の効用』ベスト30」というサブタイトルがついています。著者は、元「日本一のニート」。1978年生まれ。大阪府大阪市出身。京都大学総合人間学部を24歳で卒業し、25歳で就職。できるだけ働きたくなくて社内ニートになるものの、28歳のときにtwitterとプログラミングに出会った衝撃で会社を辞めて上京。それ以来、毎日ふらふらと暮らしているとか。シェアハウス「ギークハウスプロジェクト」発起人。フジテレビ「ザ・ノンフィクション」に4年連続で出演。主な著書に『しないことリスト』『ニートの歩き方』などがあります。
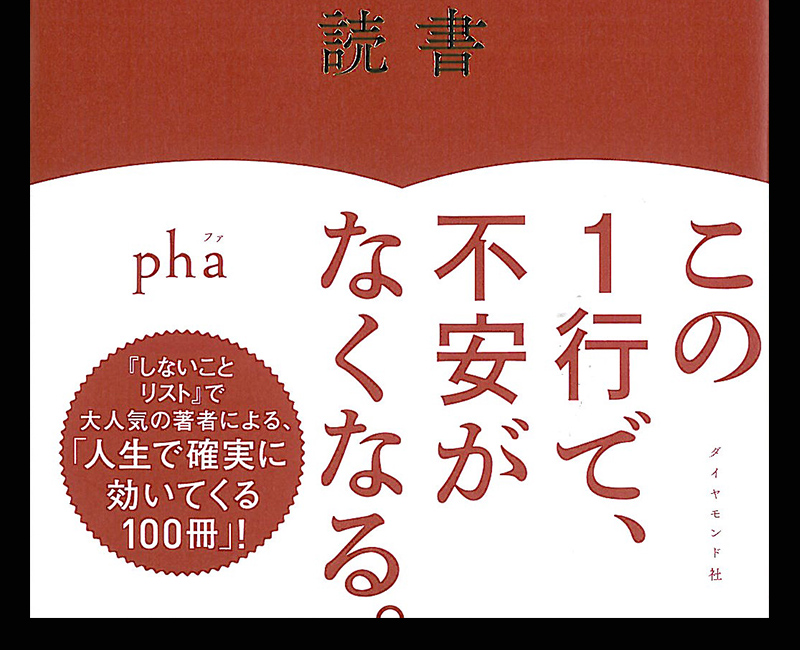 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「この1行で、不安がなくなる」「『しないことリスト』で大人気の著者による、『人生で確実に効いてくる100冊』!」と書かれています。また、帯の裏には「読書は、同調圧力と戦うのに役に立つ。」「身の回りにいる人たちよりも、会ったこともない人が書いた本のほうが、自分のことを理解してくれている、ということがよくある。」「本は、いつだって、孤独な人間の味方なのだ。」と書かれています。さらに、カバー前そでには「何度も読み返してボロボロになった本が、あなたの心を守ってくれる。」とあります。
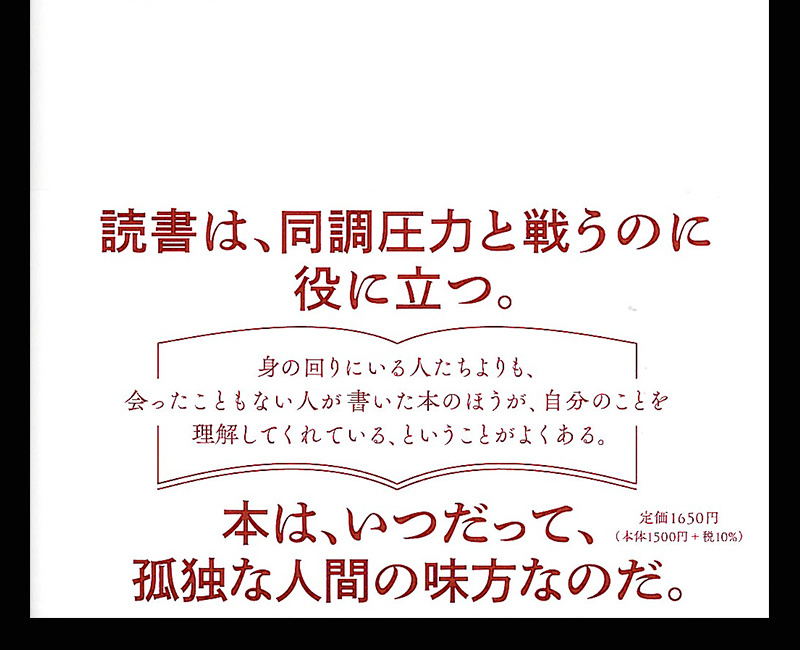 本書の帯の裏
本書の帯の裏
アマゾンの「出版社からのコメント」には、以下のように書かれています。
「☆テレビやネット、ベストセラー『しないことリスト』などで大人気のpha氏。★『一般的な生き方のレールから外れて、独自のやり方で生きてこれたのは、本を読むのが好きだったからだーー』☆本書では、人生を支える『土台』になるような本の読み方を、30個のエピソードと100冊の本で紹介する」「読書には、2つの種類がある。『すぐに効く読書』と、『ゆっくり効く読書』だ。一見、すぐに効くほうがよさそうに思うけど、そうとは限らない。時間はかかってしまうけど、遅れてじわじわと、しかし確実に大きく人生を変えてくれる−−−−そんな読書のやり方を紹介しようと思う。本が僕の人生を支えてくれた。もし、本がなかったら、僕の世界はすごく狭いままで、自分に自信も持てなくて、つまらない人生を送っていただろう。読書は、周りの同調圧力と戦うのに役に立つ。自分だけが違う意見を持っているとき、たった1人で立ち向かっていくのは大変だそんなとき、自分を守ってくれるのが本だ。本はいつだって、孤独な人間の味方なのだ」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章 読書で「人生の土台」をつくる
1章 読書で「ロールモデル」を見つける
2章 読書で「世界を動かすルール」を知る
3章 読書で「日常の暮らし」をひっくり返す
4章 読書で「自分のころ」を誰よりも知る
「おわりに」
本書の冒頭には、「読書には、2つの種類がある。『すぐに効く読書』と、『ゆっくり効く読書』だ。一見、すぐに効くほうがよさそうに思えるけれど、そうとは限らない時間はかかってしまうけれど、遅れてじわじわと、しかし確実に大きく人生を変えてくれる――『すぐに効く読書』の例は、仕事術やライフハックなどの実用書だ。そういう本を読んだあとは、『自分も前向きに頑張ってみよう』という気持ちになる。しかし、効果が薄れていくのも速い。一瞬だけ元気になる栄養ドリンクみたいなものだ。『すぐに効く読書』は、今の状況をちょっとだけ改善するのには有効だ。しかし、大きく人生を変えるのには向いていない」と書かれています。
根本的な生き方を変えるためには、「ゆっくり効く読書」が必要になってくるとして、著者は「『ゆっくり効く読書』の例は、一見、実用性がなさそうな、小説やノンフィクションや学術書などだ。『すぐに効く読書』が今まで知っている枠組みの中で役に立つものだとしたら、『ゆっくり効く読書』は、その枠組み自体を揺さぶって変えてくれるものだ」と述べます。また、現代は物事の移り変わるスピードがものすごく速いとして、著者は「新型コロナウイルスが流行する前と後で世界の様子がガラッと変わってしまったように、数年後がどうなっているかを予想することも難しい」とも述べています。
そして、今の時代は単に何かを知っているだけではすぐに時代遅れになってしまうという著者は、「知識を詰め込むだけではなく、根本的に物事を考えるための価値観や枠組みを持つことが必要だ。そして、根本的に物事を考えるための価値観や枠組みを手に入れるためには、『すぐに効く読書』ではなく『ゆっくり効く読書』が必要なのだ。時代が変化しても価値を失わないような『知識や思考能力』。世間の動きに流されずに、自分の考えを持って生きるための『自信』。信じていいものと信じてはいけないものを見分けるための『バランス感覚』。『ゆっくり効く読書』は、そんな人生の土台を得るための読書だ」と述べます。
序章「読書で『人生の土台』をつくる」の01「人生を『本当に変えたい』から本を読む」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「本を読む人はみんな、多かれ少なかれ、自分の今の状況を何か変えたいと思っている人だそれは、退屈な時間をちょっと充実させたい、と思っているだけの人かもしれない。もしくは、毎日がつらくて、何とかして今の状況から抜け出したいと思っている人かもしれない。『変えたい』という気持ちにはいろいろあるだろうけれど、何かを変えたいと思っていることは確かだ」
何も不満がない人は本を読む必要はないという著者は、「読書というのは、どこにあるのかわからない現状からの抜け道を、手探りで探すような行為なのだ。読書をすると、なぜ、世界を変えることができるのか。その理由は、世界は言葉でできているからだ。言葉でできた世界を変えるためには、別の言葉をぶつけるしかない」と述べます。
「『同調圧力』と戦うために」では、読書は周りの同調圧力と戦うのに役に立つと指摘し、著者は「多くの人たちの中で自分だけが違う意見を持っているとき、たった一人で立ち向かっていくのはなかなか大変だ。そんなとき、自分を守ってくれるのが本だ。身の回りにいる人たちよりも、会ったこともない人が書いた本のほうが、自分のことを理解してくれている、ということがよくある。読書はいつだって、孤独な人間の味方なのだ」と述べるのでした。
03「『知識を得ること』の本当の意味」の冒頭では、本というのは人生のシミュレーションツールみたいなものだとして、著者は「本を読むと、行ったことのない国や、普段関わることのない人の人生や、やったことのないような大失敗を、まるで自分で体験したかのように感じることができる。人は本を読むことで、「自分がこういう状況になったらどうするか」ということを頭の中でシミュレーションする。一度しかない人生を、本の中なら何千回も生きられる。そして、その内容を、自分の人生に取り入れて生かすことができる。本を読めば読むほど、人生の中での行動の選択肢が増える。つまり、読書によって人生の自由度が上がっていくのだ」と書きだしています。
1章「読書で『ロールモデル』を見つける」の04「自分と同じ『ダメさ』を持った人を見つける」の冒頭を、著者は「成功した人の話を読むと、爽快でスカッとする。だけど、自分もマネをして同じようにやってみようとしても、そんなに簡単にうまくはいかない。たいていの人は、天才ではないし、すごい人間でもない。ダメな部分を抱えて、悩んだり失敗したりしているのが大多数の人間だ。だから、本当に人生の参考になるのは、成功した人のことを書いた本ではなくて、たくさん失敗をしたことのある『ダメ人間』について書いた本だと思うのだ」と書きだします。
05「どんな難しいことも『簡単な言葉』で考えることができる」の冒頭を、著者は「難しいことを難しい言葉で説明するのはそんなに難しくない。本当に頭のいい人というのは、難しいことを簡単な言葉で説明することができる人のことだ。僕はそのことを、橋本治から学んだ」と書きだし、橋本治の文章の特徴は、複雑なことを簡単な言葉で、粘り強く考え続けるところにあると指摘します。
たとえば、著書『「わからない」という方法』では、橋本治は「『わからない』をスタート地点とすれば、『わかった』はゴールである。スタート地点とゴール地点を結ぶと、『道筋』が見える。『わかる』とは、実のところ、『わからない』と『わかった』の間を結ぶ道筋を、地図に書くことなのである。『わかる』ばかりを性急に求める人は、地図を見ない人である。常にガイドを求めて、『ゴールまで連れて行け』と命令する人である」と書きます。
この文章を少しまどろっこしいと感じる人もいるかもしれないとしながらも、著者は「だけど、これは思考の道筋をきちんと一つ一つたどっているからこんな文章になっているのだ。橋本治はいつも、いきなり結論を述べて終わりにするのではなく、どういう道筋でその結論にたどり着くかという経緯を示してくれる。物事を考えるというのはどういうことかを、丁寧に読者に教えてくれているのだ。そんな面倒なことをやっていたのは、読者に対して本当の意味で親切な人だったからなのだと思う」と述べています。橋本治の文章はわたしも好きですが、確かにそうですね。
「『外の世界』への興味」では、人は自分の今の環境に不満があるとき、そこから抜け出すための手がかりとして、誰かに恋をするとして、著者は「思春期には、なぜみんな恋愛をするのだろうか。子ども時代は家庭の中にいればそれで満足だった。だけど、人は成長していくにつれて、家庭が与えてくれるものだけでは物足りなくなってくる。新しい自分の可能性を探そうとして、外の世界に興味を持つ。それが恋愛につながっていくのだ。つまり、恋愛とは、人生で道に迷ったとき、新しい可能性が恋愛という皮をかぶってやってくる、というようなものなのだ」と述べます。うーん、これはちょっと極論のようにも思いますね。現在の環境に満足していても、人は恋愛をする生き物ではないでしょうか?
06「いい読書はアイデンティティを奪うほど嫉妬させる」の「『制約』が人を自由にする」では、短歌が取り上げられます。短歌というのは、言葉によってこの現実の見え方を変化させようとする呪文であるという著者は「それは小説家が小説によって現実とは別の世界を作り出すのとは少し違う。小説家は、小説は小説、現実は現実、というのをちゃんと区別している。だけど短歌は、小説のように現実とは別の世界を作るのではない。自分が生きているこのつまらない現実の解釈を、直接書き換えてしまおうという大それた祈り、それが短歌だ」と述べています。これは納得ですね。
そして、短歌の中には葛藤がないといいます。短歌は「自分はこれをこう見てこう感じた」というのを主張するだけだとして、著者は「それは自分が見たものや自分の感情を肯定することで、つまりは自己肯定の作業だ。自分への疑いがない分、小説を書くことよりも短歌を詠むことのほうが、自己中心的で不遜な行為なんじゃないかと思うことがある」と述べるのでした。わたしも歌を詠みますが、著者の短歌論はとても鋭いと思いました。
08「『挫折した話』『負けた話』こそ、教科書になる」の冒頭を、著者は「人が挫折する話を読むのが好きだ。ニュースや映画などでは、勝った人間の話ばかりが取り上げられる。だけど、その1人の勝者の裏には、負けて悔しい思いをしている人がたくさんいるはずだ。僕は、そちらのほうに興味が湧く。努力をしていた人間が勝つのは、ベタすぎてあまり深みがない。『努力をしてきたにもかかわらず、勝てなかった』。これが人生だと思う。生きるというのは大体、挫折をすることだ。勝ちよりも負けのほうにこそ、人間の複雑で深い感情が表れるものだし、勝つことよりも負けることのほうが、人間を成長させるずっと勝ってばかりで挫折を経験していない人間とは、あまり仲良くなりたくないなと思う」と書きだしています。
2章「読書で『世界を動かすルール』を知る」の11「『社会学』は、自己責任論から解き放ってくれる」では、たった1冊の本を読むことで、世界の見え方がガラッと一変してしまうことがあるとして、著者は「読書というのは、『物事を考えるときの新しい視点』を自分の中にインプットしてくれるものだからだ」と述べ、ラクな気持ちで生きるのに役立つ、「自己責任を弱めて、ダメな自分を肯定するための視点」を3つ紹介します。その3つの視点とは、「社会学」と「脳科学」と「進化論」です。
「自分のせいか、環境のせいか」では、生存者バイアスから逃れるために、著者はいつも「自己責任は50%」と考えるようにしていることを告白し、自己責任が100%というのは人間に厳しすぎる。とはいえ、自己責任は0%ですべて環境のせいというのもちょっと乱暴だ。個人の頑張りで変えられる部分はあるし、自力でなんとかしたい気持ちは大切だ。だから、『自己責任は50%』くらいがちょうどいいと思っている」と述べます。また、「『選んでいる』じゃなく『選ばされている』」では、著者がそうした考え方になったのは「社会学」の影響が大きいとして、「社会学というのは、人間を個人の単位で見るのではなく、社会全体の視点から説明しようとする学問だ」と述べています。
「人間には『パターン』がある」では、「人間は環境によってかなりの部分を決められている」という考え方は最も重要であり、それは他者への理解や優しさを生み出すということだといいます。また、「学問で人は優しくなれる」では、人間には、自分と違うタイプの人に対する拒否反応があることを指摘し、著者は「それは僕たちが部族社会で生きていた頃に脳の中に刻み込まれた性質なので、そう思ってしまうこと自体はしかたがない。しかし、人間は知識を得ることで、自分と異なる他者への理解が生まれ、寛容さを持つことができる。それが勉強や読書の大事な効用なのだ」と述べます。
社会学の次に、脳科学が重要だといいます。12「脳科学が『人間はただのアルゴリズムだ』と教えてくれる」では、一条真也の読書館『ホモ・デウス』で紹介したイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリの世界的ベストセラーに書かれている例をあげて、「ある実験では、人間の脳に電極を埋め込んで微弱な電流を流すと、うつ病の症状が治まるという結果が出ているらしい。また別の実験では、脳に磁気を流しながら兵士向けの戦場シミュレーターに入ると、まったく動揺せずに冷静な気持ちで、襲いかかってくる20人の敵兵士を正確に撃ち倒すことができるようになったという。人間の脳が操作可能になってくると、『人間の考えることが一番尊い』という信仰も揺らいでくる。そんなものは、外からの刺激でどうとでも変わるものだからだ」と書いています。
社会学、脳科学と並んで重要なのが進化論です。
14「『進化心理学』で人間を俯瞰して見る」では、進化論とても画期的で強力な理論だったので、あらゆる学問のジャンルに影響を及ぼして、さまざまな新しい学問が生まれたことが指摘されます。「自分が悪いのではなく『脳』が悪い」では、著者は「進化心理学の例を1つ出すと、人間が安定して維持できる人間関係の数は150人くらいだという説がある。それ以上の数の人間関係は、あまりきちんと気にかけることができないという限界が、どうやら脳にはあるらしい。その理由は、もともと人間が150人くらいの集団の中で暮らしていたからだ。この数は、ダンバーという人が提唱したので『ダンバー数』と呼ばれる」と述べています。
「『助け合い』は人間だけなのか」では、利他行動、つまり「人間がなぜ他者を助けるのか」ということには進化的な理由があるといいます。要は、「困っている奴を助けたら、自分が困っているときに助けてもらえる」からだとして、著者は「助け合ったほうが、それぞれが孤独に生きていくよりもお互いにメリットがあって、生き残りやすい。助け合いをしない遺伝子を持っている個体は生き残りにくかったので、滅びてしまった。だから、今残っている人類はみんな多かれ少なかれ、助け合いを好むようになっている」と述べます。
3章「読書で『日常の暮らし』をひっくり返す」の21「『お金以外の人生の価値』を持っておこう」の「今も存在する『貝殻のお金』では、貝殼のお金を法定通貨として使っているパプアニューギニアの「トーライ」という社会の話を持ち出して、著者は「貝殻のお金を使っているというと、すごく未開な生活のようなイメージを持ってしまうけれど、そうではない。ちゃんとした町もあって、普通の貨幣もちゃんと流通しているところで、貝殻のお金も使われているのだ」と述べています。
貝殻のお金は、「タブ」と呼ばれていて、普通のお金とは別の意味を持っています。会社などで労働をして受け取るのは普通のお金ですし、買い物をするのも普通のお金です。著者は、「タブはどう使われるかというと、買い物をすることもできるし、交換所でタブと普通のお金を交換することもできる。しかし、タブのメインの使い道は他にある。それは、結婚式や成人式や葬式など、冠婚葬祭のときに贈るものとして使われるのだ」
「『人望の多さ』をあらわす通貨」では、この社会では「タブをたくさん持っている」ということは、「親戚や地域の中で人望がある」ということを表しているとして、著者は「彼らにとっては会社で仕事をして普通のお金を稼ぐことよりも、地域や親戚に貢献してタブをたくさん貯めることのほうが大切とされている。ちなみに、貯めたタブは、その人が死んだら全部、葬式のときに来た人に配ってしまう。葬式のときにたくさんタブが集まっていると、「あの人はすごい人物だったんだな」とみんなに尊敬される。そうやって死ぬのが最高に名誉なことなのだ」と述べます。唯葬論的な経済と言えるかもしれません。
「人間関係を取るか、自由を取るか」では、わたしたちの社会でも、お金以外の名誉とか人望といった価値基準はあるが、それに対応するタブのようなものはないとして、著者は「だから、社会からの尊敬が欲しいお金持ちは、いい家に住んだり、いい車に乗ったり、もしくはどこかに多額の寄付をしたりして、社会に認めてもらおうとする。タブを持たない僕たちは、冠婚葬祭のときには普通のお金の中からキレイな新札を探して特別な袋に入れて贈るという、面倒くさいことをしないといけない。その点は、トーライ社会のほうがよくできているなと思う」と述べます。
ただ、コミュニティの中での名誉や人望を表すタブが大事にされる社会は、親戚や地域などの人間関係がとても密な社会だという見方もできるとして、著者は「そうしたしがらみを断ち切って、すべてをお金で解決できるほうが気楽で自由でいい、と考える人も多いだろう。お金という1つの基準ですべてが判断される資本主義社会というのは、親族や地域とあまり関わらず、自由に生きられる社会のことでもあるのだ」との述べるのでした。
27「『意見の違う人間がいる』意味を考える」の「『ワイドショー』が生まれたわけ」では、そもそも、人はなぜ正義を求めるようになったのだろうかと読者に問いかけ、著者は「人は、助け合ったほうが生存に有利だから、助け合いを行うようになった。だけど、ただ単に他者を助けるだけだと、助けてもらうばかりで人を助けないずるい奴ばかりが得をしてしまう。これでは助け合いは成立しない。なので、ずるい奴は助けないという対策が必要になった」と述べています。これも非常に納得ですね。
小さい集団なら、誰がずるい奴かはわかりやすいと言えます。しかし、人間の場合は、社会が大きくなりすぎました。だから、自分が見たものだけで判断するのではなくて、「あいつはずるい奴だ」という人から聞いた話を参考にする必要ができたとして、著者は「これが噂話やゴシップの起源だ。人間はなぜこんなに人の噂話が好きなのか。なぜ、ワイドショーや週刊誌には誰かのゴシップばかりが取り上げられるのか。それは、ずるい奴を排除することが、人間の集団には必要だったからなのだ。ずるい奴を排除しないと、人間の集団は弱ってしまうから、人間はずるい奴を叩くとドーパミンが出て気持ちよさを感じるように進化してきたのだ」と述べます。人気のYouTube動画などを見ると、確かに他人の噂話が花盛りですね。
pha著(ダイアモンド社)「はたして正義は本当に正義か」では、著者は「正しい物語は危険だ。わかりやすくて気持ちがいいから、みんな信じ込みたがってしまう。そして暴走を始めてしまう。本当は、世の中に絶対に正しい物語なんていうのはないのだ。大体の場合は、みんなある程度正しくて、ある程度間違っているという、そんな曖昧な話ばかりだ。そんなわかりにくくてフニャフニャしたコンニャクみたいなのが、この世界だ。正しい物語を求めてしまうのは、曖昧さに耐えられない人間の心の弱さなのだ」と述べるのでした。読書論の類はたくさん読んできたわたしですが、本書には何とも不思議な味わいがありました。社会学・脳科学・進化論の3つの視点で、さまざまな物事の本質を読み解いていくのは刺激的でしたし、多くの読者は3つの視点を使いたくなるのではないでしょうか。