- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2118 プロレス・格闘技・武道 『プロレス社会学のススメ』 斎藤文彦&プチ鹿島著(集英社)
2022.03.29
『プロレス社会学のススメ』斎藤文彦&プチ鹿島著(集英社)を読みました。知的好奇心を最高に刺激してくれる名著でした。「コロナ時代を読み解くヒント」というサブタイトルがついています。斎藤氏は1962年東京都杉並区生まれ。プロレスライター、コラムニスト。一条真也の読書館『プロレス入門』、『ブルーザー・ブロディ 30年目の帰還』、『忘れじの外国人レスラー伝』などで紹介した著書があります。鹿島氏は1970年長野県生まれ。大阪芸術大学放送学科卒。「時事芸人」として各メディアで活動中。『教養としてのプロレス』、『プロレスを見れば世の中がわかる』などで紹介した著書があります。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「プロレスを語ることは今の時代を語ることである」「『プロレスライター』&『時事芸人』が最強タッグ結成!」「『KAMINOGE』人気連載がついに待望の初書籍化!!」と書かれています。
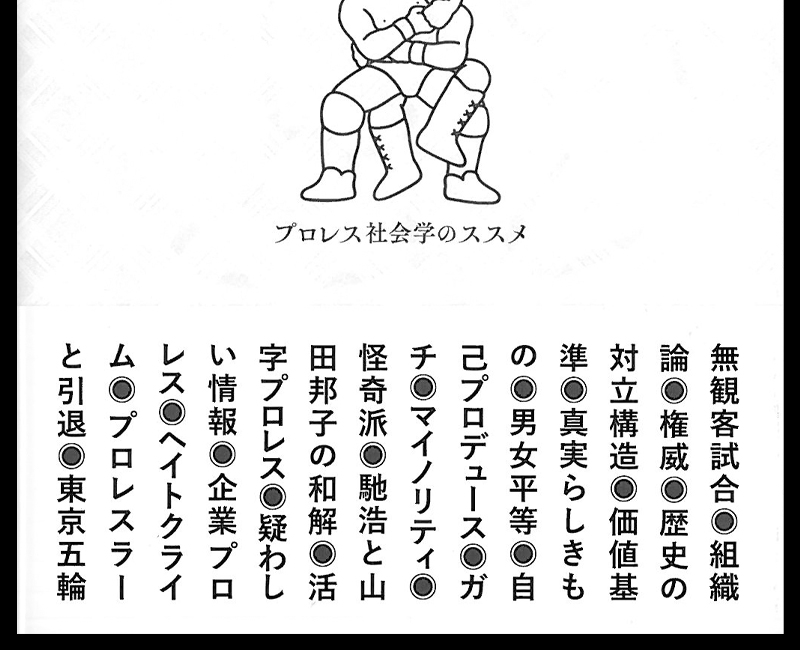 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「無観客試合◎組織論◎権威◎歴史の対立構造◎価値基準◎真実らしきもの◎男女平等◎自己プロデュース◎ガチ◎マイノリティ◎怪奇派◎馳浩と山田邦子の和解◎活字プロレス◎疑わしい情報◎企業プロレス◎ヘイトクライム◎プロレスラーと引退◎東京五輪
本書の「目次」は、以下の通りです。
「はじめに」
第1回 プロレスにおける無観客試合
第2回 WWE史から学ぶ”社会集団”
としての組織論
第3回 NWA史から見る”権威”とは
いかにして作られるのか?
第4回 ”権威”とは、歴史の対立構造や
価値基準によって作られる
第5回 情報の確認と検証がされないまま
”真実らしきもの”が作られていくネット時代
第6回 女性の地位向上や男女平等が
叫ばれている現代社会とプロレスの関係性
第7回 “ウォリアーズ世代”はイチから自己プロデュース
ができた時代の最後のスーパースターたち
第8回 “ガチ”という言葉の意味
第9回 プロレスから学んだマイノリティの意識
第10回 アンダーテイカー完全引退で考える
”怪奇派”のルーツ
第11回 馳浩と山田邦子の和解から振り返る
『ギブUPまで待てない!!』
第12回 独自の発展を遂げた
日本の活字プロレスメディア
第13回 プロレスから学ぶ
「疑わしい情報」の取り扱い方
第14回 ”企業プロレス”全盛の
いまこそWCWの歴史を紐解く
第15回 ヘイトクライムとプロレス社会
第16回 プロレスラーと引退
第17回 東京五輪とは何だったのか?
「あとがき」
本書には、わたしの知らなかったこと、面白過ぎるエピソードがたくさん書かれていました。第2回「WWE史から学ぶ”社会集団”としての組織論」では、以下のような会話が展開されます。
斎藤 レッスルマニアの4と5が、トランプ・プラザというドナルド・トランプが経営するカジノホテルで開催されたんですね。だからプロレスファンは大統領になるはるか前からトランプのことを知っていたんです。
鹿島 大統領選でのトランプの演説を見て、「この感じ、どっかで見たな」と思ったら、WWEにおけるビンスのキャラそのままだったっという。
斎藤 実際にトランプは、2007年の『レッスルマニア23』でリングに上がってビンスと対峙しましたからね。ウマガとボビー・ラッシュリーに代理戦争をさせて。
鹿島 ビンスもトランプも‟ヅラ疑惑があって、負けたほうがつるっ禿にされるという、最高の敗戦者髪切りマッチですよね(笑)。大統領選のとき、日本のワイドショーでもさんざんあの映像が使われていましたよ。
1980年代のアメリカン・レスラーの多くはステロイドを使用していましたが、1988年の法改正で医療目的以外では所持をしてもいけないし、処方箋なしに売ったり買ったりすることが重罪になりました。この流れでWWEではハルク・ホーガンに代表されるマッチョなスーパーヘビー級の時代が終わりましたが、レスラーたちは会社の命令でステロイドを打たされていた組織的犯罪の疑惑が生まれ1994年7月、WWEの社主ビンス・マクマホンは逮捕・在宅起訴されます。この件について、斎藤氏は「結局ビンスは証拠不十分で裁判は無罪になって終わったんです。そして今後はこの件に関しての取材も受けないし、コメントもしないと宣言した。だから、そこでステロイド時代が終わったこともまた事実なんですね。ブレット・ハートやショーン・マイケルズがチャンピオンになり、ホーガンはWWEを去ってライバル団体WCWに行った。そこからアメリカマット界は二大メジャーリーグ時代が始まるんです」と語ります。
鹿島氏が「ホーガンが動いたことで時代が動いて、価値観の多様性も生まれましたよね」と言うと、斎藤氏は「ホーガンがWWEに残っていたら、ブレット・ハートとショーン・マイケルズが新し時代のスーパースターになれなかっただけでなく、そのすぐあとのストーンコールドもザ・ロックも出てきていなかったと思います」と述べます。ここで聞き手の堀江ガンツ氏から「新日本も、1989年(平成元年)に猪木さんが参院選に当選してセミリタイアにならなければ、闘魂三銃士が若くして主役になることはなかったのと同じで」と発言があり、それを受けて鹿島氏が「全日本も天龍がSWSに行ったことで、四天王が出てきたわけで、組織ってそういうおもしろさがありますね」と述べています。
本書で最も面白かったのは第3回「NWA史から見る”権威”とはいかにして作られるのか?」の内容です。NWAというのは世界プロレス界の最高権威とされていて、NWAのチャンピオンはプロレスの真の世界ヘビー級王者というイメージがありました。日本プロレス崩壊後は全日本プロレスだけがNWAとのパイプを持ち、ジャイアント馬場はNWA王座に挑戦できるけれども、新日本プロレスのアントニオ猪木は挑戦できないということで、猪木ファンだったわたしは悔しい思いをしていたものでした。しかし、そのNWAは「プロレス団体」ではなく、アメリカ中に点在する大小のプロレス団体がNWAに加盟して、世界チャンピオンをシェアしていました。だからこそ、全日本のようにNWAに加盟しないと自分のところの興行にNWA世界王者を呼べず、なかなか加盟させてもらえなかった新日本は呼べなかったわけです。
そのNWAについて、以下のような会話が展開されます。
斎藤 NWA世界王者ですけど、ボクらの子どもの頃、『ゴング』などの専門誌にNWA世界王者の系譜が載っていましたよね。
鹿島 「第〇代王者は誰」とかですよね。いやもう、たまらなかったです。
斎藤 その系譜には「1908年、フランク・ゴッチがジョージ・ハッケンシュミットとのタイトルマッチで王座を統一して初代NWA世界王者となる」と必ず書かれていましたけど、フランク・ゴッチが獲得した世界王座は、NWAとはまったく無関係なんです。厳密にいうと、その3年前の1905年、G・ハッケンシュミットとトム・ジェンキンスがニューヨークで闘って、勝ったハッケンシュミットを初代世界王者とする学説もあることはあるんです。
この発言にわたしは驚きましたが、さらに斎藤氏は「フランク・ゴッチの統一世界王座はNWAとはまったく別のものです。NWAが立ち上がったのは1948年ですから、戦後のものです。だからフランク・ゴッチだけじゃなくて、ロシアからヨーロッパを経由してアメリカに渡ったジョージ・ハッケンシュミット、1920年代のエド・ストラングラー・ルイス、‟胴締めの鬼”ジョー・ステッカー、1930年代の‟黄金のギリシャ人”ジム・ロンドス。この人たちはNWAとはなんの関係もないんです。でも、その当時の諸派の「世界王座」を保持していた超大物たちであることはたしかで、アメリカでは1920年代、第一次世界大戦が終わって好景気が来た頃にプロレスブームがあったんですね」と述べます。
「そのNWAができる前は、アメリカ各地にチャンピオンがいて、NWAと名の付かない世界チャンピオンもいたんですよね?」と堀江氏が質問すると、斎藤氏は「何人もいました。エド・ストラングラー・ルイスとそのグループが1920年代に全米を統一しようとしたし、ボストンAWAという大きな団体もあって、ジム・ロンドスの時代にも全米を統一しようとした組織が存在した。それぞれ違う団体で。それらはいずれもワールドチャンピオンで、1948年に初めて付けられたわけじゃなくて、ピンキー・ジョージというアイオワのプロモーターがその数年前からすでに使っていた団体名なんです。そのピンキー・ジョージも、NWA創立メンバーのひとりで、「あっ、いいじゃん。その名前にしよう!」ってことでNWAをそのまま使うことになった」と答えています。
それを聞いた鹿島氏が「もう、その時点でルー・テーズも世界チャンピオンだったんですか?」と質問しますが、斎藤氏は「旧NWA王者ルー・テーズと、新NWA王者オービル・ブラウンで統一選をやって、新しい世界チャンピオンを作りましょう、それは素晴らしいビジネスになる」っていう話になったんです。ところが、オービル・ブラウンが自動車事故に遭ってケガをしたことで、統一戦をやることになったんです。1949年11月にルー・テーズがそのまま繰り上がった。そういう系譜を突き詰めていけば、初代NWA世界チャンピオンはルー・テーズから数えるのが正しいのかな、とは思います」と答えています。
そこから、フランク・ゴッチから数えるNWA世界王者の系譜はセントルイスのプロモーターであったサム・マソニックの捏造であったことが明らかになります。斎藤氏が「世界王座のルーツをたどることで年表上はつながりましたということで、マソニックさんには歴史をでっち上げたという感覚はあまりなかったと思います。『ボクらは正統だから、フランク・ゴッチまでさかのぼりますよ』というだけで。それで昭和30年代の日本のプロレスマスコミは、結果的にセントルイスのパンフレットをそのまま翻訳しちゃったんです」と言うと、鹿島氏は「マソニック史観をそのままいただいちゃったわけですね」と語るのでした。もともと力道山が追い求めていたのはNWA王座ではなくて‟世界王者ルー・テーズが持つ黄金のベルト”だったのです。
NWAの正体をめぐる刺激的な会話の最後に、両者は以下のように語り合っています。
斎藤 結局、猪木さんにとってNWA幻想というのは、馬場さんそのものだったような気がします。そのNWAを超えるために、プロボクシング世界王者のモハメド・アリや、柔道金メダリストのウィリエム・ルスカと異種格闘技戦をやったり、IWGPを発案したりしたわけだから。
鹿島 NWA=馬場であり、それ以上の価値を持ってくるという。
斎藤 NWA主流派vs反主流派といったストーリーもすべて、馬場―猪木の対立構造だったんです。日本のプロレス史を形成してきた、馬場vs猪木の対立構造を理解するために欠かせない価値観あるいは価値基準が「世界最高峰NWA」だったんだと思います。
第5回 「情報の確認と検証がされないまま”真実らしきもの”が作られていくネット時代」では、‟超獣”ブルーザー・ブロディに関する興味深いエピソードが以下のように語られます。
斎藤 メルボルンでアンドレ・ザ・ジャイアントをボディースラムで投げてキングコング・ニードロップでフォールしたっていう有名なストーリーがありますね。
鹿島 ありますね。あれも都市伝説なのかどうなのか、ファンにはたまらない逸話ですけど、本当のところはどうなんですか?
斎藤 ブロディ自身も「アンドレをボディースラムで投げて、最後はフォールした」って豪語しているんですけど、映像がないんです。
鹿島 UFOの映像がないのと一緒ですよね。墜落したとは言うけれど、証拠が残されていない(笑)。
それが真実なのかどうか、マニア的な感覚でいくら調べても調べても出てこないと告白した上で、斎藤氏は「だから、あれはきっと伝説なんだろうなとボクは思います。ローラン・ボックvsアンドレ・ザ・ジャイアントの映像がないのと一緒で」と言います。すると鹿島氏が「だけど、そういう伝説が作られるとき、かならず利用されるアンドレもまた凄いですよね」と言えば、斎藤氏は「それはアンドレという存在自体が生きる伝説だからでしょうね。「俺はアンドレをフォールした」って、ブロディが勲章として語るくらいですから」と言います。そして、ブロディは「普通のキングコング・ニードロップでは倒せないから、トップロープからのニードロップを決めたんだ」とディテールにもこだわっていたことを指摘すると、鹿島氏は「ファンとしたら、そういう幻想に乗っかる気持ちよさっていうのもありますからね」と述べるのでした。
ブロディといえば、プロレスの勝敗にこだわったことで知られています。要するに、なかなか負け役を受けなかったのですが、負けるにしても負け方に異常にこだわったといいます。以下の会話が展開されます。
斎藤 負け方によって試合の意味合いが全然違ってくるんです。だから「ギブアップとピンフォールのどっちが嫌ですか?」て聞くと、アメリカ人レスラーの感覚で言えば、ギブアップがいちばん屈辱的なんですね。その中でもっとも屈辱的なのは、リング中央でスリーパーホールドで失神するとか。それがいちばん屈辱なんです。
鹿島 戦闘不能状態にされるのがいちばんの屈辱だと。
斎藤 「だったらまだフォール負けのほうがいい」っていう感じで。実際、ボクはブロディにもその質問をぶつけてみたら、「ギブアップ負けがいちばん屈辱的に決まっているじゃないか」って言っていて、横にいたジミー・スヌーカも「それはそうだよ」って言ってたから、やっぱりアメリカ人の感覚はそうなんです。
‟超獣コンビ”でブロディのパートナーだったスタン・ハンセンは、カウントスリーを取られた瞬間に起き上って大暴れするみたいなことをやりました。それで「ダメージはないぞ」とアピールするわけです。そこで、以下の会話が展開されます。
斎藤 それがブロディと反戦の考え方だと思うんですね。クイックフォールならまだよくて、大の字で負けるのはとにかくダメ。だからブロディがジャンボ(鶴田)さんお雪崩式ブレーンバスターからのバックドロップを喰らって、ワン、ツー、スリーを取られたっていうのは、最高級の負け方だったんです。
鹿島 「ジャンボならその負け方でもいい」と思うくらい、ブロディの中で鶴田さんの評価が高かったということですよね。
斎藤 評価が高かったし、ブロディが日本人レスラーでいちばん気に入っていたのがジャンボさんだから。背丈といい、リズムやスピードが凄く合うんです。「猪木よりも誰よりもジャンボさんがナンバーワン」っていうのはブロディ本人がずっと言っていたことなので。
――だからブロディは結局、猪木さんには一度もフォール負けしませんでしたもんね。
『ブルーザー・ブロディ30年目の帰還』の著者である斎藤氏によれば、ブロディは没後30年以上経ってもプロレスファンに宿題を突きつけているといいます。「プロレスは試合結果が演出されたエンターテインメント」というロジックだけでは、いまだにブロディというレスラーを解読・解明できないというわけです。1984年からWWFによる全米制圧作戦がスタートし、各地のローカル団体がどんどん潰れていきましたが、斎藤氏は「ブロディが亡くなった1988年7月の3~4カ月前には、かつて‟世界最高峰”と呼ばれた連合組織NWAも沈没するんです。NWAフロリダとか、NWAセントラルステーツとか、NWA加盟テリトリーがどんどん潰れていったときです。ザ・シークさんのデトロイトも潰れたし、ディック・ザ・ブルーザーのインディアナポリスも潰れた。総本山セントルイスも潰れた。そしてNWAクロケット・プロがテレビ王テッド・ターナーに買収されてWCWが誕生。WWEとWCWの2大メジャー時代に突入するわけです。ブロディのように、ある団体と揉めても、すぐに次の団体に移るということができない時代になっていったんです。
さらに、以下の会話が繰り広げられます。
斎藤 ブロディぐらいの大物ならWWFと大型契約も結べたと思います。でもWWFに行ってしまったら、いくらブロディであってもハルク・ホーガンの敵役のひとりでしかなく、レッグドロップ(ギロチンドロップ)を喰らって、ワン、ツー、スリーは避けられなかったでしょう。あのアンドレだってそうだったんだから。それがわかっていたからこそ、ブロディは行かなかったし、ハンセンも行かなかった。
鹿島 自分の価値を守るために、あえてメジャーには行かないっていう生き方ですよね。
斎藤 アメリカでの‟職場”が少なくなってきたからこそ、ふたたび全日本プロレスに本格的に腰を据えるようになった。
鹿島 1988年(昭和63年)に行われた鶴田vsブロディの連戦が、どちらもピンフォール決着になったのは、全日本が大物同士の対戦であっても完全決着がつく物語を提供していく先駆けにもなりましたよね。
斎藤 あの時点で馬場さんは、ハンセンvsブロディを準備していたんです。それは1回で終わるものではなくて、鶴田vs天龍と同じように何度もやるつもりだったんでしょう。決着がついても、負けたほうの価値が下がらないような形で、鶴田、天龍、ハンセン、ブロディの4人がしのぎを削る、5年ぐらい続く物語になっていたかもしれない。
「シュート」という言葉をめぐる両者の会話も興味深いです。
鹿島 「シュート」という言葉は、昔から使われていたんですか?
斎藤 「シュート」そして「ワーク」という言葉は、アメリカで昔から使われていた言葉です。「狙撃する」っていう意味でのシュートですから。
――物騒な言い方をすると「殺しにいく」ですよね。
斎藤 だから(カール・)ゴッチ先生は「シュート」という言葉が嫌いだったんですね。「そんな卑しい言葉は使うな!」って感じで。特にレスラー以外の人がそういったスラングを遣ったりすると、凄く嫌悪感を露わにしていましたね。
鹿島 それこそ「わかったような口を利くな」ってことでもあったんでしょうね。
斎藤 ゴッチ先生の前ではそういった下品な言葉を使っちゃいけないんです。だから佐山(サトル)さんが最初に「シューティング」って言葉を使ったときも、「何がシューティンぐだ。狙撃でもするのか?」ってあまりよく思わなかったんです。単語そのものの響きとしてね。
――「おまえ、それ‟射精”って意味だぞ」って言ったという話もありますよね(笑)。
「シュート」談話の延長戦上で、伝説の力道山vs木村政彦戦についても語られます。斎藤氏は「序盤戦はふたりともクリーンファイトを意識してか、お互いに笑みをたたえるようなシーンがあったり、なんか変な感じはあるんですね。ボクの中でいちばんの違和感は、最後、力道山に張り手を食らった木村政彦がうつ伏せに倒れてノックアウトされますよね? それは画的には惨敗に見えるけど、『俺はもうこのまま起きないで寝ておくわ』っていう感じにも見えるんです」と言います。そして、「だから厳密に言うと、シュートですらないという可能性も考えられる。実際、力道山が木村の顔面を蹴り上げ、張り手を入れてボコボコにしたと言えばたしかにそうだし、よく言われる『本当は引き分けにするはずだったところを力道山が途中で裏切った』というのは、きっとその通りなんだろうけど、にもかかわらず、両者は試合後にいちおう握手している。だからフィクションもノンフィクションも含めて、試合後に生まれた話というのはいろいろあるのではないかと感じます」と述べます。それを聞いた堀江氏が「残された映像や、限られた証言だけでは、まだわからないことが多いだけですよね」と言うと、斎藤氏は「この試合にかぎった話ではないですけど、『プロレス』っていうのは、そう簡単にすべてを定義することはできないんです。力道山vs木村政彦にしても、66年というとてつもなく長い時間が経過した現在でもまだまだ新しい仮説を立てることができる」と語るのでした。確かに、そうですね。
力道山vs木村政彦は団体のエース同士の対戦でもありましたが、斎藤氏は「一般的な知名度や格付けでは、柔道の神様である木村政彦のほうが、元関脇で相撲を廃業してややブランクがあった力道山よりグレードが高かったかもしれない。しかしながら力道山のまわりには、‟プロレス文化を日本に導入した人たち”がいたんです。つまり、力道山個人が凄いイマジネーションで、プロレスという新しいスポーツエンターテインメントをたったのひとりでアメリカから導入したわけじゃなくて、それ以前からアメリカ側から日本へのプロレスの輸入計画は始まっていたんです」と語ります。すると、鹿島氏が「個人で立ち上げたベンチャー企業じゃないってことですね。バックにもっと大きな存在がいるという」と合いの手を入れれば、斎藤氏は「力道山がまだ相撲界にいた頃から、表社会も裏社会も含めてアメリカのエンターテインメント産業を日本に持ち込むために動いていた人脈ネットワークがあって、三菱電機という大スポンサーがいて、テレビという新しいメディアがあって、プロレスは初めて成り立つものだった。だから力道山は、そのプロレスという日本における新しいスポーツエンターテインメントを担う人に‟選ばれた人”であり、木村政彦はそのチョイスではなかった、とも言えるんです」と語ります。わたしはこの発言に驚くとともに、「なるほど!」と膝を叩きました。確かに、日本へのプロレスの導入が政治案件であった可能性は大いにあると思います。
力道山戦後、木村政彦は引き分けの約束を力道山が破ったことなどを暴露し、大騒ぎになりました。プロレスが真剣勝負ではないことが明るみに出たのです。この件についても、以下のような会話が展開されています。
斎藤 プロレスにおける勝ち負けの部分がプロデュースされているものであったとしても、「ジャンケンポンで決めてもいい」という程度の理解なんですよ。木村政彦という人は。ボクらがこの連載で何度も論じてきたように、勝敗がプロデュースされているものであれば、勝っても負けてもいいわけではなく、むしろ勝たなきゃいけないんです。
鹿島 逆説的に、プロレスは勝ち負けに凄く重要な意味があるという。
――実際、力道山vs木村政彦は、シュート云々は別として、勝つのと負けるのとではえらい違いがあったわけですもんね。それはのちの武藤敬司vs高田延彦と同様に。
斎藤 武藤vs高田の場合は、負けたUインターナショナルはその翌年に崩壊してしまいましたからね。それぐらい大きな影響と結果が出ることなんです。
そして、最後に以下の会話が展開されるのでした。
鹿島 馬場さんも猪木さんも、プロレスにおける勝ち負けがいかに大事かわかっていて、その上で「リングに上がれば何が起こるかわからない」という警戒心も当然持っているわけですもんね。
斎藤 そういう意味で、木村政彦と言う人は本質的にプロレスラーではなかったんだろうなと思いますね。「ガチンコ」か「ガチンコじゃないもの」しかない。だから、ガチじゃないプロレスの勝敗はジャンケンポンでもいいやという感覚。でも力道山はプロレスラーである以前に相撲取りだったので、相撲の価値観としての「ガチ」も「ボンナカ」も「その中間にあるもの」も最初から知り尽くしていたと思うんですよ。幕内まで行った人なので。
鹿島 なるほど! 相撲から検証が必要かも。
斎藤 つまり「ガチンコ」という言葉があるっていうことは、そうじゃないものもあるということだし。「ボンナカ」や「注射」「星の貸し借り(売り買い)」「八百長」と言う言葉があるのもまた、そうじゃないものがあるということですからね。
第9回「プロレスから学んだマイノリティの意識」では、日本にプロレスが紹介された草創期に来日したシャープ兄弟が取り上げられます。力道山が最初にデカい白人のシャープ兄弟を日本に呼んで倒したことに敗戦後の意気消沈していた日本人たちは熱狂したわけですが、斎藤氏は「シャープ兄弟はややフィクションなんですね。あのふたりはじつはアメリカ人じゃなくて、アメリカで活躍するカナダ人だったんです。でも太平洋戦争において日本が戦争をした相手はあくまでも”鬼畜米英”なので、力道山が空手チョップで倒す相手はアメリカ人じゃなきゃいけなかった。カナディアンだとやや成立しくにいですからね」と語っています。それを聞いた堀江氏は、「だからプロレスってパラレルワールドですよね。実際はメキシコ人はスペイン人に征服されたし、日本はアメリカに戦争で負けたけれど、リング上ではマヤ、アステカの英雄がスペイン人を駆逐して、日本人がでっかいアメリカ人を倒す。メタファーとしてそういったものが描かれているという、黒人やヒスパニックのベビーフェイスというのも、マイノリティの逆襲ですし」と述べています。
さらに、プロレスにおけるマイノリティの問題について、斎藤氏は「WWE の前身のWWWFのチャンピオンだったブルーノ・サンマルチノはイタリア移民で、東海岸一帯のイタリアン・アメリカンのヒーローだった。のちのシルベスター・スタローンの映画みたいなものですね。そのあとに出てきたペドロ・モラレスはプエルトリカンだから、モチーフ的には『ウエスト・サイド・ストーリー』。それからブルーノ・サンマルチノの前のニューヨークのヒーローは、”アルゼンチーナ”アントニオ・六花。だから人種のるつぼであるニューヨークには絶大な人気を誇るエスニックヒーローというのがずっといたんですよね。むしろ黒人スターより、こっちのほうが人気者だった。そしてバディ・ロジャースはいわゆるWASPで、キャラクター的にはいわゆるヒールだった」と語っています。
第10回「アンダーテイカー完全引退で考える”怪奇派”のルーツ」では、以下のような興味深い会話が展開されます。
斎藤 おそらく最初の怪奇派と呼べるカテゴリーは、マスクマンの登場でしょうね。
鹿島 なるほど。顔を隠しているわけですもんね。
斎藤 1873年、パリに現れた「ザ・マスクド・レスラー」という人物が最初とされていて、きちんとしたマスクじゃなく、袋みたいな感じですね。
鹿島 でも覆面レスラーというのは大発明ですよね。それがパリで誕生したという。
――『エレフェント・マン』みたいな感じですね。
斎藤 アメリカよりヨーロッパのほう、特にフランスがプロレスが盛んになったのが早かったんですね。1873年というと、日本では明治6年ですから。
鹿島 日本が文明開化した頃、パリにはすでにマスクマンがいた(笑)。
斎藤 マスクマンが登場人物として成立するということは、完全に「プロレス」になっているということでしょうね。
また、怪奇派については以下のような会話も展開されています。
斎藤 アメリカでの最初のマスクマンは、1916年にニューヨークに出現したマスクド・マーベル。この人の場合は正体暴きが新聞ネタになって、新聞記者にその素顔をバラされた。第二次世界大戦後は、その後の怪奇派のマスクマンの元祖的な存在として、ザ・マミーなんかもいましたね。
鹿島 ミイラ男っていうキャラクターは最高ですよね。チョップすると身体から白い粉が舞うっていう(笑)。
――ボクなんかも、子どもの頃に読んでいた『プロレス大百科』で、ザ・マミーとか怪奇派のページが大好きだったんですよ。
斎藤 ザ・シークもそこに入っていましたね。火を吐くアラビア人ってことで。だから火を毎回吐いてくれるのかと思ったら、そうでもないのね(笑)。
――めったに火は出さないですよね。しかも口から吹くんじゃなくて、手品みたいに手から火を出すという(笑)。
斎藤 のちの(ジャイアント・)キマラあたりも怪奇派ですよね。
第11回「馳浩と山田邦子の和解から振り返る『ギブUPまで待てない!!』」では、プロレスとテレビの関係が語られています。斎藤氏が「おそらく、日本とアメリカのいちばんのちがいはお金の問題です。日本だと放映権料という形で、テレビ局からプロレス団体に年間で莫大な資本が投下されるわけです。それは力道山が日本プロレスを立ち上げた頃からずっと続いていたことで、新日本が通常の試合中継ではなく、『ギブUPまで待てない!!』というバラエティ形式を受け入れたのも、放送形態は変わっても、年間契約の放映権料は変わらずにもらえたからですよね」と語ります。堀江氏が「それが団体運営の生命線なわけですもんね」と合いの手を入れれば、斎藤氏は「80年代当時、1週間単位で2500万とも3000万とも言われる放映権料がテレビ朝日から新日本に支払われていたわけですよね。そうすると月額にして約1億2000万円。年間だと15億円近くになる。それだけの予算があれば、アンドレ・ザ・ジャイアントだって、毎シリーズのように来ちゃいますよ」と語ります。
鹿島氏が「数年前、僕はテレビ関係者に話を聞いたんですけど、猪木さん、馬場さんというのは、プロレス団体の長であると同時に、毎週テレビのゴールデンタイムで高視聴率を取らなければならない、プロデューサーでもあったと」と語っています。堀江氏が「興行会社であると同時に、ゴールデンタイムの番組を作る制作会社のトップでもあるという」と合いの手を入れると、鹿島氏は「そしてボクらファンは漠然とプロレスは永遠に続くもんだと思っていたけど、猪木さんや馬場さんからすればいつテレビが打ち切られるかわからないし、もしテレビから切られたら、プロレスというジャンル自体がなくなるかもしれない恐怖と闘いながら、毎週高視聴率を叩き出していた。凄いテレビマンでもあったんですよね」と語ります。また、斎藤氏が「昭和の新日本プロレスというのは、製作総指揮・監督・主演、すべてアントニオ猪木です。ミスター高橋はクリエイティブにはかすってもいない。レフェリーは黒子です」と言えば、堀江氏が「猪木さんって、ビンス・マクマホンがメインイベントをやってるのと一緒ですもんね」と合いの手を入れます。猪木はビンス・マクマホンとハルク・ホーガンが合体した存在だったのです!
第13回「プロレスから学ぶ『疑わしい情報』の取り扱い方」の最後では、前田日明が立ち上げたリングスが言及されます。堀江氏が「『リングスってワークでしょ?』とか、ネットで聞きかじった情報でわかったようなことを言う人もいますけど、プロレスから総合格闘技への過渡期っていう革命的なことが行われていた時代を想像しようとすらしないのは、どうかなって思いますよ」と言えば、鹿島氏は「もう二度と味わえないような、いい時代を観られたんですよね」と語り、斎藤氏は「プロレスか総合格闘技かっていう時代性もそうだけど、ヴォルク・ハンとかディック・フライとか、プロレスがない国の人たちにプロレス的な観客との対話みたいなものを教えて、言葉が通じない者同士で試合をさせて、日本のファンを熱狂させたのは凄いこと。そして最終的には(アリスター・)オーフレイムとか、(エメリヤーエンコ・)ヒョードルのような、MMAの世界で最強と呼ばれる選手たちを世に出したんだから、前田さんの総合プロデューサーとしての功績はもっと評価されていいと思う」と述べるのでした。まったく同感です。前田日明は偉大なり!!
第17回「東京五輪とは何だったのか?」では、2021年にコロナ禍の最中に強行開催された東京五輪からナショナリズムについて語り合われます。
――「多様性」が大きなテーマになっている現代の五輪において、これだけあからさまなナショナリズムを見せられると「これ、本当に2021年!?」って思うんですよ。プロレスで言えば、力道山時代じゃないんだからっていう。
斎藤 力道山時代のナショナリズムで言えば、「力道山が憎きアメリカ人を倒すことで、敗戦国である日本を高揚させた」っていう定説がありますけど、その定説自体がじつは1983年(昭和58年)くらいに作られたものなんですね。
鹿島 えっ、そうなんですか!?
斎藤 ”犯人”と言うとちょっと変ですが、それを定説化した方々がいるんです。
――誰ですか?
斎藤 まず、村松友視先生です。戦後、力道山の空手チョップでアメリカ人をバッタバッタとなぎ倒して、ナショナリズムを高揚させたっていうのは、たしかに村松先生の少年時代の記憶なんだろうけど、それが定説として一気に広まったのは力道山の没後20年の活字と映像による力道山の”回顧ブーム”からなんです。
――つまり、『私、プロレスの味方です』が出たころだと。
斎藤 本当に当時の観客がアメリカ人レスラーを心から憎んでいたとしたら、日本プロレス黎明期の力道山&木村政彦vsシャープ兄弟のときに鬼畜米英の続きみたいに「アメリカ人を殺せ!」ってなるはずでしょ? でも、そんなことは誰も言っていないんです。
また、戦後のアメリカによる日本のマインドコントロールについて、以下の会話が展開されます。
斎藤 戦後にアメリカから輸入された最初のスポーツカルチャーがプロレスであることはたしかなんです。これは陰謀論と言ってしまえばそういうことにもなるのかもしれないけれど、トルーマン大統領の「3S」政策ってありましたよね。国民をコントロールするための「スポーツ、スクリーン、セックス」です。だから成り立ちとしては、アメリカ側が指名した日本国内におけるプロレスの”総理大臣”が力道山で、コンプライアンスの時代じゃないから読売新聞も”裏社会”も一緒になって力道山を応援して、NHKも日本テレビもプロレスを中継したでしょ。
鹿島 日本テレビ初代社長の正力松太郎さんは、その後、政界にも行くわけじゃないですか。そして日本テレビでは、力道山のプロレス中継とディズニーのアニメを隔週でやっていたというのは、いわゆる3S的な狙いがあるんだという説もありますよね。
斎藤 そういう説はあります。ブルーカラーはプロレス、ホワイトカラーはディズニーを楽しみなさいっていう。
大相撲を廃業した力道山は、タニマチを頼って新田建設の現場監督になります。そのとき、GHQ慰問興行に「おまえも出場せよ」という話があって、2週間だけ力道山と遠藤幸吉がプロレスの練習をしてそのままリングに上がりました。そのときの対戦相手はコーチをしてくれたボビー・ブランズで、それが力道山のプロレス・デビュー戦でした。その後、アメリカ修行に出るわけですが、以下の会話が展開されます。
斎藤 そこもまたミステリアスなんだけど、どうマンが得手も日本のパスポートを持ってアメリカ修行に行っているんですね。力道山の出身地は朝鮮半島の咸鏡南道浜京郡龍源面というところです。「いつ帰化したの?」っていう素朴な疑問は残るわけですが、帰化はしていない。これとは別に長崎県大村市にも謎の戸籍があったりする。となると、なんらかの超法規的措置がなされたと解釈したほうが自然なんです。
鹿島 政治のトップに近い人たちが関わってたってことですよね。ということは、黎明期のプロレスというのは「政治案件」だったってことでしょうね。
斎藤 だから傀儡と言えば傀儡かもしれないし、力道山がもの凄いカリスマ性を持ったスーパースターであったこともまぎれもない事実ではあるけれど、「力道山ひとりのイマジネーションと行動力でアメリカからプロレスを持ってきた」というのは、あとから作られたストーリーですね。
そして、日本にプロレスが入ってきた秘密について、以下のように語り合われるのでした。
斎藤 表社会と裏社会も含めて、プロレスは戦後の復興文化のひとつの象徴ということになるのかもしれない。そして、そこにはアメリカの思惑が多分に絡んでいるわけだから、リング上で提示されたコンテンツが日本人vsアメリカ人であったとしても、政治的なステートメントとしては「アメリカ人を殺せ!」とはならないんです。
鹿島 たしかにそうですね。
斎藤 つまり力道山のプロレスは、アメリカとの講和条約と復興の証なのです。
鹿島 アメリカからもたらされたエンターテインメントですもんね。
斎藤 それがテレビという、これもアメリカからもたらされたニューメディアと合体して大ブームになったわけです。
――勧善懲悪だし、わかりやすいわけですよね。
斎藤 ”憎き鬼畜米英”と言う役どころでシャープ兄弟が来たわけではないんです。力道山がナショナリズムを高揚させたというのは、もちろんそういう面もなかったことはないかもしれないけど、だいたいは村松友視さんをはじめとする80年代の言論人があとから言い出して、それがリアルタイムで力道山を観ていない世代からのちのメディアにバトンタッチされていく過程でもう疑う余地のない定説になっちゃったんです。
鹿島 要はテレビコンテンツを楽しんでいたわけですよね。
本書は432ページの大著ですが、全篇こんなふうに刺激的な考察が満載です。わたしは読みながら、何度も「うーん」と唸りました。これまでモヤモヤしていた多くのプロレスの謎が解けました。特に、NWAの伝統が捏造だったこと、日本におけるプロレスの導入は政治案件だったことには大きな衝撃を受け、大いに知的好奇心を刺激されました。さすがはアメリカのプロレスに精通した斎藤文彦氏です。また、衝撃の事実の数々を斎藤氏から引き出した鹿島氏も素晴らしい。『プロレス社会学のススメ』というタイトルはまったく「看板に偽りなし」であり、久々にこんなにも面白い本を読んだ気がします。プロレスに関心のあるすべての読書家にオススメです!