- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2007 歴史・文明・文化 『宇宙からいかにヒトは生まれたか』 更科功著(新潮選書)
2021.02.21
『宇宙からいかにヒトは生まれたか』更科功著(新潮選書)を読みました。「偶然と必然の138憶年史」のサブタイトルです。2016年2月に刊行された時点で購入はしていたのですが、なかなか読む機会がありませんでした。しかしながら、一条真也の読書館『リーダーの教養書』で紹介した本の中で、出口治明氏が強く本書を推薦しており、読みたいと思いました。著者は1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業勤務を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。現在、東京大学総合研究博物館研究事業協力者、明治大学・立教大学兼任講師、東京学芸大学・早稲田大学・文教大学非常勤講師。著書に、一条真也の読書館『爆発的進化論』、『絶滅の人類史』で紹介した本などがあります。
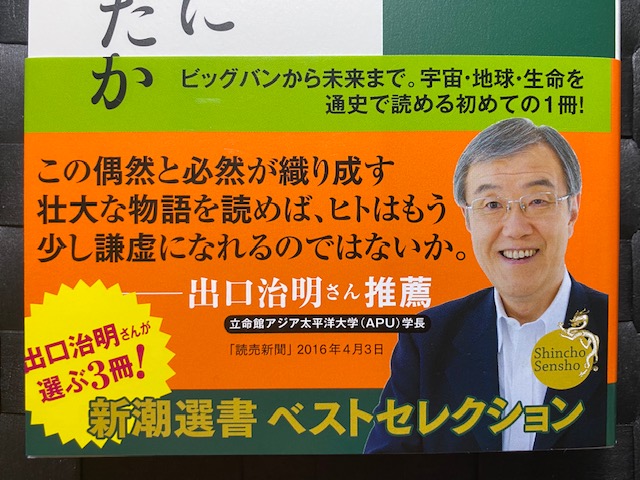 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、出口氏の顔写真とともに、「ビッグバンから未来まで。宇宙・地球・生命を通史で読める初めての1冊!」「この偶然と必然が織り成す壮大な物語を読めば、ヒトはもう少し謙虚になれるのではないか。――出口治明さん推薦(立命館アジア太平洋大学(APU)学長)(「読売新聞」2016年4月3日)「出口治明さんが選ぶ3冊! 新潮選書ベストセレクション」と書かれています。
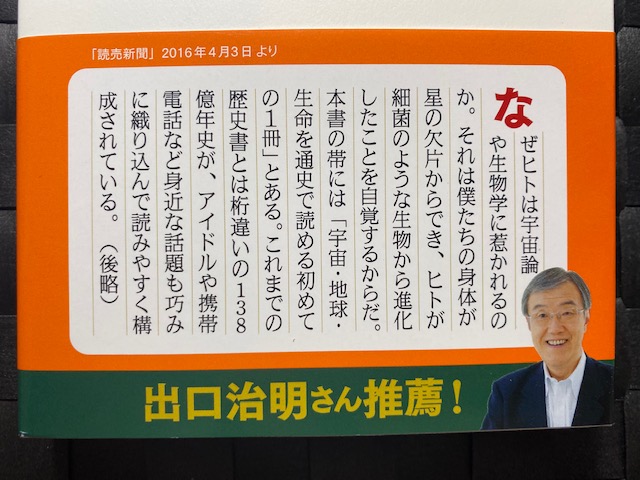 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏にも、なんと出口氏の写真がまたも使われり、「『読売新聞』2016年4月3日より」「なぜ人は宇宙論や斉物学に惹かれるのか。それは僕たちの身体が星の欠片からでき、ヒトが細菌のような生物から進化したことを自覚するからだ。本書の帯には『宇宙・地球・生命を通史で読める初めての1冊』とある。これまでの歴史書とは桁違いの138憶年史が、アイドルや携帯電話など身近な話題も巧みに織り込んで読みやすく構成されている。(後略)」「出口治明さん推薦!」と書かれています。素晴らしい推薦文ですが、何も帯の両面に出口氏の顔写真を入れることはないと思いますね。せめて、表は著者の顔写真にすべきではないでしょうか?
カバー裏表紙には、「いつか人類が滅んだとしても、地球の上では、生命の進化は続いていくのだ」として、「私たちはなぜここにいるのだろうか? 宇宙は人類のために誕生したのではなく、たまたま地球がヒトの生存に適していただけなのだ。人間を中心とした地球史観を排し、宇宙創成のビッグバンから地球の誕生、そして生命が生まれ進化していく様を、生物と無生物の両方の歴史を織り交ぜながらコンパクトに描いた初めての試み」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」
第1部 宇宙の誕生
(138憶年前~)
第1章 たくさんの宇宙
第2章 ビッグバン
第3章 太陽系の誕生
第2部 地球の形成
(45・5億年前~)
第4章 地球と月の誕生
第5章 地殻の形成
第6章 大気と海の形成
第3部 細菌の世界
(40億年前~)
第7章 生命の誕生前夜
第8章 生命の起源
第9章 初期の生命
第10章 光合成
第4部 複雑な生物の誕生
(19憶年前~)
第11章 真核生物の誕生
第12章 多細胞生物の出現
第13章 スノーボールアース
第5部 生物に満ちた惑星
(5・4億年前~)
第14章 カンブリア爆発
第15章 生物の陸上進出
第16章 大森林の時代
第17章 恐竜の繁栄
第18章 巨大隕石の衝突
第19章 哺乳類の繁栄
第20章 人類の進化
最終章 地球と生命の将来
「あとがき」
第1部「宇宙の誕生(138憶年前~)」の第1章「たくさんの宇宙」では、「宇宙は3種類ある」として、著者は以下のように述べています。
「もしも宇宙がたくさんあるなら、私たちが奇跡的な宇宙に住んでいることを説明するのは簡単だ。私たちは『よく調節された』宇宙に住んでいる。『よく調節された』というのは『人間に都合よく調節された』と言い換えてもよい。でも考えてみれば、『人間に都合よく調節された』宇宙にしか、人間は生まれることができないのだ。逆にいえば、『人間に都合よく調節されていない』宇宙もたくさんあるはずである。それは宝くじを買った人のほとんどがはずれているようなものだ。しかし、そういう宇宙では、人間は生まれることができない」
かつて著者は、生物学は不幸な学問だと思っていたそうです。物理学や化学は、普遍的で広く適用できる法則をあつかうことができます。いっぽう生物学は、地球の生物というたった1つの例しか調べることができません。他の惑星の生物でも発見されれば、すこしは学問の幅が広がるかも知れませんが、現在のように地球の生物だけを扱っているのでは、しょせんは個別的な学問にすぎないだろうと思っていたとか。しかし、現在では「もしも宇宙がたくさんあるのなら、それぞれの宇宙で万有引力定数などが異なっている可能性がある」と思っているそうです。
著者は、「それぞれの宇宙で、物理法則は違うのかも知れない。そうであれば、物理学も化学も、適用できるのは私たちの宇宙だけということになる。つまり、物理学も化学も、生物学と同じく個別的な学問ということになる。そうなってくると、むしろ生物学は幸せな学問かも知れない。他の宇宙の物理法則を調べられる可能性は、まず間違いなくゼロだ。しかし、他の星の生物が発見される確率は、ゼロではない。可能性が低いとはいえ、希望をもつことはできるのだから」と述べています。
第2部「地球の形成(45・5億年前~)」の第4章「地球と月の誕生」では、「月はどうやってできたのか」として、「太陽系で最大の惑星は、木星である。直径で、地球の11倍もある。2番目は土星で、地球の9倍だ。大きな衛星を持っているのも、やはり木星である。木星の4大衛星といわれるガニメデ、カリスト、イオ、エウロパは、およそ200個ある太陽系の衛星中、1位、3位、4位、6位の大きさを誇る。大きさで木星の4大衛星に食い込んでいるのは、土星のタイタン(2位)と地球の月(5位)だけだ」と書かれています。
土星は大きい惑星なので当然としても、ずっと小さな地球が、こんなおおきな衛星を持っているのは不思議なことです。半径で地球の4分の1以上もある月は、地球にとって身分不相応に大きな衛星なのだとして、著者は「このように大きな衛星が、どうして形成されたのだろうか。当然ながら、月の成因については古くから関心がもたれ、いくつもの仮説が提唱されてきた。現在もっとも有力なのは1975年にハートマンとデービスが提唱した『ジャイアント・インパクト説』だ。地球が形成されて間もない頃に、火星ぐらいの原始惑星が、地球に衝突したというのである。ちなみに、火星の直径はだいたい地球の半分で、月の直径はだいたい火星の半分である」と説明しています。
また、地球上の最古の岩石(約42億8000万年前とされている)よりも古い岩石が月にはあることを紹介し、著者は「月の表面には水も空気もないので風化作用がなく、地球よりも古い岩石が残りやすいらしい。調べられた月の岩石の中で最古のものは、およそ45億年前のものである。したがってジャイアント・インパクトは、これよりも前に起こったことになる。もしも原始地球が形成されたのが45億5000万年前頃だとすれば、その後の5000万年間のどこかでジャイアント・インパクトが起こり、月が形成され、そして地球もほぼ現在の大きさになったのであろう」と述べています。
第6章「大気と海の形成」では、「なぜ地球は美しく見えるのか」として、著者は「1961年にボストーク1号に乗って、初めて地球を外から眺めたガガーリンは、地球の美しさに強い印象を受けた。暗い宇宙空間の中で、円光に包まれて青く光る地球に感動したのである。円光に見えたのは大気で、青かったのは海である。また、ガイア理論で有名なジェームズ・ラブロックも、地球の美しさに強く感動した1人である。地球を1つの生命体とみなすガイア理論を思いついたきっかけは、青く光る地球の美しさだったらしい。地球には大気と海があるので、ひときわ美しいのだ」と述べています。
地球は「水の惑星」などと呼ばれますが、著者は「地球の表面の7割以上は、海で覆われている。そのため、地球は水の惑星と言われることもある。だが海の水は、地球の全質量のわずか0.02%に過ぎない」と書き、さらには「ありふれた隕石であるコンドライトに含まれる水よりも、地球の水の割合は少ない。じつは水は、宇宙にたくさん存在する化合物の1つなのだ。地球はどちらかというと、宇宙の中で水の少ないところなのである」と述べるのでした。この事実はわたしも知らなかったので、かなり驚きました。
本書には、地球や月だけでなく、太陽についても興味深い事実が書かれています。「太陽は明るくなっている」として、著者は「永遠に変わらないものはない。それは人の世の話だけではない。空に輝く太陽だって、同じ明るさで輝き続けることはできないのだ。実は太陽は、少しずつ明るくなっている。だから地球に届く熱も、だんだん多くなっている。あと10億年もすれば、地球は太陽にあぶられて、カラカラに乾いた星になってしまうだろう。それはそれで心配だが、ここでは昔に目を向けてみよう。現在、太陽がだんだんに明るくなっているということは、昔は暗かったということだ。地球ができたころの太陽は、今よりも30%ぐらい暗かったと考えられているのである」と述べているのです。
また、著者は「太陽が暗ければ、地球は寒くなるだろう。だんだんと明るくなってきたとはいえ、しばらくの間は、まだまだ太陽は暗かった。普通に考えれば、20億年前ぐらいまでは、地球は凍りついていたはずなのだ。だが、遅くとも38億年前には地球には海があった。地球はその初期から凍りついてはいなかったのだ」とも述べます。この不思議な現象を、有名な惑星科学者であったカール・セーガンは「暗い太陽のパラドックス」と呼んでいました。
「地球は生きているか?」として、著者は「地球が生きていると考えた人は、昔からたくさんいた。それが半ば常識だった時代もあった。レオナルド・ダ・ビンチも地球を生物だと考え、その証拠を得ようとして研究したようだ。最近では、この章の冒頭で述べたガイア理論がそれに近い。提唱者のジェームズ・ラブロックはいろいろな言い方をするのでやや分かりにくいが、『生物は自らの存続に最適なように地球環境を維持している。つまり生物を含めた地球は、自己調節システムを備えている。したがって、地球は1つの巨大な生命体として理解するのが適切である』という主張らしい」と述べています。
著者によれば、現在、地球に生息する生物が持っている特徴というものは、おおまかに言って3つあるそうで、「1つは『境界』だ。外界と自己を分ける仕切りで、具体的には細胞膜がこれに当たる。2つ目は『代謝と恒常性』だ。物質やエネルギーを外界とやりとりして、境界の内側の状態を一定に保つことだ。『動的平衡状態にあること』や『自己調節システムがあること』は、この2つ目の特徴の別の表現だろう。3つ目は『複製』だ。人間でいえば子供を作ることである。現在の地球に生息しているすべての『生物』は、この3つの特徴を持っている」と述べています。
第3部「細菌の世界(40億年前~)」の第7章「生命の誕生前夜」では、「すべての生物は中心原理に従っている」として、著者は「生物の遺伝子はDNAでできている。このDNAをもとにしてRNAを合成し、DNAの情報をRNAに移す。そしてさらに、RNAの情報をもとにしてタンパク質が合成される。このタンパク質が生命現象の主役である。私たちが歩いたり考えたりできるのは、このタンパク質がさまざまな働きをしているからだ。この、「遺伝子」から「生命現象の主役」までの「DNA(情報)→RNA(情報)→タンパク質(生命現象の主役)」という流れは、すべての生物が共有している。そこで「セントラルドグマ(中心原理)と呼ばれている」と述べています。
このセントラルドグマにすべての生物が従っているということは、このドグマが成立したことが、生命の誕生にとって重要なステップだったということだろうと、著者は推測します。では、このセントラルドグマはどうやって進化したのかについて、「実は、生命の起源のドラマの中で、もっともよく”放送”されているのが、このセントラルドグマの話である。なぜなら、セントラルドグマの進化には、1つの謎があるからだ。この謎のせいで、セントラルドグマの話は人気があるのである」と述べています。
第8章「生命の起源」では、「電車とは何だろう」として、著者は「電車とは何か。それに答えるためには色々な電車を見る必要がある。山手線しか知らなければ、『電車とは何か』はわからないのだ。『生命とは何か』という問いも、それに似ている。私たちは地球の生命しか知らない。だから『生命とは何か』はよくわからない。地球外生命がたくさん見つかって初めて、生命とは何かを論じることができるのだ。この章で述べることは地球上の生命から考えられることだけである。だからもしかしたら『電車とは緑色のものである』みたいな的外れなことを言ってしまうかも知れない。それは地球外生命が見つかっていない現時点では、仕方のないことだろう。それでも、『生命』について述べるときにはいつもそういう危険性があることを、頭の片隅に置いておく必要はあるだろう」と述べています。この比喩は秀逸ですね。
第9章「初期の生命」では、「すべての生物はただ1種の共通祖先から進化してきた」として、著者は「現在の地球には多くの生物がいる。名前がついているものだけでもおよそ200万種と言われ、その半分以上は昆虫である。もちろん未発見の生物もたくさんいるはずなので、どのぐらいの生物種が地球に生息しているかはわからない。少なくとも1000万種程度はいるだろう。ひょっとしたら1億種以上いるかも知れない。しかし、こんなに数が多くても、地球のすべての生物はただ1種の共通祖先から進化してきたと考えられている」と述べています。興味深い話です。
また、「ルカ――すべての生物の最終共通祖先」として、現在の地球のすべての生物は、ただ1種の最終共通祖先から進化してきたものであることを指摘し、著者は「この全生物の最終共通祖先のことをルカ(LUCA:Last Universal Common Ancestorの略)という。たまに勘違いをしている人がいるが、ルカは最初の生物というわけではない。おそらくルカが生きていたのは、最初の生物が生まれてから何億年もあとの時代であろう。当然、ルカがいた時代にも、ルカ以外にたくさんの細菌(バクテリア)がいたに違いない。だが、ルカ以外の細菌は、すべて子孫を残すことなく絶滅してしまった。現在まで子孫を残しているのは、ルカだけなのだ」と述べます。
さらに、「生命は遅くとも38億年前には誕生していた」として、著者は「岩石は頑丈なものではあるが、さすがに太古の地球で形成された岩石のほとんどは、風化作用などで消失してしまっている。しかし中には30億年以上も昔の岩石が残っている場所が、何ヵ所かある。極寒の地であるグリーンランドのイスアも、そんな場所の1つだ。そのイスアの岩石から、コペンハーゲン大学のロージングが、生命の最古の証拠を見つけたと報告したのは1999年であった。およそ38億年前の変成岩から、軽い炭素同位体比が測定されたのである」と述べています。
そして、「子孫から祖先を推定するのは難しい」として、著者は「私の遺伝子は、両親から受け継いだものである。両親の遺伝子は、祖父母から受け継いだものである。このように世代を通じて遺伝子が伝わることを垂直伝達という。だが遺伝子は、必ずしも垂直伝達で伝わるとは限らない。まったく別の生物やウイルスから、いきなり遺伝子が入ってくることもあるのだ。このような垂直伝達以外の遺伝子の受け渡しを水平伝達(あるいは水平遺伝子移行)という。遺伝子の本体はDNAであるが、私たちヒトのDNAの数%は、ウイルスによって運び込まれたものだと言われている。水平伝達はそう珍しいことではないのである。特に細菌では、遺伝子の水平伝達が比較的よく起きる。したがって、ルカを推定するときには、この遺伝子の水平伝達が大きな問題になってくる。場合によっては、別々の種だった細菌が、共生などの形で融合することもあるらしい。すると、その細菌のすべての遺伝子が水平伝達されてしまう。2種が1種に融合してしまうのだ」と述べるのでした。
第10章「光合成」では、著者は「今の私たち(ヒト)は、肉や野菜などを食べて生きている。しかし肉も、というかウシやブタなども、植物を食べて生きている。つまり、植物がなければ、私たちは肉を食べることもできないわけだ。結局私たちは、植物のおかげで生きているわけである。では、植物はどうやって生きているかというと、光合成という仕組みを使って、太陽光のエネルギーを利用して生きている。つまり、太陽光のエネルギーが、まず植物の中に蓄えられる。その植物を食べることによって、動物はエネルギーを手に入れる。そのエネルギーを使って、動物は歩いたり泳いだりしているわけだ。ということは結局私たちも、太陽光のエネルギーを利用して生きているわけである」と述べています。
第4部「複雑な生物の誕生(19憶年前~)」の第12章「多細胞生物の出現」では、著者は「どうしてヒトは必ず死ぬのだろうか」と読者に問いかけ、「その答えは、ヒトが多細胞生物だからだ。必ず死ぬのは、多細胞生物だけなのだ」と述べます。多細胞生物とは、単に「細胞がたくさん集まった生物」ではありません。それは群体といい、同種の生物が集まって、ただ連結しているものです。その証拠に、群体を作っているどの単細胞生物も、永遠に分裂を続けて死なない可能性を持っているといいます。
しかし、多細胞生物は、そうではありません。著者は、「たとえば私の手は、私が死んだらそれでおしまいだ。子供に伝えることはできない。私の手は、使い捨てなのだ。しかし私の身体のすべてが、使い捨てというわけではない。それでは子孫が残せない。使い捨てではないものが1つだけある。それは生殖細胞だ。もちろん実際に子供になるのは、生殖細胞の中のほんの一部に過ぎない。それでもすべての生殖細胞には、子孫に伝えられる可能性はあるのだ。すべての生殖細胞には、永遠の命をもつ可能性があるのだ。そこが、手などを作っている体細胞との違いである。体細胞は必ず死ぬ運命なので、永遠の命をもつ可能性はゼロである」と述べます。
第13章「スノーボールアース」では、「地球が凍りついたもう1つの証拠」として、地球は太陽光によって暖められていますが、届いた太陽エネルギーのすべてを受け取っているわけではないことを指摘し、「現在の地球は、太陽エネルギーの約70%を受け取り、残りの約30%を反射している。この反射率を惑星アルベドという。つまり地球の惑星アルベドは、約0.3だ。ところでスノーボールアースになると、地球は雪や氷で真っ白になる。白いということは、可視光線の大部分を反射しているということだ。すると惑星アルベドが上って、地球はますます冷えてしまうことになる」と述べます。
現在の地球の平均気温は、およそ15℃です。これがスノーボールアースになると、マイナス40℃近くまで低下したといわれています。著者は、「海洋は、すべて厚さ1000メートル以上の氷で閉ざされていただろう。海面が氷で閉ざされれば、大気中の二酸化炭素は海に溶け込めないので、大気中から消費されない。しかし、地表が凍りついていることには関係なく、火山活動は同じペースで起きるだろう。したがって二酸化炭素は、火山ガスの形で大気中に供給され続けることになる。大気中の二酸化炭素は、ゆっくりと増加していく。そして、二酸化炭素がある濃度を超えた時、その強烈な温室効果で、ついに地球を覆っていた氷が溶け始めるのだ」と述べます。さらに、いったん氷が溶け始めると、海洋や大陸が姿を現します。すると惑星アルベドが下がって、地球は太陽エネルギーを多く吸収するようになり、ますます温度が上昇していくのです。
第17章「恐竜の繁栄」では、「ダイナソーの誕生」として、著者は「絶滅したすべての生物の中で、最も人気があるのは恐竜だろう。これは子供だけに限った話ではない」と述べます。真偽のほどは知らないとしながらも、著者は以下のように述べています。「古生物学者になった人の半分は、恐竜が好きだったのがきっかけで、その道に入ったのだ」という話を聞いたこともあるそうです。ちなみに著者自身も、昔から恐竜は大好きだとか。ここ数10年で恐竜のイメージは大きく変化したとして、著者は「以前、恐竜は『知能が低くて動きののろい、絶滅した大きな爬虫類』と思われていた。しかし現在のイメージはまったく異なる。知能は低くないし、動きはのろくないし、絶滅さえしていない。変わっていないのは『大きな爬虫類』というところぐらいだ。こんなにイメージが変化したのに、人気が全然衰えないのが不思議なぐらいである」
第18章「巨大隕石の衝突」では、「地球はエコスフィアと同じこと」として、著者はこう述べています。
「NASAが開発した生態系モデルに『エコスフィア』というものがあった。残念ながら私は持っていなかったが、少し前には数万円で買えたらしい。完全に密閉されたバレーボールぐらいのガラスの球の中に、水や塩類などの必要な物質とともに、エビと藻類と微生物が入っている。藻類をエビが食べ、エビの排泄物を微生物が分解し、それが藻類の栄養になるらしい。エビが呼吸したり、微生物が排泄物を分解したりするのには、酸素が必要だが、それは藻類が光合成をして放出してくれるので大丈夫だ。とにかく光さえ当てておけば、エサをやる必要もないし、水を換える必要もない。エコスフィアの中で完全な生態系が成立しているので、永久とは言わないまでも、10年ぐらいはもつらしい」
アマゾンで確認すると、今でもエコスフィアが売られていました。著者は、「エネルギーは、光の形でエコスフィアに入っていき、熱の形で出ていく。このエネルギーの流れを止めることはできない。たとえじっとしたまま動かなくても、生物は生きているだけでエネルギーを使っているのだ。だから、エコスフィアを崩壊させるのは簡単だ。エコスフィアを照らしている電灯のコンセントを、そっと抜くだけで、エコスフィアの生態系はたちまち崩壊して、生物は死んでしまうだろう」と説明しています。また、「地球という生態系は、物質に関しては循環しているのである。しかし、エネルギーは循環していない。地球は太陽から、いつも莫大なエネルギーを与えられている。これが地球の生態系の動力源だ。だから地球の生態系を崩壊させようと思ったら、太陽のコンセントをそっと抜くだけでいい。そしてそれが、白亜紀末の大量絶滅を引き起こした一因だった」とも述べます。
「隕石の衝突によって大量絶滅は起きたのか」として、隕石の衝突によって何が起きたのかについては、いくつかのストーリーが提唱されていることが紹介されます。猛火、地震、津波、舞い上がった硫酸塩による酸性雨、地表や大気の高温化などで、地球は地獄と化した可能性もあります。しかし、生物にとっての脅威はそれだけではなかったとして、著者は「衝突によって舞い上がった微細な粒子が空を覆い、地表に届く太陽光を激減させたのだ。猛火によって発生した煤も、太陽光を遮るのに一役買ったかも知れない。ともかく太陽光が届かなければ、地球上は暗くて寒冷な世界になったに違いない。そして何よりも重要なことに、ほぼすべての生物のエネルギー源である光合成が停止しただろう。この暗い世界がどのくらい続いたのかは、よくわからない。数ヵ月だったかも知れないし、数年だったかも知れない。ともかく、しばらくの間、地球を照らす明かりのコンセントは抜かれたのだ」と述べています。
第19章「哺乳類の繁栄」では、「人類が滅亡しても細菌は生き残る」として、新生代は、哺乳類が適応放散した時代なので、「哺乳類の時代」と呼ばれることもあると紹介しながらも、著者は「しかし本当は、「細菌の時代」がふさわしい。いや、生命が誕生して以来、地球はずっと細菌の時代だったのだ。圧倒的に数が多いし、遺伝的な多様性も莫大だ。もしも核戦争で人類が滅亡しても、細菌は平気で繁栄し続けるに違いない。細菌はもっとも絶滅しにくい生物なのだ。その根本的な理由は、小さいからだ。小さい生物の方が、個体数も増やしやすいし、食物が少なくても大丈夫だし、狭いところにも入り込めるので、絶滅させるのが難しいのだ。散らかっている部屋を片付けるときも、大きなゴミを全部拾うことは簡単だが、小さなゴミを拾い尽くすのは大変だろう。それと同じことである」と述べています。
「有胎盤類の系統」として、サルの仲間である霊長類は北方獣類ですが、約4000万年前にはアフリカにも住んでいたことが知られていると指摘し、著者は「おそらく流木か浮き島に乗って、ヨーロッパからアフリカに流れ着いたのであろう。そのアフリカに渡った霊長類の中から、私たちの祖先になる類人猿が進化したのである。そして約2000万年前にアフリカ大陸とユーラシア大陸が陸続きになったとき、類人猿は2つの道を選ぶことができた。1つはユーラシアに戻ることだ。この、ユーラシアに戻った類人猿から、テナガザルとオランウータンが進化した。2つ目の道は、そのままアフリカに住み続けることだ。この、アフリカにとどまった類人猿から、ゴリラとチンパンジーとボノボと、そして私たちヒトが進化したのである」と述べます。
第20章「人類の進化」では、「チンパンジーはヒトに進化するのか」として、ヒトに一番近縁な生物はチンパンジーとボノボであることを指摘し、著者は「ボノボは、ピグミーチンパンジーと呼ばれていたこともある、少し小柄なチンパンジーの仲間である。その次にヒトに近縁な生物はゴリラである。つまり系統的にいえば、これら4種の中で最初に分岐をして、独自に進化し始めたのがゴリラということになる。それから、ヒトに至る系統と、チンパンジーやボノボに至る系統が枝分かれした。チンパンジーとボノボに至る系統の中で、チンパンジーとボノボが分岐したのは、さらにその後ということになる」と述べています。
また、ヒトに至る系統がチンパンジーやボノボに至る系統と分かれたのは、およそ700万年前のことであるとして、著者は「ヒトに至る系統はその後も分岐をくりかえして、様々な種を生み出していった。これらの種すべてを『人類』『ヒト族』『ホミニン』などという。つまり系統的にみて、チンパンジーやボノボよりもヒトに近い生物を人類というわけだ。現在までに知られている人類はおよそ25種で、その中には有名なネアンデルタール人も含まれている」と述べています。
さらに、「地球には様々な人類が生息していた」として、著者は以下のように述べるのでした。
「地球は多様な人類の惑星だった。だが、約4万年前にシベリア南部で、デニソワ人が絶滅。約2万8000年前にはスペインで、ネアンデルタール人が絶滅。約1万7000年前にフローレス島で、ホモ・フロレシエンスが絶滅。そして、とうとう地球上の人類は、ホモ・サピエンス1種だけになってしまった。すべて合わせれば数10種、いやもしかしたら100種以上いた人類が、たった1種になってしまったのだ」
最終章「地球と生命の将来」では、「ヒトは最後の生物ではない」として、これまでに発見された25種ぐらいの化石人類について見てみると、それらの中で200万年以上に渡って存続した種はいないことを指摘し、著者は「だからといって、ヒトも200万年以内に絶滅するとは限らないが、まあ数100万年ぐらい経てば絶滅している可能性が高いだろう。意外にあっさりと、来世紀あたりに絶滅してしまうかも知れないし。ともあれヒトが絶滅したあとも、地球や生命の歴史は何事もなかったかのように続いていくにちがいない。ひょっとしたらヒトが絶滅した後で、ヒトよりも知能の高い生物が現れるかも知れない。それらが語る地球と生命の歴史は、私たちが語った地球と生命の歴史よりも長いものになるだろう。私たちが絶滅した後も、歴史は続いていくのだから。残念なことに、私たちはそれを読むことはできないけれど」と述べています。
また、「地球の生命の歴史は50億年」として、著者は地球がこれから50億年以上、太陽系の惑星として存在し続けるだろうと推測し、「地球が誕生したときから考えれば、およそ100億年の長きに渡って、地球は太陽系の惑星であり続けることになる。そして最後は、赤色巨星となった太陽に飲み込まれて、地球はその一生を終えるのだ。しかしそれよりもずっと前、おそらく今から10億年後(遅くとも20億年後)には、気温の上昇によって地表にあった液体の水はすべて蒸発し、海は消滅してしまう。そうなれば、もはや生物は存在できない。つまり地球の歴史は、約45億年前から約50数億年後までのおよそ100億年だが、生物の歴史は、約40億年前から約10億年後までのおよそ50億年というわけだ。私たちヒトが生きている現在は、地球の生命の歴史のだいたい5分の4が終わった時点ということになる。残りは5分の1、およそ10億年だ」と述べます。
そして、著者は「ヒトが絶滅しても、何事もなかったように地球上では生物が進化していく。太陽系が消滅しても、何事もなかったように、宇宙は存在し続ける。そしてこの宇宙が消滅しても、何事もなかったように、他の宇宙は存在し続け、別の宇宙も生まれてくる。時間と空間を超越した、眼がくらむような果てしない物語の中で、一瞬だけ輝く生命……それが私たちの本当の姿なのだろう」と述べるのでした。この詩のような文章は、読む者の心に強い印象と感動を与えます。
「あとがき」で、著者は「私たちの祖先は40億年もの間、ただの一度も途切れることなく細胞分裂をし続けてきた。その結果、あなたが存在するのだ。それだけでも大したものだ。そもそも生物というものは、生きるために生きているだから、人生に意味のない季節はないのである」と述べます。「地球は素晴らしい奇跡的な星です。だから大切にしましょう」といった言葉を聞くたびに、少し変な気分になるという著者は「じゃあ、もしも地球がありふれた星だったら、大切にしなくてよいのだろうか。もちろん、そんなことはない。地球という惑星は、ありふれていようが、あと10億年しか生物が住めなかろうが、かけがえのない存在なのだ」と述べます。
そして、著者は「世界に真の勇気はただ1つしかない。世界をあるがままに見ることである。そしてそれを愛することである」というロマン・ロランの言葉を紹介します。ロマン・ロラン情熱的なフランスの文学者であり、ノーベル文学賞の受賞者でもありますが、本書が自然科学の書でありながら文学の香りもするのは、著者がロランの愛読者だったならば納得です。比喩も素晴らしく、エレガントな文章を書く著者は、最後に「日々の生活はもちろん、周囲の身近な物事や人々も含めて、生命や地球や宇宙をありのままに見て、そしてそれらを好きになる。もしもこの本が、わずかでもその役に立てばよいのだけれど」と記すのでした。