- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2020.12.06
12月5日、京都で、冠婚葬祭互助会業界の仲間の葬儀に参列しました。故人はわたしよりも年少の方でしたが、遺されたご家族の深い悲しみに接して、わたしも涙が止まりませんでした。そして、生前に縁のあった方々とのお別れの儀式としての葬儀の必要性を改めて痛感しました。故人の御冥福を心よりお祈りいたします。
さて、現在わたしは『鬼滅の刃』についての本を書いていますが、物語の奥に潜んでいる日本人の精神性を探るために、神道・儒教・仏教の影響を考察しています。そこで、『神・儒・仏の時代』島薗進・高埜利彦・林淳・若尾政希編(春秋社)を再読しました。
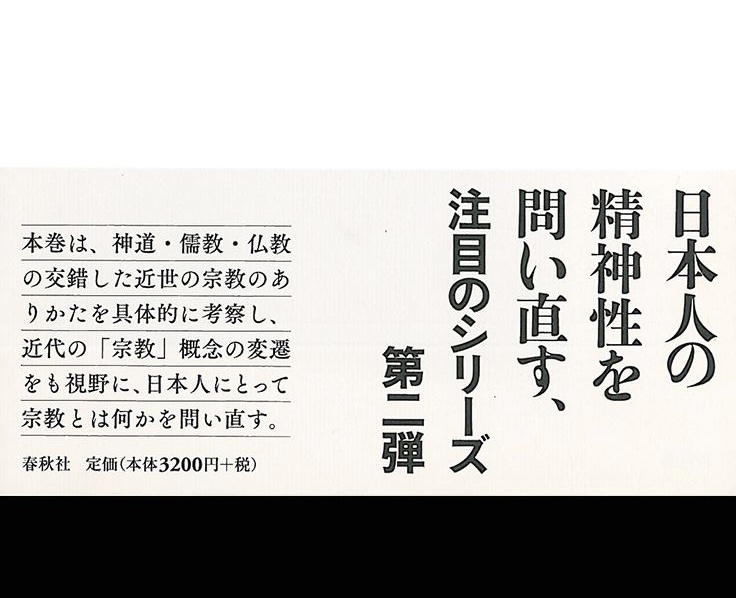 本書の帯
本書の帯
帯には「日本人の精神性を問い直す、注目のシリーズ第2弾!」として、「本巻は、神道・儒教・仏教の交錯した近世の宗教のありかたを具体的に考察し、近代の『宗教』概念の変遷をも視野に、日本人にとって宗教とは何かを問い直す」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章 神・儒・仏の時代(若尾政希)
第一章 「天道」思想と「神国」観(神田千里)
第二章 神・儒・仏の交錯
――「太平記読み」とその時代(若尾政希)
第三章 近世仏教と民衆救済
――黄檗宗の利他の精神と社会事業
(蓑輪顕量)
第四章 神・儒・仏の三教と日本意識(前田勉)
第五章 民衆信仰の興隆(神田秀雄)
第六章 「復古」と考証(高橋章則)
第七章 近代的世界像と仏教
――梵暦運動と須弥山儀(岡田正彦)
第八章 宗教概念と日本
――Religionとの出会いと
土着思想の再編成(オリオン・クラウタウ)
序章「神・儒・仏の時代」の二「近世は神・儒・仏の時代なのか」では、一橋大学教授の若尾政希氏が「『儒教の時代』という言い方への違和感」として、以下のように書いています。
「儒教、とりわけ朱子学が江戸幕府の正統教学として採用されたという――かつて丸山眞男が『日本政治思想史研究』で述べたような――理解は、現在では(1980年代半ば以降)否定されている(渡辺浩『近世日本社会と宋学』、辻本雅史『近世教育思想史の研究』)。17世紀の初めに日本列島で始まったばかりの商業出版により、多くの儒書が出版され、儒教を学ぶ人たちが出てきたのは事実であるが、朱子学が大きな意味を持ってくるのは、18世紀末の松平定信(1758~1829)による寛政改革まで待たねばならなかった。そのときはじめて、幕府の学校として昌平坂学問所(もと林家の家塾を継承して)が開設され、朱子学が『正学』として奨励されたのであって、それ以前に幕府が朱子学を正統教学として採用したという事実はない」
日本の近世を「儒教の時代」とのみ意義づけてしまうと、近世という時代を捉え損なうことになるとして、若尾氏は「日本の近世に儒書が多数出版されたのだが、実は最も多く出版されたのは仏書であった。大量の仏書が出版され読まれ、すべての人々がどこかの寺の檀家となり、先祖を祀るようになった日本近世こそ、中世とは異なった意味で、『仏教の時代』とも言うことができるのである」と述べています。
第一章「『天道』思想と『神国』観」の二「『天道』思想の諸特徴」では、東洋大学教授の神田千里氏が、「『天道』の特質」として、こう書いています。
「『天道』の語は古代からみられる。『日本書紀』に『政治の筋道が天道に適う時には天瑞(天よりの徴)が現れる』(天武天皇12年乙未条)とあるのは早い例であるが、平安時代の説話集『今昔物語集』にも『親の敵討ちは天道も許し給うことである』(巻第二五)とみえる。中世にはしばしばみられ、例えば鎌倉幕府の史書『吾妻鏡』の、承久の乱に関する記述にもみえる。京都に討伐軍を発遣した後、北条義時の館に落雷があった。朝廷に弓を引くことに対する天罰の徴ではないか、とたじろぐ義時を大江広元は励まし、討伐軍発遣の是非は『天道の決断』に仰ぐべきで恐れることはないと述べている(承久3年6月8日条)。人間の行為を審判する天の摂理の表現として、古代から『天道』の語が用いられていた」
また、「『天道』思想とキリシタン」として、ある時期にイエズス会もデウスの訳語に「天道」を用いていたことは、日本人キリシタンへの宣教師による説法の書状を収録しているとされる『貴理師端往来』の「各々が天道を心にとめて日夜お寺へ参詣して後生を願うべし」との記述からも窺えることを指摘し、神田氏は「有名なキリシタン大名大村純忠の起請文では、誓約の内容に背いた場合には天道のガラサ(恩寵)を失う、との自己呪詛文言が記されている(『龍造寺文書』天正4年6月16日大村純忠起請文)。少なくともキリシタンの間では天道とデウスは同じであった」と述べています。
さらに、三「『天道』思想のひろがり」では、神田氏は「『天道』ないし神仏の冥慮は人知を超えたものであり、人間の立場からはひたすら信仰するしかないが、行動については人知で選択しうる儒教道徳しかない、という思考が、他者の信仰への不介入・容認につながることは想像にたやすい。日本では欧米のような宗教戦争がなかったとよく言われるが、このような観念が一般化していたとすれば、それは当然の帰結ともいえよう」と述べるのでした。非常に興味深い見解であると思います。
第二章「神・儒・仏の交錯――『太平記読み』とその時代」の三「天道委任論の形成と定着」では、若尾政希氏が、日本の近世において、将軍は天道から人民の統治を委任されたという天道による大政委任論(天道委任論)が説かれたことを指摘します。たとえば岡山藩主池田光政は、1650年代半ばの家臣への教諭で、「上様ハ日本国中の人民を天より預り被成候、国主ハ一国の人民を上様より預り奉る、家老と士とハ其君を助けて、其民を安クせん事をはかる者也」(「申出覚」、藩法研究会編『藩法集I 岡山藩上』)と述べています。若尾氏は、「このように、天道が将軍に政権を預け、将軍が国主(大名)に一国の支配を預けたとする天道委任論が、将軍による全国支配、大名による領内支配を正当化する――イデオロギーの――役割を果たしたのである」と述べています。
ここで想起されるのは中国の天の思想ですが、若尾氏は「天によって正当化され荘厳化されるという点では、日本の近世は中国と類似しているのである」と述べます。また、「天道委任論の背景」として、「天道委任論が説かれた背景として、戦国時代の天道思想の流行をあげることができる。打ち続く合戦のなかで戦国武将は天道に身を委ねた。天道に命運をかけ合戦に臨み、敗北には『天運尽き』たとして運命を甘愛する。勝利したときには『天道の冥加・加護』だと感謝する。こうして権力闘争を勝ち抜いた者は、天道に認められたのだという観念が成立したのである。なぜ、天道思想がはやったのか。おそらく戦国武将が『太平記』をはじめとした軍記物語を愛好したことと無関係ではあるまい。なぜなら軍記物語の物語世界には天の思想が織り込まれているからである」と述べます。
天道委任論は、1697(元禄10)年に刊行された『農業全書』のような、民衆にも身近な書物に引かれ、近世社会の通念・常識となっていきますが、注意すべきは、日本近世の将軍が天の祭祀を行なったことは一度もないことであると指摘し、若尾氏は「これは、儒教国家である中国や朝鮮――天の祭祀が不可欠であった両国――とは決定的に異なっている点である」と述べています。
四「天道・コスモロジーと思想形成」では、「心の時代」として、若尾氏は以下のように述べています。
「16世紀日本=『戦国』の世は、とにかく生き抜くことが先決であった。『偃武』の世に移行した17世紀日本では、いかに生きるか、生き方の質が問われるようになった。『いな物じや、心は我がままなれど、ままにならぬは、いな物じや』(『いな物』1656(明暦2)年刊行)と、心がままにならないことを歌った俗謡が流行し、心をいかに修めるかをテーマとした啓蒙的な仮名草子が作られるようになり、産声をあげたばかりの本屋から陸続と出版された。そして、そうした書物を読んで心を修めたと実感する人々――いわば『書物の時代』の子――がでてきた時代、日本の近世とはそのような時代である。日本の近世は『書物の時代』であるが、同時に『心の時代』である。それはともに現代まで続いているが、その始まりの時代と意義づけることができよう」
五「おわりに――天道委任論と『天地の子』論」では、若尾氏は「日本の近世において、天道(天)は政権を正当化していたが、天道の役割はそれに止まらない。その一方で、天道はすべての人々の親として、その行動の指針を与える存在となったのである。中国では、天から選ばれた皇帝のみが天子として天を祀ることができ、他の者は天と関わることはできなかったのであるから、日本近世のあり方は明らかに逸脱である。どうしてこんなことが可能となるのか。考えられるのは、将軍が天の祭祀を行わなかったこと、すなわち将軍が天道を独占しなかったから、天道は――いわば『御天道様』として――万民に開放されたのである」と述べるのでした。
第三章「近世仏教と民衆救済――黄檗宗の利他の精神と社会事業」の一「はじめに」では、東京大学教授の蓑輪顕量氏が「近世という時代の精神的な特徴をあげるとすれば、心の重視であろう。心と言っても、それは唯心的な傾向を強く持っていた」と述べています。17世紀初頭に活躍した曹洞宗の僧侶である鈴木正三(1579~1655)は、「己心の弥陀」「己心の浄土」という用語を用い、自らの心の中に浄土が存在すると説きました。また、臨済宗の盤珪永琢(1622~1693)は、「不生の仏心」という言葉を盛んに用い、喜びも怒りも、すべて自分の心が生み出したものであると、平易な言葉で説法を行いました。蓑輪氏は、「このように、近世の時代精神の中には、人間の心を重視しようという風潮が存在していた」と述べます。
二「日本における黄檗宗の成立」では、「黄檗宗の特徴」として、「明代の臨済宗は宋代の臨済宗とはいくつかの点で異なったが、まったく新しい宗というわけではない。しかし、明代の臨済宗は華厳・天台・浄土等の諸宗の教義を受け入れ、教義の中心は華厳に置いたとみえ、宋代の臨済宗とは異なる側面を持った。それは教学的な部分に留まらず、日常の規矩の点でも異なった。宋代では禅堂の中で坐禅修行を行い、食事もそこで取ったが、明代の福建の臨済宗は、修行を行う専門道場である禅堂以外に食事をするための斎堂を別に持った。それは種堂と中庭を挟んで対になる位置に作られた。日常の生活の中で食事を大事にする習慣を持っていたのである。こうして、寺院の建築、日常の規矩などに新機軸をもった新しい宗として黄檗宗が成立した。なお1874(明治7)年、明治政府の教部省により強引に臨済宗黄檗派にされるが、後に黄檗宗を名乗り、正式に一宗として認知されている」と書かれています。
四「大蔵経の刊行」では、「鉄眼の大蔵経刊行事業」として、「黄檗宗の僧侶による事業として重要なものが、我が国最初の本格的木版摺大蔵経の刊行である。これは鉄眼道光によって成し遂げられた。大蔵経の刊行は、日本においては、天台宗の僧侶であった宗存(生没年不詳、17世紀)による京都北野の経王堂における宗存版(または古活字版と呼ばれる)がまず最初に存在する。これは比叡山が中心に進めたものであったが、残念ながら完成せずに終わった。後にそれは天海僧正(1536~1643)によって継承され、東叡山寛永寺の大蔵経に継承される。これがいわゆる天海版大蔵経である。この大蔵経は、木活字によって摺印された合計623巻を数える非常に貴重なものであるが、残念ながら刊行部数は少なく、またすぐに解版されてしまったという(渡辺守邦『寛永寺蔵天海版木活字を中心とした出版文化財の調査・分類・保存に関する研究』)。その結果、黄檗宗の鉄限版が、日本最初の本格的大蔵経の刊行となった」とあります。
五「黄檗宗の教理的な特徴」では、「書・煎茶・精進料理」として、「黄檗宗の僧侶は書に秀でた者が多かった。書の伝統を持ち、能筆が何人も輩出した。中でも、隠元、木庵性瑫、即非如一(1616~1671)の3名は、黄檗の三筆として名高く、その作品は高く評価された。隠元は中国に居たときに費隠に師事しており、中国における書の伝統を踏まえていたことが知られる。黄檗の僧侶たちは、日本において貴族階級の人々を始めとして一般にも書を教えている。彼らの書風は中国南朝風でありながらも質実なものであったという。また煎茶の習慣を一般に広めたのも黄檗宗の僧侶たちである。もっとも喫茶の習慣そのものは、早く奈良朝期に紹介されており、天平時代には、法会の中間日にお茶を僧侶に振る舞っている記録が知られている。抹茶の習慣は中世の時代、栄西によって紹介され臨済宗を介して広まっていったが、煎茶の習慣は、黄檗宗の僧侶を介して日本の社会に広く普及したと考えられる」と書かれています。
黄檗の僧侶は食材の上でも新たなものを日本に紹介しました。それは福建料理に基づきます。蓑輪氏は、「寺院の食事は精進であったが、食材は精進であっても、見た目は肉類にみえるような工夫が考えられたのである。大法要や大行事の後に、全山の僧侶が一堂に会して食事を取る会食は謝茶と呼ばれるのであるが、その時に独特の料理が振る舞われた。それは普茶料理と呼ばれた。基本は4人が一卓を囲む形式であり、料理は野菜の煮付けの盛り合わせである笋羹、味をつけた油の揚げ物である油ジ(食篇に「茲」)を中心としたが、その料理に大豆を原料とした、肉に似せた食材が登場したのである。その典型が雁もどきであり、それは雁の肉に似せたものであった。それ以外にも鯨の肉、ウナギ、蒲鉾、竹輪に似せたものが工夫されていた。それらの原型は、福建の素菜料理であるが、これが日本の社会の中に広まり、新しい食材となっていったのである」と述べています。
七「おわりに」では、近世に新たに伝えられた黄檗宗は、臨済宗妙心寺の龍渓性潜の尽力により江戸幕府と朝廷の双方から外護を受けることができるようになったことを紹介し、蓑輪氏は「黄檗宗が、近世の時代に大きな活躍をなした新仏教であったことは間違いない。わずか100年に満たない間に日本全国に、それも街道の要所や港湾都市に、1000を越える末寺を展開させたことから考えても、活発な活動がなされたと考えられる。また、それは一方で、黄檗宗が為政者から必要とされる宗派となっていたことを物語っているのかもしれない。しかし、無住の寺院を復興した例が多かったということは、一方で檀家を持たない寺院として出発することが多かったことも意味する。その故もあってか、現在は寺院数もそれほど多くはなく、知名度自体もそれほど高いとは言えない。しかし、現在の各宗派に与えた影響は大きく、また日本の文化に与えた影響も大きかった」と述べます。
さらに、蓑輪氏は「特に黄檗宗の僧侶による社会活動は大きなインパクトを与えるものであった。それは大乗の利他の精神がまさに発揮されたものであった。そのような点で、黄檗宗の伝来は、日本にとって画期的な出来事であったのである。龍渓の黄檗興隆、了翁の不忍経蔵及び後の勧学講院に結実する日本最初の公開図書館の設立、鉄眼の大蔵経開版、鉄牛の椿海の干拓事業と、黄檗宗の僧侶によって、言わば4つの大事業が成し遂げられたのである。そこには間違いなく大乗の利他の精神が深く横たわっている。黄檗宗の事績は、否が応でも当時の人々に、他者の利益、すなわち利他の心を考えさせる、大きな契機になっていたと思われるのである」と述べるのでした。わたしが住む小倉にも黄檗宗の寺院がありますが、黄檗宗の文化性がここまで突出していたものとは知りませんでした。蓑輪顕量氏の論考を読み、とても勉強になりました。
第四章「神・儒・仏の三教と日本意識」の二「儒仏論争と神道」では、愛知教育大学教授の前田勉氏が「17世紀の儒仏論争」として、「18世紀前半の日本意識の特徴を考えようとするとき、まず特筆すべきは、日本意識の強調者たちが、インドの仏教や中国の儒学とは異なる日本人の死後観を提示しようとしていた点である。たとえば、増穂残口は、『仏の法でなければうかまぬに極りたり共、日本へ生れし不祥に、我朝の道にて是非是非うかまんと思ふが、日本人の意地なり』(『有象無象小社探』巻下)と説いていた」と述べています。
17世紀、近世日本のなかで、中国宋代に成立した朱子学が本格的に学ばれ始めました。林羅山(1583~1657)、山崎闇斎(1618~1682)がその代表者ですが、前田氏は「中国の士大夫=読書人官僚の学問である朱子学に、彼らが魅かれた理由の1つは、それが仏教にたいする批判的理論を提供していたことにある。もともと、朱子にとって『最大にして最強、殆んど脅威とも云える敵は他ならぬ仏教、とりわけ禅』であった(三浦國雄『「朱子語類」抄』)。朱子はこの禅仏教の闊達な心の主体性を取り込む一方で、仏教を君臣・父子・夫婦・長幼・朋友の五倫を否定する出世間の教えであると批判して、修己治人の立場を鮮明にしていた。羅山や闇斎たちは、この朱子学の仏教批判=排仏論を武器に、古代以来の分厚い伝統をもつ仏教勢力にたいして、果敢にも原理的な批判を加え始めたのである。とくに、彼らが批判の矛先を向けたのは、仏教の来世観だった。『厭離穢土 欣求浄土』の言葉があるように、来世への希求こそが仏教教義の根本をなしていたからである。朱子学者たちは、仏教の来世観、すなわち輪廻転生・因果応報説にたいして、その虚妄さを批判した」と述べます。
また前田氏は、「中途半端な心の不安」として、「増穂残口と垂加神道は、こうした仏教と儒学との間で、どちらとも態度を決めかねている不安な人々に、仏教でも、また儒学でもない、新しい日本人の死後観を提示したのである」と述べ、さらに「垂加神道の救済論」として、「生前に自らの魂を神として祀り上げる生祀という奇妙な行為を行った山崎闇斎に端を発する垂加神道は、18世紀前半の享保期に最盛期を迎え、天皇への忠誠を媒介にして、死後に『此国』の『守護奉持の神霊』(『神道野中の清水』巻四)となると説いていたからである。冒頭に紹介した神籬伝は、その中核となる極秘伝であった。神籬とは、もともと神代紀の天孫降臨の段の一書に、高皇産霊が、降臨する天忍穂耳尊に天児屋命と太玉命をつけ従わせた時に、天児屋命への神勅として出てくる言葉である。垂加神道によれば、この神籬とは、『日守木』を意味し、生きている間に、日(太陽)=天照大神=天皇を守護することによって、死後に『此国ノ神』となることができる教えだと解釈された」と述べるのでした。
第五章「民衆信仰の興隆」の一「はじめに――本章の課題と分析の視点」では、天理大学教授の神田秀雄氏が「17世紀中葉以降、江戸幕府や諸藩が寺請制度を施行したことはよく知られている。そしてその制度のもとで、ほとんどの人は何らかの仏教宗派に登録されたから、江戸時代は日本史上もっとも仏教が広まった時代だとさえ言われることがある。しかし、江戸時代の人々には、単に寺請けを得るためだけに宗者(所属する仏教宗派)を選んだ人も少なくなかった。また公認宗派の寺院から表向きの寺講けを得ながら、隠れキリシタン、隠れ念仏、隠れ題目(日蓮宗不受不施派)などの禁制宗派の信仰を保つ人々もいた」と述べます。
また神田氏は、江戸時代は宗教史的に不毛な時代だったわけではないとして、「むしろ民衆の宗教的活動はかなり活発に展開されており、たとえば仏教宗派でも、浄土真宗や日蓮宗のように、末端信者の活動を含めて、宣教活動が非常に活発な宗派も存在した。しかし総じて言えば、江戸期民衆の宗教的活動の昂揚は、仏教宗派の発展がすべてではなく、むしろその全体は、民俗的ないし神仏習合的な要素を広く含みつつ、きわめて多様な展開を示していた。そして後述するように、18世紀以降にはいくつもの霊場信仰(民俗宗教)が急速な高まりを見せ、翌世紀初頭以降には、何人かの教祖によって新しい宗教が創唱されていくのである」と述べています。
二「『泰平の世』の宗教秩序」では、「秩序形成の画期と道具立て」として、神田氏は「民衆信仰の興隆という視角から近世的な宗教秩序の形成を捉えるとすれば、その画期はむしろ元禄期(1688~1703)に求めるべきだろう。というのは、同期にはおよそ次のような諸事実を確認できるからである」と述べます。その1つは、元禄期の江戸に開帳の流行がはじめて起こったという事実です。もう1つは、突然に何かの利益が言われだし、急速に多くの参詣者を集める流行神と呼ばれる宗教事象も、その出現の画期が元禄期に想定できることです。
さらに付け加えると、近世期には、交通の発達を背景に、遠隔地の霊場参詣を焦点とする信仰(民俗宗教)もさまざまなかたちで流行していました。神田氏は、「そうした事例には、伊勢神宮や紀州の熊野権現、信濃の善光寺や安芸の厳島神社などの古来の霊場も含まれるのだが、特に18世紀以降大流行したいくつかの事例もあった。富士山や御嶽山などの山岳霊場や、讃岐の象頭山金毘羅大権現、下総の成田不動などはまさにそうした事例であり、それらは近世における民衆信仰の興隆を代表する事例群だとも言えるのである」と述べるのでした。
第八章「宗教概念と日本――Religionとの出会いと土着思想の再編成」の二「言葉と近代」では、東北大学大学院博士課程を修了し、現在はハイデルベルク大学研究員のオリオン・クラウタウ氏が「Relogion以前の宗教」として、「『宗教』という言葉は、いくつかの漢訳仏典に記されていることからも分かるように、漢語としては、中国唐代(618~907)には用いられていたことが知られている。しかしながらそれは、ブッダの根本真理である『宗』と、その究極的な真実を表現する『教』という2文字から成る仏教的概念を表す熟語であって、明らかに今日の我々が用いる『宗教』とは連続するものではなかった(中村元「『宗教』という訳語」『日本学士院紀要』46巻2号)」と書いています。
三「前近代日本と諸宗教の領域」では、「キリシタンと『宗門』」として、クラウタウ氏は「近代的な意味での『宗教』が翻訳語として初めて登場するのは、世情が『御一新』に沸いた頃のことであると考えられる。しかし、この時期には、『宗教』は、religionに与えられた翻訳語のひとつに過ぎなかった。すなわち『宗教』以外には、例えば『宗法』や『宗門』、さらには『法教』や『徳教』といった言葉が用いられたのである(山口輝臣『明治国家と宗教』、30頁)」と書いています。
六「近代的な学知と『宗教』」では、「『哲学』と『宗教』」として、1880年代において次第に「宗教」として認識されるようになりつつあった仏教は、「東京大学」という体制の中では、同じく訳語として登場した「哲学」なる呼称の下で教えられていたことを指摘し、クラウタウ氏は「『宗教』を『哲学』の枠組みのうちに据えるこうした語りについて、宗教史学者の林淳は、哲学科設置に深く関与した井上哲次郎(1856~1944)の働きかけの可能性を指摘する。すなわち、官立大学での『宗教』研究に対する懸念への配慮とともに、『西洋哲学』に対抗し得る『東洋哲学』なるカテゴリーの下に、仏教や儒教を再構築することを、井上が意図していたというのである(「近代日本における仏教学と宗教学」『宗教研究』333号、33~35頁)」と書きます。
「おわりに」では、「宗教」にどのような要素を含めるのか、あるいはそれから如何なるものを排除すべきなのかは、明治期に限定した問題ではないとして、クラウタウ氏は「現代日本において、初詣や七五三などの儀礼的な行為を、『宗教的』と断言するのに躊躇する者は多く存在しており、こうしたメンタリティを有する人々のなかには、『宗教』への疑惑を示しつつも、『スピリチュアル』への関心を表明する者も少なくない。新たな用語の登場によって日本列島の信仰体系が再編成され、それぞれの領域が変遷していくことは、明治期も現代も変わることはない。明治期に始まった言葉としての『宗教』の歴史は、今もなお続いているのである」と述べるのでした。
この最後の「現代日本において、初詣や七五三などの儀礼的な行為を、『宗教的』と断言するのに躊躇する者は多く存在し」とか、「こうしたメンタリティを有する人々のなかには、『宗教』への疑惑を示し」といった言い回しが気になります。日本人の宗教について話がおよぶとき、かならずと言ってよいほど語られる話題があります。いわく、正月には神社に初詣に行き、七五三なども神社にお願いする。しかし、バレンタインデーにはチョコレート店の前に行列をつくり、クリスマスにはプレゼントを探して街をかけめぐる。結婚式も教会であげることが多くなった。そして、葬儀では仏教の世話になる・・・・・・。
もともと古来から神道があったところに仏教や儒教が入ってきて、これらが融合する形によって日本人の伝統的精神が生まれてきました。そして、明治維新以後はキリスト教をも取り入れ、文明開化や戦後の復興などは、そのような精神を身につけた人々が、西洋の科学や技術を活かして見事な形でやり遂げたわけです。まさに、「和魂洋才」という精神文化をフルに活かしながら、経済発展を実現していったのです。
神道は日本人の宗教のベースと言えますが、教義や戒律を持たない柔らかな宗教であり、「和」を好む平和宗教でした。天孫民族と出雲民族でさえ非常に早くから融和してしまっています。まさに日本は大いなる「和」の国、つまり大和の国であることがよくわかります。神道が平和宗教であったがゆえに、後から入ってきた儒教も仏教も、最初は一時的に衝突があったにせよ、結果として共生し、さらには習合していったわけです。日本文化の素晴らしさは、さまざまな異なる存在を結び、習合していく寛容性にあります。それは、和(あ)え物文化であり、琉球の混ぜ物料理のごときチャンプルー文化です。
かつて、ノーベル文学賞を受賞した記念講演のタイトルを、川端康成は「美しい日本の私」とし、大江健三郎は「あいまいな日本の私」としました。どちらも、日本文化のもつ一側面を的確にとらえているといえるでしょう。たしかに日本とは美しく、あいまいな国であると思います。しかし、わたしならば、「混ざり合った日本の私」と表現したいです。衝突するのではなく、混ざり合っているのです。無宗教なのではなく、自由宗教なのです。
 『知ってビックリ!日本三大宗教のご利益』
『知ってビックリ!日本三大宗教のご利益』
拙著『知ってビックリ!日本三大宗教のご利益』(だいわ文庫)のサブタイトルは「神道&仏教&儒教」といいます。前作の『ユダヤ教vsキリスト教vsイスラム教』(だいわ文庫)では、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三宗教の間に「vs」を入れました。歴史および現状を見ればその通りですが、このままでは人類社会が存亡の危機を迎えることは明らかです。そして、神道、仏教、儒教の三宗教の間には「&」を入れました。これまた、日本における三宗教の歴史および現状を見ればその通りだからです。そして、なんとか日本以外にも「&」が広まっていってほしいというのが、わたしの願いです。
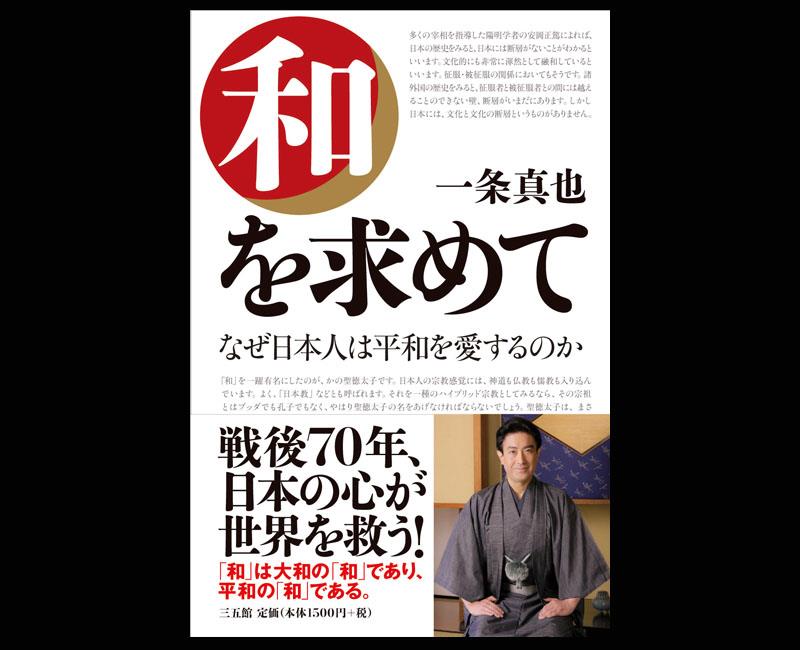 『和を求めて』(三五館)
『和を求めて』(三五館)
「vs」では、人類はいつか滅亡してしまうかもしれない。「&」なら、宗教や民族や国家を超えて共生していくことができる。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教をはじめ、ありとあらゆる宗教の間に「&」が踊り、世界中に「&」が満ち溢れた「アンドフル・ワールド」の到来を祈念するばかりです。そして冠婚葬祭こそが、そのアンドフル・ワールドの入口に続いていると信じています。冠婚葬祭が宗教を結ぶ。冠婚葬祭が人類の心を結ぶ。そんな夢を、わたしは本気で抱いています。最後に、「&」を日本語で表現するなら「和」です。終戦70年となる2015年、わたしは平和への願いを込めて『和を求めて』(三五館)を上梓しました。本書『神・儒・仏の時代』は編者の1人が島薗進先生であったことから手に取った1冊でしたが、学術的な論考集ながら多角的に日本人の「こころ」を研究した内容で、大変勉強になりました。
