- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2020.10.13
発売されたばかりの『緊急提言 パンデミック』ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳(河出書房新社)を読みました。「寄稿とインタビュー」というサブタイトルがついています。一条真也の読書館『サピエンス全史』、『ホモ・デウス』、『21Lessons』で紹介した三部作で著作累計が世界2750万部突破した世界的歴史学者・哲学者の著者が、コロナ禍について発信した寄稿・インタビューを日本オリジナル編集の書籍として刊行されたものです。 非常に興味深い内容で、128ページを1時間で一気に読了!
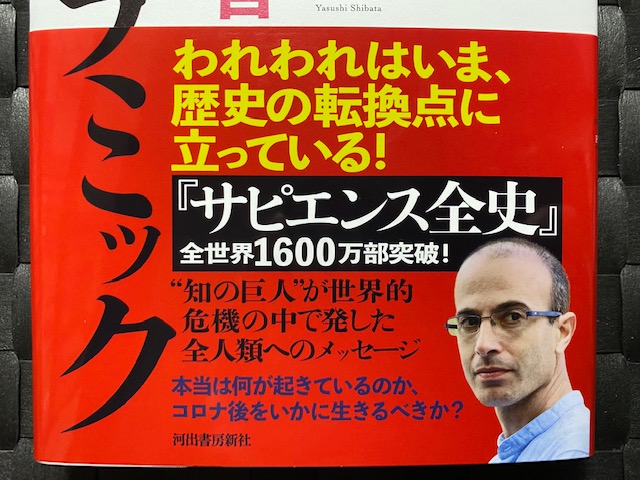 本書の帯
本書の帯
本書の帯には著者ハラリの顔写真とともに「われわれはいま、歴史の転換点に立っている!」「『サピエンス全史』全世界1600万部突破!」「”知の巨人”が世界的危機の中で発した全人類へのメッセージ!」「本当は何が起きているのか、コロナ後をいかに生きるべきか?」と書かれています。
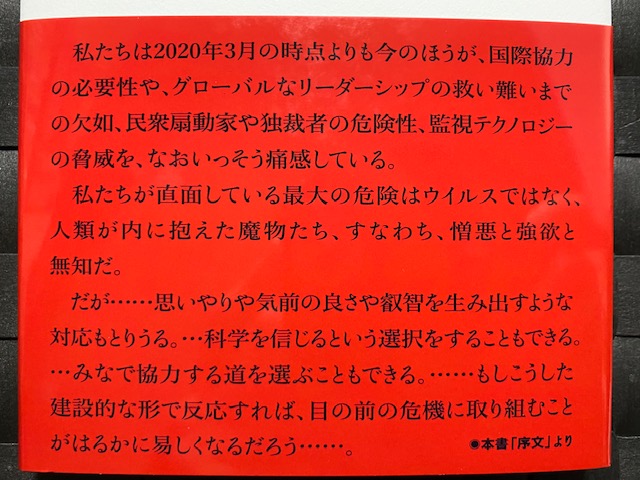 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「私たちは2020年3月の時点よりも今のほうが、国際協力の必要性や、グローバルなリーダーシップの救い難いまでの欠如、民衆扇動家や独裁者の危険性、監視テクノロジーの脅威を、なおいっそう痛感している。私たちが直面している最大の危険はウイルスではなく、人類が内に抱えた魔物たち、すなわち、憎悪と強欲と無知だ。だが……思いやりや気前の良さや叡智を生み出すような対応もとりうる。……科学を信じるという選択をすることもできる。……みなで協力する道を選ぶこともできる。……もしこうした建設的な形で反応すれば、目の前の危機に取り組むことがはるかに易しくなるだろう……」(本書「序文」より)
さらにカバー前そでには、こう書かれています。
「本書は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという一大危機を人類が迎えるなかで、著者が緊急に発表した見解を収録したものだ。日本オリジナル版。前半は『タイム』誌と『フィナンシャル・タイムズ』紙と『ザ・ガーディアン』紙への寄稿である。後半はNHKのETV特集のインタビューだ。『ユヴァル・ノア・ハラリとの60分』として放送された。それぞれ単独でも読みごたえ、見ごたえのある内容だが、みな切り口が異なるので、いずれも評判が高かったこれらの記事やインタビューをすべてまとめて読み、著者の目を通じて今回のコロナ禍をより多面的・多角的に眺め、考える機会を提供するというのが、本書刊行の狙いとなる」(「訳者あとがき」より)
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「序 文」
人類は新型コロナウイルスといかに闘うべきか
──今こそグローバルな信頼と団結を
歴史に見る厖大な犠牲者
感染症との闘い
新型コロナウイルス感染症の意味
ウイルスの変異という脅威
ウイルスと人間の境界
必要なのは互いの信頼と団結
コロナ後の世界──今行なう選択が今後長く続く
変化を私たちにもたらす
新しい監視ツール
重大な分岐点──「皮下」監視
緊急事態の一時的な措置は後まで続く
──プディング令
プライバシーか健康か
「石鹸警察」はなぜ不要か
科学と公共機関とマスメディアへの「信頼」
グローバルな情報共有
医療と経済と移動のグローバルな合意
アメリカという空白
死に対する私たちの態度は変わるか?
──私たちは正しく考えるだろう
避けようのない運命──死の意味
死は技術的問題に
延びる寿命は死後の世界への関心を失わせた
死に対する人間の態度
神の罰ではなくワクチンを
人命を守るためにさらに力を
いずれは死すべき存在
生の意義を考えるのは私たち一人ひとり
緊急インタビュー「パンデミックが変える世界」
インタビュアー 道傳愛子
発展途上国とウイルスの変異
歴史の決定的な瞬間
独裁か民主主義か
民主主義国家による大規模な監視社会
生体情報収集用のブレスレット
治安機関と医療機関
独り歩きをする緊急措置
透明で双方向の情報
どんな情報とどんな科学者を信じるべきか
協力と情報共有
集団的リーダーシップの必要性
パンデミックを生き延びるために
「出 典」
「訳者あとがき」
「序文」では、著者は「これまでの感染症と同じで、COVID-19に関しても、けっして忘れてはならないことがある。それは、ウイルスが歴史の行方を決めることはない、それを決めるのは人間である、ということだ」として、「人間はウイルスより圧倒的に強力であり、この危機にどう対応するかを決めるのは、私たちなのだ。ポストコロナの世界のあり方は、今私たちが下すさまざまな決定にかかっている」と述べています。
また、最大の危険はウイルスではなく、人類が内に抱えた魔物たち、すなわち、憎悪と強欲と無知であると指摘しつつも、著者は「憎悪や強欲や無知を生み出すような反応を見せる必要はない。思いやりや気前の良さや叡智を生み出すような対応もとりうる。他者にこの感染症の責任を負わせて非難する代わりに、みなで協力する道を選ぶこともできる。自分たちがより多く手に入れることばかり考えずに、持てるものを他者と分かち合うという選択も可能だ。もしこうした建設的な形で反応すれば、目の前の危機に取り組むことがはるかに易しくなるだろうし、ポストコロナの世界は、格段に繁栄し、円満なものとなることだろう」と述べるのでした。
2020年3月15日「タイム」誌に掲載された「人類は新型コロナウイルスといかに闘うべきか──今こそグローバルな信頼と団結を」と題する寄稿文の冒頭を、著者は「多くの人が新型コロナウイルスの大流行をグローバル化のせいにし、この種の感染爆発が再び起こるのを防ぐためには、脱グローバル化するしかないと言う。壁を築き、移動を制限し、貿易を減らせ、と。だが、感染症を封じ込めるのに短期の隔離は不可欠だとはいえ、長期の孤立主義政策は経済の崩壊につながるだけで、真の感染症対策にはならない。むしろ、その正反対だ。感染症の大流行への本当の対抗手段は、分離ではなく協力なのだ」と書きだしています。
「新型コロナウイルス感染症の意味」として、著者は「この歴史は、現在の新型コロナウイルス感染症について、何を教えてくれるのだろうか?」と問いかけ、「第一に、国境の恒久的な閉鎖によって自分を守るのは不可能であることを、歴史は示している。グローバル化時代のはるか以前の中世においてさえ、感染症は急速に広まったことを思い出してほしい」と述べています。また、「第二に、真の安全確保は、信頼のおける科学的情報の共有と、グローバルな団結によって達成されることを、歴史は語っている。感染症の大流行に見舞われた国は、経済の破滅的崩壊を恐れることなく、感染爆発についての情報を包み隠さず進んで開示するべきだ。一方、他の国々はその情報を信頼できてしかるべきだし、その国を排斥したりせず、自発的に救いの手を差し伸べなくてはいけない」と述べます。
「ウイルスの変異という脅威」として、著者は「こうした感染症について人々が認識するべき最も重要な点は、どこであれ1国における感染症の拡大が、全人類を危険にさらすということだ。それは、ウイルスが変化するからだ。コロナのようなウイルスは、コウモリなどの動物に由来する。それが人間に感染すると、当初は、人間という宿主にはうまく適応していない。だが、人間の体内で増殖しているうちに、ときおり変異を起こす。ほとんどの変異は無害だ」と述べます。
続けて、著者は「だが、たまに変異のせいで感染力が増したり、人間の免疫系への抵抗力が強まったりする。そして、このウイルスの変異株が人間の間で今度は急速に広まる。たった1人の人間でも、何兆ものウイルス粒子を体内に抱えている場合があり、それらが絶えず自己複製するので、感染者の1人ひとりが、人間にもっと適応する何兆回もの新たな機会をウイルスに与えることになる。個々のウイルス保有者は、何兆枚もの宝くじの券をウイルスに提供する発券機のようなもので、ウイルスは繁栄するためには当たりくじを1枚引くだけでいい」と述べるのでした。
「必要なのは互いの信頼と団結」として、今日、人類が深刻な危機に直面しているのは、新型コロナウイルスのせいばかりではなく、人間どうしの信頼の欠如のせいでもあると指摘し、著者は「感染症を打ち負かすためには、人々は科学の専門家を信頼し、国民は公的機関を信頼し、各国は互いを信頼する必要がある。この数年間、無責任な政治家たちが、科学や公的機関や国際協力に対する信頼を、故意に損なってきた。その結果、今や私たちは、協調的でグローバルな対応を奨励し、組織し、資金を出すグローバルな指導者が不在の状態で、今回の危機に直面している」と述べます。
2008年の金融危機のときや、2014年にエボラ出血熱が大流行したときには、アメリカはその種の指導者の役をこなしました。しかし近年、アメリカはグローバルなリーダーの役を退いてしまいました。現在のアメリカの政権は、世界保健機関のような国際機関への支援を削減しています。そして、アメリカはもう真の友は持たず、利害関係しか念頭にないことを、「アメリカ・ファースト」として全世界に非常に明確に示したのです。
著者は、「アメリカが残した空白は、まだ他の誰にも埋められていない。むしろ、正反対だ。今や外国人嫌悪と孤立主義と不信が、ほとんどの国際システムの特徴となっている。信頼とグローバルな団結抜きでは、新型コロナウイルスの大流行は止められないし、将来、この種の大流行に繰り返し見舞われる可能性が高い。だが、あらゆる危機は好機でもある。目下の大流行が、グローバルな不和によってもたらされた深刻な危機に人類が気づく助けとなることを願いたい」と述べています。
著者は、顕著な例を挙げます。新型コロナウイルスの大流行は、EU(欧州連合)が近年失った各国民の支持を再び獲得するまたとない機会になりえるとして、「EUのなかでも比較的恵まれている国々が、大きな被害が出ている国々に、資金や機器や医療従事者を迅速かつ惜しみなく送り込めば、どれだけ多くの演説をもってしても望めないほど効果的に、ヨーロッパの理想の価値を立証できるだろう。逆に、もし各国がそれぞれ自力で対処せざるをえなければ、今の大流行はヨーロッパ統合の終焉を告げる弔いの鐘を鳴らすことになりかねない」と述べます。
そして、著者は「今回の危機の現段階では、決定的な戦いは人類そのものの中で起こる。もしこの感染症の大流行が人間の間の不和と不信を募らせるなら、それはこのウイルスにとって最大の勝利となるだろう。人間どうしが争えば、ウイルスは倍増する。対照的に、もしこの大流行からより緊密な国際協力が生じれば、それは新型コロナウイルスに対する勝利だけではなく、将来現れるあらゆる病原体に対しての勝利ともなることだろう」と述べるのでした。
2020年3月20日「フィナンシャル・タイムズ」紙に寄稿した「コロナ後の世界――今行なう選択が今後長く続く変化を渡したちにもたらす」では、著者はまず、「この危機に臨んで、私たちは2つのとりわけ重要な選択を迫られている。第一の選択は、全体主義的監視か、それとも国民の権利拡大(エンパワーメント)か、というものだ。第二の選択は、ナショナリズムに基づく孤立か、それともグローバルな団結か、というものだ」と指摘します。
「新しい監視ツール」として、感染症の流行を食い止めるためには、各国の全国民が特定の指針に従わなくてはいけないと指摘し、これを達成する主な方法を2つ示します。1つは、政府が国民を監視し、規則に違反する者を罰するという方法です。近年は、政府も企業も、なおいっそう高度なテクノロジーを使って、人々の追跡・監視・操作を行なってきたとしながらも、油断していると、今回の感染症の大流行は監視の歴史における重大な分岐点になるかもしれないと、著者は訴えます。
「重大な分岐点――『皮下』監視」として、著者は、「一般大衆監視ツールの使用をこれまで拒んできた国々でも、そのようなツールの使用が常態化しかねないからだけではなく、こちらのほうがなお重要だが、それが『対外』監視から『皮下』監視への劇的な移行を意味しているからでもある。これまでは、あなたの指がスマートフォンの画面に触れ、あるリンクをクリックしたとき、政府はあなたの指が何をクリックしているかを正確に知りたがった。ところが、新型コロナウイルスの場合には、関心の対象が変わる。今や政府は、あなたの指の温度や、皮下の血圧を知りたがっているのだ」と述べています。
また、著者は「ぜひとも思い出してもらいたいのだが、怒りや喜び、退屈、愛などは発熱や咳とまったく同じで、生物学的な現象だ。だから、咳を識別するのと同じ技術を使って、笑いも識別できるだろう。企業や政府が揃って生体情報を収集し始めたら、私たちよりもはるかに的確に私たちを知ることができ、そのときには、私たちの感情を予測することだけではなく、その感情を操作し、製品であれ政治家であれ、何でも好きなものを売り込むことも可能になる」と述べ、さらには「全国民がリストバンド型の生体情報センサーの常時着用を義務づけられた2030年の北朝鮮を想像してほしい。もし誰かが、かの偉大なる国家指導者の演説を聞いているときに、センサーが怒りの明確な徴候を検知したら、その人は一巻の終わりだ」と述べるのでした。
「緊急事態の一時的な措置は後まで続く――プディング令」として、著者は以下のように述べています。
「たとえ新型コロナウイルスの感染者数がゼロになっても、データに飢えた政府のなかには、新型コロナウイルスの第二波が懸念されるとか、新種のエボラウイルスが中央アフリカで生まれつつあるとか、何かしら理由をつけて、生体情報の監視体制を継続する必要があると主張する者が出てきかねない。わかっていただけただろうか? 近年、私たちのプライバシーをめぐって激しい闘いが繰り広げられている。新型コロナウイルス危機は、この闘いの転機になるかもしれない。人々はプライバシーと健康のどちらを選ぶかと言われたなら、たいてい健康を選ぶからだ」
そして、「グローバルな情報共有」として、著者は「私たちが直面する第二の重要な選択は、ナショナリズムに基づく孤立と、グローバルな団結との間のものだ。感染症の大流行自体も、そこから生じる経済危機も、ともにグローバルな問題だ。そしてそれは、グローバルな協力によってしか、効果的に解決しえない。このウイルスを打ち負かすために、私たちは何をおいても、グローバルな形で情報を共有する必要がある。情報の共有こそ、ウイルスに対する人間の大きな強みだからだ。中国の新型コロナウイルスとアメリカの新型コロナウイルスは、人間に感染する方法について情報交換することができない、だが、新型コロナウイルスとその対処方法に関する教訓を、中国はアメリカに数多く伝授できる」と述べるのでした。こうした情報の共有が実現するためには、グローバルな協力と信頼の精神が必要とされるのは言うまでもありません。
2020年4月20日「ザ・ガーディアン」紙に寄稿した「死に対する私たちの態度は変わるか?――私たちは正しく考えるだろう」では、「避けようのない運命――死の意味」として、著者は「近代以降の世界を方向づけてきたのは、人間は死を出し抜き、打ち負かせるという信念だ。だが、それは画期的な態度だった。人間は歴史の大半を通じて、おとなしく死を甘受してきた。近代後期まで、ほとんどの宗教とイデオロギーは、死を避けようのない運命としてきたばかりか、人生における意味の主要な源泉として捉えてきた」と述べています。
続けて、著者は「人間の存在にとって最も重要な出来事は、本人が息を引き取った後に起こった。人は死んでから初めて、生にまつわる本当の秘密を知るに至った。そしてようやく永遠の救済を得るか、あるいは果てしない断罪に苦しむことになった。死のない――したがって天国も地獄も生まれ変わりもない――世界では、キリスト教やイスラム教やヒンドゥー教のような宗教は、何の意味もなさなかっただろう。歴史の大半を通じて、最高の頭脳の持ち主たちは、死に意味を与えることにせっせと励み、死を打ち負かそうなどとはしなかった」と述べます。
その後、科学が発達し、医学が進歩したことによって、人間の寿命は格段に延びました。「延びる寿命は死後の世界への関心を失わせた」として、著者は「人間は命を守って寿命を延ばす試みで大成功を収めてきたので、私たちの世界観は根底から変わった。伝統的な宗教が死後の世界こそ意味の主な源泉であると考えていたのに対して、18世紀以降は、自由主義や社会主義やフェミニズムのようなイデオロギーは、死後の世界への関心をすべて失った」と述べています。ただし、相変わらず死に対して中心的役割を与えている現代のイデオロギーが1つだけあるとして、著者は「ナショナリズムだ。ナショナリズムは情に訴えるときや切羽詰まってきたときには、国のために命を捧げる者は誰でも国民の集合的記憶の中で永遠に生き続けることを約束する」と述べます。
さらに、「死に対する人間の態度」として、著者は「今回のパンデミックで、死に対する人間の態度は変わるだろうか?」と問いかけ、「おそらく、変わらない。まったくその逆だ。COVID-19のせいで、私たちは人命を守ろうと、なおさら努力するようになる可能性が高い。なぜなら、COVID-19に対して社会が見せる反応として最も目立つのは、諦めではなく、憤慨と期待が入り交じったものだからだ。中世ヨーロッパのような近代以前の社会で感染症が勃発したときには、人々はもちろん命の危険を感じ、愛する人の死に打ちのめされたが、主な反応は諦めだった」と述べています。人々は、これは神の思し召し、あるいは、人類の罪に対する天罰だと自分に言い聞かせたのでした。中世ヨーロッパでは、ペストの流行によって「メメント・モリ(死を想え)」という思想が生まれましたが、今回のCOVID-19の流行は「メメント・モリ」とは無縁なのでしょうか。
そして、「いずれは死すべき存在」として、著者は「人は何世紀にもわたって宗教にすがり、死後も永遠に存在し続けると信じて不安を和らげてきた。今では精神の安定を保つために宗教の代わりに科学を頼り、医師がいつでも救ってくれる、自分のアパートで永遠に生き続けられると信じて不安を軽減しようとすることがある。だが、現在必要とされているのは、バランスの取れたアプローチだ。私たちは、感染症に対処するにあたっては科学を信頼すべきだが、自分は一時的な存在であり、必ず死ぬという事実に取り組む責務も、依然として担わなくてはならない」と述べるのでした。ならば、やはり死生観というものが不可欠であり、「メメント・モリ」と無縁ではいられないと言えるでしょう。
2020年4月25日にNHKのEテレで放送された緊急インタビュー「パンデミックが変える世界」(インタビュアー:道傳愛子)では、著者は「メディアや一般の人々に言いたいのは、感染症そのものだけに注目しないでほしいということです。『今日、何人感染したか』『病院には人工呼吸器が何台あるか』――こういったことは重要ですが、政治情勢にも注意を払ってほしいと思います。なぜなら、政治家たちは今、何十億、何兆ドルものお金を給付金などに注ぎ込むとともに、非常に重要な決定を下しているからです」と語っています。
このパンデミックが終息した後、新たな秩序が確立したときには、今下されている決定を変更するのは非常に困難であるとして、著者は「あなたがたとえば2021年に首相に選ばれたとしたら、それはパーティが終わった後に会場にやって来るようなもので、残っていることと言えば、汚れた食器を洗うことぐらいのものです」と日本人がドキッとするようなことを言います。さらに著者は、「ですから政治家たちは今、絶好の機会を迎えています。経済や教育システムや国際関係のルールブックをすっかり書き直すことができるのですから。ただし、この機会は束の間のものです。そして、選択肢はじつにたくさんあります。私たちが正しい選択をすることを願ってやみません」と語っています。
「より長い人間の歴史の中、つまりサピエンスの全歴史の中で、このパンデミックはどんな意味を持っているのでしょう?」というインタビュアーの道傳氏の質問に対して、著者は「人類はもちろん、このパンデミックを生き延びます。私たちはこのウイルスとは比べものにならないほど強いし、過去にもこれよりはるかに深刻な感染症を何度も生き延びてきました。今回も生き延びることに疑問の余地はありません。この感染症が最終的にどのようなインパクトを与えるかは、あらかじめ決まっているわけではなく、私たち次第です。この危機がどのような結末を迎えるかは、私たちが選ぶのです。もし選択を誤り、ナショナリズムに基づく孤立主義や独裁者を選び、科学を信用しないで陰謀論を信じることを選べば、歴史に残る大惨事を招くでしょう。何百万もの人が命を落とし、経済は危機に陥り、政治は大混乱になります。」と答えています。
一方で、「パンデミックを生き延びるために」として、著者は「逆に、もし賢い選択をし、グローバルな連帯や民主的な責任を選び、科学を信頼することを選べば、そのときは、たとえ死者が出たとしても、苦しみが引き起こされたとしても、後から振り返れば、この危機は人類にとって素晴らしい転換点だったことが見て取れるでしょう――ウイルスを克服した節目だけだっただけではなく、私たちが内なる魔物を打ち負かした節目だったように。憎しみを乗り越えた時点、錯覚や妄想を乗り越え、真実を信頼し、以前よりはるかに強く、はるかに統一された種となった時点だったと思えることでしょう」とも述べています。このポジティブな考え方は、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)で、わたしが示した「何事も陽にとらえる」考え方に通じています。
同書で、わたしは以下のように述べました。
「考えてみると、こんなに人類が一体感を得たことが過去にあったであろうか。戦争なら戦勝国と敗戦国がある。自然災害なら被災国と支援国がある。しかし、今回のパンデミックは『一蓮托生』ではないか。『人類はみな兄弟』という倫理スローガンが史上初めて具現化したという見方もできないだろうか。今回のパンデミックを大きな学びとして、人類が地球温暖化をはじめとした地球環境問題、そして長年の悲願である戦争根絶と真剣に向き合うことができることを望むばかりである。人類はこれまでペストや天然痘やコレラなどの疫病を克服してきたが、それは、その時々の共同体内で人々が互いに助け合い、力を合わせてきたからだ。あわせて、新型コロナはITの普及によって全世界にもたらされている悪い意味での『万能感』を挫き、人類が自然に対しての畏れや謙虚さを取り戻すことが求められる」
NHKのインタビューの最後は、道傳氏が「コロナの世界で毎朝目覚めるたびに、あなたはどのようにして恐れを克服しているのでしょうか?」と質問します。それに対して、著者は「コロナへの恐れを克服するために2つのことをしています。第一に、私はこの危機の間も毎日2時間瞑想しています。いや、この危機の間だからこそかもしれません。私はヴィパッサナー瞑想をしています」「第二に、私は科学に頼ることで恐れを克服しています。つまるところは、もし私たちが科学を信頼すれば、この危機を容易に乗り越えることができるでしょう。反対に、もしあらゆる種類の陰謀論に屈してしまえば、私たちの恐れが煽られるだけで、人々は不合理な行動に走るでしょう。つまえい、心を開き、科学的で合理的な目で状況を眺めれば、私たちはこの危機を脱する道を見つけられるのです」と語るのでした。「瞑想の実践」と「科学への信頼」というバランス感覚に、この若き「知の巨人」の凄味を見た思いです。
「訳者あとがき」で、柴田裕之氏は「国民が正しい選択をし、人類が今回のコロナ危機さえ乗り越えられればいいのか? もちろん違う。監視テクノロジーが民主的に活用され、上下双方向に情報が流通するとともに、グローバルな信頼関係が確立された社会が実現すれば素晴らしいが、じつは、著者にしてみれば、それすら私たちにとっての究極の目的ではない。そのような社会が実現した暁には、私たちは何をするのか? それこそが肝心で、核心にあるのは、あるいは核心の入口にあるのは、死や自らの脆弱さ、はかなさと向かい合い、生の意義を考えること、となる。歴史学者であると同時に哲学者でもある著者らしい見識と言える」と述べています。哲学とは「死の学び」とソクラテスは言いました。やはり、著者が言いたいのは「メメント・モリ」ではないでしょうか。わたしには、そう思えます。
