- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1815 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『藤波辰爾自伝』 藤波辰爾著(草思社)
2019.12.26
『藤波辰爾自伝』藤波辰爾著(草思社)を読みました。「未完のレジェンド」というサブタイトルがついています。長州力とか前田日明に関する本は次から次に出るのに、彼らとともに新日本プロレスのニューリーダーとされた著者の本は一向に出ません。もともと長州と前田の2人がスターになったのも藤波のおかげだと考えていますので、著者の本が読みたくなりました。本書は2010年11月25日に刊行されています。著者は1953年、大分県生まれ。1970年に日本プロレスに入門。師アントニオ猪木の新日本プロレス旗揚げを機に同団体へ移籍。以降、長州力、前田日明、ベイダーらを相手に名勝負を繰り広げる。1999年に新日本プロレスの社長に就任するも志半ばで退任。
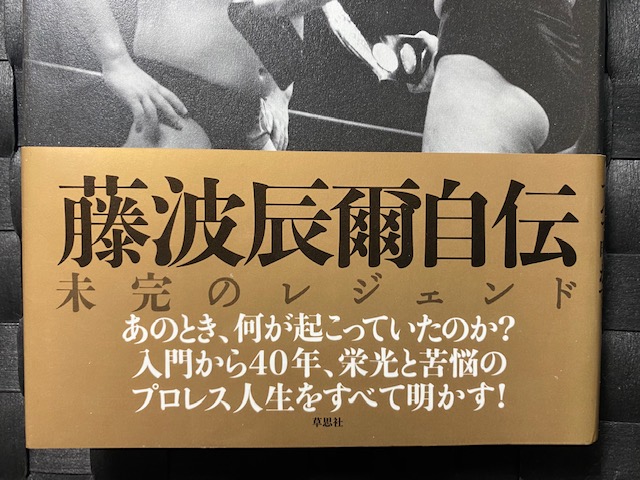 本書の帯
本書の帯
カバー表紙には、師であるアントニオ猪木からチャンペンベルトを手渡される著者の写真が使われ、帯には「あのとき、何が起こっていたのか? 入門から40年、栄光と苦悩のプロレス人生をすべて明かす!」と書かれています。また、カバー前そでには、以下のように書かれています。「今なおファンの脳裏に鮮烈な記憶を残す試合の陰で何が起こっていたのか?『名勝負製造機』としてマット界を牽引しつづけてきた名レスラーが、プロレスラーとして、そして団体トップとして味わった栄光と苦悩を真摯に綴る!」
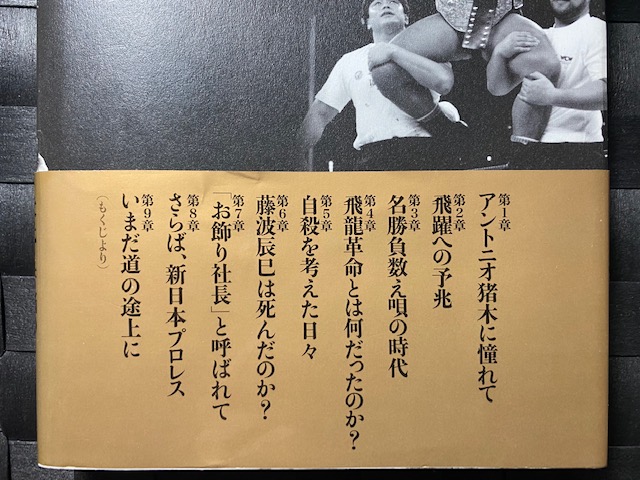 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
プロローグ 猪木さんの背中を流していた少年
第1章 アントニオ猪木に憧れて
第2章 飛躍への予兆
第3章 名勝負数え唄の時代
第4章 飛龍革命とは何だったのか?
第5章 自殺を考えた日々
第6章 藤波辰巳は死んだのか?
第7章 「お飾り社長」と呼ばれて
第8章 さらば、新日本プロレス
第9章 いまだ道の途上に
エピローグ そして、再び――
「年表」
著者は、1970年に日本プロレスに入門し翌年デビュー。72年、アントニオ猪木の新日本プロレスに旗揚げに参加。74年にカール・ゴッチ杯で優勝し、75年に海外遠征に。78年、MSGでWWWFジュニア王座を獲得し凱旋、ドラゴンブームを巻き起こしました。81年、ヘビー級転向。82年、WWFインターナショナル・ヘビー級王座を獲得。同年、長州力との抗争が始まり「名勝負数え歌」と称されました。85年、IWGPタッグリーグ優勝戦で猪木から初のフォール勝ちを収めています。そんな著書の2010年時点での心境が本書には綴られています。
プロローグ「猪木さんの背中を流していた少年」では、「リングとは夢が実現できるところ」として、著者は以下のように述べています。
「誤解を恐れずに言えば、プロレスとは心身ともに鍛えあげられた格闘家同士が、まるでダンスを踊るかのごとく互いの呼吸を合わせて動いていくスポーツだ。それができなければ決していい試合にはなりえない、とても奥の深いスポーツだ。プロレスの名勝負とは、レスリングの基本をマスターした者たちが、いいコンディションの中で研ぎ澄まされた互いの感性を披露し合ってはじめてできあがるものだ。こうした勝負ができたときは、勝敗に関係なく、じつに心地いい気分になる」
この一文は、素晴らしい名文です。おそらくはプロのライターの手が入っているでしょうが、プロレスの本質を美しく語っていると思いました。
第1章「アントニオ猪木に憧れて」では、内気で弱気だった少年時代を振り返って、著者は「ケンカを怖がる自分を変えたい」「弱気に支配されてしまう自分を強くしたい」「自分の中の恐怖心に打ち克ちたい」といった思いが16歳だった自分を突き動かしたとして、以下のように述べています。
「弱い自分にコンプレックスを抱いているとき、テレビで猪木さんの闘いを見る。苦難の果てに強豪外国人を倒し、猪木さんはガッツポーズを見せる。猪木さんのガッツポーズを見ていると、その瞬間だけは『弱い自分』を忘れることができるような気がした。そして、『明日からも頑張ろう』という勇気をもらった」
藤波少年にとって、アントニオ猪木は前向きに生きるための教祖であり、彼は完全な猪木信者だったのです。
第2章「飛躍への予兆」では、付き人を務めていた猪木が日本プロレスから除名されたために、苦労して入団した日本プロレスから退団し、旗揚げしたばかりの新日本プロレスに移籍した頃の心境が書かれています。
「猪木さんの姿を見ていると、何も不安など感じなかった。『この人についていけば何も心配はないんだ』『必ず何かができるんだ』と自然と思わせてくれるエネルギーが猪木さんには満ちていた。50代の後半となり、もうすぐ還暦を迎えようとしている現在まで、この思いは変わらない。それぐらい猪木さんの持つエネルギーは絶大なもので、近くにいる人を安心させるものだったのだ」
長い年月が過ぎ、著者は新日本プロレスの社長になりました。しかし、会長であった猪木の思惑で会社は格闘技路線に進みます。第8章「さらば、新日本プロレス」では、「プロレスが失ったもの」として、以下のように述べています。
「僕の社長時代には、完全に総合格闘技ブームが定着していた。ブームの定着に伴って、『プロレスラーが総合に出場したらどうなるのか?』とマスコミは煽り、それによって、しだいにファンの期待も大きくなっていった。当時、新日本プロレスからも藤田和之や永田裕志、ケンドー・カシンこと石沢常光、安田忠夫らが、総合のリングに挑戦していった。総合格闘技についての僕の見解は、当初から『絶対にかかわってはいけない』というものだった。総合ブームが起き始めた頃、プロレスラーが一切かかわっていなかったなら、後の大ブームは決して起こらなかったことだろう」
また、著者は総合格闘技について、こうも述べています。
「総合の舞台で、藤田や安田が勝利したこともあった。それでも、その勝利は新日本に対しては何の恩恵ももたらさなかった。藤田や安田が新日本の大会に出場しても、それが観客動員につながることはなかった。総合の舞台ではプロレスラーは『勝って当たり前、負けたら大失態』という、非常に損な役回りを演じさせられていただけだった。やはり、プロレス界は決して総合格闘技に関与してはいけなかった」
第9章「いまだ道の途上に」では、長州が著者の前で「オレたちは、プロレスの匠かもしれないな」という印象的な言葉を口にしたことを紹介し、かつては「名勝負数え唄」を繰り広げた著者と長州の関係が大きく変わったのが、著者が腰の負傷から復帰した後のことであるとして、こう述べます。
「それまでたんなる『ライバル』だった長州が、このころから『同志』という感覚に変わっていったように思う。これはたんに、長い期間ともに働いたことだけで芽生えた感情ではない。長い期間ともに過ごすことはもちろん、お互いにメインイベンターとして団体を背負ってきたから芽生えた連帯感なのだ。興行の世界に生きる者として、日々、重い責任を味わった者同士がわかちあえる感覚なのだ。それが、長州の言う『匠』なのだろう」
エピローグ「そして、再び――」では、「プロレスとは何か?」として、著者は以下のように述べています。
「――プロレスとは何ですか? 若い頃から、何度も聞かれた質問だ。ひと言で言い表すことはとても難しいけれど、あえて定義するとすれば、『プロレスとは、格闘技の総合芸術だ』と言うことができるのかもしれない。厳しい鍛錬によって、身体を極限まで鍛えあげた者同士が万全の体調の下で、磨き抜かれた技術を競い合う。さらに、人間の感情表現として、怒りや哀しみだけではなく、楽しさやうれしさも自分の肉体で表現する。しばしば『プロレスはショーだ』と批判を受ける。ショー的な要素はたしかにある。けれども、誤解しないでほしいのは、僕らは『痛くもないのに痛いふりをしている』わけでは決してないということだ。誤解を恐れずに言えば、本当に痛いから、『否応なしに痛い表情をしている』のだ」
この言葉も、プロレスの本質を見事に語っています。
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「プロレスとは、鍛えた者同士がお互いの技を受けながら強さを表現するものだから、選手同士の信頼感が大切になってくる。『橋本対小川戦』は、互いの信頼関係がなかったので、あの試合はプロレスではない。だから、あのような後味の悪い殺伐としたものになってしまったのだ。けれども、僕と前田の試合は、闘いの中で二人のあいだに信頼関係のようなものが芽生えてきた。だから、観客を熱狂させる試合になりえたのだし、ベストバウト賞を獲得するような立派なプロレスの試合となった」
本書の刊行は10年近く前ですが、当時ですでにプロレス界に入ってから40年の歳月を数えていました。ということは現在は入門50年の大きな節目を迎えるところですね。2017年4月20日には、後楽園ホールで「藤波辰爾デビュー45周年記念ツアーinTOKIO」が開催されました。会場は満員御礼、猪木、長州、木村健吾、藤原、佐山、前田らも激励に駆けつけ大盛況でした。つねに「格闘技の総合芸術」であるプロレスを追求し、対戦相手を光らせてきた著者だからこそ、今でも絶大な信頼を得ているのでしょう。