- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.08.13
死者を想う季節の中で、『死に逝く人は何を想うのか』佐藤由美子著(ポプラ新書)を読みました。「遺される家族にできること」というサブタイトルがついています。著者はホスピス緩和ケア専門の米国認定音楽療法士。アメリカのホスピスで10年、音楽療法を実践。13年に帰国、15年から青森慈恵会病院緩和ケア病棟でセッションを提供。著書に『ラスト・ソング』(ポプラ社)があります。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、病床でギターを奏でる著者の写真とともに、「いつか訪れる大切な人との別れ。その準備はできていますか?」「1200人以上を見届けた音楽療法士が穏やかな『見送り』のあり方を提案」と書かれています。帯の裏には、「何を考えているかわからない」「一緒にいるのがつらい」「途方に暮れる家族に贈る希望の書」と書かれています。
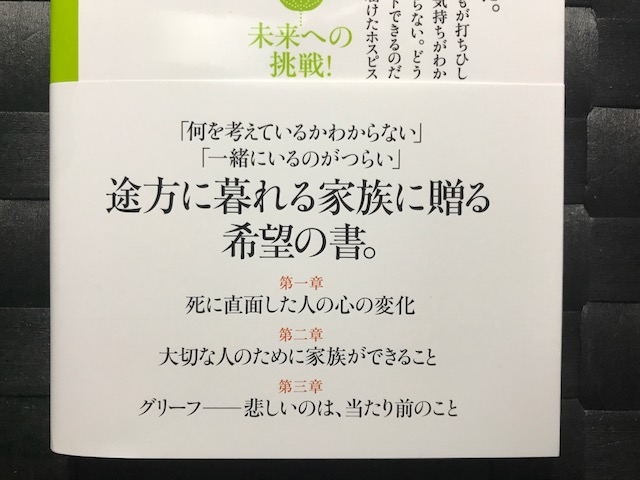 本書の帯の裏
本書の帯の裏
さらにカバー裏表紙には、「1回しかない『最期のお別れ』を、かけがえのない時間にするために」として、以下のように書かれています。
「大切な人との死別はつらい。あまりのつらさに誰もが打ちひしがれるだろう。そもそも私たちは死に逝く人の気持ちがわからない。何かしたいのに、何をしたらいいかがわからない。どうすれば、末期の患者さんの心に寄り添い、サポートできるのだろう?本書では、1200人以上の人生を見届けたホスピス音楽療法士が、数多くの実話を紹介しながら、穏やかな『見送り』に必要なことを説く」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 死に直面した人の心の変化
一、孤独感(Isolation)
二、ショックと否定(Shock&Denial)
三、怒りと悲しみ(Anger&Sadness)
四、不安と恐怖(Anxiety&Fear)
五、希望(Hope)
第二章 大切な人のために家族ができること
一、やり残したことを叶えるためのサポート
二、その人の人生の物語を知る(ライフ・レビュー)
三、正直な会話をする――そのための3つのことば
四、象徴的なメッセージを見逃さない
五、音楽で気持ちを伝えるためのヒント
第三章 グリーフについて
――悲しいのは、当たり前のこと
一、グリーフを経験している人の心
二、遺される子どものグリーフについて
「おわりに」
「参考資料」
「はじめに」では、「患者さんを『癒す』ことができるのは、本人だけ」として、著者は以下のように述べています。
「死に直面したとき、人はさまざまな痛みや苦しみを経験する。病気に伴う体の痛みや不快感の大半は、薬をうまく使うことによって抑えることができるが、スピリチュアルペイン(精神的な痛み)は薬では解決できないため、対応が難しい。もちろん、そのような患者さんと向き合わざるを得ない家族の苦しみも、同様に大きくつらいものとなるだろう。スピリチュアルペインとは、簡単に言えば、自分らしく生きられなくなった悲しいや、人生の意味を見出せない苦しみ、人生を振り返ってやり残したことへの後悔、大切な人との関係を修復できない苦悩などを指す。それらの痛みを『癒す』ことが容易でないことは、想像できると思う」
また、著者は以下のようにも述べています。
「本来の意味での『癒し』が実現するためには、その人自身が問題と向き合い、取り組む必要がある。なぜなら、心が回復したり成長したりするために必要な力は、その人の中にしかないからだ。死に直面した人の場合も同じで、彼らを『癒す』ことができるのは、本人だけだ。末期の病気とともに生きる人びとがもともと持っている力を引き出し、彼らが尊厳ある穏やかな最期を迎えることができる『環境』をつくること。それがホスピスケアの目的であり、音楽を通して患者さんや家族に寄り添い、それを実現するのが音楽療法士の役割だと私は思っている。そしてこの過程において、家族は重要な役目を果たす。いや、家族だからこそ果たせる役目があるのだ」
「『看取り』から『見送り』へ」として、著者は「人の死に立ち会うことは、赤ちゃんの誕生に立ち会うことに似ている。新しい命をこの世に迎えるように、亡くなる人が次のステージへと向かう手助けをすることが求められるからだ。その感覚は、『看取る』というよりは『見送る』に近い」と述べ、さらに以下のように述べます。
「現在、日本国内では、約8割の人が病院で亡くなる。ホスピスケアや在宅ケアを利用する人はごく一部にすぎない。そして、信じがたいことかもしれないが、病院では日々、苦しみながら亡くなっていく患者さんたちがたくさんいる。自分の意思ではない延命治療を受けている人。治る見込みがないのにいつまでも治療を続けて、その副作用に苦しみ息絶える人。十分な疼痛ケアを受けられず、激しい痛みとともに旅立つ人。彼らの多くは、自分の死と満足に向き合うこともなく、死への準備もできずに亡くなる。それは、とても悲しいことではないだろうか?」
また著者は、「ホスピスは『場所』ではなく『ケア』そのもの」として、以下のように述べています。
「ホスピスと緩和ケアは、どちらも生命を脅かす病を患った患者さんに苦痛がないよう、医療行為のみならず心のケアを提供することを目的としている。そして、ホスピスケアは末期の患者さんに提供されるものだが、緩和ケアは早期の患者さんにも提供される。これがホスピスと緩和ケアの最も大きな違いだ。どちらも本来、病名を問わず必要な人に提供されるべきケアである」
さらに、「死に直面した人の体に起こる変化」として、著者は述べます。
「『死』には絶対に共通の点がひとつだけあり、それは、いくら死期が近いとわかっても、実際にその人がいつ亡くなるかは誰にもわからない、ということだ。衰弱したまま数日間生きる人もいれば、たった数時間で旅立っていく人もいる。このいわゆる『待ち時間』は、家族にとって精神的にも肉体的にも最も疲労が伴う期間となる。
そして、「患者さんが最期まで生き抜くための力」として、著者はこう述べるのでした。
「『死』に際したとき、人は、今まで命を維持してきたさまざまなものを必要としなくなる。体のエネルギーもどんどんなくなっていく。見守る家族が無力感を抱くのも無理はない。家族や医療者が何をしようと、失われていくものだ。しかし、それでもなお、患者さんには残されている力がある。それは、スピリチュアル(精神的)なエネルギーだ。本論で詳述するが、それこそが、彼らが最期の瞬間まで生き抜くことを支える力となる。また、多くの人は知らないが、聴覚は最期まで残る感覚だ。反応がなく、目も開けられない患者さんであっても、耳はちゃんと聞こえている」
第一章「死に直面した人の心の変化」では、「死に逝く人の気持ちがわからない理由」として、著者は以下のように述べています。
「患者さんと周囲との関係には、すき間ができていくのだ。何より、最も大きな原因は、私たちには『死』について教えてくれる人が誰もいなかった、ということだろう。昔は死がもっと身近にあり、病気の人に接することも頻繁にあった。だが、今やたいていの死が病院で起こるので、医療者でもない限り、一般の人が死を目のあたりにすることは、一生のうちで教えるほどしかない。ほとんどの病院では、死期が近づいた患者さんは個室へと移される。本人とご家族のためという理由もあるが、むしろこれは、他の患者さんを動揺させないための措置だ。このように日本では、多くの人が死を迎える病院においてさえも、死が遠くに追いやられているのである」
また、「対応が難しい5つの心の変化」として、著者はエリザベス・キューブラ―・ロスの『死ぬ瞬間――死とその過程について』を取り上げます。精神科医のロスは、同書で、死の受容のプロセスとして5つの段階を提示しました。末期の病気の宣告されたときから死に至るまでに、「否定」→「怒り」→「取引」→「抑うつ」→「受容」という段階があるという考えで、非常に有名です。著者の佐藤氏は「この本は医療関係者を含め、多くの人が死について考えるきっかけをつくったという意味で大きな功績を残した。ただ、いくつか問題点も指摘されている。そのひとつとして、死を迎える人の心を『段階』として考えた点が挙げられる。彼女は、患者さんがひとつひとつの段階を通過することで、最終的に死を受け入れる『受容』の段階にたどり着くと言った」
続けて、佐藤氏は以下のように述べています。
「しかし、『受容』は何も死という旅の最終地点ではなく、あらゆる段階で見られる現象だ。また、すべての患者さんが5つの段階を通るとは限らない。ひとりひとり道のりが違うため、パターン化するのは非常に難しい。死と向き合ったときに起こる感情やそれへの対応方法は、患者さんがそれまで生きてきた人生や性格、周りのサポートの有無、彼らを取り巻く環境などによっても大きく変化する。患者さんの気持ちというのは波のように絶え間なく変化するし、その変化に特定のパターンがあるわけでもないから、極めてランダムなのだ」
二「ショックと否定(Shock&Denial)」では、「『死』はきれいごとではない」として、著者は以下のように述べます。
「死ぬということは、決してきれいごとではない。人生が終わることへのショックや否定の気持ちから、一歩前に進むには時間がかかる。歩むペースがひとりひとり違うように、死への準備にもそれぞれのペースがあるのだ。周りはそれを見守ることしかできないが、患者さんの心の準備ができたときにはしっかりサポートしてほしい。それが重要だ」
三「怒りと悲しみ(Anger&Sadness)」では、「怒りの底にある悲しみや苦しみ」として、著者は以下のように述べます。
「死と向き合う人は、今まで大切にしてきたすべてを失うという感覚に襲われている。家族、友人、仕事、趣味、ペット、将来の夢。過去も未来も、文字通りすべてだ。患者さんは、この打ちのめされるような悲しみと向き合っていることを、周りの人には知っておいてほしい。それに気づいて初めて、怒りに囚われた患者さんを励まそうと考えることもできる。しかし、励ますのもまた難しい。なぜなら、その励ましが患者さんから悲しみを表現する機会を奪い、喪失感を一層深くしてしまうこともあるからだ」
四「不安と恐怖(Anxiety&Fear)」では、著者は、「死と向き合ったときに人間が感じる「恐怖」は、死そのものへの恐怖というより、死に至るまでの恐怖である場合が多い。祖父のように寝たきりになることを恐れる人もいれば、痛みが増すのではないか、苦しいのではないか、適切なケアが受けられないのではないか、と不安になる人もいる。このような場合、周りの協力で患者さんの不安は軽減される」と述べています。
また、「死にまつわる『不確かさ』」として、著者はこう述べます。
「『人間が抱く最も古く強い感情は恐怖であり、その中で最も古く強い恐怖は、不確かさの恐怖である』と語ったのは、ホラー作家のハワード・フィリップス・ラヴクラフトである。彼の言うように、人間にとってわからないことほど恐いものはない。結論を知ってしまえば『そんなものか』ということであっても、その正体がわからないままに予期しているときは恐ろしく思えてしまう。死を迎えるまでの過程は、まさにこの『不確かさ』とともに生きることに等しいため、患者さんの中には恐怖心が募っていくのである」
かつて、俳優の丹波哲郎さんが「死が怖いのはわからないからだ。死後の世界がわかれば、死は怖くなくなる」と言って、映画「大霊界」を作られたことが思い出されます。
著者は、「選択肢を増やすことで不安を軽減する」として、こう述べています。
「死と向き合う人には、なるべく『コントロール感』(sense of control)を持たせることが重要だ。コントロール感とは文字通り、本人にコントロールできる『感覚』があるということだ。私たちはコントロール感が少なくなればなるほど不安を感じやすくなる。わかりやすい例をあげると、車よりも飛行機のほうが怖いという人ははるかに多い。統計から見れば、車よりも飛行機のほうがはるかに安全なのに、なぜだろう。車の運転は自分でコントロールできる、もっと正確に言えば、コントロールできる『感覚』がある。一方、飛行機は自分の身を他人に任せなければいけないのでコントロール感が低い。だから恐怖が増すのだ」
また、「宗教は恐怖に囚われた心を救えるか?」として、著者は述べます。
「恐怖に関連して、多くの人から聞かれる質問にお答えしたい。それは、『宗教を信じている人は死を恐れないのか?』という問いだ。多くの日本人は特定の宗教を信仰していないから穏やかな死が迎えられないのではないか、欧米人はクリスチャンだから安らかに死を受け入れられるのではないか。このように考える人は驚くほど多い。簡単に答えると、宗教の有無で死への恐怖をはかることはできない。キリスト教徒の場合、天国に行くという希望が死の恐怖を和らげる場合もあるが、その反面、地獄へ行くかもしれないという恐怖とともに亡くなる人もいる。今まで出会った中で最も死を恐れた人は、皮肉にも信仰深い人だった。日本人の患者さんは仏教徒や信仰を持たない人が多いが、『亡くなった人がお迎えに来てくれる』『死んだ人にあの世で会いたい』という希望に支えられている患者さんは多い。死への恐怖は、宗教よりもむしろ『スピリチュアリティー』に関係している」
さらに、宗教について、著者は述べます。
「宗教とはある集団の信仰であるのに対して、スピリチュアリティーとは神聖なものと自分、世界と自分との関係性を指す。他人を思いやる気持ち、感謝の気持ち、自分を生き生きとさせるもの、人生に意味を与えるもの。そういったものが、その人のスピリチュアリティーと言える。つまり、すべての人に宗教心があるわけではないが、スピリチュアリティーは誰もが持っているものなのだ」
そして、著者は「私たちは死ぬときに、人生で得たものを持ってはいけない。死んだあとに残るのは、自分が他人に与えたものだけだ。他者といい関係を築き、満足した人生を送った人ほど後悔は少ない。そして、そういう人ほど死を恐れないものだ。だからこそ、『やり残したこと』を解決することが、患者さんの不安や恐怖を軽減する上でとても大切になる」と述べるのでした。
五「希望(Hope)」では、「死に逝く患者さんの、未来への希望」として、著者は以下のように述べています。
「希望がなければ人生ははじまらないし、意味あるものとして終わらない。そう語ったのは発達心理学者のエリック・エリクソンだが、事実、治る見込みがなかったとしても、患者さんにはさまざまな希望がある。『お正月を家族と過ごしたい』『家で最期のときを過ごしたい』『孫に会いたい』『旅行したい』『好きなものが食べたい』『好きな音楽が聴きたい』『ペットと生活したい』。まずは、患者さんにどのような希望があるかを知ることが大切だ。そして彼らの希望を叶えることが、心の支えにつながる」
第二章「大切な人のために家族ができること」の一「やり残したことを叶えるためのサポート」では、「悲しみは前もってやってくる」として、著者はこう述べています。
「グリーフとは、簡単に言えば大切な人との別れによって起こる深い悲しみのことだ。そして、グリーフは何も死別の後だけに起こるものではない。実際に死が起こる前に経験するグリーフを『アンティシパトリーグリーフ』と呼ぶ。アンティシパトリーとは『予期しての』という意味で、大切な人の死を予期して起こるグリーフのことだ。アンティシパトリーグリーフの症状は、当然だが、グリーフのそれと似ている。ショック、否定、怒り、後悔、深い悲しみ、不安、孤立感など、さまざまな感情が入り交じる。夜眠れない、食欲がない、集中できない、物忘れが激しくなるなど、身体的・認知的な影響が出る場合も多い」
二「その人の人生の物語を知る(ライフ・レビュー)では、 人生を振り返り、内省することを「ライフ・レビュー(回想)」ということが説明され、「回想は、死に直面した人に必ず起こる。死が迫ってきたとき、本人が意識してもしなくても、これまでの人生で起こったことや、健康だったころはあまり考えなかった昔の思い出が自然とよみがえってくるのだ。『走馬灯』という言葉があるが、人は、人生の危機に接したときに回想を経験する。死とは、言ってみれば人生最大の危機なのだろう」「回想には極めて重要な役割がある。過去を振り返り、内省することで彼らは人生の意味に気づき、現状を乗り越える力を得ていく。そしてときには、やり残したことに気づいたりもするのだ」と述べられています。
さらに「死を超えるものとは?」として、著者は「死を超えるものがあるとしたら、それはまさしく愛であろう。死に逝く人たちもまた、それに気づくのだ」と述べ、「『ボーナブル』な私たちと『大きな器』の話」として、「末期の患者さんというのは、とてもボーナブル(vulnerable)な状況にある。ボーナブルとは、誰かの支えを必要としていたり、困っていたり、傷つきやすくなっている『状態』を指す。日本語にはない表現で、『弱者』とも意味が違う。ボーナブルは、患者さんに限らず誰もが経験することだ。たとえば、言葉の話せない国に行ったとき、暗い夜道を1人で歩いているとき、風邪にかかったときなどには、ボーナブルな状態になり得る。そして死期が近づいているとき、私たちは人生で最もボーナブルな状態にあると言えるだろう」と述べています。
三「正直な会話をする――そのための3つのことば」では、著者は「許す」ということについて、以下のように述べています。
「許すとは、何も相手の行為を無条件に肯定することではない。許すとは、「過去に起こったことは、もう変えることができない」と、ただ受け入れることなのだ。そうすることで初めて、私たちは怒りや後悔から自由になれる。怒りを持ち続けるということは、とてもしんどいことだ。エネルギーも時間も相当に消耗する。許すこと、受け入れることには勇気がいる。でもそれは、何よりも自分自身のために必要な行為なのだろう」
また、「今、伝えることの大切さ」として、著者は以下のように述べます。
「人は、自らの死を悟る。患者さんに病気のことを隠し通すことはできない。だからこそ、ここで重要なのは、告知をするかしないか、ということではない。どのように告知をするか、そしてそのあとどうやってサポートしていくかだ。つまり、『弱い人を守る』という視点ではなく、『ボーナブルな状態にある彼らをいかに支えるか』という視点でのアプローチが求められるのである」
四「象徴的なメッセージを見逃さない」では、「ビジョンや夢」として、著者は以下のように述べています。
「死を迎える数週間前に、患者さんが亡くなった家族や友人に関するビジョンや夢を見るということは、研究結果からもわかっている(近年ニューヨーク州のホスピスで行われた研究では、患者さんが見た夢やビジョンはすでに亡くなった家族や友人に関するものが多く、それらは彼らに安らぎを与えるものだと判明した)。患者さんは、その人たちが見守ってくれているとか、もうすぐお迎えに来る、というような感覚があると語る。家族は驚くかもしれないが、これはあくまでも普通の現象であり、患者さんにとっては大きな意味を持つのだ」
すでに他界した家族が迎えに来るという「お迎え現象」と呼ばれるものは、アメリカのホスピスでもよくあるそうで、人類共通だといいます。この「お迎え現象」について、著者は以下のように述べます。
「これらの体験は患者さんにとっては意義深い体験だが、それを受け止める家族の側が困惑してしまうことが多い。『単に夢を見ただけだよ』『お母さんは昔亡くなったじゃないの』『おじいさんが見えるはずない』『薬のせいで混乱しているに違いない』『幻覚を見ているだけだろう』――このような言葉を、家族からよく聞く。もし、あなたが死に逝く人の夢やビジョンを単なる幻覚だと切り捨て、その意味を理解できないでいると、彼らとの距離はどんどんと開いていくことになるだろう。そして、ときにそれが、患者さんの葛藤の原因になってしまうこともある」
第三章「グリーフについて――悲しいのは、当たり前のこと」では、著者は以下のように述べています。
「死との向き合い方に個人差があるように、グリーフの過程も千差万別だ。あなたがどのようにグリーフを経験するかは、あなたの性格や人生経験、大切な人がどのように亡くなったか、その人との関係はどうだったかなど、さまざまな要素が影響する。反応にも個人差があり、悲しみで涙が止まらない人もいれば、しばらくの間ショックで何も感じない人もいる。どれが正しいということはない。どれもその人なりの自然なグリーフの表れなのだ」
一「グリーフを経験している人の心」では、「孤独感」として、著者は述べます。
「本来、グリーフは社会的な過程である。グリーフを乗り越えるためには、家族や友人、同僚や近所の人々など、周りからのサポートが必要なのだ。しかし現代社会ではそのサポートが欠けているため、本人の孤独感は強まってしまう。また、グリーフの過程はひとりひとり違うので、理解するのが難しい。たとえば、夫を亡くした未亡人同士でもグリーフは異なる。故人の亡くなり方や年齢など、さまざまな要素がグリーフに影響を及ぼすからだ。そして、亡くなった人との関係やあなたの性格も影響する。だから、子どもを亡くした両親であっても、それぞれグリーフの反応が違うというのは、ごく普通のことなのだ。アメリカ人の作家ウィラ・キャザーが言うように、他人の心は、それがどんなに自分自身の近くにあったとしても、『暗い森(dark forest)』のようなものなのだ。人の心は根本的にはわからない。どんなに優れたセラピストであっても、である」
これは、わたしの実体験からもよく理解できます。「人の心は根本的にはわからない」というのは、とても共感できます。
また「ショックと否定」と、著者は述べます。
「アメリカ人作家のジョーン・ディディオンは『悲しみにある者』で、長年連れ添った夫を亡くしたのちの1年間を振り返っている。夫が心臓発作で亡くなったあと、しばらくの間、ジョーンは『摩訶不思議な考え(magical thinking)』をしていたと語っている。たとえば、彼女は亡くなった夫の靴を捨てることできなかった。彼が帰ってきたときに靴がないと困ると思ったからだ。そして夫の臓器提供を拒否した理由も、臓器がなければ彼は生き返ることができないと感じたからだった。このように『死んだ人がもしかしたら帰ってくるかもしれない』という感覚は、グリーフの症状のひとつだ。愛する人の死を、頭では理解していても、心では受けとめられていないのである」
さらに「不安と恐怖」として、著者は述べます。
「イギリス人の作家C・S・ルイスは妻の死後、『グリーフが恐怖とよく似ているとは、誰も教えてくれなかった』という有名な言葉を残した。彼は妻の死に際し、心の動揺や不安が、恐怖の感情と同じだと思ったのである。グリーフのときに私たちが恐怖を感じる理由のひとつは、大切な人を失うことで自分の死への認識が高まることにある。自らの『死すべき運命』を否定することができなくなるし、他の家族もいつか失うという事実からも逃れられなくなるのだ。中には、自分はこれからどうなってしまうのだろう、という漠然とした不安に襲われる人もいる。新しく果たさなければいけない責任や役割に、圧倒されることもあるだろう」
著者は、「今日妻と会うことができない、という事実は受けとめることができる。でも、彼女と一生会えないという事実を受けとめることはできない」という妻を亡くした70代の男性の言葉を紹介しています。そして、「周囲にサポートを求める」として、以下のように述べています。
「故人が死に至った過程を何度も繰り返し話すというのも、グリーフの症状のひとつである。病気を悟ったころから今に至るまでの経過や、そのときの気持ちなどを何回も語っている自分に気づくときがあると思う。これが実は、グリーフの過程において重要な役割を果たす。ショックな出来事があったとき、それを受けとめて前に進むまでには果てしなく時間がかかる。そんなとき、誰かに話をすることによって、受け入れたくない出来事を少しずつ受け入れることができるようになるのだ」
また、「複雑なグリーフは専門家に頼る」として、著者は述べます。
「自殺や他殺による死や、事故や災害で多くの人を同時に失った場合などは、当然、グリーフもかなり複雑になる。たとえ家族を病気で失ったとしても、あなたが以前に複雑なグリーフを経験したことがある場合や、故人との関係がこじれていた場合、あるいはもともとの精神状態などによって、複雑になる場合もある。自分も一緒に死にたかったなどと思ったり、人を信頼できなくなったり、月日が経っても故人の死を認めることができなかったりすることもあるだろう。もしかしたら、亡くなった人の死を自分のせいだと思ってしまうかもしれない。このような症状がある場合は、いち早く専門家の助けを求めて欲しい」
二「遺される子どものグリーフについて」では、著者は以下のように述べています。
「大人のグリーフと比べ、子どものグリーフは複雑化しやすい。家族を失ったあと、子どもは大人と同じようにさまざまな感情を抱くが、子どもはその複雑な感情を的確に表現する言葉を持っていないため、気持ちが行動に出てしまいがちだ。グリーフを乗り越えられなかった子どもは、のちに非行に走ったり、登校拒否やひきこもりになったりする場合もある。周囲の大人の反応によって、子どものグリーフの過程は大きく変わる」
「子どもせいではないと伝える。そして、亡くなった人の話を避けない」として、著者は以下のように述べます。
「人が亡くなったとき、周囲の大人は死んだ人の話を避けようとする。これも子どもを守りたいという気持ちからだと思うが、逆効果になる。子どもは、死んだ人が忘れられてしまったと感じるだろう。大人と同様に、子どもも大切な人を忘れてほしくないという希望を持っているのだ。それに、故人の話を避けることは、子どもから死について質問したり気持ちを表現したりする場を奪うことになりかねない」
続けて、著者は以下のように述べています。
「ショックを与えないために、お葬式やお通夜に子どもは参加させないほうがいいのでは?と考える人もいるようだ。しかし、このような場があるからこそ、子どもは大切な人にきちんとお別れすることができる。無理に参加させる必要はないが、子どもが自分で決められる年齢であれば、本人にどうしたいか聞くといい。あらかじめお葬式がどういうものなのか説明しておけば、子どもも安心できるだろう。亡くなった人への最期の贈り物として、子どもが書いた絵や手紙、故人と一緒に撮った写真やおもちゃをお棺に入れることも、子どもがお別れをする手助けとなる」
また、「思春期の子どものグリーフ」として、著者は述べます。
「この世代の子どもたちにできることはシンプルだ。『悲しんでもいい』ということを、教えてあげればいい。グリーフにはさまざまな感情があって、それは避けて通れないもので、今感じている気持ちがどんなにつらくても、いつか必ず変化する――。そういうことを、周りの大人たちから伝えてあげてほしいのだ」
続けて、著者は以下のように述べています。
「大切な人を失った子どもは、人生の過程の中で何度もグリーフを経験する。卒業式、就職、結婚式、出産など、人生における大きな出来事を経験するたびに、亡くなった人のことを思い出すからだ。しかし、これは彼らのグリーフが解決していないことを意味するのではない。その悲しみは、彼らの成長過程においてあくまでも普通のことであり、そのたびに素直に悲しむことで、彼らは何度でもそれを乗り越え、強く、未来へと歩んでいけるのだ」
さらに、「グリーフは『克服する』ものではなく、『乗り越えていく』もの」として、著者は以下のように述べています。
「心の傷は目に見えないだけで、体の傷と似ている。最初は血が止まらず痛いが、そのうち、かさぶたができる。私の腕には、中学生のころに転んでできた傷がある。今でも他の皮膚と色は違うし、触った感触も違う。グリーフも同じように、時間が経つにつれ痛みは減っても傷跡は消えない。大切な人が占めていた心のスペースを埋めることはできないのだ。つまり、グリーフとは『克服する』」(get over)ものではなく、『乗り越えていく』(get through)ものと言える」
そして、著者は「強く愛することができる人だけが、大きな悲しみを経験する。しかし、その愛こそがグリーフを乗り越える力となる」というロシア人の小説家トルストイのことばを紹介し、「喪失の悲しみから前進するための原動力は、あなたの故人への愛情なのである」と訴えるのでした。本書は、ホスピス緩和ケアの実践を積み重ねてきた著者だからこそ到達した地点から「グリーフケア」の本質と可能性を語った名著であり、グリーフケアに関わるすべての人々に読んでいただきたいと思います。
