- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1595 プロレス・格闘技・武道 『ゴング格闘技ベストセレクション 1986-2017』 ゴング格闘技・編(イースト・プレス)
2018.09.06
『ゴング格闘技ベストセレクション 1986-2017』ゴング格闘技・編(イースト・プレス)を読みました。格闘技専門誌「ゴング格闘技」は1986年に創刊されました。それから31年で通算300号を達成。長期連載した「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」が第43回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞するなど、格闘技を題材に多くの著名作品、著者を輩出しました。本書は同誌の過去の記事やインタビューの名作セレクションで557ページもありますが、非常に面白かったです。
 本書の帯
本書の帯
帯には「格闘技にすべてを―『ゴング格闘技』三十一年の取材史。」「『木村政彦vsエリオ・グレイシー』『VTJ前夜の中井祐樹』を含む、”ゴン格”珠玉のノンフィクション&インタビュー傑作選」と書かれています。
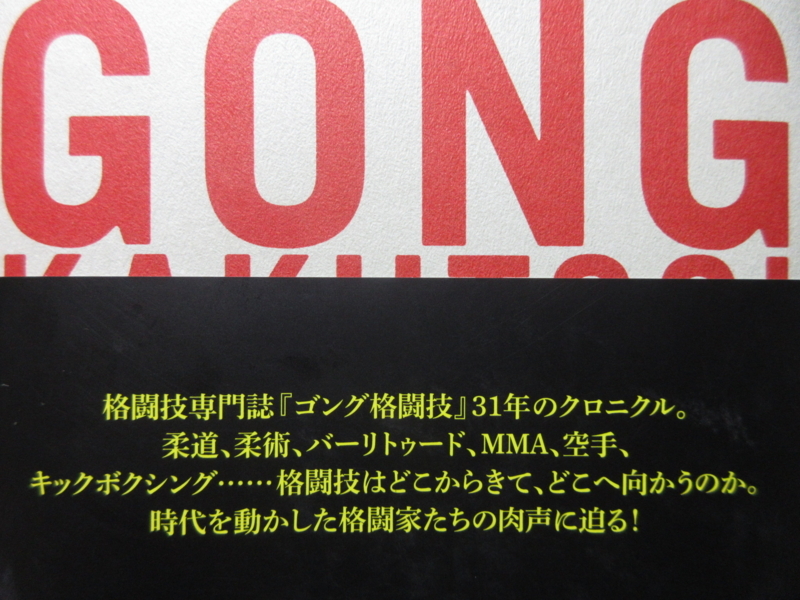 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「格闘技専門誌『ゴング格闘技』31年のクロニクル。柔道、柔術、バーリトゥード、MMA、空手、キックボクシング・・・・・・格闘技はどこからきて、どこへ向かうのか。時代を動かした格闘家たちの肉声に迫る!」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
第1章 柔道と柔術
第2章 ヴァーリトゥード・ジャパン
第3章 日本総合格闘技
2017 PLAYBACK! Japan MMA
《コラム》UFCありき―と、させなかった夜明け前の歩み
第4章 MMA、世界の頂
2017 PLAYBACK! Overseas MMA
《コラム》UFCから始まったMMAの25年
第5章 空手とは何か
第6章 立ち技格闘技の挑戦
2017 PLAYBACK! Striking
《コラム》カラテの伝播とキック・K-1の誕生
第1章「柔道と柔術」の「木村政彦対エリオ・グレイシー~マラカナンスタジアムの戦い」では、1951年10月23日に柔道史上最強とされる”鬼の木村”こと木村政彦がブラジルのマラカナンスタジアムでグレイシー柔術のエリオ・グレイシーと戦ったエピソードが綴られています。筆者の増田俊也氏は、ネット上にアップされた木村の試合前の表情について以下のように述べています。
「当時は今とは比べものにならないほどブラジルは遠かったであろう。しかし、地球の裏側に来てさえ、木村はこの地上に自分より強い生き物がいるなどとは露ほども思っていないのである。たしかに、柔道がまだ実戦性を持ち、総合格闘技のなかったこの時代、木村が世界最強だった可能性は非常に高い。このときの木村の表情や所作が、私にはそれぞれの地で生態系の頂点に立つライオンやホッキョクグマ、シベリアトラなどに見えてしかたがない。目の前に美味そうな肉があればそれを食らい、美しい雌が目につけば躊躇なくのしかかる。怖いものなど何もないのだ」
増田氏は「木村、ヒクソンと戦わば」として、木村政彦とエリオの息子である”400戦無敗”の柔術家ヒクソン・グレイシーがお互いに全盛期に激突していたらどうなったかという興味深いシミュレーションを行います。増田氏から意見を求められたブラジリアン柔術家の植松直哉氏は以下のように述べています。
「ヒクソンの柔術の試合をそんなに多く見ていないので断言はできないですけれども、ネット上にアップされてるヒーガン・マチャドとやった試合を見るかぎり、ああいうミスをするのであれば、木村先生の抑え込みが非常に強烈なので……。エリオとヒクソンの技術の系統は同じだと思うんです。となると、木村先生が普通に勝つのではないかと思います。木村先生はただの寝技の強い柔道家ではないですからね。キムラロック(腕緘み)という絶対の極め技を持ってますから、そこに強みがあります。ただ時間はかかると思います。エリオよりヒクソンの方がフィジカルが強いので」
また、異種格闘技戦に対する植松氏の以下の意見には納得しました。
「よく異種格闘技戦のことをバスケットボールとサッカーとどちらが強いかというのと同じだという批判をする人がいますけど、僕は違うと思うんです。球技とは違うんですよ、格闘技は。ルールを削っていけば柔道対柔術、柔道対空手、柔術対ボクシングというのは論じられるわけですね」
「これをスポーツとして興行としてやったら違うと思うんですけど、こうしてどちらが強いかという果し合いでやったら、決闘だと思うんですよね。そのために必要最低限のお互いのルールを決めているだけであって、やはり武道を名乗る以上、柔道もブラジリアン柔術も実戦という想定だけは忘れてはいけないと思います」
柳澤健氏が書いた「講道館史観を越えて―光の柔道、影の柔術」も興味深い内容でした。柳澤氏は、20世紀初頭に大人気を博した探偵小説の主人公であるシャーロック・ホームズとアルセーヌ・ルパンの名前を出して、以下のように述べます。
「ホームズもルパンも、実は柔術の使い手でした。1903年にコナン・ドイルが発表した『空き家の冒険』は、宿敵モリアーティ教授と共にスイスのライヘンバッハの滝に落下して死んだはずのホームズが『自分は日本のバリツを使って危地を脱したのだが、手下に復讐されるのを恐れて潜伏していた』と、親友ワトソンに説明するシーンから始まります」
バリツとは柔術のことで、柳澤氏は「1906年にモーリス・ルブランが発表した『アルセーヌ・ルパンの脱獄』には、逮捕しようと襲いかかってきたガニマール警部を、ルパンが日本の柔術をつかって撃退するシーンが登場します」と書かれています。
なぜ、当時のヨーロッパで柔術がそれほど有名だったのでしょうか?
それは、1人の日本人柔術家が前田光世以前に異種格闘技戦を行ない、大評判を詠んだからでした。その男の名は谷幸雄。天神真楊流の柔術家で、身長は160センチに満たず、体重は60キロもありませんでした。そんな彼が演芸場で「誰の挑戦でも受ける。私を打ち破ったものには大金を差し上げる。ただし柔道着を着ること」と言ったのです。黄色い顔をした小男の挑戦に、キャッチ・アズ・キャッチ・キャンの母国であるイギリスの人々は大笑いして「賞金はもらった!」と、我先に名乗りを上げました。しかし、谷幸雄を打ち負かした者は1人もいなかったのです。
谷幸雄は生涯に数千試合を戦い、大金持ちになりました。キャッチ・アズ・キャッチ・キャンのライト級王者であるジミー・メラーにも勝利しました。柳澤氏は、以下のように書いています。
「小さな日本人が、雲をつくような大男をギブアップさせ、失神KOに追い込んだこと、そして失神させた相手に活を入れ、蘇らせた事実は『日本人は一度死んだ相手を蘇えらせることができるのか!』とイギリス人を仰天させました。
かくしてスモール・タニと、活殺自在の神秘的な格闘技『ジュウジツ』の名は英国中に轟き、たちまちのうちにドーバー海峡を超え、ルパンの作者モーリス・ルブランの耳に達したのです」
谷幸雄のフォロワーは数知れないとして、柳澤氏は以下のように述べます。
「谷のすぐ後に渡英したRAKUこと上西貞一も英国で有名になりました。不遷流の伝説的柔術家・田辺又右衛門の弟子にあたる三宅多留次は、谷幸雄と戦って完勝した後、アメリカに渡ってプロレスラーとなり、ハワイで沖識名に技を教えました。つまり力道山は三宅の孫弟子にあたります。
堤宝山流の東勝熊はニューヨークでプロレスラーのジョージ・ボスナーと戦って敗れました。有名なアド・サンテルは、ボスナーの弟子筋にあたります。
これらの柔術家の他に、前田光世、伊藤徳五郎、佐竹信四郎、大野秋太郎のいわゆる『キューバの四天王』、アド・サンテルとの試合中に大金持ちの未亡人に見初められて結婚した太田節三、靖国神社でアド・サンテルと戦った後、アメリカ西海岸に渡った庄司彦雄らの柔道家たちがいます」
続けて、柳澤氏は以下のように述べるのでした。
「その他、数知れない無名の柔術・柔道家たちが見ず知らずのボクサーやレスラーとリアルファイトを行ない、少数の『プロレス』を行ないました。
日本には、彼ら柔術・柔道家が自らの血と汗と涙と痛みで作り出した『異種格闘技戦』の伝統が存在するのです。
その伝統があるからこそ、私たちはアントニオ猪木を愛し、UWFを愛し、グレイシー柔術を愛し、PRIDEを愛し、総合格闘技を愛するのです。さらに言えば、殴り倒しての勝利よりも、関節技や絞めの勝利に、ロマンを強く感じる傾向にあるのもそのためでしょう」
かつて、講道館柔道に実力で立ち向かった柔術家がいました。
不遷流四世・田辺又右衛門です。彼は恐るべき寝技の使い手であり、講道館の猛者たちを得意の十字締めで次々と締め落とし、あるいは必殺の足搦みで靭帯損傷に追い込みました。その結果、加納治五郎は足搦みを禁じ手にしてしまったのです。柳澤氏は述べます。
「柔道においては、立ち技と寝技は車の両輪などと言われますが、講道館は、現在に至るまでずっと寝技を忌避し、蔑視し続けてきました。その原点は田辺又右衛門にあると言って良いでしょう。
その結果、講道館柔道は寝技に対して、致命的な『盲点』を持つようになります。神永昭夫はヘーシンクに抑え込まれ、岡野功はサンボの選手に巴投げから腕ひしぎ十字固めで敗れました。戦後最強の柔道家である山下泰裕でさえ、蟹挟みで重症を負った経験を持っています。日本最強の寝技師と言われた加藤博剛が、ブラジルの柔術家フラビオ・カントの前に手も足も出ないまま、腕ひしぎ十字固めで完敗したのは記憶に新しいところです」
最強の柔術家といえば、ヒクソン・グレイシーです。
「2013年11月20日。ヒクソン・グレイシーは、闘いに赴く息子クロンの魂を思い、涙した。」で、堀内勇氏はヒクソンへのインタビューの最後に、「日本の読者や柔術愛好家たちにメッセージを」と呼びかけ、以下のようなヒクソンの言葉を引き出しています。
「柔術を愛する者たちはみんな、練習を続けるべきだよ。柔術というのは単なる競技ではないんだ。自分を見つめ、問題に出会ってその解決を探せるようになるのが柔術なんだ。そのことを経験して、自分自身に関する知識を得ることで人は成長する。仕事でも、家庭でも、友人関係においてもね。私は読者のみなさんに、マーシャルアーツを通じてこのような心の成長を体験し、より良い人間となっていただきたいと思っているよ」
ヒクソンに果敢に挑んで敗れた日本人格闘家に修斗ウェルター級王者だった中井祐樹がいます。「バーリトゥード・ジャパン・オープン95」で、「打倒ヒクソン」に燃える修斗が日本の格闘技界の最後の切り札として出場させたのが、中井祐樹でした。ところが、中井のトーナメント1回戦の相手は「第1回UFC」で準優勝し、「喧嘩屋」の異名をとるオランダの巨漢空手家、ジェラルド・ゴルドーでした。ゴルドーが198cm・100kgなのに対し、中井は170cm・70kgしかありませんでした。マスコミは「危険だ」といって騒ぎましたが、激闘の末に中井は4ラウンドにヒールホールドでゴルドーに一本勝ちしました。しかし、この試合中にゴルドーのサミングを受け、右眼を失明したのです。じつに凄惨な試合でした。
第2章「バーリトウード・ジャパン」の「VTJ前夜の中井祐樹。」で、増田俊也氏は、伝説のVTJ95について、次のように書いています。
「この大会が、本当の意味で日本のMMA(総合格闘技)の嚆矢となった。
神風を起こしたのは、たしかにグレイシー一族でありUFCであった。
しかし、神風が吹くだけでは大きな波がおこるだけで、その波を乗りこなせるサーファーがいなければ、波はただ岸にぶつかり砕けて消えるだけだ。
神風が起こした大波を、右眼失明によるプロライセンス剥奪という死刑宣告と引き替えに乗りこなした中井祐樹がいたからこそ、日本に総合格闘技が根付き得た。それだけは格闘技ファンは絶対に忘れてはいけない」
1994年に「バーリトゥード・ジャパン・オープン94」が開催され、ヒクソン・グレイシーが優勝を飾りました。当時はプロレス全盛時代で、修斗の真剣勝負興行は世間に認知されていませんでした。その頃、海外ではノールール(バーリトゥード)の大会「第1回UFC」が開催されました。優勝したのはホイス・グレイシーという無名の柔術の選手でした。ホイスはその後もUFCの連覇を続けますが、「実は僕より10倍強い兄がいる」と語った発言に、修斗を主宰する佐山聡が注目しました。佐山は、ホイスの兄でグレイシー一族最強のヒクソン・グレイシーを日本に招いて、日本初のノールール(バーリトゥード)の格闘技大会を開くことを決定したのです。
第3章「日本総合格闘技」の「佐山聡、修斗のすべてを語る。『修斗が打倒すべきは自分たちの姿、今の自分たちに満足しないことです』」というインタビュー記事で、熊久保英幸氏は「TBSの修斗のドキュメントで、広島の夏合宿を取材しているときもすごい緊張感があって、竹刀を持っている佐山さんは、とても怖かったです」と言います。それに対して、佐山は次のように答えるのでした。
「あれは合宿では当然です。あれはアドレナリンを上げる練習だったんですよ。今だから全部……これを言ったら次の合宿で方法を変えるしかないんですけど、合宿のときはいかにアドレナリンを上げていくか、というのが僕の課題なんです」
続けて、佐山聡は以下のように述べます。
「あの場面ではキックミットを蹴らせるんですよね。そして、『キミの100%の力で5発蹴ってみて』と言って、選手は思い切り蹴っているんですが、100%の力じゃないんです。そこで僕が豹変するわけです。竹刀も輪っかを上げておいて、ぶらんぶらんにしていて音だけが出て痛くないようにして『お前、俺が言ったようになんでできないんだあ』って思い切り叩くんです。その後のビンタも音が出るように殴るんですよ。それを続けると10分でも100%の力が出るんですよ。これがアドレナリンなんです。これを体に染み込ませるんです」
ホイス・グレイシーがUFC1で優勝したときの衝撃は、日本格闘技界を一変させました。
そのとき、佐山は「マウントの取り方に衝撃を受けましたね」と語っています。「ホイスが登場したときに立ち技の打撃はいらないんだ、という風潮がありましたね」という熊久保氏の発言に対して、佐山は次のように答えます。
「それは僕にはまったくないです。柔術の方が全然有利と言われていますが、実際には互角なんです。総合格闘技には総合格闘技の打撃があるんですよ。それと修斗の理想としては、街の中で誰と戦ったとしても対処ができるように、すべてを持っていたほうがいいと思うんです。それが撲のいう打・投・極、あるいは戦いを修めるということなんです。ただ単に総合格闘技やバーリトゥードに勝ちなさい、というのではなく、打・投・極が回転してすべてが揃って修斗です。寄り集まって揃ったのが修斗ではないんです」
第5章「空手とは何か」の「極真超人録 大山倍達総裁が語る極限への挑戦。」では、有名な山籠もりの間、「何を考え暮していたのか」という熊久保氏の質問に対して、大山倍達が以下のように答えています。
「”俺は昭和の宮本武蔵になるんだ、誰にも負けない”ということを考えていたね。私は自分自身が大きくないことを知っていた。1メートル73センチしか無くて、体重も80キロちょっとしかなかったから。でも、俺はこの小さい体で世界を征服してやろうじゃないか、と思った。それには強さしかない、と。学問ができるわけでもなければ、科学者になれるわけでもなく、他の人のように知識が豊富でもない。頼れるのは自分の身1つ、すなわち自分の肉体、これしかない。
それには、超人的な記録を作るほかに道は無い。では、超人的な記録とは何か、と。超人的な記録とは、人に出来ないことをやるということだよ。人に出来ないことをやるには、それくらいのことをしなければいけないのか? そんなことを毎日考えていて、一発で牛が倒れるくらいになってやればいいじゃないか、と思ったんだね」
第6章「立ち技格闘技の挑戦」の「黒崎健時、魂のメッセージ 闘将の遺産。」は、大山倍達の高弟の1人で”格闘技の鬼”と怖れられた黒崎健時へのインタビュー記事です。1964年2月、「打倒ムエタイ」の命を大山倍達より受けた黒崎健時、中村忠、藤平昭雄(後の大沢昇)の3人はバンコックに降り立ち、ムエタイ選手と戦いました。中村と藤平の2人は無名選手を相手に勝利したものの、黒崎は元タイ国ウェルター級チャンピオンのラウィー・デーチャーチャイに一矢も報いることができず、刀折れ矢尽きる形で、1ラウンドで、12歳年下のタイ人の軍門に下ります。黒崎にとっては生まれて初めてのグローブマッチでしたが、完敗でした。
そのときの屈辱が、後に黒崎をキックボクシングの名伯楽とし、キック史上最強の日本人選手である藤原敏男を育てたわけですが、黒崎は以下のように語っています。
「人間には強い時期もあれば、弱い時期もあるのだ。完全無欠の格闘家など、この世にひとりもいない。
それでなくても、私は今まで”伝説の人”として語られ過ぎたきらいがある。世の中には、あまりにも伝説の人が多すぎる。伝説が1人歩きして、本来の姿が何倍にも膨れあがってしまっているのだ。周りの人間が作りあげた偶像に、本人もその気になっている。私はそのような愚か者にだけはなりたくないのだ。もちろん私に敬意を表してくれるのはうれしいが、みじめな敗北があったからこそ、私は『格闘技の鬼』に徹することができたのだ。私は最初から『鬼』だったわけでもない。そのことを分かって欲しいのだ。格闘技の原点は『強さ』ではない。強くなりたいというあくなき探究心である」
この他、本書には高島学氏による格闘技史についてのコラムが掲載されていますが、複雑な格闘技の変遷をうまくまとめて整理しており、とても参考になりました。
「UFCありき―と、させなかった夜明け前の歩み」の冒頭、「日本のMMAの歴史は、1992年11月12日に始まったわけではない」として、高島氏は以下のように書いています。
「世界的規模でいえば、MMAの歴史はUFCから始まったことは間違いない。ただし、国単位で見ると米国をはじめ世界中の国のほとんどが打撃と組み技&寝技が合体したコンバットスポーツをUFCで知ったのとは違い、日本にはそこに通じる格闘技、武道&武術文化が存在していた。それはバーリトゥードの母国であるブラジル、コンバットサンボが存在したロシアなどと同様に非常に稀なケースである。さらに我々の国にはプロレスという―殴って、投げて、極める動きがリング上で繰り広げられるエンターテインメントが、しっかりと根付いていた。日本の格闘技界は1993年11月12日の時点で、総合的な格闘技や全局面を想定した武道、さもなくば武術の血が連綿と受け継がれ、プロレスという衣服を纏っていたのである」
「UFCから始まったMMAの25年」では、高島氏はUFCが誕生するのに必要だったピースを以下のように紹介します。
「近年、戦争と紛争の影響で大きな被害を受けた、イラクの古代遺跡バビロン。その壁画に残る紀元前3000年頃に2人の男性が組み合うレスリングのような徒手格闘技。同じく紀元前1600年頃に古代ギリシャで生まれたパンクラチオン。西暦495年に建立された嵩山少林寺で伝えられてきた武術。時が流れ1584年にシャム王国で国技となったムエタイ。18世紀に朝鮮の村祭りで行なわれていたテッキョン。松村宗昆、武田惚角、本部朝基らが鍛錬し、伝播した術。それら全てがMMAには散りばめられて、絡み合っているといっても過言ではない」
このコラムの最後に、高島氏は以下のように述べるのでした。
「技術的な側面で現代のMMAを俯瞰して眺めると、依然としてスクランブル&打撃という絶対的な幹が存在するものの、ファイター達は枝葉の部分でアドバンテージを得るために、さまざまな格闘技の要素を取り入れ、戦いの幅がさらに広がっている。
時には幹自体がボクシングやレスリングではなく、空手やテコンドー、散打という個性的なファイターも見られるようになってきた。この25年間には格闘技、武道、武術の叡智と経験値が詰まっている。世界中に土着格闘術が見られるように格闘技は文化だ。その文化と経済がシンクロした今、MMAはどのような発展をしていくのか。僅か25年、されど25年――これからの25年は果たして……」