- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2018.08.13
8月は「死」について考える季節です。
『ルポ 最期をどう迎えるか』共同通信生活報道部著(岩波書店)を読みました。共同通信の連載を単行本化したもので、全部で128ページです。
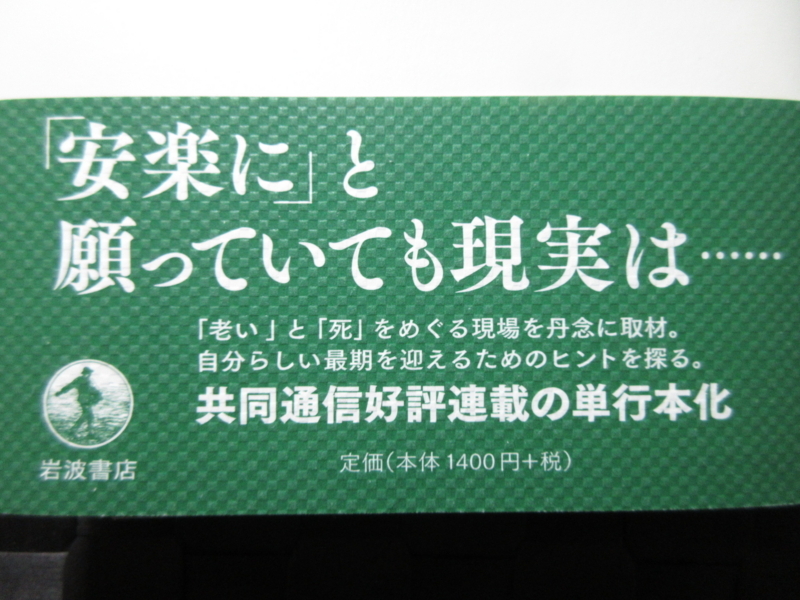 本書の帯
本書の帯
帯には「『安楽に』と願っていても現実は・・・・・・」と大書され、「『老い』と『死』をめぐる現場を丹念に取材。自分らしい最期を迎えるためのヒントを探る」「共同通信好評連載の単行本化」と書かれています。
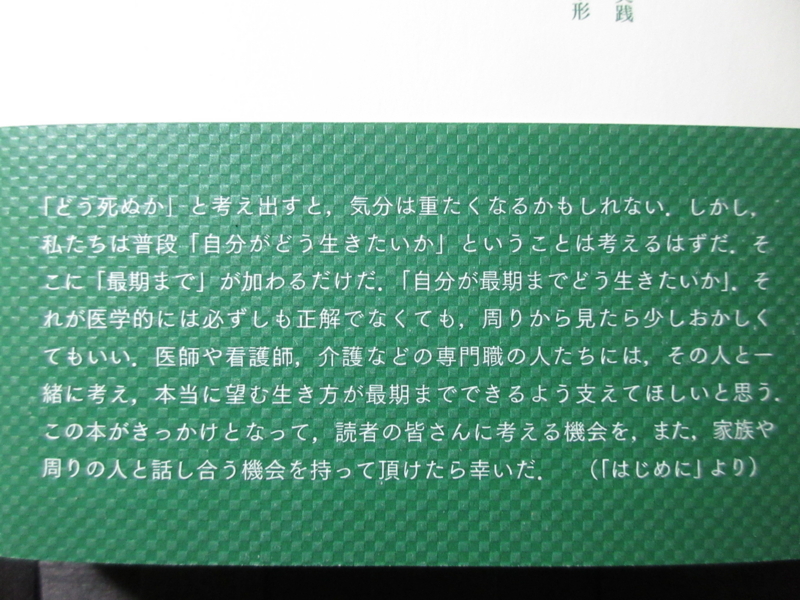 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「2020年代半ば、日本は年間死者数が150万人を超す『多死社会』を迎える。高齢者は人生の最期をどう過ごすのか。家族はどのように『看取り』に臨むのか。終末期医療の現実とは。在宅医療、特養ホーム、救急病棟など『老い』と『死』をめぐる現場を丹念に取材。自分らしい最期を迎えるためのヒントを探る。共同通信の好評連載を単行本化。用語解説のコラムや識者へのインタビューも収録」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに―最期までどう生きたいか」
第1部 自分らしい「死」とは―「思い」と「現実」の間で
第1章 自宅で看取る
第2章 延命治療どこまで
第3章 認知症に寄り添って
第4章 ひとり身で逝く
第2部 「多死社会」にどう向き合うか
第5章 旅立ちの介護―高齢者住宅での「看取り」の実践
第6章 第二のわが家で―ホームホスピスという新たな形
第7章 喪失とともに―広がるグリーフケア
第8章 救命のジレンマ―葛藤する医師たち
第9章 終末医療の形―政官学の模索
「おわりに―自分らしい最期のために」
「はじめに―最期までどう生きたいか」では、共同通信生活報道部「終末医療」取材班キャップである市川亨氏が「多死社会」のアウトラインを示します。わたしたちの社会は確実に「死ぬ人が多くなる」時代に突入しています。年間の死者数は2016年に初めて130万人を突破しました。これは20年前に比べて、1.5倍の数です。今や、1日あたり平均3500人以上が亡くなる「多死社会」を迎えつつあるのです。国の推計によれば、ピークの2040年には年間訳168万人に達します。これから20年余りでさらに40万人近く増えるわけです。
多死社会においては、もちろん子どもや若い人も亡くなります。しかし、統計によれば、日本で亡くなる人のうち64歳以下は10人に1人にすぎません。亡くなった歌手の西城秀樹さんは享年63歳だったので、ギリギリ64歳以下でした。死者数の90%は65歳以上の高齢者であり、今後その割合はさらに高まります。今から30年後には95%になると推計されています。亡くなる人の圧倒的多数は高齢者なのです。そんな多死社会に向かう中で、いわゆる「平穏死」を求める人が多いですが、現実はなかなか希望通りにはいきません。
市川氏は、以下のように述べています。
「私たちは人が亡くなることを『不幸』と呼ぶ。確かに、自分の家族や親しい人との別れはつらく悲しいことだ。しかし、私たちはあまりにも『死』をタブー視し、忌避していないだろうか。誰にでも訪れ、身のまわりで経験することがどんどん増えていくのに、『死』の話題を避けるあまり、本人が望んでいなかった形で最期を迎えることになったり、遺された家族が苦悩したりしていないだろうか」
わたしは、人が亡くなっても「不幸」とは呼びません。
「死は不幸ではない」という言葉は、わたしの多くの著書に登場します。わたしが日頃から考えていることです。「不幸」の反対は「幸福」です。物心ついたときから、わたしは人間の「幸福」というものに強い関心がありました。学生のときには、いわゆる幸福論のたぐいを読みあさりました。それこそ、本のタイトルや内容に少しでも「幸福」の文字を見つければ、どんな本でもむさぼるように読みました。
そして、わたしは、こう考えました。政治、経済、法律、道徳、哲学、芸術、宗教、教育、医学、自然科学・・・人類が生み、育んできた営みはたくさんある。では、そういった偉大な営みが何のために存在するのかというと、その目的は「人間を幸福にするため」という一点に集約される。さらには、その人間の幸福について考えて、考えて、考え抜いた結果、その根底には「死」というものが厳然として在ることを思い知りました。
そこで、わたしが、どうしても気になったことがありました。それは、日本では、人が亡くなったときに「不幸があった」と人々が言うことでした。わたしたちは、みな、必ず死にます。死なない人間はいません。いわば、わたしたちは「死」を未来として生きているわけです。その未来が「不幸」であるということは、必ず敗北が待っている負け戦に出ていくようなものです。
わたしたちの人生とは、最初から負け戦なのか。どんな素晴らしい生き方をしても、どんなに幸福感を感じながら生きても、最後には不幸になるのか。誰かのかけがえのない愛する人は、不幸なまま、その人の目の前から消えてしまったのか。亡くなった人は「負け組み」で、生き残った人たちは「勝ち組」なのか。わたしは、そんな馬鹿な話はないと思いました.わたしは、「死」を「不幸」とは絶対に呼びたくありません。なぜなら、そう呼んだ瞬間、わたしは将来かならず不幸になるからです。そして、人が亡くなっても「不幸があった」と言わなくなるような葬儀の実現をめざしています。
「はじめに―最期までどう生きたいか」の最後に、市川氏は「『どう死ぬか』と考え出すと、気分は重たくなるかもしれない。しかし、私たちは普段『自分がどう生きたいか』ということは考えるはずだ。そこに『最期まで』が加わるだけだ。『自分が最期までどう生きたいか』。それが医学的には必ずしも正解でなくても、周りから見たら少しおかしくてもいい。医師や看護師、介護などの専門職の人たちには、その人と一緒に考え、本当に望む生き方が最期までできるように支えてほしいと思う」と書いています。
第1部「自分らしい『死』とは―『思い』と『現実』の間で」の第3章「認知症に寄り添って」では、最初に、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるという予想が示されます。後藤武史(64、仮名)の母である美枝子(94、仮名)は千葉県松戸市の介護付き有料老人ホーム「松戸ニッセイエデンの園」に入居して8年。自宅にいたころからの認知症が少しづつ重くなっていました。老人ホームに入居した美枝子は、黒い文箱を肌身離さず持ち歩くようになっていました。亡くなった美枝子の両親や夫、武史ら家族と撮影した30枚ほどの写真が入っていました。
本書には、以下のように書かれています。
「美枝子の担当だった介護福祉士の浜田暁洋(39)は、美枝子が文箱から写真を取り出したのを見て『ご家族ですか』と尋ねた。『これが武史』。息子はすぐに判断がついたが、成人式の振り袖姿の女性が誰だか思い出せない。『お孫さんですかね』。浜田が助け舟を出すと、孫娘を思い出せた安心感からか顔をほころばせ、うなずいた。記憶は薄れつつあっても、家族写真は美枝子の心のよりどころであり、宝物だった」
第2部「『多死社会』にどう向き合うか」の第7章「喪失とともに―広がるグリーフケアの冒頭には、「長年連れ添った伴侶の死。支えとなってきた家族や地域社会のつながりが薄れゆく今、残された者はどのように深い喪失感と向き合うのだろう」と書かれています。
ここでは、横浜市郊外の公団に住む小柴喜代治(74)が登場します。彼の妻である泰子は肺がんのために64歳で亡くなっていました。
小柴は伴侶を失った悲嘆から立ち直れないとして、「小柴のように、身近な人を亡くした喪失感にさいなまれ、心身の不調を覚える人は少なくない。普通の反応だが、うつ病や自殺に至る人もいる。そうした最悪のケースを避け、悲しみを受け入れていく過程を『グリーフワーク』、第三者による支援を『グリーフケア』『グリーフサポート』などと呼ぶ」と書かれています。
続けて、以下のように書かれています。
「グリーフは英語で『深い悲しみ』『悲嘆』といった意味だ。グリーフケアの考え方は欧米で生まれ、国内では1995年の阪神・淡路大震災や2005年のJR福知山線脱線事故の遺族支援で注目されるようになった。死別の理由や失った相手が親か子どもかでもケアの仕方は変わってくると言われ、近年は全国のホスピスや介護施設で支援グループが活動している」
わたしは、まさに阪神・淡路大震災、JR福知山線脱線事故におけるグリーフケアに取り組んできた高木慶子先生が初代所長である上智大学グリーフケア研究所の客員教授を務めています。また、わが社では、グリーフワークの自助グループ(Self Help Group)=「月あかりの会」を立ち上げ、その活動をサポートしてきました。ここでは「愛する人を喪失した対処から、愛する人のいない生活への適応のサポート」を行っていますが具体的には「人生の目標を見出せるサポート」「喜びや満足感を見出せるサポート」「自分自身をケアすることをすすめる」「他者との関わりや交わりをすすめ、自律感の回復を促す」ことをサポートするようにしています。
また、「月あかりの会」では、「癒し」「集い」「学び」「遊び」というキーワードで様々な活動を行っています。その中でも、「笑来」とユーモアによる癒しという視点で活動を行っています。「笑い」とは「和来」という意味でもあり、ある意味で最大の「癒し」となります。悲嘆にくれる遺族に無理なく笑いを提供する場を創出すべく、わが社では毎月1回の「笑いの会」の開催、および本社のある北九州だけで年間300回を越える見学会で落語会の開催などを行い、そこにご遺族をお招きしています。
第9章「終末期医療の形―政官学の模索」では、超高齢化と多死時代を迎える日本社会の変化に対して、政治、行政、学界はどう向き合おうとしているのか、その現状が報告されます。
「文藝春秋」2016年12号には「私は安楽死で逝きたい」という見出しの記事が掲載されました。筆者は橋田壽賀子(91)。「おしん」「渡る世間は鬼ばかり」などのドラマで日本を代表する脚本家ですが、彼女は「希望するならば、本人の意思をきちんと確かめたうえで、さらに親類縁者がいるならば判をもらうことを条件に安楽死を認めてあげるべきです」と訴えました。
2017年3月、国会内で取材に応じた民進党参議院議員の増子輝彦(69)は、「終末期医療が雑誌の特集で話題になるのは1つの時代の流れ。問題提起してもらうのは決して悪いことではない」と語りました。「平穏死」を提起する動きや、静かに広がる「終活」ブームが念頭にあったのかもしれません。増子議員は超党派の国会議員約200人でつくる「終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟」の会長です。この会は、患者自らが「尊厳死」を選ぶ権利を法律で定めようと、2005年に発足したものです。
わたしは、「終末医療」の終末という言葉が好きではありません。
「終活」も「終末活動」という意味で、やはり終末が入っています。
「終末」という言葉には、違和感を覚えます。なぜなら、「老い」の時間をどう豊かに過ごすかこそ、本来の終活であると思うからです。そこで、わたしは「終末」の代わりに「修生」、「終活」の代わりに「修活」という言葉を提案しています。「修生」とは文字通り、「人生を修める」という意味です。
「修生活動」とは人生の集大成です。かつての日本人は、「修業」「修養」「修身」「修学」という言葉で象徴される「修める」ということを強く意識していました。自分から前向きに、積極的に修めることにより人格を高め、人間として成長することを目指したのです。「終活」という言葉には、死を間近にした人が、仕方なく死の準備をしてこの世から去っていくというニュアンスがあり、それではあまりに寂しすぎます。わたしは、人生の最期まで「修生活動」をして人間として成長し、人生を堂々と卒業していくべきであると考え、「修活」という言葉を提案しています。
「おわりに―自分らしい最期のために」では、共同通信生活報道部の内田泰が「本書の主題は何か。人びとが『老い』を迎える過程はどのようなものか、すなわち、人びととはどのように日々の『生』を紡いでいるのか―という点にあります」として、さらに米国の医師であるアトゥール・ガワンデが著書『死すべき定め』で書いた「生まれ落ちたその日から、私たち全員が老化しはじめる。この人生の悲劇から逃れるすべはない」という言葉を紹介します。そして、「老化を悲劇と捉えるかどうかはともかく、平均寿命が女性87.14歳、男性80.98歳で、総人口に占める65歳以上人口(高齢化率)が27.3%に達する日本では、大多数の人は老化のプロセスが相当程度に進んだ後で、命の終わりを迎えることになります」
そして最後に、内田氏は以下のように述べるのでした。
「さまざまな現場を取材する中で、高齢者自身の『意思決定』の難しさという課題が浮かび上がりました。認知症や身体の衰弱、病気による痛みのために適切な判断を下すのが困難だったり、家族への遠慮などから本音を言い出せなかったりして、『本当は自分の人生はこうやって締めくくりたい』という意思に反して最期の日々を過ごす可能性もあるのです。それでは看取った家族にも悔いが残ります」
処方箋となるキーワードとして、内田氏は「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」を紹介します。これは「終末期医療について患者が自身の意思に沿った治療を受けられるよう、事前に家族や医療従事者と繰り返し話し合うプロセス」のことですが、非常に興味深いです。今後、日本でもACPの考え方や実践が広がっていくのでしょうか。
