- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.07.31
『ロラン・バルト 喪の日記』ロラン・バルト著、石川美子訳(みすず書房)を読みました。2009年に発行された本の新装版です。タイトルからして、唯葬論者であるわたしが読まなければならない本であることは明白です。
著者は1915年生まれのフランスの批評家・思想家です。53年に『零度のエクリチュール』を出版して以来、現代思想に多大な影響を与えました。 75年に彼自身が分類した位相によれば、(1)サルトル、マルクス、ブレヒトの読解をつうじて生まれた演劇論、『現代社会の神話(ミトロジー)』(2)ソシュールの読解をつうじて生まれた『記号学の原理』『モードの体系』(3)ソレルス、クリテヴァ、デリダ、ラカンの読解をつうじて生まれた『S/Z』『サド、フーリエ、ロヨラ』『記号の国』(4)ニーチェの読解をつうじて生まれた『テクストの快楽』『彼自身によるロラン・バルト』などの著作があります。その後も、『恋愛のディスクール・断章』『明るい部屋』を出版しましたが、80年2月25日に交通事故に遭い、3月26日に亡くなりました。
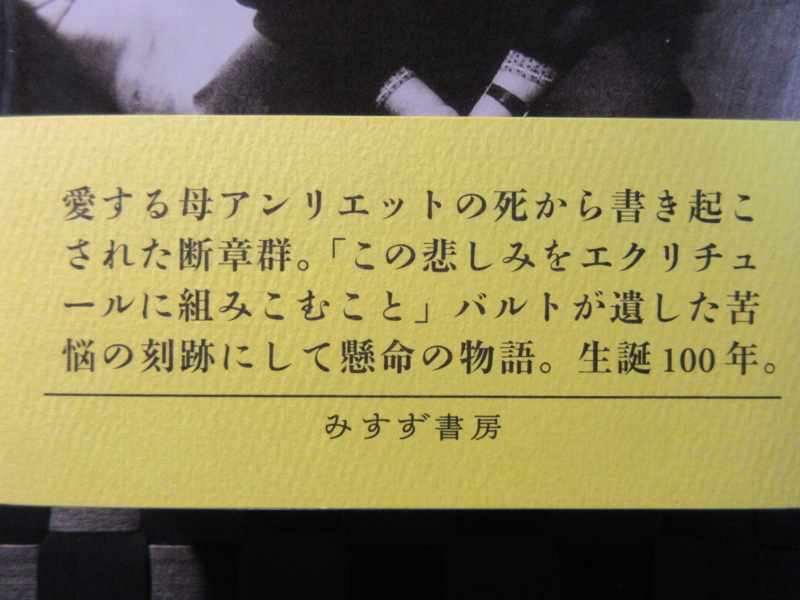 本書の帯
本書の帯
本書のカバーには最晩年のロラン・バルトの写真が使われ、帯には以下のように書かれています。 「愛する母アンリエットの死から書き起こされた断章群。『この悲しみをエクリチュールに組みこむこと』バルトが遺した苦悩の刻跡にして懸命の物語。生誕100年」
またカバー裏には、以下のような内容紹介があります。
「『1978年8月18日 彼女が臥せっていて、そこで亡くなり、いまはわたしが寝起きをしている部屋のその場所。彼女のベッドの頭部をくっつけてあった壁に、イコンを置いた―信仰からではない―。そこのテーブルの上には、いつも花をかざってある。それゆえに、もう旅をしたくなくなっている。そこにいられるように、けっして花をしおれさせたりしないように、と。』 最愛の母アンリエットは1977年10月15日に亡くなる。その死は、たんなる悲しみをこえた絶望的な思いをもたらし、残酷な喪のなかで、バルトはカードに日記を書きはじめた。二年近くのあいだに書かれたカードは320枚、バルト自身によって五つに分けられ『喪の日記』と名づけられた。 とぎれとぎれの言葉が、すこしずつかたちをなして、ひとつの作品の輪郭をえがきはじめるのが日記からかいまみられる。そうして、母の写真をめぐる作品『明るい部屋』が生まれたのだった。 『喪の日記』は、最晩年のバルトがのこした苦悩の刻跡であり、愛するひとを失った者が『新たな生』をはじめようとする懸命の物語である。そこから浮かびあがってくるのは、言葉で生かされている者が言葉にすがって立ち上がろうとする静やかなすがたなのである」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」
喪の日記 1977年10月26日-1978年6月21日
日記のつづき 1978年6月24日-1978年10月25日
(新たなつづき) 1978年10月26日-1979年9月15日
日付のない断章 マムについてのメモ
訳註・解説
訳者の石川美子氏による「まえがき」には以下のように書かれています。
「バルトは、その生涯を母アンリエットとともに暮らした。肺結核の治療のために学生サナトリウムですごした約5年間と、アレクサンドリア大学やモロッコのラバト大学で教えた2年間をのぞいては、バルトが母のもとを離れたのは短期間の旅行のあいだにすぎなかった。とりわけ1976年からは、老いて体力のおとろえた母が暮らしやすいようにと小ぶりのアパルトマンに引っ越して、ふたりきりで寄りそうように暮らしていた。だが、その母が1977年10月25日に亡くなる。その死は、たんなる悲しみをこえた絶望的な思いをバルトにもたらした。残酷な喪のなかで、彼は日記を書きはじめたのである」
また、「まえがき」には以下のように書かれています。
「母アンリエットは、バルトにとって、ただひとりの愛する女性、人生のただひとりのパートナーだったのである。そのような存在を失ったバルトは、暗い喪のなかで、言葉にすがりつくようにして日記を書きはじめた。喪の苦悩が発作のように断続的におとずれて、取り乱した断片的な文章を書きなぐるしかないこともあった。自殺への思いをしるすこともあった。だが彼は日記をやめなかった。自分が悲しみにたえらえるのは、『そのことを語り、文にすることができるからだ』と知っていた。『わたしの悲しみは説明できないが、それでも語ることはできるのだ』と(78年8月1日の日記より)」
本書の内容は本当に短い断章です。 その中で、わたしにとって印象的なものがいくつかありました。 それらを以下に紹介したいと思います。
1977年10月26日 「新婚初夜という。 では、はじめての喪の夜は?」
1977年11月1日 「わたしをもっとも苦しめるのは、まだら状の喪である―多発性硬化症のような。」
1977年11月4日 「今日、夕方5時ごろ、すべてがほぼ片づいた。どうしようもない孤独感がある。くすんでいて、こええからはわたし自身の死以外に終わりようのない孤独が。」
1977年11月15日 「死が事件であり、予期せぬできごとであり、それゆえに人を集めて、興味をひき、緊張させ、感情をかきたてて、茫然とさせる、という時期がある。そして、ある日のこと、もはや事件ではなくなる。縮まって、取るに足りないことになり、語られなくなる。陰翳で、手だてのない、べつの持続になる。いかなる語りの論法もありえない、ほんとうの喪になる。」
1977年11月15日 「―胸がはりさけそうになったり、いたたまれなくなったりして、ときおり、生がこみあげてくる」
1977年11月19日 「[立場の混乱]。数か月のあいだ、わたしは彼女の母親になっていた。だから自分の娘を亡くしたようなものだ。(母を亡くすよりも大きな悲しみなのではないか? そのことは考えていなかった)。」
1977年11月21日 「『鬱病』が何から生じうるのかが、やっとわかった。去年の夏の日記を読みかえすと、わたしは『魅了される』(夢中になる)と同時に、失望もする。つまり、必死で書いたものは、やはりつまらないということである。悲しみの底にいながらエクリチュールにしがみつくことさえできなくなったそのときに、『鬱病』は始まるのだろう。」
1977年12月9日 「喪とは、心身の不調であり、ゆさぶりをかけられない状況である。」
1978年2月12日 「―雪。パリに大雪。ふしぎだ。 ―彼女はけっしてもどってこないのだから、雪を見ることはできないし、わたしが彼女と雪の話をすることもできない。そう思って、苦しむ。」
1978年2月16日 「今朝もまた雪だ。そしてラジオでは、ドイツ歌曲。なんと悲しいことか!―かつての朝のことを思う。病気で学校を休み、彼女といっしょにいる幸せをあじわった朝。」
1978年3月23日 「書くことがわたしのなかで愛情の『鬱滞』を変え、『危機』を弁証法化してゆく、という信念と、おそらくは確証がある。 ―『プロレス』のことはすでに書いた。もう見たいとは思わない ―『日本』も同じだ
この日の日記に書かれていることは、わたしにはショックでした。 なぜなら、わたしはロラン・バルトの本をけっこう読んでいるのですが、一番好きなのが彼がプロレスについて言及した「レッスルする世界」というエッセイが収められた『神話作用』であり、二番目に好きなのが日本についてのユニークな見方が炸裂した『表象の帝国』だからです。わたしとしては、もっともっとバルトに「プロレス」と「日本」について語ってほしかった!
1978年6月24日 「内面化した喪では、徴候はほとんどみえない。 それが、絶対的な内面の実現である。ところが、あらゆる賢明な社会は、喪を外面化することを規定し、体系化したのだった。 わたしたちの社会の居心地の悪さは、喪を否認していることにある。」
1978年7月18日 「それぞれの人が、自分なりの悲しみのリズムをもっている。」
正直に言って硬骨な文章が多く、難解に感じる読者も多いのではないかと思います。しかし、バルトが綴った日々の断章群からは、最愛の人を失った深い悲しみが切々と伝わってきます。実際に愛する人を亡くした人が読めば、さらに魂を揺さぶられるような思いがするのではないでしょうか。 母親を亡くして悲しみに打ちひしがれている人へのプレゼント・ブックとしても最適だと思います。
