- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1142 読書論・読書術 『エリートたちの読書会』 村上陽一郎著(毎日新聞社)
2015.11.04
『エリートたちの読書会』村上陽一郎著(毎日新聞社)を読みました。
著者は1936年生まれの科学哲学者です。東京大学人文系大学院博士課程修了。東京大学教養学部、同先端科学技術研究センター、国際基督教大学などの教授を経て、2014年3月まで東洋英和女学院大学学長を務めました。また、東京大学・国際基督教大学名誉教授、日本アスペン研究所副理事長でもあります。専攻は科学史・科学哲学で、著書に『科学史の逆遠近法』(講談社学術文庫)、『あらためて学問のすすめ』(河出書房新社)など多数。翻訳書もシャルガフ『ヘラクレイトスの火』(岩波書店)、ケストラー『偶然の本質』 (ちくま学芸文庫)など多数あります。
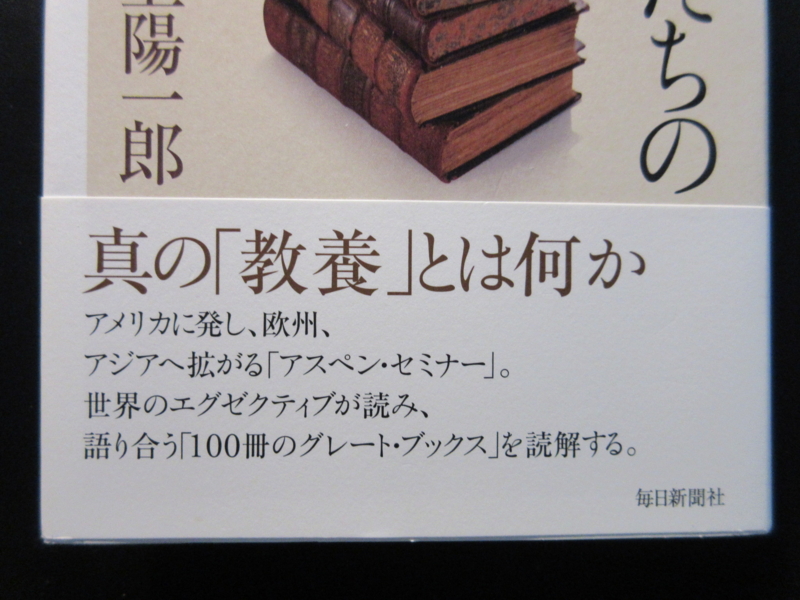 「真の『教養』とは何か」と書かれた本書の帯
「真の『教養』とは何か」と書かれた本書の帯
本書の帯には「真の『教養』とは何か」と大書され、続いて「アメリカに発し、欧州、アジアへ拡がる『アスペン・セミナー』。世界のエグゼクティブが読み、語り合う『100冊のグレート・ブックス』を読解する」と書かれています。
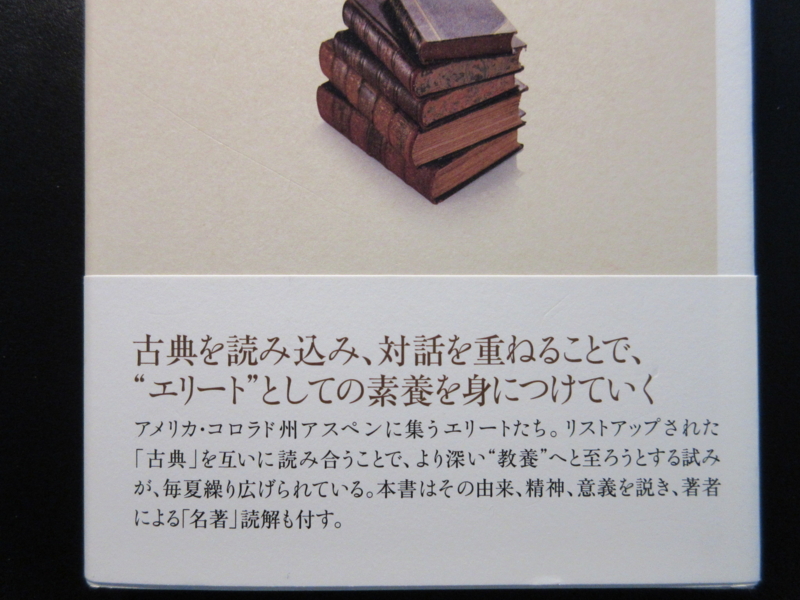 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には「古典を読み込み、対話を重ねることで、”エリート”としての素養を身につけていく」と書かれ、続いて「アメリカ・・コロラド州アスペンに集うエリートたち。リストアップされた『古典』を互いに読み合うことで、より深い”教養”へと至ろうとする試みが、毎夏繰り広げられている。本書はその由来、精神、意義を説き、著者による『名著』読解も付す」とあります。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「書物についての書物 あとがきに近いはしがき」
1.エリートたちの読書会
百冊のグレート・ブックス―本との三層の対話
2.読書は対話である
読書と翻訳に共通するもの
名著逍遥1―芭蕉『おくのほそ道』
名著逍遥2―『平家物語』
名著逍遥3―アリストテレス『自然学』
名著逍遥4―プロティノス『善なるもの一なるもの』
名著逍遥5―アレクシス・トクヴィル『アメリカのデモクラシー』
名著逍遥6―ハイゼンベルク『部分と全体』
「百冊のグレート・ブックス―本との三層の対話」の冒頭では、「エリート」という言葉を取り上げ、もともとこの言葉が好感をもって迎えられないことが多いのが、日本社会であるとして、次のように述べています。
「『エリート臭』だとか、『エリートぶって』など、他人を貶めるときに利用されるのがほとんどで、「あの人はエリートだ」という評言が、純粋にプラスの意味で使われることは、まずなさそうです。ヨーロッパ語での『エリート』は、例えば英語の〈elect〉という言葉と同語源です。この単語は『選ぶ』という意味ですから、『選ばれた(人々)』ということになります」
著者は、さらに「エリート」という言葉について述べます。
「ヨーロッパ語の『エリート』では、『選ぶ』のはもちろん選挙民ではありません。言うまでもないことですが、『選んだ』のは神です。神によって特別に『選ばれた』人々、神から特別の『贈り物』を受けた人々が『エリート』ということになります。『贈り物』と書きました。英語では、誰もが知っているように、『贈り物』を〈gift〉と言います。因みに、この言葉はよく知られた動詞〈give〉と同根です。しかし、例えば、この語を動詞として用い、その受け身形〈gifted〉を造りますと、意味は『才能豊かな』ということになります。実は〈gift〉には、本来『才能』という意味もあるのです」
さらに著者は英仏のエリート養成システムに言及した後で、次のように述べます。
「神への信仰を離れても、オルテガも『大衆の反逆』のなかで書いているように、『エリート』とは、自分が他人と比較して、より優れていると認めて只管満足する人などではない、ましてや、凡俗を蔑み、自己の優位を自負することに喜びを見出すだけの輩ではない、ということだけははっきりさせておきたいと思います。そうではなくて、他人に対してよりも、より多くのことを自分に対して求めようとする人、もう少し別の表現を使えば、『他人に対してよりも、遥かに自分に対して厳しい人』が、エリートであり、さらに言えば、そのことをもって、社会と他人のために尽くそうとする人がエリートである、と言えるでしょう」
「エリート」のための、あるいは「リーダーシップ」涵養のための特別な読書プログラムというものがあります。著者は「グレート・ブックスという試み」として、以下のように紹介します。
「話は第二次世界大戦終結後間もないアメリカに遡ります。アメリカの企業人であったW・P・ペプケ(Walter P.Paepcke,1896~1960)は、たまたま初めて訪れたコロラド州アスペンの風光に魅せられ、この地を、様々な領域の人々が寝食をともにしながら、『自らを高め合う』ことのできるような場所にしたい、という思いに囚われました。彼は手始めに、1949年、ゲーテの生誕200年を祝うイベントを、アスペンで開催することにします。20日間の日程で開催されたこの会議には、アルベルト・シュヴァイツァー(ドイツの医師、オルガン演奏家、社会運動家)、ホセ・オルテガ=イ=ガセット(スペインの哲学者)、アルトゥール・ルービンシュタイン(ポーランド=アメリカのピアニスト)、ソーントン・ワイルダー(『我が町』などで知られるアメリカの作家、劇作家)ら、広汎な領域の著名な人々が集まりました」
この流れから「グレート・ブックス」が生まれました。
この「グレート・ブックス」は、アメリカ特有の教育プログラムであるとして、著者は以下のように述べます。
「源は第三代大統領トマス・ジェファソンまで遡るという人もおります。ジェファソンは、折りに触れて繰り返し、周囲の人々に、重要な読むべき書物のリストを送っていたと言われるからです。1909年にはハーヴァード大学が51巻からなる『ハーヴァード・クラシックス』を編纂、刊行しています。実際に読むことのできる百科全書的な叢書としての『グレート・ブックス』は、普通このシリーズを指します。東西の古典が、比較的読みやすい英語に翻訳されて集められているものです」
著者は、アメリカ人のヨーロッパ・コンプレックスの存在を指摘し、彼らのヨーロッパ古典への憧憬について次のように述べます。
「実際の百科全書的な書籍ではなく、教育プログラムとしての『グレート・ブックス』は、ちょうど今問題にしている1920年代から30年代にかけて、コロンビア大学に発祥し、シカゴ大学が発展させたものを指しています。コロンビアの教授であったアースキン(John Erskine,1879~1950)が1919年に始めたものが最初だと言われますが、100冊のリストを示して、そのなかから選んだテクストを土台に、教室では、教授や講師の解説や説明はできるだけ抑制し、学生たちの開かれた対話を重ねる、という方法のカリキュラムでした。専門に傾きがちな大学の性格を考慮した、新しい「リベラル・アーツ」教育の出発でした。
1970年代後半には、椎名武雄(当時日本アイ・ビー・エム)、小林陽太郎(当時富士ゼロックス)、あるいはジャーナリスト松山幸雄(当時朝日新聞社)といった日本人たちがアメリカ・アスペンのセミナーを相次いで体験し、一様に大きな衝撃を受けて帰国しました。
著者は「日本のアスペン研究所」として、以下のように述べています。
「椎名は、直ちに日本アイ・ビー・エム社の主宰で、天城アスペン会議を立ち上げ、小林も富士ゼロックス社を基盤にキャンプ・ニドムを発足させる、など、いわばパイロット的な活動を開始します。そして最終的に、彼らを中心に日本アスペン研究所が立ち上げられます。1998年のことでした。とりあえず、テクスト集の編纂が課題になりました。大学に在籍する研究者のなかから、美学・倫理学の今道友信、アメリカ史の本間長世を中心に、哲学の坂部恵(以上の三者は、残念ながら、今日では故人になりました)、生命科学の中村桂子らの協力を得て、日本独自のテクスト集が生まれました」
現在、日本のエグゼクティヴ・セミナーで使われているテクストは6つのカテゴリーに分けられており、その内容は以下の通りです。
【1】世界と日本
1.ジョージ・ケナン『二十世紀を生きて』関元訳、同文書院インターナショナル
2.岡倉天心『東洋の理想』講談社学術文庫
3.朝河貫一『日本の禍機』講談社学術文庫
4.和辻哲郎『鎖国』岩波文庫
5.坂口安吾『日本文化私観』河出文庫
6.ヴァーツラフ・ハヴェル「ポストモダンの世界における自己超越の探求」
1994年、アメリカで行った講演の原稿
【2】自然・生命
1.チャールズ・ダーウィン『種の起源』八杉龍一訳、岩波文庫
2.ジュール・ミシュレ『山』大野一道訳、藤原書店
3.ヤーコブ・ユクスキュル『生物から見た世界』日高敏隆、野田保之訳、新思索社
4.ヨーハン・ゲーテ『科学方法論』、『形態学序説』木村直司他訳、潮出版社
5.レイチェル・カーソン『沈黙の春』青樹簗訳、新潮社
6.ヨハネ・パウロ二世「進化に関する教書」法王庁科学アカデミーでの講演
7.ヴェルナー・ハイゼンベルク『部分と全体』山崎和夫訳、みすず書房
【3】認識
1.大森荘蔵「論理的ということ」(『流れとよどみ』から)産業図書
2.フランシス・ベーコン『学問の促進』服部英次郎他訳、河出書房版「世界の大思想」所収
3.ジャンバティスタ・ヴィーコ『学問の方法』上村忠男他訳、岩波文庫
4.プラトン『ソクラテスの弁明』久保勉訳、岩波文庫
5.ルネ・デカルト『方法序説』谷川多佳子訳、岩波文庫
6.ヴァスバンドゥ『唯識二十論』梶山雄一訳、中央公論社版「世界の名著」所収
【4】美と信
1.芭蕉『おくのほそ道』(岩波書店版「日本古典文学大系」所収)
2.ダンテ『神曲』野上素一訳、筑摩書房
3.聖書『創世記』関根正雄訳、岩波文庫
『マタイによる福音書』第5章、第6章
『ヨハネによる福音書』第8章
4.道元『正法眼蔵』岩波文庫、『現代訳 正法眼蔵』高橋賢陳訳、理想社
5.ルーミー『ルーミー語録』井筒俊彦訳、岩波書店
6.カント『永遠平和のために』宇都宮芳明訳、岩波文庫
7.アウグスティヌス『告白』山田晶訳、中央公論社版「世界の名著」所収
【5】ヒューマニティ
1.福沢諭吉『学問のすすめ』岩波文庫
2.モンテーニュ『エセー』荒木昭太郎訳、中央公論社版「世界の名著」所収
3.『古事記』岩波文庫
4.孔子『論語』岩波文庫
5.海保青陵『稽古談』岩波書店版「日本思想大系」所収
6.山川菊枝「母性保護と経済的独立」(『婦人公論』1918年9月号)
7.アリストテレス『ニコマコス倫理学』高田三郎訳、岩波文庫
8.キケロ『友情について』中務哲郎訳、岩波文庫
【6】デモクラシー
1.ロック『市民政府論』鵜飼信成訳、岩波文庫
2.「アメリカ独立宣言」斎藤眞訳、『アメリカ学入門』南雲堂所収
3.トクヴィル『アメリカにおけるデモクラシー』岩永健吉郎他訳、研究社(現在は岩波文庫にもあり)
4.リップマン『世論』掛川トミ子訳、岩波文庫
5.吉野作造『吉野作造評論集』岩波文庫
6.石橋湛山『石橋湛山評論集』岩波文庫
本書では、書物を「歴史的な遺産」ととらえています。
著者によれば、古代ギリシャの都市国家では、地中海における海洋交通が、国家の運命に決定的な意味を持っていたといいます。つまり「船」あるいは「軍艦」を多く持つことが、国家の死命を制する条件だったのです。
この「船」が「クラシック」と関係があるとして、著者は次のように述べます。
「『船』は国家にとって決定的な意味を持ったのです。それが『クラシック』という言葉の出発点にあるのです。同時に、都市国家の市民として、国家に『船』を寄進することのできるような富裕、上流の『階級』の人、というところから、『(上流)階級』(クラス)の意味が、同じ語源から派生したと言われます。『プロレタリアート』という言葉の語源も、その問題に関わります。ラテン語では『プロレ』というのは、『次の世代』を意味します。つまり、市民として、『船』はおろか、『次の世代』を提供することでしか、国家に貢献できないクラスの人が、ラテン語では〈proletarius〉と言われました。そこから『プロレタリアート』(proletariat)という言葉が生まれました。哀しい思いをそそられる話ですが、いずれにしても、『国家にとって本質的に重要なもの』の原意から、『人間の存在にとって本質的な大切なもの(こと)』が『クラシック』である、ということになります」
そう、「クラシック」とは「人間存在にとって本質的なもの」なのです。
さらに文字という大発明について、著者は次のように述べています。
「どこの文化圏でも、文字を持たない時代はあったでしょうが、そこでも、自分たちの民族の出自を伝える神話や、自分たちを取り巻く世界の開闢に関する神話などを持ち、口承で伝えることで、文化の統合的な働きを生み出してきました。それが、文字の発明によって、書物という形で、残され、読み継がれるようになったことは、人間社会における、最も画期的な出来事だったに違いありません。先のリストのなかでも、『古事記』や『創世記』がそれに当たります。それらは、民族の、そしてそこに含まれる人間一人一人の運命をも左右するような力を備えたものでした。『クラシック』が、国家の命運に関わるもの、という意味を持っていたのも、故なきことではないと思い至ります」
本書の第2部「読書は対話である」では、「名著逍遥」ということで、さまざまな本を取り上げた著者の個人的な読書エッセイといった感があります。その中でも、プロティノス『善なるもの一なるもの』についてのくだりが興味深かったです。著者は以下のように述べています。
「もともとプラトンの哲学の根底には、現実の世界を仮象と見なし、真実の世界としての『もう1つの世界』が存在する、という前提があります。この考え方は、容易に象徴主義に移行する可能性を宿しています。というのは、2つの世界の間には、当然何らかの繋がりがあり、一方の世界の何物かは、他方の世界の何物かの象徴である、と考えられるからです。そして、そのことを認めると、一方の世界の何物かを操作することによって、他方の世界の(それに対応する)何物かを操作することが可能になる、という呪術的な、あるいは魔術的な考え方を許容する余地が生まれます」
さらに著者は、「ヨーロッパ」という概念について述べます。
「ヨーロッパという概念が成立して以来、ヨーロッパは、古代ギリシャ・ローマの哲学体系を、自分たちの手に入れようと、永年に亘って努力を重ねてきた。それは、大まかに言えば、2段階に分かれていた。第1段階は『12世紀ルネサンス』で、古代ギリシャの哲学から、アリストテレス主義を取り込むことに費やされた。第2段階は『ルネサンス』で、古代ギリシャ哲学から、プラトン主義を取り込むことに費やされた。どちらも、基盤であるキリスト教神学の上に、そうした哲学をアマルガム化することが、究極の目標であった」
著者は、それゆえ12世紀から17世紀までのヨーロッパを「大ルネサンス」と呼ぶことを提案します。この「ルネサンス」的動機から、ヨーロッパが開放されるのは、18世紀の啓蒙主義によってであり、それは新たな近代的市民層の勃興とも符節を合わせていたというのです。
 日本版「グレート・ブックス」をめざした『世界の名著』
日本版「グレート・ブックス」をめざした『世界の名著』
本書は一般の読書人にはとっつきにくい内容かもしれませんが、「教養」とか「名著」というものに関心がある人にとっては貴重な示唆が与えられる本ではないかと思います。なお、本書に登場する「グレート・ブックス」は中央公論社の『世界の名著』シリーズが誕生する契機となりました。わが書斎の書棚の最上段には、正続の『世界の名著』全88巻が鎮座しています。まるで「知の神棚」のようなイメージであります。