- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1122 哲学・思想・科学 『「歓待」の精神史』 八木茂樹著(講談社)
2015.09.24
『「歓待」の精神史』八木茂樹著(講談社)を読みました。
「北欧神話からフーコー、レヴィナスの彼方へ」というサブタイトルがついています。著者は1966年福井県生まれの神話学者、現代倫理学者です。
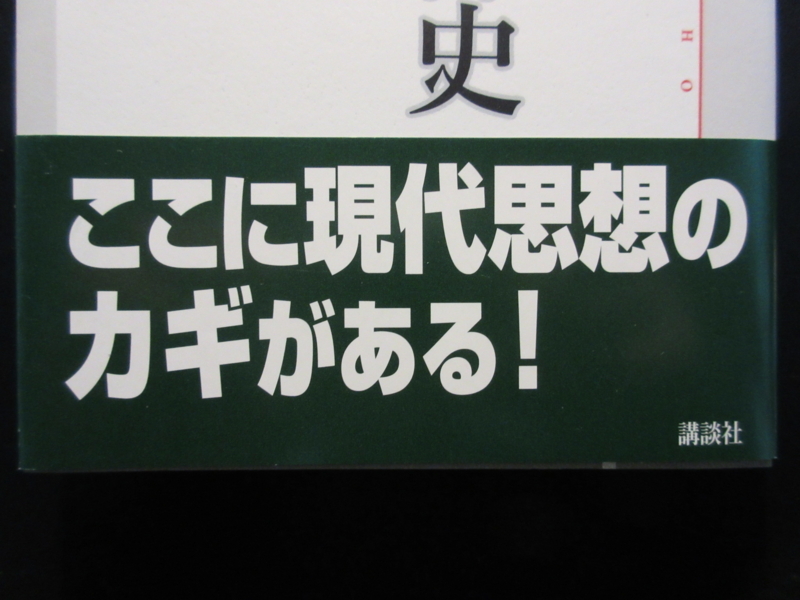 「ここに現代思想のカギがある!」と書かれた本書の帯
「ここに現代思想のカギがある!」と書かれた本書の帯
本書の帯には「ここに現代思想のカギがある!」と書かれています。
「歓待(ホスピタリティ)」がフーコー、レヴィナス、デリダに代表される現代思想の重要な概念として注目を浴びています。本書は、北欧神話を素材に「歓待」思想の根源をさぐり現代に接続するという意欲作です。
カバー裏には、以下のような内容紹介があります。
「何ものかわからないものの訪れを無条件に受け入れて喜ぶ。この『歓待』の精神は、一方では、現代思想の重要なキーワードとして、ますます注目をあびている。フーコーやレヴィナスやデリダの思考は、どのような射程をもつのか。北欧神話に『歓待』の根源的なかたちを見出し、現代思想に架橋することで、新たな倫理を構想する、清新な論考」
本書の目次は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
第一章 北欧神話の基本構造
第二章 「歓待」の萌芽―北欧神話が語り継いだもの
第三章 神話から現代倫理へ―フーコーとレヴィナスを架橋として
第四章 「歓待」の倫理
第五章 「歓待」が生みだすもの―「共‐同体」へ 終 章 環境思想としての「歓待」の倫理
「あとがき」
本書を読んで、まず第三章「神話から現代倫理へ―フーコーとレヴィナスを架橋として」の冒頭に書かれている次の箇所が興味深かったです。
「アルバイトの店員たち。彼や彼女らは、もはやその個々人の生き生きとした生から切り離され、常に交換可能な労働者という名の『物』に置き換えられて、個人としての固有性を失っている。そして、今日、なぜ非正規雇用(アルバイト・パート)が増大しているのかを考えると、この『物』化の持つ意味がよりいっそう鮮明になるであろう。効率性、それも数字上の利益の増大だけを目的とした社会の要請(たとえばGDPをはじめとする諸数値が経済の指標とされ、それら経済指標を増加していくことが、社会の使命とされている)。そこには、一切を数字(おかね)という単一の尺度、単一の価値観によって把握しようとする流が垣間見える―確かに、単一化するほどに、高い効率性を生じさせることができるであろう。複雑性は無駄(無用・不必要ではない)を生じさせる―」
また、「言葉」について述べられた以下の箇所も興味深かったです。
「言葉は『ことの葉』でもある。繊細な配慮とともに用いられ、幾重にも重なった『ことの葉』、それによって紡がれる織物は、時に黄金の輝きをも凌駕するきらめきを見せる。しかしながら、『ことの端』の無反省で過剰な羅列は、空疎を生み出すに過ぎず、言葉が持つ信頼そのものを喪失させてしまう。現代は『ブログ』に代表されるように、個人が歴史的にもっとも大量の言葉を発し、それが残されている時代である(もちろん、すべての人間に平等ではなく、きわめて偏ったものであるが)。しかし、その事が同時に言葉の力の喪失を惹き起こしてはいないか」
著者はさらに「言葉」について、次のように述べます。
「ローマン・ヤーコブソンが述べるように、人が最初に身につける言語機能が『交話的機能』であるとするなら、言語能力の基礎を揺るがしかねないこの過剰にして空疎な言葉(ことの端)の氾濫は、交流の拒絶を惹き起こすものになるであろう。言葉の使用が言葉を殺す。他者に対する言葉の喪失、それが今日の社会のありようであるということは、社会を形成する基盤でもある人と人とのかかわりにも当然根本的変化をもたらしているであろう。そしてこの『交話的機能』の原型が触覚的次元であることを考えるならば、言葉の空疎化は触覚性の喪失となる。生身の触れあい、温もりの交わしあいの喪失。それはしだいに他者を排除する隔たりを生み出しているのではないか」
第四章「『歓待』の倫理」では、「歓待」の非共同性について次のように述べられます。
「私たちに身近なさまざまな語りのうちに『歓待』のありようを見ることができる。その1つとして昔話『鶴の恩返し』をあげることができよう。雪の夜訪れた娘をそのまま家に招きいれ、その娘の望みどおりに糸を買い、機が織られる。見るなというタブーが守られているかぎりにおいて。ところが、そのタブーが侵され、娘が何ものであるかが明らかになるとき、娘は鶴となり空に消えていく。よく知られたこの話に、『歓待』の様相が明確に見られる」
訪れてきた娘は、鶴の化身でした。それは人間を超えた神的存在であり、彼女が織る織物は超日常性を持っているのです。
この訪れるものが持つ神的超越性は他の民族の伝承においても見られます。
たとえばアイヌ民族は、訪れる異邦人に対して決して侮った対応をしてはならないと考え、語り伝えてきました。なぜなら、異邦人とは自分たちにとって何ものかわからないからです。
また、オデュッセウスの帰還の際、アンティノオスが浮浪者を殴った行為に対し、仲間は「もし(浮浪者が)天においでの神だとしたら。いかにも神様方はしばしば、他国から来た渡り者に姿を似せて、諸国をお巡りなさるというのに」と言って非難しています。
さらに「ヘブライ人への手紙」には、「旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人は、気づかずに天使たちをもてなしました」と述べられています。
この他にも、日本における来訪神伝説など、多くの語りが、訪れてくるものの神的超越性を示しています。
著者によれば、「歓待」を行うことが共同体からの逸脱を惹き起こすという「歓待」の非共同体性は、じつは「歓待」という営みの基本です。ここで「歓待」のパラドックスという問題が生じてきますが、訪れるものを受け入れるという行為を行っているものの1つに、ホテルや病院があります。どちらも、ヨーロッパ諸国において語源的に「歓待(hospitalite)」と同根であり、これらのありようを考えることは、「歓待」のありようを考える手がかりを与えてくれます。
まず著者は、ホテルを例にして次のように述べます。
「旅人は一日の旅程を終え、辿りついた土地(そこがどこであろうと)にホテルを見出し、投宿する。それはあくまで旅人の行為である。それに対し、ホテルはいかなるありようをしているのか。ホテルは、動くことなく、いつとも、どこからとも知れぬ旅人の訪れを待ち受けるのである。同時に旅人に対して私たちはなんら要求することも、規制することもない。『歓待は他者の歓迎にある。それは私に他者の来訪を予告しない』。『歓待』のイニシアチブは旅人が有しているのであり、主人が有しているものではない。『歓待』は常に一方的に襲来してくるものである。『歓待とは、何よりもまず待つことである』」
また著者は、ホテルに続いて病院について以下のように述べます。
「病院も、特に救急病院を考えるなら、おなじありようであることはすぐに分かるであろう。突然担ぎこまれた患者、そのものが何ものであるかを問うことなく、受け入れ、全能力をもって、応対することが、病院に求められている(もちろん、これらが理念型であり、現実の社会ではいろいろと問題があることは否めないが)」
著者は、これが「他なるもの」の訪れに対して、いかに振る舞いうるかという問いの答えを示唆しているとし、以下のように述べます。
「『歓待』を行う『私』は『他なるもの』の訪れに対して何もできない。『私』は、一切の主体的行為を止めなければならない。主体的行為が行為者の意識によって生じるものである以上、それは必然的に行為者の関心‐利害に基づいたものである」
しかしながら、著者は「歓待」において襲来してくるものが、「私」の関心‐利害の意味づけでは汲むことができないものである以上、「他なるもの」と関わるためには「私」の関心‐利害を排した行為―いいかえれば非主体的行為―が求められるとして、次のように述べます。
「『訪問する権利』は訪れる『他なるもの』にあるのであり、受け入れる『私』にはないのである。『私』は、ホテルや病院と同じく、自ら動くことなく、ただひたすら待つのみである。そして、『他なるもの』は常に不意に襲来してくる。一切の能動を捨てた完全な受動。これが―完全な受動を行為ということが許されるなら―『私』が取れる行為である」
著者は「歓待」の法外性という問題も提起し、次のように述べています。
「『歓待』の際に訪れる『他なるもの』は同時に法外なものであり、同化されえないものである。この、『法外なものの受け入れ』=『歓待』の唯一無二の掟は、同時に『私』が『他なるもの』に対して、問いかけることができないということを意味する。『あなたは誰ですか』『どこから来ましたか』『目的は』などなどの問いかけは、必然的に、それに対する応答を要求する。そしてその応答、あるいは応答拒否によって、『私』は、『他なるもの』に対しレッテルを貼り、『私』にとって理解可能な範疇(排除対象という理解も含む)に入れる。つまり問いかけは『他なるもの』の『他人』化である。これに対して、襲来する『他なるもの』は、それが優れて『他なるもの』であるがゆえに、『歓待』を行う『私』に対して『あらゆる限定以前に、あらゆる先取り以前に、あらゆる同定以前に』、ただ受け入れるという法外な行為を要請する。『私はあなたが誰であるのかなたにたずねはしない。あなたの出身地も、あなたが赴く場所も』」
さらに著者は、「神話」についても以下のように述べています。
「神話は、私たちの世界が、ある意味その根源から切り離された存在であることを語っている。そしてこの世界において、非‐知の根源から、不意に訪れてくる異人を受け入れることは、たしかに異常なことであり、シャーマン化の初期体験が示すように、安定し、秩序だった共同体から逸脱し、無秩序のただなかに投げ出される。しかし、まさにこのとき、人はその超越的存在、根源と分かち難く結ばれた存在であることを確信するのではないのか」
そして著者は、「宗教」について以下のように述べます。
「宗教(religion〈re+ligare〉)はその語源上『つなぐ』という意味を含んでいる。いいかえれば、宗教意識は根源から切り離された『私』を、再び根源につなぎとめ、回帰させる意識ということも言えよう。この根源への交通。この時、今まで述べてきた『歓待』の持つ意味が明確になる。徹底した自己の無根拠性の意識、そこから生じる自己存在への不安。そうした意識に基づく『他なるもの』の無条件の受け入れは、主/客のディコトミーを破砕し、法に基づく社会から逸脱し、根源である『他なるもの』と一体となることで根源へと『私』をつなぎとめるのではないか」
わたしは『決定版 おもてなし入門』(実業之日本社)を著しましたが、そこで「おもてなし」も宗教と深く関わっていることを述べました。
日本人の”こころ”は神道・仏教・儒教の3つの宗教によって支えられており、冠婚葬祭の中ではそれらが完全に共生しています。また、日本流「おもてなし」にもそれらの要素が入り込んでいます。
 『決定版 おもてなし入門』(実業之日本社)
『決定版 おもてなし入門』(実業之日本社)
例えば、神道の「神祭」では、物言わぬ神に対して、お神酒や米や野菜などの神饌(しんせん)を捧(ささ)げます。この「察する」という心こそ、「おもてなし」の源流といえるのではないでしょうか。また、仏教には無私の心で相手に施す「無財の七施(しちせ)」があります。さらに前述した「礼」は儒教の神髄そのものです。これらすべてが、日本の「おもてなし」文化を支えています。
『決定版 おもてなし入門』が「ジャパニーズ・ホスピタリティの真髄」を説明した本であるなら、本書『「歓待」の精神史』はヨーロッパに起源を持つ「ホスピタリティ」を哲学する内容の本であると言えるでしょう。