- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.04.08
『遊動論』柄谷行人著(文春新書)を読みました。
著者は1941年兵庫県生まれ。現代日本における文芸批評の第一人者として有名な人物でしたが、現在は「哲学者」を名乗っています。「柳田国男と山人」というサブタイトルがついた本書は、かつて雑誌に連載したという柳田国男論をじつに40年ぶりに完成させた内容となっています。
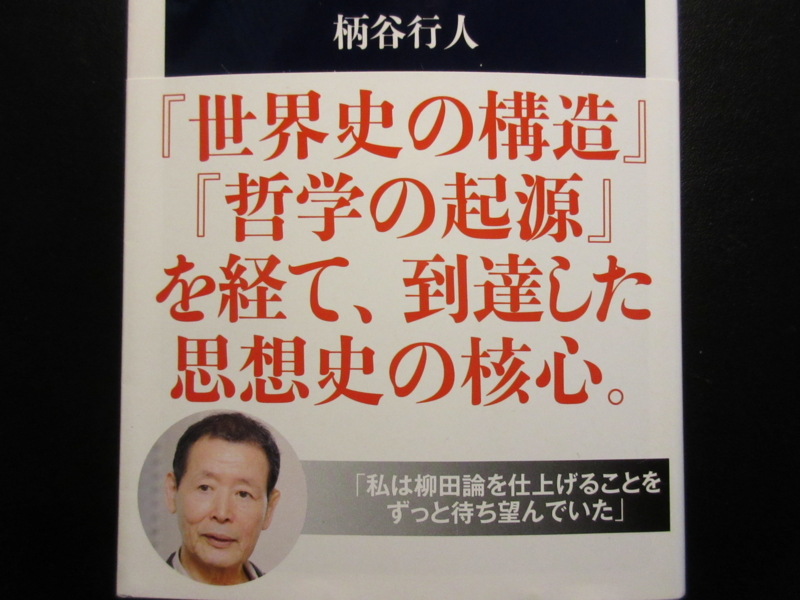 本書の帯
本書の帯
本書の帯には著者の顔写真とともに、「『世界史の構造』『哲学の起源』を経て、到達した思想史の核心」「私は柳田論を仕上げることをずっと待ち望んでいた」と書かれています。
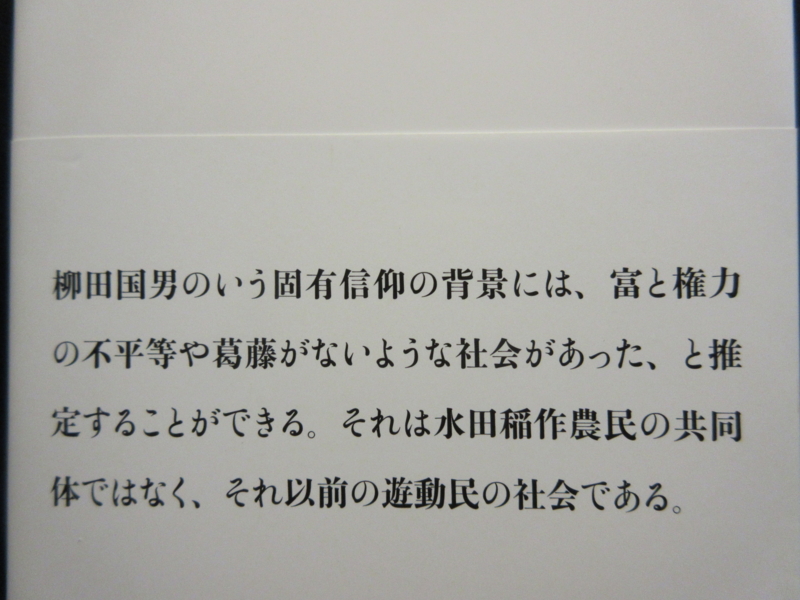 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には、「柳田国男のいう固有信仰の背景には、富と権力の不平等や葛藤がないような社会があった、と推定することができる。それは水田稲作農民の共同体ではなく、それ以前の遊動民の社会である」と書かれています。
さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「民俗学者・柳田国男は『山人』を捨て、『常民』に向かったといわれるが、そうではない。『山人』を通して、国家と資本を乗り越える『来たるべき社会』を生涯にわたって追い求めていた。『遊動性』という概念を軸に、その可能性の中心に迫った画期的論考」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
第一章 戦後の柳田国男
1 戦中から戦後へ
2 柳田の敗北
3 農民=常民の消滅
4 非常民論
第二章 山人
1 近代と近代以前
2 農政学
3 焼畑狩猟民の社会
第三章 実験の史学
1 供養としての民俗学
2 山人と島人
3 公民の民俗学
第四章 固有信仰
1 新古学
2 固有信仰
3 祖霊信仰と双系制
4 「場」としての家
5 折口信夫と柳田国男
6 固有信仰と未来
付論 二種類の遊動性
1 遊動的狩猟採集民
2 定住革命
3 二種類のノマド
4 柳田国男
「あとがき」
「主要参考文献」
「柳田国男年譜」
第一章「戦後の柳田国男」の1「戦中から戦後へ」の冒頭を著者は次のように書き出しています。
「柳田国男は初期の段階で山人、漂泊民、被差別民などを論じていたが、後期にはそれから離れ、彼が『常民』と呼ぶものを対象とするようになり、『一国民俗学』を唱えるようになった。そのことが重視され、且つ批判的に語られるようになったのは、1970年代から80年代にかけてである。それまで、柳田に対するそのような見方はなかった。柳田の初期の仕事についてはよく知られてはいたが、文学的な仕事であると見なされていた。つまり、その後の民俗学や歴史学に結実する可能性をはらむ若書きであると考えられていた。ところが、その初期の仕事の方が重視されるようになり、さらに、柳田が後にそれを放棄したことが非難されるようになったのである」
2「柳田の敗北」では、戦時下に書かれた『先祖の話』が取り上げられ、以下のように述べられています。
「柳田は、1945年空襲警報を聞きながら『先祖の話』を書いた。敗戦の近いことを知っていたはずだから、彼はこの本を戦後に向けて書いたのである。柳田はつぎのようにいう。日本では、人が死んだら魂は裏山の上空に昇って、祖霊(氏神)となり、子孫を見守る。これはそれまで他の著作でも述べてきた持論である。『先祖の話』が異なるのは、つぎのように緊急性をもった問いにある。それは、外地で戦死した若者らの霊をどうするのか、という問いである」
その『先祖の話』で、柳田国男は以下のように書いています。
「少なくとも国のために戦って死んだ若人だけは、何としてもこれを仏徒のいう無縁ぼとけの列に、疎外しておくわけには行くまいと思う。もちろん国と府県とには晴の祭場があり、霊の鎮まるべき処は設けられてあるが、一方には家々の骨肉相依るの情は無視することができない」
これを受けて、柄谷氏は以下のように述べます。
「国家は戦没者を『晴の祭場』に祀ろうとするであろうが、そんなことで死者の霊は浮かばれない。事実、戦後に戦没者の霊は靖国神社に祀られ、それは今も国際的な政治的争点となっている。しかし、柳田によれば、こんな神社に祀ることで霊は浮かばれない。死者が”先祖”になれないからだ。では、どうすればよいのか。本書の最後に、柳田は若い戦死者を養子縁組によって『先祖』にすることを提案している。《新たに国難に身を捧げた者を初祖とした家が、数多くできるということも、もう一度この固有の生死観を振作せしめる一つの機会であるかも知れぬ》。そして、これこそ、この本の主題である。しかし、当然ながら、この案は実行されなかった」
戦後、柳田の関心は沖縄に向かいます。そして、書かれた本が『海上の道』でした。著者は述べます。
「『海上の道』では、中国南部の稲作農民が沖縄に渡り、さらに”海上の道”を通って、日本列島にやってきたと説かれている。しかし、沖縄人が日本に属するかどうかは、同祖であったか否かによって決まるのではない。現実に、平等に扱われているか否かによって決まる。実際、同祖でありながら、異なる国家を形成した民族は少なくない。しかも、沖縄人はもともと琉球王国を形成していたのだ。もし沖縄が日本にとって切り離すことができないような一部であるなら、平等に扱うべきであり、沖縄だけを犠牲にするのはおかしい。『同じ日本人』として扱っていないなら、彼らは独立を求めて然るべきである。柳田国男が1952年以後にいおうとしたのは、沖縄の人々をこれ以上犠牲にするな、ということであった。では、柳田国男の死後、1972年の『沖縄返還』で、何が実現されたか。本土の米軍基地を沖縄に集中することになっただけである。沖縄人を平等に扱うどころではない。柳田がそれを知ったら憤慨しただろう。その意味で、柳田の南島論は、まさに彼の敗北を刻印するものである」
続いて、3「農民=常民の消滅」において「吉本隆明の柳田論」を取り上げます。以下のように吉本の代表作である『共同幻想論』にも言及しています。
「柳田の仕事はその出発点から農政と切り離せないものであった。さらに、民俗学といっても、それは根本的に史学であった。それはいわば、『経済的下部構造』と密接したものであった。しかし、この時期から、柳田の仕事は、そのような面を還元した『民俗学』ないし『文学』として読まれるようになった。そのように柳田を読む態度を代表したのが、吉本隆明の『共同幻想論』(1968年)である」
ちなみに、40年前に著者・柄谷行人氏が柳田論を書いたのは『共同幻想論』を意識してのものであったとされています。
『共同幻想論』は、柳田に『遠野物語』をテキストとしています。これについて、著者は以下のように述べています。
「『遠野物語』を書いた頃、彼は、歴史的に先住民が存在し、その末裔が今も山地にいると考えていた。その後も、彼は山人が実在するという説を放棄したことはない。ただ、それを積極的に主張しなくなっただけである。たとえば、事実がどうかを確認できないが、少なくとも、人々がかく信じていることは事実だ、というような言い方をするようになった。『遠野物語』の段階でも、すでにそうであった。ゆえに、そこでは、山人や妖怪は村人らの幻想であるかのように読める。しかし、柳田は実在としての山人を否定したことは一度もなかったのである」
第二章「山人」の1「近代と近代以前」では、著者は「柳田が農政学に向かったことが偶発事でないこと、さらに、そこから『民俗学の研究』に導かれたということは明らかである。その根底に、飢饉の民を救う『経世済民』という儒教的理念がある」として、さらに次のように柳田の父親について述べています。
「柳田国男の実父(松岡約斎)は平田篤胤派の神官であった。神官の家に生まれたのではなく、中年をすぎて神官になった。柳田がいうように、『敬虔なる貧しい神道学者』であったことは疑いない。したがって、柳田が『幽冥界』の交流に関心を抱いたのは、『父母が相ついで死んでしまった』からではない。子供の頃から関心が深かったのである。平田国学を身近に学んだ者なら、これは当然のことである。そして、それは『経世済民』という儒教的理念と対立するものではない」
柳田が農政学を研究し農商務省に入った動機は、飢饉を絶滅したいということでした。飢饉の記憶は柳田の記憶から離れなかったのです。『遠野物語』には、かつて非常な飢饉の年に、西美濃の山の中で炭を焼く男が、わが子二人を、まさかりで殺した事件が紹介されています。これについて、著者は以下のように書いています。
「これは飢饉によって起こった事件である。しかし、このような事件が起こるのは、飢えた者らが絶望的に孤立しているからだ。柳田の前にはいつも『貧しい農村』という現実があり、それを解決することが彼の終生の課題であった。が、彼にとって、『貧しさ』はたんに物質的なものではなかった。農村の貧しさは、むしろ、人と人の関係の貧しさにある。柳田はそれを『孤立貧』と呼んでいる。では、どうすればよいのか。柳田が協同組合について考えたのはそのためである。《共同団結に拠る以外に、人の孤立貧には光明を得ることはできないのであった》(『明治大正史世相篇』)」
第三章「実験の史学」の1「供養としての民俗学」の冒頭でも、著者は次のように述べています。
「柳田国男にとって、農政学は協同組合に集約される。とすれば、彼が”山人”に注目したのは、農政学を離れることではなかった。民俗学と見える彼の著作は、平地人、つまり稲作農民に、かつてありえたものを想起させ、それが不可能ではないと悟らせるために書かれた。彼が”山人”に見出したのは、『共同自助』をもたらす基礎的条件としての遊動性であった」
柳田は「日本の学界にはミンゾクガクというものが現在は二つある」と述べました。たしかに、民俗学(フォークロア)と民族学(エスノロジー)は日本語では同音であり紛らわしいと言えます。しかし、著者は述べます。
「柳田にとって、山人研究は『供養』を意味した。滅ぼされた先住民を、征服者の子孫であり、且つ、その先住民の血を引いているかもしれない自分が、『一巻の書』をなすことによって、弔うこと。つまり、彼は、征服する者と制服される者を同一のレベルで考えていた。それがこの学問の特性なのだ。したがって、柳田にとって、植民地下の『未開社会』を考察する民族学と、『同胞の文化』を探求する民俗学という区別は存在しなかったのである」
晩年の柳田は沖縄に関心を向けましたが、「山人と島人」として、著者は以下のように述べています。
「南島に向かったとき、柳田は先住民としての『山人』を放棄したといわれる。しかし、南島において、彼は山人の問題を別の角度から考えたのである。たとえば、1904年、人類学者鳥居龍蔵は沖縄本島に、突起のついた縄文土器を見出し、沖縄が日本内地と文化的に共通することを唱えた。それを縄文人と呼ぶかどうかは別としても、沖縄に、縄文土器に類似する土器をもった狩猟採集民がいたことはまちがいないのである。すると、彼らは到来した稲作農耕民によって駆逐されたか、ないしは完全に吸収されたということになる」
沖縄では、死者は海上の理想郷「ニライカナイ」へ行くとされていますが、著者は以下のように述べます。
「柳田は祖霊信仰に関して、死者の霊は近くの山の上に向かう、といっている。しかし、沖縄では祖霊は海の向こう(ニライカナイ)に行く。ここで、どちらが祖型であるかと問うべきではない。沖縄には本土のような山がない。ゆえに、祖霊は海の向こうに行く。柳田は本土で山の上に見ていたものを、沖縄では海の向こうに見た。だが、山か海かは重要ではない。また、どちらが原形であるともいえない。いずれも孤島における現象なのだから」
第三章「実験の史学」では、神社合祀への反対についても触れています。1906年、いわゆる「神社合祀令」が出されたとき、柳田は反対しました。南方熊楠と知り合い、頻繁に文通するようになったのも、神社合祀への反対運動がきっかけでした。それは、小さな神社を廃して大きな神社に統合する政策であり、1914年までに20万あった神社のうちの7万が取り壊されました。これは政治的に中央集権化の一環でしたが、地域共同体を解体して行政的区域に還元してしまうことを意味しました。これに対して、南方と柳田は共同で反対運動を行ったのです。
南方の反対理由は主に「鎮守の森」が消滅することによる生態系の破壊であり、自然環境問題でしたが、柳田のそれは違いました。著者は述べます。
「神社は歴史的にたえず統廃合されてきた、しかし、柳田の考えでは、神社は根本的に氏神信仰、つまり、祖霊信仰にある。つまり、どんなに統廃合されても、それは祖霊信仰を保持するものでなければならない。しかるに、政府の神社合祀令は、全国の神社をまとめて国家神道の下に統制することを目指している。それに対して、柳田は、各家の祖霊信仰に立ち戻ることを主張したのである」
柳田はまた、祭が巨大化し壮麗になっていくことにも反対でした。祭は基本的に、小さく、静かで、真剣なものです、それが大がかりで派手なものになったとき、変質したとして反対しました。著者は述べます。
「祭りが巨大化するのは、人々が祭の当事者ではなく、見物人となったからである。それはまた、人々がすでに家や共同体を出てしまっていることを意味する。同様のことが、神社が巨大化すること、あるいは国家神道の形成についていえる。そのようなところに、柳田がいう固有信仰は残っていない。柳田国男が巨大化・壮麗化を嫌ったことは、祭や神社のことだけではない。柳田の視線は、つねに、小さく無名なものに注がれている。通常、歴史において子供が役割を果たすことはほとんどない。しかし、柳田国男の史学では、『小さき者』(児童)が重要なのである」
それでは、柳田のいう「固有信仰」とは何なのか。第4章「固有信仰」の1「新古学」で、著者は述べています。
「柳田がいう『固有信仰』は、稲作農民の社会では痕跡しか残っていない。それはむしろ、それ以前の焼畑狩猟民の段階に存在したものである。ゆえに、固有信仰を求めることは、実は、山人を求めることにほかならない。
このような固有信仰を探求する時点で、柳田の民俗学は神道史研究と重なる」
著者は、柳田国男は平田篤胤よりも本居宣長に近いとして、述べます。
「宣長は儒教・道教を『漢意(からごころ)』、仏教を『仏ごころ』として批判した。が、同時に、彼は日本の神道をも『漢意』に染まっていると批判したのである。神道学者らがいう日本固有の『神道』は、実は、仏教や道教・儒教から得た理論を用いて体系化したものにすぎない。神道は、そのような理論ではなく、『事実』、いいかえれば現実に人が生きている有り様に見出されなければならない。そこで、宣長は『古(いにしえ)の道』を、『古事記』に見出そうとした。彼は自らの学問をたんに『古学』と呼んだ。それを『国学』にしたのが平田篤胤である」
しかし、その宣長を柳田は批判しました。宣長は文献主義的すぎるというのです。著者は以下のように述べています。
「たとえば、宣長は、仏教で悟りを得たから、あるいは救済を信じるから、もはや死に拘泥しないというのは、漢意的な欺瞞であるという。人が死ねば、黄泉の国(根の国)へ行く、したがって、死ぬことはたんに悲しい、というべきだ、と。しかし、宣長自身は浄土教の門徒であり、死後、魂が地底に留まるとは考えていなかったがずである。皮肉にも、そのほうがむしろ『古の道』に近い考えなのだ。
宣長とは対照的に、平田篤胤は、文献以外の方法をとろうとした。たとえば、霊能者からの聞書きなどを進んでおこなった。その意味では、柳田は篤胤に近いといえるが、根本的な態度においては宣長の『古学』を受け継いだ。柳田の学問は、いわば、民俗学的方法による古学ということができる。彼が自らの仕事を『新国学』と呼んだとき、そのような含意があった。ただ正確を期すなら、柳田国男の民俗学=史学は、『新国学』というより『新古学』と呼ぶべきだろう」
そして著者は、柳田の「固有信仰」について説明します。
「柳田国男が推定する固有信仰は、簡単にいうと、つぎのようなものである。人は死ぬと御霊(みたま)になるのだが、死んで間もないときは、『荒みたま』である。すなわち、強い穢れをもつが、子孫の供養や祀りをうけて浄化されて、御霊となる。それは、初めは個別的であるが、一定の時間が経つと、一つの御霊に融けこむ。それが神(氏神)である。祖霊は、故郷の村里をのぞむ山の高みに昇って、子孫の家の繁盛を見守る。生と死の二つの世界の往来は自由である。祖霊は、盆や正月などにその家に招かれ共食し交流する存在となる。御霊が、現世に生まれ変わってくることもある」
さらに、著者は柳田のいう「固有信仰」について述べます。
「柳田がいう固有信仰の核心は、祖霊と生者の相互的信頼にある。それは互酬的な関係ではなく、いわば愛にもとづく関係である。柳田が特に重視したのは、祖霊がどこにでも行けるにもかかわらず、生者のいる所から離れないということである。このような先祖崇拝は日本固有のものだ、と彼は考えた」
死者が祖霊になるのに一定の時間がかかり、そのためには子孫の供養が必要だという考えは、世界中どこでも共通しています。だから、子孫が不可欠なのです。
著者は、「場」としての家について語り、次のように述べます。
「『先祖の話』の最後で、柳田は、政治家は理解しないだろうといいながら、一つの政策を提言する。それは、戦争で死んだ若者は子供がいないから、先祖にはなれない、そこで、死者の養子となることで、彼らを先祖(初祖)にするようにせよ、というものである。《新たに国難に身を捧げた者を初祖とした家が、数多くできるということも、もう一度この固有の生死観を振作せしめる一つの機会であるかも知れぬ》。
死者の養子になることは、『固有の生死観』(固有信仰)にある、と柳田はいう。しかし、これは、祖先崇拝において一般に見られるものではない。先に、日本の固有信仰の特徴として、養子や結婚による縁があるとか、さらに、その者が家に何らかの関係をもつのであれば、祖霊の中に入れられるということを述べた。これはおそらく、双系制と関連している。双系制社会では、先祖に関する見方が単系制社会と異なるのだ。単系制では、父系であろうと母系であろうと、先祖は一つである。それを目印にして、集団が組織される。しかるに、双系制では、出自が何であれ、今人が帰属する場が大事である。『家』がそのような場である」
柳田は「先祖」とは血縁とは無関係であると述べたのです。これに関して、著者は以下のように述べています。
「日本では『遠い親戚より近い他人』という考えが一般的である。それは、祖霊に関してもあてはまる。『近い他人』が先祖となりうるのだ。
したがって、柳田国男が『先祖の話』で、戦死した若者の養子となることで彼らを初祖にすることを提唱したのは、奇矯なことではなかった。もともと、次・三男が本家から分家して初祖となることはありふれていた。大事なのは、死者を祀る子孫がいることであって、それが養子であっても構わない。血のつながりのない人たちが、オヤ・コ、あるいは先祖・子孫となるのは、珍しいことではない。柳田自身、柳田家に入った養子として、祖霊を祀ったのである」
柳田の関心はあくまで固有信仰にあり、民俗学はそれを探る方法にほかならないと考えていました。しかし、柳田の弟子であり、同様に神道と民俗学について研究していた折口信夫はそうは考えませんでした。日本の敗戦を覚悟していた柳田と違って、折口はそれをまったく予期しておらず、1945年夏になって、日本の神々が敗れたのだと考えました。そして、神道を「民族教」から「人類教」にしなければならないと訴えたのです。折口の神道人類教化とは、神道から先祖崇拝の要素を取り除くことにほかなりませんでした。
しかし、柳田国男の考えはまったく違いました。著者は述べます。
「神道から先祖崇拝を取り去り、人類教として世界に広めようというような発想は、柳田が最も嫌うものであった。かつて、明治国家がヨーロッパの教会建築を真似て各地の神社を合併し巨大化しようとしたとき、反対したように。小さいこと、あるいは、弱いことは、普遍的であることと背反しない。そのような考えが、柳田国男の思想の核心にある。強大なものは没落する。おそらく柳田が空襲警報を聞きながら『先祖の話』を書いていたとき、そのような光景が迫り来るのを感じていたのだろう」
本書を読んで、わたしは日本の歴史と社会を理解するために、今でも柳田国男の民俗学が大いに役立つことを思い知りました。本書は『共同幻想論』を意識して書かれたそうですが、同書が柳田の『遠野物語』論であるならば、本書は『先祖の話』論であると思いました。それにしても、『世界史の構造』『哲学の起源』といった大著を経て、著者が最後に到達したのが柳田国男の思想であったことは、わたしにとって驚きであり、また大きな喜びでもありました。最後に正直に言うならば、「遊動」についての著者の意見はあまりピンときませんでした。『世界史の構造』で提唱した「遊動」の理論を柳田「山人」論で証明したかったのでしょうが、牽引布教のように感じました。
