- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0545 書評・ブックガイド 『野蛮人の図書室』 佐藤優著(講談社)
2012.02.21
『野蛮人の図書室』佐藤優著(講談社)を読みました。
「知のモンスター」と呼ばれる著者は、これまでにも『功利主義者の読書術』(新潮社)、立花隆氏との共著である『僕らの頭脳の鍛え方』(文春新書)などのブックガイドを世に送り出してきました。それらの本を興味深く読んだわたしは、このモンスターによる新たなブックガイドも楽しく読ませていただきました。
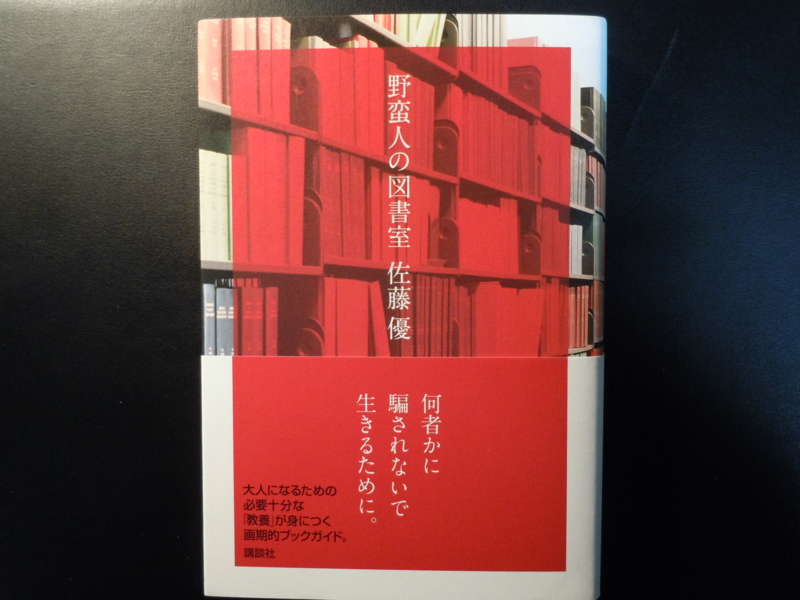
本書の帯には「何者かに騙されないで生きるために。」というキャッチコピーに続いて、「大人になるための必要十分な『教養』が身につく画期的ブックガイド。」と書かれています。「大人になるための」というフレーズは、もともとが「週刊プレイボーイ」の連載だったためでしょうか。本書の「目次」は、以下のようになっています。
まえがき「ようこそ、ラズベーチク・ライブラリーへ」
第一章:人生を豊かにする書棚
第二章:日本という国がわかる書棚
第三章:世界情勢がわかる書棚
第四章:頭脳を鍛える書棚
あとがき「司書室にて」
まえがき「ようこそ、ラズベーチク・ライブラリーへ」の冒頭で、著者は述べます。
「われわれは、誰もが野蛮人である。この現実を見据えることが重要だ。
現代社会は複雑で、世の中で起きていることを正確に理解するためにはさまざまな知識が必要になる。確かに日本は世界でもっとも教育水準の高い国だ。アジアにありながら欧米列強の植民地にならず、太平洋戦争敗北後の荒廃から社会と国家を見事に復興させたわが日本民族は、客観的に見て優秀である。しかし、現在の日本が衰退傾向にあることは、残念ながら、事実である。どうしてなのだろうか?」
著者は、それを解く鍵をドイツの社会哲学者ユルゲン・ハバーマスに求めます。そして、ハバーマスの「順応の気構え」という言葉に注目して、次のように述べます。
「理解できないことが生じたときに『誰かが説得してくれる』と無意識のうちに思って、自分の頭で考えることをやめてしまうのが『順応の気構え』だ。テレビのワイドショーでは、殺人事件、芸能人のスキャンダル、政治、経済、外交などについて、コメンテーターが15~30秒でコメントをする。『よくわからないけれど、有名な人がそういうのだから』と無意識のうちに思って、順応してしまうのである。そうするうちに人類は徐々に野蛮人化していく。そして、最後には自分が野蛮人であるということにすら気づかなくなってしまう。文明国であったドイツからアドルフ・ヒトラーが出てきたのも、ドイツ人の多くが自分の頭で考えることをやめ、『順応の気構え』を持つようになってしまったからだ」
さて、生きていく上で「教養」が必要だということは誰もが知っています。では、読書によって教養をつけるためのコツのようなものがあるのでしょうか。著者は「ある」と断言し、次のように述べています。
「数学で分数が理解できていない人が、微分、積分に関する本を読んでも、絶対に内容を理解することはできない。それと同じように政治や経済、あるいは恋愛についても、本には読む順番がある。世の中には難しい内容を入門者向けにわかりやすく書いた本がある。こういう本をきちんと読んでおけば、自分の頭で現在起きている出来事を読み解くことができるようになる」
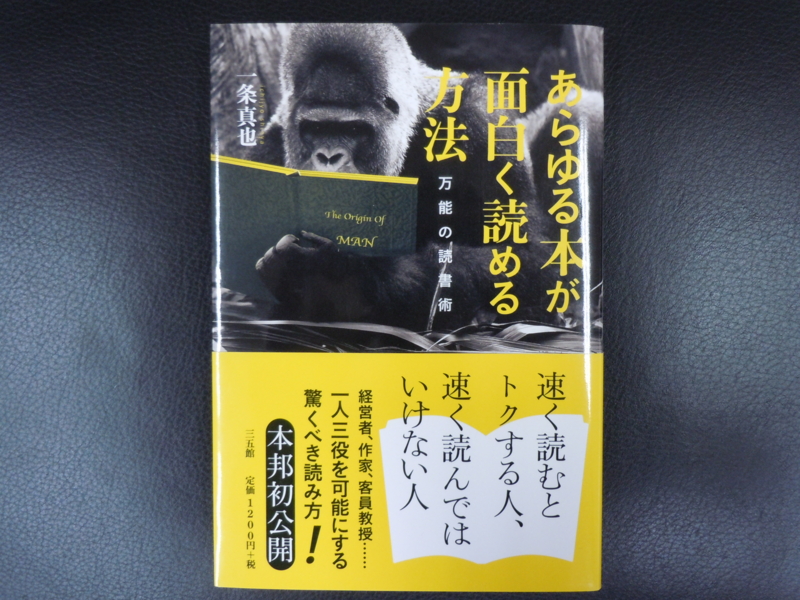
これを読んで、わたしは自分自身の読書体験を思い出しました。拙著『あらゆる本』(三五館)に書いていますが、わたしが2001年10月に社長に就任したときにまず決心したのが、「数字に強い社長になろう」ということでした。それまでは、数字というものをあまり意識したことがありませんでしたし、高校のときから数学には苦手意識を持っていました。はっきりいって、数字には弱かったのです。
しかし、社長になったことで、金融や経済のことを学び直す必然性にかられたのです。
そのとき、いきなり金融論や簿記の専門書に取りかかるよりもまず、数そのものを好きになるべきだと考えました。当時、『数の悪魔』(ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー著、 丘沢静也訳、晶文社)など、面白い数学本がいろいろと出ていたので、それらを片っ端から読んでいきました。数学関係の分野を読み終えると、続いて会計の本へ。それから金融論からミクロ経済、マクロ経済を読んで、経済学、経営論へ。そこからブーメランを描くように、哲学分野に戻ってくるまで、徹底して金融・経済・経営を学びました。
『稲盛和夫の実学 経営と会計』(日本経済新聞社)で、「経営者たる者、会計に疎いようでは失格!」という啓蒙をしっかりと受けてから、『会計のことが面白いほどわかる本』(天野敦之著、中経出版)で会計の基本を、『金融入門』(岩田規久男著、岩波新書)で金融の基本を、『ミクロ経済学』(武隈慎一著、新経済学ライブラリ・新世紀社)でミクロ経済学の基本を『マクロ経済学』(伊藤元重著、日本評論社)をマクロ経済学の基本を学びました。それぞれ入門書における名著です。
基本的知識を得た後は、それぞれの分野の本を20冊ずつくらい読みました。内容は、だんだんレベルアップしていきました。そして、このあたりからケインズとかハイエクといった経済学の専門書に取りかかっていきました。
もし勉強しはじめてすぐにケインズやハイエクにとりかかっていたとしたら、チンプンカンプンで挫折してしまったかもしれませんが、入門書から始め、ある程度の本を読んでいましたから、意外にすんなりと読むことができました。
もともと、わたしは大学の政治経済学部の経済学科で経済学は学んでいたはずなのですけどね。当時はディスコに夢中で、まったく勉強しませんでしたから(笑)。
多くの経済学者たちのなかでも、わたしとしてはシュンペーターの考えが一番しっくりきました。シュンペーターは、イノベーションの重要性を説いた人で、ウィーン大学の経済学教授だったドラッカーの父親の弟子です。ドラッカー自身も、経済に対する考え方はシュンペーターの影響を強く受けています
さて、本書は、さまざまなテーマを取り上げ、それに関係する本を2冊紹介するというスタイルです。たとえばテーマが「猫」「ウミガメ」「京都」なら、それぞれ「猫が教える『信頼関係』」「ウミガメに見る女の本質」「京都に学ぶ人間の裏・表」といったふうなタイトルのブックガイドになるわけです。
このようなタイトルが全部で57並べられています。1冊あたりを紹介する文字数は『功利主義者の読書術』や『僕らの頭脳の鍛え方』に比べるとずっと少ないので物足りない気もしましたが、なかなかユニークな視点で読書案内しているので勉強になりました。その中で、特に印象に残った部分をいくつか紹介したいと思います。
まず、「ひとつの映画を二度楽しむ」というタイトルでは、『納棺夫日記 増補改訂版』青木新門著(文春文庫)、『啓蒙の弁証法 哲学的断想』ホルクハイマー、アドルノ著、徳永恂訳(岩波文庫)が取り上げられています。『納棺夫日記』といえば、映画「おくりびと」の原作として知られますが、著者は「率直に言うが、映画による感動には危険な面がある」といきなり喝破し、次のように述べます。
「かなり厳しい表現だが、映画やテレビなど、映像と音声が合わさったメディアによる感動は、画面の中の出来事と現実の出来事を同一視させる機能がある。
だが、現実の生活は映画よりもはるかに複雑だ。現実の生活でほんとうの感動を得るためには映画だけでは不十分だ。それに何かが付加されなければならない。
『おくりびと』を見た後、『納棺夫日記』を読むことで感動の質が変わってくる。例えば、死に直面した人間に関する著者の考察に評者は深く考えさせられた。
<誰かに相談しようと思っても、返ってくる言葉は「がんばって」のくり返しである。/朝から晩まで、猛烈会社の営業部のように「がんばって」とくり返される。親族が来て「がんばって」と言い、見舞い客が来て「がんばって」と言い、その間に看護婦が時々覗いては「がんばって」となる。/癌の末期患者に関するシンポジウムかなにかだったと思うが、国立がんセンターのH教授が発言した言葉だけを覚えている。/ある末期患者が「がんばって」と言われる度に苦痛の表情をしているのに気づき、痛み止めの注射をした後「私も後から旅立ちますから」と言ったら、その患者は初めてにっこり笑って、その後顔相まで変わったという話であった>
(『納棺夫日記 増補改訂版』青木新門著《文春文庫》64頁~65頁)」
著者は、「映画をきっかけに、もとになった本や原作を読むことだ」と読者に訴えます。そして、「活字によって、自分の頭の中でイメージを思い浮かべることで、映画を見て直接受けるのとは異なった感動を経験することができる」とアドバイスするのです。
また、「司馬遼太郎の世界観」というタイトルでは、『坂の上の雲』全8巻、司馬遼太郎著(文春文庫)、『司馬遼太郎を読む』中村稔著(青土社)が取り上げられています。日本の国民作家といえば、なんといっても司馬遼太郎の名が最初に挙げられます。その歴史観は「司馬史観」と呼ばれ、日本人の意識に大きな影響を与えています。昨年末で放映が終了したNHKドラマスペシャル「坂の上の雲」は多くの視聴者の感動を呼び、その原作小説もよく読まれました。しかし、著者は次のように述べています。
「詩人の中村稔は、この小説で司馬遼太郎が展開した歴史観についてこう述べる。
<『坂の上の雲』は秋山好古、真之兄弟と、それに加えて、正岡子規を軸として、明治初期から日本海海戦にいたる時期までを描いた歴史小説ですから、何故日本とロシアが戦わなければならなかったか、を書くのは当然です。司馬さんはこう書いています。
『日露戦争をおこしたエネルギーは歴史そのものであるとしても、その歴史のこの当時のこの局面での運転者のひとりが、ニコライ2世であった』、また、『どちらがおこしたか、という設問はあまり科学的ではない。しかし、強いてこの戦争の戦争責任者を四捨五入してきめるとすれば、ロシアが8分、日本が2分である。そのロシアの8分のうちほとんどはニコライ2世が負う。この皇帝の性格、判断力が、この大きなわざわいをまねいた責任を負わなければならない』。このロシアが8分、日本が2分という思い切りのいい歴史の割り切り方が司馬史観といわれるものであろうと思いますし、これが、司馬さんの作品の魅力であることは間違いないと思います>」
かつて外務省に在籍した著者はロシア問題の専門家でしたが、この中村稔の著書を読んで、次のように述べます。
「日露戦争の責任をロシア8、日本2と振り分ける客観的根拠はどこにもない。当時は帝国主義の時代だった。近代国家となるためには、帝国主義政策に基づいて勢力圏確保のための戦争をする必要があった。それを指導者の性格や判断力に帰してしまい、さらにそのことが妙に説得力をもってしまうのが司馬史観の魔力である。
評者は、小説はあくまでも娯楽であると考える。現実の歴史を小説によって理解しようとすることはきわめて危険である」
著者は『坂の上の雲』における教育観の問題にも言及します。
秋山信三郎好古は、子どもの頃は「信」と呼ばれていました。『坂の上の雲』の第1巻には、父が好古に向かって「信や、貧乏がいやなら、勉強をおし」と言う場面が出てきます。この言葉に続いて、「これが、この時代の流行の精神であった。天下は薩長にとられたが、しかしその藩閥政府は満天下の青少年にむかって勉強をすすめ、学問さえできれば国家が雇傭するというのである」と司馬遼太郎は書いています。しかし、これに対して、著者は次のように述べるのです。
「学問は本来、真理を追究するためのものだ。それがここでは就職の手段となっている。そして、よい成績をとってよい就職をすれば、経済的に苦労しないという俗物精神がここで褒め讃えられている。こういう姿勢でいくら勉強をしても、受験に合格する力はついても、物事を判断するために役立つ教養は身につかない。
お受験、学習塾通い、苛酷な受験競争、大学でも就職試験のための予備校に通い、勉強漬けになっても、その目標が就職であると、就職後、覚えた内容は数年で頭から消えていく。こういう勉強は結局、時間の無駄にしかならない。
『坂の上の雲』型の勉強では、国際競争に耐えることができるような真の教養人は生まれてこないと評者は考える」
うーん、手厳しいですな。国民的名作『坂の上の雲』もしょせんは野蛮人の読み物というわけですね。失礼ながら、この考え方は著者が東大閥に牛耳られている外務省においてキャリアの道を歩まなかったことも影響しているような気がします。もしも間違っていたら、ごめんなさいね。
そして、「プロレスは社会の縮図だ」という素敵な(笑)タイトルでは、『アントニオ猪木自伝』猪木寛至著(新潮文庫)、『みんなのプロレス』斎藤文彦著(ミシマ社)が取り上げられています。著者が外交官としてモスクワの日本大使館に勤務していた頃、なんとアントニオ猪木氏のアテンド係だったそうです。猪木氏は当時、参議院議員を務めていました。著者は、以下のように当時を振り返ります。
「猪木さんは酒が強い。評者も体質的にアルコールはけっこう体に入るほうだ。2人でウオトカを2~3本飲む。その時、猪木さんは必ず力道山の思い出について話す。
<力道山は普段もゴルフの練習用に、柄の先に鉛の玉がついているクラブを持ち歩いていた。綺麗に振れるとカチーンと音がする。ある夜、酔っぱらった力道山が「おいアゴ、ちょっと来い」と言うので、近づくと、そのクラブで思い切り頭を殴られた。目から星が散って、カチーンといい音がした。私は何も悪いことはしていなかったと思う。あのときは、熱が下がらずに1週間ぐらい寝込んでしまった。
やはりどこかで理由もなく殴られたとき、殺意を覚えたこともあった。そのとき、たまたま目の前に料理包丁があったのだ。一瞬、頭の中に『刺してやろうか』という気持ちがよぎった。だが勿論、刺さなかった。相手は師匠だし、私にはそんな度胸はない>
同じく付き人をしていたジャイアント馬場氏は、力道山にこのような扱いをされたことはないと猪木さんは言っていた。猪木さんは力道山をまったく恨んでいない。むしろ、あの激しさがどこから生まれたかを探究したいという気持ちが強かった。
それが力道山の祖国である北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)との交流に猪木さんが取り組む動機なのである。猪木さんは、『プロレスは労働者階級に楽しんでもらうスポーツだ。プロレスは社会の縮図だ』と言っていた」
力道山から受けた虐待を猪木氏が回想する発言など、『力道山の真実』という本の内容そのままなので、プロレスに目がないわたしはコーフンしてしまいました。
プロレスを「民主社会のスポーツ」であるととらえる著者は、「単なる目立ちたがり」とか「守銭奴」などと何かと批判されがちな猪木氏に対しても優しい目を向けています。
そして、著者は「猪木さんは、プロレスがヤラセのショーであるという見方に大反発していた。猪木さんの話を聞いて、評者もプロレスラーが死と隣り合わせの職業だということがよくわかった。猪木さんの場合、イラクからの人質解放に命がけで取り組んだが、その背景にもプロレスラーとしての猪木さんの死生観がある。ロシアとのからみでも命を失いかけたことがある」と述べています。そして、最後に著者は「今の日本の政界に命がけで政治に取り組む政治家が少ないことが残念だ」と書いています。
アントニオ猪木氏といえば、北朝鮮でも巨大興行を打ちました。本書には「北朝鮮とミサイル」というタイトルもあり、『テポドンを抱いた金日成』鈴木琢磨著(文春新書)、『平成20年版 日本の防衛―防衛白書―』防衛省編集(ぎょうせい)が取り上げられています。そこで、著者は次のように北朝鮮の今後について述べています。
「北朝鮮は、おそらく2012年の金日成生誕100周年を目処にして国家指導者の代替わりを計画しているのだと思う。後継者が誰であるかについて、固有名詞はそれほど重要でない。金正日の息子であれば誰でもいいのだ。
<革命は銃である。革命武力なくしては革命の勝利は達成できないし、勝利した革命も守り抜けない。そもそも首領さま[金日成]の思想と偉業を実現していく革命闘争は反革命勢力との深刻な闘争を伴う。力の対決で勝利する決定的担保は革命武力の不敗性にある>これは1998年4月25日付朝鮮労働党機関紙『労働新聞』の記事の一部だ。
北朝鮮は、『革命武力の不敗性』を日本との関係でも証明しようとしている。
このような北朝鮮の脅威に対して、国民が一丸となって対抗すべきだ」
実際は、昨年の12月に金正日は死去し、三男である金正恩が後継者に決定しました。
そして最近、三五館から『横田めぐみさんと金正恩』(飯山一郎著)という物凄い内容の本が刊行されました。三五館といえば、佐藤優氏は同社から刊行された『検察に死の花束を捧ぐ』(柴野たいぞう著)を高く評価しているとか。「出版界の青年将校」こと中野長武さんが衆院議員会館で佐藤氏に会った際、「この本は素晴らしいので、私もいろんなところで宣伝します」と言われたそうです。ならば、当代一のインテリジェンスである佐藤氏は、果たして『横田めぐみさんと金正恩』という稀代の奇書をどう読むのか? わたしは、そのことに非常に関心があるのです。いや、ほんとに。