- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0532 文芸研究 『遠野物語と源氏物語』 鎌田東二編(創元社)
2012.01.22
『遠野物語と源氏物語』鎌田東二編(創元社)を読みました。
2009年に開催された「物語の発生する場所とこころ~遠野物語と古典」と題するシンポジウムの内容を掲載した本です。京都府と京都大学こころの未来研究センター主催で、遠野市にある「遠野物語研究所」の共催により行われたシンポジウムです。
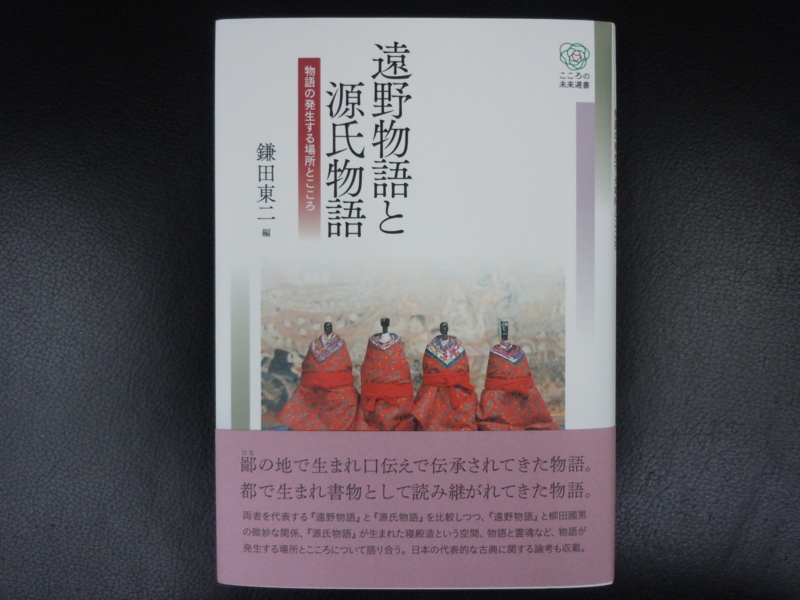
本書の帯には、「鄙の地で生まれ口伝えで伝承されてきた物語。都で生まれ書物として読み継がれてきた物語。両者を代表する『遠野物語』と『源氏物語』を比較しつつ、『遠野物語』と柳田國男の微妙な関係、『源氏物語』が生まれた寝殿造という空間、物語と霊魂など、物語が発生する場所とこころについて語り合う。日本の代表的な古典に関する論考も収載。」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「はじめに」 (鎌田東二)
〈基調講演〉
『遠野物語』と『源氏物語』の距離 (山折哲雄)
〈第一部〉
『源氏物語』の場所とこころ (山本淳子)
歌と物語の発生 (上野誠)
『遠野物語』の場所とこころ
討議1 (石井正己・山本淳子・上野誠・鎌田東二)
〈第二部〉
東北おばあたちの発声現場 (川村邦光)
『遠野物語』における場所とこころの接点 (河合俊雄)
コメント (山折哲雄)
討議2 (川村邦光・河合俊雄・山折哲雄・鎌田東二)
閉会のあいさつ (高柳俊郎)
〈論考〉
『遠野物語』と「古典」 (鎌田東二)
「あとがき」 (鎌田東二)
本書はすべてが興味深い内容ですが、特に関心を惹かれた点がいくつかありました。
まず、宗教学者の山折哲雄氏の基調講演「『遠野物語』と『源氏物語』の距離」で、柳田國男の「方言周圏論」に触れた部分です。方言周圏論とは、ある場所の最も古層の文化意識を表す言葉は、コンパスで500キロ、1000キロと円を描いたときの最も外周部のあたりに分布しているという考え方です。山折氏は、次のように述べています。
「京都を中心にコンパスで半径1000キロメートルの円を描いた場合、北の1000キロメートルの最果ての地域がちょうど下北半島になるわけです。そこからコンパスをぐるっと南のほうに回しますと、沖縄諸島がある。
そういう意味のことを柳田さんは言われています。
今日の話題の1つにもなると思いますけれども、実は、下北半島には『イタコ』といって、死者の魂を呼び降ろし、いってみれば魂の操作をする職業的な宗教者、つまりシャーマンが現に存在しているわけです。あの人々は、そういう意味での古層に属する言葉を操る人々である。ちょうど同じように、京都から計って反対側の1000キロメートルかなたにある沖縄諸島では、『ユタ』という、同じようなシャーマンが今日なお活動している。
柳田さんはそれをはっきりと実証したわけではございませんが、今日、下北半島の、たとえば恐山で行われているイタコのホトケ降ろしという現象と、南の沖縄諸島で行われているユタによる死者の魂の操作、鎮魂儀礼とは、同じ根っこに生えた2つの伝承形態であるという意味のことを言っているのです。言葉の上でも、『イタコ』と『ユタ』は似ているような感じがいたします。言語学的に言って、こういう語源解釈がどれほど正しいかは置くとして、私はかなり説得力がある議論だなと思って、いつも思い返しているのです」
また、山折氏は『遠野物語』に出てくる「寒戸の婆」について、きわめて興味深い説を展開します。「寒戸の婆」とは、神隠しに遭った少女が30年ぐらい経ってから帰ってくるという話です。ある家の少女が行方不明になって、30年の時間が経過してから、風が強く吹く火に、老婆がすーっとその家に現れて、人々の間を通り抜けていきます。
「おまえは、あのときにいなくなった娘かい?」と訊くと、「そうだ」と答える。「なぜ、ここに来たのか?」という問いには「懐かしくなって、やって来た」と答え、すーっと通り抜けてまた去っていく。そして、「風の強く吹く日は、『寒戸の婆』が現れるぞ」と言って、みんな不安げに語り合ったという話です。
この「寒戸の婆」は、神隠しに遭って30年間姿を隠していた生きている人間なのか、それともすでに死んでしまっている亡霊なのかはわかりません。このような正体不明な存在が里人の間に出現し、一時的な交流をして、また姿を消してしまうのです。この「寒戸の婆」について、山折氏は以下のように述べます。
「私は、もしかすると、これが『源氏物語』の世界になって、あの六条御息所の話に化身するのではないかと思うのです。六条御息所が言い過ぎであるならば、六条御息所の生き霊、死に霊の問題です。六条は生き霊の姿で、源氏の恋人、葵の上の体に乗り移って、葵の上を呪い殺してしまう。これは『源氏物語』の冒頭に出てくる話です。
それから、六条御息所が亡くなったあとは、その死霊が、今度は紫の上に取り憑いて、紫の上を病気に誘い、やがて死に至らしめる。六条御息所の生き霊、死に霊の働きの源泉をたどっていくと、もしかすると、『寒戸の婆』に行くのかもしれない。それだけではない。『源氏物語』には、『寒戸の婆』のごとき霊的な存在が、『もののけ』という形をとっていくつも出てまいります」
もちろん、『遠野物語』よりも『源氏物語』のほうがはるかに古い物語で、1000年も前に書かれているわけです。しかし、その内容は『遠野物語』のほうが古い世界を扱っており、それが『源氏物語』に影響を与えた可能性があるというのですね。一種の時間の逆転現象が起こっているわけで、非常に面白いと思いました。
また、民俗学者の川村邦光氏の「東北おばあたちの物語の発声現場」が非常に興味深かったです。東北の巫女たちは、青森、岩手、秋田の北部あたりまでは、「イタコ」と呼ばれます。岩手県の南のほうや宮城県では、「オカミン」とか「オガミサマ」と呼ばれます。福島県の人々は、「ワカ」とか、「ワカドノ」という名前で呼びます。彼女たちは、死者の代弁、いわゆる「口寄せ」を行います。口寄せをする巫女は、まず神降ろしをして、いろんな神様を呼びます。そしてホトケ降ろしの言葉を称えて、それからホトケさんが出てくるといったパターンを踏襲します。この東北の巫女たちの口寄せが『源氏物語』の世界に通じるとして、川村氏は次のように述べるのです。
「ある意味では、物語を説いていく初めの言葉というか。『葵上』のあたりからか、いつから始まるのかわかりませんが、定型化された言葉によってある種の状況をつくる。『蘆毛の駒に、手綱揺り掛け』と、馬に乗ってくるのかどうかわかりませんが、百里の道からだんだん近づいてくる。そういう雰囲気や場面を構成しながら死者を登場させて、死者の語りを行っていくのが、口寄せのひとつの場面のつくり方、あるいは、物語のつくり方と言ってよいかと思います」
そして、川村氏は「物語によって弔いを行う」ということを説明します。口寄せのメカニズムとは、遺族に対して、故人が死んだことを納得させるのではなく、巫女自身が、ある程度の情報をもとに、それなりに物語をつくって、死者の思い出を語るというのです。それによって、誰もが納得するという働きがあるというのです。こういった物語によって弔いを行っていくというひとつの重要な側面があるとして、川村氏は次のように述べます。
「有名なところでは、『平家物語』です。『源氏物語』ではなくて『平家物語』であるのは、ひとつには、平家の怨霊たち、怨霊になるであろう人たちを弔うものとしてあの物語があったのだろうし、琵琶の語りもあったのだろうと想像されます。
死者を弔う物語は、これまで、おそらく日本全国であっただろうと思われます。弥次さん、喜多さんの場合は、静岡あたりの宿で聞いていたはずです。
『浮世床』では江戸で聞いている。あと、長塚節の『土』という小説は茨城県のほうですが、そこにも口寄せの風景が描かれています」
東北だけではなく、沖縄でがユタが、ミーソグという、あの世の死者を呼び出して話をするという習慣が現在でもあります。川村氏は「霊魂を成長させる文化」というものがあるとして、次のように述べています。
「こういう口寄せもまた、死んだ人を弔う、うまく成仏してもらうために供養する意味があると思います。ある程度の年齢、いわば寿命で亡くなればいいのですが、若いときに亡くなってしまう場合もあります。いま現在も、亡くなった子どもを抱えた親たちは、大変といえば大変です。だいたいの場合、子どもを亡くしたいまの親は、子どもをビデオで撮ったり、写真で撮ったりして、それを見たり、常に飾ったりしている。部屋もそのままにしておく。死んだ子どもは子どものままでしかないと言ったらいいのかな。これが現状で、子どもを亡くした親たちは子どもからなかなか離れることができない。絶えず思い返さざるを得ない。遺品もいっぱい置いてあるということです」
川村氏は、そういった文化に対して、亡くなった子どもたちの霊魂が成長していくという文化もあるようだと述べます。亡くなってから霊魂を成長させていく文化があるのではないかというわけです。寿命が来て亡くなった人ではない場合、すなわち若死にした人の場合は、霊魂を成長させなければ成仏できないという考えがあったのではないかとして、次のように述べます。
「そこで思い出したのは、折口信夫のことです。自分の婿養子といったらいいのか、折口春洋が硫黄島の戦闘で亡くなったのですが、なかなか諦めきれない。戦後間もなく、供養としてだと思いますが、折口信夫は2人の歌集を出しています。
もう1つ、別の話ですが、折口信夫によりますと、いろんな霊は、あの世のある場所において修練しなければいけないと言っています。魂を浄めていかなければいけないと言う。多少間違っているかもしれませんが・・・・・・。
それを助けていくのが、村の若者たちである。村の若者たちは、成人式や盆踊り、念仏踊りのときに、いろんな苦しい修行をして、一緒に共同しながら若くして死んだ人の霊魂を浄め高めていく、と言っていたのではないかと思います。このようにして霊魂を成長させていく文化が、一方にあるのではないかと思います」
わたしは、『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)や『のこされた あなたへ』(佼成出版社)などで、「物語こそはグリーフケアの最大の文化装置である」と書きましたが、「亡くなってから霊魂を成長させていく文化」とはまさにグリーフケアそのものです。
さて、折口信夫といえば、「討議2」でも取り上げられます。山折哲雄氏が「再評価すべき心意伝承の世界」として、以下のように語っています。
「これは、柳田さんにも折口さんにも共通した民俗学的方法の基本だと思いますけれども、みなさんは、民俗社会に伝えられたものはだいたい3つの分野に分けてお考えになっているようであります。目に見えるもの、耳に聞こえるもの、そして、こころで感ずるもの、この3分野です。表現の仕方は、いろいろあったと思いますが。
ところが、近代化の過程で、民俗社会が崩壊していく。そのとき崩壊する主たるものは、目で見えるもの、耳で聞こえるものだった。この分野はどんどん崩壊したり、変化したり、失われていったわけです。
しかし、目に見えない、こころで感ずる世界、すなわち心意伝承の分野だけは、そう簡単には崩れないよということを、お二人とも言っています。その『心意』というのは、無意識層に横たわっている意識と言ってもいいし、その無意識の世界に動機づけられたさまざまな日常的な行動というところまでのばして考えることもできると思います」
戦後の民俗学は、社会科学とかマルクス主義の影響を受けました。そのために、目に見えるもの、耳で聞こえるもの、形あるものに限定した唯物論的な民俗社会の研究が主流を占めたとして、山折氏は次のように語っています。
「そういう心意伝承に立ち入ることは、客観的でない、合理的でない、証明がなかなかしにくいといった観点から避けられてきたような気がしますが、ここまで日本の社会が変化してまいりますと、もしかすると、折口、柳田の言った心意伝承の世界こそ、われわれはもっと大事にしなければならない、再発見していかなければならない、そして再評価しなければならない、そういう時代にいま来ているのではないかと私は思っております」
この山折氏の意見に、わたしは全面的に賛成します。
本書の最後に収められている「論考」も興味深く読みました。鎌田東二氏の『遠野物語』と「古典」をめぐる論考で、「物語」の発生する場所とこころを探っています。
まず、鎌田氏は『遠野物語』が1910年(明治43年)という年に刊行されたことに注目します。1910年はこの上なく物騒な年でした。なぜなら、ハレー彗星が地球に最接近し、日本では大逆事件が起こったからです。鎌田氏は、次のように述べています。
「わたしは、この1910年という年を、世界史のターニング・ポイントの年であったと考えている。その理由は、ハレー彗星の到来により、地球上に初めて世界同時性についてのリアルな意識と地球史的危機意識が芽生え始めた年であるといえるからだ」
さらに、1910年にはさまざまな特筆すべき事件がありました。鎌田氏は、これを「1910年問題」としてとらえ、次のように書いています。
「1910年という年には、『白樺』派の旗揚げ、鈴木大拙訳によるスェーデンボルグ『天界と地獄』の翻訳、東京帝国大学心理学助教授の福來友吉による透視や念写の超能力実験が行われ、『閉塞』状況の内面突破とでもいうべき動きが起こっていた。それは100年前の”スピリチュアル・ブーム”であったといえる。そのような中で、同年に京都帝国大学助教授に転任した西田幾多郎は翌年1月に『善の研究』を出版した。それは『純粋意識』の考察を通して『時代閉塞』の内面突破をはかった試みであったといえよう」
わたしは宮沢賢治によって生み出された奇跡のような霊的宇宙物語をこよなく愛する者ですが、この『銀河鉄道の夜』の原型がハレー彗星であたという以下の指摘には大変驚きました。鎌田氏は述べます。
「盛岡高等農林(現在の岩手大学農学部)時代の宮澤賢治の親友として知られる保阪嘉内は、このハレー彗星を甲府中学の寮があった甲府城付近から見て、『「まるで夜行列車のようだ」と心を躍らせた』という(2010年5月24日付朝日新聞記事)。このとき13歳の保阪嘉内はハレー彗星の飛来の様子をスケッチに描いている。それは、南アルプスの薬師岳、観音岳、地蔵岳の3つのピークをオレンジ色の筋を引きながら飛び越えて甲斐駒ケ岳の山頂の上空に至ろうとする瞬間を描写している美しくも雄大な光景である。ハレー彗星の到来が13歳の少年の心に大きな印象を与え、のちに盛岡高等農林に進学して宮澤賢治と出逢ったとき、同年齢の宮澤賢治にこの図を見せてハレー彗星の体験の神秘を熱っぽく語ったであろうことが想像される。このときの強い印象が種の1つとなって、宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』が構想されていったことも興味深い事実である。保阪嘉内はそのスケッチの中に、『銀漢ヲ行ク彗星ハ 夜行列車ノ様ニニテ 遥カ虚空ニ消エニケリ』と書き入れている。まるで、『銀河鉄道の夜』そのものである」
いやあ、『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」精読』(岩波現代文庫)という著書を持つ鎌田氏だけあって、さすがに鋭い見方をされますね。感服しました。
最後に、鎌田氏は『古事記』が偽書である可能性などに触れます。そして、「古典」について次のように述べています。
「『古典』という制度を疑ってみること、『古典』そのものの価値も内容も疑ってみること。そしてそこからまったく異なる『古典』の異貌を見い出すこと。そんな『古典研究』も必要だし、意味あるものだと考える」
その意味では、100周年を迎えた現代の古典である『遠野物語』を通して、1000年前の大古典である『源氏物語』を読むと、まったく新しい異貌が見えてきたように思います。そして、その二大古典に並ぶほどに、『銀河鉄道の夜』という童話は日本の物語の歴史に残るのではないかと感じました。