- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0534 論語・儒教 『洗脳論語』 苫米地英人著(三才ブックス)
2012.01.25
『洗脳論語』苫米地英人著(三才ブックス)を読みました。
本書は看過すべきと思っていたのですが、あえて取り上げることにしました。いやはや、なんとも奇妙な本なのです。いわゆる「トンデモ本」というやつですか。
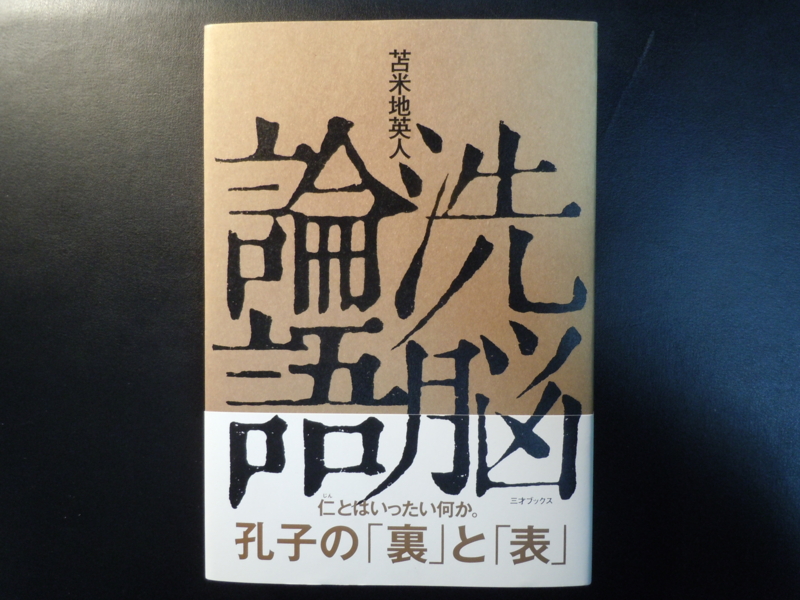
本書は、第1章「儒教と洗脳」、第2章「論語洗脳」、第3章「論語からの解放」といった構成になっています。平たく言うと、儒教は人を区別する教えであり、論語は「人間を奴隷にする洗脳書」であるという内容です。これほど書いてある内容に違和感を持った本は、島田裕巳氏の著書『人はひとりで死ぬ』以来です。
そういえば、島田氏と本書の著者である苫米地氏は非常に親しいとか・・・・・「類は友を呼ぶ」と言いますが、お二人は考え方も似ているのでしょうか。
それにしても、なぜ、論語が「人間を奴隷にする洗脳書」なのか。著者は、まず日本でも日常的に使われている「先生」という言葉に注目します。「はじめに」で、著者は次のように述べています。
「『先生』は、紛れもなく差別を助長する言葉です。
そして、それは儒教教育によるものです。
日本は名目上、階級制度を否定した憲法を基盤とする法治国家なので、子供達に『先生』と呼ばせるのは本当は違憲です。にもかかわらず、現実には堂々と儒教教育がなされています。『先生』という言葉は、相手に権威を意識させます。権威ある者に従属させられる洗脳となります」
なんか、もうこれを読んだだけでも「この人、大丈夫?」と思ってしまいますが、著者によれば、民主主義では、権威からの脱却が1つのテーマとしてあったといいます。そして、これを世界で最初に成功させたのが、アメリカ合衆国でした。アメリカは、イギリスとの戦争を経て独立を果たしました。さらに、万民の平等が保障された国の憲法を制定したことで、脱権威を実現させたというのです。それを踏まえて、著者は次のように書いています。
「これはイエス・キリストがやろうとしたことです。キリストは、権威は神にしかないと言いました。人間は皆平等であり、権威などない、と。しかし、結果としてはこのキリストの願いが叶うことはありませんでした。キリストの死後400年が経ち、ローマ帝国がキリスト教を国教として採用したことで、人間であるキリスト教の聖職者に絶大な権威が生まれ、教皇を頂点としたランク付けのシステムが成立してしまったのです。
釈迦もそうです。釈迦は全ての者を平等として扱いましたが、後の仏教徒の一部には差別のシステムを築き上げた者もいます」
このあたりは、わたしには異論はありません。たしかに、キリストも釈迦も世俗の「権威」を否定し、人間の「平等」を訴えました。
しかし、続いて著者が述べている次の言葉は納得できません。それは、「実は、孔子はキリストや釈迦と違って、始めから差別思想を支持していました。そして、権威中心の『支配の論理』を採用していたのです」というものです。孔子が最重要視した「礼」は、「人間尊重」という意味です。そこには、あらゆる人を人間として尊重せよというメッセージが込められています。もちろん、孔子は目上の者への「礼」を必要としましたが、それがそのまま差別思想に結びつくはずがありません。
著者は、論語を危険な書物であると断じて、次のように述べます。
「論語が私達を輝かしい未来へと導くことはないでしょう。むしろ、逆です。読み方次第で論語は私達の人生を見誤らせる危険な書とさえ言えます。論語を通じて感じることは、孔子は人々に奴隷になることを奨励するため、自分の教えを広めたのではないかということです」
こうなると、もうムチャクチャですが、著者はさらに次のように述べています。
「論語の本質的な役割は『権力者が民衆を支配できるように洗脳する』ことです。
皇帝などの権力者が、民衆をひと所に縛り付けて奴隷にするために利用した、洗脳書とさえ言えるのです。
前半に誰もが受け入れやすい文言を入れておき、後半に本当に言いたいことを入れるのは、論語の1つの定型ですが、これは厳しく言えばカルトの教義にありがちな手法です。『世界平和』や『潤いのある人生を送るために』といった文の後に、多少怪しい文言を挟んでも、読む人はすんなりと受け入れてしまいます。
論語にはそうした『支配の論理』が随所に散見されます。
ですから、論語を鵜呑みにするのは、大変危険と言えるのです」
オウム信者を脱洗脳して有名になったという著者は、「人間は必ず何かに洗脳されている」と断言します。親、教師、友人、マスメディアなど、何者かに洗脳され、束縛されて生きているというのです。そして、日本にとって最も大きな束縛の1つが「論語」なのだそうです。著者は、次のように読者に対して警鐘します。
「本当に心豊かな人生を送りたいのであれば、論語による束縛から解放されなければいけません。そして、論語だけではなく、あらゆるものからも脱洗脳し、一度、本当の自由を獲得しなければなりません」
著者は、昔から論語に非常に注目していたそうです。
しかし、論語が決して「豊かな人生を送るために有用な書」だから注目したのではなく、一般的な解釈の裏に隠されたカラクリについて興味を抱いており、「人間を奴隷にする洗脳書」として危険視しているからだそうです。
著者は「事実、儒教の教えが根付いている現在の日本は、完全に『奴隷の国』と化しています」とまで書いています。まったく理解に苦しむ発言ですが、本書に出てくる「ペーシング」と「リーディング」という手法のくだりは興味深く読みました。著者によれば、洗脳書というのは始めに受け入れやすい文を提示しておいて、次の文に真意を忍ばせているそうです。これは、「ペーシング」と「リーディング」と呼ばれる手法なのだそうですが、著者は次のように述べています。
「出だしに違和感がなければ、全てを受け入れてしまうというのは、人間の持つ心理的性質の1つ。話し手は、まず相手が受け入れやすいように相手の歩調(ペース)に合わせて話を組み立てます。これがペーシングです。そして、それに引き込まれて相手が話し手の考えを受け入れてしまうと、その相手は話し手にラポールを築きます」
ラポールとは、変性意識下で被験者が相手に好感を持つ現象のことだとか。変性意識とは「仮想世界に臨場感がある状態」で、著者は次のように述べます。
「映画俳優や催眠術師がモテるのもこのラポールが作用しています。ラポールが形成されると、話し手は相手を引っ張って(リードして)、変化を引き起こす働き掛けができるようになります。これがリーディングです」
もっとも、「ペーシング」と「リーディング」に興味を持ったからといって、それがそのまま論語に使われているとは思いませんが。
正直言って、著者の儒教理解には重大な欠陥があるように思います。それは、著者の『「生」と「死」の取り扱い説明書』を読んだときに痛感しました。同書で、著者は、「現代において、生と死を考えない宗教はまずあり得ません。その意味で、宗教は死の専門家なのです」と述べています。そして、死者を忌み嫌う日本人に大きな影響を与えた宗教として、仏教とともに儒教を取り上げ、著者は次のように述べます。
「儒教というのは、シャーマニズムです。孔子の母親はシャーマンでした。日本も卑弥呼がシャーマンとして有名です。天皇家ももともとはシャーマンでした」
ここまでは良いのですが、ここから先の発言がちょっと疑問です。
「昔は、政治的リーダーと社会的リーダー、宗教的リーダーが同じでしたから、リーダーである以上、自分の家系が最も尊いという論理を受け入れざるを得ません。あるいは、積極的に利用したのかもしれません。
いずれにしても、シャーマニズムは自動的に先祖崇拝の思想となるのです。
残念なことに、先祖崇拝は儒教という高度に洗練された差別主義を生んでしまいました。シャーマンである国家のトップの先祖が最も偉く、家系を継ぐ権利は明確に規定され、長男が一番で、次男が次、以下、三男、四男・・・・・となります。
シャーマニズムは、あの世の権力もこの世の権力も、両方ともシャーマン個人、あるいはその家系が独占しています。あの世の権力とこの世の権力との区別がありません」
儒教に対する著者の見方は、残念ながら「浅薄」と表現するしかありません。著者の儒教理解の浅さは、『テレビは見てはいけない』(PHP新書)でも感じました。儒教だけではなく、シャーマニズムについても、いや宗教そのものについても著者の見方がいかに偏っているか、次の発言を見ればわかります。
「この世の権力とあの世の権力をはっきりと分けるというのが、近代宗教の大きな特徴です。分けられていないものはシャーマニズムという未開の文化ということになります」
シャーマニズムという未開の文化!このような進歩主義的な宗教観こそ、ユダヤ・キリスト教に代表される一神教的なものです。今時、こんな前近代的な宗教観を堂々と述べる人物がいたとは驚きです。著者は、なんでもチベット仏教を修行した経験があるそうですが、本当でしょうか?
著者に限らず、儒教ほど誤解されている宗教はないのではないでしょうか。多くの人は、高級官僚をつくるための教養を与える宗教であるとしか思っていません。中には儒教は道徳であり、宗教ではないという人もいます。
しかし、儒教くらい宗教らしい宗教はありません。宗教の大きな目的の一つが魂の救済であるとするなら、儒教はそれに大きく関わっています。中国の世界観では、人の魂には「魂(こん)」と「魄(はく)」があるとされます。人が死ぬと、魂は天に昇り、魄は地に潜る。そして、子孫が先祖を祀る儀式を行えば、天と地からそれぞれ戻ってきて再生すると考えられているのです。
中国人にとって最大の不安は、子孫が途絶えてしまうことです。なぜなら、もし子孫が途絶え、先祖である自分を祀る儀礼を行ってくれないとしたら、わが魂と魄は分裂したままさまよい、永遠に再生できないからです。本当の意味で、自分は死んでしまうのです。
ならば、どうすべきか。天下の乱れをなくしてしまえば、そのような事態を未然に防げると考えたのです。人々がみな幸福に暮らしていれば、家が絶えるという不幸な事態も起きないと考えたのです。そこで儒教では、政治を重んじました。正しい政治が行われることによって、生者のみならず死者もが救われるというのが儒教の思想でした。
「儒」という文字にその思想が込められています。後漢の許慎が完成した『説文解字』は最も権威ある文字の解説書とされます。それによると、儒とは「柔なり。術士の称なり」とあり、柔和なことがその意味であるといいます。「武」に対する「文」のようなものでしょう。
また、アメカンムリが入っており、雨に濡れるの「濡」という字に似ています。清の文字学者・段玉裁は、アメカンムリの下の「而」は下に垂れたヒゲであるとしました。乾いたヒゲはごわごわして、あちこちにぶつかります。一方、雨に濡れたヒゲは柔らかくスムーズであり、よって「儒」とは人間が社会でスムーズに生活する教えということになるのです。
儒教が宗教であることの理由はまだあります。
中国哲学者で、儒教研究の第一人者として知られる加地伸行氏によれば、宗教とは「死ならびに死後の説明者」であるといいます。人間にとって究極の謎である死後の説明ができるものは宗教だけです。そして、個人のみならずその民族の考え方や特性に最もマッチした説明ができたとき、その民族において心から支持され、その民族の宗教になるのです。
中国の場合、漢民族に最もしっくりくる「死ならびに死後の説明」に成功したのが儒教であり、儒教のあとに登場する道教でした。そのため、儒教や道教は漢民族に支持され、国民宗教としての地位を得たのです。仏教は漢民族の支持を得られなかったため、中国では確たる地位を得ることができず、ついには国民宗教となることができなかったのです。この3つの宗教の死生観を見てみると、仏教には「輪廻転生」、道教には「不老長生」、儒教には「招魂再生」というコンセプトがあります。
仏教は生死を超えて「仏」になろうとします。道教は生死を一体化して「仙人」になろうとします。そして、儒教は生きているときには、「聖人」になろうとし、死後は祖先祭祀によって生の世界に回帰するわけです。
さて、本書『洗脳論語』に戻りましょう。
トンデモ思考が炸裂している本書で、おかしな点を指摘していたらキリがありません。そこで、超おかしい以下の2つの解釈を紹介したいと思います。
まず、「林放礼の本を問う。子曰く、大なるかな問いや。礼は其の奢ならんより寧ろ倹せよ。喪は其の易ならんよりは寧ろ戚せよ、と」いう言葉です。この言葉の解釈が、本書の143ページに以下のように掲載されています。
「弟子の林放が礼について尋ねた時の孔子の答えです。
孔子は『それは重要な質問だ。礼は、豪奢にするのではなく、控えめにするのがよい。葬式は形だけではなく、心から哀悼の意を持って行うべきである』と言っています。
これはつまり、礼においてはお金が問題ではないということです。
お金ではなく心の問題だと。
そのまま受け取ればいい言葉です。でも、もともと儒教の葬式は式次第が細かく規定され、お金をかけて盛大に行われます。それが儒教における本来の礼です。
また、気になるのは、孔子が弟子の問いに対して『よい質問だ』と褒めている点。論語を通して私が感じたのは、孔子が何かを褒めるのは答えに窮している時ということです。もしかしたら、孔子は誰かの葬式に訪れた際、持ち合わせがなく、香典を払えなかったのではないでしょうか。それを林放に突っ込まれたので、お金ではなく、心の問題だと切り返したのかもしれません」
また、「己の欲せざる所は、人に施すこと勿かれ」という有名な言葉があります。この言葉の解釈が、191ページに次のように書かれています。
「『己の欲せざる所は、人に施すこと勿かれ』というのは、簡単です。
『己が欲しいもの』とは、『自分(=あなた)が欲しいもの』ということ。
『人に施す』とは、『私(=孔子)に施しなさい』ということです。
また、あの世の論理ではなく、この世の論理で解釈すると、施すのは『お金』です。
この文ではそこまでは言及していませんが、『あなたが欲しくないものを私(孔子)に与えるな』と言うことで、自分が欲しいと思うものを孔子に渡しなさいという間接的な物言いをしているように考えられます」
いかがですか、このような論語の解釈がありえるでしょうか? 著者自身の拝金主義を孔子に重ねる姿は、ほとんど妄想の世界です。著者はよく、自身の著書で「スコトーマ」という言葉を使います。思い込みによって、真実の姿が見えなくなるといったような意味ですが、著者こそスコトーマから脱却することが必要ではないでしょうか。
わたしが、本書で最も違和感を感じた箇所を最後に紹介します。著者は、本書の第3章「論語からの解放」の終わりで、次のように述べています。
「日本の小学校教育に『道徳』が入っていることは、明らかに違憲です。
日本は法治国家を謳っています。法治国家とは、法律を判断の基準として設け、それに従う国です。誰でも悪いことをすれば刑法に則って裁きを受けますし、争いが起きれば法に則って対処します。物事の善悪は、法律以外で判断してはいけません。
しかし、道徳というのは、法とは別の判断基準を設けることです。法律的には悪いけど、道徳的には決して悪いとは言えないという、法とは違う判断基準が植え付けられます。
しかも、道徳は宗教です。儒教、道教の流れを汲んだ価値観である以上、宗教を教えることになります。私立小学校であれば問題ありませんが、公立の小学校での宗教教育は憲法で禁止されています。儒教を教えたければ、ミッション系や仏教系のように、儒教系の私立小学校を設立すればいい。公立で、しかも科目として導入されているのは、明らかな憲法違反です」
この文章を読んで、みなさんはどうお考えになりますか?
わたしは、ここ数年、「礼と法について」という講演を若い司法修習生の方々に行っています。講演の最後に、わたしは「法律的には許されても、人間として許されないことがある」と述べました。
酒気帯び検査を切り抜けたからといって、飲酒運転は絶対に許されません。相手が泣き寝入りしようが、セクハラを許してはなりません。いくら証拠がなくても、ウソを言って人を騙してはなりません。結局は、法律とは別に「人の道」としての倫理があり、それこそが「礼」なのです。
現実世界における法律の影響力は絶大です。しかし、大切なのは「礼」と「法」のバランス感覚なのです。これから「こころ」が育っていく小学生にとって「礼」を教える、すなわち道徳教育が必要なのは当たり前ではありませんか。これ以上、子どもたちに道徳を教えなくなったら、この国はいったいどうなってしまうのでしょうか。
おそらく、著者は本書の内容を本気で信じてはいないのではないでしょうか。親友の島田裕巳氏と同じく、本を売るために意図的に奇異な発言をしているようにも思えます。その意味で、本書はもうひとつの『葬式は、要らない』かもしれません。
しかし、本を売るという商業主義=拝金主義のために聖なるもの、すなわち孔子という聖人や論語という聖典を貶めることは許されません。
もともと『論語』のみならず、『聖書』にしろ『コーラン』にしろ、偉大な聖典というものは読む者の心に多大な影響を与えます。尋常ならぬ影響力を人心に及ぼすから聖典なのだと言ってもよいでしょう。それに「洗脳」という負のレッテルを貼ることは納得できません。
著者は権威に屈しないことを矜持とされているのなら、また聖典というものをリスペクトする心がないのなら、次は『洗脳聖書』いや『洗脳コーラン』でも書かれてみてはいかがですか? もし、本当に『洗脳コーラン』を書いたら、わたしは著者を認めましょう。
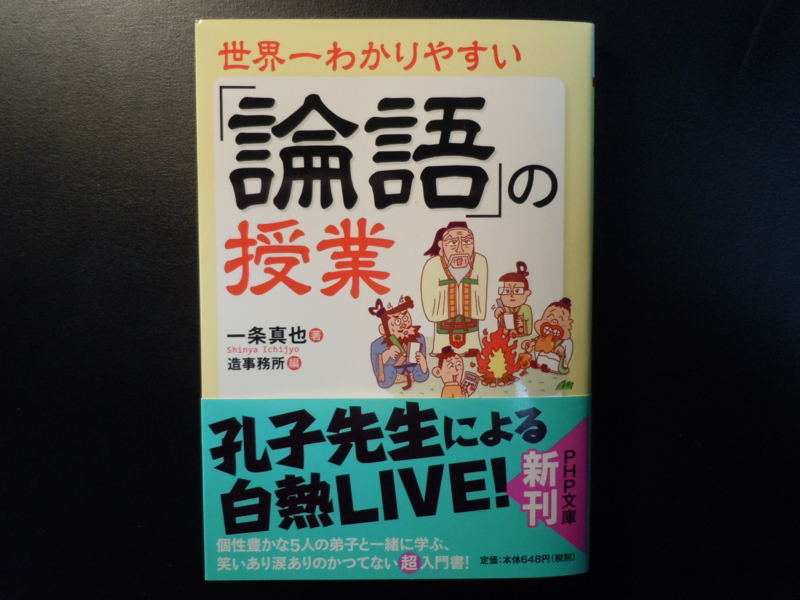
わたしは、『世界一わかりやすい「論語」の授業』(PHP文庫)という本を書きました。論語は、孔子とその弟子の言行を弟子たちがまとめた書物です。
孔子は、紀元前551年、現在の中国に生まれました。同じ聖人であるブッダとほぼ同時代の人で、ソクラテスより80数年早いですね。千数百年にわたって論語は、わたしたちの祖先に読みつがれてきました。
意識するしないにかかわらず、これほど日本人の心に大きな影響を与えてきた書物は他に存在しません。とくに江戸時代に徳川幕府が儒学を奨励するようになると、必読文献として、武士階級のみならず、庶民の間にも広く普及しました。
論語には、「君子」という言葉が多く登場します。初めは地位のある人を、後に徳のある人を指す言葉になりました。君子は、いわゆる最高の人格者である聖人とは異なります。あくまで現実社会に存在する立派な人格者で、生まれつきなれるものではありません。論語の憲問篇に「君子は上達す」とあるように、努力すれば達しうる境地、それが君子なのです。
儒教とか君子とかいうと、孔子には堅苦しくストイックな印象があるのかもしれません。でも、孔子は大いに人生を楽しんだ人だと思います。なにしろ、酒を飲み、きれいな色の着物を好み、音楽を愛した人でした。論語には「楽しからずや」「悦ばしからずや」といったポジティブな言葉が多く見受けられます。仏典や聖書には人間の苦しみや悲しみについては出てきても、楽しみや喜びなどはまず見当たりません。この点、論語にポジティブな言葉が多いのは、本当にすばらしいことだと思います。
また、論語に出てくる孔子は完全無欠な聖人としてではなく、血の通った生身の人間として描かれています。そして、孔子は何よりも偉大な先生でした。論語の魅力、孔子の実像を知るためにも、拙著『世界一わかりやすい「論語」の授業』をぜひお読み下さい。