- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2012.01.15
『茶の本』岡倉覚三著、村岡博訳(岩波文庫)を再読しました。
岡倉覚三は、「岡倉天心」という名のほうが有名でしょう。そう、この読書館で紹介した名著『東洋の理想』の著者です。
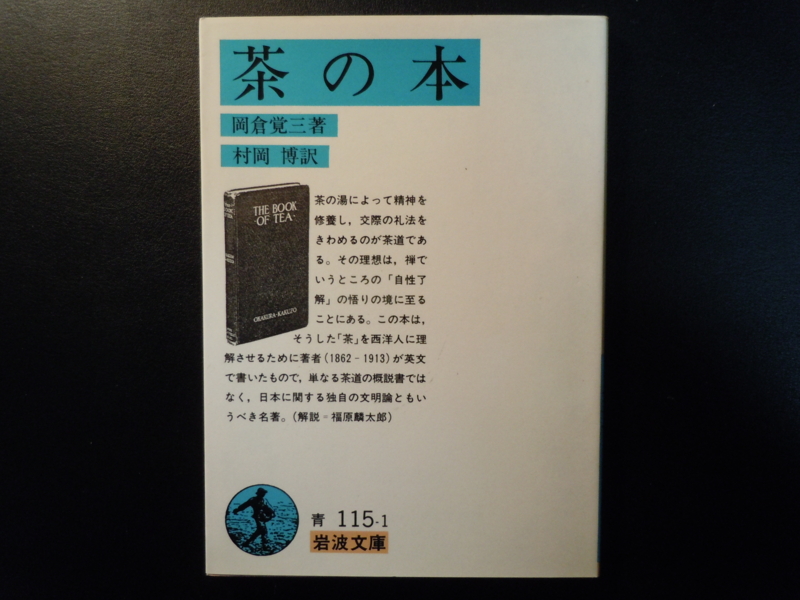
茶の湯によって精神を修養し、交際の礼法をきわめるのが茶道です。それは、「ジャパニーズ・ホスピタリティ」とも呼べる高度な文化と言えるでしょう。
本書は、けっして単なる茶道の概説書ではありません。日本についての独自の文明論として著者が英文で書いたものです。
本書の第一章「人情の碗」は、次のような格調高い文章で始まっています。
「茶は薬用として始まり後飲料となる。シナにおいては八世紀に高雅な遊びの一つとして詩歌の域に達した。十五世紀に至り日本はこれを高めて一種の審美的宗教、すなわち茶道にまで進めた。茶道は日常生活の俗事の中に存する美しきものを崇拝することに基づく一種の儀式であって、純粋と調和、相互愛の神秘、社会秩序のローマン主義を諄々と教えるものである。茶道の要義は『不完全なもの』を崇拝するにある。いわゆる人生というこの不可解なもののうちに、何か可能なものを成就しようとするやさしい企てであるから」
茶は、現在のインドと中国の国境上にあたるヒマラヤ東部の山林地帯が原産地とされています。カメリアシネンシスという椿科の常緑樹の葉、芽、花を乾燥させ、これを煎じて飲むのです。最初は、飲み物というよりも、薬や食材でした。
茶はまず、中国で普及します。中国の神話によれば、最初に茶をたてたのは神農とされています。紀元前28世紀から紀元前27世紀に君臨したと言われる、伝説上の第二代皇帝です。初代皇帝は火と調理と音楽を見つけたと言われていますが、神農は農業と鋤を人々に教え、薬草を発見したことで知られます。
伝説では、神農が飲み水を沸かしているときに、自生の茶の枝を火にくべていると、突風が吹いて茶の葉が何枚か鍋の中に落ち、偶然に繊細かつすっきりとした味わいの飲み物ができたのだそうです。もちろん、これは、あくまでも伝説です。
茶がいつ、どのようにして中国で普及したのかは不明です。でも、どうやら仏教僧の働きによるものだったことは間違いないようです。
仏教僧に限らず、道教僧も、茶は集中力を高め、疲れを吹き飛ばしてくれることを知っていました。茶に含まれるカフェインの効能ですが、そのため茶を飲むことが瞑想をする上で大変有益であると気づいていました。
かの老子は、茶は不老不死の霊薬に欠かせない材料であると信じていたそうです。その道教の徒である陸羽という人物が八世紀に登場し、『茶経』を著しました。茶は4世紀までにはかなり一般化していましたが、中国史において黄金時代を迎えるのは陸羽の活躍した唐の時代です。唐において、茶は中国人にとって国民的な飲み物となったのです。
陸羽こそは茶を喉の渇きを癒すための単なる飲み物から、文化のシンボルへと変えた人物でした。彼の登場後、中国では茶の味がわかり、これを愛でることが評価されるようになりました。とりわけ、茶葉の種類の違いを見分けられることが高く評価されました。茶を入れることは、一家の主にのみ許された名誉あることであり、上手に優雅な作法で入れられないのは恥とされました。
王朝では、茶を中心とする会や宴が人気となりました。皇帝は特定の泉から取ってこさせた水で入れた特別な茶を飲み、これが後に特別な茶を「年貢」として皇帝に納めるという伝統につながってゆくのです。
その後、茶の人気は宋の時代も続きましたが、13世紀に中国人がモンゴルの支配下に入ると、茶の文化は一気に衰退します。反対にモンゴル人が排斥され、明朝が起こると、中国文化再評価の機運が生じて、その流れの中で茶の人気は再燃します。
陸羽が唱えた茶の作法はますます複雑化し、より入念かつ詳細な手順が良しとされるようになりました。もともと宗教的な飲み物であった茶は原点回帰を果たし、茶の文化は一種の宗教的次元にまで高められました。
こうして茶は肉体のみならず、精神をも癒す飲み物としての地位を獲得したのです。
しかし、茶の文化を極めた地は日本でした。 日本人は六世紀頃からすでに茶を飲んでいましたが、茶の栽培と茶摘み、茶の入れ方や飲み方に関する本格的な知識が中国から入ってきたのは12世紀のことです。
伝えたのは、臨済宗の祖である栄西でした。彼は茶の健康効果を讃える書も著しており、茶はヘルシー・ドリンクとして認められたわけです。栄西は、自分で育てた茶によって源実朝の病を癒し、それ以降、実朝は茶を大変好むようになったとされています。
そして、茶の人気は将軍家から日本全国へと広がってゆきます。14世紀にはすでに、日本社会の全階層に浸透していました。日本の気候は茶の栽培によく適していたのでしょう。かなり貧しい家でさえ、茶の木を何本か育てていたといいます。必要なとき、葉を1、2枚摘んで、茶を入れるためにです。
日本における茶の文化は、「茶道」として芸術の域にまで高められました。茶道は単に一定の作法で茶を点て、それを一定の作法で飲むだけのものではありません。実際は、宗教や哲学、茶道具や茶室に置く美術品など、幅広い知識や感性が必要とされる非常に奥深い総合芸術なのです。栄西が日本に茶を伝えた事実からも明らかなように、茶道はまず、禅と深い関わりがあります。
禅宗は「今をどう生きるか」を説く仏教の一派ですが、茶道には禅の精神が随所に生きています。いや、むしろ禅の思想が茶道の根本にあると言ってもいいでしょう。かの千利休をはじめとした偉大な茶人はすべて禅の修行者でもありました。人は茶室の静かな空間で茶を点てることに集中するとき、心が落ち着き、自分自身を見直すことができます。
茶の本質が内に向かう飲み物であることは、茶室を考えてみればよくわかります。茶室は狭い空間です。縮みの空間をつくり出すところに、その美学があったと言えます。室内装飾の簡素化と、その空間を縮小しようとしたことから、「わび」や「さび」といった茶の新世界が出現したのです。
コロンブスは広い海の彼方に新大陸を発見しましたが、茶文化のコロンブスであった村田珠光は、逆に書院座敷を四畳半に区切り、その空間を屏風で狭く囲った瞬間、新しい別の宇宙を発見したのです。そして、より簡素化された草案茶室を完成させた千利休は、四畳半茶室にさらなる「縮み」のベクトルを導入しました。三畳、二畳、ついには一畳台目という極小空間に至り、それを利休は理想の茶室としたのです。
利休によって、茶はさまざまな心的情報を与えることが明らかになりました。
まず、茶室で茶を飲むと人は「平和」になります。
かつては武士といえども必ず刀を預けてから茶室内に入りました。武器ほど茶室に似合わないものはありません。茶室で点てられる、もてなしの茶は主人自身がみんなが一部始終を見ている前で点てられました。
このことは重要です。それまでの茶は、殿中の茶と呼ばれるものでした。
つまり宴会の料理と同じで、別の部屋で点てた茶、作った料理が」運ばれてきたのです。それだと、こっそり毒を入れたものが運ばれてくるかもしれません。殿中の茶を飲むことは、大変な不安や不信感を伴うものだったのです。
そんな不安や不信感を拭い去る画期的な作法こそ、主人自らが抹茶を取り出し、それを茶碗に入れて点てるという点前(だったわけです。
そしてその主人の点てた濃茶は、みんなで廻し飲みされました。この作法は茶に毒が入っていないこと、すなわち安全が保障された飲み物であることを確認することでした。人間の相互不信を解消し、逆にそのまま相互信頼の関係をつくってゆく、茶室はまさに平和な空間に他なりませんでした。
また、茶室で茶を飲むと人は「平等」になります。先に紹介した廻し飲みというのも、平和を実現するとともに、すべての人を平等に扱っているわけです。そもそも茶室の中における主人と客人との関係は、主従関係を離れた対等の関係でした。
そこでは、身分の差を超えて、あくまで個人対個人の関係だったのです。近代民主主義の時代ならともかく、身分制と主従関係を基本として構成されている前近代社会の中にあって、このような人間関係が茶室の中で実現したことは奇跡的でさえありました。
さらに前衛芸術家としての利休は、偉大な心理学者であり、一流の空間プランナーでもありました。茶室には、露地、中門、飛石、蹲踞、躙口といった、利休が張りめぐらせたさまざまな仕掛けを見つけることができます。そこでは天下人も富豪も、他の人々と同じ歩幅で敷石を踏み、必ず頭を下げなければ中には入ることができませんでした。中に入った後も、狭い空間ゆえに互いに正座して身を寄せ合わなければなりません。茶室では、すべての人間が平等となるのです。
さらに茶は、21世紀における心ゆたかな社会、つまりハートフル・ソサエティの到来に深く関わっています。ハートフル・ソサエティとは人間の心が最大の価値を持つ社会ですが、そこでは「ホスピタリティ」が一番のキーワードになります。
サービス業界を中心に「ホスピタリティ」の重要性がいたる所で叫ばれています。もともと、茶道の世界は「ジャパニーズ・ホスピタリティ」そのものでした。すなわち、きわめて密度の濃い「もてなし」の文化だったのです。茶は単なる飲料ではありません。ただ、ペットボトルで飲めばよいというものではない。茶には「もてなし」の心が欠かせないのです。
茶で「もてなす」とは何か。それは、最高のおいしいお茶を提供し、最高の礼儀をつくして相手を尊重し、心から最高の敬意を表することに尽きます。
そして、そこに「一期一会」という究極の人間関係が浮かび上がってきます。人との出会いを一生に一度のものと思い、相手に対し最善を尽くしながら茶を点てることを「一期一会」と最初に呼んだのは、利休の弟子である山上宗二です。「一期一会」は、利休が生み出した「和敬静寂」の精神とともに、日本が世界に誇るべきハートフル・フィロソフィーであると言えるでしょう。
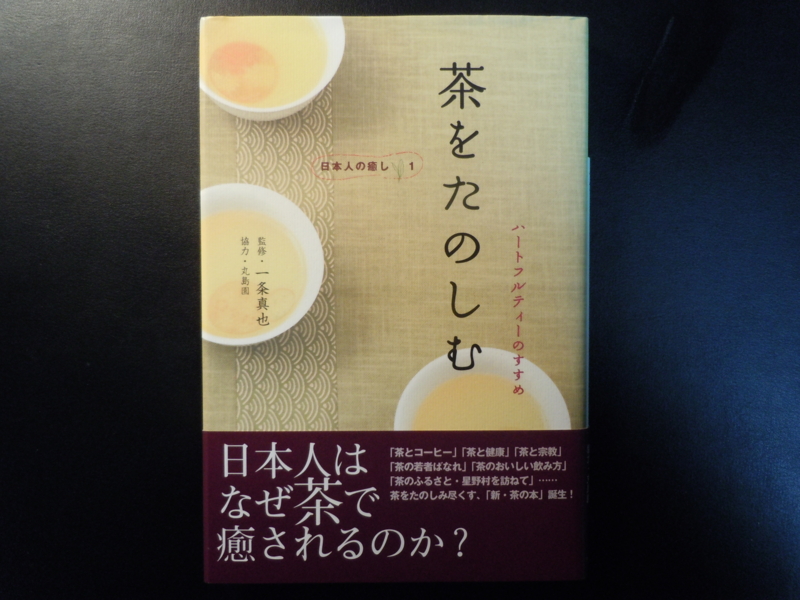
また、家庭においてもリビングルームはあっても、いわゆる「茶の間」が消えつつあると言われています。日本の茶の間とは、母親が入れてくれたお茶を飲みながら、家族が互いを思いやり、気づかい、いたわり、何よりもつながり合う空間でした。家庭という共同体がドロドロと溶けてゆく中で、茶の間の復活が必要なのではないでしょうか。
このように、茶室における「もてなし」の茶にしろ、茶の間における「つながり」の茶にしろ、茶とは良い人間関係づくりというものに徹底的に関わっているのです。
わたしの会社のミッションは「冠婚葬祭を通じて、良い人間関係づくりのお手伝いをする」です。茶は、まさに冠婚葬祭に代表されるヒューマン・コミュニケーションのシンボルに他なりません。わたしたちは、これからも茶を飲みながら、広くホスピタリティの提供に努めていきたいと思います。そこから「天下布礼」が始まるのです。
わたしは、偉大なる『茶の本』へのアンサーブックとして、『茶をたのしむ』(現代書林)を書きました。ご一読いただければ幸いです。
