- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0396 オカルト・陰謀 『陰謀論にダマされるな!』 竹下節子著(ベスト新書)
2011.07.28
『陰謀論にダマされるな!』竹下節子著(ベスト新書)を読みました。
巷にあふれる終末論と陰謀論。それらがいかに生まれたかのルーツを紐解きながら、 実社会にどのような影響を与えているかを述べています。さらには、終末論や陰謀論との賢い付き合い方を示した本です。
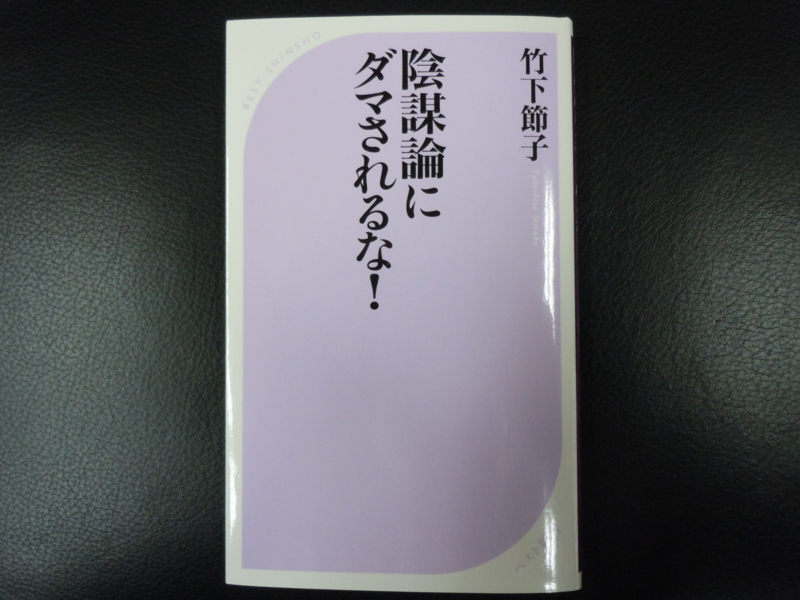
著者はフランス在住の比較文化史家で、バロック音楽奏者でもあります。東京大学大学院比較文学比較文化修士課程修了。同博士課程、パリ大学比較文学博士課程を経て、高等研究所でカトリック史、エゾテリズム史を修めています。現在、ネットなどのサーバー空間において、終末論や陰謀論が肥大化する一方です。まるで、情報が飽和する中で、個人の不安や恐怖を養分としているかのようです。
陰謀論の主役を見てみると、フリーメイスン、イルミナティ、ユダヤ人、ヴァティカン、アメリカ政府などが繰り返し登場していることに気づきます。これらの面々は、いろいろな組み合わせで再利用され、便利に使いまわされます。時には互いに陰謀論を投げかけ合い、やがて、そこに擬似科学を駆使した陰謀論が入り込んでいくという構図になっています。
最初は、事件の解説型陰謀論として生まれ、やがて、メガ陰謀論、終末予言型陰謀論へと進化する。アポロの月面着陸、9・11同時多発テロのケースなどが好例ですね。キリスト教を中心とした西洋思想史に精通した著者は、本書で、いわば「陰謀論の仕分け」に挑みます。もちろん、無数の陰謀論と終末論を前にして、伝統的な知性による取捨選択は容易ではありません。しかし、それでもなお、著者は「世界は悪意に支配されている」という考えへの対処の仕方を前向きに説きます。
本書の目次構成は、以下のようになっています。
プロローグ―人はなぜ陰謀論と終末論にはまるのか
第1章 終末論はいかにして生まれたか
第2章 グローバル化する現代の終末論・陰謀論
―陰謀論カフェ「ティーパーティ」にて・その1
ティータイム 『ダ・ヴィンチ・コード』の嘘?
第3章 陰謀論はいかにして生まれたか
第4章 陰謀論の心理学
―陰謀論のカフェ「ティーパーティ」にて・その2
エピローグ―終末論の見分け方と陰謀論の仕分け方
「プロローグ―人はなぜ陰謀論と終末論にはまるのか」の冒頭において、著者は次のように書いています。
「一部の人やマニアのものだった陰謀論や終末論は、20世紀の末ごろから大衆文化のテーマの1つとしてなじみ深いものとなった。さらに、21世紀の初頭の米国同時多発テロと『テロとの戦い』の始まり、地球規模の環境破壊への国際的対策が推進される様子、加えて、金融危機と不景気などを養分とするかのように、陰謀論と終末論は互いにリンクしながら単なるサブカルチャーの域を超えて広まっている」
陰謀論や終末論とは、いったい何なのか? 著者は、時代の文脈で読むべき特異現象、特定の文化や宗教や伝統との結びつき、あるいは人間性と結びついた普遍的なものである可能性などを考慮しつつも、その本質に「物語」の存在を見ます。そして、著者は次のように述べています。
「私たちの生きている世界は、いうまでもなく多様で複雑な世界だ。小さい共同体の中で一生過ごせた時代とも違って今は、情報量も多いし、実際に目にする事物も伝統的な思考で分類したり処理したりできるものは少ない。いわゆるポスト・モダンの時代は、この多様性が市民権を得て、マイノリティに光が当たったと言えば聞こえはいいが、それまで多くの人が生きる指針にしてきた『大きな物語』が消えた不安定な時代でもある。その結果、人は個人的で小さな物語をばらばらに生きるようになってしまった」
「小さな物語」とは、たとえば、どんなブランドの何を買うかという消費行動によってアイデンティティを得ようとしたり、精神世界の修行や健康法を渡り歩いて「元気で長生き」を人生の目標にしたり、「本当の自分」を探したり「自己実現」を夢みたりすることなど。
中には、自分の物語を完成することができずに命を絶ってしまう人も多いのです。著者によれば、「個人」が分断され委縮していく過程と、陰謀論や終末論が肥大していく過程とは連動しているといいます。陰謀論や終末論とは、失われた「大きな物語」の影なのかもしれません。著者は、終末でなく「終末論」は問題であり、陰謀ではなく「陰謀論」が問題であると訴えます。さらに、そこに「死」という視点を持ってきて、著者は次のように述べます。
「私たちは自分がいつか死ぬことを『知っている』。けれども死がいつどのようにやってくるのかは分からない。その実存的な不安は、昔は宗教や民族や家族の大きな物語の中に組み込まれていた。けれども、今や分断されて『自己実現』や『自立』を期待される個人の人生プランの中で、死は想定されていない。だとしたら、個々人から疎外された『私の死』が、『世界の終わり』に投影されているのだろうか」
「私の死」や「世界の終わり」は、その時期と状況をあらかじめ知ることはできません。著者は、その「不可知」を逃れたり拒否したりするのが、自死であり、終末予言であると言うのです。すなわち、終末予言とは自死のメガ・ヴァージョンであるというわけです。
著者は、「大きな物語」の喪失が陰謀論や終末論を生んだと主張します。そして、「プロローグ」の最後で次のように述べています。
「大きな物語も、自由も、尊厳までも失ってしまった人々は、たったひとりで陰謀論や終末論を消費して、よくできた小さな物語の中に避難するのだ。けれどもそれは見せかけの安心にすぎない。世界を分かりやすく陰謀論に還元したり終末論で収束させたりしてしまうのは、本当は、思考の停止だ。いのちを停止させる自死も、死もその一部である複雑系の多様な世界の中で、他者といのちを分け合いながら生きていく力を放棄する時に選ばれる」
では、わたしたちは、どうすればいいのでしょうか。著者は、「陰謀論や終末論から、距離をとってみることだ」とシンプルに説きます。なぜなら、いまや陰謀論や終末論は「表の世界」や「正論」と区別のつかない状態に入り組んで混ざっていたり、時代を覆う空気として定着していたりしているからです。
さて、著者はキリスト教の造詣が深いことで知られています。第1章「終末論はいかにして生まれたか」で、そのあたりの知識が大いに生かされています。著者は、第1章の冒頭で「終末論は一神教から生まれた」と断言した上で、次のように述べます。
「現在、人類の3分の1が宗教文化の基礎にしている一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)は、奴隷状態や捕囚状態を経験して荒野の民族大移動を強いられたユダヤ民族の民族神が進化して成立したものだ。一神教の神は人型の神でもなく、動物や自然物や自然現象に託された神でもなく、名前すらない抽象的な万物の創造主だ。この神は、時折なす啓示によって意思を表明するが、その真意や長期的な意図は、被創造物にすぎない人間には完全に理解できるものではない。確かなのは、人間を含む世界が、創造神によって創られたのだから、『始まり』があったと言うことだ。初めもなく終わりもない『無限』は神だけであり、被創造物はすべて、神の意志によって終末を迎える。『始まり』のない世界には終末論も芽生えようがない」
一神教が、多くの多神教の宗教やアニミズムなどと違う点とは何か? それは、人間と人間を取り巻く世界である「自然」を「神の被造物」という同じカテゴリーに入れたことが最大のポイントとなります。一神教が登場する以前の世界はそうではなかったとして、著者は述べます。
「そもそも、ヒトは他者の死を意識し、自分の死を想像し、死後の世界に思いをめぐらせる唯一の動物だと言われていて、埋葬儀礼や死生観の登場がそもそもヒトの特徴となっている。人生に始まりと終わりがあり、肉体が一度朽ちると戻ってこないという不可逆性の認識はヒトにとって普遍的なものだ。同時に、そのヒトの有限さと比べて、少なくとも数世代にわたる観察によって、自然の不変性や循環性が、無限とか永遠とか悠久という概念をヒトにもたらした。一神教以前の世界では、自然には始まりも終わりもなかったのだ」
著者のこの発言には、非常に共感しました。「埋葬儀礼や死生観の登場がそもそもヒトの特徴となっている」というくだりなど、わたしの考えとまったく一緒です。そう、人間とは「葬儀するヒト」としての「ホモ・フューネラル」なのです。
さて、一神教から生まれた終末論は、これまでに多くの「世界の終わり」のイメージを人々に与えてきました。本書を読むと、じつに多くの「世界の終わり」の日が予言され、ことごとく何事も起こらずに「その日」が過ぎ去ってきたことがわかります。著者は、次のように述べています。
「大局的に見れば、ヨーロッパにおいて予告された『世界の終わり』の特定は、フランスの歴史作家ジャン・マリーがリスト・アップしたものによると多数に上る。2012年12月21日の日付は、キリスト教成立以来、よく知られたもののうちで183番目に当たる。キリスト教の根幹には神の国の到来を「期待」する神学がある。それに基づいて予感される世界の終わりが恐怖を煽るペシミスティックなものである限り、キリスト教社会は、平均して10年に一度は『世界の終わりの予告日』を生き延び続けたわけで、世界とは、いつも、予告された終わりと終わりとの間、なのである」
いま、最も旬な「世界の終わり」は、何と言っても、2012年でしょう。すっかり知名度の上がったマヤ暦が、2012年を世界の終わりとしているのです。
この2012年終末説は、アメリカのニューエイジ系の4冊の書物によって少しずつメジャーになってきました。最初は、1975年にSF作家フランク・ウォータースが『神秘のメキシコ』の中で、マヤ暦の大きなサイクルが2011年12月24日に終わると書きました。マヤ暦は20進法で、360×20=7200日が1カトゥンで、20カトゥンが1バクトゥン、13バクトゥンが1サイクルだというのです。
同年に、デニス・マケンナとテレンス・マケンナが、『不可視の風景』でこの日付を2012年12月21日だと修正しました。冬至における銀河の中心と太陽の黄道のコンビネーションが言及されています。この時点ではまだ先の話だったせいか、あまり広まることはありませんでした。
しかし、1987年にアーティストで幻視系歴史家と自称するホゼ・アグエイアスが『マヤン・ファクター』という本を書きました。アグエイアスは、同書で銀河の中心と太陽と地球と人類をつなぐ光線について書き、平和への瞑想というイベントを世界中に呼びかけました。
さらに、1995年、ジョン・ジェンキンスが著書『マヤ2012宇宙創生記』で、冬至と銀河の中心の直列が、人類のスピリチュアルな進化のチャンスであると説きました。これ以来、マヤの2012年終末説は非常に有名になったのです。
2012年といえば、もう来年ですが、わたしたちの運命はいかに? 「1999年の7月の月に恐怖の大王が降ってくる」というノストラダムスの大予言以来の迫り来る破滅の日ですが、これを無事に迎えたとしても、わたしたちは安心できないようです。著者は次のように述べます。
「たとえ2012年が無事に過ぎても、次には2014年4月10日が終末の日だというカバラの予告が控えているし、その後にも2017年9月9日がある。それはアユルヴェーダ医学のある皮膚科医によると、メキシコ南部のサポテカ文明の1000年前のシャーマンによって予言された終末の日だ。その日には時空に小さな穴があいて、香港の朝食がセントルイスのディナーになり、ヒトラーが給仕するというような混乱が起きることになっている」
終末の日を特定する根拠は、あるときは最新科学であったりします。また、あるときは古代の秘法であったりします。なぜ、最新と古代の相反するものが両方とも登場するのか。それについて、著者は次のように述べています。
「最新科学も、古代の秘法も、『普通の人』にとっては同じようにブラック・ボックスで、呪文と同じ効果を持つのだ。そのハイブリッドな形としては、『古代の秘法=実は宇宙人によって伝えられた現代よりはるかに高度な技術』というものがある。どの場合でも、共通点は、『今ここ』ではないものに根拠を求める心理かもしれない」
これはもう、ロマン主義の特徴そのものですね。終末の日を信じる人々は、ロマンティストなのです。
わたしが興味深く思ったのは、「古代文明の予言」とは西洋文明から見たエキゾティシズムに過ぎないという以下の著者の指摘でした。
「2012年12月21日の『世界の終わり』には、銀河の中心と太陽と地球が一列に並ぶことによる太陽の磁気エネルギーの変化やフォトンの影響で人類の環境が深刻なダメージを受けるという擬似科学的な説明と、古代マヤ文化(地理的にも時代的にも現代のデフォルトである西洋文明からかけ離れている)の暦にそれがすでに予言されていたというエキゾティシズム、さらにそれを補強するような『古代マヤ文明=現代文明よりも優れた宇宙人の文明』説とが複合している。
これに加えて、日本に独特の現象も存在する。
日本で人気の陰謀論や終末予言はいわゆる『欧米』経由のものが多い。『欧米』にとってエキゾティックな『古代文明』の予言についても、日本にとっての『後進国』に隠れていた遺跡を欧米人の学者や冒険家が発見したり解読したりというストーリーが好まれるし、一種の権威づけにもなっているのだ」
著者によれば、さまざまな陰謀論のルーツは欧州発だそうです。それが米国で膨らみ、各国に広がっていくケースが多いとか。いわば、アメリカとは陰謀論や終末論の工場だと言えるでしょう。著者は述べます。
「そのアメリカ的な陰謀論や終末予言が、メディアの国際化のともなって「民主化」し「商品化」して、世界中にマーケットを形成してしまったのが現代の状況である。西洋オカルティズムの文脈のない日本のような国ではなおさら、さまざまなトリヴィアな情報だけが、市場原理によって無批判に導入され配布されては消費されていく。ましてや、『2012』のような大資本商業映画が、そのプロモートのために擬似科学的な終末警告サイトをネット上に巧妙に立ち上げたりするのだから、リアルとヴァーチャルの境界の見分けはますます不確かになっていくのである」
そして、陰謀工場では、さまざまなアイテムの組み合わせが行われます。著者は、次のように述べています。
「フリーメイスン、イルミナティ、ユダヤ人、ヴァティカン、アメリカ政府など、陰謀論に繰り返して登場するこのような面々は、いろいろな組み合わせで使いまわされ、時には当事者同士で陰謀論を投げかけ合いさえした。やがて、そこに、擬似科学を駆使した陰謀論が入り込む。事件の解説型陰謀論から、メガ陰謀論、終末予測型陰謀論へとも進化している。しかし、一時期隆盛を極めた科学系のものは現在やや減る傾向にある。インターネットはもともと大学など研究機関で発展してきたものだけあって、本物の科学者たちは、ウェブ世界に慣れているし常駐しているので、集団で一種の批判精神を発揮したり疑似科学の言説を監視することも少なくないからだ」
本書には「陰謀論カフェ」として、都内某所に2ヶ月に1度行われる陰謀論についての議論の様子が紹介されています。その中に登場する被害妄想などを中心としたセラピストの男性が、次のように陰謀論をわかりやすく整理しています。
「一般に陰謀論の言説の特徴というのは2つありまして、まず、強迫的で反復的なところです。偏執狂(パラノイア)と同じ形態の構造があるんですね。
もう1つの特徴は、『秘密の権力』『見えない力』『地下活動』のように、つかみどころがなく検証のしようのない言葉を連発しながらその論の内部はえらく『自明』なものとして強調されていることです。メカニック時系列がはっきりした因果関係が展開されているのです。擬似科学のようにマニアックに論証されているんです。根本のところが成り立っていないんですけれど」
彼によれば、それは、人間には誰にでもある2つの傾向の2つともに馴染むそうです。 1つは、信仰や非合理なものにすがったり受け入れてしまうという傾向。もう1つは、人間の行為や歴史的事象は論理的であることを求める気持ちです。人間にとって、偶然や運不運といったものは受け入れ難いのです。
「陰謀論カフェ」は、陰謀についてのトリビア的知識の宝庫でした。たとえば、以下の松本清張に関するくだりなど興味深かったです。
「1960年に出て、評判になった松本清張の『日本の黒い霧』を覚えていられると思うんだけど、下山事件など戦後の怪事件はすべて占領軍諜報機関の策謀という話ね。あれなんか、「黒い霧」が流行語になったように戦後抑圧されていた日本人の民族主義の内圧を開放する役割、つまりガス抜きを果たしたと思うんだよね」
「あのころ、三島由紀夫が松本清張を日本の純文学界から爪はじきにしようとした話をご存じかな。三島は松本清張の説を俗で荒唐無稽な陰謀史観だと攻撃したんだ。占領下で自主規制してきた民族主義に飢えた俗耳に快い史観だとね。そういうのを一種の常識にしてしまったから、『アメリカ憎し』の集合無意識が21世紀まで実はだらだら続いているんだと思うがね」
それにしても、陰謀論や終末論というやつは面白いですね。そして、面白いだけに厄介この上ないものです。こんな陰謀論や終末論との付き合い方について、著者は「エピローグ―終末論の見分け方と陰謀論の仕分け方」の最後に次のように書いています。
「無数の陰謀論や終末論を前にして、ほんとうに頼りになるのは『ナンセンスを嗅ぎ分ける嗅覚』であり、ある種のエレガンスである。内容よりもパッションを伝達したり、知っていること以上のことを知らせたり、とりあえずの到達地点を最終最高の場所のように伝えたり、自分の殻に閉じこもって他を切り捨てたり、絶対善や絶対悪を振り回したり、他者との信頼と連帯の可能性を信じることをやめたり、自分よりも相対的に弱い人、小さい者、苦境にある人を見捨てたり抑圧したり尊重の念を欠いたりすることは、いずれも、エレガンスにかける。エレガンスによって、人は他の人や世界との平和な関係性を、少しずつ、育んでいけるのだ」
まさに、「その通り!」と言うしかありません。最後に「エレガンス」という言葉が目に飛び込んできて、なんだか背筋が伸ばされたような気がしました。東日本大震災以来、アメリカによる人工地震説を信じている人がいるそうです。ぜひ、そういう人たちも本書を読んでほしいです。でも、彼らにいくら「陰謀論にダマされるな!」と言っても、「それも陰謀だ!」と言い返されるのがオチですかね?(笑)