- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0237 宗教・精神世界 『国家神道と日本人』 島薗進著(岩波新書)
2011.01.03
『国家神道と日本人』島薗進著(岩波新書)を読みました。
著者は、東京大学大学院教授で、日本を代表する宗教学者として知られています。京都大学こころの未来研究センター教授である鎌田東二先生とは大変親しく、わたしは鎌田先生から著者を紹介していただきました。非常に温厚で、気さくな方です。
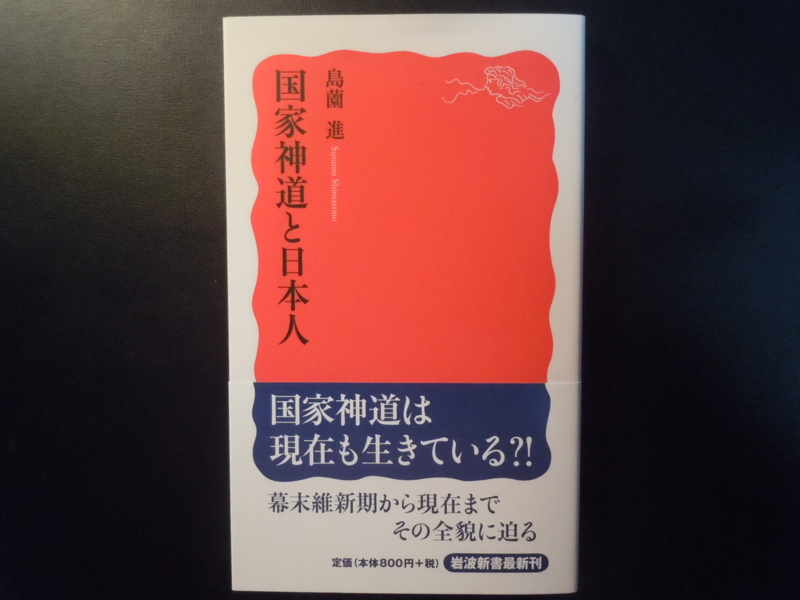
国家神道は現在も生きている?!
著者は、民衆宗教や新宗教を主な研究課題としてきましたが、2000年頃から日本人の「こころ」の謎を探る上で「国家神道」についての関心を深め、研究を重ねてきました。本書は、その研究活動のひとまずの成果であると言えるでしょう。
「国家神道」は戦前の国家主義と結びつき日本人の精神的支柱として機能してきたとされています。太平洋戦争での敗戦により、それは解体し、消滅したのでしょうか。その問いに対して、著者は「否」とはっきり答えます。もちろん規模は格段に縮小しているものの、戦後も国家神道は存続しているとして、次のように述べます。
「戦後の国家神道は二つの明確な座をもっていた。一つは皇室祭祀であり、もう一つは神社本庁などの民間団体を担い手とする天皇崇敬運動である。前者は見えにくい形で隠れているが現存の法制度の中での国家神道の核であり、後者はその核を見据えつつ国家神道的な制度を拡充していこうとする団体や運動体である。さまざまな政治・宗教・文化団体があり、さらに広く国民の間にゆきわたっている天皇崇敬や国体論的な考え方、心情がある。これらに支えられつつ、国家神道は戦後も存続し続けて今日に至っているのだ」
本書は、以下の5つの章から構成されています。以下に「目次」を示します。
第一章 国家神道はどのような位置にあったのか? ―宗教地形―
第二章 国家神道はどのように捉えられてきたか ―用語法 ―
第三章 国家神道はどのように生み出されたか? ―幕末維新期―
第四章 国家神道はどのように広められたか? ―教育勅語以後―
第五章 国家神道は解体したのか? ―戦後―
これに、「はじめに―なぜ、国家神道が問題なのか?」と「あとがき」が付きます。
著者は、「国民国家の時代には国家的共同性への馴致が目指されるが、民衆自身の思想信条は為政者や知識階級の思惑を超えて歴史を動かす大きな要因となる。また、啓蒙主義的な世俗主義的教育が進む近代だが、にもかかわらず民衆の宗教性は社会が向かう方向性を左右する力を持つことが少なくない」という近代史の逆説を紹介した後、これをよく例示するものこそが日本の国家神道の歴史であると述べています。
さらに著者は、神道を神社とのかかわりのみで見るのは狭いとらえ方であるとし、宮中祭祀や天皇崇敬の装置を視野に入れます。そして、明治維新期の国家構想、民間宗教との位相、国民の関与などを丹念に追うのです。日本の宗教および精神史理解のベースを提示する意欲作と言えるでしょう。
本書でまず興味深かったのは、「国家神道」というものの定義についてです。
狭義から広義まで、じつにさまざまな「国家神道」観が存在しましたが、その中で葦津珍彦による定義が注目されます。葦津は、戦後の神道界の立て直しに尽力し、神社新報社の主筆を長く務めた人物です。
彼は、宗教学者の村上重良が著書『国家神道』(岩波新書)で展開した国家神道論に徹底的に反対していました。村上の国家神道論とは、国家神道の主体を神社神道ととらえ、かつ国家神道が強大な力を持ったというものです。これに対して、葦津は1987年に刊行した『国家神道とは何だったのか』(神社新報社)で、国家神道というものを「在野神道諸流」として位置づけます。
在野神道諸流とは、神祇官再興運動を担った人々や、頭山満の玄洋社、内田良平の黒龍会、出口王仁三郎の皇道大本、5・15事件、2・26事件に関与した人々などを指しています。主に、天皇の直接統治により君民一体的な国家の実現を求める皇道主義的な諸集団を念頭に置いているようです。葦津は「国家神道」という言葉を「尊皇」や「敬神」を掲げる精神運動という意味でとらえたと言えるでしょう。
本書を読んで強く感じたのは、このような非常にデリケートな問題を論じているにもかかわらず、著者が終始一貫してニュートラルな姿勢を崩していないことです。岩波新書で国家神道をテーマとする本を出すとなれば、当然ながら批判的な論調の本であると誰もが予想します。読書界には、岩波新書の本が国家神道や天皇制を肯定するはずなどないという認識が厳然としてあります。
しかし、本書における著者に立場は非常にニュートラルなものであり、それは伊勢神宮や靖国神社を説明した箇所からもよくわかります。たとえば、著者は伊勢神宮について以下のように述べています。
「明治維新によって、伊勢神宮は国家神道の中心施設として生まれ変わることとなった。多くの民間人が関わり、地域社会に密着した宗教施設であった伊勢神宮を、祭政一致国家の政府中央と直結した、神聖な帝国施設として生まれ変わらせねばならなかった。明治期には、全国のさまざまな神社が国家施設的な特徴をもつものへと変化するよう促されたが、伊勢神宮の改革はその先頭を切るものだった。天皇家の祖神を祀る神社であるから、それは当然のことと考えられた」
また、著者は靖国神社については以下のように述べています。
「国家神道は仏教やキリスト教や天理教のような救済宗教と異なり、個人の運命に関わり死後の救いを約束したり、苦悩する個々人の魂に訴えかけるというような実存的深みの次元はさほどもっていない。国家神道と諸宗教との二重構造ということの中には、救済や死後の生、あるいは苦悩からの解放といった実存的な問題は私的な領域に本領がある諸宗教に任せ、国家神道は公的な秩序の領域を司るというような分業的な意味合いもあった。ところが若くして死んでいく兵士の運命に関わる靖国神社の場合は、避けがたく実存的な苦悩や癒し・慰めの次元が入り込まざるをえない。人々の心の奥深い部分をも揺り動かす力をもっているという点で、靖国神社は国家神道の中で特別の重みをもつ施設となった」
最後に、当然ながら本書を読んで、わたしは「神道とは何か」ということを考えました。わたしの関心の対象は、あくまで「国家」よりも「神道」にあるからです。
明治維新から教育勅語の発布を経て、日本では「政教分離」と「祭政一致」が両立する制度枠組が確立していきました。国家神道も国民生活に深く浸透するようになりましたが、大日本帝国憲法では「信教ノ自由」を謳っていました。
しかし、実際には国家神道と信教の自由、あるいは思想の自由の間にはせめぎあいがあり、国家神道が信教および思想の自由を脅かす事件が相次ぎました。
特に有名なのは、内村鑑三の不敬事件、久米邦武の筆禍事件、天理教の公認運動の3つです。その中で、わたしは久米邦武の神道論に非常に興味を抱きました。歴史学者として名高かった久米は、1891年に「史学会雑誌」に発表した「神道は祭天の古俗」という論文によって神道を誹謗したとして帝国大学教授の職を失いました。その論点を紹介するために、島薗氏による要約を以下に引用させていただきます。
この論文で久米は、まず敬神崇仏に基づく国体の美風を称揚した上で、独自の宗教論、神道論を展開している。――神道は仏教や儒教のような教説体系がなく、宗教とよぶにたるような論理教説をもっていない。
神道の中核というべき皇室や伊勢神宮の祭祀は、古代的な「祭天の古俗」、すなわち普遍的に見られた共同体祭祀に由来するものだ。日本では「天御中主」とよばれたが、中国では皇天上帝とよばれ、インドでは「天堂」「真如」とよばれたもので、根源は同じものであり、「東洋祭天の古俗」と言えるという。
伊勢神宮は天照大神を祀るとされるが、これは日本独自のものではなく、「東洋祭天の古俗」の一形態で、本来は皇帝が天を祀って統治に当たるものだった。朝鮮からの渡来者の像が記紀の物語に投影されている可能性もある。三種の神器も日本独自のものではなく、「祭天の神座を飾る物」だったはずだ。神道は「祭天」、つまりは天を祀る共同体の祭祀であり、地祇(土地の神)や人鬼(死者の霊)を祀るものではなく、神社は「古時国県の政事堂」だった。そもそも祭天は人類が原始時代に神というものを考え出したのに由来するが、神道においてはそこから儒学や陰陽道や仏教が流入したのであるから、神道だけに頼ろうとするのは賢明ではない。久米の論点はおおよそ以上のようなものだった。(『国家神道と日本人』45-46頁)
この島薗氏の要約を読む限り、わたしには久米邦武の主張はまったく正しいとしか思えません。何よりも神道を誹謗したなどというレベルを超え、神道が日本人だけのものではなく、広く人類全体に関わる宗教であることを喝破しています。
ネイティブ・アメリカンの人々が信じるグレート・スピリットとは、わたしたち日本人にとっての八百万の神々と同じです。 まさに神道というのは日本だけでなく、この地球上に偏在するものなのです。かの折口信夫が太平洋戦争での敗戦時に述べた「人類教としての神道」という言葉も、おそらくはそういった意味であると思います。
わたしには、久米邦武が折口信夫や鎌田東二の先達であったと思えてなりません。彼の神道観には、比較宗教学的視点というか人類的視点があります。
今後、機会があれば、久米邦武という歴史学者について調べてみたいです。