- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0199 メディア・IT 『ネット・バカ』 ニコラス・G・カー著、篠儀直子訳(青土社)
2010.10.16
『ネット・バカ』ニコラス・G・カー著、篠儀直子訳(青土社)を読みました。
タイトルにインパクトはありますが、いささか扇情的な印象もあります。サブタイトルは「インターネットが わたしたちの 脳にしていること」で、帯のキャッチコピーが「『グーグル化』でヒトはバカになる」です。大体の内容がわかりますね。
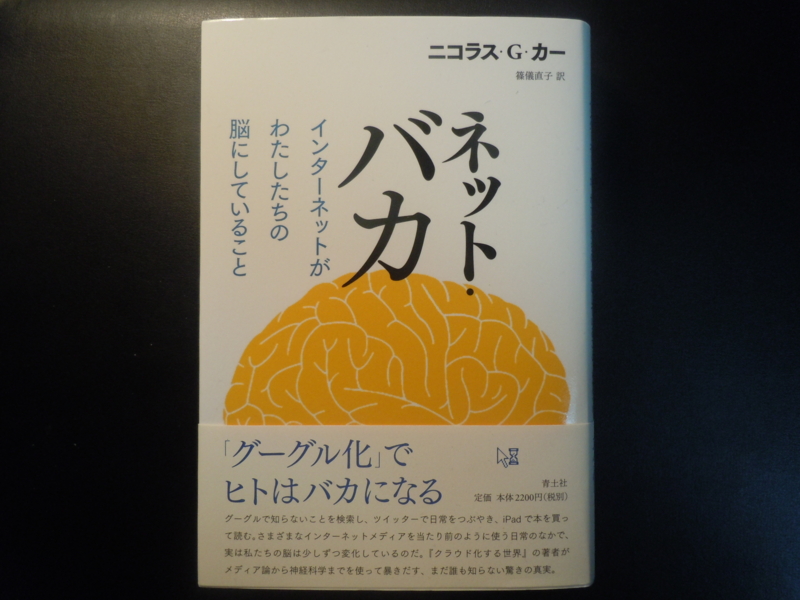
「グーグル化」でヒトはバカになる
著者は、『クラウド化する世界』などの著書で知られ、テクノロジーを中心とした社会的、文化的、経済的問題を論じるアメリカの著述家です。
本書のプロローグ「番犬と泥棒」の冒頭で、マーシャル・マクルーハンの『メディア論―人間の拡張の諸相』(みすず書房)について触れています。21世紀になって再評価されている名著ですが、この本の中心には一つの予言がありました。その予言とは「直線思考の解体」であり、20世紀の「電子メディア」、すなわち電話、ラジオ、映画、テレビは、わたしたちの思考と感覚に対するテクストの暴政を打倒するであろうとマクルーハンは述べたのです。
数世紀にわたって私的読書と印刷媒体に閉じこめられ、孤立化し、断片化されてきたわたしたちの自己は、再び一つになろうとしている。そして、世界全体が一部族の村のようになろうとしている。いわゆる「地球村(グローバル・ビレッジ)」の誕生です。
カーによれば、「メディアはメッセージである」という『メディア論』の名文句があまりにも有名になり過ぎたために、マクルーハンについて忘れられたことがあるといいます。それは、マクルーハンが新しいコミュニケーション・テクノロジーが持つ変容のパワーを無条件に認め、祝福していただけではないということです。彼はまた、このパワーが持つ脅威についても警告し、その脅威に無知であることの危険性も訴えていたのです。新メディアが登場するたび、人々は必ず、それが伝える情報の内容のみにとらわれてしまうことを、マクルーハンは理解していたのです。
『メディア論』という本は賛否両論を巻き起こしましたが、カーは次のように述べます。
「支持派も懐疑派も見逃しているのが、マクルーハンの次のような見解だ。長期的に見れば、われわれの思考や行動に影響を与えるのは、メディアの伝える内容よりも、むしろメディア自体である。世界に対するわれわれの窓として、およびわれわれ自身に対する窓として、大衆メディアはわれわれの見るもの、ならびにその見方を形成する――そして、もしも充分に活用された場合、個人としてのわれわれひとりひとりを、および社会としてのわれわれを、大衆メディアは結果的に変化させることになる。『テクノロジーの効果は、意見や概念のレヴェルで生じるのではない』とマクルーハンは言う。むしろそれは『知覚パターンを着実に、いささかの抵抗にも出会うことなしに』変化させていくのだと。このショウマンは多少の誇張を行なっているが、指摘されている点は重要だ。メディアが魔法をかけるのは、あるいはいたずらを行なうのは、神経自体に対してなのである」
著者は日々多くの時間をコンピュータ・スクリーンを見ることに使い、メールのやりとりをし、さらにはネットのサイトやサービスに慣れ親しんでいます。そのうち、自分の神経が、そして脳が大きな影響を受け始めたことを自覚します。
自分の習慣や日常的行動が変化したというだけでなく、脳の働き方自体が変わりつつあるように思えてきたのです。著者は、一つのことに数分かそこらしか集中できなくなっていることを不安に思い始めます。最初は、脳の年齢的な衰えのせいだろうとも考えますが、そのうち次のようなことに気づきます。
「わたしの脳は、単にふらふらさまよっているだけではない。飢えていたのだ。ネットが与えてくれるのと同じだけの量を食べさせてくれと、それは要求していた――そして与えられれば与えられるほど、さらに空腹になるのだった。コンピュータから離れているときも、わたしはメールをチェックしたり、リンクをクリックしたり、ググってみたりしたくてたまらなかった。接続していたかったのだ。マイクロソフトのワードが、血と肉を持ったワープロへとわたしを変えたのと同様に、インターネットはわたしを、高速データ処理機械、いわば人間版HALへと変えたのだとわたしは気づいた」
ちなみにHALとは、アーサー・C・クラーク原作でスタンリー・キューブリック監督によって映画化されたSFの金字塔「2001年宇宙の旅」に登場するスーパーコンピュータです。20世紀におけるコンピュータの代名詞であった「IBM」の3つのアルファベットのそれぞれ直前の文字をつなぎあわせて「HAL」と名づけられたことはよく知られています。
本書には、新しいテクノロジーが人間に影響を与えた多くの興味深いエピソードが紹介されていますが、その中には、哲学者フリードリヒ・ニーチェの逸話もありました。
ニーチェは20代前半のころ、落馬して負傷した後遺症で、視力が非常に落ちた時期がありました。読書しても、本のページを集中して見つめると、ひどく疲れて苦痛をおぼえ、ときには割れるような頭痛や嘔吐の発作が起きたのです。当然ながら執筆は早めに切り上げねばならず、そのうちに執筆自体をあきらめねばならないことを予想し、ニーチェは絶望しました。
万策尽きた彼は、デンマークの王立ろうあ協会の会長であるマリング=ハンセンが発明した「ライティングボール」というタイプライターを注文しました。このライティングボールがニーチェを救いました。ブラインドタッチを覚えたことで、ニーチェは目を閉じて指先の感覚だけで執筆できるようになったのです。
しかし、この装置はニーチェの仕事に微妙な影響を与えていました。友人の作家で作曲家のハインリッヒ・セーゲリッツは、ニーチェの文体における変化に気づきました。文がタイトになって、まるで電報のようになっていたのです。また、そこには力強さのようなものも加わっていました。本書には、次のように書かれています。
「それはあたかも、このマシンのパワー―その『鉄』―が、何らかの謎めいた形而上学的メカニズムによって、刻印される言葉へと乗り移っているかのようだった。ニーチェ宛ての手紙にセーゲリッツは『この器械によって、あなたはおそらく新しいイディオムさえ身につけるでしょう』と書き記し、自分の仕事、すなわち『音楽と言語』における『わたしの「思考」は、ペンと紙という性質によってしばしば規定されています』と指摘した」
それに対するニーチェの答は、「そのとおりです。執筆の道具はわれわれの思考に参加するのです」というものだったそうです。
地図と時計が「精神の道具」であり、わたしたちの思考の方法に大きな影響を与えてきたという著書の指摘も非常に刺激的でした。まず、地図について著者は次のように述べます。
「個人としてのわれわれの知的成熟は、自分の環境をどのように絵に描くか、あるいはどのような地図にするかを通じてたどることができる。目に見えるとおりに土地の特徴を写し取る原始的な段階から始まり、地理的およびトポグラフィー的空間の、より正確で、より抽象的な表象へとわれわれは進んでいく。言い換えれば、見えるものを描くことから、知っているものを描くことへと進歩するのだ」
地図は、地上や天空の広い範囲を詳細に表象するだけではなく、思考を表現するメディアとなります。たとえば、戦略地図、伝染病の伝播分析図、人口成長予想図などを見れば、それがよく理解できるでしょう。
地図学者のヴィンセント・ヴァーガは、「空間内での経験を、空間の抽象化へと転換した知的プロセスは、思考モードにおける革命である」と述べています。著者も、地図は情報を蓄積し、伝達するだけでなく、特定の視覚モードや思考モードを体現するものであると述べます。より頻繁に、より熱心に地図を使えば使うほど、人々の知性は、現実を地図的なやり方で理解するようになるわけです。
そして、地図が空間に対して行ったことを、もうひとつの「精神の道具」である機械時計は、時間に対して行いました。つまり、自然現象を、その現象の人工的・知的概念へと翻訳するという行為です。著者は述べます。
「人類は、その歴史においてずっと長いこと、連続的で循環的なフローとして時間を体験していた。時間が『測られて』いる場合、計測はこの自然プロセスを強調するような器具を用いて行なわれていた。たとえば、円を描いて影が回る日時計、砂が流れ落ちる砂時計。水が流れていく水時計。時間を正確に測る必要も、一日を細かい単位に分割する必要もなかった。ほとんどの人々にとっては、太陽と月、星々の動きさえあれば、時計などなくても事足りた」
機械時計は、わたしたちの時間に対する見方を変えました。また、地図と同様に、思考の方法をも変えました。著者は、さらに次のように述べます。
「長さの等しい単位の連続として時計が時を再定義すると、われわれの知性は、分割と計測という組織化機能に重点を置きはじめたのだ。あらゆる事物や現象のなかに、全体を構成する部分が見えるようになり、次に、その各部分を構成するそのまた部分が見えはじめた。物質世界の目に見える表層の裏から、抽象的パターンを見出すことに重点を置くという意味で、われわれの思考はアリストテレス的になっていった。われわれを中世から連れ出し、ルネサンスへ、さらには啓蒙主義時代へと押しやっていく上で、時計は決定的な役割を果たしたのである」
最後に、ドラッカー以前のマネジメントの歴史における最重要人物フレデリック・テイラーの科学的管理手法に関する部分が興味深かったです。
ニーチェがライティングボールを買ってまもなくのこと、フィラデルフィアにあるミッドヴェイル・スチール社の工場で、若きテイラーがストップウォッチを持って現れました。テイラーは、機械工の能率を上げることを目的とした有名な実験を開始しました。蒸気機関の発明から1世紀あまりが経過した頃でした。テイラー自身が「システム」と呼んだ工業に対するタイトな振り付けは、世界中の工場主に歓迎されました。工場主たちは、最大速度、最大効率、最大のアウトプットを求めていました。
そして彼らは、テイラーの時間動作研究の成果を用いて業務を体系化し、労働者の作業を配列したのです。テイラーは工場主たちに向けて、「過去においては、人間が第一であった。未来においては、システムが第一でなければならない」と宣言しました。テイラーの思想が、後に「マネジメント」を完成させたドラッカーのそれといかに違っているかは明白ですね。ドラッカーのマネジメントとは、何よりも「人間第一」だからです。
1993年に刊行された『技術vs人間―ハイテク社会の危険』(新樹社)という本において、著者のニール・ポストマンは、テイラーの科学的管理システムが基づく6つの前提を次のように指摘しています。
1.人間の労働と思考の、唯一ではなくとも第一のゴールが、効率的であるということ。
2.あらゆる面において、技術的計算が人間の判断よりまさるということ。
3.それどころか人間の判断は、だらしなさや曖昧さ、不必要な複雑さなどに毒されているため、信用ならないということ。
4.主観は明晰な思考をさまたげるものだということ。
5.計量できないものは、存在しないか無価値であるかのどちらかだということ。
6.市民の営為は、専門家によって最もよく導かれ、行われるということ。
そして、本書の著者であるカーは、以上の前提はグーグル社の知的倫理をも見事に表わしているという指摘をしています。たしかにグーグル社は、市民の営為を最もよく導くのが専門家だとは思っていないでしょう。彼らの考える最良のガイドとはソフトウェア・アルゴリズムに他なりません。テイラーの時代に強力なデジタル・コンピュータがあれば、テイラーもきっとソフトウェア・アルゴリズムに従ったであろうと考える著者は、次のように述べます。
「グーグル社は、正しさの感覚を労働に持ちこんでいる点でもテイラーに似ている。この会社は自身の主義に対し、深い、ほとんどメシア的とも言える信仰を抱いている。CEOの言によれば、グーグルは単なるビジネスではない。『道義的な力』なのだ。この企業が喧伝する『使命』は、『世界中の情報を組織し、普遍的にアクセス可能で使用可能なものとすること』である」
一般に、グーグルはGEや日本のファースト・リテーリング(ユニクロ)などと並んで、ドラッカー理論の影響を強く受けている企業とされているようですが、わたしはそれはまったくの誤りであると確信します。くどいようですが、ドラッカーのマネジメントとは「人間第一」であり、「科学的管理手法が第一」ではないからです。
現在、飛ぶ鳥を落とす勢いのグーグルは今後も快走を続けるのでしょうか。著者の見方は非常にシビアであり、次のように述べています。
「グーグルは将来、一瞬の成功だったということになるかもしれない。インターネット企業の生涯が悲惨だったり残酷だったりすることはまれだが、その寿命が短い傾向にあるのは確かだ。彼らのビジネスは、ソフトウェア・コードという目に見えないものから成り立つ、つかみどころのないものであるから、その防衛は脆弱になる。繁栄中のオンライン・ビジネスを時代遅れにするには、新鮮なアイディアを持った鋭いプログラマーがいさえすればよい。より正確な検索エンジンの開発、ネット広告のよりよい方法の発案が、グーグルにとっては破滅となりうる。だが、この企業があとどれだけのあいだ、デジタル情報のフローの支配権を維持できるかどうかにかかわらず、その知的倫理は、メディアとしてのインターネットの一般的倫理でありつづけるだろう。ウェブ作成者とツール作成者はこれからも、情報の小片を次々得たいというわれわれの飢餓感をあおり、またそれに答えることで、トラフィックを惹きつけ、金を得ようとするだろう」
わたしは、著者のこの見方は鋭いと思います。本書は、マクルーハンの『メディア論』と同じく、大いなる予言の書となるかもしれません。本書を読んで、いろんなことを知ることができましたし、いろんなことを考える機会を与えられました。ネットばかりやっていてはバカになるとのことですが、本書を読めば、ずいぶん賢くなれることは間違いないようですね。