- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0111 読書論・読書術 『新書がベスト』 小飼弾著(ベスト新書)
2010.07.11
著者は、株式会社オン・ザ・エッヂ(現ライブドア)の取締役最高技術責任者(CTO)を務め、同社の上場に貢献した経歴の持ち主だそうです。現在は書評ブロガーとして知られ、月間100万PVを誇るとか。すごいですね!
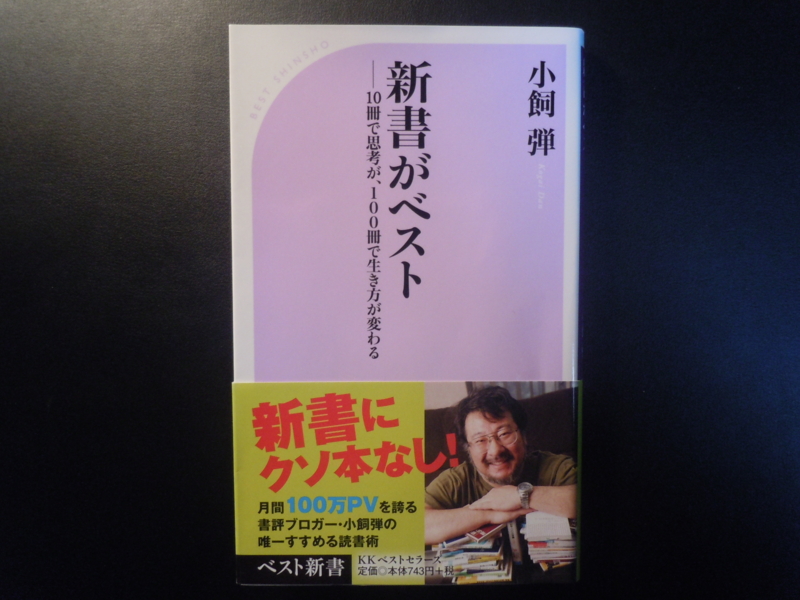
10冊で思考が、100冊で生き方が変わる
わたしはライブドアという会社にも設立者の堀江貴文氏にも、ずっと大きな違和感を感じてきました。ですから、著者が同社の幹部であったと聞くと、正直あまり良い印象は持ちません。それに、著者の前著である『空気を読むな、本を読め』(イースト・プレス)を読みましたが、はっきり言って、わたしにはピンと来ませんでした。しかしながら、本書はなかなかの好著だと思いました。
本書では、とにかく「新書」を読むことを薦めています。類書に『だから、新書を読みなさい』奥野宣之著(サンマーク出版)がありましたが、この本は新書を絶賛しながら、自らが新書の体裁を取っていませんでした。その点、本書は正真正銘の新書です。なおかつ、ベスト新書から『新書がベスト』というタイトルの本を出すところにネーミング・センスの良さが感じられます。
本書の冒頭で、著者はこう言います。
「これからの世の中で生き残りたければ、新書を読め」
本書で著者が言いたいことは、たったこれだけのことだそうです。インターネットが発達し、莫大な情報を誰でも簡単に取り出せる時代になりました。著者は、膨大な情報に取り囲まれているからこそ本を活用しなければ生き残れないとして、次のように述べます。
「このような世界において人間が生き残ろうとするならば、方法はただひとつ。機械にはできない仕事をすることしかありません。それは、仕組み自体を改良したり、新しい仕組みをつくったりすることです」
それができないのなら、機械よりも安い労働力として働かされるしかないというのです。
「仕組み自体の改良」あるいは「新しい仕組みをつくる」とは、要するに、イノベーションでしょう。ドラッカーも説いたように、イノベーションは「知識の蓄積」から生まれます。人間は、まったくゼロから創造性を発揮することはできません。偉大な創造の背景には、必ず先達の歩みがあります。その意味で、創造の達人とは読書の達人でもあります。
グーグル創業者の2人も、読書によって大きなイノベーションを可能にしました。本を読むことによる学習力が創造力につながるのです。
わたしは最近、「創造の母とは本と悟るとき 新しきもの生まれ出るなり」という短歌を詠んだばかりです。本書で著者が言っていることも同じだったので、ちょっと驚きました。さらに、著者は次のように述べています。
「昔なら、新しいアイデアを出し仕組みをつくることは、ごく一部の人のやることで、仕事ですらありませんでした。ちょっとしたアイデアをたまたま思いついたら、それだけで一生食えてしまえることだってありました。砂糖水に炭酸を入れて売るだけで、億万長者になることができたのです」
続けて著者は、「しかし、おそらく20世紀以降、誰もが何らかの知的なアウトプットを求められるようになってきました」と述べます。知的なアウトプットは、科学者の発見や芸術家の創作だけに限りません。新しいビジネスの企画を考えたり、現状を分析して報告書にまとめたり、さらには小売店で商品の効果的な並べ方を考えることも、立派な知的なアウトプットなのです。
グーグルのような検索エンジンを活用すれば、いくらでもネットから情報を取り出すことができます。ネットがあれば、「本は、要らない」と考える人もいるかもしれません。しかし著者は、本の価値というものは内容が偏っていることにあると断じます。そして、はっきりと次のように述べます。
「ひとりの著者が、独断と偏見による考えを披露するのが本です。両論併記の中庸な意見より、いろいろな立場からの独断と偏見をいくつも取り入れた方が、はるかに情報として意味があるのです。これは、スゴ本とダメ本の差でもあります」
著者は、本を読むことが強みになるかどうかは冊数にかかっているとします。そして、その境目をズバリ、1000冊としています。著者によれば、プロの物書きは300冊の本を読んだら1冊書けるといいます。
かつて、かの浅田彰氏が「300冊読んだら、1冊の著者が書ける」と発言し、わたしもその言葉を信じていました。実際に、浅田氏は300冊の文献を読んでから『構造と力』を書いたそうです。しかし、これはあくまでもアウトプットがすでに習慣化されているプロの場合で、そうでないアマチュアは、その3倍、つまりは1000冊ぐらい読まないと、けっして本を書くことはできません。著者は、述べます。
「自分は本なんか書くことはない」と思う人がいるかもしれませんが、現代において文章を書かずにお金をもらえる仕事はほとんどありません。たとえば、会社勤めをしている人は、頻繁に報告書やレポートを書いているでしょう。まったく文書を書く必要がないのは、特殊な分野の職人くらいのものです」
なるほど、これには大いに賛同してしまいました。
ただ、著者の発言で賛同しかねる部分もあります。著者は「ハードカバーは滅びてしまえ」と言っています。生き残ることを目的とした読書では、さまざまな分野の本をたくさん「読み飛ばす」ことが重要であり、そのためにはどこでも気軽にさっと読める本であることが必須条件だというのです。著者は、言います。
「単純なことですが、読む際に手の中で本がしなるのとしならないのとでは、読みやすさが全然違ってきます。ハードカバーはしなりませんから、電車の中で片手で読むこともできない。利便性のない、ありえないつくりになっているのです」
ここまでは、まだ何とか理解できます。わたしも出張で飛行機や新幹線の中で読む本には、よほどのことがない限り、ハードカバーを選びません。文庫や新書が中心で、少なくともソフトカバーの本がほとんどです。たしかに片手で読むには、しなる本のほうが読みやすいからです。しかし、次のような著者の発言には首を傾げざるを得ません。
「ハードカバーには、本を滅多に買わない人が『俺って、こんな分厚い本を買って読んだんだよ、すごいでしょ』と達成感を味わうくらいの意味合いしかありません」
「本を読むのが好きな人でハードカバーが好きだと言う人は、これまで会ったことがありません」
これは、いくら何でも言いすぎでしょう。わたしは、この意見には反対です。第一、わたしは本を読むのが好きですけど、ハードカバー大好きですよ!
わたしは新書を読むのも好きですし、自らも『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)や『葬式は必要!』(双葉新書)などの新書も書いています。もちろん、どちらも愛着のある著書ですが、書きたいことの半分以下しか書けなかった本でもあります。つまりは、新書というメディア・スタイルはコンパクトなゆえに限界もあるのです。
わたし自身、新書を読んで興味を持ったテーマは、その後で必ず専門書を読むことにしています。専門書は、当然ながらハードカバーです。価格も高いです。でも、安価でコンパクトだからといって出版物がすべてソフトカバーになり、著者が言う「ハードカバーは滅びてしまえ」が現実のものとなったら、日本人は確実に馬鹿になるでしょうね。三五館の星山佳須也社長などは逆にアンチ新書派で、わたしが書評やブログで新書を取り上げると、「一条さんも新書なんか読まれるんですか?」と言われるほどです。
本を書く著者たる者、新書なんかで安易にインプットせず、しっかりした専門書を読むべしという暗黙のプレッシャーをかけられるわけです。結局、新書には良い部分もあり、限界もある。理想の読書生活とは、ソフトカバーもハードカバーもともに読むことではないかと思います。
だいたい、たくさんの本を「読み飛ばして」、どうするのでしょうか。いったい、何の新しい仕組みをつくるというのでしょうか。このあたりの著者の主張にはついていけません。よくある多読や速読のすすめ、さらには金儲けのための読書術にもつながる空気を強く感じました。
でも、本書が一連のフォトリーディング本と一線を画しているのは、PartⅢ「新書レーベルめった斬り!」の存在です。これは、新書読みの達人である著者にしか書けない絶妙な「新書入門」となっています。元祖の岩波新書から、最新の新書レーベルまで、あますところなくその特色を描き、レーベル内の傑作を紹介する手際は見事です。
たとえば、岩波新書の傑作は永六輔著『大往生』、中公新書は本川達雄著『ゾウの時間 ネズミの時間』、ちくま新書は青砥恭著『ドキュメント 高校中退』、光文社新書は竹内薫著『99.9%は仮説』、新潮新書は加藤徹著『貝と羊の中国人』を挙げていますが、なかなかの選択眼だと思います。
また、都甲潔著『プリンに醤油でウニになる』(サイエンス・アイ新書)、阿部等著『満員電車がなくなる日』(角川SSC新書)、掛谷英紀著『学者のウソ』(ソフトバンク新書)、齋藤正明著『会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ』(マイコミ新書)など、新興のレーベルから隠れた名著を次々に発掘している「通」ぶりなど、さすがは書評を書かせたら当代一のアルファ・ブロガーであると感心しました。間違いなく、著者は新書に関して日本一の目利きではないでしょうか。
それぞれの新書レーベルの特徴も的確にとらえています。たとえば、「文春新書」と「集英社新書」の両レーベルが右寄りと左寄りで好対照。たとえば、「講談社現代新書」と「講談社+α新書」のコンセプトが迷走している。たとえば、「青春新書インテリジェンス」は、スゴ本とダメ本が玉石混合である。
こんなことは、著者に言われて初めて気づき、大いに納得しました。そして、著者は何かと話題の多い「幻冬舎新書」についてもメスを入れます。
「幻冬舎新書のイメージは、いい意味でも悪い意味でも、売るための努力を惜しまないことでしょう」などと評しています。センセーショナルなタイトルをつけることも特徴で、夏野剛著『グーグルに依存し、アマゾンを真似るバカ企業』とか、武田邦彦著『偽善エコロジー』などが有名です。
しかし著者は、『偽善エコロジー』に関して、「ただし、読む上では注意も必要です」「著者の主張は聞くに値しますが、データや論理の展開での間違いが目立ちます」と述べています。最近は、『偽善エコロジー』を批判的に検証する本まで生まれています。
となると、幻冬舎新書で最近のセンセーショナルなタイトルの本が気になりますね。そうです、島田裕巳著『葬式は、要らない』です。
じつは、この本にもデータ上の明らかな間違いがあります。というのも、この本は「日本の葬儀費用は世界一高い」などとセンセーショナルに謳っており、本の帯にもそのことが書かれています。日本の葬儀費用は平均231万円で、韓国は37万円、アメリカが44万円などと比較しています。でも、この数字がまったくのデタラメであることを、葬儀専門誌「SOGI」の編集長である碑文谷創氏が暴いてくれました。
日本のデータは2007年(平成19年)のもの。一方、韓国やアメリカは1994年(平成6年)のもの。なんと、それらのデータには13年もの開きがあるのです!! しかも、この10年間で、韓国は葬祭会館の建設ラッシュで葬儀費用は飛躍的に高騰しているのです。
さらに、島田氏の国際比較には大きなトリックがあります。日本の葬儀には香典という習慣があります。香典を参列者からいただいた結果、喪家は飲食をふるまったり、香典返しとしての返礼品を用意します。しかし、この比較においては、香典収入は一切カウントせず、逆に飲食代や返礼品代は支出費用としてしっかりカウントしているのです。これは明らかに不正な費用算出であり、数字のトリックと言われても仕方ありません。
それはともかく、本書『新書がベスト』は非常に優れた新書入門と言えます。本書を読んで、たくさん新書が読みたくなりました。また、わたし自身、新しい新書を書いてみたくなりました。
ところで、本書と同じベスト新書から、わたしは監修書を出しています。『100文字でわかる世界の宗教』という本です。コンパクトに世界の宗教のエッセンスがわかると好評で、版を重ねています。よろしければ、ぜひお読み下さい。

宗教がわかれば、世界が見える!